あなたにおすすめの小説

田舎の幼馴染に囲い込まれた
兎角
恋愛
25.10/21 殴り書きの続き更新
都会に飛び出した田舎娘が渋々帰郷した田舎のムチムチ幼馴染に囲い込まれてズブズブになる予定 ※殴り書きなので改行などない状態です…そのうち直します。

初色に囲われた秘書は、蜜色の秘処を暴かれる
ささゆき細雪
恋愛
樹理にはかつてひとまわり年上の婚約者がいた。けれど樹理は彼ではなく彼についてくる母親違いの弟の方に恋をしていた。
だが、高校一年生のときにとつぜん幼い頃からの婚約を破棄され、兄弟と逢うこともなくなってしまう。
あれから十年、中小企業の社長をしている父親の秘書として結婚から逃げるように働いていた樹理のもとにあらわれたのは……
幼馴染で初恋の彼が新社長になって、専属秘書にご指名ですか!?
これは、両片想いでゆるふわオフィスラブなひしょひしょばなし。
※ムーンライトノベルズで開催された「昼と夜の勝負服企画」参加作品です。他サイトにも掲載中。
「Grand Duo * グラン・デュオ ―シューベルトは初恋花嫁を諦めない―」で当て馬だった紡の弟が今回のヒーローです(未読でもぜんぜん問題ないです)。


憐れな妻は龍の夫から逃れられない
向水白音
恋愛
龍の夫ヤトと人間の妻アズサ。夫婦は新年の儀を行うべく、二人きりで山の中の館にいた。新婚夫婦が寝室で二人きり、何も起きないわけなく……。独占欲つよつよヤンデレ気味な夫が妻を愛でる作品です。そこに愛はあります。ムーンライトノベルズにも掲載しています。


罰ゲームで告白されたはずなのに、再会した元カレがヤンデレ化していたのですが
星咲ユキノ
恋愛
三原菜々香(25)は、初恋相手に罰ゲームで告白されたトラウマのせいで、恋愛に消極的になっていた。ある日、職場の先輩に連れていかれた合コンで、その初恋相手の吉川遥希(25)と再会するが、何故かヤンデレ化していて…。
1話完結です。
遥希視点、追記しました。(2025.1.20)
ムーンライトノベルズにも掲載しています。

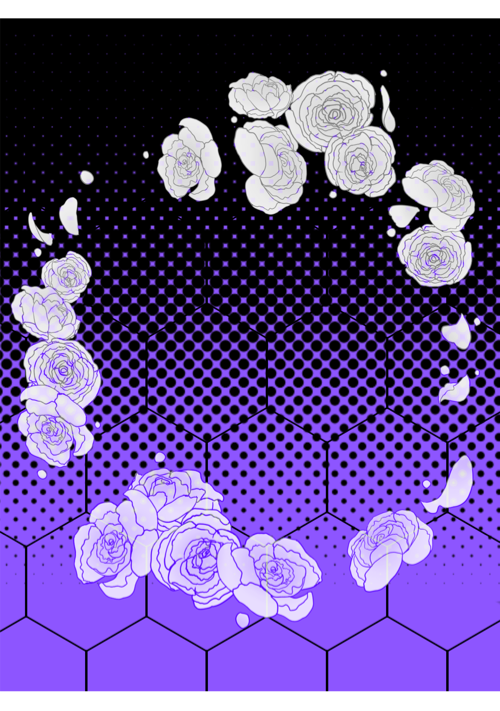
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















