16 / 17
第十六話 時間
しおりを挟む
私はもう、そう長くはないみたい。
天に召される時がもう時期来るだろう。
病気だから仕方がなかった。正直まだ生きたかったが。
私がとても行きたかった動物園でたくさんの動物とも触れ合えることができた。4、5歳の少女に戻ったかのように、たくさん笑った。
そろそろ帰ろうとしていた。
すると、優奈がこんなことを提案してきた。
「由香里、あっちに行こう。」
「え?待ってよ。何があるの?」
一体何があるのかわからなかったけど、私は優奈と一緒にある場所に行った。
外に行った。何が青い光のようなものが燦々と輝いていた。宮殿のように。
イルミネーションだった。
100万個にLED ライトが漆黒の夜を青く照らしてくれていた。
私はとても感動した。私のためにこんなに尽くしてもらった優奈には申し訳ないと思った。
「これが目当てだったんだね。」
「うん。2人で行きたかった場所なんだ。」
私たちは唖然としていた。
青色に輝くLEDライトがすごく豪華絢爛に見えたからだ。駅前のイルミネーションを遥かに超える迫力さに私は落ち着かなくなっていた。
ここで、私は優奈にある話を持ちかける。
最後にここで話しておきたかった。
「優奈。私がいなくなったらどうするの?」
私は心配そうに優奈に問いかけた。
「普通に何もなく暮らしてるよ。」
「わかりにくいと思ってたけど私、表では何もない風を装ってた。でも中を見たら苦しんで泣いてた私が出てきたんだ。夢に。」
私は優奈の二重人格ぶりに全身が震えてしまった。
「正直ね、驚いてるの。
高校でまさか出会えるなんて思わなかったよ。美術部で出会えた人が本当の従姉妹だったなんて。従姉妹だったらもっと早く知り合いたかったよ。」
「私もだよ。」
私も同じ気持ちだった。
もし小学校の時に知っていれば、他人に対しての見方が少し変わるようになっていたのにと後悔していた私だった。
しかし、優奈はあくびをした後みたいに目に涙を浮かべていた。
「私ね。中学生の時にすっごくびっくりしたんだ。」
「何を?」
私は優奈の発言に疑問を抱いていた。
「血だらけのあなたが中学のグラウンドでの朝礼で屋上から自殺をしようとしてたということをね。テレビでリアルタイムで見てたんだ。」
私は目を虚ろにしていたが、大きな音にビックリするように目を開かせた。
「そうだったんだ。」
という一言しか言えなかった。
「当時、思ってたんだ。私は同じ中学生なのにこんなに違うことってあるんだなって。しかも名前が公開されてたけど、それを聞いてとても慌てたの。まさか小学校の同級生だったなんて思わなかった。もし、私があの子だったら何をしてたのかなって思ってた。私がこんな目にあってしまうのではないかという恐怖が体に馴染んでしまったよ。」
「そうだったんだ。」
自殺未遂は全国ネットのニュースで中継になっていたほどだった。けど、私の家まで報道記者が押しかけてくることは一切なかった。
私もあの時は苦しかったという感情を遥かに超えて、死ななければならないという死刑を宣告されたように、義務感が私を襲った。
高校で優奈に会っていなかったら、私はとっくのとうに自殺を謀っていたのだろう。
「優奈は私の恩人かもしれない。」
と優奈に言い放った。
「ありがとう。」
優奈は私に抱きついてきた。
私の体はいつのまにかボロボロになっていた。
身体中の骨が浮き始めている。
こんなに脆くなった私の体を抱きしめてくれるなんて。従姉妹というのはこんなにも大切な存在だったんだと思い知らされる。
私たちはイルミネーションをバックに話をしていた。最後かもしれない写真も撮った。
2人とも笑っていた。
もしかしたら帰れるかもしれない。
もう一度先生に会いたい。
私はまだ大丈夫。まだ行ける。
という自信がついた。なぜこんなにも命の瀬戸際にこんなことができるのだろうか。
動物園のトイレで大量の血を吐いたのにも関わらず私は命が消え去るその瞬間まで一生懸命になっていた。
みんなが待ってくれる。
光のある未来に行かなきゃいけない。
私はまだ頑張れる。
私たちは急いで旅館に戻ろうと帰りの新幹線に乗った。雲すらないくらい夜だった。
ネオンに輝く建物がひとつもない。
ただ電線を繋ぐ櫓のようなものの小さな赤い光が見えるだけだった。
私はここで体調が急変した。
「はー、はー、はー、」
私は過呼吸になり、座ることができずに横たわっていた。
今見えるのは震えている手足だけだった。
私はもうそこまできている。改めて実感した。
制服は黒く、汚れがひどくてボロボロだった。そして血が大量に付着した。私の顔も優奈の手鏡で見せてもらったが、さらにひどくなっていた。
もっと長く行きたい人もたくさんいるのに、なぜ人は好きな時に死ぬことができないのか。
特に私みたいな余命宣告がある病気を持っている人はこのように感じることができるだろう。学生の自殺なんかよりずっと悔しい。
私だって成人してみたかった。
着物を借りて、それを着て成人式に出席して、垢抜ける私を見せたいという欲望も最近湧き上がってきたのだ。
それなのに私は16でこの世を去ってしまうことになる。いや本当に死んでいたのはもっと前かもしれない。妹が助けてくれなかったら私はもう雲の上にいることになる。
私はとうとう手足の震えが痺れに変わった。
麻痺寸前まで陥った。
「だ、めだ。もう、動けない。」
「由香里!ここで死なないでよ!」
優奈も叫びまくった。
「この電車にお医者さんはいらっしゃいませんか?」という医者を探す方法としてよくあることだが、現実ではそうは行かなかった。
急いで裕太に電話をした。
「もしもし!由香里がどんどん衰弱してる!旅館までなんとか私が持ち帰るから待っててね!」
といい直ぐに切った。
「後もう少しの辛抱だからね。」
私はもう何も見えなかった。新幹線の走行音と人の話し声しか聞こえなかった。
私たちは2時間後、午後10時に札幌に戻ってきたのだ。
優奈は由香里を抱えて2人分の荷物を持ちながら恐る恐る改札を出た。
秋だったので、特別に暑いとか寒いとかは全くなかった。木々の葉っぱが橙になる前だった。
「おい!お前たち!」
声が太かった。その声の主は悠木先生だった。
「由香里、もうボロボロじゃないか。学校で普段明るく優奈と談笑していて、朝旅館から笑顔で見送ったあの由香里はもう見れないのか。」
優奈はこの一日の間私に起こったことを片っ端からメモをし、先生に渡した。そして、事細かく話したという。
「ありがとう優奈。実はなかなか戻ってこなくて心配してたんだ。優奈から裕太先生に電話が来たのを隣で聞いていたんだ。駅前にいれば俺が担いで旅館で運んであげるよ。」
「ありがとうございます先生。」
「お前も結構苦労しただろう。」
「いいえ、従姉妹ですから、これぐらいのことはしないと。」
「やっぱいい奴を従姉妹に持ったな。由香里。」
「は、い、おかげ、ですく、われま、した。」
体が衰弱していくせいか、私は普通に喋れなくなっていった。
「あいつらが心配してるんだ。早く行こう。」
「は、い、おね、がいし、ます。」
誰かの靴の音が聞こえる。
コンクリートの道路を全力疾走しているような感じだった。
「先生。由香里はどんどん青ざめてきてます。」
ゆうなが先生に言うと、着ていたTシャツを脱いだ。
「何してるんですか?」
「このぐらいはしておかないと風邪引くだろ。」
目が覚めたら、大人の背中に抱かれていた。
由香里の背中に先生のTシャツがかけられた。
「なんか、あった、かい、」
上半身裸になった先生はさらに加速していった。鍛え抜かれた肉体、くっきり割れている腹筋に釘付けになるわけがなかった。
「これで走りやすくなった。」
気がついたら私は旅館の前にいた。
ついに帰ってこれたのだ。
今日の夜は帰ってこないって断言していたが、不可能を可能に変えることが今できたんだ。
私の視界には多くの生徒がいた。
心配そうに見る人や青ざめている顔に怯えている人もいた。
「由香里!」
「大丈夫!」
「大丈夫か?」
みんなの声が聞こえる。しかし、ただの叫び声にしか聞こえなかった。
「お前ら、もう夜遅いんだからあとは先生に任せて部屋に帰りなさい。」
「何でですか?」
「だってクラスメイトですよ?人が死ぬって言うのにみられないって不謹慎です。」
「今までいじめてきた奴の言うことじゃねえだろ!」
「お前らなんかあれじゃん。いじめてた奴が死ぬから正直嬉しいんだろ?居なくならないでって言う程度の低い芝居しかできないんだ。由香里のいじめが発覚したときに言おうと思ったのにあの時は怖かったんだ。」
先生の怒りの怖さにみんなは怯えた。
「確かにそうだったね。なんでこの人をいじめてきたんだろう。」
「確かにそうね。間違ってたわ。」
「ごめんなさい!」
クラスメイトみんながボロボロの私に向かって謝って頭を下げた。
「いいよ。別に、気に、してない、から。」
ここにいるみんなは涙以外の感情はすでになくなっていたかのように、涙が出て、鼻を啜る音が聞こえていた。
「バタン!!!!!」
由香里は先生の首に手を組んでいたのに、手の力がなくなり、落ちて倒れてしまった。
私は再び意識を無くした。目を瞑ったまま何も動くことはなかった。
うっすらと明るくて、淡い色の光が見えてきた。私は天使になったかのように思えた。
みんなはもういない。天国に旅立ってしまったのか。もう上で見守るしかないのか。
「はっっっ!」
私は目が覚めた。どうやら夢を見ていたようだ。見渡すと旅館のベットにいて、そこにはみんながいた。
それと同時に私の嫌な思い出や記憶もどこかに置いてきたように忘れていた。
「あれ?優奈は?」
「優奈はいま下にいるよ。待っててね。」
先生と生徒たちみんなが見守ってくれていた。
「なんで、いるの?」
「当たり前だよ。見守りにきたんだよ。さっき聞いてみたんだ、もう時間がないってさ。」
生徒の1人が言った。
「もう、みんな知ってるって。」
先生が寂しそうに言った。
「なんでですか?まだ助けられるかもしれないじゃないですか?って聞いたんだ。もう時間がなくて治す最中に絶命してしまうかもって、言われたんだ。」
「ちょっと席を外してもらえないか?2人きりで話がしたい。」
先生の言葉通りに生徒たちは由香里のいる部屋から姿を消し、それぞれの部屋にチリチリに戻った。
「由香里、最後に言っておきたいことがある。」
「教師になって俺は初めてこのクラスの担任になったんだ。いろんな先生から色々と言われたよ。」
「初めてなんだから失敗はたくさんしろ。」
「このぐらいの仕事はやって当然なんだからもっとやれ。」
「けどな。由香里を見たらそう言うことを言っている暇はなかったと思ったんだ。実は俺、消防士になろうとしていたんだ。大学で公務員系の仕事に就きたいと思って、訓練も頑張った。4年生の9月に近くの消防署での就職が決まったんだが、人数不足で署内が回らなくなり、署自体が廃業になってしまったんだ。」
先生は過去のことを話し出した。
「でも俺は社会全般が好きだった。社会の教員を目指そうと消防署での訓練を受けていると同時に教員試験の勉強もやってたんだ。無事に合格して教師になって、この学校に来てお前に出会うことができた。消防士の訓練を受けていたからか病弱なお前をいろいろなところで助けることができたよ。肉体的、精神的にも全て由香里に自分ができることを全て尽くすことができた。好きな職業には就けなかったけど、教師でも人を助けることはできるんだってお前がいてくれたおかげで本当に思えるようになったよ。だからもしお前が亡くなったとしても、みんな最後まで諦めずに何かに取り組むだろう。俺もお前の分まで頑張るからな。由香里。今まで本当にありがとう。俺は悔しいぞ。もっとたくさんそばで一緒にいたかったぞ・・・。」
先生は大号泣していた。
持っていたハンカチでは受け止めきれなかった。
先生の人生経験から私がいてくれたおかげで今の先生があると言うことを教えてくれた。
先生の人生も壮絶だったのかもしれない。
人それぞれ違う人生を送っているのは不思議なことだと思う。
「コンコン」
ドアの音がした。
ガチャ。とドアを開けると優奈がいた。
「由香里、お父さんから聞いたんだ。もう時間がないんでしょ?」
「そうみたいだな。優奈。先生も最後まで見届けるつもりだぞ。」
「先生。」
「私も由香里の従姉妹で本当に良かったと思ってる。本当にありがとう。」
するとある女性の声が聞こえた。
「由香里!あなたなの?生きてるの?」
そう叫んだ人物は由美だった。
「お母さん、な、んで?」
私の視界にかすかにお母さんの姿があった。私は必死に手を差し伸べようとしていた。
「あの時にお別れしようと思ってたんだけどね。どうしても伝えたいことがあって北海道まで来てしまった。」
勝手にいなくなるなんてお母さんが許さないからって言われても今更遅いだろう。
実は仕事で行けなくなったのだが、
由美が勤めている会社は全国に数カ所の支所がある。その中で札幌支所に出張ができると聞いた途端に、部長に頭を下げてお願いをしたと言う。
そのことを聞いた他の人は驚いた。
「お別れの挨拶なしに見送られても困るよね。由香里。」
修学旅行前が本当に最後だと思っていた。けど、また会えた。生きててよかった。ここまで生きているのも奇跡としか言えない。
由美は由香里に本音を伝えた。
「由香里。ごめんね。お母さんあなたのこと見捨ててないからね。そんなこと全く思ってないよ。たしかに私たちは4人家族だった。けど、あなたが死んでしまったら私1人になってしまうけど、由香里や他の2人がいてくれたおかげで楽しかった。家族の暖かさを噛み締めて生きてきた。特に私は由香里と妹の由梨奈を産んでその後の育児が好きだった。毎日が刺激的だった。育児は誰もが一度はイライラしたりして投げ出してしまうことはほとんどの親にあり得ることだけど、私は全くなかったよ。みんな愛してた。私は大丈夫よ。1人でやってあげる自信が今ついた。だって3人が見守ってくれるんだもん。頑張って、生きるね。」
「由美さん。」
「俺も泣きそうだ。」
室内にいた全員が涙に誘われた。
これが本当の親子の絆だと思い知らされた。
裕太が部屋にきた。
「僕もあなたに人生を救われました。あなたがいてくれたおかげで優奈と従姉妹だって気づくことができたんだから。」
「そうだったんですね。言ってくれたんだ。」
「もしかして恵のことですか?」
「うん。一番口が硬かった人なので全然話してくれなかったでしょう。でも裕太さんが説得してくれたからこんな嬉しい結果なったんです。私たち姉妹の関係がよくなれそうな気がします。ありがとうございます。」
「いいえ、私は当たり前のことをしただけてますよ。」
もう午後11時55分か。
「そろそろ1人にしてあげてください。私はここで診ますので。」
みんなは由香里の客室から退室した。
外から見守ろうとしてくれたときに。
「ピーピーピーピー」
事は急転した。
私の脈、心拍数が低下していく。
「大丈夫ですか!聞こえてますか!由香里さん!私です!裕太です!」
裕太は必死で叫んだが、私は起きることはなかった。
心拍数等が低下しているうちに呼吸器をつけられた。発作も起こっていたが、今直してしまうと、完璧に私が絶命してしまうからしなかったのだ。
まだ鳴り止まない。
サイレンの音がずっと鳴りっぱなしだ。
由美たちが室内に入ってきて、
「由香里!大丈夫!まだ大丈夫!」
みんな私の冷たくて青ざめた手を握ってくれた。命の瀬戸際にある私をこんなに思ってくれているなんて思わなかった。
全て私の思い込みは皆無だった。
私は最後に気力を振り絞ってこうみんなに伝えた。
「さい、ごま、で、あり、がとう。がんばっ、て、い、生きて、ね。」
私の最後の叫びに涙が止まらなかった一同。しかし、これを伝えた後、私は意識を無くした。
もう時間が来てしまったようだ。
23時59分のことだった。
もうすぐ日にちが変わる。
その時まで私は頑張って息をしよう。
「ピーピー」
サイレンが急に消えた。
日にちが変わって、0時00分に脈、心拍数が0になった。
急にいなくなってしまった。
みんなは現実を見ている気分だろう。
今までたくさんの時間を過ごしてきた人間が、息絶えた瞬間を想像できないに違いない。
たとえ泣いたとしても私は戻ってこないんだと。
1分前の私ならまだ何か声をかける事はできたのに。
翌日、私の訃報を伝えると、
みんなは当然のように泣き崩れていた。
「なんで最後が見れなかったんだよ。」
と嘆くものもいた。
その中で優奈が1番悲しんでいた。
やっといとこを見つけることが出たのに、すぐにいなくなってしまうことが彼女の頭の中では考えられなかった。たとえ私の余命宣告が言われたとしても。
下を俯いていて、何をしようとしているのかわからなかった。
彼女の中で私が死んだ後に自決を考えていたが、親しい人が死んでしまったことから、
この人の分まで行けてやるぞと言う闘争心に優奈は燃えていた。
まるで、私が妹と死別するみたいに。
長かった4日間の修学旅行を終え、
学校に着いたのは最終日の夕方だった。
みんな誰も笑ってはいなかった。
とても気まずくなってしまったが、これで私の存在が1人でも多く残るのならそれでいいのだと、生前思っていた。私の遺体も同時に学校に着いた。先生たちが見ると、白骨化していた。
「まさかこんなことになる事は分かっていても泣いてしまうものなんだ。」
今まで生徒だった人の白骨化死体を見ると、
味わったことのないとんでもない感情に襲われてしまうのだ。
「あいつの分まで頑張って生きるぞ。
俺の恩人よ。」
悠木先生は夕暮れが山に沈み、暗くなる空に向かって決心した。
第十七話に続く。
天に召される時がもう時期来るだろう。
病気だから仕方がなかった。正直まだ生きたかったが。
私がとても行きたかった動物園でたくさんの動物とも触れ合えることができた。4、5歳の少女に戻ったかのように、たくさん笑った。
そろそろ帰ろうとしていた。
すると、優奈がこんなことを提案してきた。
「由香里、あっちに行こう。」
「え?待ってよ。何があるの?」
一体何があるのかわからなかったけど、私は優奈と一緒にある場所に行った。
外に行った。何が青い光のようなものが燦々と輝いていた。宮殿のように。
イルミネーションだった。
100万個にLED ライトが漆黒の夜を青く照らしてくれていた。
私はとても感動した。私のためにこんなに尽くしてもらった優奈には申し訳ないと思った。
「これが目当てだったんだね。」
「うん。2人で行きたかった場所なんだ。」
私たちは唖然としていた。
青色に輝くLEDライトがすごく豪華絢爛に見えたからだ。駅前のイルミネーションを遥かに超える迫力さに私は落ち着かなくなっていた。
ここで、私は優奈にある話を持ちかける。
最後にここで話しておきたかった。
「優奈。私がいなくなったらどうするの?」
私は心配そうに優奈に問いかけた。
「普通に何もなく暮らしてるよ。」
「わかりにくいと思ってたけど私、表では何もない風を装ってた。でも中を見たら苦しんで泣いてた私が出てきたんだ。夢に。」
私は優奈の二重人格ぶりに全身が震えてしまった。
「正直ね、驚いてるの。
高校でまさか出会えるなんて思わなかったよ。美術部で出会えた人が本当の従姉妹だったなんて。従姉妹だったらもっと早く知り合いたかったよ。」
「私もだよ。」
私も同じ気持ちだった。
もし小学校の時に知っていれば、他人に対しての見方が少し変わるようになっていたのにと後悔していた私だった。
しかし、優奈はあくびをした後みたいに目に涙を浮かべていた。
「私ね。中学生の時にすっごくびっくりしたんだ。」
「何を?」
私は優奈の発言に疑問を抱いていた。
「血だらけのあなたが中学のグラウンドでの朝礼で屋上から自殺をしようとしてたということをね。テレビでリアルタイムで見てたんだ。」
私は目を虚ろにしていたが、大きな音にビックリするように目を開かせた。
「そうだったんだ。」
という一言しか言えなかった。
「当時、思ってたんだ。私は同じ中学生なのにこんなに違うことってあるんだなって。しかも名前が公開されてたけど、それを聞いてとても慌てたの。まさか小学校の同級生だったなんて思わなかった。もし、私があの子だったら何をしてたのかなって思ってた。私がこんな目にあってしまうのではないかという恐怖が体に馴染んでしまったよ。」
「そうだったんだ。」
自殺未遂は全国ネットのニュースで中継になっていたほどだった。けど、私の家まで報道記者が押しかけてくることは一切なかった。
私もあの時は苦しかったという感情を遥かに超えて、死ななければならないという死刑を宣告されたように、義務感が私を襲った。
高校で優奈に会っていなかったら、私はとっくのとうに自殺を謀っていたのだろう。
「優奈は私の恩人かもしれない。」
と優奈に言い放った。
「ありがとう。」
優奈は私に抱きついてきた。
私の体はいつのまにかボロボロになっていた。
身体中の骨が浮き始めている。
こんなに脆くなった私の体を抱きしめてくれるなんて。従姉妹というのはこんなにも大切な存在だったんだと思い知らされる。
私たちはイルミネーションをバックに話をしていた。最後かもしれない写真も撮った。
2人とも笑っていた。
もしかしたら帰れるかもしれない。
もう一度先生に会いたい。
私はまだ大丈夫。まだ行ける。
という自信がついた。なぜこんなにも命の瀬戸際にこんなことができるのだろうか。
動物園のトイレで大量の血を吐いたのにも関わらず私は命が消え去るその瞬間まで一生懸命になっていた。
みんなが待ってくれる。
光のある未来に行かなきゃいけない。
私はまだ頑張れる。
私たちは急いで旅館に戻ろうと帰りの新幹線に乗った。雲すらないくらい夜だった。
ネオンに輝く建物がひとつもない。
ただ電線を繋ぐ櫓のようなものの小さな赤い光が見えるだけだった。
私はここで体調が急変した。
「はー、はー、はー、」
私は過呼吸になり、座ることができずに横たわっていた。
今見えるのは震えている手足だけだった。
私はもうそこまできている。改めて実感した。
制服は黒く、汚れがひどくてボロボロだった。そして血が大量に付着した。私の顔も優奈の手鏡で見せてもらったが、さらにひどくなっていた。
もっと長く行きたい人もたくさんいるのに、なぜ人は好きな時に死ぬことができないのか。
特に私みたいな余命宣告がある病気を持っている人はこのように感じることができるだろう。学生の自殺なんかよりずっと悔しい。
私だって成人してみたかった。
着物を借りて、それを着て成人式に出席して、垢抜ける私を見せたいという欲望も最近湧き上がってきたのだ。
それなのに私は16でこの世を去ってしまうことになる。いや本当に死んでいたのはもっと前かもしれない。妹が助けてくれなかったら私はもう雲の上にいることになる。
私はとうとう手足の震えが痺れに変わった。
麻痺寸前まで陥った。
「だ、めだ。もう、動けない。」
「由香里!ここで死なないでよ!」
優奈も叫びまくった。
「この電車にお医者さんはいらっしゃいませんか?」という医者を探す方法としてよくあることだが、現実ではそうは行かなかった。
急いで裕太に電話をした。
「もしもし!由香里がどんどん衰弱してる!旅館までなんとか私が持ち帰るから待っててね!」
といい直ぐに切った。
「後もう少しの辛抱だからね。」
私はもう何も見えなかった。新幹線の走行音と人の話し声しか聞こえなかった。
私たちは2時間後、午後10時に札幌に戻ってきたのだ。
優奈は由香里を抱えて2人分の荷物を持ちながら恐る恐る改札を出た。
秋だったので、特別に暑いとか寒いとかは全くなかった。木々の葉っぱが橙になる前だった。
「おい!お前たち!」
声が太かった。その声の主は悠木先生だった。
「由香里、もうボロボロじゃないか。学校で普段明るく優奈と談笑していて、朝旅館から笑顔で見送ったあの由香里はもう見れないのか。」
優奈はこの一日の間私に起こったことを片っ端からメモをし、先生に渡した。そして、事細かく話したという。
「ありがとう優奈。実はなかなか戻ってこなくて心配してたんだ。優奈から裕太先生に電話が来たのを隣で聞いていたんだ。駅前にいれば俺が担いで旅館で運んであげるよ。」
「ありがとうございます先生。」
「お前も結構苦労しただろう。」
「いいえ、従姉妹ですから、これぐらいのことはしないと。」
「やっぱいい奴を従姉妹に持ったな。由香里。」
「は、い、おかげ、ですく、われま、した。」
体が衰弱していくせいか、私は普通に喋れなくなっていった。
「あいつらが心配してるんだ。早く行こう。」
「は、い、おね、がいし、ます。」
誰かの靴の音が聞こえる。
コンクリートの道路を全力疾走しているような感じだった。
「先生。由香里はどんどん青ざめてきてます。」
ゆうなが先生に言うと、着ていたTシャツを脱いだ。
「何してるんですか?」
「このぐらいはしておかないと風邪引くだろ。」
目が覚めたら、大人の背中に抱かれていた。
由香里の背中に先生のTシャツがかけられた。
「なんか、あった、かい、」
上半身裸になった先生はさらに加速していった。鍛え抜かれた肉体、くっきり割れている腹筋に釘付けになるわけがなかった。
「これで走りやすくなった。」
気がついたら私は旅館の前にいた。
ついに帰ってこれたのだ。
今日の夜は帰ってこないって断言していたが、不可能を可能に変えることが今できたんだ。
私の視界には多くの生徒がいた。
心配そうに見る人や青ざめている顔に怯えている人もいた。
「由香里!」
「大丈夫!」
「大丈夫か?」
みんなの声が聞こえる。しかし、ただの叫び声にしか聞こえなかった。
「お前ら、もう夜遅いんだからあとは先生に任せて部屋に帰りなさい。」
「何でですか?」
「だってクラスメイトですよ?人が死ぬって言うのにみられないって不謹慎です。」
「今までいじめてきた奴の言うことじゃねえだろ!」
「お前らなんかあれじゃん。いじめてた奴が死ぬから正直嬉しいんだろ?居なくならないでって言う程度の低い芝居しかできないんだ。由香里のいじめが発覚したときに言おうと思ったのにあの時は怖かったんだ。」
先生の怒りの怖さにみんなは怯えた。
「確かにそうだったね。なんでこの人をいじめてきたんだろう。」
「確かにそうね。間違ってたわ。」
「ごめんなさい!」
クラスメイトみんながボロボロの私に向かって謝って頭を下げた。
「いいよ。別に、気に、してない、から。」
ここにいるみんなは涙以外の感情はすでになくなっていたかのように、涙が出て、鼻を啜る音が聞こえていた。
「バタン!!!!!」
由香里は先生の首に手を組んでいたのに、手の力がなくなり、落ちて倒れてしまった。
私は再び意識を無くした。目を瞑ったまま何も動くことはなかった。
うっすらと明るくて、淡い色の光が見えてきた。私は天使になったかのように思えた。
みんなはもういない。天国に旅立ってしまったのか。もう上で見守るしかないのか。
「はっっっ!」
私は目が覚めた。どうやら夢を見ていたようだ。見渡すと旅館のベットにいて、そこにはみんながいた。
それと同時に私の嫌な思い出や記憶もどこかに置いてきたように忘れていた。
「あれ?優奈は?」
「優奈はいま下にいるよ。待っててね。」
先生と生徒たちみんなが見守ってくれていた。
「なんで、いるの?」
「当たり前だよ。見守りにきたんだよ。さっき聞いてみたんだ、もう時間がないってさ。」
生徒の1人が言った。
「もう、みんな知ってるって。」
先生が寂しそうに言った。
「なんでですか?まだ助けられるかもしれないじゃないですか?って聞いたんだ。もう時間がなくて治す最中に絶命してしまうかもって、言われたんだ。」
「ちょっと席を外してもらえないか?2人きりで話がしたい。」
先生の言葉通りに生徒たちは由香里のいる部屋から姿を消し、それぞれの部屋にチリチリに戻った。
「由香里、最後に言っておきたいことがある。」
「教師になって俺は初めてこのクラスの担任になったんだ。いろんな先生から色々と言われたよ。」
「初めてなんだから失敗はたくさんしろ。」
「このぐらいの仕事はやって当然なんだからもっとやれ。」
「けどな。由香里を見たらそう言うことを言っている暇はなかったと思ったんだ。実は俺、消防士になろうとしていたんだ。大学で公務員系の仕事に就きたいと思って、訓練も頑張った。4年生の9月に近くの消防署での就職が決まったんだが、人数不足で署内が回らなくなり、署自体が廃業になってしまったんだ。」
先生は過去のことを話し出した。
「でも俺は社会全般が好きだった。社会の教員を目指そうと消防署での訓練を受けていると同時に教員試験の勉強もやってたんだ。無事に合格して教師になって、この学校に来てお前に出会うことができた。消防士の訓練を受けていたからか病弱なお前をいろいろなところで助けることができたよ。肉体的、精神的にも全て由香里に自分ができることを全て尽くすことができた。好きな職業には就けなかったけど、教師でも人を助けることはできるんだってお前がいてくれたおかげで本当に思えるようになったよ。だからもしお前が亡くなったとしても、みんな最後まで諦めずに何かに取り組むだろう。俺もお前の分まで頑張るからな。由香里。今まで本当にありがとう。俺は悔しいぞ。もっとたくさんそばで一緒にいたかったぞ・・・。」
先生は大号泣していた。
持っていたハンカチでは受け止めきれなかった。
先生の人生経験から私がいてくれたおかげで今の先生があると言うことを教えてくれた。
先生の人生も壮絶だったのかもしれない。
人それぞれ違う人生を送っているのは不思議なことだと思う。
「コンコン」
ドアの音がした。
ガチャ。とドアを開けると優奈がいた。
「由香里、お父さんから聞いたんだ。もう時間がないんでしょ?」
「そうみたいだな。優奈。先生も最後まで見届けるつもりだぞ。」
「先生。」
「私も由香里の従姉妹で本当に良かったと思ってる。本当にありがとう。」
するとある女性の声が聞こえた。
「由香里!あなたなの?生きてるの?」
そう叫んだ人物は由美だった。
「お母さん、な、んで?」
私の視界にかすかにお母さんの姿があった。私は必死に手を差し伸べようとしていた。
「あの時にお別れしようと思ってたんだけどね。どうしても伝えたいことがあって北海道まで来てしまった。」
勝手にいなくなるなんてお母さんが許さないからって言われても今更遅いだろう。
実は仕事で行けなくなったのだが、
由美が勤めている会社は全国に数カ所の支所がある。その中で札幌支所に出張ができると聞いた途端に、部長に頭を下げてお願いをしたと言う。
そのことを聞いた他の人は驚いた。
「お別れの挨拶なしに見送られても困るよね。由香里。」
修学旅行前が本当に最後だと思っていた。けど、また会えた。生きててよかった。ここまで生きているのも奇跡としか言えない。
由美は由香里に本音を伝えた。
「由香里。ごめんね。お母さんあなたのこと見捨ててないからね。そんなこと全く思ってないよ。たしかに私たちは4人家族だった。けど、あなたが死んでしまったら私1人になってしまうけど、由香里や他の2人がいてくれたおかげで楽しかった。家族の暖かさを噛み締めて生きてきた。特に私は由香里と妹の由梨奈を産んでその後の育児が好きだった。毎日が刺激的だった。育児は誰もが一度はイライラしたりして投げ出してしまうことはほとんどの親にあり得ることだけど、私は全くなかったよ。みんな愛してた。私は大丈夫よ。1人でやってあげる自信が今ついた。だって3人が見守ってくれるんだもん。頑張って、生きるね。」
「由美さん。」
「俺も泣きそうだ。」
室内にいた全員が涙に誘われた。
これが本当の親子の絆だと思い知らされた。
裕太が部屋にきた。
「僕もあなたに人生を救われました。あなたがいてくれたおかげで優奈と従姉妹だって気づくことができたんだから。」
「そうだったんですね。言ってくれたんだ。」
「もしかして恵のことですか?」
「うん。一番口が硬かった人なので全然話してくれなかったでしょう。でも裕太さんが説得してくれたからこんな嬉しい結果なったんです。私たち姉妹の関係がよくなれそうな気がします。ありがとうございます。」
「いいえ、私は当たり前のことをしただけてますよ。」
もう午後11時55分か。
「そろそろ1人にしてあげてください。私はここで診ますので。」
みんなは由香里の客室から退室した。
外から見守ろうとしてくれたときに。
「ピーピーピーピー」
事は急転した。
私の脈、心拍数が低下していく。
「大丈夫ですか!聞こえてますか!由香里さん!私です!裕太です!」
裕太は必死で叫んだが、私は起きることはなかった。
心拍数等が低下しているうちに呼吸器をつけられた。発作も起こっていたが、今直してしまうと、完璧に私が絶命してしまうからしなかったのだ。
まだ鳴り止まない。
サイレンの音がずっと鳴りっぱなしだ。
由美たちが室内に入ってきて、
「由香里!大丈夫!まだ大丈夫!」
みんな私の冷たくて青ざめた手を握ってくれた。命の瀬戸際にある私をこんなに思ってくれているなんて思わなかった。
全て私の思い込みは皆無だった。
私は最後に気力を振り絞ってこうみんなに伝えた。
「さい、ごま、で、あり、がとう。がんばっ、て、い、生きて、ね。」
私の最後の叫びに涙が止まらなかった一同。しかし、これを伝えた後、私は意識を無くした。
もう時間が来てしまったようだ。
23時59分のことだった。
もうすぐ日にちが変わる。
その時まで私は頑張って息をしよう。
「ピーピー」
サイレンが急に消えた。
日にちが変わって、0時00分に脈、心拍数が0になった。
急にいなくなってしまった。
みんなは現実を見ている気分だろう。
今までたくさんの時間を過ごしてきた人間が、息絶えた瞬間を想像できないに違いない。
たとえ泣いたとしても私は戻ってこないんだと。
1分前の私ならまだ何か声をかける事はできたのに。
翌日、私の訃報を伝えると、
みんなは当然のように泣き崩れていた。
「なんで最後が見れなかったんだよ。」
と嘆くものもいた。
その中で優奈が1番悲しんでいた。
やっといとこを見つけることが出たのに、すぐにいなくなってしまうことが彼女の頭の中では考えられなかった。たとえ私の余命宣告が言われたとしても。
下を俯いていて、何をしようとしているのかわからなかった。
彼女の中で私が死んだ後に自決を考えていたが、親しい人が死んでしまったことから、
この人の分まで行けてやるぞと言う闘争心に優奈は燃えていた。
まるで、私が妹と死別するみたいに。
長かった4日間の修学旅行を終え、
学校に着いたのは最終日の夕方だった。
みんな誰も笑ってはいなかった。
とても気まずくなってしまったが、これで私の存在が1人でも多く残るのならそれでいいのだと、生前思っていた。私の遺体も同時に学校に着いた。先生たちが見ると、白骨化していた。
「まさかこんなことになる事は分かっていても泣いてしまうものなんだ。」
今まで生徒だった人の白骨化死体を見ると、
味わったことのないとんでもない感情に襲われてしまうのだ。
「あいつの分まで頑張って生きるぞ。
俺の恩人よ。」
悠木先生は夕暮れが山に沈み、暗くなる空に向かって決心した。
第十七話に続く。
0
あなたにおすすめの小説

Hand in Hand - 二人で進むフィギュアスケート青春小説
宮 都
青春
幼なじみへの気持ちの変化を自覚できずにいた中2の夏。ライバルとの出会いが、少年を未知のスポーツへと向わせた。
美少女と手に手をとって進むその競技の名は、アイスダンス!!
【2022/6/11完結】
その日僕たちの教室は、朝から転校生が来るという噂に落ち着きをなくしていた。帰国子女らしいという情報も入り、誰もがますます転校生への期待を募らせていた。
そんな中でただ一人、果歩(かほ)だけは違っていた。
「制覇、今日は五時からだから。来てね」
隣の席に座る彼女は大きな瞳を輝かせて、にっこりこちらを覗きこんだ。
担任が一人の生徒とともに教室に入ってきた。みんなの目が一斉にそちらに向かった。それでも果歩だけはずっと僕の方を見ていた。
◇
こんな二人の居場所に現れたアメリカ帰りの転校生。少年はアイスダンスをするという彼に強い焦りを感じ、彼と同じ道に飛び込んでいく……
――小説家になろう、カクヨム(別タイトル)にも掲載――

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。
ピコサイクス
青春
大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。
真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。
引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。
偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。
ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。
優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。
大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。
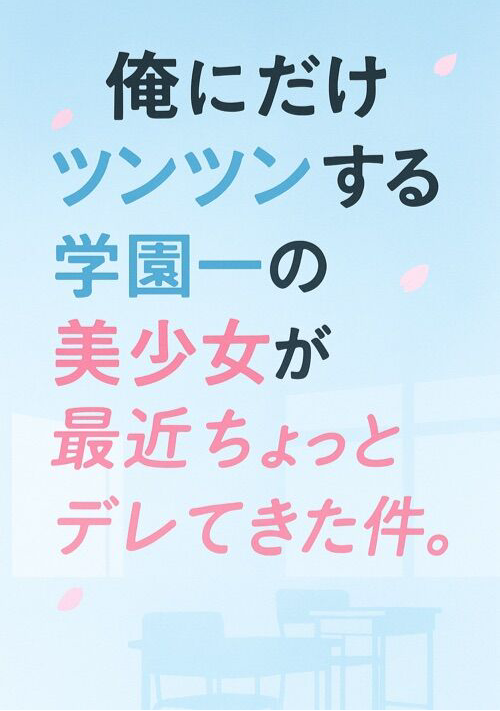
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

現実とサキュバスのあいだで ――夢で告白した相手が、同居を始めた話
そう
青春
ある日家に突然現れた謎のサキュバスのホルさん!
好感度はMAXなようで流されるがまま主人公はホルさんと日常を過ごします。
ほのぼのラブコメというか日常系小説
オチなどはなく、ただひたすらにまったりします
挿絵や文章にもAIを使用しております。
苦手な方はご注意ください。

妹の仇 兄の復讐
MisakiNonagase
青春
神奈川県の海に近い住宅街。夏の終わりが、夕焼けに溶けていく季節だった。
僕、孝之は高校三年生、十七歳。妹の茜は十五歳、高校一年生。父と母との四人暮らし。ごく普通の家庭で、僕と茜は、ブラコンやシスコンと騒がれるほどではないが、それなりに仲の良い兄妹だった。茜は少し内気で、真面目な顔をしているが、家族の前ではよく笑う。特に、幼馴染で僕の交際相手でもある佑香が来ると、姉のように慕って明るくなる。
その平穏が、ほんの些細な噂によって、静かに、しかし深く切り裂かれようとは、その時はまだ知らなかった。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。

キャバ嬢(ハイスペック)との同棲が、僕の高校生活を色々と変えていく。
たかなしポン太
青春
僕のアパートの前で、巨乳美人のお姉さんが倒れていた。
助けたそのお姉さんは一流大卒だが内定取り消しとなり、就職浪人中のキャバ嬢だった。
でもまさかそのお姉さんと、同棲することになるとは…。
「今日のパンツってどんなんだっけ? ああ、これか。」
「ちょっと、確認しなくていいですから!」
「これ、可愛いでしょ? 色違いでピンクもあるんだけどね。綿なんだけど生地がサラサラで、この上の部分のリボンが」
「もういいです! いいですから、パンツの説明は!」
天然高学歴キャバ嬢と、心優しいDT高校生。
異色の2人が繰り広げる、水色パンツから始まる日常系ラブコメディー!
※小説家になろうとカクヨムにも同時掲載中です。
※本作品はフィクションであり、実在の人物や団体、製品とは一切関係ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















