12 / 24
第一章
第十二話 『お茶会はじまりました』
しおりを挟む
襲撃の夜からしばらくの日数が経った今も、変わらずエセルバート様の家庭教師は不審な動きを繰り返していた。
勉強部屋の結界は毎回張られ、中でなにが行われているかまったくわからない。
たまに顔を合わせるが、いつも尊大な態度で声をかけてくる。言葉は下手に出ているが、小娘だと馬鹿にしていることがありありとわかった。舐めるような視線を寄こすことも不快だ。
先代伯爵の威光を借りているにしても、ここまで大きな顔をできるのは何故なのだろう。
女中のロナに聞いてみたが、彼女が入ったころにはすでにこのような状況だったのだという。庭師のトラシスさんも、先代が連れてきた家庭教師だということ以外は詳しく知らないそうだ。
ただ、亡くなる前の先代伯爵は屋敷内で絶対的存在で、誰も逆らえなかったのだという。息子である現マティアス卿ですらもだ。
もういない先代伯爵は今も、この屋敷を支配しているのかもしれない。
そんなある日、ちょっとした変化に気づいた。
エセルバート様の勉強部屋の結界が、下方まで広がっていたのだ。
四階にある勉強部屋から三階の半ばまで、結界とは思われないよう小細工をされた跡が外からでもわかる。とはいえ、余程気を付けていないとわからないだろう。訪問するたびに観察していたから気づけたのだ。
「ねぇロナ、近々お屋敷で催し物でもあるの?」
「いいえ、そういった話は出ておりませんが……。なにかありましたか?」
帰りがけにロナに尋ねてみるも、不思議そうに首を傾げられた。
「西棟が少し気になって……。ごめんなさい、きっと気のせいね」
「シャルティーナ様、以前も気になさっていましたね。わたしにはなーんにも感じられませんけど」
さっぱりとした口調でロナが言い切る。伯爵家の女中としては少々いただけないかもしれないが、彼女のこういったところが好ましいと思う。
わたしは帰宅してすぐ、リヴィ様の元へ青い小鳥を飛ばした。これはリヴィ様にも相談すべきことだろう。
あの男がなにを考えているのかわからないが、ひとりよりふたりならばなにか思いつくかもしれない。
次の日の朝、すぐにリヴィ様から招待状が届いた。
対外的には、コートナー伯爵からの茶会の招待状だ。マティアス伯爵家でお会いしたときにゆっくり話をしたいと約束したことを理由に、個人的な招待をさせて欲しいとの文面が書かれている。茶会とはいえ、参加者はわたしとリヴィ様だけなのだけれど。
「御師様、本日はコートナー卿にご招待いただいていますので行ってまいります」
「ああ、例の若き伯爵か」
「はい」
「コートナー卿は魔法に興味があるようだからね。以前もここへ訪ねてきて、魔法とはなんなのかとあれこれと聞いてきた」
「そうだったのですか」
「歳が近い方が話しやすいだろう。気をつけて行っておいで」
「はい。昼食はいつもどおり用意しておきましたので、きちんと食べてくださいね」
「はいはい、ありがとう」
わたしの言葉をのん気にかわし、御師様がひらりと手を振る。本当に大丈夫だろうか。
リヴィ様が用意してくれた馬車に乗り込みながら、夕飯までには必ず帰らなければと考えた。
馬車が連れてきてくれた場所は、王都内のコートナー伯爵邸だった。
マティアス伯爵家も素晴らしい屋敷と庭園だったが、こちらも負けてはいない。
深い緑色の屋根が印象的な風格ある屋敷と、庭園の植物がうまく調和している。小さな滝のような噴水は、石畳で囲まれた浅い池に繋がり、水草が花を咲かせる大きな池へと繋がっていた。
重厚な表玄関から、見目麗しい青年が優雅な足取りで馬車へ近づいてくる。リヴィ様だ。
微笑みを浮かべ、馬車から降りるわたしに手を差し伸べてくれる姿は、初めてお会いしたときと変わりがなく、ほっと息を吐く。
「コートナー伯爵、本日はお招きいただき光栄にございます」
「やぁ、シャルティーナ嬢。わざわざ来てもらってすまないね。君が襲われたと聞いたときは、心配で胸が潰れるかと思ったよ。元気そうでよかった」
「事々しいですわ、これでも魔法士見習いです」
「それとこれとは話が別だ。君を心配しているものはここにもいるのだと、覚えておいて」
「ありがとうございます、コートナー卿」
まるで妹にでも言い聞かせるような口調で、リヴィ様が困った笑みを浮かべた。
そういえば妹君が三人いらっしゃったはず。わたしも同じ括りとして思われているのだろうか。それにしてはうちの兄と全然違う叱り方だと、おかしくなって小さく笑った。
リヴィ様が通してくださった部屋は、友人を招くときに使用する応接室だった。
「向こうの応接室は堅苦しいからね。ここは気楽に過ごせるよう、控えめにしつらえているんだ。楽にして欲しいな」
肌触りの良い生地が張られているふかふかの椅子に導かれ、緊張しながら腰を下ろす。さすが伯爵家、控えめといっても高級品で揃えられているらしい。
ふと、すぐ傍に置かれた飾り棚が目に入った。落ち着いた木の色合いで作られたその上に、窓からの光を受けて様々な色に変化する石の置物が飾られている。
「リヴィ様、もしかしてそれは、七色石の原石では……?」
「そうだよ。気づいたかい?」
悪戯っぽく笑って、リヴィ様が七色石の表面を指でなぞった。
「これは父の代に造られた魔道具でね、ふたつで一組のものなんだ」
「なんのための魔道具ですか?」
「簡単に言えば、使い勝手の悪い電話だね。もうひとつの原石を持っている相手にだけ繋がるんだよ」
「緊急時の伝達手段としては充分では?」
「それが、そういまくはいかなくてね。携帯性がないからどこでも使えるわけじゃない。こんなに大きい七色石をふたつ用意するために莫大な金が要る。その割に繋がるところが一ヶ所だけというのも残念じゃないか。スマホを知っている身としては、もどかしいばかりだよ」
「確かに」
リヴィ様が大げさに肩を竦める。わたしは苦笑しながら頷いた。
伯爵家だから造ることのできた魔道具なのだろう。こんな大きな原石、研究所でも見たことがない。一体どれだけ費用がかかるのやら。
費用度外視の魔道具といえば、御師様からいただいた銀の腕輪を思い出した。今も左手首に収まっているそれは、もうただの腕輪になっているけれど、魔法の触媒にもなるとおっしゃっていた。
もしかしたら、魔力を溜めておける器になるのではないだろうか。いざというときの補給魔道具として使えるのではないか。七色石のきらめく表面を見つめながら考える。
そんなことを考えていたら、品の良い老年の侍女がお茶とお菓子を持ってきてくれた。
「我が家特製の茶だよ。他とは少し違う配合をしていてね。さぁどうぞ」
目の前に置かれたカップからかぐわしい香りが漂ってくる。一口いただくと、うっとりするほど心地良い香りが鼻腔に広がり、僅かな苦みを残しながらお茶がするりと喉をとおっていった。
「おいしいです……! こんなにおいしいお茶をいただいたのは初めて……!」
「よかった、気に入ってくれて嬉しいよ」
輝くような笑みを浮かべ、リヴィ様が肘掛けに頬杖をついてわたしを見つめた。
――やっぱりイケメンってずるい。
勉強部屋の結界は毎回張られ、中でなにが行われているかまったくわからない。
たまに顔を合わせるが、いつも尊大な態度で声をかけてくる。言葉は下手に出ているが、小娘だと馬鹿にしていることがありありとわかった。舐めるような視線を寄こすことも不快だ。
先代伯爵の威光を借りているにしても、ここまで大きな顔をできるのは何故なのだろう。
女中のロナに聞いてみたが、彼女が入ったころにはすでにこのような状況だったのだという。庭師のトラシスさんも、先代が連れてきた家庭教師だということ以外は詳しく知らないそうだ。
ただ、亡くなる前の先代伯爵は屋敷内で絶対的存在で、誰も逆らえなかったのだという。息子である現マティアス卿ですらもだ。
もういない先代伯爵は今も、この屋敷を支配しているのかもしれない。
そんなある日、ちょっとした変化に気づいた。
エセルバート様の勉強部屋の結界が、下方まで広がっていたのだ。
四階にある勉強部屋から三階の半ばまで、結界とは思われないよう小細工をされた跡が外からでもわかる。とはいえ、余程気を付けていないとわからないだろう。訪問するたびに観察していたから気づけたのだ。
「ねぇロナ、近々お屋敷で催し物でもあるの?」
「いいえ、そういった話は出ておりませんが……。なにかありましたか?」
帰りがけにロナに尋ねてみるも、不思議そうに首を傾げられた。
「西棟が少し気になって……。ごめんなさい、きっと気のせいね」
「シャルティーナ様、以前も気になさっていましたね。わたしにはなーんにも感じられませんけど」
さっぱりとした口調でロナが言い切る。伯爵家の女中としては少々いただけないかもしれないが、彼女のこういったところが好ましいと思う。
わたしは帰宅してすぐ、リヴィ様の元へ青い小鳥を飛ばした。これはリヴィ様にも相談すべきことだろう。
あの男がなにを考えているのかわからないが、ひとりよりふたりならばなにか思いつくかもしれない。
次の日の朝、すぐにリヴィ様から招待状が届いた。
対外的には、コートナー伯爵からの茶会の招待状だ。マティアス伯爵家でお会いしたときにゆっくり話をしたいと約束したことを理由に、個人的な招待をさせて欲しいとの文面が書かれている。茶会とはいえ、参加者はわたしとリヴィ様だけなのだけれど。
「御師様、本日はコートナー卿にご招待いただいていますので行ってまいります」
「ああ、例の若き伯爵か」
「はい」
「コートナー卿は魔法に興味があるようだからね。以前もここへ訪ねてきて、魔法とはなんなのかとあれこれと聞いてきた」
「そうだったのですか」
「歳が近い方が話しやすいだろう。気をつけて行っておいで」
「はい。昼食はいつもどおり用意しておきましたので、きちんと食べてくださいね」
「はいはい、ありがとう」
わたしの言葉をのん気にかわし、御師様がひらりと手を振る。本当に大丈夫だろうか。
リヴィ様が用意してくれた馬車に乗り込みながら、夕飯までには必ず帰らなければと考えた。
馬車が連れてきてくれた場所は、王都内のコートナー伯爵邸だった。
マティアス伯爵家も素晴らしい屋敷と庭園だったが、こちらも負けてはいない。
深い緑色の屋根が印象的な風格ある屋敷と、庭園の植物がうまく調和している。小さな滝のような噴水は、石畳で囲まれた浅い池に繋がり、水草が花を咲かせる大きな池へと繋がっていた。
重厚な表玄関から、見目麗しい青年が優雅な足取りで馬車へ近づいてくる。リヴィ様だ。
微笑みを浮かべ、馬車から降りるわたしに手を差し伸べてくれる姿は、初めてお会いしたときと変わりがなく、ほっと息を吐く。
「コートナー伯爵、本日はお招きいただき光栄にございます」
「やぁ、シャルティーナ嬢。わざわざ来てもらってすまないね。君が襲われたと聞いたときは、心配で胸が潰れるかと思ったよ。元気そうでよかった」
「事々しいですわ、これでも魔法士見習いです」
「それとこれとは話が別だ。君を心配しているものはここにもいるのだと、覚えておいて」
「ありがとうございます、コートナー卿」
まるで妹にでも言い聞かせるような口調で、リヴィ様が困った笑みを浮かべた。
そういえば妹君が三人いらっしゃったはず。わたしも同じ括りとして思われているのだろうか。それにしてはうちの兄と全然違う叱り方だと、おかしくなって小さく笑った。
リヴィ様が通してくださった部屋は、友人を招くときに使用する応接室だった。
「向こうの応接室は堅苦しいからね。ここは気楽に過ごせるよう、控えめにしつらえているんだ。楽にして欲しいな」
肌触りの良い生地が張られているふかふかの椅子に導かれ、緊張しながら腰を下ろす。さすが伯爵家、控えめといっても高級品で揃えられているらしい。
ふと、すぐ傍に置かれた飾り棚が目に入った。落ち着いた木の色合いで作られたその上に、窓からの光を受けて様々な色に変化する石の置物が飾られている。
「リヴィ様、もしかしてそれは、七色石の原石では……?」
「そうだよ。気づいたかい?」
悪戯っぽく笑って、リヴィ様が七色石の表面を指でなぞった。
「これは父の代に造られた魔道具でね、ふたつで一組のものなんだ」
「なんのための魔道具ですか?」
「簡単に言えば、使い勝手の悪い電話だね。もうひとつの原石を持っている相手にだけ繋がるんだよ」
「緊急時の伝達手段としては充分では?」
「それが、そういまくはいかなくてね。携帯性がないからどこでも使えるわけじゃない。こんなに大きい七色石をふたつ用意するために莫大な金が要る。その割に繋がるところが一ヶ所だけというのも残念じゃないか。スマホを知っている身としては、もどかしいばかりだよ」
「確かに」
リヴィ様が大げさに肩を竦める。わたしは苦笑しながら頷いた。
伯爵家だから造ることのできた魔道具なのだろう。こんな大きな原石、研究所でも見たことがない。一体どれだけ費用がかかるのやら。
費用度外視の魔道具といえば、御師様からいただいた銀の腕輪を思い出した。今も左手首に収まっているそれは、もうただの腕輪になっているけれど、魔法の触媒にもなるとおっしゃっていた。
もしかしたら、魔力を溜めておける器になるのではないだろうか。いざというときの補給魔道具として使えるのではないか。七色石のきらめく表面を見つめながら考える。
そんなことを考えていたら、品の良い老年の侍女がお茶とお菓子を持ってきてくれた。
「我が家特製の茶だよ。他とは少し違う配合をしていてね。さぁどうぞ」
目の前に置かれたカップからかぐわしい香りが漂ってくる。一口いただくと、うっとりするほど心地良い香りが鼻腔に広がり、僅かな苦みを残しながらお茶がするりと喉をとおっていった。
「おいしいです……! こんなにおいしいお茶をいただいたのは初めて……!」
「よかった、気に入ってくれて嬉しいよ」
輝くような笑みを浮かべ、リヴィ様が肘掛けに頬杖をついてわたしを見つめた。
――やっぱりイケメンってずるい。
0
あなたにおすすめの小説

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

オバサンが転生しましたが何も持ってないので何もできません!
みさちぃ
恋愛
50歳近くのおばさんが異世界転生した!
転生したら普通チートじゃない?何もありませんがっ!!
前世で苦しい思いをしたのでもう一人で生きて行こうかと思います。
とにかく目指すは自由気ままなスローライフ。
森で調合師して暮らすこと!
ひとまず読み漁った小説に沿って悪役令嬢から国外追放を目指しますが…
無理そうです……
更に隣で笑う幼なじみが気になります…
完結済みです。
なろう様にも掲載しています。
副題に*がついているものはアルファポリス様のみになります。
エピローグで完結です。
番外編になります。
※完結設定してしまい新しい話が追加できませんので、以後番外編載せる場合は別に設けるかなろう様のみになります。

異世界に転移してしまった私、古民家をもらったのでカフェを始めたら大盛況。国王陛下が頻繁に来るのですが、どうしたらいいですか?
来栖とむ
ファンタジー
ブラック企業で疲れ果てた30歳の元OL・美里(みさと)が転移した先は、見渡す限りの深い森。
そこで彼女が授かったのは、魔女の称号……ではなく、一軒の**「日本の古民家」**だった!
亡き祖母が遺したその屋敷には、異世界では失われたはずの「お醤油」「お味噌」「白いお砂糖」という禁断の調味料が眠っていて――。
「えっ、唐揚げにそんなに感動しちゃうの?」
「プリン一口で、国王陛下が泣いちゃった……!?」
おにぎり、オムライス、そして肉汁溢れるハンバーグ。
現代日本の「当たり前」が、この世界では常識を覆す究極の美食に。
お掃除のプロな親子や、お忍びの王様、さらにはツンデレな宮廷料理人まで巻き込んで、
美味しい香りに包まれた、心もお腹も満たされるスローライフが今、始まります!
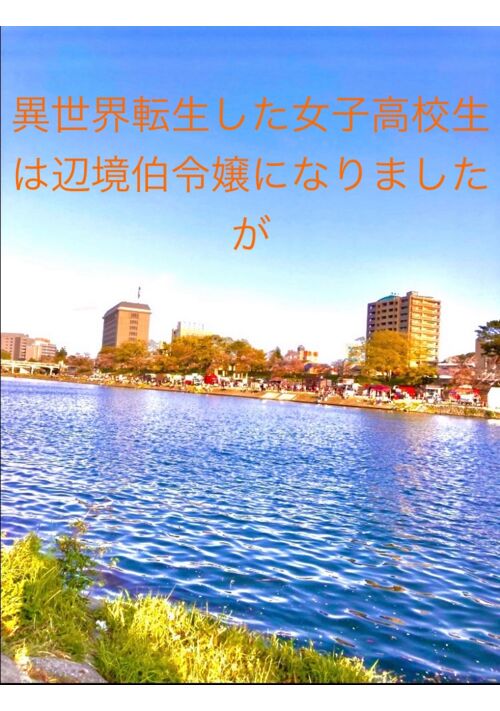
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

神様の忘れ物
mizuno sei
ファンタジー
仕事中に急死した三十二歳の独身OLが、前世の記憶を持ったまま異世界に転生した。
わりとお気楽で、ポジティブな主人公が、異世界で懸命に生きる中で巻き起こされる、笑いあり、涙あり(?)の珍騒動記。

悪役令嬢の追放エンド………修道院が無いじゃない!(はっ!?ここを楽園にしましょう♪
naturalsoft
ファンタジー
シオン・アクエリアス公爵令嬢は転生者であった。そして、同じく転生者であるヒロインに負けて、北方にある辺境の国内で1番厳しいと呼ばれる修道院へ送られる事となった。
「きぃーーーー!!!!!私は負けておりませんわ!イベントの強制力に負けたのですわ!覚えてらっしゃいーーーー!!!!!」
そして、目的地まで運ばれて着いてみると………
「はて?修道院がありませんわ?」
why!?
えっ、領主が修道院や孤児院が無いのにあると言って、不正に補助金を着服しているって?
どこの現代社会でもある不正をしてんのよーーーーー!!!!!!
※ジャンルをファンタジーに変更しました。

【本編完結】転生令嬢は自覚なしに無双する
ベル
ファンタジー
ふと目を開けると、私は7歳くらいの女の子の姿になっていた。
きらびやかな装飾が施された部屋に、ふかふかのベット。忠実な使用人に溺愛する両親と兄。
私は戸惑いながら鏡に映る顔に驚愕することになる。
この顔って、マルスティア伯爵令嬢の幼少期じゃない?
私さっきまで確か映画館にいたはずなんだけど、どうして見ていた映画の中の脇役になってしまっているの?!
映画化された漫画の物語の中に転生してしまった女の子が、実はとてつもない魔力を隠し持った裏ボスキャラであることを自覚しないまま、どんどん怪物を倒して無双していくお話。
設定はゆるいです

【完結】乙女ゲーム開始前に消える病弱モブ令嬢に転生しました
佐倉穂波
恋愛
転生したルイシャは、自分が若くして死んでしまう乙女ゲームのモブ令嬢で事を知る。
確かに、まともに起き上がることすら困難なこの体は、いつ死んでもおかしくない状態だった。
(そんな……死にたくないっ!)
乙女ゲームの記憶が正しければ、あと数年で死んでしまうルイシャは、「生きる」ために努力することにした。
2023.9.3 投稿分の改稿終了。
2023.9.4 表紙を作ってみました。
2023.9.15 完結。
2023.9.23 後日談を投稿しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















