24 / 24
第一章
第二十四話 『新しい日々がはじまりました』
しおりを挟む
「シャルティーナ様、旦那様がお呼びです」
夫人の部屋から戻る途中、ダストンさんがわたしを呼び止めた。丁寧な言葉に頷き、執務室までついていく。
中にはすでにマティアス卿がいらした。革張りの椅子を勧められ、女中が温かい茶を出してくれる。卿が片手で合図をすると、使用人たちは静かに部屋を出ていった。ダストンさんだけが残り、扉の近くで控えている。
「半ば住み込みのような形になってしまったが、不自由はないか、シャルティーナ」
「ご配慮いただきありがとうございます、マティアス卿。とてもよくしていただいております。その上、伯爵家の書庫まで拝見できるなど夢のようですわ」
「君のおかげで娘たちが助かったのだ。そのくらいは礼にもならん」
そう言って主人席へ座った卿は、肘掛けに頬杖をつき小さく息を吐いた。
「まさか先代が煩いの種を遺していたとはな。娘たちを伯爵家の者として立派に育てようと思っていたとはいえ、あのような……。すべて、当主であるわたしの失態だ」
「賊は巧妙な魔法を使っておりました。卿がお気づきになられなかったこと、無理もありません」
表情こそ変わっていないが、後悔がにじみ出る声音で卿が呟く。わたしは思わず茶器を置き、卿へ向き直った。
リンドールたちの計画的な犯行は、魔力がないものたちにはその一端すら感じ取れなかっただろう。なにかがおかしい、ただそれだけしか理解できなかったはずだ。
「先代は魔力のある者を屋敷から追い払った。エセルの乳母も魔力があったため、突然解雇を言い渡されている。その意図にもっと早く気づいていたならば、先代が存命中であったとしても対策はできただろうが……。すべては今更の話だ」
膝の上で手を組み、椅子に深く沈み込んだ卿が天を仰ぐ。己の力不足を嘆いているのだろうか。
「先代は、子の立場から見ても非情なお方だった。家名を守るためには身内ですら使い捨てる。親としての愛情を注いでもらった記憶などまったくない。わたしはダストンに育てられたようなものだ」
卿の言葉は、今まで見聞きした話を裏付けるものだった。やはり先代卿は周囲を支配し続けたのだろう。それは現マティアス卿が子供だったころから、いや、先代卿がこの家を継ぐ前から始まっていたのかもしれない。
「恐れながら旦那様」
「なんだ」
それまで静かに控えていたダストンさんが言葉を挟んだ。
「三十年ほど前まで我が王国は内政が不安定、三国の関係も良好とは言えませんでした。その時代を生きてきたお方でございます。非情にならざるを得なかったのではないかと」
「わかっている、父も見えない苦労をしていたのだろう。……しかし実の孫にあのような仕打ちなど、到底許されることではない」
苦々しい表情でマティアス卿が息を吐く。実父だからこそ、先代がなにをしようとしていたのか、そのためにどんな手段を選んでいたのか、思うことがあるのだろう。
隣り合う二国を含めた三国同盟は、今でこそ平穏に均衡を保っている。
だが五十年ほど前から始まった三国間の領土争いの爪痕は、未だ各地に残ったままだ。
更に三十年前には王国の王位継承権を争い、王家、貴族間で血生臭い事件が多発した。それ以来、王家の血を引く方は随分少なくなってしまったと聞く。
そういった背景は理解できる。できるのだが、納得はできない。
「余計な口を挟みました。ご無礼お許しください」
「構わない、お前は良く仕えてくれている」
「もったいないお言葉です」
ダストンさんは表情を変えることもなく、背筋を綺麗に伸ばしたまま頭を下げた。読めない方だけれど、そのくらいの力量がなければ伯爵家の家令は務められないのだろう。
わたしはまだまだ未熟だと己を振り返っていると、マティアス卿がこちらを振り返って微笑んだ。
「シャルティーナ、今後はエセルのことも見てはもらえないだろうか」
「……え?」
思わぬ言葉に、少し間の抜けた声を上げてしまった。慌てて口許を押さえる。
「娘たちは君に懐いている。魔法士ルディの弟子である君ならば、立場的にも充分だ。もちろん給金も上げよう。どうかあの子たちを導いてくれないか」
ゆっくりと立ち上がった卿は、執務机の後ろにある窓の傍へ立ち、外へ目を向けた。美しい金の髪が光に反射し輝いている。
「三国間の国交は改善されてきたとはいえ、均衡を崩そうと企む輩が消えたわけではない。しかし、王国内での生活の自由は回復している。エセルもエリスも、貴族内であれば自由を許される時代だ。そうあるべく、当主であるわたしが動かなくてはならない」
窓から差し込む午後の光を浴びた卿の視線は、遠い未来を見ているようだった。上に立つものとして、そして父として、マティアス卿は新たな決意をされているのだろう。
この屋敷で家庭教師を任されてから、わたしの中の高位貴族への印象は、好意的な方へと変わった。そんな方々に仕えられるのならば、精一杯努めたいと思う。
「わたしでよろしければ、誠心誠意お仕えいたします」
「――娘たちを頼むよ」
振り返りながら微笑んだマティアス卿は、位など関係なく、家族を思う父親の表情をなさっていた。
もうお亡くなりになった先代伯爵はともかく、伯爵夫妻はエセル様たちのことを愛していらっしゃる。
先ほどの言葉のとおり、これまで先代の支配が強かったのだ。呪いのように家中に蔓延し、夫妻も、姉妹も、使用人たちすらもそれに囚われていた。
もしかしたら卿は、それを知った上で御師様に家庭教師の打診をしたのかもしれない。なにかを変えたいのだと、望みを託して。
だからと言って、幼い少女を虐待することは許されない。今まで放置していたという罪を償い、親子関係の修復もできたらいいのだけれど。
エセル様が本当の意味での悪役令嬢になる前に、お救いできてよかった。
おいしそうな焼き菓子を手に、リヴィ様がお見舞いに来てくださった。
「お手柄だったね、シャル」
うららかな昼下がり。心地よい風が吹く中庭に整えられた茶会用の机。置かれた籠の中を嬉しそうに覗き込んで、どれを食べようか選んでいる姉妹の様子に、ふたりでほっと息をつく。
「リヴィ様のおかげです。騎士団を呼んでくれたのはリヴィ様でしょう?」
「幼馴染が騎士団長だからね。例の七色石の魔道具は、騎士団長の執務室に繋がってるのさ。有効に使わないと」
そう言って、リヴィ様が嫌味のない笑顔で片目を瞑る。自分の顔がいいことをわかっている仕草だ。さすがイケメンは違う。
姉妹とは少し離れた木陰で、わたしたちは声を潜め話していた。侍女や女中の数は最低限だが、あまり聞かれたくないことだけに、内緒話のように見えてしまうのは仕方ないだろう。
「ゲームではエセル嬢の背景なんて描かれていなかったけれど、酷いものだったんだね。あんな風になってしまうのもわかるよ」
「ええ、本当に、酷いものでした……。あの状況が長年続いていたのかと思うと、遣りきれません」
最近増えてきた、エセル様の屈託のない笑顔。ゲームで描かれていた険しい表情からは想像できないほど、穏やかで優しい、少女らしい笑みだ。
楽しげな姉妹を見つめていると、リヴィ様が更に声をひそめて囁いた。
「でもこれで、『この世界』がゲームとは違うものであることが確実になってきた」
「……はい」
「これから先、悪役令嬢エセルバートは生まれない。主人公の前に立ちはだかることもない。余程のなにかが起こらなければ、の話だけれど」
「そう……ですね……」
リヴィ様の言葉に頷くが、頭の中には疑問ばかり浮かんでくる。わたしの様子に気付いたのだろう。リヴィ様は軽い笑みを浮かべ、片手をひらりと振った。
「前にも言っただろう? そもそも、僕や君が別の世界の記憶を持っていること自体、ゲームとは違うんだ。僕は元々攻略対象のはずなのに、その知識を持ち、君と出会ってエセル嬢を間接的に助けた」
おっしゃっていることは理解している。だが本当に違うのだろうか。
違うというなら、何故わたしたちに前世の記憶があるのだろう。
「理解はしているつもりなのですが、本当に伯ネスの世界ではないのかどうか、未だに確信できないのです」
「僕にもわからないが、個人的には違うと考えている。限りなく似た世界ではあるけれどね」
顎に手を当て、緩く腕を組んだリヴィ様は、わたしを真っ直ぐに見つめた。木漏れ日がお顔に落ち、時折瞳を金に輝かせている。
「主人公は偉大なる魔法士ルディに師事し、若きコートナー卿には騎士団長の幼馴染がいる。それは伯ネスでも同じだ。ただ、それ以降が違う。どのルートでも、エセル嬢が立ちはだかるはずだった」
「それが、変わってしまった。本当は伯ネスの世界なのに、わたしが記憶を持っているから、エセル様を助けたから……。そうも考えられませんか」
今まで考えていた不安を吐露すれば、リヴィ様は軽く目を瞠った。まるで意外だとでもいうように。
「確かに。だが、いたいけな少女を助けたことは正しいことだ。それを気に病むことはないよ」
「でも、そのせいで、リヴィ様の進む道まで変えてしまったとしたら……」
「僕の?」
胸の前で両手を握り締める。言葉にしたことによって、不安が形を持ってしまった。それが内側から侵食してくるように思えて、わたしは身体を震わせた。
「巻き込んでしまうだなんて、のん気なことを言ったけれど、最初からわたしがシャルティーナにならなければ、リヴィ様がこの世界へ転生することもなかったのかもしれない……」
そうだ、最初から始まっていた。わたしがシャルティーナとして生まれたときから、すべては始まっていたのだ。
十五歳のときの覚醒は、ただの通過点に過ぎない。
「以前、御師様に言われたのです。わたしは、良くも悪くも王国を変化させる、と」
「ルディ様がそんなことを?」
「わたしがいるから、世界が歪んだんだわ。そうとしか、思えない……」
身体の震えが止まらない。青い空、心地良い風、光を遮る雲もない穏やかな日和だというのに、巣食いはじめた不安は足元の大地すら不安定にさせているように思えた。
そっと、温かな掌が肩へ触れた。リヴィ様が気遣わしげな瞳を向けてくれている。
「少なくとも、僕に関しては、君が原因ではないことは確かだな」
「何故、断言できるのですか?」
「まずひとつ、僕は君よりも先に生まれている」
「あ……」
口許を上げて言い切るリヴィ様を見つめながら、思わず小さな声を上げてしまう。
リヴィ様は背筋を伸ばし、優雅な足取りで、中天から傾きかけた光の元へと歩んでいった。
「そしてもうひとつ。――君とは関係なく、前世の『わたし』自身が原因だからだよ」
振り返ったリヴィ様の瞳が、日差しを受けて金色に輝いている。微笑みを浮かべたお顔からは、なにも読み取ることができなかった。
「麗しいお嬢様たち、食べたいものは決まったかな?」
「ええ、リヴィエール様。わたくしはこれ、上に乗ったミシァンの蜜付けが宝石のようで綺麗だわ」
「わたくしのものはシビリアンの花びらがのっているの! ほんとうにお花がさいているみたいでしょう?」
楽しげな声に混じるのは春の花の名だ。咲いた花を甘味漬けにしたものが出回ると、もうすぐ夏がやってくる。春にほころび、そして夏を呼ぶ花々だ。
「先生! 早く先生も選んでくださいな!」
花のようにほころぶ笑顔が美しい姉妹がわたしを呼ぶ。その隣では、麗しい青年が優しい笑みをたたえていた。
考えなければならないこと、やらなければならないことはまだまだある。
だが、穏やかな時間が流れる今だけは、わたしも笑っていていいのかもしれない。
木から離れ、青い空の下へと足を踏み出す。眩い日差しに思わず目を細めると、暖かな風がいたずらに髪を揺らしながら吹き抜けていった。
夫人の部屋から戻る途中、ダストンさんがわたしを呼び止めた。丁寧な言葉に頷き、執務室までついていく。
中にはすでにマティアス卿がいらした。革張りの椅子を勧められ、女中が温かい茶を出してくれる。卿が片手で合図をすると、使用人たちは静かに部屋を出ていった。ダストンさんだけが残り、扉の近くで控えている。
「半ば住み込みのような形になってしまったが、不自由はないか、シャルティーナ」
「ご配慮いただきありがとうございます、マティアス卿。とてもよくしていただいております。その上、伯爵家の書庫まで拝見できるなど夢のようですわ」
「君のおかげで娘たちが助かったのだ。そのくらいは礼にもならん」
そう言って主人席へ座った卿は、肘掛けに頬杖をつき小さく息を吐いた。
「まさか先代が煩いの種を遺していたとはな。娘たちを伯爵家の者として立派に育てようと思っていたとはいえ、あのような……。すべて、当主であるわたしの失態だ」
「賊は巧妙な魔法を使っておりました。卿がお気づきになられなかったこと、無理もありません」
表情こそ変わっていないが、後悔がにじみ出る声音で卿が呟く。わたしは思わず茶器を置き、卿へ向き直った。
リンドールたちの計画的な犯行は、魔力がないものたちにはその一端すら感じ取れなかっただろう。なにかがおかしい、ただそれだけしか理解できなかったはずだ。
「先代は魔力のある者を屋敷から追い払った。エセルの乳母も魔力があったため、突然解雇を言い渡されている。その意図にもっと早く気づいていたならば、先代が存命中であったとしても対策はできただろうが……。すべては今更の話だ」
膝の上で手を組み、椅子に深く沈み込んだ卿が天を仰ぐ。己の力不足を嘆いているのだろうか。
「先代は、子の立場から見ても非情なお方だった。家名を守るためには身内ですら使い捨てる。親としての愛情を注いでもらった記憶などまったくない。わたしはダストンに育てられたようなものだ」
卿の言葉は、今まで見聞きした話を裏付けるものだった。やはり先代卿は周囲を支配し続けたのだろう。それは現マティアス卿が子供だったころから、いや、先代卿がこの家を継ぐ前から始まっていたのかもしれない。
「恐れながら旦那様」
「なんだ」
それまで静かに控えていたダストンさんが言葉を挟んだ。
「三十年ほど前まで我が王国は内政が不安定、三国の関係も良好とは言えませんでした。その時代を生きてきたお方でございます。非情にならざるを得なかったのではないかと」
「わかっている、父も見えない苦労をしていたのだろう。……しかし実の孫にあのような仕打ちなど、到底許されることではない」
苦々しい表情でマティアス卿が息を吐く。実父だからこそ、先代がなにをしようとしていたのか、そのためにどんな手段を選んでいたのか、思うことがあるのだろう。
隣り合う二国を含めた三国同盟は、今でこそ平穏に均衡を保っている。
だが五十年ほど前から始まった三国間の領土争いの爪痕は、未だ各地に残ったままだ。
更に三十年前には王国の王位継承権を争い、王家、貴族間で血生臭い事件が多発した。それ以来、王家の血を引く方は随分少なくなってしまったと聞く。
そういった背景は理解できる。できるのだが、納得はできない。
「余計な口を挟みました。ご無礼お許しください」
「構わない、お前は良く仕えてくれている」
「もったいないお言葉です」
ダストンさんは表情を変えることもなく、背筋を綺麗に伸ばしたまま頭を下げた。読めない方だけれど、そのくらいの力量がなければ伯爵家の家令は務められないのだろう。
わたしはまだまだ未熟だと己を振り返っていると、マティアス卿がこちらを振り返って微笑んだ。
「シャルティーナ、今後はエセルのことも見てはもらえないだろうか」
「……え?」
思わぬ言葉に、少し間の抜けた声を上げてしまった。慌てて口許を押さえる。
「娘たちは君に懐いている。魔法士ルディの弟子である君ならば、立場的にも充分だ。もちろん給金も上げよう。どうかあの子たちを導いてくれないか」
ゆっくりと立ち上がった卿は、執務机の後ろにある窓の傍へ立ち、外へ目を向けた。美しい金の髪が光に反射し輝いている。
「三国間の国交は改善されてきたとはいえ、均衡を崩そうと企む輩が消えたわけではない。しかし、王国内での生活の自由は回復している。エセルもエリスも、貴族内であれば自由を許される時代だ。そうあるべく、当主であるわたしが動かなくてはならない」
窓から差し込む午後の光を浴びた卿の視線は、遠い未来を見ているようだった。上に立つものとして、そして父として、マティアス卿は新たな決意をされているのだろう。
この屋敷で家庭教師を任されてから、わたしの中の高位貴族への印象は、好意的な方へと変わった。そんな方々に仕えられるのならば、精一杯努めたいと思う。
「わたしでよろしければ、誠心誠意お仕えいたします」
「――娘たちを頼むよ」
振り返りながら微笑んだマティアス卿は、位など関係なく、家族を思う父親の表情をなさっていた。
もうお亡くなりになった先代伯爵はともかく、伯爵夫妻はエセル様たちのことを愛していらっしゃる。
先ほどの言葉のとおり、これまで先代の支配が強かったのだ。呪いのように家中に蔓延し、夫妻も、姉妹も、使用人たちすらもそれに囚われていた。
もしかしたら卿は、それを知った上で御師様に家庭教師の打診をしたのかもしれない。なにかを変えたいのだと、望みを託して。
だからと言って、幼い少女を虐待することは許されない。今まで放置していたという罪を償い、親子関係の修復もできたらいいのだけれど。
エセル様が本当の意味での悪役令嬢になる前に、お救いできてよかった。
おいしそうな焼き菓子を手に、リヴィ様がお見舞いに来てくださった。
「お手柄だったね、シャル」
うららかな昼下がり。心地よい風が吹く中庭に整えられた茶会用の机。置かれた籠の中を嬉しそうに覗き込んで、どれを食べようか選んでいる姉妹の様子に、ふたりでほっと息をつく。
「リヴィ様のおかげです。騎士団を呼んでくれたのはリヴィ様でしょう?」
「幼馴染が騎士団長だからね。例の七色石の魔道具は、騎士団長の執務室に繋がってるのさ。有効に使わないと」
そう言って、リヴィ様が嫌味のない笑顔で片目を瞑る。自分の顔がいいことをわかっている仕草だ。さすがイケメンは違う。
姉妹とは少し離れた木陰で、わたしたちは声を潜め話していた。侍女や女中の数は最低限だが、あまり聞かれたくないことだけに、内緒話のように見えてしまうのは仕方ないだろう。
「ゲームではエセル嬢の背景なんて描かれていなかったけれど、酷いものだったんだね。あんな風になってしまうのもわかるよ」
「ええ、本当に、酷いものでした……。あの状況が長年続いていたのかと思うと、遣りきれません」
最近増えてきた、エセル様の屈託のない笑顔。ゲームで描かれていた険しい表情からは想像できないほど、穏やかで優しい、少女らしい笑みだ。
楽しげな姉妹を見つめていると、リヴィ様が更に声をひそめて囁いた。
「でもこれで、『この世界』がゲームとは違うものであることが確実になってきた」
「……はい」
「これから先、悪役令嬢エセルバートは生まれない。主人公の前に立ちはだかることもない。余程のなにかが起こらなければ、の話だけれど」
「そう……ですね……」
リヴィ様の言葉に頷くが、頭の中には疑問ばかり浮かんでくる。わたしの様子に気付いたのだろう。リヴィ様は軽い笑みを浮かべ、片手をひらりと振った。
「前にも言っただろう? そもそも、僕や君が別の世界の記憶を持っていること自体、ゲームとは違うんだ。僕は元々攻略対象のはずなのに、その知識を持ち、君と出会ってエセル嬢を間接的に助けた」
おっしゃっていることは理解している。だが本当に違うのだろうか。
違うというなら、何故わたしたちに前世の記憶があるのだろう。
「理解はしているつもりなのですが、本当に伯ネスの世界ではないのかどうか、未だに確信できないのです」
「僕にもわからないが、個人的には違うと考えている。限りなく似た世界ではあるけれどね」
顎に手を当て、緩く腕を組んだリヴィ様は、わたしを真っ直ぐに見つめた。木漏れ日がお顔に落ち、時折瞳を金に輝かせている。
「主人公は偉大なる魔法士ルディに師事し、若きコートナー卿には騎士団長の幼馴染がいる。それは伯ネスでも同じだ。ただ、それ以降が違う。どのルートでも、エセル嬢が立ちはだかるはずだった」
「それが、変わってしまった。本当は伯ネスの世界なのに、わたしが記憶を持っているから、エセル様を助けたから……。そうも考えられませんか」
今まで考えていた不安を吐露すれば、リヴィ様は軽く目を瞠った。まるで意外だとでもいうように。
「確かに。だが、いたいけな少女を助けたことは正しいことだ。それを気に病むことはないよ」
「でも、そのせいで、リヴィ様の進む道まで変えてしまったとしたら……」
「僕の?」
胸の前で両手を握り締める。言葉にしたことによって、不安が形を持ってしまった。それが内側から侵食してくるように思えて、わたしは身体を震わせた。
「巻き込んでしまうだなんて、のん気なことを言ったけれど、最初からわたしがシャルティーナにならなければ、リヴィ様がこの世界へ転生することもなかったのかもしれない……」
そうだ、最初から始まっていた。わたしがシャルティーナとして生まれたときから、すべては始まっていたのだ。
十五歳のときの覚醒は、ただの通過点に過ぎない。
「以前、御師様に言われたのです。わたしは、良くも悪くも王国を変化させる、と」
「ルディ様がそんなことを?」
「わたしがいるから、世界が歪んだんだわ。そうとしか、思えない……」
身体の震えが止まらない。青い空、心地良い風、光を遮る雲もない穏やかな日和だというのに、巣食いはじめた不安は足元の大地すら不安定にさせているように思えた。
そっと、温かな掌が肩へ触れた。リヴィ様が気遣わしげな瞳を向けてくれている。
「少なくとも、僕に関しては、君が原因ではないことは確かだな」
「何故、断言できるのですか?」
「まずひとつ、僕は君よりも先に生まれている」
「あ……」
口許を上げて言い切るリヴィ様を見つめながら、思わず小さな声を上げてしまう。
リヴィ様は背筋を伸ばし、優雅な足取りで、中天から傾きかけた光の元へと歩んでいった。
「そしてもうひとつ。――君とは関係なく、前世の『わたし』自身が原因だからだよ」
振り返ったリヴィ様の瞳が、日差しを受けて金色に輝いている。微笑みを浮かべたお顔からは、なにも読み取ることができなかった。
「麗しいお嬢様たち、食べたいものは決まったかな?」
「ええ、リヴィエール様。わたくしはこれ、上に乗ったミシァンの蜜付けが宝石のようで綺麗だわ」
「わたくしのものはシビリアンの花びらがのっているの! ほんとうにお花がさいているみたいでしょう?」
楽しげな声に混じるのは春の花の名だ。咲いた花を甘味漬けにしたものが出回ると、もうすぐ夏がやってくる。春にほころび、そして夏を呼ぶ花々だ。
「先生! 早く先生も選んでくださいな!」
花のようにほころぶ笑顔が美しい姉妹がわたしを呼ぶ。その隣では、麗しい青年が優しい笑みをたたえていた。
考えなければならないこと、やらなければならないことはまだまだある。
だが、穏やかな時間が流れる今だけは、わたしも笑っていていいのかもしれない。
木から離れ、青い空の下へと足を踏み出す。眩い日差しに思わず目を細めると、暖かな風がいたずらに髪を揺らしながら吹き抜けていった。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

オバサンが転生しましたが何も持ってないので何もできません!
みさちぃ
恋愛
50歳近くのおばさんが異世界転生した!
転生したら普通チートじゃない?何もありませんがっ!!
前世で苦しい思いをしたのでもう一人で生きて行こうかと思います。
とにかく目指すは自由気ままなスローライフ。
森で調合師して暮らすこと!
ひとまず読み漁った小説に沿って悪役令嬢から国外追放を目指しますが…
無理そうです……
更に隣で笑う幼なじみが気になります…
完結済みです。
なろう様にも掲載しています。
副題に*がついているものはアルファポリス様のみになります。
エピローグで完結です。
番外編になります。
※完結設定してしまい新しい話が追加できませんので、以後番外編載せる場合は別に設けるかなろう様のみになります。

異世界に転移してしまった私、古民家をもらったのでカフェを始めたら大盛況。国王陛下が頻繁に来るのですが、どうしたらいいですか?
来栖とむ
ファンタジー
ブラック企業で疲れ果てた30歳の元OL・美里(みさと)が転移した先は、見渡す限りの深い森。
そこで彼女が授かったのは、魔女の称号……ではなく、一軒の**「日本の古民家」**だった!
亡き祖母が遺したその屋敷には、異世界では失われたはずの「お醤油」「お味噌」「白いお砂糖」という禁断の調味料が眠っていて――。
「えっ、唐揚げにそんなに感動しちゃうの?」
「プリン一口で、国王陛下が泣いちゃった……!?」
おにぎり、オムライス、そして肉汁溢れるハンバーグ。
現代日本の「当たり前」が、この世界では常識を覆す究極の美食に。
お掃除のプロな親子や、お忍びの王様、さらにはツンデレな宮廷料理人まで巻き込んで、
美味しい香りに包まれた、心もお腹も満たされるスローライフが今、始まります!
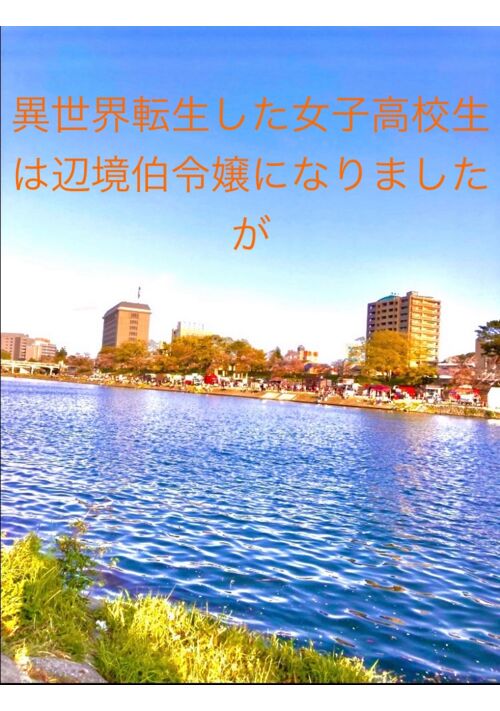
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

神様の忘れ物
mizuno sei
ファンタジー
仕事中に急死した三十二歳の独身OLが、前世の記憶を持ったまま異世界に転生した。
わりとお気楽で、ポジティブな主人公が、異世界で懸命に生きる中で巻き起こされる、笑いあり、涙あり(?)の珍騒動記。

悪役令嬢の追放エンド………修道院が無いじゃない!(はっ!?ここを楽園にしましょう♪
naturalsoft
ファンタジー
シオン・アクエリアス公爵令嬢は転生者であった。そして、同じく転生者であるヒロインに負けて、北方にある辺境の国内で1番厳しいと呼ばれる修道院へ送られる事となった。
「きぃーーーー!!!!!私は負けておりませんわ!イベントの強制力に負けたのですわ!覚えてらっしゃいーーーー!!!!!」
そして、目的地まで運ばれて着いてみると………
「はて?修道院がありませんわ?」
why!?
えっ、領主が修道院や孤児院が無いのにあると言って、不正に補助金を着服しているって?
どこの現代社会でもある不正をしてんのよーーーーー!!!!!!
※ジャンルをファンタジーに変更しました。

【本編完結】転生令嬢は自覚なしに無双する
ベル
ファンタジー
ふと目を開けると、私は7歳くらいの女の子の姿になっていた。
きらびやかな装飾が施された部屋に、ふかふかのベット。忠実な使用人に溺愛する両親と兄。
私は戸惑いながら鏡に映る顔に驚愕することになる。
この顔って、マルスティア伯爵令嬢の幼少期じゃない?
私さっきまで確か映画館にいたはずなんだけど、どうして見ていた映画の中の脇役になってしまっているの?!
映画化された漫画の物語の中に転生してしまった女の子が、実はとてつもない魔力を隠し持った裏ボスキャラであることを自覚しないまま、どんどん怪物を倒して無双していくお話。
設定はゆるいです

【完結】乙女ゲーム開始前に消える病弱モブ令嬢に転生しました
佐倉穂波
恋愛
転生したルイシャは、自分が若くして死んでしまう乙女ゲームのモブ令嬢で事を知る。
確かに、まともに起き上がることすら困難なこの体は、いつ死んでもおかしくない状態だった。
(そんな……死にたくないっ!)
乙女ゲームの記憶が正しければ、あと数年で死んでしまうルイシャは、「生きる」ために努力することにした。
2023.9.3 投稿分の改稿終了。
2023.9.4 表紙を作ってみました。
2023.9.15 完結。
2023.9.23 後日談を投稿しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















