30 / 51
不穏な影
しおりを挟む
レティシアが王城で仕事を始めてから数週間が過ぎた。
今のところ、それなりに新しい職場になじむことができていると思う。
「また、研究かよ?」
不意にかけられた声に、レティシアは机の上から視線を上げた。
視線の先には、同僚の魔法使いアンリがいた。
寄りかかっていた戸口から身体を起こし、近づいてくる。
初日からレティシアに棘のある言葉を投げつけてきたアンリは、ぶつぶついいながらも王城を案内してくれた。
案内された訓練場で、攻撃魔法を仕掛けられたので、穏便にお話し合いをさせていただいた。
それ以来、アンリは早々に猫を被ることをやめぞんざいな口調で話しかけてくるようになった。
「そうですよ。もう少し消費魔力を抑える改良をしたくて」
「ちょっと、見せてみろよ」
アンリが机の上に広げられた魔法陣の書かれた紙を覗き込んでくる。
護衛の仕事では攻撃魔法よりも防御魔法の使用頻度が高い。長時間魔法陣を起動したままになるため、少しでも消費を抑えるべく、レティシアは魔法陣を見直していた。
「うわ、こまけぇ」
「そう?」
かわいい顔をしているアンリは、口は悪いけれど、話をしてみると意外に裏表のない性格をしていた。
魔法に関しては興味津々で、いずれは魔導士になりたいらしい。
となると、魔導士であるレティシアのやっていることが気になるらしく、よく研究を覗きにくる。
なつかない猫が少しずつ打ち解けてくれているような気がして、レティシアはわりにアンリのことが好きなってきている。
近衛に所属する魔導士はレティシアひとりだけで、魔法使いはアンリのほかにも何人かいた。
けれど彼らはあからさまにレティシアのことを無視してくるので、なるべく近寄らないようにしている。
幸いにも、基本的には剣を持った近衛兵士が三人と魔法使いがひとりの組み合わせで護衛をすることになっているので、レティシアが他の魔法使いと仕事が一緒になることはない。
いきなり外部から来た魔導士が、近衛の一員となったのが気に入らないのかもしれない。
けれど侯爵夫人であるレティシアの地位はそれなりに高く、彼らの地位では無視するしかないのだだろう。
週に五日ほどの勤務のうち、半分ほどは陛下の護衛で、残りの半分はこれまでと変わらず研究に費やしている。
王城の中に一室を賜ったので、レティシアはそこで魔法陣の改良にいそしんでいた。
レティシアの得意分野は治癒魔法ではあるが、攻撃魔法や、補助魔法などももちろん使える。そうでなければ魔導士など名乗れない。
王城の図書室には魔法書も多く、ベルクール研究所にも引けをとらぬほどの蔵書があった。
それもあって、最近は近衛の控え室にいるよりも、図書室か研究室にいることのほうが多かった。
これまで研究してきた魔法陣も、実際に使ってみるといろいろと改良点が見つかるので、現場で働くのも悪くないと思い始めている。
「なあ、ここのルーンはこっちとつなげるのじゃダメなのか?」
「ああ、それですね。ここは……」
アンリに問われた魔法陣の改良箇所を説明する。
彼はなかなか着目点がよく、鋭い質問が多い。きっと彼ならばいずれ魔導士になれるだろう。
「レティ、いいか?」
アンリとふたりで魔法陣をああでもない、こうでもないといじくっていると、聞きなれた声がかけられた。
「アロイス、どうしました?」
レティシアは机から離れてアロイスの前に移動した。
王城で会うアロイスの眉間にはいつも皺がよっている気がする。
「仕事だ。同行してくれ」
「はい。アンリ、途中ですがここまでです」
「わかったよ。またな」
アンリはつまらなさそうに魔法陣の書かれた紙を放り出し、ふいとレティシアとアロイスの隣を通り抜けていった。
レティシアとアロイスも部屋を出て王の執務室に向かう。回廊を歩いていると、アロイスが話しかけてきた。
「ずいぶんと仲良くなったみたいだな」
「そうでしょうか? まあ、話しかけてくるのは彼くらいですけれど」
レティシアは自嘲する。
ほかの魔法使いと連携が問われるような任に就くとしたら、少し難しいかもしれないという自覚はある。
けれど自分が魔導士であること、侯爵夫人であることは変えようがない。彼らと仲良くやっていくのならば、自分の実力で彼らを納得させるしかない。
「それで、どのようなお仕事ですか?」
「陛下の視察に同行してくれ」
「承知しました。すぐに出ますか?」
「ああ」
「それにしても急ですね」
「陛下にはよくあることだ」
アロイスが嘆息する。
レティシアもうなずいた。
ここ数週間の経験でしかないが、国王が予定されていない行動をとるのは珍しくない。
そのたびに近衛は安全確保に四苦八苦しているようだった。
今のところは平和な世が続き、国王に不満を持つ者は少ない。けれどいつの世も王に対して不満を持つ者はいる。
王を戴く民の一人として、守れる力があるのならば尽くしたい。
間近で王の姿を見るようになって、レティシアはそんなふうに思うようになっていた。
「では、私は先に馬車の安全を確認しておきます」
「ああ、頼んだ」
アロイスが軍服の裾を翻し立ち去る。
レティシアは宣言した通り、馬車寄せに向かう。王のために用意された馬車に乗り込み、魔法陣が仕掛けられていないかを確認する。
魔力の痕跡を慎重に探ると、レティシアの感覚に引っかかるものがあった。
――これは防御の魔法陣じゃない……。
レティシアは座席の下を探った。指先にかさりとした感触が触れる。無理やり魔力を流して魔法陣を強引に塗り替える。
その瞬間、ばちりと強い反発を感じて思わず手を引く。
「……っ」
指先には小さな切り傷ができ、うっすらと血が滲んでいた。
「レティ、どうした?」
振り向くとアロイスが馬車の扉を開けたところだった。
「魔法陣があったの。解除しようとしてちょっと……」
「怪我をしたのか!」
レティシアの指先の傷を目ざとく見つけたアロイスが、厳しい表情で近づく。
手をつかもうとするアロイスに、レティシアは慌てた。
「これくらい、すぐに治せるから」
「いや、見せろ」
アロイスは強引にレティシアの手をつかみ、傷を確認した。
「……よかった。傷は浅い」
アロイスは厳しい表情を緩め、レティシアの指先に口づけた。そのまま傷口をぺろりと舐める。
「あ、あ、アロイス!?」
「どうした? 治癒魔法を使えるのだろう?」
艶めいた表情で見上げてくるアロイスにレティシアの胸の高まりが治まらない。
今のところ、それなりに新しい職場になじむことができていると思う。
「また、研究かよ?」
不意にかけられた声に、レティシアは机の上から視線を上げた。
視線の先には、同僚の魔法使いアンリがいた。
寄りかかっていた戸口から身体を起こし、近づいてくる。
初日からレティシアに棘のある言葉を投げつけてきたアンリは、ぶつぶついいながらも王城を案内してくれた。
案内された訓練場で、攻撃魔法を仕掛けられたので、穏便にお話し合いをさせていただいた。
それ以来、アンリは早々に猫を被ることをやめぞんざいな口調で話しかけてくるようになった。
「そうですよ。もう少し消費魔力を抑える改良をしたくて」
「ちょっと、見せてみろよ」
アンリが机の上に広げられた魔法陣の書かれた紙を覗き込んでくる。
護衛の仕事では攻撃魔法よりも防御魔法の使用頻度が高い。長時間魔法陣を起動したままになるため、少しでも消費を抑えるべく、レティシアは魔法陣を見直していた。
「うわ、こまけぇ」
「そう?」
かわいい顔をしているアンリは、口は悪いけれど、話をしてみると意外に裏表のない性格をしていた。
魔法に関しては興味津々で、いずれは魔導士になりたいらしい。
となると、魔導士であるレティシアのやっていることが気になるらしく、よく研究を覗きにくる。
なつかない猫が少しずつ打ち解けてくれているような気がして、レティシアはわりにアンリのことが好きなってきている。
近衛に所属する魔導士はレティシアひとりだけで、魔法使いはアンリのほかにも何人かいた。
けれど彼らはあからさまにレティシアのことを無視してくるので、なるべく近寄らないようにしている。
幸いにも、基本的には剣を持った近衛兵士が三人と魔法使いがひとりの組み合わせで護衛をすることになっているので、レティシアが他の魔法使いと仕事が一緒になることはない。
いきなり外部から来た魔導士が、近衛の一員となったのが気に入らないのかもしれない。
けれど侯爵夫人であるレティシアの地位はそれなりに高く、彼らの地位では無視するしかないのだだろう。
週に五日ほどの勤務のうち、半分ほどは陛下の護衛で、残りの半分はこれまでと変わらず研究に費やしている。
王城の中に一室を賜ったので、レティシアはそこで魔法陣の改良にいそしんでいた。
レティシアの得意分野は治癒魔法ではあるが、攻撃魔法や、補助魔法などももちろん使える。そうでなければ魔導士など名乗れない。
王城の図書室には魔法書も多く、ベルクール研究所にも引けをとらぬほどの蔵書があった。
それもあって、最近は近衛の控え室にいるよりも、図書室か研究室にいることのほうが多かった。
これまで研究してきた魔法陣も、実際に使ってみるといろいろと改良点が見つかるので、現場で働くのも悪くないと思い始めている。
「なあ、ここのルーンはこっちとつなげるのじゃダメなのか?」
「ああ、それですね。ここは……」
アンリに問われた魔法陣の改良箇所を説明する。
彼はなかなか着目点がよく、鋭い質問が多い。きっと彼ならばいずれ魔導士になれるだろう。
「レティ、いいか?」
アンリとふたりで魔法陣をああでもない、こうでもないといじくっていると、聞きなれた声がかけられた。
「アロイス、どうしました?」
レティシアは机から離れてアロイスの前に移動した。
王城で会うアロイスの眉間にはいつも皺がよっている気がする。
「仕事だ。同行してくれ」
「はい。アンリ、途中ですがここまでです」
「わかったよ。またな」
アンリはつまらなさそうに魔法陣の書かれた紙を放り出し、ふいとレティシアとアロイスの隣を通り抜けていった。
レティシアとアロイスも部屋を出て王の執務室に向かう。回廊を歩いていると、アロイスが話しかけてきた。
「ずいぶんと仲良くなったみたいだな」
「そうでしょうか? まあ、話しかけてくるのは彼くらいですけれど」
レティシアは自嘲する。
ほかの魔法使いと連携が問われるような任に就くとしたら、少し難しいかもしれないという自覚はある。
けれど自分が魔導士であること、侯爵夫人であることは変えようがない。彼らと仲良くやっていくのならば、自分の実力で彼らを納得させるしかない。
「それで、どのようなお仕事ですか?」
「陛下の視察に同行してくれ」
「承知しました。すぐに出ますか?」
「ああ」
「それにしても急ですね」
「陛下にはよくあることだ」
アロイスが嘆息する。
レティシアもうなずいた。
ここ数週間の経験でしかないが、国王が予定されていない行動をとるのは珍しくない。
そのたびに近衛は安全確保に四苦八苦しているようだった。
今のところは平和な世が続き、国王に不満を持つ者は少ない。けれどいつの世も王に対して不満を持つ者はいる。
王を戴く民の一人として、守れる力があるのならば尽くしたい。
間近で王の姿を見るようになって、レティシアはそんなふうに思うようになっていた。
「では、私は先に馬車の安全を確認しておきます」
「ああ、頼んだ」
アロイスが軍服の裾を翻し立ち去る。
レティシアは宣言した通り、馬車寄せに向かう。王のために用意された馬車に乗り込み、魔法陣が仕掛けられていないかを確認する。
魔力の痕跡を慎重に探ると、レティシアの感覚に引っかかるものがあった。
――これは防御の魔法陣じゃない……。
レティシアは座席の下を探った。指先にかさりとした感触が触れる。無理やり魔力を流して魔法陣を強引に塗り替える。
その瞬間、ばちりと強い反発を感じて思わず手を引く。
「……っ」
指先には小さな切り傷ができ、うっすらと血が滲んでいた。
「レティ、どうした?」
振り向くとアロイスが馬車の扉を開けたところだった。
「魔法陣があったの。解除しようとしてちょっと……」
「怪我をしたのか!」
レティシアの指先の傷を目ざとく見つけたアロイスが、厳しい表情で近づく。
手をつかもうとするアロイスに、レティシアは慌てた。
「これくらい、すぐに治せるから」
「いや、見せろ」
アロイスは強引にレティシアの手をつかみ、傷を確認した。
「……よかった。傷は浅い」
アロイスは厳しい表情を緩め、レティシアの指先に口づけた。そのまま傷口をぺろりと舐める。
「あ、あ、アロイス!?」
「どうした? 治癒魔法を使えるのだろう?」
艶めいた表情で見上げてくるアロイスにレティシアの胸の高まりが治まらない。
0
あなたにおすすめの小説

このたび、あこがれ騎士さまの妻になりました。
若松だんご
恋愛
「リリー。アナタ、結婚なさい」
それは、ある日突然、おつかえする王妃さまからくだされた命令。
まるで、「そこの髪飾りと取って」とか、「窓を開けてちょうだい」みたいなノリで発せられた。
お相手は、王妃さまのかつての乳兄弟で護衛騎士、エディル・ロードリックさま。
わたしのあこがれの騎士さま。
だけど、ちょっと待って!! 結婚だなんて、いくらなんでもそれはイキナリすぎるっ!!
「アナタたちならお似合いだと思うんだけど?」
そう思うのは、王妃さまだけですよ、絶対。
「試しに、二人で暮らしなさい。これは命令です」
なーんて、王妃さまの命令で、エディルさまの妻(仮)になったわたし。
あこがれの騎士さまと一つ屋根の下だなんてっ!!
わたし、どうなっちゃうのっ!? 妻(仮)ライフ、ドキドキしすぎで心臓がもたないっ!!

王太子妃専属侍女の結婚事情
蒼あかり
恋愛
伯爵家の令嬢シンシアは、ラドフォード王国 王太子妃の専属侍女だ。
未だ婚約者のいない彼女のために、王太子と王太子妃の命で見合いをすることに。
相手は王太子の側近セドリック。
ところが、幼い見た目とは裏腹に令嬢らしからぬはっきりとした物言いのキツイ性格のシンシアは、それが元でお見合いをこじらせてしまうことに。
そんな二人の行く末は......。
☆恋愛色は薄めです。
☆完結、予約投稿済み。
新年一作目は頑張ってハッピーエンドにしてみました。
ふたりの喧嘩のような言い合いを楽しんでいただければと思います。
そこまで激しくはないですが、そういうのが苦手な方はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。

「君の作った料理は愛情がこもってない」と言われたのでもう何も作りません
今川幸乃
恋愛
貧乏貴族の娘、エレンは幼いころから自分で家事をして育ったため、料理が得意だった。
そのため婚約者のウィルにも手づから料理を作るのだが、彼は「おいしいけど心が籠ってない」と言い、挙句妹のシエラが作った料理を「おいしい」と好んで食べている。
それでも我慢してウィルの好みの料理を作ろうとするエレンだったがある日「料理どころか君からも愛情を感じない」と言われてしまい、もう彼の気を惹こうとするのをやめることを決意する。
ウィルはそれでもシエラがいるからと気にしなかったが、やがてシエラの料理作りをもエレンが手伝っていたからこそうまくいっていたということが分かってしまう。

愛しい人、あなたは王女様と幸せになってください
無憂
恋愛
クロエの婚約者は銀の髪の美貌の騎士リュシアン。彼はレティシア王女とは幼馴染で、今は護衛騎士だ。二人は愛し合い、クロエは二人を引き裂くお邪魔虫だと噂されている。王女のそばを離れないリュシアンとは、ここ数年、ろくな会話もない。愛されない日々に疲れたクロエは、婚約を破棄することを決意し、リュシアンに通告したのだが――

ソウシソウアイ?
野草こたつ/ロクヨミノ
恋愛
政略結婚をすることになったオデット。
その相手は初恋の人であり、同時にオデットの姉アンネリースに想いを寄せる騎士団の上司、ランヴァルド・アーノルト伯爵。
拒否に拒否を重ねたが強制的に結婚が決まり、
諦めにも似た気持ちで嫁いだオデットだが……。
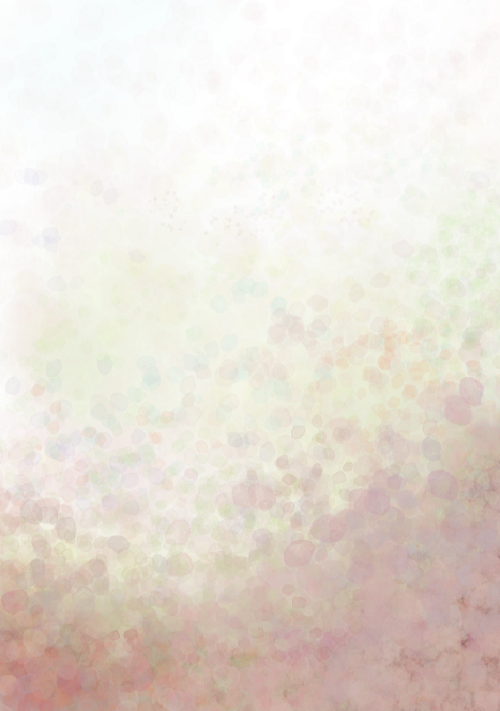
「今とっても幸せですの。ごめんあそばせ♡」 捨てられ者同士、溺れちゃうほど愛し合ってますのでお構いなく!
若松だんご
恋愛
「キサマとはやっていけない。婚約破棄だ。俺が愛してるのは、このマリアルナだ!」
婚約者である王子が開いたパーティ会場で。妹、マリアルナを伴って現れた王子。てっきり結婚の日取りなどを発表するのかと思っていたリューリアは、突然の婚約破棄、妹への婚約変更に驚き戸惑う。
「姉から妹への婚約変更。外聞も悪い。お前も噂に晒されて辛かろう。修道院で余生を過ごせ」
リューリアを慰めたり、憤慨することもない父。マリアルナが王子妃になることを手放しで喜んだ母。
二人は、これまでのリューリアの人生を振り回しただけでなく、これからの未来も勝手に決めて命じる。
四つ違いの妹。母によく似たかわいらしい妹が生まれ、母は姉であ、リューリアの育児を放棄した。
そんなリューリアを不憫に思ったのか、ただの厄介払いだったのか。田舎で暮らしていた祖母の元に預けられて育った。
両親から離れたことは寂しかったけれど、祖母は大切にしてくれたし、祖母の家のお隣、幼なじみのシオンと仲良く遊んで、それなりに楽しい幼少期だったのだけど。
「第二王子と結婚せよ」
十年前、またも家族の都合に振り回され、故郷となった町を離れ、祖母ともシオンとも別れ、未来の王子妃として厳しい教育を受けることになった。
好きになれそうにない相手だったけれど、未来の夫となる王子のために、王子に代わって政務をこなしていた。王子が遊び呆けていても、「男の人はそういうものだ」と文句すら言わせてもらえなかった。
そして、20歳のこの日。またも周囲の都合によって振り回され、周囲の都合によって未来まで決定されてしまった。
冗談じゃないわ。どれだけ人を振り回したら気が済むのよ、この人たち。
腹が立つけれど、どうしたらいいのかわからずに、従う道しか選べなかったリューリア。
せめて。せめて修道女として生きるなら、故郷で生きたい。
自分を大事にしてくれた祖母もいない、思い出だけが残る町。けど、そこで幼なじみのシオンに再会する。
シオンは、結婚していたけれど、奥さんが「真実の愛を見つけた」とかで、行方をくらましていて、最近ようやく離婚が成立したのだという。
真実の愛って、そんなゴロゴロ転がってるものなのかしら。そして、誰かを不幸に、悲しませないと得られないものなのかしら。
というか。真実もニセモノも、愛に真贋なんてあるのかしら。
捨てられた者同士。傷ついたもの同士。
いっしょにいて、いっしょに楽しんで。昔を思い出して。
傷を舐めあってるんじゃない。今を楽しみ、愛を、想いを育んでいるの。だって、わたしも彼も、幼い頃から相手が好きだったってこと、思い出したんだもの。
だから。
わたしたちの見つけた「真実の愛(笑)」、邪魔をしないでくださいな♡

【完結】番としか子供が産まれない世界で
さくらもち
恋愛
番との間にしか子供が産まれない世界に産まれたニーナ。
何故か親から要らない子扱いされる不遇な子供時代に番と言う概念すら知らないまま育った。
そんなニーナが番に出会うまで
4話完結
出会えたところで話は終わってます。

悪女と呼ばれた王妃
アズやっこ
恋愛
私はこの国の王妃だった。悪女と呼ばれ処刑される。
処刑台へ向かうと先に処刑された私の幼馴染み、私の護衛騎士、私の従者達、胴体と頭が離れた状態で捨て置かれている。
まるで屑物のように足で蹴られぞんざいな扱いをされている。
私一人処刑すれば済む話なのに。
それでも仕方がないわね。私は心がない悪女、今までの行いの結果よね。
目の前には私の夫、この国の国王陛下が座っている。
私はただ、
貴方を愛して、貴方を護りたかっただけだったの。
貴方のこの国を、貴方の地位を、貴方の政務を…、
ただ護りたかっただけ…。
だから私は泣かない。悪女らしく最後は笑ってこの世を去るわ。
❈ 作者独自の世界観です。
❈ ゆるい設定です。
❈ 処刑エンドなのでバットエンドです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















