13 / 50
第1章
第13話
しおりを挟む
□
執務室に緊張が走る。
陽春は冷や汗をにじませながら、アスカ付きの侍女──清夏の報告に耳を傾けていた。
「……今、なんと申した」
低く落ちたリオールの声には、明らかに抑えきれない怒気が滲んでいた。
清夏はひとつ深く息を吸い、頭を下げたまま、はっきりとした声で告げる。
「アスカ様のもとに、宦官が遣わされました 」
次の瞬間、椅子の脚が大きな音を立てて引き摺られた。
リオールが立ち上がったその動きに、部屋の空気が一瞬で凍りつく。
少年の身にしては不相応な、王の血が宿る者だけが持つアルファの威圧が、室内を支配した。
「誰が──そんな命を?」
低く、喉の奥で鳴る獣のような声。
その問いかけに、清夏は唾液を飲み込んだ。
「……王命とのことです」
「なぜ、今この瞬間にそんなことをする必要がある……! アスカは──」
リオールの拳が机に叩きつけられた。
重い音が響き、机の上の書類が宙に舞った。
「……私と会うことすら拒んでいたのに」
その声には、怒りの奥に痛みが混じっていた。
アスカに拒絶されたこと。それを理由に身を引いた自分。
けれど、その影で、別の誰かがアスカに触れようとしている。
その事実が、許せなかった。
「すぐに向かう」
誰かが何かを発言するよりも早く、リオールは駆け出していた。
陽春が「お待ちを!」と叫んだが、その声も届かない。
怒りに満ちたまま、リオールはアスカのもとへと走り抜けた。
間に合わないかもしれない。
頭ではそうわかっていても、足は止められなかった。
リオールがアスカのもとに着いた時、そこはあまりにも静まり返っていた。
誰もいないかのような、そこだけ切り取られたかのような空間は異質で。
静かに宮の中に入れば、小さく啜り泣く声が聞こえた。
アスカが発情期に入ってからというもの、リオールは毎日抑制剤を飲んではいるが、それでも完全に防げるわけではないフェロモンの香りが動悸を速くさせる。
「──アスカ様……」
薄氷の声が悲痛に満ちている。
リオールはこの先にいるアスカの姿を想像して、怒る心を鎮めること無く扉を開いた。
「アスカ……っ」
「っ!」
中にいたアスカも薄氷も、リオールの声を聞いて肩を大きくふるわせた。
薄氷は慌てて平伏す。
アスカは怯えたような顔でリオールを見てすぐ、何を言うことも無く俯いた。
「──さがれ」
静かに命令され、薄氷はそのまま部屋を後にする。
寝台で上体を起こし、手元に視線を落としているアスカの衣服や髪は、少し乱れてはいるが、誰かに触れられたような形跡は見当たらない。
「アスカ……アスカ、こちらをむいては、くれないか」
「っ、」
アスカの肩が震えている。
その細い背に、リオールは思わず手を伸ばしかけて──しかし、止めた。
もし今、触れてしまえば、自分の中の怒りが堰を切ってあふれてしまいそうだった。
声を荒げてはならない。眉をひそめてもいけない。
今はただ、静かに、穏やかに、彼の隣にいるべきなのだとわかっていた。
「……大丈夫だ。誰も、そなたに触れない。私が、絶対にそうさせない」
言葉とは裏腹に、拳は震えていた。
爪が食い込むほどに手を握りしめ、掌からは血が溢れる。
嗅ぎ取った甘く熱を帯びた香り。
その香りに、別の男の存在が混じっていなかったこと。
それだけが、唯一の救いだった。
──どうして、アスカがこんな目に遭わなければならなかったのだ。
怒りが胸を刺す。だが、それを顔には出さない。
「無事で、良かった」
「っ、リオール様……っ」
リオールはゆっくりと微笑んだ。
無理矢理貼り付けたその顔は、まるで仮面のよう。
アスカの手が伸びてきて、リオールの手に重なる。
熱い体温。きっと今は起きていることすら辛いに違いないはず。
それでも──自分の手を取ってくれた。
守りきれなかったという悔しさと、それでもなお求められたことへの救いが、胸を締めつける。
「眠れそうか……?」
「……はぁ、リオール様……」
リオールの顔を見て、声を聞いて、匂いを嗅いで、アスカは少し安心したのか、甘く熱を帯びた声で名前を呼ばれると、リオールの腰がズクンと疼いた。
そんな体の反応に気づかなかったかのように、冷静にアスカを寝台に寝かせる。
リオールの指が、そっとアスカの髪を梳く。
細い肩はまだ小さく震えているけれど、少しずつ呼吸が落ち着いていった。
「大丈夫だ。何も怖くない。そばにいる」
その囁きに、アスカは微かに頷く。
まぶたがゆっくりと閉じられた。
リオールはしばらくの間、その寝顔をじっと見つめていた。
指一本触れぬよう、ただ静かに。
アスカが安らかに眠ってくれることが、今は何よりも救いだった。
小さな寝息を確認してから、リオールはそっと立ち上がり、息を詰めるようにして扉を開け、音を立てぬよう閉じる。
──そして、次の瞬間だった。
バンッ、と廊下の壁に拳が叩きつけられた。
「……ふざけるな……ッ」
声を殺しながら、リオールは荒く息を吐く。
手の甲はその衝撃でぱっくりと裂け、血が滲む。
顔を上げたその瞳は、いつもの冷静さなど欠片もなかった。
剥き出しの怒りと、どうしようもない無力感。
今にも噛みつきそうな獣のような呼吸。
「殿下ッ」
陽春が顔を青ざめさせ、慌てて駆け寄る。
「……私が、触れられないからと、宦官なんぞを送り込むとは……っ!」
低く呟いたその声には、ただ怒りだけではなく、自分を責めるような痛みも滲んでいた。
触れたいと思った。
けれど、アスカは拒んだ。それは、自分がまだ子供だからだ。
そのことを、理解していたし、受け入れていたはずだった。
──だが、
「だからって……っ、どうして、他の男が許されるのだ……!」
リオールの声がわずかに震える。
『代わり』を宛てがわれるほど、自分は無力なのか。
そう思うたび、胸の奥に針が突き刺さるようだった。
震える手で、壁を殴る。
何度も、何度も、声を殺しながら。
思い出すのは──怯えた目で自分を見た、アスカの顔だった。
涙に濡れた睫毛、恐怖が色濃く映る瞳。
震える声で、自分の名を呼んだときのあの表情が、焼きついて離れない。
リオールの肩が、ぶるりと揺れる。
胸の奥からこみ上げるのは、悔しさだった。
「……私は、皇太子だというのに……」
ぎり、と奥歯を噛み締める。
王の命令ひとつで、大切な人に手をかけさせるような仕打ちを、ただ黙って見ていることしかできないなんて。
リオールは拳を握りしめたまま、低く息を吐いた。
抑え込んでいた感情の波が、ゆっくりと形を成し始める。
「アスカを守れるのは……私しかいない」
ただ隣にいるだけでは、足りない。
優しく手を差し伸べるだけでは、何も変えられない。
だったら──変えればいい。
この理不尽を、国を。
アスカの涙を、二度と、見なくて済むように。
リオールは、そっと拳を開いた。
血の滲む掌を見つめながら、静かに言葉を落とす。
「……陛下に会わせろ。今すぐに、だ」
「はっ」
陽春は急いで廊下を駆けていく。
その後ろ姿を見送ると、リオールはわずかに目を伏せた。
「──殿下」
不意に声が掛けられ、そちらを一瞥すると、清夏がすぐそばにたっていた。
「先に手当を」
「……かまわん。放っておけ」
「それはできません。そのままではきっと、アスカ様が悲しまれます」
そう言われるとリオールは手を差し出すしかなかった。
医務官が足早にやって来て、手際良く傷の手当をする。
「殿下。陛下とのお話が終わり次第、こちらにいらっしゃいますか」
薄氷が尋ねると、リオールは「……そうだな」と言葉を紡ぐ。
「もしも、アスカが私を呼ぶのなら、必ずここに戻ってこよう」
それは少しの期待が込められていた。
発情期とはいえ、体を重ねなくてもいい。
フェロモンに反応して体が疼こうが、ただそばにいて見守ることはできる。
「アスカが目を覚ましたら、伝えておいてくれ。──私は、どのようなアスカも愛している」
薄氷は息を飲み、そうして確かに頷いた。
王座の間に呼び出されたリオールは、いつものように頭を下げたりせず、静かに国王を見据える。
「──陛下。ひとつ、お話がございます」
「なんだ、急に。おまえが礼儀を欠くとは珍しいな」
「礼儀を尽くすに値しない命令が、つい先程、ございましたので」
王は目を細める。だが、リオールは怯まなかった。
「発情期のオメガに無断で宦官を宛てがうなど、暴挙です。私情ではなく、国家の安寧を考える者のすることではありません」
「……私情ではない、だと?」
「はい。もしこれが貴族の誰かに向けられた命令であっても、私は同じように意見したでしょう」
少しだけ間を置いて──リオールは一歩、王に近づく。
「王たる者は、力を誇示することで威厳を保つのではなく、理によって民と臣下を導くべきです。私はそう信じています」
玉座の上、威圧感すら纏って座る王の前で、リオールは一歩も退かずにその瞳を見据えていた。
睨むのでも、媚びるのでもない、真っすぐな視線。
「……私が黙して従っていたのは、幼さからでも、陛下を恐れていたからでもありません」
王の眉がわずかに動いた。
「それが、この国の秩序であり、王命であるならば、それには従わなければならないと、心得ております。──ですが」
リオールの声がわずかに低くなる。
「──これは、越えてはならぬ一線でした」
側に仕える者たちが一瞬で息を飲み、空気が凍りつく。
「……先程から、感情で語るな。王は常に、国家の安定を──」
「語っているのは、感情ではありません」
リオールの声は鋭く、しかし決して声を荒げはしない。
「感情であれば──私はここで剣を抜き、貴方の喉元にそれを突き立てていることでしょう」
王の目が細められる。
その鋭利な沈黙すら、リオールは正面から受け止めた。
「ですが、私は皇太子です。王に成る者です。ならば、理を以て、語りましょう」
しばしの間、王は沈黙する。
リオールの瞳は燃えていた。
怒りと、決意とが混ざりあいながら、それでも一切を押し隠し、堂々と恐れることなく立っている。
──その姿に、王はひとつの確信に至った。
「……あのオメガを、それほどまでに愛しているのか?」
低く投げかけられた言葉に、リオールは答えない。
けれど、その沈黙こそがすべてを物語っていた。
王はゆっくりと立ち上がる。
「ならば、愛で王権を変えてみせるがいい! 情にすがるような王を、余は必要としない。力で押し通す王だけが、王座に座る資格を持つのだ」
リオールは、王の言葉をこう理解した。
愛したいなら愛せばいい。
だがその結果、国をどう保ち、どう治めるのか。その全責任を負える覚悟があるのか。
リオールは、静かに頭を下げる。
「承知しました、陛下」
その姿に、かすかに微笑を浮かべた王は、玉座に腰を下ろす。
「せいぜい、抗ってみせよ、皇太子」
玉座の間に、静寂が満ちていた。
二つのまなざしが交差し、やがて静かに離れる。
愛を手にした少年が、王となる確かな第一歩を踏み出した。
執務室に緊張が走る。
陽春は冷や汗をにじませながら、アスカ付きの侍女──清夏の報告に耳を傾けていた。
「……今、なんと申した」
低く落ちたリオールの声には、明らかに抑えきれない怒気が滲んでいた。
清夏はひとつ深く息を吸い、頭を下げたまま、はっきりとした声で告げる。
「アスカ様のもとに、宦官が遣わされました 」
次の瞬間、椅子の脚が大きな音を立てて引き摺られた。
リオールが立ち上がったその動きに、部屋の空気が一瞬で凍りつく。
少年の身にしては不相応な、王の血が宿る者だけが持つアルファの威圧が、室内を支配した。
「誰が──そんな命を?」
低く、喉の奥で鳴る獣のような声。
その問いかけに、清夏は唾液を飲み込んだ。
「……王命とのことです」
「なぜ、今この瞬間にそんなことをする必要がある……! アスカは──」
リオールの拳が机に叩きつけられた。
重い音が響き、机の上の書類が宙に舞った。
「……私と会うことすら拒んでいたのに」
その声には、怒りの奥に痛みが混じっていた。
アスカに拒絶されたこと。それを理由に身を引いた自分。
けれど、その影で、別の誰かがアスカに触れようとしている。
その事実が、許せなかった。
「すぐに向かう」
誰かが何かを発言するよりも早く、リオールは駆け出していた。
陽春が「お待ちを!」と叫んだが、その声も届かない。
怒りに満ちたまま、リオールはアスカのもとへと走り抜けた。
間に合わないかもしれない。
頭ではそうわかっていても、足は止められなかった。
リオールがアスカのもとに着いた時、そこはあまりにも静まり返っていた。
誰もいないかのような、そこだけ切り取られたかのような空間は異質で。
静かに宮の中に入れば、小さく啜り泣く声が聞こえた。
アスカが発情期に入ってからというもの、リオールは毎日抑制剤を飲んではいるが、それでも完全に防げるわけではないフェロモンの香りが動悸を速くさせる。
「──アスカ様……」
薄氷の声が悲痛に満ちている。
リオールはこの先にいるアスカの姿を想像して、怒る心を鎮めること無く扉を開いた。
「アスカ……っ」
「っ!」
中にいたアスカも薄氷も、リオールの声を聞いて肩を大きくふるわせた。
薄氷は慌てて平伏す。
アスカは怯えたような顔でリオールを見てすぐ、何を言うことも無く俯いた。
「──さがれ」
静かに命令され、薄氷はそのまま部屋を後にする。
寝台で上体を起こし、手元に視線を落としているアスカの衣服や髪は、少し乱れてはいるが、誰かに触れられたような形跡は見当たらない。
「アスカ……アスカ、こちらをむいては、くれないか」
「っ、」
アスカの肩が震えている。
その細い背に、リオールは思わず手を伸ばしかけて──しかし、止めた。
もし今、触れてしまえば、自分の中の怒りが堰を切ってあふれてしまいそうだった。
声を荒げてはならない。眉をひそめてもいけない。
今はただ、静かに、穏やかに、彼の隣にいるべきなのだとわかっていた。
「……大丈夫だ。誰も、そなたに触れない。私が、絶対にそうさせない」
言葉とは裏腹に、拳は震えていた。
爪が食い込むほどに手を握りしめ、掌からは血が溢れる。
嗅ぎ取った甘く熱を帯びた香り。
その香りに、別の男の存在が混じっていなかったこと。
それだけが、唯一の救いだった。
──どうして、アスカがこんな目に遭わなければならなかったのだ。
怒りが胸を刺す。だが、それを顔には出さない。
「無事で、良かった」
「っ、リオール様……っ」
リオールはゆっくりと微笑んだ。
無理矢理貼り付けたその顔は、まるで仮面のよう。
アスカの手が伸びてきて、リオールの手に重なる。
熱い体温。きっと今は起きていることすら辛いに違いないはず。
それでも──自分の手を取ってくれた。
守りきれなかったという悔しさと、それでもなお求められたことへの救いが、胸を締めつける。
「眠れそうか……?」
「……はぁ、リオール様……」
リオールの顔を見て、声を聞いて、匂いを嗅いで、アスカは少し安心したのか、甘く熱を帯びた声で名前を呼ばれると、リオールの腰がズクンと疼いた。
そんな体の反応に気づかなかったかのように、冷静にアスカを寝台に寝かせる。
リオールの指が、そっとアスカの髪を梳く。
細い肩はまだ小さく震えているけれど、少しずつ呼吸が落ち着いていった。
「大丈夫だ。何も怖くない。そばにいる」
その囁きに、アスカは微かに頷く。
まぶたがゆっくりと閉じられた。
リオールはしばらくの間、その寝顔をじっと見つめていた。
指一本触れぬよう、ただ静かに。
アスカが安らかに眠ってくれることが、今は何よりも救いだった。
小さな寝息を確認してから、リオールはそっと立ち上がり、息を詰めるようにして扉を開け、音を立てぬよう閉じる。
──そして、次の瞬間だった。
バンッ、と廊下の壁に拳が叩きつけられた。
「……ふざけるな……ッ」
声を殺しながら、リオールは荒く息を吐く。
手の甲はその衝撃でぱっくりと裂け、血が滲む。
顔を上げたその瞳は、いつもの冷静さなど欠片もなかった。
剥き出しの怒りと、どうしようもない無力感。
今にも噛みつきそうな獣のような呼吸。
「殿下ッ」
陽春が顔を青ざめさせ、慌てて駆け寄る。
「……私が、触れられないからと、宦官なんぞを送り込むとは……っ!」
低く呟いたその声には、ただ怒りだけではなく、自分を責めるような痛みも滲んでいた。
触れたいと思った。
けれど、アスカは拒んだ。それは、自分がまだ子供だからだ。
そのことを、理解していたし、受け入れていたはずだった。
──だが、
「だからって……っ、どうして、他の男が許されるのだ……!」
リオールの声がわずかに震える。
『代わり』を宛てがわれるほど、自分は無力なのか。
そう思うたび、胸の奥に針が突き刺さるようだった。
震える手で、壁を殴る。
何度も、何度も、声を殺しながら。
思い出すのは──怯えた目で自分を見た、アスカの顔だった。
涙に濡れた睫毛、恐怖が色濃く映る瞳。
震える声で、自分の名を呼んだときのあの表情が、焼きついて離れない。
リオールの肩が、ぶるりと揺れる。
胸の奥からこみ上げるのは、悔しさだった。
「……私は、皇太子だというのに……」
ぎり、と奥歯を噛み締める。
王の命令ひとつで、大切な人に手をかけさせるような仕打ちを、ただ黙って見ていることしかできないなんて。
リオールは拳を握りしめたまま、低く息を吐いた。
抑え込んでいた感情の波が、ゆっくりと形を成し始める。
「アスカを守れるのは……私しかいない」
ただ隣にいるだけでは、足りない。
優しく手を差し伸べるだけでは、何も変えられない。
だったら──変えればいい。
この理不尽を、国を。
アスカの涙を、二度と、見なくて済むように。
リオールは、そっと拳を開いた。
血の滲む掌を見つめながら、静かに言葉を落とす。
「……陛下に会わせろ。今すぐに、だ」
「はっ」
陽春は急いで廊下を駆けていく。
その後ろ姿を見送ると、リオールはわずかに目を伏せた。
「──殿下」
不意に声が掛けられ、そちらを一瞥すると、清夏がすぐそばにたっていた。
「先に手当を」
「……かまわん。放っておけ」
「それはできません。そのままではきっと、アスカ様が悲しまれます」
そう言われるとリオールは手を差し出すしかなかった。
医務官が足早にやって来て、手際良く傷の手当をする。
「殿下。陛下とのお話が終わり次第、こちらにいらっしゃいますか」
薄氷が尋ねると、リオールは「……そうだな」と言葉を紡ぐ。
「もしも、アスカが私を呼ぶのなら、必ずここに戻ってこよう」
それは少しの期待が込められていた。
発情期とはいえ、体を重ねなくてもいい。
フェロモンに反応して体が疼こうが、ただそばにいて見守ることはできる。
「アスカが目を覚ましたら、伝えておいてくれ。──私は、どのようなアスカも愛している」
薄氷は息を飲み、そうして確かに頷いた。
王座の間に呼び出されたリオールは、いつものように頭を下げたりせず、静かに国王を見据える。
「──陛下。ひとつ、お話がございます」
「なんだ、急に。おまえが礼儀を欠くとは珍しいな」
「礼儀を尽くすに値しない命令が、つい先程、ございましたので」
王は目を細める。だが、リオールは怯まなかった。
「発情期のオメガに無断で宦官を宛てがうなど、暴挙です。私情ではなく、国家の安寧を考える者のすることではありません」
「……私情ではない、だと?」
「はい。もしこれが貴族の誰かに向けられた命令であっても、私は同じように意見したでしょう」
少しだけ間を置いて──リオールは一歩、王に近づく。
「王たる者は、力を誇示することで威厳を保つのではなく、理によって民と臣下を導くべきです。私はそう信じています」
玉座の上、威圧感すら纏って座る王の前で、リオールは一歩も退かずにその瞳を見据えていた。
睨むのでも、媚びるのでもない、真っすぐな視線。
「……私が黙して従っていたのは、幼さからでも、陛下を恐れていたからでもありません」
王の眉がわずかに動いた。
「それが、この国の秩序であり、王命であるならば、それには従わなければならないと、心得ております。──ですが」
リオールの声がわずかに低くなる。
「──これは、越えてはならぬ一線でした」
側に仕える者たちが一瞬で息を飲み、空気が凍りつく。
「……先程から、感情で語るな。王は常に、国家の安定を──」
「語っているのは、感情ではありません」
リオールの声は鋭く、しかし決して声を荒げはしない。
「感情であれば──私はここで剣を抜き、貴方の喉元にそれを突き立てていることでしょう」
王の目が細められる。
その鋭利な沈黙すら、リオールは正面から受け止めた。
「ですが、私は皇太子です。王に成る者です。ならば、理を以て、語りましょう」
しばしの間、王は沈黙する。
リオールの瞳は燃えていた。
怒りと、決意とが混ざりあいながら、それでも一切を押し隠し、堂々と恐れることなく立っている。
──その姿に、王はひとつの確信に至った。
「……あのオメガを、それほどまでに愛しているのか?」
低く投げかけられた言葉に、リオールは答えない。
けれど、その沈黙こそがすべてを物語っていた。
王はゆっくりと立ち上がる。
「ならば、愛で王権を変えてみせるがいい! 情にすがるような王を、余は必要としない。力で押し通す王だけが、王座に座る資格を持つのだ」
リオールは、王の言葉をこう理解した。
愛したいなら愛せばいい。
だがその結果、国をどう保ち、どう治めるのか。その全責任を負える覚悟があるのか。
リオールは、静かに頭を下げる。
「承知しました、陛下」
その姿に、かすかに微笑を浮かべた王は、玉座に腰を下ろす。
「せいぜい、抗ってみせよ、皇太子」
玉座の間に、静寂が満ちていた。
二つのまなざしが交差し、やがて静かに離れる。
愛を手にした少年が、王となる確かな第一歩を踏み出した。
53
あなたにおすすめの小説

【完結】愛されたかった僕の人生
Kanade
BL
✯オメガバース
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。
今日も《夫》は帰らない。
《夫》には僕以外の『番』がいる。
ねぇ、どうしてなの?
一目惚れだって言ったじゃない。
愛してるって言ってくれたじゃないか。
ねぇ、僕はもう要らないの…?
独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。

〈完結〉【書籍化・取り下げ予定】「他に愛するひとがいる」と言った旦那様が溺愛してくるのですが、そういうのは不要です
ごろごろみかん。
恋愛
「私には、他に愛するひとがいます」
「では、契約結婚といたしましょう」
そうして今の夫と結婚したシドローネ。
夫は、シドローネより四つも年下の若き騎士だ。
彼には愛するひとがいる。
それを理解した上で政略結婚を結んだはずだったのだが、だんだん夫の様子が変わり始めて……?

夫には好きな相手がいるようです。愛されない僕は針と糸で未来を縫い直します。
伊織
BL
裕福な呉服屋の三男・桐生千尋(きりゅう ちひろ)は、行商人の家の次男・相馬誠一(そうま せいいち)と結婚した。
子どもの頃に憧れていた相手との結婚だったけれど、誠一はほとんど笑わず、冷たい態度ばかり。
ある日、千尋は誠一宛てに届いた女性からの恋文を見つけてしまう。
――自分はただ、家からの援助目当てで選ばれただけなのか?
失望と涙の中で、千尋は気づく。
「誠一に頼らず、自分の力で生きてみたい」
針と糸を手に、幼い頃から得意だった裁縫を活かして、少しずつ自分の居場所を築き始める。
やがて町の人々に必要とされ、笑顔を取り戻していく千尋。
そんな千尋を見て、誠一の心もまた揺れ始めて――。
涙から始まる、すれ違い夫婦の再生と恋の物語。
※本作は明治時代初期~中期をイメージしていますが、BL作品としての物語性を重視し、史実とは異なる設定や表現があります。
※誤字脱字などお気づきの点があるかもしれませんが、温かい目で読んでいただければ嬉しいです。

【完結】可愛いあの子は番にされて、もうオレの手は届かない
天田れおぽん
BL
劣性アルファであるオズワルドは、劣性オメガの幼馴染リアンを伴侶に娶りたいと考えていた。
ある日、仕えている王太子から名前も知らないオメガのうなじを噛んだと告白される。
運命の番と王太子の言う相手が落としていったという髪飾りに、オズワルドは見覚えがあった――――
※他サイトにも掲載中
★⌒*+*⌒★ ☆宣伝☆ ★⌒*+*⌒★
「婚約破棄された不遇令嬢ですが、イケオジ辺境伯と幸せになります!」
が、レジーナブックスさまより発売中です。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

愛しい番に愛されたいオメガなボクの奮闘記
天田れおぽん
BL
ボク、アイリス・ロックハートは愛しい番であるオズワルドと出会った。
だけどオズワルドには初恋の人がいる。
でもボクは負けない。
ボクは愛しいオズワルドの唯一になるため、番のオメガであることに甘えることなく頑張るんだっ!
※「可愛いあの子は番にされて、もうオレの手は届かない」のオズワルド君の番の物語です。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
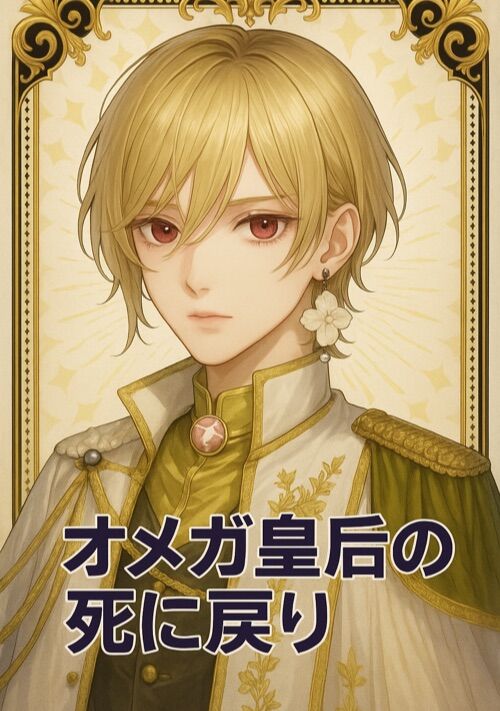
【完結・ルート分岐あり】オメガ皇后の死に戻り〜二度と思い通りにはなりません〜
ivy
BL
魔術師の家門に生まれながら能力の発現が遅く家族から虐げられて暮らしていたオメガのアリス。
そんな彼を国王陛下であるルドルフが妻にと望み生活は一変する。
幸せになれると思っていたのに生まれた子供共々ルドルフに殺されたアリスは目が覚めると子供の頃に戻っていた。
もう二度と同じ轍は踏まない。
そう決心したアリスの戦いが始まる。

流れる星、どうかお願い
ハル
BL
羽水 結弦(うすい ゆずる)
オメガで高校中退の彼は国内の財閥の一つ、羽水本家の次男、羽水要と番になって約8年
高層マンションに住み、気兼ねなくスーパーで買い物をして好きな料理を食べられる。同じ性の人からすれば恵まれた生活をしている彼
そんな彼が夜、空を眺めて流れ星に祈る願いはただ一つ
”要が幸せになりますように”
オメガバースの世界を舞台にしたアルファ×オメガ
王道な関係の二人が織りなすラブストーリーをお楽しみに!
一応、更新していきますが、修正が入ることは多いので
ちょっと読みづらくなったら申し訳ないですが
お付き合いください!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















