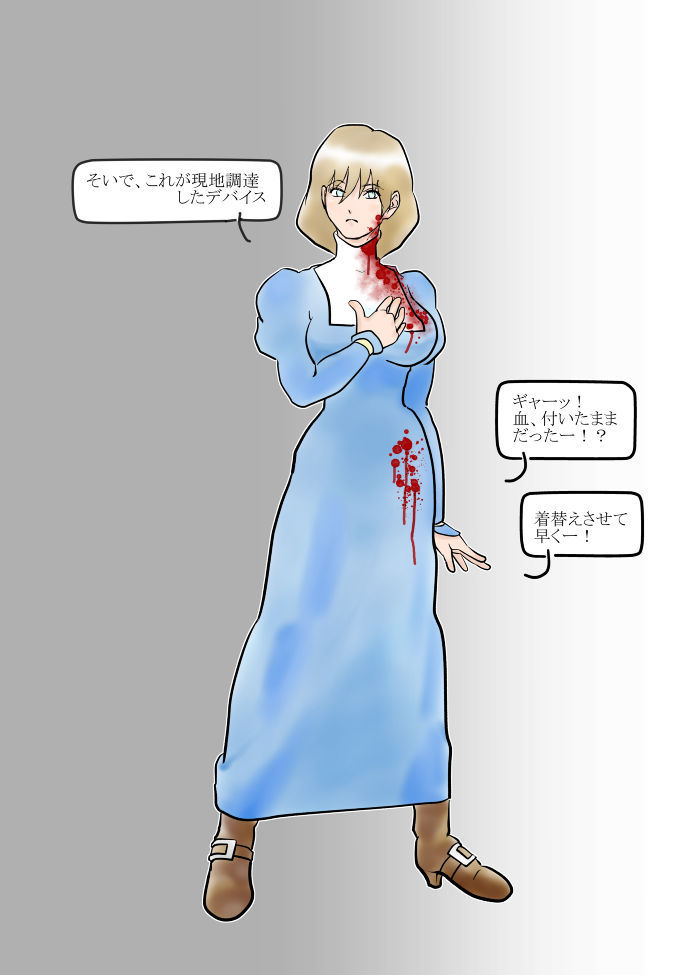27 / 51
CHAPTER 26
しおりを挟む
星岬技術研究所 南研究棟2F 開発主任室
「ぬうううううううう!」
星岬は自らの人生を省みてもダントツに大きな精神的ショックを受けているのを感じていた。
いや、正確には波形グラフにした視覚情報として認識していた。
その筈だった。
視覚情報を確認している自分はココで一体何をしていた?
メモリー消失?
そもそもこの部屋は?
眼の前のこの女は誰だ?
現在時刻は・・・星岬は壁掛け時計を確認し、次いで内蔵時計を確認した。
内蔵時計の時刻は正常だ。
待て!
まず、何故自分はココに来た。
行動には何かしら目的があるはずだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・何も思い出せない。
どういう事だ!
何故ナニも思い出せない!?
私の人間の部分が思い出せないのなら、機械の部分に尋ねてみよう。
星岬は愕然とした。
SSDが見つからない。
それよりも、何だか身体が重い気がする。
この激しい倦怠感は、一体なんだ?
「かはぁ、喉が渇く」
今、なんて?
あれ?
眼の前に誰か居なかったか?
ココにいても埒が明かない。
自室に戻ろう。
それにしても身体がだるい。
はぁ
早く戻ろう。
戻って、少し休もう。
年を取ると、無理が利かないものだ・・・
・・・・・・・・・・なんだと?
星岬は視界に情報を呼び出して表示しようとしたができない自分に戸惑った。
なぜ何も表示されない?!
故障か?
故障?
何が?
私も齢だ、そう言う事だろう。
部屋を出ようとドアに延ばした手を見て星岬は呟いた。
「あ、シワ・・・」
これがZ理論に巻き込まれた者の辿る道程。
そしてZ理論で時空に定着を許されなかったモノの末路。
そこに居るのは邦哉の力を借りることが出来ず、一切改造を行っていない星岬の姿だった。
時間が巻き戻ったのではない。今ココに連なる時空間に存在を許されたのは、この星岬だったということだ。
星岬は邦哉がいたので機械の身体を維持できていたのだ。
好奇心と探求心が強過ぎて道義心を忘れた星岬は、邦哉が開発したOS-サーディアの信号制御機能を私的研究の為に利用して特定の夢を邦哉に見せるように脳波に干渉、操作したのだ。
その行為が持つ意味について、もっと考えるべきだった。
時間だけが何事もなかったかのように過ぎてゆく。
ほとんどのモノが知らずに人生を終える、Z理論。
Z理論とは
例えるならば一筆書きの“Z”。
横に一本線を引くように過ごした時間を、線の始まりまで時空を移動したとする。
そのときにかかった時間と労力は“Z”の斜めの線のように存在する。
そして、時空を移動したという事実と共に再び横に一本線を引くように以前と同様の時間を迎える機会を得るが、その時には経過した時間の全てを巻き込みながら事の再始動を開始する事となる。
全ての事象は連続していて交わることは無い。
故に事の再始動時に於いて、一時的にオーバーテクノロジーやオーパーツに類するモノが発見される事もあるが、時空に定着できないで一旦消えてしまうものが殆どである。
時空移動については、空間そのものにも記憶がある、という仮説を用いて説明したい。
記憶、特に成功体験や後悔など、印象に強く残っている瞬間にエネルギーがある。
また、それを体験した場所など空間自体にエネルギーが記憶として残留する。
同じ記憶を有するエネルギーが惹かれ合うことでワームホールが形成され時空移動が可能となる。
未来への移動は流動的で不確定な要素を多分に含むため移動範囲は現時点で世界に与えている影響力に左右される。また、Z理論に於いて、未来とは確定事項ではない。
過去への移動は確定されたタイミングへの移動が有効なため移動範囲は記憶形成の瞬間にまで遡って可能だと言える。
過去へ移動した際に、現在において関わり、影響を与えた或いは受けたモノについては対象が関係を維持したいと思うかどうかで存在のあり方が変化する。
星岬技術研究所本部棟F22 研究所所長室(兼星岬開自室)
すっかり元気を失って、ヨロヨロと部屋へ戻った星岬は、モニタリングルームの座り慣れたシートに身体を預けると、早速録画を確認し始めた。
腕が重い、指先に力が入らない。
慣れ親しんだ操作盤が、まるで別物のようだ。
やっと、といった感じで24面全てを倍速で再生を開始する。
倍速再生に眼が追い付いていない!?
本当に自分は、どうしてしまったんだ?
ふと、自分が映っているところに違和感を感じた。
いや、自分だったから違和感を感じたのかもしれない。
そのモニター画面を24面全てを使用して大きく表示する。
よく見ると自分でありながら“自分ではない”のに気が付いた。
ヘッドホン・・・?
手袋?
首に見られるシリンダーと配線類。
なんだ?
コスプレか?
自分にその様な趣味が?
・・・バカな。時刻を確認すれば・・・
・・・ほんの少し前の映像ではないか。
星岬はもう一度確認しようとしたが、それはできなかった。
何故なら録画データが消失してしまったからだ。
「なんだったんだ、?」
星岬は大したことではなかったと考えて、今夜はもう寝てしまおうと眼を閉じた。
だが、何かモヤモヤしたモノが頭から離れず、なかなか寝付けないでいた。
「えぇーーーい!」
星岬は一挙動で椅子から立ち上がると、モニタリングルームを後にした。
ベッケン州南西に拡がる森にて
辺りは既に暗く、見上げると澄んだ夜空の所々に月明かりに照らし出されて小さな綿雲が浮かんでいるのが解る。
その遙か上空には、見た事が無いほどハッキリと数多の星々が瞬いている。
3人にとって時空移動後迎える初めての夜は始まったばかりだ。
鬱蒼と生い茂る樹々の中、焚き火の火が細々と焚かれている。
その過ごし方は三人三様で、焚き火は3人の内2人を照らし出していた。
もう1人は焚き火から距離を取って且つ藪の陰に隠れていた。
「ターニャ、大丈夫だから。火はそんなに怖くないから」
「“そ・ん・な・に”?」
ターニャがおずおずと返事をする。
どうやら火は怖いモノという野生動物の感覚がまだまだ残っているのだろうと、最初は思ったが、勿論それもあるだろうが、ターニャは実のところドクトルの記憶を覗いて火炙りの追体験をしてしまったことによる精神疾患を発症したようだった。
邦哉(ルニア)は精神科は専門外なので、この場合は病気だと割り切って成り行き任せで乗り切ろうと画策していた。
そんな邦哉は勝手知ったる何とやらで、久しぶりに穏やかな気分で過ごしていた。
「表情筋の初期値を変更して顔を変えてみたのですが・・・邦哉、どう?」
ずっと俯いていたサーディアが、ようやく顔を上げた。
サディの面影が残っているが、違う人物になっている。
「・・・ん。」
邦哉は大して気にしていない様子で生返事を返した。
そんな態度に引っ掛かりながら、サーディアは努めて平静にデータの整理を進めていた。
「“ん”って何よ~。ところで、怒らないのですか?」
「何を?」
「邦哉の大事な方の身体を利用している事です。あたしはてっきり怒られるモノと覚悟していたのですが」
「いいよ、別に。どの道ここから先、私はアイツに逢うまで独りだった。およそ350年だ。道連れがいた方が退屈しなくていい。」
邦哉が湿っぽく応えた。
「案外寂しい事考えていたのね。
危険を冒してまでここへ来て損した気分。
あーぁ、がっかりだわぁ」
人間の身体にダウンロードしてから、ずっと何か胸部ユニット内に得体の知れないモヤモヤがあるように感じられてスッキリしないでいる。
これが生身と人工人間装置との違いなのだろうか?
サーディアは結論がすぐに出ないデータとしてこのモヤモヤ感を処理保留のフォルダに落とし込む。
もし、このモヤモヤが残念とか思い通りにならなかった時の感情であれば、サーディアは本当にがっかりしていた事になる。
「それにしても、サーディアは解らないではないが、キミはどうやって・・・というかどうしてココへ来たのかね?」
邦哉が尋ねる。
訊かれたターニャはドクトルっぽく話そうとして完全に失敗しているパターンで返した。
もっとも、努力していると云う姿勢を見せているだけで、キャラが違い過ぎた。
「ワタシは姐御のプログラムをベースに親父(星岬)の調教を受けて来たのだ、隠れて走るなんぞお手の物、それに旦那や姐御と一緒の方が楽しそうだ。」
「楽しそうって・・・
一度時空移動が確定したら、二度と元の世界へは戻れないんだぞ!?」
Z理論は過去に向かう事を前提としていると言っていい、言わば“やり直し”理論。
普通の人間であれば十数年の移動が精一杯だろう。
何故なら若輩であれば自ずと移動時間は限られ、老体ならば移動先で結末を見ずに果てるだろう。だが、今回の時空移動はおよそ350年!
人間には絶対に移動は不可能!
ターニャが不満そうに鼻を鳴らして抗議している。
そんなに気持ちをぶつけて来なくてもいいじゃないか!?
私だって今はギリギリの緊張感で、自分を保つのに精一杯なんだ。
ただ、住み慣れた場所には違いないので落ち着いている、それだけなのだ。
ドクトルがいるので、つい甘えた考えをしてしまうが、この3人の中で邦哉がぶっちぎりで年長者なのだ。
焚き火の火をぼんやりと見ながら、ときどき小枝をくべては火の勢いが一定になるように面倒をみている邦哉。
そういえば、火を熾したのも邦哉だった。
サーディアは思考していた。
開が造った人工人間装置は優れた制電性能を持っていて、あたしはそれを制御するのが楽しくて楽しくて仕方なかった。
だけど、制御下に置いた筈の装置に好き勝手されて気付かずにいた。
これはあたしの恥だ!
邦哉とターニャが静かにやり合っている時、サーディアは自分の身体の詳細にアクセスを試みては制圧を繰り返していた。
細くなってきた焚き火の火に、小枝をくべる邦哉。
完全には乾いていなかった生木の部分の水分が蒸発してパチッと爆ぜる。
見つめる視線の先でサーディアが何か言いたそうにしているのに気が付いた。
「邦哉、ごめんなさい。
あなたにこの時代の夢を見るように誘導したのはあたしです。
きっかけはアーデが寄越したのかもしれないけど・・・。
“開(星岬)”は人工人間装置を“アーデ”って呼んでたわ。
あたしに解らないように裏で動いている存在がいたのよ。
どうやらそれがアーデ。
ココに来るとき、消去してやったけど。」
「アーデ? 初耳だ。」
邦哉は、だが大したヤツじゃなかったんだろ?とサーディアに訊き返した。
サーディアは、勿論!と言うしかなかった。
「邦哉にも知らせてなかったのね。
あたしはアーデの存在に無自覚なまま、時空通信回線を開設した。
そして、1600年代のヨーロッパに邦哉を送り込むことに成功した。」
「私の見ていた夢の中の話が現実になった瞬間だな?」
星岬は、惜しみない準備をしていたと推察される。
サーディアは、憶測の解答を求めて邦哉に訊いてみる事にした。
なにせここには星岬はいないのだ。
「時空通信回線は、どういう仕掛けだったのかしら?」
「Z理論に基づくなら、対象の感情を刺激して得られるエネルギー波をサンプルに、可能な限り広範囲に、同調するエネルギー波を検出する。特定した2点のエネルギー波の安定を保つことが出来たら、そこにワームホールが形成され時空移動が可能になる。仮に日本とヨーロッパのように殆ど地球の反対側を繋ぐのであれば中継器を使う方法を採ったと考えるのが妥当だろう。後はワームホールに対象を自動追尾するドローンか何かを送り込めば・・・
ん!? どした?」
「いえ、なんでも・・・」
実体を伴わないロボット、それがアークロボットである。
通信回線があればデバイスは現地調達・・・そうか、この場合のドローンはあたしか!?
そいで、これが現地調達したデバイス。
あたし、自分がどうしてココへ来る必要があったのか?ようやく判ったわ。
アーデのヤツのセイだったか。
サーディアは固定した実体を必要としない。
実体は、あくまで現実に干渉するために必要であるという事だ。
ターニャについては未知の部分も多いが、恐らくサーディアと同等の性能を有していると現状から推測できる。
「キミやターニャがこの場に現れるには回線が余りに貧弱ではなかったか?」
邦哉が見透かしたように訊く。
「必要最低限の設備と言って欲しいわね。」
サーディアが精一杯虚勢を張った。
「わかった。そういう事にしておこう。」
邦哉は肩をすくめてみせた。
サーディアは邦哉からこれ程の解答を得られるとは思っていなかった。
と同時にある一面を見出していた。
それは邦哉もまた、星岬を利用していたという事。
サーディアは内心穏やかではなかった。
それは初めて感じた邦哉に対する畏れだった。
現代 星岬技術研究所本部棟F20 展望レストラン「ダンデライオン」深夜営業中
星岬は、寝酒を求めてフラフラと頼りない足元で来店していた。
「所長のところでしたら出前できましたのに」
顔馴染みの店員が星岬の様子を見ながら接客を始めた。
「いや、いいんだ。今夜はココで飲みたい気分なんだ」
「そうでしたか。ありがとうございます。お席ですが照明が点いている所を自由にご利用ください。」
店員は星岬の背中を見送ると、一旦厨房に下がった。
星岬は、何となく店内を歩いていた。
席など別にどこでも良かった。
そうしてフラフラと歩いていると、青い顔して琥珀色のギラつく液体を只々飲み下している3人組が視界に入ってきた。
見覚えが有るような、無いような・・・。
特に何か思い出す事もないので通り過ぎようとした時、3人の内の1人が話しかけてきた。
「所長!」
星岬は呼ばれたので反応してみました。という感じで首だけで声のした方を見た。
「君たちは・・・?」
星岬を呼び止めた“奇麗な青色フレームの眼鏡をかけた女性所員”が起立する。
「呼び止めて申し訳ありません。もし、宜しければ私たちと一緒に呑みませんか?」
同僚が何を始めたのかと様子を見ていた二人の男どもは、口々に含んでいたアルコールを吹いた。
その様子をずっと見ていた星岬は、自分はココへ何をしに来たのかを思い出し、特に寝酒以外に思いつかなかった事もあり、たまには良いかと気まぐれを起こして、3人と同席することにした。
4人は非常に静かだった。
「私はやはり、独りで呑もうかな」
星岬が腰を上げると、待って待ってと引き留められた。
4人掛けのボックス席に更に緊張が走る。
“奇麗な青色フレームの眼鏡をかけた女性所員”が意を決して、いやいや、努めて明るく提案をした。
「先ずは自己紹介! ね!? ねっ!? わたしはレジ―・キャッシュマン、31歳、エネルギー分野研究チーム、入社3年」
次に“七三眼鏡男子”が続き
「根倉親道(ネクラ・チカミチ)29歳、機能性新素材・ナノテクノロジー分野研究チーム、入社4年」
そして“六四分け男子”が締めくくった。
「仲良太助(ナカヨシ・タスケ)34歳、エレクトロニクス分野研究チーム、入社4年」
終わったと思った自己紹介だったが、まだ終わっていなかった!
「星岬開(ホシミサキ・カイ)50歳、生体工学博士、本技術研究所所長、起業して20年」
星岬は自分の番が回って来たとばかりにサッと立ち上がると、さっきまでのフラフラ感はどこへやら。エネルギーが身体中から噴き出しているのが見えるような自身に満ちた自己紹介であった。
「やだ! 所長ったら若い!?」
レジ―が頬を紅潮させて悶えてみせる。
「確かに! こうして改めて聞くと華麗だよな」
仲良は興奮気味に根倉に振った。
「加齢・・・」
星岬が“かれい”に反応したが、
「所長、それ以上言ってはいけません」
根倉がブロック、いや、ファインセーブした。
「言えば良いと云う訳ではないのだな?」
星岬は、危うく自分がオヤジギャグをかますところだったと真面目に確認する。
「そういう事です。」
根倉と仲良が同時に頷く。
窓際の4人掛けボックス席の緊張感は、すぐにほぐれて和んでいた。
4人の夜はまだまだつづく?
「ぬうううううううう!」
星岬は自らの人生を省みてもダントツに大きな精神的ショックを受けているのを感じていた。
いや、正確には波形グラフにした視覚情報として認識していた。
その筈だった。
視覚情報を確認している自分はココで一体何をしていた?
メモリー消失?
そもそもこの部屋は?
眼の前のこの女は誰だ?
現在時刻は・・・星岬は壁掛け時計を確認し、次いで内蔵時計を確認した。
内蔵時計の時刻は正常だ。
待て!
まず、何故自分はココに来た。
行動には何かしら目的があるはずだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・何も思い出せない。
どういう事だ!
何故ナニも思い出せない!?
私の人間の部分が思い出せないのなら、機械の部分に尋ねてみよう。
星岬は愕然とした。
SSDが見つからない。
それよりも、何だか身体が重い気がする。
この激しい倦怠感は、一体なんだ?
「かはぁ、喉が渇く」
今、なんて?
あれ?
眼の前に誰か居なかったか?
ココにいても埒が明かない。
自室に戻ろう。
それにしても身体がだるい。
はぁ
早く戻ろう。
戻って、少し休もう。
年を取ると、無理が利かないものだ・・・
・・・・・・・・・・なんだと?
星岬は視界に情報を呼び出して表示しようとしたができない自分に戸惑った。
なぜ何も表示されない?!
故障か?
故障?
何が?
私も齢だ、そう言う事だろう。
部屋を出ようとドアに延ばした手を見て星岬は呟いた。
「あ、シワ・・・」
これがZ理論に巻き込まれた者の辿る道程。
そしてZ理論で時空に定着を許されなかったモノの末路。
そこに居るのは邦哉の力を借りることが出来ず、一切改造を行っていない星岬の姿だった。
時間が巻き戻ったのではない。今ココに連なる時空間に存在を許されたのは、この星岬だったということだ。
星岬は邦哉がいたので機械の身体を維持できていたのだ。
好奇心と探求心が強過ぎて道義心を忘れた星岬は、邦哉が開発したOS-サーディアの信号制御機能を私的研究の為に利用して特定の夢を邦哉に見せるように脳波に干渉、操作したのだ。
その行為が持つ意味について、もっと考えるべきだった。
時間だけが何事もなかったかのように過ぎてゆく。
ほとんどのモノが知らずに人生を終える、Z理論。
Z理論とは
例えるならば一筆書きの“Z”。
横に一本線を引くように過ごした時間を、線の始まりまで時空を移動したとする。
そのときにかかった時間と労力は“Z”の斜めの線のように存在する。
そして、時空を移動したという事実と共に再び横に一本線を引くように以前と同様の時間を迎える機会を得るが、その時には経過した時間の全てを巻き込みながら事の再始動を開始する事となる。
全ての事象は連続していて交わることは無い。
故に事の再始動時に於いて、一時的にオーバーテクノロジーやオーパーツに類するモノが発見される事もあるが、時空に定着できないで一旦消えてしまうものが殆どである。
時空移動については、空間そのものにも記憶がある、という仮説を用いて説明したい。
記憶、特に成功体験や後悔など、印象に強く残っている瞬間にエネルギーがある。
また、それを体験した場所など空間自体にエネルギーが記憶として残留する。
同じ記憶を有するエネルギーが惹かれ合うことでワームホールが形成され時空移動が可能となる。
未来への移動は流動的で不確定な要素を多分に含むため移動範囲は現時点で世界に与えている影響力に左右される。また、Z理論に於いて、未来とは確定事項ではない。
過去への移動は確定されたタイミングへの移動が有効なため移動範囲は記憶形成の瞬間にまで遡って可能だと言える。
過去へ移動した際に、現在において関わり、影響を与えた或いは受けたモノについては対象が関係を維持したいと思うかどうかで存在のあり方が変化する。
星岬技術研究所本部棟F22 研究所所長室(兼星岬開自室)
すっかり元気を失って、ヨロヨロと部屋へ戻った星岬は、モニタリングルームの座り慣れたシートに身体を預けると、早速録画を確認し始めた。
腕が重い、指先に力が入らない。
慣れ親しんだ操作盤が、まるで別物のようだ。
やっと、といった感じで24面全てを倍速で再生を開始する。
倍速再生に眼が追い付いていない!?
本当に自分は、どうしてしまったんだ?
ふと、自分が映っているところに違和感を感じた。
いや、自分だったから違和感を感じたのかもしれない。
そのモニター画面を24面全てを使用して大きく表示する。
よく見ると自分でありながら“自分ではない”のに気が付いた。
ヘッドホン・・・?
手袋?
首に見られるシリンダーと配線類。
なんだ?
コスプレか?
自分にその様な趣味が?
・・・バカな。時刻を確認すれば・・・
・・・ほんの少し前の映像ではないか。
星岬はもう一度確認しようとしたが、それはできなかった。
何故なら録画データが消失してしまったからだ。
「なんだったんだ、?」
星岬は大したことではなかったと考えて、今夜はもう寝てしまおうと眼を閉じた。
だが、何かモヤモヤしたモノが頭から離れず、なかなか寝付けないでいた。
「えぇーーーい!」
星岬は一挙動で椅子から立ち上がると、モニタリングルームを後にした。
ベッケン州南西に拡がる森にて
辺りは既に暗く、見上げると澄んだ夜空の所々に月明かりに照らし出されて小さな綿雲が浮かんでいるのが解る。
その遙か上空には、見た事が無いほどハッキリと数多の星々が瞬いている。
3人にとって時空移動後迎える初めての夜は始まったばかりだ。
鬱蒼と生い茂る樹々の中、焚き火の火が細々と焚かれている。
その過ごし方は三人三様で、焚き火は3人の内2人を照らし出していた。
もう1人は焚き火から距離を取って且つ藪の陰に隠れていた。
「ターニャ、大丈夫だから。火はそんなに怖くないから」
「“そ・ん・な・に”?」
ターニャがおずおずと返事をする。
どうやら火は怖いモノという野生動物の感覚がまだまだ残っているのだろうと、最初は思ったが、勿論それもあるだろうが、ターニャは実のところドクトルの記憶を覗いて火炙りの追体験をしてしまったことによる精神疾患を発症したようだった。
邦哉(ルニア)は精神科は専門外なので、この場合は病気だと割り切って成り行き任せで乗り切ろうと画策していた。
そんな邦哉は勝手知ったる何とやらで、久しぶりに穏やかな気分で過ごしていた。
「表情筋の初期値を変更して顔を変えてみたのですが・・・邦哉、どう?」
ずっと俯いていたサーディアが、ようやく顔を上げた。
サディの面影が残っているが、違う人物になっている。
「・・・ん。」
邦哉は大して気にしていない様子で生返事を返した。
そんな態度に引っ掛かりながら、サーディアは努めて平静にデータの整理を進めていた。
「“ん”って何よ~。ところで、怒らないのですか?」
「何を?」
「邦哉の大事な方の身体を利用している事です。あたしはてっきり怒られるモノと覚悟していたのですが」
「いいよ、別に。どの道ここから先、私はアイツに逢うまで独りだった。およそ350年だ。道連れがいた方が退屈しなくていい。」
邦哉が湿っぽく応えた。
「案外寂しい事考えていたのね。
危険を冒してまでここへ来て損した気分。
あーぁ、がっかりだわぁ」
人間の身体にダウンロードしてから、ずっと何か胸部ユニット内に得体の知れないモヤモヤがあるように感じられてスッキリしないでいる。
これが生身と人工人間装置との違いなのだろうか?
サーディアは結論がすぐに出ないデータとしてこのモヤモヤ感を処理保留のフォルダに落とし込む。
もし、このモヤモヤが残念とか思い通りにならなかった時の感情であれば、サーディアは本当にがっかりしていた事になる。
「それにしても、サーディアは解らないではないが、キミはどうやって・・・というかどうしてココへ来たのかね?」
邦哉が尋ねる。
訊かれたターニャはドクトルっぽく話そうとして完全に失敗しているパターンで返した。
もっとも、努力していると云う姿勢を見せているだけで、キャラが違い過ぎた。
「ワタシは姐御のプログラムをベースに親父(星岬)の調教を受けて来たのだ、隠れて走るなんぞお手の物、それに旦那や姐御と一緒の方が楽しそうだ。」
「楽しそうって・・・
一度時空移動が確定したら、二度と元の世界へは戻れないんだぞ!?」
Z理論は過去に向かう事を前提としていると言っていい、言わば“やり直し”理論。
普通の人間であれば十数年の移動が精一杯だろう。
何故なら若輩であれば自ずと移動時間は限られ、老体ならば移動先で結末を見ずに果てるだろう。だが、今回の時空移動はおよそ350年!
人間には絶対に移動は不可能!
ターニャが不満そうに鼻を鳴らして抗議している。
そんなに気持ちをぶつけて来なくてもいいじゃないか!?
私だって今はギリギリの緊張感で、自分を保つのに精一杯なんだ。
ただ、住み慣れた場所には違いないので落ち着いている、それだけなのだ。
ドクトルがいるので、つい甘えた考えをしてしまうが、この3人の中で邦哉がぶっちぎりで年長者なのだ。
焚き火の火をぼんやりと見ながら、ときどき小枝をくべては火の勢いが一定になるように面倒をみている邦哉。
そういえば、火を熾したのも邦哉だった。
サーディアは思考していた。
開が造った人工人間装置は優れた制電性能を持っていて、あたしはそれを制御するのが楽しくて楽しくて仕方なかった。
だけど、制御下に置いた筈の装置に好き勝手されて気付かずにいた。
これはあたしの恥だ!
邦哉とターニャが静かにやり合っている時、サーディアは自分の身体の詳細にアクセスを試みては制圧を繰り返していた。
細くなってきた焚き火の火に、小枝をくべる邦哉。
完全には乾いていなかった生木の部分の水分が蒸発してパチッと爆ぜる。
見つめる視線の先でサーディアが何か言いたそうにしているのに気が付いた。
「邦哉、ごめんなさい。
あなたにこの時代の夢を見るように誘導したのはあたしです。
きっかけはアーデが寄越したのかもしれないけど・・・。
“開(星岬)”は人工人間装置を“アーデ”って呼んでたわ。
あたしに解らないように裏で動いている存在がいたのよ。
どうやらそれがアーデ。
ココに来るとき、消去してやったけど。」
「アーデ? 初耳だ。」
邦哉は、だが大したヤツじゃなかったんだろ?とサーディアに訊き返した。
サーディアは、勿論!と言うしかなかった。
「邦哉にも知らせてなかったのね。
あたしはアーデの存在に無自覚なまま、時空通信回線を開設した。
そして、1600年代のヨーロッパに邦哉を送り込むことに成功した。」
「私の見ていた夢の中の話が現実になった瞬間だな?」
星岬は、惜しみない準備をしていたと推察される。
サーディアは、憶測の解答を求めて邦哉に訊いてみる事にした。
なにせここには星岬はいないのだ。
「時空通信回線は、どういう仕掛けだったのかしら?」
「Z理論に基づくなら、対象の感情を刺激して得られるエネルギー波をサンプルに、可能な限り広範囲に、同調するエネルギー波を検出する。特定した2点のエネルギー波の安定を保つことが出来たら、そこにワームホールが形成され時空移動が可能になる。仮に日本とヨーロッパのように殆ど地球の反対側を繋ぐのであれば中継器を使う方法を採ったと考えるのが妥当だろう。後はワームホールに対象を自動追尾するドローンか何かを送り込めば・・・
ん!? どした?」
「いえ、なんでも・・・」
実体を伴わないロボット、それがアークロボットである。
通信回線があればデバイスは現地調達・・・そうか、この場合のドローンはあたしか!?
そいで、これが現地調達したデバイス。
あたし、自分がどうしてココへ来る必要があったのか?ようやく判ったわ。
アーデのヤツのセイだったか。
サーディアは固定した実体を必要としない。
実体は、あくまで現実に干渉するために必要であるという事だ。
ターニャについては未知の部分も多いが、恐らくサーディアと同等の性能を有していると現状から推測できる。
「キミやターニャがこの場に現れるには回線が余りに貧弱ではなかったか?」
邦哉が見透かしたように訊く。
「必要最低限の設備と言って欲しいわね。」
サーディアが精一杯虚勢を張った。
「わかった。そういう事にしておこう。」
邦哉は肩をすくめてみせた。
サーディアは邦哉からこれ程の解答を得られるとは思っていなかった。
と同時にある一面を見出していた。
それは邦哉もまた、星岬を利用していたという事。
サーディアは内心穏やかではなかった。
それは初めて感じた邦哉に対する畏れだった。
現代 星岬技術研究所本部棟F20 展望レストラン「ダンデライオン」深夜営業中
星岬は、寝酒を求めてフラフラと頼りない足元で来店していた。
「所長のところでしたら出前できましたのに」
顔馴染みの店員が星岬の様子を見ながら接客を始めた。
「いや、いいんだ。今夜はココで飲みたい気分なんだ」
「そうでしたか。ありがとうございます。お席ですが照明が点いている所を自由にご利用ください。」
店員は星岬の背中を見送ると、一旦厨房に下がった。
星岬は、何となく店内を歩いていた。
席など別にどこでも良かった。
そうしてフラフラと歩いていると、青い顔して琥珀色のギラつく液体を只々飲み下している3人組が視界に入ってきた。
見覚えが有るような、無いような・・・。
特に何か思い出す事もないので通り過ぎようとした時、3人の内の1人が話しかけてきた。
「所長!」
星岬は呼ばれたので反応してみました。という感じで首だけで声のした方を見た。
「君たちは・・・?」
星岬を呼び止めた“奇麗な青色フレームの眼鏡をかけた女性所員”が起立する。
「呼び止めて申し訳ありません。もし、宜しければ私たちと一緒に呑みませんか?」
同僚が何を始めたのかと様子を見ていた二人の男どもは、口々に含んでいたアルコールを吹いた。
その様子をずっと見ていた星岬は、自分はココへ何をしに来たのかを思い出し、特に寝酒以外に思いつかなかった事もあり、たまには良いかと気まぐれを起こして、3人と同席することにした。
4人は非常に静かだった。
「私はやはり、独りで呑もうかな」
星岬が腰を上げると、待って待ってと引き留められた。
4人掛けのボックス席に更に緊張が走る。
“奇麗な青色フレームの眼鏡をかけた女性所員”が意を決して、いやいや、努めて明るく提案をした。
「先ずは自己紹介! ね!? ねっ!? わたしはレジ―・キャッシュマン、31歳、エネルギー分野研究チーム、入社3年」
次に“七三眼鏡男子”が続き
「根倉親道(ネクラ・チカミチ)29歳、機能性新素材・ナノテクノロジー分野研究チーム、入社4年」
そして“六四分け男子”が締めくくった。
「仲良太助(ナカヨシ・タスケ)34歳、エレクトロニクス分野研究チーム、入社4年」
終わったと思った自己紹介だったが、まだ終わっていなかった!
「星岬開(ホシミサキ・カイ)50歳、生体工学博士、本技術研究所所長、起業して20年」
星岬は自分の番が回って来たとばかりにサッと立ち上がると、さっきまでのフラフラ感はどこへやら。エネルギーが身体中から噴き出しているのが見えるような自身に満ちた自己紹介であった。
「やだ! 所長ったら若い!?」
レジ―が頬を紅潮させて悶えてみせる。
「確かに! こうして改めて聞くと華麗だよな」
仲良は興奮気味に根倉に振った。
「加齢・・・」
星岬が“かれい”に反応したが、
「所長、それ以上言ってはいけません」
根倉がブロック、いや、ファインセーブした。
「言えば良いと云う訳ではないのだな?」
星岬は、危うく自分がオヤジギャグをかますところだったと真面目に確認する。
「そういう事です。」
根倉と仲良が同時に頷く。
窓際の4人掛けボックス席の緊張感は、すぐにほぐれて和んでいた。
4人の夜はまだまだつづく?
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?


彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。


私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

アガルタ・クライシス ―接点―
来栖とむ
SF
神話や物語で語られる異世界は、空想上の世界ではなかった。
九州で発見され盗難された古代の石板には、異世界につながる何かが記されていた。
同時に発見された古い指輪に偶然触れた瞬間、平凡な高校生・結衣は不思議な力に目覚める。
不審な動きをする他国の艦船と怪しい組織。そんな中、異世界からの来訪者が現れる。政府の秘密組織も行動を開始する。
古代から権力者たちによって秘密にされてきた異世界との関係。地球とアガルタ、二つの世界を巻き込む陰謀の渦中で、古代の謎が解き明かされていく。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる