26 / 34
26 無意識から始まる意識
しおりを挟む
昼間から始まったパーティーは夕刻にお開きとなった。
その後の片付けにてんてこ舞いだったリリアナだが、残念ながらそのまま宿舎に直行することは叶わなかった。
何故なら、同じく疲れているはずのジルベルトに、いつも通り小屋へ来いと呼び出しをくらっていたからだ。
「鉄人ですか? それとも超人? え、ドM変態?」
女官が王太子にかけた言葉である。言われたジルベルトは顎に手を添えて図面とにらめっこしながら呟いた。
「誉められた」
「誉めてないっ」
リリアナは自分の台詞を取られてプーッと頬を膨らませ、ジルベルトは図面からリリアナに視線を移し「あはは」と楽しそうに声を上げた。
その一瞬のギャップに、リリアナはまた謎の胸の苦しさを味わった。
その綺麗な顔を、あまり無邪気に緩めて欲しくない。心臓に悪い。と、心中でぼやきながらリリアナもジルベルトの横に腰をおろした。
「どうだった、パーティーは。いい男が沢山いただろ」
「仕事に集中してましたし、なんならジルベルト様に邪魔された感ありますけどっ」
「へー、お前ってルチャーノみたいなのが好みだったのか」
「別にそんなのないですって」
「ふーん……」
興味があるのかないのか、ジルベルトの返しはいまいち鈍く、妙な沈黙が小屋に残った。
なんとなくリリアナは身じろぎして、座り直す。
「そ、そういえば、そのルチャーノさんから手紙受け取ったんですけど」
「ああ」
「ノルド様――じゃなくてアンナ様からの手紙だったんですけど、オヴェスト様への謝罪の手紙をことづけられたんです。宛先がわからないからと」
「そうか。俺も知らされてはないから、チェルソン通して聞いてみとくよ」
「それで私、出来ればオヴェスト様と直接話をさせてもらいたくて……休日多めに取って行ってきていいですか?」
そこでジルベルトは視線をリリアナに再び向けた。
「行くのか?」
「はい。手紙じゃ色々聞きづらいんですよね。あの池事件のこと、どーにも気になって」
「そりゃ俺も気にはなってるけど、どこの領地か知らないぞ? 遠方だったらどーするんだ」
「なので長めの休暇を」
「……」
ジルベルトは押し黙ってしまった。
リリアナはなんとなく、前世のオフィスレディだった頃を思い出した。職場の上司に有給もらう時のあの独特の重苦しさを。
しばらく無言でジーッと見つめられて、リリアナは妙に緊張してきた。その無言の圧に耐えてようやく、ジルベルトが口を開いた。
「……じゃあ二日な。二日で行って帰ってこれる距離なら許そう」
「なぜ二日だけなんですか」
「お前を野放しにすることに、一抹の不安を覚えるどころか胸騒ぎしか起きないからだ」
「失礼なっ。過保護ですかっ」
ブッとリリアナが吹き出せば、眉間に皺を寄せていたジルベルトもフッと脱力したように微笑む。
「間違っても池に飛び込むなよ。困ったら、ちゃんと大人を呼ぶんだぞ」
「子供のお使いですかっ」
ふたりでひとしきり笑いあってから、リリアナはポンッと手を打った。
「あ、そうだ。ジルベルト様が私いない間寂しい思いをしないように、これ、渡しておきますね」
「なんで俺が寂しがらなきゃならないんだよ」
そう言いながらも、リリアナがポケットから取り出した紙を素直に受け取った。
そこには、色んな形の絵と簡単な説明文が書き込まれていた。
「私が思い出した便利グッズです」
「思い出した?」
「あ、思い付いたってやつです。夢で見たというか。これなんかどうです? 炊飯器って言って、釜の前に人がはり付いていなくても時間が来ればお米が炊き上がるんです。あとこれは、電話って言って、遠く離れた相手と声のやり取りが出来るもので」
「すごいな!」
ジルベルトはパアッと顔を輝かせた。
「え、どういう仕組みでいけば、遠くの声が届くんだろうか!」
「それなんですよねー。私もその辺の知識がさっぱりで、もっと普段から身近なことに興味を持つべきでしたねー」
この世界にはまだ電気の文化がない。鉱石の力でどこまで近付けることが出来るのか、リリアナには思い付かないのだ。
「お前ほんと、俺を飽きさせないな」
つくづくと、感心したようにジルベルトはメモ用紙とリリアナを見比べている。
「でも、それだけじゃ、実現させるにはなんの手掛かりにもなりませんよ」
リリアナ的には不甲斐ない自分にしょぼくれている。もっと自分に知識があれば、王子の本当の力になれただろうと思うと、少し寂しいとも思ってしまう。
「なんだよ、その顔は」
ジルベルトはご機嫌に笑っていた。
「実現だなんて、もっとずっと先にあるもんなんだから。どうすればどうやったらって、考えて想像して失敗して気付いて、そういう過程がワクワクして一番大事なことだろ」
「……ジルベルト様」
リリアナは目を見開いた。
王子がいつもどうして、疲労困憊の中でも小屋で物作りに没頭するのかを、そして彼の本質を、なんとなくわかった気がした。
王太子としての自分と本来の性分が大きく剥離している中で、バランスを保つ為に切り替える為に、てのもあるかもしれないけど。彼にとっては趣味の範囲を越えて、なくてはならないものなのだろう。物作りをすることで、自分を養い構築しているのかもしれない。
急に黙りこんだリリアナに、ジルベルトは大きな瞳を瞬かせてから口の端をニッと上げてみせた。
「俺に惚れるなよ」
「……だっ」
リリアナはいつもの調子で言い返そうとして、言葉に詰まった。
オットーならともかく、いやオットーでさえ本来ならお目通りにも叶わないような、自分とは対極にあるような人間である。ましてや目の前のジルベルトは、このマルクレン王国の王太子殿下。
うっかり恋していいような相手ではないし、庶民はそのうっかりすら有り得ないほど遠い遠い雲の上の存在である。
(あまりにも、勘違い起こすほどに距離が近すぎるんだ)
紫と青が角度によってじんわりと色を変えていく吸い込まれそうな瞳。陶器のようにすべらかな肌を持ちつつ男らしい顎や喉のライン。サラサラと凪いだ風でさえ拾ってしまうまばゆい銀髪。
間近で見るには、恐ろしいほど清廉潔白で美麗にもほどがある。
そんな完璧な王子が時々、溢すように無邪気な笑顔をみせてくる。まるで自分達の間に、溝も壁も薄い膜でさえないように名を呼びからかい、無防備な姿をさらけ出して。
どこかできっと、ずっと自衛は働いている。リリアナは薄々それに気付いている。
自分はいずれ酒場の娘に戻るし、王太子殿下は妃を娶る。城下町で披露パレードで自分は街道から大きく手を振って「おめでとう!」と叫んでいるのさえ鮮やかに想像もできる。
だからリリアナは「惚れませんっ」と言い切った。
なのに今度は、ジルベルトの耳が赤く染まってきた。
「お、お前、そーゆうことはもっとはやく瞬発で拒否しろっ。もたつくようなことじゃないだろっ」
「はやかったですってばっ」
「いーや、おそすぎだっ」
それぞれの作業に意識を向けるように、ふたりして背中を向けて座り直した。
背中越しになれば、余計に相手の気配や呼気に、意識がとらわれてしまうというのに。
その後の片付けにてんてこ舞いだったリリアナだが、残念ながらそのまま宿舎に直行することは叶わなかった。
何故なら、同じく疲れているはずのジルベルトに、いつも通り小屋へ来いと呼び出しをくらっていたからだ。
「鉄人ですか? それとも超人? え、ドM変態?」
女官が王太子にかけた言葉である。言われたジルベルトは顎に手を添えて図面とにらめっこしながら呟いた。
「誉められた」
「誉めてないっ」
リリアナは自分の台詞を取られてプーッと頬を膨らませ、ジルベルトは図面からリリアナに視線を移し「あはは」と楽しそうに声を上げた。
その一瞬のギャップに、リリアナはまた謎の胸の苦しさを味わった。
その綺麗な顔を、あまり無邪気に緩めて欲しくない。心臓に悪い。と、心中でぼやきながらリリアナもジルベルトの横に腰をおろした。
「どうだった、パーティーは。いい男が沢山いただろ」
「仕事に集中してましたし、なんならジルベルト様に邪魔された感ありますけどっ」
「へー、お前ってルチャーノみたいなのが好みだったのか」
「別にそんなのないですって」
「ふーん……」
興味があるのかないのか、ジルベルトの返しはいまいち鈍く、妙な沈黙が小屋に残った。
なんとなくリリアナは身じろぎして、座り直す。
「そ、そういえば、そのルチャーノさんから手紙受け取ったんですけど」
「ああ」
「ノルド様――じゃなくてアンナ様からの手紙だったんですけど、オヴェスト様への謝罪の手紙をことづけられたんです。宛先がわからないからと」
「そうか。俺も知らされてはないから、チェルソン通して聞いてみとくよ」
「それで私、出来ればオヴェスト様と直接話をさせてもらいたくて……休日多めに取って行ってきていいですか?」
そこでジルベルトは視線をリリアナに再び向けた。
「行くのか?」
「はい。手紙じゃ色々聞きづらいんですよね。あの池事件のこと、どーにも気になって」
「そりゃ俺も気にはなってるけど、どこの領地か知らないぞ? 遠方だったらどーするんだ」
「なので長めの休暇を」
「……」
ジルベルトは押し黙ってしまった。
リリアナはなんとなく、前世のオフィスレディだった頃を思い出した。職場の上司に有給もらう時のあの独特の重苦しさを。
しばらく無言でジーッと見つめられて、リリアナは妙に緊張してきた。その無言の圧に耐えてようやく、ジルベルトが口を開いた。
「……じゃあ二日な。二日で行って帰ってこれる距離なら許そう」
「なぜ二日だけなんですか」
「お前を野放しにすることに、一抹の不安を覚えるどころか胸騒ぎしか起きないからだ」
「失礼なっ。過保護ですかっ」
ブッとリリアナが吹き出せば、眉間に皺を寄せていたジルベルトもフッと脱力したように微笑む。
「間違っても池に飛び込むなよ。困ったら、ちゃんと大人を呼ぶんだぞ」
「子供のお使いですかっ」
ふたりでひとしきり笑いあってから、リリアナはポンッと手を打った。
「あ、そうだ。ジルベルト様が私いない間寂しい思いをしないように、これ、渡しておきますね」
「なんで俺が寂しがらなきゃならないんだよ」
そう言いながらも、リリアナがポケットから取り出した紙を素直に受け取った。
そこには、色んな形の絵と簡単な説明文が書き込まれていた。
「私が思い出した便利グッズです」
「思い出した?」
「あ、思い付いたってやつです。夢で見たというか。これなんかどうです? 炊飯器って言って、釜の前に人がはり付いていなくても時間が来ればお米が炊き上がるんです。あとこれは、電話って言って、遠く離れた相手と声のやり取りが出来るもので」
「すごいな!」
ジルベルトはパアッと顔を輝かせた。
「え、どういう仕組みでいけば、遠くの声が届くんだろうか!」
「それなんですよねー。私もその辺の知識がさっぱりで、もっと普段から身近なことに興味を持つべきでしたねー」
この世界にはまだ電気の文化がない。鉱石の力でどこまで近付けることが出来るのか、リリアナには思い付かないのだ。
「お前ほんと、俺を飽きさせないな」
つくづくと、感心したようにジルベルトはメモ用紙とリリアナを見比べている。
「でも、それだけじゃ、実現させるにはなんの手掛かりにもなりませんよ」
リリアナ的には不甲斐ない自分にしょぼくれている。もっと自分に知識があれば、王子の本当の力になれただろうと思うと、少し寂しいとも思ってしまう。
「なんだよ、その顔は」
ジルベルトはご機嫌に笑っていた。
「実現だなんて、もっとずっと先にあるもんなんだから。どうすればどうやったらって、考えて想像して失敗して気付いて、そういう過程がワクワクして一番大事なことだろ」
「……ジルベルト様」
リリアナは目を見開いた。
王子がいつもどうして、疲労困憊の中でも小屋で物作りに没頭するのかを、そして彼の本質を、なんとなくわかった気がした。
王太子としての自分と本来の性分が大きく剥離している中で、バランスを保つ為に切り替える為に、てのもあるかもしれないけど。彼にとっては趣味の範囲を越えて、なくてはならないものなのだろう。物作りをすることで、自分を養い構築しているのかもしれない。
急に黙りこんだリリアナに、ジルベルトは大きな瞳を瞬かせてから口の端をニッと上げてみせた。
「俺に惚れるなよ」
「……だっ」
リリアナはいつもの調子で言い返そうとして、言葉に詰まった。
オットーならともかく、いやオットーでさえ本来ならお目通りにも叶わないような、自分とは対極にあるような人間である。ましてや目の前のジルベルトは、このマルクレン王国の王太子殿下。
うっかり恋していいような相手ではないし、庶民はそのうっかりすら有り得ないほど遠い遠い雲の上の存在である。
(あまりにも、勘違い起こすほどに距離が近すぎるんだ)
紫と青が角度によってじんわりと色を変えていく吸い込まれそうな瞳。陶器のようにすべらかな肌を持ちつつ男らしい顎や喉のライン。サラサラと凪いだ風でさえ拾ってしまうまばゆい銀髪。
間近で見るには、恐ろしいほど清廉潔白で美麗にもほどがある。
そんな完璧な王子が時々、溢すように無邪気な笑顔をみせてくる。まるで自分達の間に、溝も壁も薄い膜でさえないように名を呼びからかい、無防備な姿をさらけ出して。
どこかできっと、ずっと自衛は働いている。リリアナは薄々それに気付いている。
自分はいずれ酒場の娘に戻るし、王太子殿下は妃を娶る。城下町で披露パレードで自分は街道から大きく手を振って「おめでとう!」と叫んでいるのさえ鮮やかに想像もできる。
だからリリアナは「惚れませんっ」と言い切った。
なのに今度は、ジルベルトの耳が赤く染まってきた。
「お、お前、そーゆうことはもっとはやく瞬発で拒否しろっ。もたつくようなことじゃないだろっ」
「はやかったですってばっ」
「いーや、おそすぎだっ」
それぞれの作業に意識を向けるように、ふたりして背中を向けて座り直した。
背中越しになれば、余計に相手の気配や呼気に、意識がとらわれてしまうというのに。
2
あなたにおすすめの小説

王太子様お願いです。今はただの毒草オタク、過去の私は忘れて下さい
シンさん
恋愛
ミリオン侯爵の娘エリザベスには秘密がある。それは本当の侯爵令嬢ではないという事。
お花や薬草を売って生活していた、貧困階級の私を子供のいない侯爵が養子に迎えてくれた。
ずっと毒草と共に目立たず生きていくはずが、王太子の婚約者候補に…。
雑草メンタルの毒草オタク侯爵令嬢と
王太子の恋愛ストーリー
☆ストーリーに必要な部分で、残酷に感じる方もいるかと思います。ご注意下さい。
☆毒草名は作者が勝手につけたものです。
表紙 Bee様に描いていただきました

【完結】婚約者なんて眼中にありません
らんか
恋愛
あー、気が抜ける。
婚約者とのお茶会なのにときめかない……
私は若いお子様には興味ないんだってば。
やだ、あの騎士団長様、素敵! 確か、お子さんはもう成人してるし、奥様が亡くなってからずっと、独り身だったような?
大人の哀愁が滲み出ているわぁ。
それに強くて守ってもらえそう。
男はやっぱり包容力よね!
私も守ってもらいたいわぁ!
これは、そんな事を考えているおじ様好きの婚約者と、その婚約者を何とか振り向かせたい王子が奮闘する物語……
短めのお話です。
サクッと、読み終えてしまえます。

わたくしが社交界を騒がす『毒女』です~旦那様、この結婚は離婚約だったはずですが?
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
※完結しました。
離婚約――それは離婚を約束した結婚のこと。
王太子アルバートの婚約披露パーティーで目にあまる行動をした、社交界でも噂の毒女クラリスは、辺境伯ユージーンと結婚するようにと国王から命じられる。
アルバートの側にいたかったクラリスであるが、国王からの命令である以上、この結婚は断れない。
断れないのはユージーンも同じだったようで、二人は二年後の離婚を前提として結婚を受け入れた――はずなのだが。
毒女令嬢クラリスと女に縁のない辺境伯ユージーンの、離婚前提の結婚による空回り恋愛物語。
※以前、短編で書いたものを長編にしたものです。
※蛇が出てきますので、苦手な方はお気をつけください。

嘘つくつもりはなかったんです!お願いだから忘れて欲しいのにもう遅い。王子様は異世界転生娘を溺愛しているみたいだけどちょっと勘弁して欲しい。
季邑 えり
恋愛
異世界転生した記憶をもつリアリム伯爵令嬢は、自他ともに認めるイザベラ公爵令嬢の腰ぎんちゃく。
今日もイザベラ嬢をよいしょするつもりが、うっかりして「王子様は理想的な結婚相手だ」と言ってしまった。それを偶然に聞いた王子は、早速リアリムを婚約者候補に入れてしまう。
王子様狙いのイザベラ嬢に睨まれたらたまらない。何とかして婚約者になることから逃れたいリアリムと、そんなリアリムにロックオンして何とかして婚約者にしたい王子。
婚約者候補から逃れるために、偽りの恋人役を知り合いの騎士にお願いすることにしたのだけど…なんとこの騎士も一筋縄ではいかなかった!
おとぼけ転生娘と、麗しい王子様の恋愛ラブコメディー…のはず。
イラストはベアしゅう様に描いていただきました。

東雲の空を行け ~皇妃候補から外れた公爵令嬢の再生~
くる ひなた
恋愛
「あなたは皇妃となり、国母となるのよ」
幼い頃からそう母に言い聞かされて育ったロートリアス公爵家の令嬢ソフィリアは、自分こそが同い年の皇帝ルドヴィークの妻になるのだと信じて疑わなかった。父は長く皇帝家に仕える忠臣中の忠臣。皇帝の母の覚えもめでたく、彼女は名実ともに皇妃最有力候補だったのだ。
ところがその驕りによって、とある少女に対して暴挙に及んだことを理由に、ソフィリアは皇妃候補から外れることになる。
それから八年。母が敷いた軌道から外れて人生を見つめ直したソフィリアは、豪奢なドレスから質素な文官の制服に着替え、皇妃ではなく補佐官として皇帝ルドヴィークの側にいた。
上司と部下として、友人として、さらには密かな思いを互いに抱き始めた頃、隣国から退っ引きならない事情を抱えた公爵令嬢がやってくる。
「ルドヴィーク様、私と結婚してくださいませ」
彼女が執拗にルドヴィークに求婚し始めたことで、ソフィリアも彼との関係に変化を強いられることになっていく……
『蔦王』より八年後を舞台に、元悪役令嬢ソフィリアと、皇帝家の三男坊である皇帝ルドヴィークの恋の行方を描きます。

そのご寵愛、理由が分かりません
秋月真鳥
恋愛
貧乏子爵家の長女、レイシーは刺繍で家計を支える庶民派令嬢。
幼いころから前世の夢を見ていて、その技術を活かして地道に慎ましく生きていくつもりだったのに——
「君との婚約はなかったことに」
卒業パーティーで、婚約者が突然の裏切り!
え? 政略結婚しなくていいの? ラッキー!
領地に帰ってスローライフしよう!
そう思っていたのに、皇帝陛下が現れて——
「婚約破棄されたのなら、わたしが求婚してもいいよね?」
……は???
お金持ちどころか、国ごと背負ってる人が、なんでわたくしに!?
刺繍を褒められ、皇宮に連れて行かれ、気づけば妃教育まで始まり——
気高く冷静な陛下が、なぜかわたくしにだけ甘い。
でもその瞳、どこか昔、夢で見た“あの少年”に似ていて……?
夢と現実が交差する、とんでもスピード婚約ラブストーリー!
理由は分からないけど——わたくし、寵愛されてます。
※毎朝6時、夕方18時更新!
※他のサイトにも掲載しています。

【完結】僻地の修道院に入りたいので、断罪の場にしれーっと混ざってみました。
櫻野くるみ
恋愛
王太子による独裁で、貴族が息を潜めながら生きているある日。
夜会で王太子が勝手な言いがかりだけで3人の令嬢達に断罪を始めた。
ひっそりと空気になっていたテレサだったが、ふと気付く。
あれ?これって修道院に入れるチャンスなんじゃ?
子爵令嬢のテレサは、神父をしている初恋の相手の元へ行ける絶好の機会だととっさに考え、しれーっと断罪の列に加わり叫んだ。
「わたくしが代表して修道院へ参ります!」
野次馬から急に現れたテレサに、その場の全員が思った。
この娘、誰!?
王太子による恐怖政治の中、地味に生きてきた子爵令嬢のテレサが、初恋の元伯爵令息に会いたい一心で断罪劇に飛び込むお話。
主人公は猫を被っているだけでお転婆です。
完結しました。
小説家になろう様にも投稿しています。
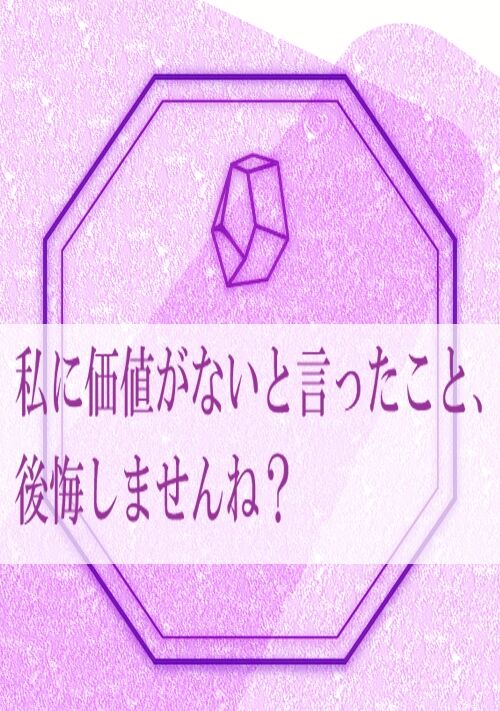
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















