あなたにおすすめの小説

【完結】姉は聖女? ええ、でも私は白魔導士なので支援するぐらいしか取り柄がありません。
猫屋敷 むぎ
ファンタジー
誰もが憧れる勇者と最強の騎士が恋したのは聖女。それは私ではなく、姉でした。
復活した魔王に侯爵領を奪われ没落した私たち姉妹。そして、誰からも愛される姉アリシアは神の祝福を受け聖女となり、私セレナは支援魔法しか取り柄のない白魔導士のまま。
やがてヴァルミエール国王の王命により結成された勇者パーティは、
勇者、騎士、聖女、エルフの弓使い――そして“おまけ”の私。
過去の恋、未来の恋、政略婚に揺れ動く姉を見つめながら、ようやく私の役割を自覚し始めた頃――。
魔王城へと北上する魔王討伐軍と共に歩む勇者パーティは、
四人の魔将との邂逅、秘められた真実、そしてそれぞれの試練を迎え――。
輝く三人の恋と友情を“すぐ隣で見つめるだけ”の「聖女の妹」でしかなかった私。
けれど魔王討伐の旅路の中で、“仲間を支えるとは何か”に気付き、
やがて――“本当の自分”を見つけていく――。
そんな、ちょっぴり切ない恋と友情と姉妹愛、そして私の成長の物語です。
※本作の章構成:
第一章:アカデミー&聖女覚醒編
第二章:勇者パーティ結成&魔王討伐軍北上編
第三章:帰郷&魔将・魔王決戦編
※「小説家になろう」にも掲載(異世界転生・恋愛12位)
※ アルファポリス完結ファンタジー8位。応援ありがとうございます。
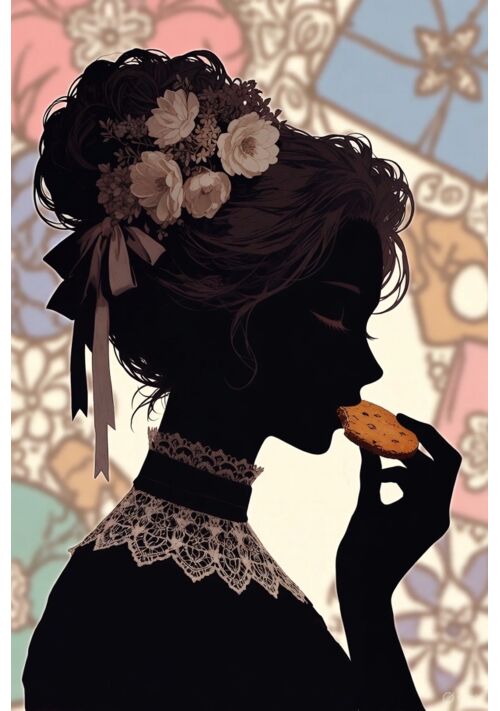
誰からも食べられずに捨てられたおからクッキーは異世界転生して肥満令嬢を幸福へ導く!
ariya
ファンタジー
誰にも食べられずゴミ箱に捨てられた「おからクッキー」は、異世界で150kgの絶望令嬢・ロザリンドと出会う。
転生チートを武器に、88kgの減量を導く!
婚約破棄され「豚令嬢」と罵られたロザリンドは、
クッキーの叱咤と分裂で空腹を乗り越え、
薔薇のように美しく咲き変わる。
舞踏会での王太子へのスカッとする一撃、
父との涙の再会、
そして最後の別れ――
「僕を食べてくれて、ありがとう」
捨てられた一枚が紡いだ、奇跡のダイエット革命!
※カクヨム・小説家になろうでも同時掲載中
※表紙イラストはAIに作成していただきました。

冷遇妃マリアベルの監視報告書
Mag_Mel
ファンタジー
シルフィード王国に敗戦国ソラリから献上されたのは、"太陽の姫"と讃えられた妹ではなく、悪女と噂される姉、マリアベル。
第一王子の四番目の妃として迎えられた彼女は、王宮の片隅に追いやられ、嘲笑と陰湿な仕打ちに晒され続けていた。
そんな折、「王家の影」は第三王子セドリックよりマリアベルの監視業務を命じられる。年若い影が記す報告書には、ただ静かに耐え続け、死を待つかのように振舞うひとりの女の姿があった。
王位継承争いと策謀が渦巻く王宮で、冷遇妃の運命は思わぬ方向へと狂い始める――。
(小説家になろう様にも投稿しています)

【完結】ひとつだけ、ご褒美いただけますか?――没落令嬢、氷の王子にお願いしたら溺愛されました。
猫屋敷 むぎ
恋愛
没落伯爵家の娘の私、ノエル・カスティーユにとっては少し眩しすぎる学院の舞踏会で――
私の願いは一瞬にして踏みにじられました。
母が苦労して買ってくれた唯一の白いドレスは赤ワインに染められ、
婚約者ジルベールは私を見下ろしてこう言ったのです。
「君は、僕に恥をかかせたいのかい?」
まさか――あの優しい彼が?
そんなはずはない。そう信じていた私に、現実は冷たく突きつけられました。
子爵令嬢カトリーヌの冷笑と取り巻きの嘲笑。
でも、私には、味方など誰もいませんでした。
ただ一人、“氷の王子”カスパル殿下だけが。
白いハンカチを差し出し――その瞬間、止まっていた時間が静かに動き出したのです。
「……ひとつだけ、ご褒美いただけますか?」
やがて、勇気を振り絞って願った、小さな言葉。
それは、水底に沈んでいた私の人生をすくい上げ、
冷たい王子の心をそっと溶かしていく――最初の奇跡でした。
没落令嬢ノエルと、孤独な氷の王子カスパル。
これは、そんなじれじれなふたりが“本当の幸せを掴むまで”のお話です。
※全10話+番外編・約2.5万字の短編。一気読みもどうぞ
※わんこが繋ぐ恋物語です
※因果応報ざまぁ。最後は甘く、後味スッキリ

この野菜は悪役令嬢がつくりました!
真鳥カノ
ファンタジー
幼い頃から聖女候補として育った公爵令嬢レティシアは、婚約者である王子から突然、婚約破棄を宣言される。
花や植物に『恵み』を与えるはずの聖女なのに、何故か花を枯らしてしまったレティシアは「偽聖女」とまで呼ばれ、どん底に落ちる。
だけどレティシアの力には秘密があって……?
せっかくだからのんびり花や野菜でも育てようとするレティシアは、どこでもやらかす……!
レティシアの力を巡って動き出す陰謀……?
色々起こっているけれど、私は今日も野菜を作ったり食べたり忙しい!
毎日2〜3回更新予定
だいたい6時30分、昼12時頃、18時頃のどこかで更新します!

置き去りにされた転生シンママはご落胤を秘かに育てるも、モトサヤはご容赦のほどを
青の雀
恋愛
シンママから玉の輿婚へ
学生時代から付き合っていた王太子のレオンハルト・バルセロナ殿下に、ある日突然、旅先で置き去りにされてしまう。
お忍び旅行で来ていたので、誰も二人の居場所を知らなく、両親のどちらかが亡くなった時にしか発動しないはずの「血の呪縛」魔法を使われた。
お腹には、殿下との子供を宿しているというのに、政略結婚をするため、バレンシア・セレナーデ公爵令嬢が邪魔になったという理由だけで、あっけなく捨てられてしまったのだ。
レオンハルトは当初、バレンシアを置き去りにする意図はなく、すぐに戻ってくるつもりでいた。
でも、王都に戻ったレオンハルトは、そのまま結婚式を挙げさせられることになる。
お相手は隣国の王女アレキサンドラ。
アレキサンドラとレオンハルトは、形式の上だけの夫婦となるが、レオンハルトには心の妻であるバレンシアがいるので、指1本アレキサンドラに触れることはない。
バレンシアガ置き去りにされて、2年が経った頃、白い結婚に不満をあらわにしたアレキサンドラは、ついに、バレンシアとその王子の存在に気付き、ご落胤である王子を手に入れようと画策するが、どれも失敗に終わってしまう。
バレンシアは、前世、京都の餅菓子屋の一人娘として、シンママをしながら子供を育てた経験があり、今世もパティシエとしての腕を生かし、パンに製菓を売り歩く行商になり、王子を育てていく。
せっかくなので、家庭でできる餅菓子レシピを載せることにしました

最愛の番に殺された獣王妃
望月 或
恋愛
目の前には、最愛の人の憎しみと怒りに満ちた黄金色の瞳。
彼のすぐ後ろには、私の姿をした聖女が怯えた表情で口元に両手を当てこちらを見ている。
手で隠しているけれど、その唇が堪え切れず嘲笑っている事を私は知っている。
聖女の姿となった私の左胸を貫いた彼の愛剣が、ゆっくりと引き抜かれる。
哀しみと失意と諦めの中、私の身体は床に崩れ落ちて――
突然彼から放たれた、狂気と絶望が入り混じった慟哭を聞きながら、私の思考は止まり、意識は閉ざされ永遠の眠りについた――はずだったのだけれど……?
「憐れなアンタに“選択”を与える。このままあの世に逝くか、別の“誰か”になって新たな人生を歩むか」
謎の人物の言葉に、私が選択したのは――

さようならの定型文~身勝手なあなたへ
宵森みなと
恋愛
「好きな女がいる。君とは“白い結婚”を——」
――それは、夢にまで見た結婚式の初夜。
額に誓いのキスを受けた“その夜”、彼はそう言った。
涙すら出なかった。
なぜなら私は、その直前に“前世の記憶”を思い出したから。
……よりによって、元・男の人生を。
夫には白い結婚宣言、恋も砕け、初夜で絶望と救済で、目覚めたのは皮肉にも、“現実”と“前世”の自分だった。
「さようなら」
だって、もう誰かに振り回されるなんて嫌。
慰謝料もらって悠々自適なシングルライフ。
別居、自立して、左団扇の人生送ってみせますわ。
だけど元・夫も、従兄も、世間も――私を放ってはくれないみたい?
「……何それ、私の人生、まだ波乱あるの?」
はい、あります。盛りだくさんで。
元・男、今・女。
“白い結婚からの離縁”から始まる、人生劇場ここに開幕。
-----『白い結婚の行方』シリーズ -----
『白い結婚の行方』の物語が始まる、前のお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















