12 / 15
第11話 王宮のお茶会
しおりを挟む
その日の朝、私の部屋にヴィヴィアン王女殿下からの贈り物が届いた。
大きな箱を開けると、そこに入っていたのは息を呑むほど美しいドレスだった。最高級のシルクで作られた混じりけのない純白のドレス。装飾は控えめだが銀糸の刺繍が施されており、光の加減で優美な波紋のように輝く。
添えられたカードには、流麗な筆記体でこう書かれていた。『キャンバスは白い方が、穢れがよく目立つでしょう?』
「……ふふっ」
私は思わず笑みを漏らした。さすがはヴィヴィアン様。このドレスは着飾るためのものではない。罠そのものだ。
今日の午後、王宮の庭園でヴィヴィアン様主催のお茶会が開かれる。本来なら侯爵夫人である私だけが招待される場だが、今回は特例として夫のオスカーと、その友人であるマリアも招かれていた。
「奥様、お召し替えを」
メイドたちが手際よく私にドレスを着せていく。鏡に映った私は、まるで戦場に赴く聖女のように凛としてどこか冷徹に見えた。
王宮へ向かう馬車の中は、異様な空気に包まれていた。私は窓の外を眺め、向かいの席にはオスカーとマリアが並んで座っている。
マリアは今日のために新調した(もちろん、我が家の予算で)ピンク色のドレスを着ていた。フリルとリボンが過剰にあしらわれ、まるでデコレーションケーキのようだ。可愛らしいと言えなくもないが、王宮の茶会にはあまりに品がない。
「ねえオスカー、私、緊張しちゃう。王女様って怖い方かしら?」
マリアがオスカーの腕にしがみつき、上目遣いで尋ねる。
「大丈夫だよ、マリア。姉上は口は悪いが、本来は聡明な方だ。君の純粋さを知れば、きっと気に入ってくれる」
オスカーは自信満々に頷いた。彼の脳内では、ヴィヴィアン様の招待状がマリアとの仲を認めるための和解の印として処理されているらしい。
昨日の資産凍結の話はどうしたのだろうか。監査が入ったなら仕方ないと楽観視しているのか、それともマリアの前で格好をつけているだけなのか。
「エリザ、お前もだぞ」
オスカーが私に矛先を向ける。
「姉上の前で、マリアをいじめたりするなよ。せっかくの機会なんだ。仲良くしてくれ」
「……ええ、承知いたしました。マナーを守ってくださる限りは」
私は扇子で口元を隠し短く答えた。 仲良く? ええ、精一杯歓迎させていただきますわ。ヴィヴィアン様と共に。
王宮の庭園は、百花繚乱の美しさを誇っていた。手入れの行き届いた芝生、咲き誇る薔薇のアーチ。
そして、そこに集うのは国の中枢を担う高位貴族の夫人たちだ。会場に足を踏み入れた瞬間、洗練された会話のさざめきが、一瞬だけ止まった。
視線の先は私ではない。私の隣で、キョロキョロと物珍しそうに辺りを見回すマリアに向けられていた。
場違いなピンクのドレス。貴族としての所作(立ち居振る舞い)の欠如。彼女が異物であることは誰の目にも明らかだった。
「あら、エリザ様。ごきげんよう」
「ごきげんよう、侯爵夫人」
知人の夫人たちが、私に挨拶をしてくる。彼女たちはマリアを視界に入れないよう巧みに無視を決め込んでいた。それが貴族社会における拒絶のサインだ。しかし、マリアにはそれが読めない。
「あ、私も! 初めましてぇ、マリアですぅ!」
マリアが会話に割り込む。夫人たちの眉がピクリと動いた。カーテシーもしない。敬称もつけない。まるで近所の井戸端会議に参加するかのような馴れ馴れしさ。
「……オスカー様の幼馴染の方、でしたか」
伯爵夫人が、凍りつくような笑顔で応対する。
「ええ! オスカーとは昔っから一緒でぇ、もう家族みたいなものなんですぅ。ね、オスカー?」
「あ、ああ。まあな」
オスカーが気まずそうに頷く。さすがの彼も、周囲の冷ややかな視線に気づき始めたようだ。しかし、マリアの暴走は止まらない。
彼女は自分が主役になれないことが不満なのだ。美しく洗練され、周囲から敬意を払われている私への嫉妬が、彼女の顔を歪ませていく。
その時、庭園の奥からファンファーレが鳴り響いた。ヴィヴィアン王女殿下の登場だ。
深紅のドレスを纏ったヴィヴィアン様は、女王のような貫禄で現れた。
その視線がゆっくりと会場を巡り、私とその横にいる二人組の上で止まる。ヴィヴィアン様はふわりと微笑んだ。獲物を見つけた猛禽類の笑みだ。
「皆様、ようこそ。今日は堅苦しい礼儀は抜きにして、楽しみましょう」
その言葉をマリアは文字通りに受け取った。「堅苦しい礼儀は抜き」それは「無礼講」という意味ではない。「洗練されたウィットを楽しもう」という意味なのだが。
お茶会が始まり、私はヴィヴィアン様の近くの席に招かれた。オスカーとマリアは末席の方だ。それが不満なのか、マリアは頻りにこちらのテーブルをチラチラと見ている。
「エリザ、そのドレス。とてもよく似合っているわ」
ヴィヴィアン様が紅茶を一口飲み、私にウィンクを送った。
「ありがとうございます、殿下。殿下のセンスには脱帽いたします」
「白はいいわね。何色にも染まる準備ができている色だもの」
その時だった。マリアが立ち上がり、ウェイターから赤ワインの入ったグラスを奪い取った。そして、千鳥足のような足取りで、私のいるメインテーブルへと近づいてきたのだ。
大きな箱を開けると、そこに入っていたのは息を呑むほど美しいドレスだった。最高級のシルクで作られた混じりけのない純白のドレス。装飾は控えめだが銀糸の刺繍が施されており、光の加減で優美な波紋のように輝く。
添えられたカードには、流麗な筆記体でこう書かれていた。『キャンバスは白い方が、穢れがよく目立つでしょう?』
「……ふふっ」
私は思わず笑みを漏らした。さすがはヴィヴィアン様。このドレスは着飾るためのものではない。罠そのものだ。
今日の午後、王宮の庭園でヴィヴィアン様主催のお茶会が開かれる。本来なら侯爵夫人である私だけが招待される場だが、今回は特例として夫のオスカーと、その友人であるマリアも招かれていた。
「奥様、お召し替えを」
メイドたちが手際よく私にドレスを着せていく。鏡に映った私は、まるで戦場に赴く聖女のように凛としてどこか冷徹に見えた。
王宮へ向かう馬車の中は、異様な空気に包まれていた。私は窓の外を眺め、向かいの席にはオスカーとマリアが並んで座っている。
マリアは今日のために新調した(もちろん、我が家の予算で)ピンク色のドレスを着ていた。フリルとリボンが過剰にあしらわれ、まるでデコレーションケーキのようだ。可愛らしいと言えなくもないが、王宮の茶会にはあまりに品がない。
「ねえオスカー、私、緊張しちゃう。王女様って怖い方かしら?」
マリアがオスカーの腕にしがみつき、上目遣いで尋ねる。
「大丈夫だよ、マリア。姉上は口は悪いが、本来は聡明な方だ。君の純粋さを知れば、きっと気に入ってくれる」
オスカーは自信満々に頷いた。彼の脳内では、ヴィヴィアン様の招待状がマリアとの仲を認めるための和解の印として処理されているらしい。
昨日の資産凍結の話はどうしたのだろうか。監査が入ったなら仕方ないと楽観視しているのか、それともマリアの前で格好をつけているだけなのか。
「エリザ、お前もだぞ」
オスカーが私に矛先を向ける。
「姉上の前で、マリアをいじめたりするなよ。せっかくの機会なんだ。仲良くしてくれ」
「……ええ、承知いたしました。マナーを守ってくださる限りは」
私は扇子で口元を隠し短く答えた。 仲良く? ええ、精一杯歓迎させていただきますわ。ヴィヴィアン様と共に。
王宮の庭園は、百花繚乱の美しさを誇っていた。手入れの行き届いた芝生、咲き誇る薔薇のアーチ。
そして、そこに集うのは国の中枢を担う高位貴族の夫人たちだ。会場に足を踏み入れた瞬間、洗練された会話のさざめきが、一瞬だけ止まった。
視線の先は私ではない。私の隣で、キョロキョロと物珍しそうに辺りを見回すマリアに向けられていた。
場違いなピンクのドレス。貴族としての所作(立ち居振る舞い)の欠如。彼女が異物であることは誰の目にも明らかだった。
「あら、エリザ様。ごきげんよう」
「ごきげんよう、侯爵夫人」
知人の夫人たちが、私に挨拶をしてくる。彼女たちはマリアを視界に入れないよう巧みに無視を決め込んでいた。それが貴族社会における拒絶のサインだ。しかし、マリアにはそれが読めない。
「あ、私も! 初めましてぇ、マリアですぅ!」
マリアが会話に割り込む。夫人たちの眉がピクリと動いた。カーテシーもしない。敬称もつけない。まるで近所の井戸端会議に参加するかのような馴れ馴れしさ。
「……オスカー様の幼馴染の方、でしたか」
伯爵夫人が、凍りつくような笑顔で応対する。
「ええ! オスカーとは昔っから一緒でぇ、もう家族みたいなものなんですぅ。ね、オスカー?」
「あ、ああ。まあな」
オスカーが気まずそうに頷く。さすがの彼も、周囲の冷ややかな視線に気づき始めたようだ。しかし、マリアの暴走は止まらない。
彼女は自分が主役になれないことが不満なのだ。美しく洗練され、周囲から敬意を払われている私への嫉妬が、彼女の顔を歪ませていく。
その時、庭園の奥からファンファーレが鳴り響いた。ヴィヴィアン王女殿下の登場だ。
深紅のドレスを纏ったヴィヴィアン様は、女王のような貫禄で現れた。
その視線がゆっくりと会場を巡り、私とその横にいる二人組の上で止まる。ヴィヴィアン様はふわりと微笑んだ。獲物を見つけた猛禽類の笑みだ。
「皆様、ようこそ。今日は堅苦しい礼儀は抜きにして、楽しみましょう」
その言葉をマリアは文字通りに受け取った。「堅苦しい礼儀は抜き」それは「無礼講」という意味ではない。「洗練されたウィットを楽しもう」という意味なのだが。
お茶会が始まり、私はヴィヴィアン様の近くの席に招かれた。オスカーとマリアは末席の方だ。それが不満なのか、マリアは頻りにこちらのテーブルをチラチラと見ている。
「エリザ、そのドレス。とてもよく似合っているわ」
ヴィヴィアン様が紅茶を一口飲み、私にウィンクを送った。
「ありがとうございます、殿下。殿下のセンスには脱帽いたします」
「白はいいわね。何色にも染まる準備ができている色だもの」
その時だった。マリアが立ち上がり、ウェイターから赤ワインの入ったグラスを奪い取った。そして、千鳥足のような足取りで、私のいるメインテーブルへと近づいてきたのだ。
285
あなたにおすすめの小説

亡き姉を演じ初恋の人の妻となった私は、その日、“私”を捨てた
榛乃
恋愛
伯爵家の令嬢・リシェルは、侯爵家のアルベルトに密かに想いを寄せていた。
けれど彼が選んだのはリシェルではなく、双子の姉・オリヴィアだった。
二人は夫婦となり、誰もが羨むような幸福な日々を過ごしていたが――それは五年ももたず、儚く終わりを迎えてしまう。
オリヴィアが心臓の病でこの世を去ったのだ。
その日を堺にアルベルトの心は壊れ、最愛の妻の幻を追い続けるようになる。
そんな彼を守るために。
そして侯爵家の未来と、両親の願いのために。
リシェルは自分を捨て、“姉のふり”をして生きる道を選ぶ。
けれど、どれほど傍にいても、どれほど尽くしても、彼の瞳に映るのはいつだって“オリヴィア”だった。
その現実が、彼女の心を静かに蝕んでゆく。
遂に限界を越えたリシェルは、自ら命を絶つことに決める。
短剣を手に、過去を振り返るリシェル。
そしていよいよ切っ先を突き刺そうとした、その瞬間――。

全てから捨てられた伯爵令嬢は。
毒島醜女
恋愛
姉ルヴィが「あんたの婚約者、寝取ったから!」と職場に押し込んできたユークレース・エーデルシュタイン。
更に職場のお局には強引にクビを言い渡されてしまう。
結婚する気がなかったとは言え、これからどうすればいいのかと途方に暮れる彼女の前に帝国人の迷子の子供が現れる。
彼を助けたことで、薄幸なユークレースの人生は大きく変わり始める。
通常の王国語は「」
帝国語=外国語は『』

巻き戻される運命 ~私は王太子妃になり誰かに突き落とされ死んだ、そうしたら何故か三歳の子どもに戻っていた~
アキナヌカ
恋愛
私(わたくし)レティ・アマンド・アルメニアはこの国の第一王子と結婚した、でも彼は私のことを愛さずに仕事だけを押しつけた。そうして私は形だけの王太子妃になり、やがて側室の誰かにバルコニーから突き落とされて死んだ。でも、気がついたら私は三歳の子どもに戻っていた。
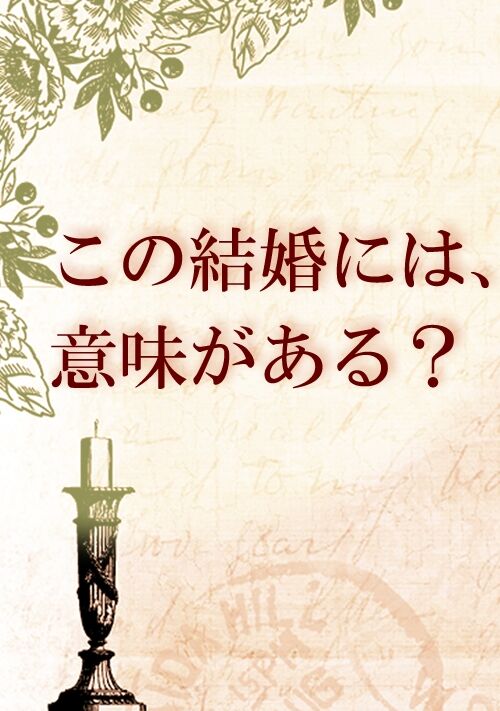
この結婚には、意味がある?
みこと。
恋愛
公爵家に降嫁した王女アリアは、初夜に夫から「オープンマリッジ」を提案される。
婚姻関係を維持しながら、他の異性との遊戯を認めろ、という要求を、アリアはどう解釈するのか?
王宮で冷遇されていた王女アリアの、密かな目的とは。
この結婚は、アリアにとってどんな意味がある?
※他のサイトにも掲載しています。
※他タイトル『沈黙の聖女は、ある日すべてを暴露する』も収録。←まったく別のお話です


その眼差しは凍てつく刃*冷たい婚約者にウンザリしてます*
音爽(ネソウ)
恋愛
義妹に優しく、婚約者の令嬢には極寒対応。
塩対応より下があるなんて……。
この婚約は間違っている?
*2021年7月完結

他の人を好きになったあなたを、私は愛することができません
天宮有
恋愛
公爵令嬢の私シーラの婚約者レヴォク第二王子が、伯爵令嬢ソフィーを好きになった。
第三王子ゼロアから聞いていたけど、私はレヴォクを信じてしまった。
その結果レヴォクに協力した国王に冤罪をかけられて、私は婚約破棄と国外追放を言い渡されてしまう。
追放された私は他国に行き、数日後ゼロアと再会する。
ゼロアは私を追放した国王を嫌い、国を捨てたようだ。
私はゼロアと新しい生活を送って――元婚約者レヴォクは、後悔することとなる。

貴方が選んだのは全てを捧げて貴方を愛した私ではありませんでした
ましゅぺちーの
恋愛
王国の名門公爵家の出身であるエレンは幼い頃から婚約者候補である第一王子殿下に全てを捧げて生きてきた。
彼を数々の悪意から守り、彼の敵を排除した。それも全ては愛する彼のため。
しかし、王太子となった彼が最終的には選んだのはエレンではない平民の女だった。
悲しみに暮れたエレンだったが、家族や幼馴染の公爵令息に支えられて元気を取り戻していく。
その一方エレンを捨てた王太子は着々と破滅への道を進んでいた・・・
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















