あなたにおすすめの小説

おっさん料理人と押しかけ弟子達のまったり田舎ライフ
双葉 鳴
ファンタジー
真面目だけが取り柄の料理人、本宝治洋一。
彼は能力の低さから不当な労働を強いられていた。
そんな彼を救い出してくれたのが友人の藤本要。
洋一は要と一緒に現代ダンジョンで気ままなセカンドライフを始めたのだが……気がつけば森の中。
さっきまで一緒に居た要の行方も知れず、洋一は途方に暮れた……のも束の間。腹が減っては戦はできぬ。
持ち前のサバイバル能力で見敵必殺!
赤い毛皮の大きなクマを非常食に、洋一はいつもの要領で食事の準備を始めたのだった。
そこで見慣れぬ騎士姿の少女を助けたことから洋一は面倒ごとに巻き込まれていく事になる。
人々との出会い。
そして貴族や平民との格差社会。
ファンタジーな世界観に飛び交う魔法。
牙を剥く魔獣を美味しく料理して食べる男とその弟子達の田舎での生活。
うるさい権力者達とは争わず、田舎でのんびりとした時間を過ごしたい!
そんな人のための物語。
5/6_18:00完結!

精霊に愛される(呪いにもにた愛)少女~全属性の加護を貰う~
如月花恋
ファンタジー
今この世界にはたくさんの精霊がいる
その精霊達から生まれた瞬間に加護を貰う
稀に2つ以上の属性の2体の精霊から加護を貰うことがある
まぁ大体は親の属性を受け継ぐのだが…
だが…全属性の加護を貰うなど不可能とされてきた…
そんな時に生まれたシャルロッテ
全属性の加護を持つ少女
いったいこれからどうなるのか…

外れギフト魔石抜き取りの奇跡!〜スライムからの黄金ルート!婚約破棄されましたのでもうお貴族様は嫌です〜
KeyBow
ファンタジー
この世界では、数千年前に突如現れた魔物が人々の生活に脅威をもたらしている。中世を舞台にした典型的なファンタジー世界で、冒険者たちは剣と魔法を駆使してこれらの魔物と戦い、生計を立てている。
人々は15歳の誕生日に神々から加護を授かり、特別なギフトを受け取る。しかし、主人公ロイは【魔石操作】という、死んだ魔物から魔石を抜き取るという外れギフトを授かる。このギフトのために、彼は婚約者に見放され、父親に家を追放される。
運命に翻弄されながらも、ロイは冒険者ギルドの解体所部門で働き始める。そこで彼は、生きている魔物から魔石を抜き取る能力を発見し、これまでの外れギフトが実は隠された力を秘めていたことを知る。
ロイはこの新たな力を使い、自分の運命を切り開くことができるのか?外れギフトを当りギフトに変え、チートスキルを手に入れた彼の物語が始まる。
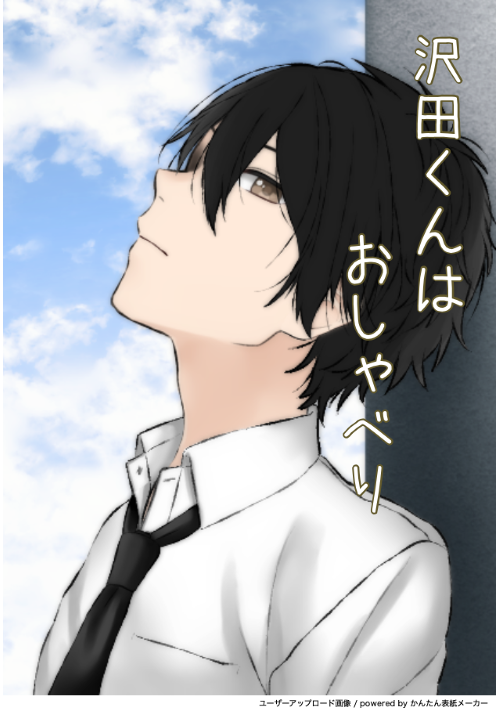
沢田くんはおしゃべり
ゆづ
青春
第13回ドリーム大賞奨励賞受賞✨ありがとうございました!!
【あらすじ】
空気を読む力が高まりすぎて、他人の心の声が聞こえるようになってしまった普通の女の子、佐藤景子。
友達から地味だのモブだの心の中で言いたい放題言われているのに言い返せない悔しさの日々の中、景子の唯一の癒しは隣の席の男子、沢田空の心の声だった。
【佐藤さん、マジ天使】(心の声)
無口でほとんどしゃべらない沢田くんの心の声が、まさかの愛と笑いを巻き起こす!
めちゃコミ女性向け漫画原作賞の優秀作品にノミネートされました✨
エブリスタでコメディートレンドランキング年間1位(ただし完結作品に限るッ!)
エブリスタ→https://estar.jp/novels/25774848

宿敵の家の当主を妻に貰いました~妻は可憐で儚くて優しくて賢くて可愛くて最高です~
紗沙
恋愛
剣の名家にして、国の南側を支配する大貴族フォルス家。
そこの三男として生まれたノヴァは一族のみが扱える秘技が全く使えない、出来損ないというレッテルを貼られ、辛い子供時代を過ごした。
大人になったノヴァは小さな領地を与えられるものの、仕事も家族からの期待も、周りからの期待も0に等しい。
しかし、そんなノヴァに舞い込んだ一件の縁談話。相手は国の北側を支配する大貴族。
フォルス家とは長年の確執があり、今は栄華を極めているアークゲート家だった。
しかも縁談の相手は、まさかのアークゲート家当主・シアで・・・。
「あのときからずっと……お慕いしています」
かくして、何も持たないフォルス家の三男坊は性格良し、容姿良し、というか全てが良しの妻を迎え入れることになる。
ノヴァの運命を変える、全てを与えてこようとする妻を。
「人はアークゲート家の当主を恐ろしいとか、血も涙もないとか、冷酷とか散々に言うけど、
シアは可愛いし、優しいし、賢いし、完璧だよ」
あまり深く考えないノヴァと、彼にしか自分の素を見せないシア、二人の結婚生活が始まる。

つまらなかった乙女ゲームに転生しちゃったので、サクッと終わらすことにしました
蒼羽咲
ファンタジー
つまらなかった乙女ゲームに転生⁈
絵に惚れ込み、一目惚れキャラのためにハードまで買ったが内容が超つまらなかった残念な乙女ゲームに転生してしまった。
絵は超好みだ。内容はご都合主義の聖女なお花畑主人公。攻略イケメンも顔は良いがちょろい対象ばかり。てこたぁ逆にめちゃくちゃ住み心地のいい場所になるのでは⁈と気づき、テンションが一気に上がる!!
聖女など面倒な事はする気はない!サクッと攻略終わらせてぐーたら生活をGETするぞ!
ご都合主義ならチョロい!と、野望を胸に動き出す!!
+++++
・重複投稿・土曜配信 (たま~に水曜…不定期更新)

エリクサーは不老不死の薬ではありません。~完成したエリクサーのせいで追放されましたが、隣国で色々助けてたら聖人に……ただの草使いですよ~
シロ鼬
ファンタジー
エリクサー……それは生命あるものすべてを癒し、治す薬――そう、それだけだ。
主人公、リッツはスキル『草』と持ち前の知識でついにエリクサーを完成させるが、なぜか王様に偽物と判断されてしまう。
追放され行く当てもなくなったリッツは、とりあえず大好きな草を集めていると怪我をした神獣の子に出会う。
さらには倒れた少女と出会い、疫病が発生したという隣国へ向かった。
疫病? これ飲めば治りますよ?
これは自前の薬とエリクサーを使い、聖人と呼ばれてしまった男の物語。

転生の水神様ーー使える魔法は水属性のみだが最強ですーー
芍薬甘草湯
ファンタジー
水道局職員が異世界に転生、水神様の加護を受けて活躍する異世界転生テンプレ的なストーリーです。
42歳のパッとしない水道局職員が死亡したのち水神様から加護を約束される。
下級貴族の三男ネロ=ヴァッサーに転生し12歳の祝福の儀で水神様に再会する。
約束通り祝福をもらったが使えるのは水属性魔法のみ。
それでもネロは水魔法を工夫しながら活躍していく。
一話当たりは短いです。
通勤通学の合間などにどうぞ。
あまり深く考えずに、気楽に読んでいただければ幸いです。
完結しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















