4 / 6
4
しおりを挟む
さっそくわたくしは、王子の目を盗んで姫に接触してみることにしました。高慢ちきな娘ではありましたが、王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
その幼さゆえに、高飛車であったのです。わたくしが耳許でそっと優しく歯の浮くような言葉をかけてやると、頬を赤らめて瞳を潤ませるのでした。思っていたよりも簡単で、わたくしは拍子抜けしてしまいました。
すこし手こずるくらいが楽しめると思っていたのに、こうも容易く転がるようではこの先、国を治めるであろう王子の支えになるのか不安を覚えました。王子のためにも国のためにも、この女子を王子の傍から離すべきなのです。
いま思えば、王子に嫌われ妬まれようが、わたくしがカエルと娘のあいだに割って入り、金の鞠でもなんでも取りにゆけばよかったのです。姫の城へ参ったとき、カエルに任せないでわたくしが出向いて話をつけてくればよかったのです。
後悔したところで過去が変わるわけではありませんが、わたくしがいまだ胸を締める鉄の帯を見るたびに馬鹿らしくなってくるのでした。
ある晩、わたくしは姫を自らの寝所へ招きました。姫は、王子の寝所へ入ってゆくときのように、薄く白く透けるドレスを着てきました。姫を隣へ寝かせ、そのきれいに結われた髪をすこしほぐしてやると、まだ肌には触れていないのに、ちいさく身じろぎをしました。
これには、幼いころの王子を寝かしつけていたことを思い出し、すこし笑いがこぼれそうになってしまいました。しかし、わたくしのこのちいさな失態にすら、姫はその気になるのでした。わたくしは姫の美しい髪をいじりながら、ずっと疑問に思っていたことを訊いてみることにしました。
「我が王子の花嫁さま、わたくしにひとつお教えくださいますか」
「ええ、私を可愛がってくださるのなら、あなたのどんなことにも答えてあげるわ」
カエルの申し出に答えたときのように、姫は言うのでした。
「たった一晩にして、我が王子を救ってくださった方法を知りたいのです。美しい姿が醜いカエルのようになってしまい、わたくしはどうすることもできなかったのです。ほうら、このように、哀しみにそして自らの不甲斐なさに心が張り裂けてしまわないよう、胸に鉄の帯を締めているのです」
「まあ‥‥」
姫はわずかに驚きましたが、鉄の帯についてはなにも言いませんでした。
「わたくしにはなにもできなかったのに、貴女は王子を呪いから救ってくださいました。王子になにをしてくださったのですか」
わたくしがくだらない演技で声を震わせると、姫はさも心を打たれたように瞳を伏せるのでした。
「いま思えば、わたしは愚か者だったわ。宝物である金の鞠を拾ってきてくださったカエル‥‥王子さまであったけれど、恩人とも言えるお方に愚かな行ないをしてしまったのだから。わたしは、あの方と約束をしたの。
わたしの傍に置き、同じ食卓で一緒にご飯を食べ、同じ盃で飲み、柔らかいベッドで一緒に眠るというのが、あの方のお願いだったわ。鞠を無事に拾ってきてくれたのだから、わたしはこれらを守るべきだったのですわ。
でも、わたしにはどうも、あの緑色にいやらしく光るカエルを愛でることは到底できないと思ったのよ。だって、あんな暗くどこを見ているのか判らない黄色い目で見つめられたら、寒くもないのに背筋が凍るわ。あたたかさのない水かきで触れられれば、具合が悪くなくても脂汗をかくわ」
姫の考えはごもっともでした。わたくしも、王子が気味の悪いカエルに変えられてしまったばかりのころは、怖気だち眩暈がしたものです。しかし、中身は愛する王子には変わりないのでわたくしも変わることなくご奉仕しました。姫がカエルを受け入れられないのも納得できるのでした。
「そしてわたしは、最低なことをしたわ。――それが結果的に、カエルの呪いを解くことに繋がったのですけれど‥‥」
いよいよ核心が聞けるのです。わたくしの心臓は早鐘のようでしたが、きつく絞められた鉄の帯がそれを静かに押さえつけるのでした。真実、それさえ聞いてしまえば、この娘は用無しになるのです。
王子を呪いから救ってくださった恩人ではありますが、それ以上に誑かした女狐なのです。この娘の傍に居たら、王子はわたくしを必要としてくれなくなってしまうのです。わたくしは、王子の従者として王子を守らなければなりません。
その幼さゆえに、高飛車であったのです。わたくしが耳許でそっと優しく歯の浮くような言葉をかけてやると、頬を赤らめて瞳を潤ませるのでした。思っていたよりも簡単で、わたくしは拍子抜けしてしまいました。
すこし手こずるくらいが楽しめると思っていたのに、こうも容易く転がるようではこの先、国を治めるであろう王子の支えになるのか不安を覚えました。王子のためにも国のためにも、この女子を王子の傍から離すべきなのです。
いま思えば、王子に嫌われ妬まれようが、わたくしがカエルと娘のあいだに割って入り、金の鞠でもなんでも取りにゆけばよかったのです。姫の城へ参ったとき、カエルに任せないでわたくしが出向いて話をつけてくればよかったのです。
後悔したところで過去が変わるわけではありませんが、わたくしがいまだ胸を締める鉄の帯を見るたびに馬鹿らしくなってくるのでした。
ある晩、わたくしは姫を自らの寝所へ招きました。姫は、王子の寝所へ入ってゆくときのように、薄く白く透けるドレスを着てきました。姫を隣へ寝かせ、そのきれいに結われた髪をすこしほぐしてやると、まだ肌には触れていないのに、ちいさく身じろぎをしました。
これには、幼いころの王子を寝かしつけていたことを思い出し、すこし笑いがこぼれそうになってしまいました。しかし、わたくしのこのちいさな失態にすら、姫はその気になるのでした。わたくしは姫の美しい髪をいじりながら、ずっと疑問に思っていたことを訊いてみることにしました。
「我が王子の花嫁さま、わたくしにひとつお教えくださいますか」
「ええ、私を可愛がってくださるのなら、あなたのどんなことにも答えてあげるわ」
カエルの申し出に答えたときのように、姫は言うのでした。
「たった一晩にして、我が王子を救ってくださった方法を知りたいのです。美しい姿が醜いカエルのようになってしまい、わたくしはどうすることもできなかったのです。ほうら、このように、哀しみにそして自らの不甲斐なさに心が張り裂けてしまわないよう、胸に鉄の帯を締めているのです」
「まあ‥‥」
姫はわずかに驚きましたが、鉄の帯についてはなにも言いませんでした。
「わたくしにはなにもできなかったのに、貴女は王子を呪いから救ってくださいました。王子になにをしてくださったのですか」
わたくしがくだらない演技で声を震わせると、姫はさも心を打たれたように瞳を伏せるのでした。
「いま思えば、わたしは愚か者だったわ。宝物である金の鞠を拾ってきてくださったカエル‥‥王子さまであったけれど、恩人とも言えるお方に愚かな行ないをしてしまったのだから。わたしは、あの方と約束をしたの。
わたしの傍に置き、同じ食卓で一緒にご飯を食べ、同じ盃で飲み、柔らかいベッドで一緒に眠るというのが、あの方のお願いだったわ。鞠を無事に拾ってきてくれたのだから、わたしはこれらを守るべきだったのですわ。
でも、わたしにはどうも、あの緑色にいやらしく光るカエルを愛でることは到底できないと思ったのよ。だって、あんな暗くどこを見ているのか判らない黄色い目で見つめられたら、寒くもないのに背筋が凍るわ。あたたかさのない水かきで触れられれば、具合が悪くなくても脂汗をかくわ」
姫の考えはごもっともでした。わたくしも、王子が気味の悪いカエルに変えられてしまったばかりのころは、怖気だち眩暈がしたものです。しかし、中身は愛する王子には変わりないのでわたくしも変わることなくご奉仕しました。姫がカエルを受け入れられないのも納得できるのでした。
「そしてわたしは、最低なことをしたわ。――それが結果的に、カエルの呪いを解くことに繋がったのですけれど‥‥」
いよいよ核心が聞けるのです。わたくしの心臓は早鐘のようでしたが、きつく絞められた鉄の帯がそれを静かに押さえつけるのでした。真実、それさえ聞いてしまえば、この娘は用無しになるのです。
王子を呪いから救ってくださった恩人ではありますが、それ以上に誑かした女狐なのです。この娘の傍に居たら、王子はわたくしを必要としてくれなくなってしまうのです。わたくしは、王子の従者として王子を守らなければなりません。
0
あなたにおすすめの小説

緑色の友達
石河 翠
児童書・童話
むかしむかしあるところに、大きな森に囲まれた小さな村がありました。そこに住む女の子ララは、祭りの前日に不思議な男の子に出会います。ところが男の子にはある秘密があったのです……。
こちらは小説家になろうにも投稿しております。
表紙は、貴様 二太郎様に描いて頂きました。

パンティージャムジャムおじさん
KOU/Vami
児童書・童話
夜の街に、歌いながら歩く奇妙なおじさんが現れる。
口癖は「パラダイス~☆♪♡」――名乗る名は「パンティージャムジャムおじさん」。
子供たちは笑いながら彼の後についていき、歌を真似し、踊り、列は少しずつ長くなる。
そして翌朝、街は初めて気づく。昨夜の歌が、ただの遊びではなかったことに。

瑠璃の姫君と鉄黒の騎士
石河 翠
児童書・童話
可愛いフェリシアはひとりぼっち。部屋の中に閉じ込められ、放置されています。彼女の楽しみは、窓の隙間から空を眺めながら歌うことだけ。
そんなある日フェリシアは、貧しい身なりの男の子にさらわれてしまいました。彼は本来自分が受け取るべきだった幸せを、フェリシアが台無しにしたのだと責め立てます。
突然のことに困惑しつつも、男の子のためにできることはないかと悩んだあげく、彼女は一本の羽を渡すことに決めました。
大好きな友達に似た男の子に笑ってほしい、ただその一心で。けれどそれは、彼女の命を削る行為で……。
記憶を失くしたヒロインと、幸せになりたいヒーローの物語。ハッピーエンドです。
この作品は、他サイトにも投稿しております。
表紙絵は写真ACよりチョコラテさまの作品(写真ID:249286)をお借りしています。


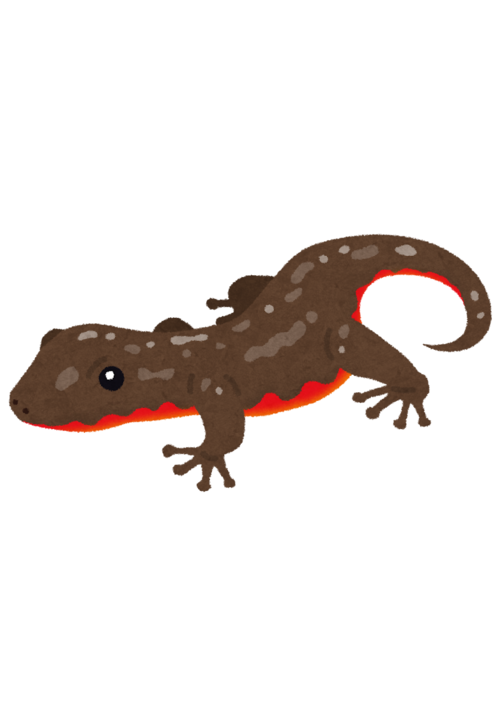

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















