あなたにおすすめの小説

緑色の友達
石河 翠
児童書・童話
むかしむかしあるところに、大きな森に囲まれた小さな村がありました。そこに住む女の子ララは、祭りの前日に不思議な男の子に出会います。ところが男の子にはある秘密があったのです……。
こちらは小説家になろうにも投稿しております。
表紙は、貴様 二太郎様に描いて頂きました。

パンティージャムジャムおじさん
KOU/Vami
児童書・童話
夜の街に、歌いながら歩く奇妙なおじさんが現れる。
口癖は「パラダイス~☆♪♡」――名乗る名は「パンティージャムジャムおじさん」。
子供たちは笑いながら彼の後についていき、歌を真似し、踊り、列は少しずつ長くなる。
そして翌朝、街は初めて気づく。昨夜の歌が、ただの遊びではなかったことに。

瑠璃の姫君と鉄黒の騎士
石河 翠
児童書・童話
可愛いフェリシアはひとりぼっち。部屋の中に閉じ込められ、放置されています。彼女の楽しみは、窓の隙間から空を眺めながら歌うことだけ。
そんなある日フェリシアは、貧しい身なりの男の子にさらわれてしまいました。彼は本来自分が受け取るべきだった幸せを、フェリシアが台無しにしたのだと責め立てます。
突然のことに困惑しつつも、男の子のためにできることはないかと悩んだあげく、彼女は一本の羽を渡すことに決めました。
大好きな友達に似た男の子に笑ってほしい、ただその一心で。けれどそれは、彼女の命を削る行為で……。
記憶を失くしたヒロインと、幸せになりたいヒーローの物語。ハッピーエンドです。
この作品は、他サイトにも投稿しております。
表紙絵は写真ACよりチョコラテさまの作品(写真ID:249286)をお借りしています。


生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

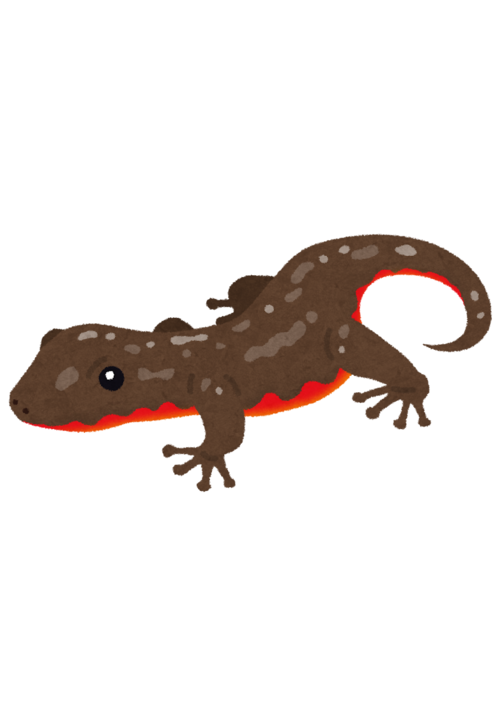

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















