23 / 35
第23話 :『その日、風が止まった』
しおりを挟む
試合開始前、風が吹いていた。
スタンドの応援団の旗がはためき、ベンチ前の整列では、千紗の髪が頬をかすめた。
「……なんか、空気が違うね」
千紗がつぶやく。
隣でスコアラーの飯塚が、こくんとうなずいた。「今日、何かが起こりそうな気がするんスよね」
準々決勝、相手は県屈指の強豪校・西陵館。
これまでの大会で3度ベスト4に進出した実績があり、桜が丘とは明確な格上だった。
――だがその日の風祭球児は、まるで別人だった。
初回。初球。
ストレート、アウトローいっぱい。
石原のミットがほとんど動かなかった。
「見た? 今の……」
スタンドの声援が一瞬だけ止まり、空気が硬直する。
二回、三回。投球は続く。
力まない。吠えない。ただ、丁寧に、鋭く。
バッターがスイングするたびに、何かが空を裂くような音がして、それをグラウンドの誰もが静かに見守っていた。
「……今日の球児、ちょっと怖いくらいですね」
石原がぽつりと言うと、ベンチの修司が応える。
「いや、あいつは“静かに怒ってる”んだよ。たぶん、自分に」
五回、まだ一人のランナーも出していない。
千紗は手帳を握ったまま、ページをめくることすら忘れていた。
「……これが“エース”か」
八回裏、桜が丘は先制に成功した。
三島のセンター前ヒット、藤木のきっちりと決めた送りバント、小野寺のタイムリーツーベース。
ベンチが小さく沸く。そのあと、またすぐに静かになる。
「今は、見てたいんだよ。球児の投球を」
そう呟いたのは、飯塚だった。
そして九回表。
マウンドには、ひとりの少年が立っていた。
たった70球目。
最後のバッターのバットが空を切り、石原のミットに収まる。
――カツン、と、乾いた音。
「試合終了、1対0。桜が丘、準決勝進出!」
どよめきではなく、静けさだった。
観客席から、何か神聖なものを見たあとのような拍手が起きる。
声援ではなく、称賛の拍手。
風が止んでいた。
まるで、空までがこの瞬間を待っていたかのように。
試合が終わって、ロッカールームに戻ってきたとき、誰もが少しずつ浮足立っていた。
控えの選手たちは口々に「ヤバくね?」「テレビ来るぞ!」なんて騒いでいたし、三島も「はー、俺、途中から息止めてたわ」なんて冗談を飛ばしていた。
でも、石原だけは、マスクを外して黙って座った。
背中を壁に預けて、使い古したキャッチャーマスクを膝の上に置く。
しばらく何も言わなかった。
顔には、笑顔もなければ、安堵の色もない。ただ、静かだった。
「9回、70球、ヒットゼロ、四球ゼロ……なんだそれ。完璧じゃん」
ぽつりとつぶやいたその声には、呆れや誇張もなかった。
どこまでも真っ直ぐに、ただ“事実”を噛みしめるような声だった。
けれどすぐに、彼は首を振った。
「でもな、あれはひとりじゃ無理だ。守備も、声も、球児の覚悟も……全部が重なった」
マウンドで受けた70球。
たしかに、全部“いい球”だった。けど、そのうち何球かは、普通なら打たれてもおかしくない。
でも、松井の横っ飛びがあった。滝川の一歩目が速かった。三島の声が、球場を支配してた。
あれは、奇跡じゃない。チームで取ったゼロだった。
石原はマスクの内側をじっと見つめる。
汗で湿ったその面に、ポケットから取り出した黒のマジックで、小さくこう記した。
“完全試合=完全なチーム”
誰に見せるわけでもない。
けれど、いつかこのマスクを誰かに譲る日が来たら、伝わればいい。
「ピッチャーだけじゃない。勝ちってのは、チーム全員でつかむものなんだ」って。
そう思ったとき、石原の口元がほんの少しだけ、笑っていた。
■
最後の一球──。
その打者が、見逃したままバットを下ろした瞬間。
球審の右手がスッと上がった瞬間。
球場の時間が、一瞬止まったように思えた。
スタンドの誰かが叫んだ。
ベンチから数人が立ち上がった。
でも、三島は守備位置で、ただ黙って立っていた。
叫ぶつもりだったのだ。
「よっしゃあ!」って、主将として、誰よりも大きな声で。
けれど──喉が詰まった。
拳を握ったまま、立ち尽くしていた。
視界の奥で、キャッチャーの石原がマウンドに駆け寄り、風祭と手を合わせたのが見えた。
何人もの部員がグラウンドに飛び出していくなか、三島だけは一歩、後ろで立っていた。
出てきたのは、絞り出すような、わずかな声。
「……すげぇな」
叫べなかったのは、きっと自分の胸がいっぱいだったからだ。
“背番号1”のあいつが、あんな投球をした。
でも、それは風祭ひとりじゃない。
石原のミット、松井と滝川の鉄壁の守備、浜中のレーザービーム。
そして、誰より大きな声で応援した藤木。
全員のプレーが積み重なって、あのゲームがあった。
三島は思った。
背番号1の背中には、俺たちが乗ってたんだ。
そして──それでも、俺は主将だとも思った。
「次だな……」
ポツリとこぼした言葉に、自分でうなずく。
まだ、準決勝がある。
それを越えれば、決勝。甲子園が見えてくる。
あいつが完全試合をやってのけた。なら、次は俺の番だ。
チームを“勝たせる”一打。俺が打つ。主将として。
グラウンドにはもう誰もいない。
でも、彼の胸には、次の試合の風がもう吹いていた。
主将として、仲間として、あの9回の時間を共有していたはずの自分が、
どこか置いていかれたような気さえした。
けれど──それは悔しさじゃなかった。
帰りのロッカールーム。
スパイクを脱ぎかけたところで、三島はふとしゃがみ込み、もう一度、靴紐を結び直した。
誰もいないベンチ裏で、独り言のように、小さくつぶやく。
「背番号1だけじゃない。……お前の背中に、全員が乗ってたんだよ」
その言葉に、返事はない。
でも三島の胸の奥には、あの一球の余韻と、確かな誇りが残っていた。
整列を終え、球児がベンチへ戻ってくる。
修司がそっと帽子を持ち上げ、目だけで合図を送った。
「ナイスピッチング」――その言葉は、ただ、帽子の動きに込められていた。
「ありがとうございました」
球児が、声に出したのはそれだけだった。
だが、それで十分だった。
その夜。
地元のローカルニュースが、桜が丘高校・風祭球児の“完全試合”を報じた。
SNSでも話題になり、野球ファンの間で「地方予選の怪物」として名前が広まる。
だが、本人はそれを知らないまま、自室でユニフォームをそっと畳んでいた。
窓の外では、あの時止まっていた風が、また少し吹き始めていた。
■
試合が終わって、ベンチがざわついて、スタンドの声援がいつまでも止まなかったそのあとも、飯塚直樹はずっと座ったままスコアブックを眺めていた。
風祭球児、完全試合達成。
ヒットゼロ、四球ゼロ、失点ゼロ、エラーもゼロ。
スコアシートの九つの回に、ゼロがずらりと並ぶ。
けれどそのページには、数字以上の“何か”が確かに詰まっていた。
飯塚は静かにペンを置いた。
「全ページにゼロが並ぶって、こんなに……しんってするんだな」
いつもなら、三回の失点に赤丸をつけたり、七回の盗塁にアスタリスクを打ったりしていた。
けれど今日だけは、ただ、何も書けなかった。
スコアブックの紙をめくる指が、ほんの少し震えている。
球児のあの球速ではなく、テンポの変化に気づいた五回裏。
石原のミットに吸い込まれる球の音が、“パン”から“すっ”に変わった七回表。
三島の守備位置が二歩下がったのを見逃さなかった八回裏。
全部、数字じゃ表せない。
けれど、数字の裏にあった心の動きを、飯塚だけは確かに見ていた。
スコアブックの欄外に、迷いながらもゆっくりとペンを走らせる。
「風が止まるって、こういうことか。俺、この1ページ、たぶん一生忘れない」
そのあと、ゆっくりとスコアブックを閉じた。
表紙の革が少し擦り切れているのが、なんだか誇らしかった。
飯塚は最後に、背表紙の下に小さくこう書き加える。
“風祭球児 完全試合達成”
その文字は、まっすぐに書いたつもりだった。
けれどよく見れば、ほんの少しだけ揺れていた。
それはきっと、書いている指の震えなんかじゃない。
あのマウンドに吹いた“風”の余韻だった。
■
試合が終わって、しばらくの間、私は何も書けなかった。
ペンを持っていた手は震えていて、ページをめくることすら怖かった。
スコアボードには、ずっと“0”が並んでいた。
まるで、それが当然だったみたいに、当たり前のように。
でも私にはわかる。
そのゼロが、どれだけ遠い場所にあったか。
そのゼロをつかむまでに、風祭くんがどれだけの“ひとり”と向き合ってきたか。
静かだった。
九回裏のマウンド。
球場の応援も、ベンチのざわめきも、誰かの声も──
全部が、いったん止まったように感じた。
“九回裏、風祭くんの背中から風の音が消えてた”
たぶん、それは緊張とかじゃなかったと思う。
ただただ、風祭くんという人のすべてが、あの一球に向かっていた。
息をする音も、踏み込む音も、ピッチャーマウンドでの動きすらも、空気を静かにしてしまうほどの集中だった。
“ミットに吸い込まれる最後の一球、音じゃなくて、空気ごと止まった”
石原くんのミットが打者の目の前でカチンと鳴って、審判の声が響いた。
“ストライクスリー”──見逃し三振。
風祭くんは、何も言わなかった。
ただ、帽子に手をやって、少しだけ空を見た。
“整列のあと、帽子を取る手がちょっと震えてた気がする”
私は知ってる。
風祭くんは、ずっと言わなかっただけ。
「勝ちたい」とか、「認められたい」とか、
そんな感情を飲み込んできたんだと思う。
あの日、転校してきてから、ずっと誰にも見せなかった涙。
それが、今日、こっそりこぼれそうになってたんじゃないかなって。
だから、最後のページにこう書いた。
「今日の風祭くん:誰にも言わなかったけど、たぶん“泣きたかった”んじゃないかな」
手帳を閉じたあと、私はこっそり笑った。
その涙が出ない強がりも、風祭くんらしいから──って。
■
夜の帰り道は、セミの鳴き声もすっかり途切れ、蝉しぐれが土に染み込むような静けさがあった。
照明の落ちた商店街を抜け、住宅街にさしかかる頃、修司は手にしていた帽子をふと見つめた。
試合が終わってからずっと、ポケットにしまおうとしてやめたそれは、何度も無意識に手のひらで握っていたせいか、つばの先が少しだけ曲がっていた。
「……クセだな」
小さく呟きながら、修司は立ち止まり、帽子のつばを親指でなぞった。
完全試合。
その言葉の重みは、ただの“すごい”では片付けられないものだった。
修司は監督として、何十年ぶりに心の奥に火が灯るのを感じていた。
けれど、それ以上に、親としての胸の奥が、ぎゅうっと締めつけられていた。
「もう……俺の背中なんて、見ちゃいねぇ」
ベンチからのサインも、采配も。
あのマウンドで投げる風祭球児は、自分の意志で球を選び、自分のテンポで試合を創っていた。
それは、かつて修司があの背番号を着て夢破れたときに、見たかった景色のはずだった。
なのに、寂しくなかった。
むしろ、誇らしかった。
もう、お前に教えることなんて、何もねぇんだな
そう思った瞬間、また帽子を握っていた。
まるでそれが、手からすり抜けてしまいそうで、逃がしたくないように。
けれど──
「見なくていい。でも、俺はお前を見てるぞ。ずっとな、球児」
誰に聞かせるでもなく、ぽつりと呟いた言葉は、夜空へ吸い込まれていった。
手の中の帽子のつばが、少し曲がっていることに気づき、修司は小さく笑った。
不器用な愛情が、きっとそこに沁み込んでいる。
歩き出すと、今度は帽子を被ることなく、胸に当てるように持ち直した。
まるで、次の試合までの道のりを、自分にも言い聞かせるかのように。
静かな夜道を、背中を丸めず、風の中を進んでいく。
父として。監督として。
そして何より、「風祭球児の一番の観客」として。
スタンドの応援団の旗がはためき、ベンチ前の整列では、千紗の髪が頬をかすめた。
「……なんか、空気が違うね」
千紗がつぶやく。
隣でスコアラーの飯塚が、こくんとうなずいた。「今日、何かが起こりそうな気がするんスよね」
準々決勝、相手は県屈指の強豪校・西陵館。
これまでの大会で3度ベスト4に進出した実績があり、桜が丘とは明確な格上だった。
――だがその日の風祭球児は、まるで別人だった。
初回。初球。
ストレート、アウトローいっぱい。
石原のミットがほとんど動かなかった。
「見た? 今の……」
スタンドの声援が一瞬だけ止まり、空気が硬直する。
二回、三回。投球は続く。
力まない。吠えない。ただ、丁寧に、鋭く。
バッターがスイングするたびに、何かが空を裂くような音がして、それをグラウンドの誰もが静かに見守っていた。
「……今日の球児、ちょっと怖いくらいですね」
石原がぽつりと言うと、ベンチの修司が応える。
「いや、あいつは“静かに怒ってる”んだよ。たぶん、自分に」
五回、まだ一人のランナーも出していない。
千紗は手帳を握ったまま、ページをめくることすら忘れていた。
「……これが“エース”か」
八回裏、桜が丘は先制に成功した。
三島のセンター前ヒット、藤木のきっちりと決めた送りバント、小野寺のタイムリーツーベース。
ベンチが小さく沸く。そのあと、またすぐに静かになる。
「今は、見てたいんだよ。球児の投球を」
そう呟いたのは、飯塚だった。
そして九回表。
マウンドには、ひとりの少年が立っていた。
たった70球目。
最後のバッターのバットが空を切り、石原のミットに収まる。
――カツン、と、乾いた音。
「試合終了、1対0。桜が丘、準決勝進出!」
どよめきではなく、静けさだった。
観客席から、何か神聖なものを見たあとのような拍手が起きる。
声援ではなく、称賛の拍手。
風が止んでいた。
まるで、空までがこの瞬間を待っていたかのように。
試合が終わって、ロッカールームに戻ってきたとき、誰もが少しずつ浮足立っていた。
控えの選手たちは口々に「ヤバくね?」「テレビ来るぞ!」なんて騒いでいたし、三島も「はー、俺、途中から息止めてたわ」なんて冗談を飛ばしていた。
でも、石原だけは、マスクを外して黙って座った。
背中を壁に預けて、使い古したキャッチャーマスクを膝の上に置く。
しばらく何も言わなかった。
顔には、笑顔もなければ、安堵の色もない。ただ、静かだった。
「9回、70球、ヒットゼロ、四球ゼロ……なんだそれ。完璧じゃん」
ぽつりとつぶやいたその声には、呆れや誇張もなかった。
どこまでも真っ直ぐに、ただ“事実”を噛みしめるような声だった。
けれどすぐに、彼は首を振った。
「でもな、あれはひとりじゃ無理だ。守備も、声も、球児の覚悟も……全部が重なった」
マウンドで受けた70球。
たしかに、全部“いい球”だった。けど、そのうち何球かは、普通なら打たれてもおかしくない。
でも、松井の横っ飛びがあった。滝川の一歩目が速かった。三島の声が、球場を支配してた。
あれは、奇跡じゃない。チームで取ったゼロだった。
石原はマスクの内側をじっと見つめる。
汗で湿ったその面に、ポケットから取り出した黒のマジックで、小さくこう記した。
“完全試合=完全なチーム”
誰に見せるわけでもない。
けれど、いつかこのマスクを誰かに譲る日が来たら、伝わればいい。
「ピッチャーだけじゃない。勝ちってのは、チーム全員でつかむものなんだ」って。
そう思ったとき、石原の口元がほんの少しだけ、笑っていた。
■
最後の一球──。
その打者が、見逃したままバットを下ろした瞬間。
球審の右手がスッと上がった瞬間。
球場の時間が、一瞬止まったように思えた。
スタンドの誰かが叫んだ。
ベンチから数人が立ち上がった。
でも、三島は守備位置で、ただ黙って立っていた。
叫ぶつもりだったのだ。
「よっしゃあ!」って、主将として、誰よりも大きな声で。
けれど──喉が詰まった。
拳を握ったまま、立ち尽くしていた。
視界の奥で、キャッチャーの石原がマウンドに駆け寄り、風祭と手を合わせたのが見えた。
何人もの部員がグラウンドに飛び出していくなか、三島だけは一歩、後ろで立っていた。
出てきたのは、絞り出すような、わずかな声。
「……すげぇな」
叫べなかったのは、きっと自分の胸がいっぱいだったからだ。
“背番号1”のあいつが、あんな投球をした。
でも、それは風祭ひとりじゃない。
石原のミット、松井と滝川の鉄壁の守備、浜中のレーザービーム。
そして、誰より大きな声で応援した藤木。
全員のプレーが積み重なって、あのゲームがあった。
三島は思った。
背番号1の背中には、俺たちが乗ってたんだ。
そして──それでも、俺は主将だとも思った。
「次だな……」
ポツリとこぼした言葉に、自分でうなずく。
まだ、準決勝がある。
それを越えれば、決勝。甲子園が見えてくる。
あいつが完全試合をやってのけた。なら、次は俺の番だ。
チームを“勝たせる”一打。俺が打つ。主将として。
グラウンドにはもう誰もいない。
でも、彼の胸には、次の試合の風がもう吹いていた。
主将として、仲間として、あの9回の時間を共有していたはずの自分が、
どこか置いていかれたような気さえした。
けれど──それは悔しさじゃなかった。
帰りのロッカールーム。
スパイクを脱ぎかけたところで、三島はふとしゃがみ込み、もう一度、靴紐を結び直した。
誰もいないベンチ裏で、独り言のように、小さくつぶやく。
「背番号1だけじゃない。……お前の背中に、全員が乗ってたんだよ」
その言葉に、返事はない。
でも三島の胸の奥には、あの一球の余韻と、確かな誇りが残っていた。
整列を終え、球児がベンチへ戻ってくる。
修司がそっと帽子を持ち上げ、目だけで合図を送った。
「ナイスピッチング」――その言葉は、ただ、帽子の動きに込められていた。
「ありがとうございました」
球児が、声に出したのはそれだけだった。
だが、それで十分だった。
その夜。
地元のローカルニュースが、桜が丘高校・風祭球児の“完全試合”を報じた。
SNSでも話題になり、野球ファンの間で「地方予選の怪物」として名前が広まる。
だが、本人はそれを知らないまま、自室でユニフォームをそっと畳んでいた。
窓の外では、あの時止まっていた風が、また少し吹き始めていた。
■
試合が終わって、ベンチがざわついて、スタンドの声援がいつまでも止まなかったそのあとも、飯塚直樹はずっと座ったままスコアブックを眺めていた。
風祭球児、完全試合達成。
ヒットゼロ、四球ゼロ、失点ゼロ、エラーもゼロ。
スコアシートの九つの回に、ゼロがずらりと並ぶ。
けれどそのページには、数字以上の“何か”が確かに詰まっていた。
飯塚は静かにペンを置いた。
「全ページにゼロが並ぶって、こんなに……しんってするんだな」
いつもなら、三回の失点に赤丸をつけたり、七回の盗塁にアスタリスクを打ったりしていた。
けれど今日だけは、ただ、何も書けなかった。
スコアブックの紙をめくる指が、ほんの少し震えている。
球児のあの球速ではなく、テンポの変化に気づいた五回裏。
石原のミットに吸い込まれる球の音が、“パン”から“すっ”に変わった七回表。
三島の守備位置が二歩下がったのを見逃さなかった八回裏。
全部、数字じゃ表せない。
けれど、数字の裏にあった心の動きを、飯塚だけは確かに見ていた。
スコアブックの欄外に、迷いながらもゆっくりとペンを走らせる。
「風が止まるって、こういうことか。俺、この1ページ、たぶん一生忘れない」
そのあと、ゆっくりとスコアブックを閉じた。
表紙の革が少し擦り切れているのが、なんだか誇らしかった。
飯塚は最後に、背表紙の下に小さくこう書き加える。
“風祭球児 完全試合達成”
その文字は、まっすぐに書いたつもりだった。
けれどよく見れば、ほんの少しだけ揺れていた。
それはきっと、書いている指の震えなんかじゃない。
あのマウンドに吹いた“風”の余韻だった。
■
試合が終わって、しばらくの間、私は何も書けなかった。
ペンを持っていた手は震えていて、ページをめくることすら怖かった。
スコアボードには、ずっと“0”が並んでいた。
まるで、それが当然だったみたいに、当たり前のように。
でも私にはわかる。
そのゼロが、どれだけ遠い場所にあったか。
そのゼロをつかむまでに、風祭くんがどれだけの“ひとり”と向き合ってきたか。
静かだった。
九回裏のマウンド。
球場の応援も、ベンチのざわめきも、誰かの声も──
全部が、いったん止まったように感じた。
“九回裏、風祭くんの背中から風の音が消えてた”
たぶん、それは緊張とかじゃなかったと思う。
ただただ、風祭くんという人のすべてが、あの一球に向かっていた。
息をする音も、踏み込む音も、ピッチャーマウンドでの動きすらも、空気を静かにしてしまうほどの集中だった。
“ミットに吸い込まれる最後の一球、音じゃなくて、空気ごと止まった”
石原くんのミットが打者の目の前でカチンと鳴って、審判の声が響いた。
“ストライクスリー”──見逃し三振。
風祭くんは、何も言わなかった。
ただ、帽子に手をやって、少しだけ空を見た。
“整列のあと、帽子を取る手がちょっと震えてた気がする”
私は知ってる。
風祭くんは、ずっと言わなかっただけ。
「勝ちたい」とか、「認められたい」とか、
そんな感情を飲み込んできたんだと思う。
あの日、転校してきてから、ずっと誰にも見せなかった涙。
それが、今日、こっそりこぼれそうになってたんじゃないかなって。
だから、最後のページにこう書いた。
「今日の風祭くん:誰にも言わなかったけど、たぶん“泣きたかった”んじゃないかな」
手帳を閉じたあと、私はこっそり笑った。
その涙が出ない強がりも、風祭くんらしいから──って。
■
夜の帰り道は、セミの鳴き声もすっかり途切れ、蝉しぐれが土に染み込むような静けさがあった。
照明の落ちた商店街を抜け、住宅街にさしかかる頃、修司は手にしていた帽子をふと見つめた。
試合が終わってからずっと、ポケットにしまおうとしてやめたそれは、何度も無意識に手のひらで握っていたせいか、つばの先が少しだけ曲がっていた。
「……クセだな」
小さく呟きながら、修司は立ち止まり、帽子のつばを親指でなぞった。
完全試合。
その言葉の重みは、ただの“すごい”では片付けられないものだった。
修司は監督として、何十年ぶりに心の奥に火が灯るのを感じていた。
けれど、それ以上に、親としての胸の奥が、ぎゅうっと締めつけられていた。
「もう……俺の背中なんて、見ちゃいねぇ」
ベンチからのサインも、采配も。
あのマウンドで投げる風祭球児は、自分の意志で球を選び、自分のテンポで試合を創っていた。
それは、かつて修司があの背番号を着て夢破れたときに、見たかった景色のはずだった。
なのに、寂しくなかった。
むしろ、誇らしかった。
もう、お前に教えることなんて、何もねぇんだな
そう思った瞬間、また帽子を握っていた。
まるでそれが、手からすり抜けてしまいそうで、逃がしたくないように。
けれど──
「見なくていい。でも、俺はお前を見てるぞ。ずっとな、球児」
誰に聞かせるでもなく、ぽつりと呟いた言葉は、夜空へ吸い込まれていった。
手の中の帽子のつばが、少し曲がっていることに気づき、修司は小さく笑った。
不器用な愛情が、きっとそこに沁み込んでいる。
歩き出すと、今度は帽子を被ることなく、胸に当てるように持ち直した。
まるで、次の試合までの道のりを、自分にも言い聞かせるかのように。
静かな夜道を、背中を丸めず、風の中を進んでいく。
父として。監督として。
そして何より、「風祭球児の一番の観客」として。
0
あなたにおすすめの小説

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。

【完結】イケメンが邪魔して本命に告白できません
竹柏凪紗
青春
高校の入学式、芸能コースに通うアイドルでイケメンの如月風磨が普通科で目立たない最上碧衣の教室にやってきた。女子たちがキャーキャー騒ぐなか、風磨は碧衣の肩を抱き寄せ「お前、今日から俺の女な」と宣言する。その真意とウソつきたちによって複雑になっていく2人の結末とは──

美味しいコーヒーの愉しみ方 Acidity and Bitterness
碧井夢夏
ライト文芸
<第五回ライト文芸大賞 最終選考・奨励賞>
住宅街とオフィスビルが共存するとある下町にある定食屋「まなべ」。
看板娘の利津(りつ)は毎日忙しくお店を手伝っている。
最近隣にできたコーヒーショップ「The Coffee Stand Natsu」。
どうやら、店長は有名なクリエイティブ・ディレクターで、脱サラして始めたお店らしく……?
神の舌を持つ定食屋の娘×クリエイティブ界の神と呼ばれた男 2人の出会いはやがて下町を変えていく――?
定食屋とコーヒーショップ、時々美容室、を中心に繰り広げられる出会いと挫折の物語。
過激表現はありませんが、重めの過去が出ることがあります。
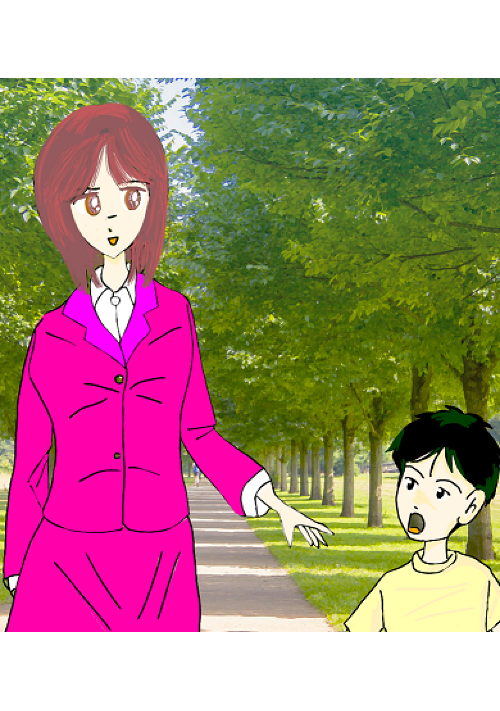
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話
登夢
恋愛
春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。

一億円の花嫁
藤谷 郁
恋愛
奈々子は家族の中の落ちこぼれ。
父親がすすめる縁談を断り切れず、望まぬ結婚をすることになった。
もうすぐ自由が無くなる。せめて最後に、思いきり贅沢な時間を過ごそう。
「きっと、素晴らしい旅になる」
ずっと憧れていた高級ホテルに到着し、わくわくする奈々子だが……
幸か不幸か!?
思いもよらぬ、運命の出会いが待っていた。
※エブリスタさまにも掲載

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















