18 / 21
つながり⑱
しおりを挟む
「わ、おいしい!」
アイスクリームショップでアイスを食べるなんてはじめての経験だ。ミント風味のアイスに小粒のキャンディが入っていて、そのキャンディが口の中でぱちぱちと弾ける。思わず目をまたたくほどにおいしい。
「よかったな」
秀星はチョコミント味、琉希は抹茶味を頼んだ。どちらもおいしそうでじいっと見ていると、琉希がアイスの入ったカップを賢太に差し出す。
「ひと口食べるか?」
「だめだ」
なぜか賢太ではなく秀星が答える。せっかくだからひと口だけ味見をさせてもらいたかったのに、と残念に思うと、秀星は自分のチョコミント味のアイスをピンク色のプラスチックのスプーンで掬い、賢太の口もとに差し出す。
「ほら。こっちを食べろ」
「うん」
ぱくりとアイスを口に含むと、爽やかな甘みがおいしい。琉希がなんとも言えないような顔で秀星と賢太を見ていて首をかしげた。
「どうしたの?」
「賢太、気がついてるか?」
「え、なに?」
琉希は苦笑するばかりで答えを教えてくれない。なんだろう、と今の自分の動きを思い返し、はっとした。もしかして俗に言う「あーん」をしたのだろうか。
「えっ! ち、ちが……」
かああっと頬が一気に熱くなり、少し俯く。そんなつもりはなかった。ただアイスがおいしそうで、秀星が食べさせてくれただけだ。隣の秀星を見るとなぜか自慢げな顔をしていて、秀星はわかっていてやったのだとさらに頬が火照った。
「兄さんってほんと、賢太といると人間くさいよな」
「俺は人間だ」
「だって昔はサイボーグみたいだっただろ」
寝てる姿さえ想像できなかった、と琉希はおかしそうに笑う。賢太もサイボーグな秀星を想像してみるが、できなかった。どう考えても優しくて恰好いい、感情に溢れた秀星しか浮かばない。たしかに出会った頃にはいろいろな感情とか味覚とか、人として大事なものが乏しかったかもしれない。でも今の秀星はそのすべてをきちんと楽しんで、喜んでいる。それが賢太にも嬉しくて仕方がない。
でも一番嬉しいのは、秀星と琉希がこうやってふざけ合ってくれることだ。互いを疎んでいたのが嘘のような仲良し兄弟――まではいかなくても、きちんとそれぞれを認めているのがわかる。
「賢太はもう大丈夫なのか?」
「うん。心配かけてごめんね」
琉希もあの事故のときに賢太を追いかけてきていたから、現場を見ている。かなり焦ったけれど、それ以上のパニック状態で狼狽する秀星を落ちつけないといけないと思ったら冷静になれたという。賢太にはそれほどに慌てる秀星は想像できないが、それだけふたりに心配も迷惑もかけたのだ。申し訳ない。
「たまにはまた前みたいに話したいな」
「できたら楽しいね」
琉希はわかっていて言っている。
琉希も賢太も、家族の回復とともに心の声が聞こえなくなった。心を塞ぐこと自体がなくなったのだ。ひとりで閉じこもる状況にさえならない。それはとても幸せで、ほんの少しだけ寂しかった。
「あれはなんだったんだろうな」
「うん。本当に」
琉希と賢太の孤独が互いの心を引き寄せたのか、それとも神様のいたずらだったのか。不可思議な現象は、今思い返しても夢の中の出来事のようだ。どうして琉希と賢太の心がつながったのか、なぜ他の誰かではなかったのか。考えてみたところでわからないけれど、きっと今があるために必要なことだったのだ。そう思えば、つらかったすべてを感謝できるような気がした。
「兄さん、睨まないでくれ」
「睨んでない。もともとこういう顔なんだ」
秀星は琉希と賢太が心の中で会話をしていたことが面白くない。それをわかっていて琉希が話題を振ってくるのは、秀星の反応を楽しんでいるのだ。けっこういたずら好きなところがある琉希と、甘くて優しい秀星の違いを見つけるたびに楽しくなる。人間だから違いがあっていいし、それを比べる必要はない。
「もしかしたら、賢太と俺は支えを求めていたのかもな」
「支え?」
「そう。ひとりが耐えられなかったから」
でも、と賢太は首をかしげる。
「それなら、どうして相手は秀星じゃなかったんだろう」
「兄さんが相手だったら、もっと嬉しかったってこと?」
意地悪なことを言うので、少し拗ねて見せる。
「そんなこと言ってないよ。秀星も琉希も、僕にはどっちも大切」
「ふうん」
秀星がどこか面白くなさそうに琉希を横目に見る。
「睨まないでくれ」
「もともとこういう顔だ」
けっこう仲良しな兄弟だな、とふたりの様子を眺めながらアイスを食べた。
大満足でアイスクリームショップをあとにし、アーケードを歩いて大きな商業ビルがあるほうに向かう。
「僕、クレープも食べてみたい」
こんなふうにいろいろと歩きまわったり食べたりするのははじめてだから、わくわくする。心が弾んで止まらないのがわかるのだろう、秀星も琉希も苦笑した。
「琉希はもう充分だろ。帰ればいい」
「兄さん、賢太以外には冷たくないか?」
三人で歩いていると、とても不思議な心持ちになる。なにかひとつ違えば、こうして三人でなんていられなかった。
「ハンバーガーもおいしそう!」
「アイスの前に昼ご飯も食べたのに、まだ食べられるの?」
琉希が苦笑いすると、秀星は正反対に柔らかく微笑んで賢太の頭を撫でた。
「賢太が食べたいならなんでも食べよう。琉希は帰れ」
早足になった賢太を見守るように、ふたりが少しうしろを並んで歩いている。秀星と琉希が並んで軽口を言い合っていることが嬉しくて足取りが弾み、なにもないところで躓いた。
「わっ」
「賢太!」
「あぶない!」
右側と左側から同時に手が伸びてきて、身体を支えてくれる。転びそうになった焦りで心臓が脈を速くしているけれど、右側から身体を支えてくれる手にはいっそう拍動が速くなる。
右側――秀星の手は、いつでも賢太を守ってくれる。なんとなくその手を握ると、自分からしたことなのに猛烈に恥ずかしくなった。
「惚気ないでくれ」
琉希が困った顔をしている。惚気ているつもりはない――ないのだけれど、秀星が手を離してくれない。
「秀星、手……」
「また転んだりしたら大変だから、つないでおこう。琉希は」
「帰らないからな」
火照る頬を片手で押さえ、秀星と手をつないで歩く。少し振り向くと、一歩うしろにいる琉希は困り顔で笑っている。幸せすぎて泣きたくなった。
アイスクリームショップでアイスを食べるなんてはじめての経験だ。ミント風味のアイスに小粒のキャンディが入っていて、そのキャンディが口の中でぱちぱちと弾ける。思わず目をまたたくほどにおいしい。
「よかったな」
秀星はチョコミント味、琉希は抹茶味を頼んだ。どちらもおいしそうでじいっと見ていると、琉希がアイスの入ったカップを賢太に差し出す。
「ひと口食べるか?」
「だめだ」
なぜか賢太ではなく秀星が答える。せっかくだからひと口だけ味見をさせてもらいたかったのに、と残念に思うと、秀星は自分のチョコミント味のアイスをピンク色のプラスチックのスプーンで掬い、賢太の口もとに差し出す。
「ほら。こっちを食べろ」
「うん」
ぱくりとアイスを口に含むと、爽やかな甘みがおいしい。琉希がなんとも言えないような顔で秀星と賢太を見ていて首をかしげた。
「どうしたの?」
「賢太、気がついてるか?」
「え、なに?」
琉希は苦笑するばかりで答えを教えてくれない。なんだろう、と今の自分の動きを思い返し、はっとした。もしかして俗に言う「あーん」をしたのだろうか。
「えっ! ち、ちが……」
かああっと頬が一気に熱くなり、少し俯く。そんなつもりはなかった。ただアイスがおいしそうで、秀星が食べさせてくれただけだ。隣の秀星を見るとなぜか自慢げな顔をしていて、秀星はわかっていてやったのだとさらに頬が火照った。
「兄さんってほんと、賢太といると人間くさいよな」
「俺は人間だ」
「だって昔はサイボーグみたいだっただろ」
寝てる姿さえ想像できなかった、と琉希はおかしそうに笑う。賢太もサイボーグな秀星を想像してみるが、できなかった。どう考えても優しくて恰好いい、感情に溢れた秀星しか浮かばない。たしかに出会った頃にはいろいろな感情とか味覚とか、人として大事なものが乏しかったかもしれない。でも今の秀星はそのすべてをきちんと楽しんで、喜んでいる。それが賢太にも嬉しくて仕方がない。
でも一番嬉しいのは、秀星と琉希がこうやってふざけ合ってくれることだ。互いを疎んでいたのが嘘のような仲良し兄弟――まではいかなくても、きちんとそれぞれを認めているのがわかる。
「賢太はもう大丈夫なのか?」
「うん。心配かけてごめんね」
琉希もあの事故のときに賢太を追いかけてきていたから、現場を見ている。かなり焦ったけれど、それ以上のパニック状態で狼狽する秀星を落ちつけないといけないと思ったら冷静になれたという。賢太にはそれほどに慌てる秀星は想像できないが、それだけふたりに心配も迷惑もかけたのだ。申し訳ない。
「たまにはまた前みたいに話したいな」
「できたら楽しいね」
琉希はわかっていて言っている。
琉希も賢太も、家族の回復とともに心の声が聞こえなくなった。心を塞ぐこと自体がなくなったのだ。ひとりで閉じこもる状況にさえならない。それはとても幸せで、ほんの少しだけ寂しかった。
「あれはなんだったんだろうな」
「うん。本当に」
琉希と賢太の孤独が互いの心を引き寄せたのか、それとも神様のいたずらだったのか。不可思議な現象は、今思い返しても夢の中の出来事のようだ。どうして琉希と賢太の心がつながったのか、なぜ他の誰かではなかったのか。考えてみたところでわからないけれど、きっと今があるために必要なことだったのだ。そう思えば、つらかったすべてを感謝できるような気がした。
「兄さん、睨まないでくれ」
「睨んでない。もともとこういう顔なんだ」
秀星は琉希と賢太が心の中で会話をしていたことが面白くない。それをわかっていて琉希が話題を振ってくるのは、秀星の反応を楽しんでいるのだ。けっこういたずら好きなところがある琉希と、甘くて優しい秀星の違いを見つけるたびに楽しくなる。人間だから違いがあっていいし、それを比べる必要はない。
「もしかしたら、賢太と俺は支えを求めていたのかもな」
「支え?」
「そう。ひとりが耐えられなかったから」
でも、と賢太は首をかしげる。
「それなら、どうして相手は秀星じゃなかったんだろう」
「兄さんが相手だったら、もっと嬉しかったってこと?」
意地悪なことを言うので、少し拗ねて見せる。
「そんなこと言ってないよ。秀星も琉希も、僕にはどっちも大切」
「ふうん」
秀星がどこか面白くなさそうに琉希を横目に見る。
「睨まないでくれ」
「もともとこういう顔だ」
けっこう仲良しな兄弟だな、とふたりの様子を眺めながらアイスを食べた。
大満足でアイスクリームショップをあとにし、アーケードを歩いて大きな商業ビルがあるほうに向かう。
「僕、クレープも食べてみたい」
こんなふうにいろいろと歩きまわったり食べたりするのははじめてだから、わくわくする。心が弾んで止まらないのがわかるのだろう、秀星も琉希も苦笑した。
「琉希はもう充分だろ。帰ればいい」
「兄さん、賢太以外には冷たくないか?」
三人で歩いていると、とても不思議な心持ちになる。なにかひとつ違えば、こうして三人でなんていられなかった。
「ハンバーガーもおいしそう!」
「アイスの前に昼ご飯も食べたのに、まだ食べられるの?」
琉希が苦笑いすると、秀星は正反対に柔らかく微笑んで賢太の頭を撫でた。
「賢太が食べたいならなんでも食べよう。琉希は帰れ」
早足になった賢太を見守るように、ふたりが少しうしろを並んで歩いている。秀星と琉希が並んで軽口を言い合っていることが嬉しくて足取りが弾み、なにもないところで躓いた。
「わっ」
「賢太!」
「あぶない!」
右側と左側から同時に手が伸びてきて、身体を支えてくれる。転びそうになった焦りで心臓が脈を速くしているけれど、右側から身体を支えてくれる手にはいっそう拍動が速くなる。
右側――秀星の手は、いつでも賢太を守ってくれる。なんとなくその手を握ると、自分からしたことなのに猛烈に恥ずかしくなった。
「惚気ないでくれ」
琉希が困った顔をしている。惚気ているつもりはない――ないのだけれど、秀星が手を離してくれない。
「秀星、手……」
「また転んだりしたら大変だから、つないでおこう。琉希は」
「帰らないからな」
火照る頬を片手で押さえ、秀星と手をつないで歩く。少し振り向くと、一歩うしろにいる琉希は困り顔で笑っている。幸せすぎて泣きたくなった。
12
あなたにおすすめの小説

この胸の高鳴りは・・・
暁エネル
BL
電車に乗りいつも通り大学へと向かう途中 気になる人と出会う男性なのか女性なのかわからないまま 電車を降りその人をなぜか追いかけてしまった 初めての出来事に驚き その人に声をかけ自分のした事に 優しく笑うその人に今まで経験した事のない感情が・・・

はじまりの朝
さくら乃
BL
子どもの頃は仲が良かった幼なじみ。
ある出来事をきっかけに離れてしまう。
中学は別の学校へ、そして、高校で再会するが、あの頃の彼とはいろいろ違いすぎて……。
これから始まる恋物語の、それは、“はじまりの朝”。
✳『番外編〜はじまりの裏側で』
『はじまりの朝』はナナ目線。しかし、その裏側では他キャラもいろいろ思っているはず。そんな彼ら目線のエピソード。

初恋ミントラヴァーズ
卯藤ローレン
BL
私立の中高一貫校に通う八坂シオンは、乗り物酔いの激しい体質だ。
飛行機もバスも船も人力車もダメ、時々通学で使う電車でも酔う。
ある朝、学校の最寄り駅でしゃがみこんでいた彼は金髪の男子生徒に助けられる。
眼鏡をぶん投げていたため気がつかなかったし何なら存在自体も知らなかったのだが、それは学校一モテる男子、上森藍央だった(らしい)。
知り合いになれば不思議なもので、それまで面識がなかったことが嘘のように急速に距離を縮めるふたり。
藍央の優しいところに惹かれるシオンだけれど、優しいからこそその本心が掴みきれなくて。
でも想いは勝手に加速して……。
彩り豊かな学校生活と夏休みのイベントを通して、恋心は芽生え、弾んで、時にじれる。
果たしてふたりは、恋人になれるのか――?
/金髪顔整い×黒髪元気時々病弱/
じれたり悩んだりもするけれど、王道満載のウキウキハッピハッピハッピーBLです。
集まると『動物園』と称されるハイテンションな友人たちも登場して、基本騒がしい。
◆毎日2回更新。11時と20時◆

あなたのいちばんすきなひと
名衛 澄
BL
亜食有誠(あじきゆうせい)は幼なじみの与木実晴(よぎみはる)に好意を寄せている。
ある日、有誠が冗談のつもりで実晴に付き合おうかと提案したところ、まさかのOKをもらってしまった。
有誠が混乱している間にお付き合いが始まってしまうが、実晴の態度はいつもと変わらない。
俺のことを好きでもないくせに、なぜ付き合う気になったんだ。
実晴の考えていることがわからず、不安に苛まれる有誠。
そんなとき、実晴の元カノから実晴との復縁に協力してほしいと相談を受ける。
また友人に、幼なじみに戻ったとしても、実晴のとなりにいたい。
自分の気持ちを隠して実晴との"恋人ごっこ"の関係を続ける有誠は――
隠れ執着攻め×不器用一生懸命受けの、学園青春ストーリー。
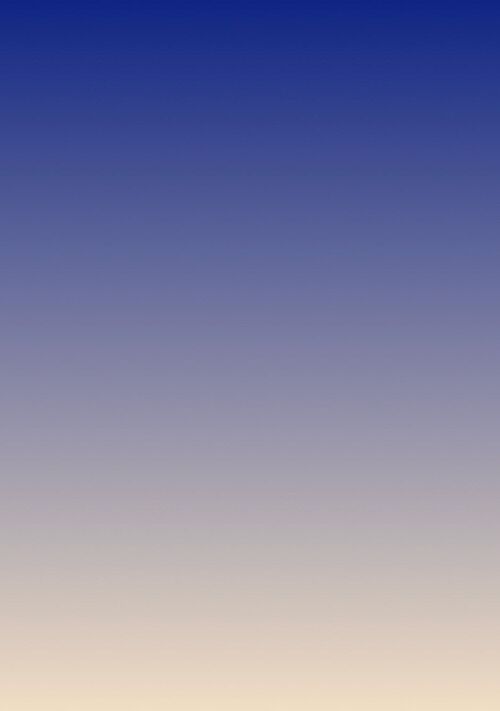
あの部屋でまだ待ってる
名雪
BL
アパートの一室。
どんなに遅くなっても、帰りを待つ習慣だけが残っている。
始まりは、ほんの気まぐれ。
終わる理由もないまま、十年が過ぎた。
与え続けることも、受け取るだけでいることも、いつしか当たり前になっていく。
――あの部屋で、まだ待ってる。

きらきらしてる君が好き
書鈴 夏(ショベルカー)
BL
冴えない一般人である齋藤達也«さいとうたつや»は、夢を見た。それは幼い頃、友人であった柊湊«ひいらぎみなと»と交わした約束の夢。
「一緒にアイドルになろう」
早々に夢を諦めていた達也は感傷的な思いを抱きながら、友人の樋口凪«ひぐちなぎ»にアイドルのライブへと誘われ、奏«そう»というアイドルの握手会に参加する。
「ったつやくん……!?」
アイドルである奏の口から飛び出したのは、彼が知るはずもない自分の名前で──
青春BLカップ参加作品です。


君と僕との泡沫は
七天八狂
BL
【ツンデレ美貌✕鈍感平凡の高校生】
品行方正才色兼備の生徒会長と、爪弾きの底辺ぼっちが親の再婚で義兄弟となった青春BLドラマ。
親の再婚で義兄弟となった正反対の二人の青春BL。
入学して以来、ずっと見つめ続けていた彼が義兄弟となった。
しかし、誰にでも親切で、みなから慕われている彼が向けてきたのは、拒絶の言葉だった。
櫻井優斗は、再婚を繰り返す母のせいで引っ越しと転校を余儀なくされ、友人をつくることを諦め、漫画を描くという趣味に没頭し、孤独に生きていた。
高校で出会った久我雅利の美貌に見惚れ、彼を主人公にした漫画を描くことに決めて、二年間観察し続けていた。
底辺ぼっちだった優斗は、周りから空気のように扱われていたから、見えない存在として、どれほど見ていても気づかれることはなかった。
そのはずが、同じ屋根の下に住む関係となり、当の本人に、絵を描いていたことまでもがバレてしまった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















