1 / 61
第1章 いざないの風
1 白竜
しおりを挟む
――逃げなきゃ。
逃げなきゃ、逃げなきゃ。早く遠くへ、逃げなきゃ!
同じような景色の中を、彼女は走り続けていた。
視線の先は果てしなく木々が生い茂り、低く暗い雨雲を持ち上げているように見えた。葉は秋の涼しさで、ゆるやかに色づき始めている。足場は所々根が突き出していて、いいとは言えなかった。
はたしてどのくらい走ったのか、彼女自身もはっきり分からなかった。山をひとつ越えたことは確かだ。辺りの風景が、徐々に見覚えのないものになってきている。
脇腹がずきずきと痛み、呼吸もままならなくなっていた。しかし、いまだ背後の追手の気配は消えない。むしろその数を増やしている気がする。
誰か、と声に出すことなく彼女は叫んだ。
(誰か、助けて……!)
頭上をなにかが通過したのが影で分かった。
彼女はハッと淀んだ空を見上げた。途端に足がもつれて、立て直す間もなく体が地面に投げ出された。それでも彼女は必死で顔を上げた。木の枝で区切られた空を、赤い影が横切るのが見えた。
瞠目すると、彼女は再び走り出そうとした。だが、立てない。
彼女の体は限界に近かった。朝からもう半日以上、山道を全力で走り続けている。どんなに足に力を込めても、どうしても自力で立ち上がることができなかった。
彼らに捕まれば、なにをされるのか分からない。これまでは地の利もあって、どうにかここまで追いつかれずにいた。しかし、自分はもう走れない。もはや、捕まるのを待つしかないのか。
彼女が諦めかけたときだった。
《……こちらへ》
誰かが囁いた気がした。風が耳元をすり抜けたような、そんな声だった。
警戒しながら、彼女はゆっくりと自分のまわりを見渡した。遠くから迫る追手のほかに、人の気配は感じない。
気のせいだろうかと彼女が思い始めた矢先、声は再び聞こえた。
《彼らに捕まってはいけない。早くこちらへ》
彼女はぐるりと視線を巡らせた。
「こちら……て、どっち?」
荒い息づかいの間に彼女が問うと、前触れなく強い風が吹いた。落ち葉が巻き上げられ、木々がざわざわとやかましく鳴る。声は言った。
《こちらへ》
どうやら風下を差しているらしい。
見当をつけた彼女は、一番近くの木まで重い体を引きずった。幹に縋りついて、無理やりに体を起こす。関節がぎしぎしと鳴らないのが不思議なほどに痛んだが、かろうじて立つことはできた。
再び風が吹いた。
《こちらへ。早く、こちらへ》
急かされるまま、彼女は必死で足を前に出した。
この声を信じていいのかは定かではない。自分を捕らえるための罠かもしれない。しかし、今の彼女にはほかに頼れるものもなかった。
終わりの見えない景色の中を、彼女は歩き続けた。いざなう声は、早くと彼女を急かす。風は背を押すように吹きつけ、歩みを助けた。いつしか雨も降り出していた。暗色の空からせわしなく灰色の線が落下し、肌をたたき、着衣を濡らしていく。
彼女が何度もよろめきながら歩いていると、ずっと同じことを繰り返していた声に変化があった。
《あの木へ》
その木を特定することは難しくなかった。向かう先に、ほかよりもひと抱えは幹が太い木が見える。近づくと、それは長い寿命を終えた枯れ木だった。広がる枝にいっさいの葉はなく、ごつごつとした幹の表面は触れるだけで皮が剥がれ落ちるほど脆くなっている。
《中へ》
「……中?」
言葉の意味を理解できず、彼女は聞き返した。声は答えた。
《木の中へ》
言われて、足元に木のうろが口を開いていることに気づいた。身をかがめて、中をそっと覗き込んでみる。木の中は大きな空洞になっているようだったが、まったく光が差しこまないため完全な闇となっていた。
《早く中へ。彼らがくる》
ためらったのは一瞬だった。入口は狭かったが、細身の彼女ならば入れないことはない。深呼吸したあと、彼女は暗いうろに体をねじ込んだ。
うろの中の空気は重くしめっていて、ひどくかび臭かった。外が晴れていればもっと違っただろうが、入口以外に光源もないため、中のようすを知ることもできない。
彼女は膝を抱えて縮こまると、ひたすら歯が鳴りそうになるのを堪えた。濡れた服が体温を奪っていくのが分かる。下の地面もじっとりとしていて、痺れた足先には感覚がなかった。
そうしているうちに、雨音とは異なった音が彼女の耳に届いた。ばしゃばしゃと泥をはね上げる、これは足音だ。彼女は凍りつき、両手をぐっと握りあわせた。
幾人もの足音が、木のすぐ傍までせまる。彼女は大声で泣き出しそうになるのを、うろから飛び出しそうになるのを必死で堪えた。うろの入口は目立たない。ここに隠れていれば、きっと自分から出ていかない限り見つからないはずだ。
それでもやはり不安や恐怖はぬぐえなかった。絶対に見つからないという保証は、どこにもないのだ。
☫
穏やかな秋の昼下がり、エフィミアはルベル山へと入っていた。
空は快晴、風は良好。辺りにはいかにものんびりとした空気が流れている。
ドラディア王国東部、アナトレーナ州オロデン村。西以外の三方をフラウ、ロサ、ルベルの山に囲まれた、自然豊かな村だ。エフィミアが今いるルベルは、村の東に接している。
エフィミアは重くなった籠をどさりと地面に置くと、しばしの休息のため木の根元に腰を下ろした。籠の中はおおかたが薬草のたぐいだったが、山菜と、栗などの木の実がいくらか。朽木で偶然見つけたしめじもひと株入っている。
心地よい風が金に近い薄茶色のおさげ髪をゆらしていった。頭上を見れば、真っ青な空と、まだらに色づく葉とのコントラストが目にも鮮やかだ。
エフィミアは、ほっと息をついた。このままうとうとしてしまいそうなほどに気持ちがいい。日は高く暖かで、お昼寝にはちょうどいい時間だ。
ぽかぽかとした日差しの中、エフィミアがうつらうつらとし始めたときだった。太陽を黒い点が横切った。ひとつではない。いくつかの小さな影が、ほかよりも少し大きい影を追いかけ、とり巻いている。
鳥の親子だろうと思い、エフィミアはぼんやりとそれを見上げていた。だが眺めているうちにそうではない気がしてきた。気のせいか、大きな影が必死に逃げ惑っているように見える。
なにとはなしにそんなことを考えていると、それらは急降下を始め、影が大きくせまってきた。近づいてくるにつれて影の形がはっきりとする。その姿をとらえたエフィミアは、ぎょっと立ち上がった。
「……竜?」
逆光になって輪郭しか見えないが、間違いなく竜だ。どういうわけか、大型の竜が幾匹もの小型竜に追われている。
エフィミアがそこを動けずにいる間にも竜は墜落する勢いで降下し、視界を占領していった。
大きな方の竜が、山につっこむ寸前で大きくはばたいた。瞬間、突風が巻き起こる。木々は枝が折れんばかりに波打ち、砂が散り、エフィミアのおさげとスカートがひるがえった。艶々とした鱗に包まれた巨体が、弧を描いて上昇する。そのあとを、小型竜たちが追った。
突風をやり過ごしたエフィミアは、反射的に竜を目で追いかけた。そして、息をのんだ。
「白い、竜……」
初めて見る種類だった。
大きな竜の体表は、日光を照り返す純白の鱗に覆われていた。大きさは人間の数倍はある。優美な曲線の二本の角に、鋭いかぎ爪をそなえた四肢。すらりと長い尾と、竜独特の大きく薄い翼を持っている。艶やかな鱗は白銀に輝き、見る者に畏怖さえ抱かせる。こんなに美しい竜を、エフィミアは他に知らない。
その竜のまわりを飛び交う、小さい方の竜の鱗はくすんだ赤をしていた。まっすぐな角は四本あり、よく見ると背に人を乗せている。
――軍用飛竜。
竜の背に騎乗し、空を駆ける精鋭部隊。竜に乗るには高度な技術が必要とされ、王国軍でも選りすぐられた者たちだ。まれに、頭上を飛び過ぎていくのを見かけることがある。
それでエフィミアは、おおよそ状況を理解した。軍の騎竜隊が白い竜を狩っているのだ。白竜がなにか悪さをしたに違いない。そうでなくて王国軍が動くようなことはないだろう。実際、肉食竜が人を襲うことはあるし、草食竜が農作物を荒らすこともある。
野生の竜が人里に現れることはまれだが、ひとたび現れれば暮らしを脅かすものには違いない。
白い竜の動きは、巨体に似合わず素早かった。しかし数と機動力では騎竜隊の方が上をいっている。しとめられるのも時間の問題だろう。
王国民なら一度は憧れる蒼穹の騎士の勇姿に胸ときめかせながら、エフィミアは上空のようすについ見入った。
一騎の赤竜が、白竜の背を大きく横切った。純白の翼のつけ根に太い槍が突き立っていた。
「やった!」
エフィミアは喜びのこぶしを握った。
天地をゆるがす竜の絶叫が、辺り一帯に響き渡る。明記しがたい、鼓膜に突き刺さる竜の悲鳴に、エフィミアは咄嗟にこぶしを開いて耳をふさいだ。飛ぶ力を失った竜の大きな体が空を切り落下する。空の高いところでは、赤竜たちが喜びを分かち合うようにゆうゆうと旋回していた。
白竜の体が大地に叩きつけられる――直前、竜の白い体が中空で霧散し、消えた。
エフィミアは声も出ず、ぽかんとした。かの竜を狩っていた騎竜兵たちも、この事態に目を瞠っていることだろう。
音も衝撃もいっさいなかった。この辺り落ちたとはとても考えにくい。消えてしまった以外にありえないのだが、一体どんな仕掛けをすればあの巨体が、一瞬にしてあと形もなく消えてしまうのか。
ふと、エフィミアは竜が消えた辺りになにかを見つけた。赤い色をした小さな輝きだった。まるで、あえかな星の輝きにも見える。
不思議に思って凝視していると、輝きは徐々に彼女のいるところへ降下しているようだった。赤く発光するなにかがゆっくりと、しかし確実にこちらに向かって落ちてくる。エフィミアはそれを受けとめようと、木の下から進み出て腕を伸ばした。
赤い輝きが、掌へと舞い降りる。ところが、受けとめたかのように思われたそれは、指の間をすり抜けた。
しまった、とエフィミアが思ったときには、どこにも輝きは見当たらなくなっていた。足元の草の間、自分の前掛けのポケット……どこにもない。まさにこつ然と消えてしまった。竜といい光といい、一体どこへいってしまったというのか。
続く不可思議な事態に腕を組み、エフィミアは真剣に考え込んだ――そのとき、異変は起きた。
逃げなきゃ、逃げなきゃ。早く遠くへ、逃げなきゃ!
同じような景色の中を、彼女は走り続けていた。
視線の先は果てしなく木々が生い茂り、低く暗い雨雲を持ち上げているように見えた。葉は秋の涼しさで、ゆるやかに色づき始めている。足場は所々根が突き出していて、いいとは言えなかった。
はたしてどのくらい走ったのか、彼女自身もはっきり分からなかった。山をひとつ越えたことは確かだ。辺りの風景が、徐々に見覚えのないものになってきている。
脇腹がずきずきと痛み、呼吸もままならなくなっていた。しかし、いまだ背後の追手の気配は消えない。むしろその数を増やしている気がする。
誰か、と声に出すことなく彼女は叫んだ。
(誰か、助けて……!)
頭上をなにかが通過したのが影で分かった。
彼女はハッと淀んだ空を見上げた。途端に足がもつれて、立て直す間もなく体が地面に投げ出された。それでも彼女は必死で顔を上げた。木の枝で区切られた空を、赤い影が横切るのが見えた。
瞠目すると、彼女は再び走り出そうとした。だが、立てない。
彼女の体は限界に近かった。朝からもう半日以上、山道を全力で走り続けている。どんなに足に力を込めても、どうしても自力で立ち上がることができなかった。
彼らに捕まれば、なにをされるのか分からない。これまでは地の利もあって、どうにかここまで追いつかれずにいた。しかし、自分はもう走れない。もはや、捕まるのを待つしかないのか。
彼女が諦めかけたときだった。
《……こちらへ》
誰かが囁いた気がした。風が耳元をすり抜けたような、そんな声だった。
警戒しながら、彼女はゆっくりと自分のまわりを見渡した。遠くから迫る追手のほかに、人の気配は感じない。
気のせいだろうかと彼女が思い始めた矢先、声は再び聞こえた。
《彼らに捕まってはいけない。早くこちらへ》
彼女はぐるりと視線を巡らせた。
「こちら……て、どっち?」
荒い息づかいの間に彼女が問うと、前触れなく強い風が吹いた。落ち葉が巻き上げられ、木々がざわざわとやかましく鳴る。声は言った。
《こちらへ》
どうやら風下を差しているらしい。
見当をつけた彼女は、一番近くの木まで重い体を引きずった。幹に縋りついて、無理やりに体を起こす。関節がぎしぎしと鳴らないのが不思議なほどに痛んだが、かろうじて立つことはできた。
再び風が吹いた。
《こちらへ。早く、こちらへ》
急かされるまま、彼女は必死で足を前に出した。
この声を信じていいのかは定かではない。自分を捕らえるための罠かもしれない。しかし、今の彼女にはほかに頼れるものもなかった。
終わりの見えない景色の中を、彼女は歩き続けた。いざなう声は、早くと彼女を急かす。風は背を押すように吹きつけ、歩みを助けた。いつしか雨も降り出していた。暗色の空からせわしなく灰色の線が落下し、肌をたたき、着衣を濡らしていく。
彼女が何度もよろめきながら歩いていると、ずっと同じことを繰り返していた声に変化があった。
《あの木へ》
その木を特定することは難しくなかった。向かう先に、ほかよりもひと抱えは幹が太い木が見える。近づくと、それは長い寿命を終えた枯れ木だった。広がる枝にいっさいの葉はなく、ごつごつとした幹の表面は触れるだけで皮が剥がれ落ちるほど脆くなっている。
《中へ》
「……中?」
言葉の意味を理解できず、彼女は聞き返した。声は答えた。
《木の中へ》
言われて、足元に木のうろが口を開いていることに気づいた。身をかがめて、中をそっと覗き込んでみる。木の中は大きな空洞になっているようだったが、まったく光が差しこまないため完全な闇となっていた。
《早く中へ。彼らがくる》
ためらったのは一瞬だった。入口は狭かったが、細身の彼女ならば入れないことはない。深呼吸したあと、彼女は暗いうろに体をねじ込んだ。
うろの中の空気は重くしめっていて、ひどくかび臭かった。外が晴れていればもっと違っただろうが、入口以外に光源もないため、中のようすを知ることもできない。
彼女は膝を抱えて縮こまると、ひたすら歯が鳴りそうになるのを堪えた。濡れた服が体温を奪っていくのが分かる。下の地面もじっとりとしていて、痺れた足先には感覚がなかった。
そうしているうちに、雨音とは異なった音が彼女の耳に届いた。ばしゃばしゃと泥をはね上げる、これは足音だ。彼女は凍りつき、両手をぐっと握りあわせた。
幾人もの足音が、木のすぐ傍までせまる。彼女は大声で泣き出しそうになるのを、うろから飛び出しそうになるのを必死で堪えた。うろの入口は目立たない。ここに隠れていれば、きっと自分から出ていかない限り見つからないはずだ。
それでもやはり不安や恐怖はぬぐえなかった。絶対に見つからないという保証は、どこにもないのだ。
☫
穏やかな秋の昼下がり、エフィミアはルベル山へと入っていた。
空は快晴、風は良好。辺りにはいかにものんびりとした空気が流れている。
ドラディア王国東部、アナトレーナ州オロデン村。西以外の三方をフラウ、ロサ、ルベルの山に囲まれた、自然豊かな村だ。エフィミアが今いるルベルは、村の東に接している。
エフィミアは重くなった籠をどさりと地面に置くと、しばしの休息のため木の根元に腰を下ろした。籠の中はおおかたが薬草のたぐいだったが、山菜と、栗などの木の実がいくらか。朽木で偶然見つけたしめじもひと株入っている。
心地よい風が金に近い薄茶色のおさげ髪をゆらしていった。頭上を見れば、真っ青な空と、まだらに色づく葉とのコントラストが目にも鮮やかだ。
エフィミアは、ほっと息をついた。このままうとうとしてしまいそうなほどに気持ちがいい。日は高く暖かで、お昼寝にはちょうどいい時間だ。
ぽかぽかとした日差しの中、エフィミアがうつらうつらとし始めたときだった。太陽を黒い点が横切った。ひとつではない。いくつかの小さな影が、ほかよりも少し大きい影を追いかけ、とり巻いている。
鳥の親子だろうと思い、エフィミアはぼんやりとそれを見上げていた。だが眺めているうちにそうではない気がしてきた。気のせいか、大きな影が必死に逃げ惑っているように見える。
なにとはなしにそんなことを考えていると、それらは急降下を始め、影が大きくせまってきた。近づいてくるにつれて影の形がはっきりとする。その姿をとらえたエフィミアは、ぎょっと立ち上がった。
「……竜?」
逆光になって輪郭しか見えないが、間違いなく竜だ。どういうわけか、大型の竜が幾匹もの小型竜に追われている。
エフィミアがそこを動けずにいる間にも竜は墜落する勢いで降下し、視界を占領していった。
大きな方の竜が、山につっこむ寸前で大きくはばたいた。瞬間、突風が巻き起こる。木々は枝が折れんばかりに波打ち、砂が散り、エフィミアのおさげとスカートがひるがえった。艶々とした鱗に包まれた巨体が、弧を描いて上昇する。そのあとを、小型竜たちが追った。
突風をやり過ごしたエフィミアは、反射的に竜を目で追いかけた。そして、息をのんだ。
「白い、竜……」
初めて見る種類だった。
大きな竜の体表は、日光を照り返す純白の鱗に覆われていた。大きさは人間の数倍はある。優美な曲線の二本の角に、鋭いかぎ爪をそなえた四肢。すらりと長い尾と、竜独特の大きく薄い翼を持っている。艶やかな鱗は白銀に輝き、見る者に畏怖さえ抱かせる。こんなに美しい竜を、エフィミアは他に知らない。
その竜のまわりを飛び交う、小さい方の竜の鱗はくすんだ赤をしていた。まっすぐな角は四本あり、よく見ると背に人を乗せている。
――軍用飛竜。
竜の背に騎乗し、空を駆ける精鋭部隊。竜に乗るには高度な技術が必要とされ、王国軍でも選りすぐられた者たちだ。まれに、頭上を飛び過ぎていくのを見かけることがある。
それでエフィミアは、おおよそ状況を理解した。軍の騎竜隊が白い竜を狩っているのだ。白竜がなにか悪さをしたに違いない。そうでなくて王国軍が動くようなことはないだろう。実際、肉食竜が人を襲うことはあるし、草食竜が農作物を荒らすこともある。
野生の竜が人里に現れることはまれだが、ひとたび現れれば暮らしを脅かすものには違いない。
白い竜の動きは、巨体に似合わず素早かった。しかし数と機動力では騎竜隊の方が上をいっている。しとめられるのも時間の問題だろう。
王国民なら一度は憧れる蒼穹の騎士の勇姿に胸ときめかせながら、エフィミアは上空のようすについ見入った。
一騎の赤竜が、白竜の背を大きく横切った。純白の翼のつけ根に太い槍が突き立っていた。
「やった!」
エフィミアは喜びのこぶしを握った。
天地をゆるがす竜の絶叫が、辺り一帯に響き渡る。明記しがたい、鼓膜に突き刺さる竜の悲鳴に、エフィミアは咄嗟にこぶしを開いて耳をふさいだ。飛ぶ力を失った竜の大きな体が空を切り落下する。空の高いところでは、赤竜たちが喜びを分かち合うようにゆうゆうと旋回していた。
白竜の体が大地に叩きつけられる――直前、竜の白い体が中空で霧散し、消えた。
エフィミアは声も出ず、ぽかんとした。かの竜を狩っていた騎竜兵たちも、この事態に目を瞠っていることだろう。
音も衝撃もいっさいなかった。この辺り落ちたとはとても考えにくい。消えてしまった以外にありえないのだが、一体どんな仕掛けをすればあの巨体が、一瞬にしてあと形もなく消えてしまうのか。
ふと、エフィミアは竜が消えた辺りになにかを見つけた。赤い色をした小さな輝きだった。まるで、あえかな星の輝きにも見える。
不思議に思って凝視していると、輝きは徐々に彼女のいるところへ降下しているようだった。赤く発光するなにかがゆっくりと、しかし確実にこちらに向かって落ちてくる。エフィミアはそれを受けとめようと、木の下から進み出て腕を伸ばした。
赤い輝きが、掌へと舞い降りる。ところが、受けとめたかのように思われたそれは、指の間をすり抜けた。
しまった、とエフィミアが思ったときには、どこにも輝きは見当たらなくなっていた。足元の草の間、自分の前掛けのポケット……どこにもない。まさにこつ然と消えてしまった。竜といい光といい、一体どこへいってしまったというのか。
続く不可思議な事態に腕を組み、エフィミアは真剣に考え込んだ――そのとき、異変は起きた。
0
あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました
大江戸ウメコ
恋愛
幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!
藤原ライラ
恋愛
ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。
ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。
解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。
「君は、おれに、一体何をくれる?」
呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?
強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。
※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~
双真満月
恋愛
不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。
なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。
※小説家になろうでも掲載中。
※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。
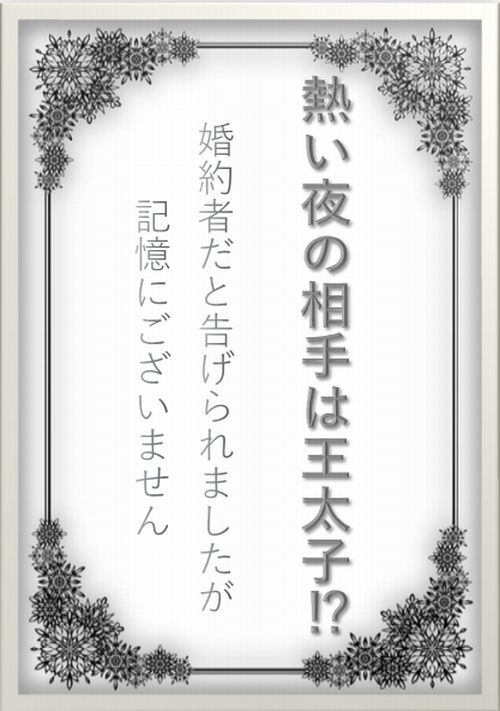
【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~
世界のボボブラ汁(エロル)
恋愛
激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。
──え……この方、誰?
相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。
けれど私は、自分の名前すら思い出せない。
訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。
「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」
……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?
しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。
もしかして、そのせいで私は命を狙われている?
公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。
全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!
※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟
飴爽かに
恋愛
この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。
彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。
クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。
悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~
花虎
恋愛
魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。
だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。
エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。
そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。
「やっと、あなたに復讐できる」
歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。
彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。
過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。
※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~
二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中
恋愛
政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。
彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。
そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。
幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。
そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















