47 / 61
第4章 騎士の忠義
15 叫び
しおりを挟む
部屋に連れ戻されたエフィミアは、乱暴に突き飛ばされて床へと倒れ込んだ。扉の閉まる音を聞きつけてそちらを見やれば、ルーファンスが紅いしずくの残る剣を手に立っていた。
垂れて乱れた極細の金髪に隠されて、表情は見えない。合間に覗く淡い碧眼だけが異様に輝いて見えた。
ルーファンスがゆっくりと足を踏み出し、エフィミアは這うように後ずさった。いつものように、悪意に満ちた気配。しかしこれまでのものとはどことなく質が違った。
悪意よりももっと強い、より純度の高い、殺意。確かな質量を持ったそれがエフィミアの体にまとわりつき、じわじわと心臓を締め上げる。
エフィミアはしばらくルーファンスを見詰めていたが、堪えきれずに体を起こし部屋の奥に向かって駆け出した。素早く反応したルーファンスがすぐ背後に迫り、刃が振り下ろされるのを感じた。
背を撫でられる感触がして、切っ先が乗馬服の上着を裂いてシャツを掠めたのが分かった。刃を躱して逃げるも、閉じられた室内ではすぐに壁に行き当たってしまう。エフィミアは壁を伝い、家具を乗り越え、振り下ろされる刃から必死に逃げた。
ルーファンスはなり振り構わず剣を振り回し、エフィミアに向かって切りかかった。カーテンが裂け、クッションの詰め物が散った。床に、壁に、調度に、鋭く傷が刻まれる。
何度も短い悲鳴をあげながら逃げ惑うエフィミアを、ルーファンスは無表情のまま執拗に追いかけ、刃を向けた。彼が刃を振るうたびに、そこについている紅いしずくが散って宙に軌跡を描いた。
銀の刃が頬をかすめて走り抜け、ベッドを乗り越えようとしたエフィミアは思わず動きを止めた。そのまま引き倒され、顔のすぐ横に剣が突き立てられる。剣の切っ先はいとも容易く寝具を刺しつらぬき、エフィミアは戦慄して、見下ろすルーファンスを見詰めた。
恐怖心を煽るのに十分な沈黙のあと、ルーファンスの口がかすかに動いた。
「……どうして」
ルーファンスの声に抑揚はなく、顔には感情の読めない無表情を貼りつかせていた。今までにない彼のようすに、エフィミアは恐れ戸惑った。
「どうして取るの。君はなんでも持っているのに。わたしの欲しいもの全部を持っているのに――それなのに、なんでわたしから取るの? わたしにはなにもないのに……」
かすかに震える声でルーファンスは囁き、瞳の輝きが増した。
「ひどいやつ――お前なんか、大嫌いだ」
ルーファンスが勢いよく寝具から剣を引き抜き、殺されると思ったエフィミアは反射的に体を強張らせて目を閉じた。咄嗟に組んだ腕で顔を守る。
だが、いくら待ってもその剣が振り下ろされる気配がなかった。不審に思って恐る恐る目を開けば、ルーファンスは剣を振り上げたまま、ためらうように動きを止めていた。
エフィミアはなかば呆然とルーファンスを見た。彼の表情に、一瞬恐怖を忘れた。
ルーファンスは体を震わせると、荒々しく突き放す動作でエフィミアから離れた。そして混乱の中にある彼女をそのままに、無言で部屋を出た。
☫
部屋を出たルーファンスは急き立てられるような心地で、駆け足に廊下を進んだ。
彼を支えるものはなにもなく、踏み出す足も浮遊感に似た頼りなさを感じる。今にも床が崩れ落ちてしまいそうな錯覚に恐怖し、ルーファンスは足を速めた。
(……もう、いやだ)
人目を避けながら、ルーファンスはひたすらに駆けた。
(誰か……)
聞く者のない、心の叫び。
(誰か、誰か、誰かっ、誰かっ!)
呼べど叫べど助けは来ない。そんなことはとっくの昔に学習した。けれど心の悲鳴は止められなかった。もう幾度あげたか分からない、叫び。
(誰か、ぼくを……!)
ルーファンスは私室に駆け込むなり乱暴に扉を閉め、何者も入れまいとするように背中で扉を押さえた。終わりなく降り積もる不安と恐怖にうもれて、ひどく息苦しかった。
長い時をかけて体内に堆積した負の感情が、今にも皮膚を突き破って外にあふれ出しそうで、ルーファンスはそれを抑えるのに必死だった。
これまでもそうだった。思い通りにならない怒りから加害衝動にのまれると、それ以外なにも見えなくなる。そのときには思考は常より冴えている気さえするのに、自制が一切機能しなくなるのだ――父が生きていたときには、こんなことはなかった。
目の前の相手を傷つけないでいられない今の自分が、ルーファンスをさいなみ続けた父の姿と似ていると気づいてしまうと、冷静でなどいられなかった。
削がれる心さえもなくなってしまえば、負の感情を堰き止めるものもなくなり、きっと本当に自分を止められなくなる。
「うっ……」
ひどい胸焼けを感じ、ルーファンスは呻いてその場にうずくまった。気分の悪さに堪えきれず床に嘔吐する。
こうしてすぐに吐いてしまうから、ものを食べるのは好きではない。ただでさえ、食事はルーファンスにとって苦痛だ。
食事の席には必ず、熱い料理や肉を切る刃物がある。作法を間違えたり、テーブルクロスを汚してしまったりするルーファンスを、父は手の中のもので即座に罰することができるのだ。
父が亡くなって、やっと緊張せず食事ができるようになったと思った。それなのに、食べた分だけ吐き出してしまうようになってしまった。そのせいで、もともと細身だったルーファンスの体はさらに目に見えて痩せ始めていた。
吐いても吐いても、気分はよくならなかった。ただ息苦しく、口の中が苦く、喉が焼けて痛くなるだけだった。もう吐くものもなくなり、ルーファンスはさらに呻いた。全身の血の気がひいて、寒気がする。泣きたいほど辛いのに、泣き方を忘れてしまった。
(父上、ぼくはどうしたらいいのですか……父上が決めてくれないと、なにもできない……)
床にうずくまったまま、ルーファンスは思い通りにならない自分に唇を噛んだ。
「こんなところにお座りになって、どうかなさったのですか」
突然かけられた声に、ルーファンスは驚いて顔を上げた。いつ現れたのか、うずくまるルーファンスの正面に漆黒の占い師が立っていた。彼女は窺うように首を傾けた。
「ご気分がすぐれないのですか」
「……ヴィナ」
ルーファンスはゆっくり体を起こし、自分よりわずかに背の高い占い師の胸に縋りついた。ルーファンスには、これから彼がとるべき行動を示してくれる者が必要だった。
「ヴィナ、わたしはこれからどうしたらいい? もう分からない」
占い師の腕が、ルーファンスを包むように抱き締めた。
「なにも恐れることなどありません。わたしがいるのですから。あなたは自分の思うとおりにすればいいのです」
黒いローブの生地をにぎって、ルーファンスは弱々しく答えた。
「……できないよ。きっとまた誰かを傷つけてしまう。アレクスまで失ってしまった……今度はヴィナを傷つけてしまうかもしれない」
子供をなだめるように金糸の髪を撫でて、ヴィナは耳元で囁いた。
「大丈夫よ、自分を恐れないで。竜王の力さえ手に入れれば、すべて思い通りになるのだから」
ヴィナは掌でルーファンスの両頬を包み、仰向かせた。彼女の掌は肌にひやりとして感じられた。
「それがもうすぐ手に入る。あと少しの辛抱で、すべてがうまくいくのよ」
「でも、ヴィナ――」
「わたしの力を分けてあげる」
頬を包まれたまま引き寄せるように唇が重ねられる。
熱いものを呑み込んだような温度を喉に感じて、ルーファンスは驚いた。喉から胸に落ちていく熱さはエフィミアとの口づけで感じるものによく似ていて、ヴィナの正体への疑問が朧に浮かぶ。
しかしその疑問さえ溶け消えるほどの安らぎを、この口づけは彼にもたらした――始めから彼女の素性などルーファンスにはどうでもいいことだ。
誰のとり次ぎもなくヴィナが王の私室に現れたとき、ここで殺されるのだ、とルーファンスは思った。彼のことを殺したいほど邪魔に思っている人物の心当たりはある。
でも彼女はルーファンスを殺さなかった。彼の愚鈍さを嘲笑わず、否定せず、誰とも比べず、なにをしようと落胆を浮かべなかった。
それは、ルーファンスにとって素性などよりずっと価値を感じられた。後ろ暗い思惑があろうと懐柔の策だろうと、構わない思えるほどの。
ルーファンスは黒髪とフードに隠された頬と首筋に手を添えて、自らもヴィナの唇を求めた。もうずっと、これほどの安らぎを感じることはなく、だからこそひときわ強く欲しているものだった。まるでゆっくりと泥に沈んでいくようで、もう抜け出せそうにない。
ヴィナの黒いフードが滑り落ちた。それに気づいて、ルーファンスは口づけをしながら彼女の顔にかかる黒髪をそっと払いのけた。そうして初めて露わになったものに、ルーファンスは思わず唇を離して一歩下がった。
薄く笑みながらローブを脱ぎ捨てたヴィナの素顔に、ルーファンスの目は釘づけられた。
美しい女だった。豊満な胸の谷間をを惜しみなくさらした黒のドレスはまるで娼婦のようなのに、真っ直ぐな立ち姿はなぜか媚びのない上品さを漂わせていた。それでもやはり、高価な磁器ように白い胸元や首筋は多くの男を籠絡してきたろうと感じる。
その上に乗った、理想的な卵形を描く輪郭と潤む黒髪に縁どられた若い女の美貌。その中で目を引く、たった一つの違和感。
「恐れないで」
ゆっくりとした動作で、ヴィナはルーファンスの右手をとって顔に触れさせた。頬のひんやりとした顔からルーファンスが目を離せずにいると、ふと彼女の瞳と視線が合った。
その瞳は、ルーファンスの碧眼と同じ青い色をしていた。
ルーファンスより年上の、かつてはよほどの美しさをたたえていだろう女。それが、どういう経緯で今にいたったのかは分からない。ルーファンスはそこに、自分と近しいものを見出した気がした。
「痛い?」
間を置いてルーファンスが問えば、ヴィナの赤い唇が楽しげに弧を描いた。
「痛いわ。この痛みが消えたことはない。あなたと同じ」
彼女の頬に触れているルーファンスの右手を、ぐっと強くつかまれる。剣で裂いてからいまだ塞がらぬ掌の傷が疼き、ルーファンスはかすかに目蓋を震わせた。
「とてもよく分かるよ」
これは、裏切りと失望の痛みだ。
ルーファンスは一歩距離を詰め、今度は彼の方からヴィナと唇を重ねた。
☫
ルーファンスの消えた扉を、エフィミアはベッドの上に座り込んで呆然と見詰めた。彼が最後に見せた表情に、エフィミアはただ戸惑っていた――彼が、泣いていたのだ。
涙は出ていないから、正確には泣いていない。しかしエフィミアには彼が泣いているように、でなければ泣くのを必死で堪えているように見えた。
耐え切れないほど辛くて辛くてたまらないときに、人が見せる表情。それこそ涙が出ていない方が、むしろ不自然に思えるほどの。
ルーファンスが初めて見せたその顔が目に焼きついて離れず、エフィミアをますます戸惑わせていた。
「なんなの……?」
エフィミアにはルーファンスの心が見えなかった。彼は辛そうな顔をしてはいたが、幼馴染みであるアレクスを刺してしまったことを後悔しているという印象は受けなかった。
後悔かそれに似たものは感じているのかもしれない。けれどそれ以上のなにかが、彼の中にはある。エフィミアはそう感じた。
もう一度ルーファンスと話せば、なにかの正体が分かるだろうかと確信なく思いながら、エフィミアはゆっくりと扉から窓の外へと視線を移した。そこでは薄く雲のかかった三日月が儚く輝き、部屋の窓を見下ろしていた。
(アレクス、どうか生きていて……)
次の日の夜、エフィミアはルーファンスがやってくるのを待ったが、彼が部屋に現れることはなかった。
垂れて乱れた極細の金髪に隠されて、表情は見えない。合間に覗く淡い碧眼だけが異様に輝いて見えた。
ルーファンスがゆっくりと足を踏み出し、エフィミアは這うように後ずさった。いつものように、悪意に満ちた気配。しかしこれまでのものとはどことなく質が違った。
悪意よりももっと強い、より純度の高い、殺意。確かな質量を持ったそれがエフィミアの体にまとわりつき、じわじわと心臓を締め上げる。
エフィミアはしばらくルーファンスを見詰めていたが、堪えきれずに体を起こし部屋の奥に向かって駆け出した。素早く反応したルーファンスがすぐ背後に迫り、刃が振り下ろされるのを感じた。
背を撫でられる感触がして、切っ先が乗馬服の上着を裂いてシャツを掠めたのが分かった。刃を躱して逃げるも、閉じられた室内ではすぐに壁に行き当たってしまう。エフィミアは壁を伝い、家具を乗り越え、振り下ろされる刃から必死に逃げた。
ルーファンスはなり振り構わず剣を振り回し、エフィミアに向かって切りかかった。カーテンが裂け、クッションの詰め物が散った。床に、壁に、調度に、鋭く傷が刻まれる。
何度も短い悲鳴をあげながら逃げ惑うエフィミアを、ルーファンスは無表情のまま執拗に追いかけ、刃を向けた。彼が刃を振るうたびに、そこについている紅いしずくが散って宙に軌跡を描いた。
銀の刃が頬をかすめて走り抜け、ベッドを乗り越えようとしたエフィミアは思わず動きを止めた。そのまま引き倒され、顔のすぐ横に剣が突き立てられる。剣の切っ先はいとも容易く寝具を刺しつらぬき、エフィミアは戦慄して、見下ろすルーファンスを見詰めた。
恐怖心を煽るのに十分な沈黙のあと、ルーファンスの口がかすかに動いた。
「……どうして」
ルーファンスの声に抑揚はなく、顔には感情の読めない無表情を貼りつかせていた。今までにない彼のようすに、エフィミアは恐れ戸惑った。
「どうして取るの。君はなんでも持っているのに。わたしの欲しいもの全部を持っているのに――それなのに、なんでわたしから取るの? わたしにはなにもないのに……」
かすかに震える声でルーファンスは囁き、瞳の輝きが増した。
「ひどいやつ――お前なんか、大嫌いだ」
ルーファンスが勢いよく寝具から剣を引き抜き、殺されると思ったエフィミアは反射的に体を強張らせて目を閉じた。咄嗟に組んだ腕で顔を守る。
だが、いくら待ってもその剣が振り下ろされる気配がなかった。不審に思って恐る恐る目を開けば、ルーファンスは剣を振り上げたまま、ためらうように動きを止めていた。
エフィミアはなかば呆然とルーファンスを見た。彼の表情に、一瞬恐怖を忘れた。
ルーファンスは体を震わせると、荒々しく突き放す動作でエフィミアから離れた。そして混乱の中にある彼女をそのままに、無言で部屋を出た。
☫
部屋を出たルーファンスは急き立てられるような心地で、駆け足に廊下を進んだ。
彼を支えるものはなにもなく、踏み出す足も浮遊感に似た頼りなさを感じる。今にも床が崩れ落ちてしまいそうな錯覚に恐怖し、ルーファンスは足を速めた。
(……もう、いやだ)
人目を避けながら、ルーファンスはひたすらに駆けた。
(誰か……)
聞く者のない、心の叫び。
(誰か、誰か、誰かっ、誰かっ!)
呼べど叫べど助けは来ない。そんなことはとっくの昔に学習した。けれど心の悲鳴は止められなかった。もう幾度あげたか分からない、叫び。
(誰か、ぼくを……!)
ルーファンスは私室に駆け込むなり乱暴に扉を閉め、何者も入れまいとするように背中で扉を押さえた。終わりなく降り積もる不安と恐怖にうもれて、ひどく息苦しかった。
長い時をかけて体内に堆積した負の感情が、今にも皮膚を突き破って外にあふれ出しそうで、ルーファンスはそれを抑えるのに必死だった。
これまでもそうだった。思い通りにならない怒りから加害衝動にのまれると、それ以外なにも見えなくなる。そのときには思考は常より冴えている気さえするのに、自制が一切機能しなくなるのだ――父が生きていたときには、こんなことはなかった。
目の前の相手を傷つけないでいられない今の自分が、ルーファンスをさいなみ続けた父の姿と似ていると気づいてしまうと、冷静でなどいられなかった。
削がれる心さえもなくなってしまえば、負の感情を堰き止めるものもなくなり、きっと本当に自分を止められなくなる。
「うっ……」
ひどい胸焼けを感じ、ルーファンスは呻いてその場にうずくまった。気分の悪さに堪えきれず床に嘔吐する。
こうしてすぐに吐いてしまうから、ものを食べるのは好きではない。ただでさえ、食事はルーファンスにとって苦痛だ。
食事の席には必ず、熱い料理や肉を切る刃物がある。作法を間違えたり、テーブルクロスを汚してしまったりするルーファンスを、父は手の中のもので即座に罰することができるのだ。
父が亡くなって、やっと緊張せず食事ができるようになったと思った。それなのに、食べた分だけ吐き出してしまうようになってしまった。そのせいで、もともと細身だったルーファンスの体はさらに目に見えて痩せ始めていた。
吐いても吐いても、気分はよくならなかった。ただ息苦しく、口の中が苦く、喉が焼けて痛くなるだけだった。もう吐くものもなくなり、ルーファンスはさらに呻いた。全身の血の気がひいて、寒気がする。泣きたいほど辛いのに、泣き方を忘れてしまった。
(父上、ぼくはどうしたらいいのですか……父上が決めてくれないと、なにもできない……)
床にうずくまったまま、ルーファンスは思い通りにならない自分に唇を噛んだ。
「こんなところにお座りになって、どうかなさったのですか」
突然かけられた声に、ルーファンスは驚いて顔を上げた。いつ現れたのか、うずくまるルーファンスの正面に漆黒の占い師が立っていた。彼女は窺うように首を傾けた。
「ご気分がすぐれないのですか」
「……ヴィナ」
ルーファンスはゆっくり体を起こし、自分よりわずかに背の高い占い師の胸に縋りついた。ルーファンスには、これから彼がとるべき行動を示してくれる者が必要だった。
「ヴィナ、わたしはこれからどうしたらいい? もう分からない」
占い師の腕が、ルーファンスを包むように抱き締めた。
「なにも恐れることなどありません。わたしがいるのですから。あなたは自分の思うとおりにすればいいのです」
黒いローブの生地をにぎって、ルーファンスは弱々しく答えた。
「……できないよ。きっとまた誰かを傷つけてしまう。アレクスまで失ってしまった……今度はヴィナを傷つけてしまうかもしれない」
子供をなだめるように金糸の髪を撫でて、ヴィナは耳元で囁いた。
「大丈夫よ、自分を恐れないで。竜王の力さえ手に入れれば、すべて思い通りになるのだから」
ヴィナは掌でルーファンスの両頬を包み、仰向かせた。彼女の掌は肌にひやりとして感じられた。
「それがもうすぐ手に入る。あと少しの辛抱で、すべてがうまくいくのよ」
「でも、ヴィナ――」
「わたしの力を分けてあげる」
頬を包まれたまま引き寄せるように唇が重ねられる。
熱いものを呑み込んだような温度を喉に感じて、ルーファンスは驚いた。喉から胸に落ちていく熱さはエフィミアとの口づけで感じるものによく似ていて、ヴィナの正体への疑問が朧に浮かぶ。
しかしその疑問さえ溶け消えるほどの安らぎを、この口づけは彼にもたらした――始めから彼女の素性などルーファンスにはどうでもいいことだ。
誰のとり次ぎもなくヴィナが王の私室に現れたとき、ここで殺されるのだ、とルーファンスは思った。彼のことを殺したいほど邪魔に思っている人物の心当たりはある。
でも彼女はルーファンスを殺さなかった。彼の愚鈍さを嘲笑わず、否定せず、誰とも比べず、なにをしようと落胆を浮かべなかった。
それは、ルーファンスにとって素性などよりずっと価値を感じられた。後ろ暗い思惑があろうと懐柔の策だろうと、構わない思えるほどの。
ルーファンスは黒髪とフードに隠された頬と首筋に手を添えて、自らもヴィナの唇を求めた。もうずっと、これほどの安らぎを感じることはなく、だからこそひときわ強く欲しているものだった。まるでゆっくりと泥に沈んでいくようで、もう抜け出せそうにない。
ヴィナの黒いフードが滑り落ちた。それに気づいて、ルーファンスは口づけをしながら彼女の顔にかかる黒髪をそっと払いのけた。そうして初めて露わになったものに、ルーファンスは思わず唇を離して一歩下がった。
薄く笑みながらローブを脱ぎ捨てたヴィナの素顔に、ルーファンスの目は釘づけられた。
美しい女だった。豊満な胸の谷間をを惜しみなくさらした黒のドレスはまるで娼婦のようなのに、真っ直ぐな立ち姿はなぜか媚びのない上品さを漂わせていた。それでもやはり、高価な磁器ように白い胸元や首筋は多くの男を籠絡してきたろうと感じる。
その上に乗った、理想的な卵形を描く輪郭と潤む黒髪に縁どられた若い女の美貌。その中で目を引く、たった一つの違和感。
「恐れないで」
ゆっくりとした動作で、ヴィナはルーファンスの右手をとって顔に触れさせた。頬のひんやりとした顔からルーファンスが目を離せずにいると、ふと彼女の瞳と視線が合った。
その瞳は、ルーファンスの碧眼と同じ青い色をしていた。
ルーファンスより年上の、かつてはよほどの美しさをたたえていだろう女。それが、どういう経緯で今にいたったのかは分からない。ルーファンスはそこに、自分と近しいものを見出した気がした。
「痛い?」
間を置いてルーファンスが問えば、ヴィナの赤い唇が楽しげに弧を描いた。
「痛いわ。この痛みが消えたことはない。あなたと同じ」
彼女の頬に触れているルーファンスの右手を、ぐっと強くつかまれる。剣で裂いてからいまだ塞がらぬ掌の傷が疼き、ルーファンスはかすかに目蓋を震わせた。
「とてもよく分かるよ」
これは、裏切りと失望の痛みだ。
ルーファンスは一歩距離を詰め、今度は彼の方からヴィナと唇を重ねた。
☫
ルーファンスの消えた扉を、エフィミアはベッドの上に座り込んで呆然と見詰めた。彼が最後に見せた表情に、エフィミアはただ戸惑っていた――彼が、泣いていたのだ。
涙は出ていないから、正確には泣いていない。しかしエフィミアには彼が泣いているように、でなければ泣くのを必死で堪えているように見えた。
耐え切れないほど辛くて辛くてたまらないときに、人が見せる表情。それこそ涙が出ていない方が、むしろ不自然に思えるほどの。
ルーファンスが初めて見せたその顔が目に焼きついて離れず、エフィミアをますます戸惑わせていた。
「なんなの……?」
エフィミアにはルーファンスの心が見えなかった。彼は辛そうな顔をしてはいたが、幼馴染みであるアレクスを刺してしまったことを後悔しているという印象は受けなかった。
後悔かそれに似たものは感じているのかもしれない。けれどそれ以上のなにかが、彼の中にはある。エフィミアはそう感じた。
もう一度ルーファンスと話せば、なにかの正体が分かるだろうかと確信なく思いながら、エフィミアはゆっくりと扉から窓の外へと視線を移した。そこでは薄く雲のかかった三日月が儚く輝き、部屋の窓を見下ろしていた。
(アレクス、どうか生きていて……)
次の日の夜、エフィミアはルーファンスがやってくるのを待ったが、彼が部屋に現れることはなかった。
0
あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました
大江戸ウメコ
恋愛
幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!
藤原ライラ
恋愛
ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。
ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。
解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。
「君は、おれに、一体何をくれる?」
呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?
強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。
※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~
双真満月
恋愛
不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。
なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。
※小説家になろうでも掲載中。
※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。
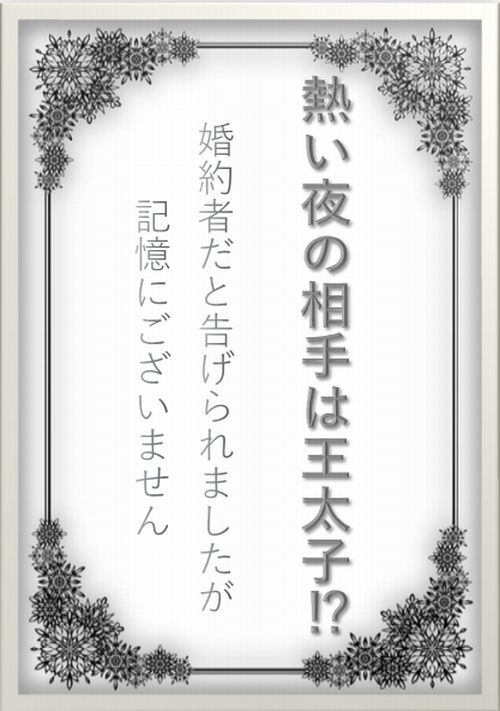
【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~
世界のボボブラ汁(エロル)
恋愛
激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。
──え……この方、誰?
相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。
けれど私は、自分の名前すら思い出せない。
訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。
「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」
……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?
しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。
もしかして、そのせいで私は命を狙われている?
公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。
全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!
※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟
飴爽かに
恋愛
この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。
彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。
クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。
悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~
花虎
恋愛
魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。
だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。
エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。
そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。
「やっと、あなたに復讐できる」
歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。
彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。
過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。
※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~
二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中
恋愛
政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。
彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。
そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。
幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。
そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















