49 / 61
第5章 竜の王国
1 想望
しおりを挟む
――出して……。
出して、出してください。ここは、いやだ……。
なにも見えない暗闇の中で、彼は泣いていた。
視界は闇の支配下で、ここがどんな場所で自分がどちらを向いているのかも分からなかった。水の流れる音が見えない壁に反響して響き渡り、深く暗い水底に沈んでいくような錯覚におちいる。足元から冷気が遠慮なく這い上がってきて、体の震えが止まらなかった。
闇の中で、時間の感覚はなかった。ここに入れられて、まだ何分も経ってないのか、もう何日も経ったのか。ひたすらに冷たい闇だけが、体の内外に滞る。
闇の虚空に響く自分の声が恐くて、彼は息を殺した。暗闇は彼に嫌な想像ばかりを掻き立てさせた。圧倒的な気配と存在感を持って、闇がうごめき出す。意味がないと分かっていても、彼はぐっと目を閉じた。
(もうやだよ。ぼくを許して、父上……)
暗く冷たく恐ろしい孤独の底で、幼い彼は泣いていた。
☫
高い位置に並ぶ窓から、早朝独特の冷え冷えとした白い光が差し込んでいた。室内を彩る金銀の装飾がその光を受けて淡く輝いている。
広間の最奧の一段高くなったところに、ひときわ贅を凝らした玉座が差し込む陽光に照らし出されていた。玉座の後ろの壁にはドラディア王家の紋章である、広げた竜の両翼が繊細に刺繍された大きなタペストリーが掲げられている。
座面に臙脂色のビロードが張られた、金の玉座。王の権威の象徴であるそれは、今はルーファンスのものだ。しかし彼はそれに座ることなく、ただ壇の下から感情のこもらない瞳で見詰めていた。
ドラディアの王祖は竜に乗って天より出でて、この地に降り立ったという。だから竜王の力を得れば、愚かな自分でもその王祖に近づけるかもしれないと思った。それも、今ではどうでもいい気がした。
冷えた空気と静寂が、広大な広間を隅々まで満たしている。今、この謁見の間にいるのは、ルーファンスだけだった。
ここに来るたびに、ルーファンスは先王である父を思い出す。
先王は、民にとって最良の王だった。実りが少ない北方の民に家畜を与え、飢饉には惜しむことなく国庫を開き、家のない民のための施設を街に作り、彼らに仕事を与えた。長雨でローラ川が決壊したときにも、彼の迅速で的確な裁量によって犠牲者は出なかった。またときには任せることも知っていた彼は、臣からの信頼も厚かった。
そんな父王がルーファンスは誇らしかった。ルーファンスは父王のようになりたいと思い、父王もそれを望んでいた。しかしその望みに、ルーファンスの器量が追いつかなかった。
ルーファンスの成長とともにそれに気づき、苛立つ父が恐かった。父の期待に応えられない自分を、ルーファンスは呪った。
なにか失敗をするたびに、なぜできないのかと殴られた。痛みに泣けば、泣くなと言ってまた殴られた。それでも次期王かと、そんなことで王が務まるものかと責める声が、幾度となく幼いルーファンスに浴びせられた。
馬から落ちて怪我をすれば、お前の王家としての威厳が足りないのだと言われ、与えられた計算式の問題を苦労の末に解けたと報告すれば、時間がかかりすぎだと叱られた。臣たちもルーファンスの器量を測っては、愚鈍で気弱な王太子にため息をついた。
そんな中で幼馴染みの少年だけが、焦ることはないと言ってくれた。ルーファンスは次第に、彼以外の者に愛情を求めることをしなくなった。その彼も、ルーファンスは失ってしまった。
ヴィナに導かれた過日の情交で、ルーファンスは射精まで至れなかった。すでに二度出したあとであったから、もう吐き出せるものがなかっただけかもしれない。それでもあの夜で、ルーファンスの中にあるなにもかもが尽きてしまったと感じた。
玉座を見詰めたまま、ルーファンスは小さく唇を噛んだ。
「たまには、かけられてはどうかな」
突然かけられた声にルーファンスは驚いたが、顔に出すことなくゆっくりと背後を振り返った。
入口の大扉から少し進んだ位置に、暗色の服を着た長身の男が立っていた。その口元に浮かぶ薄い微笑を見て、ルーファンスはわずかに目を細めた。
大扉から真っ直ぐ玉座の壇上まで敷かれた毛足の長い絨毯が足音を消し、物思いにふけっていたルーファンスは彼の接近に気づけなかった。サーランド公爵はゆっくりとルーファンスに歩み寄ってきた。
「なぜかけない。それはあなたの椅子だろうに。即位の日以来、一度も掛けていないのではないか?」
ルーファンスは答えず、歩み寄ってくる公爵を無言で見詰めた。
この叔父のことが、ルーファンスは昔から苦手だった。自身以外の何者も人とは思っていないような彼の目が、どうしても好きになれない。
ルーファンスと数歩の距離を取って立ち止まると、長身の公爵は無遠慮に見下ろしてきた。王と相対しているとは思えない明らかな不敬だったが、いつものことなのでルーファンスは気にしなかった。
向かい合ったまま一向に反応しないルーファンスに、サーランド公爵はふっと吐息を混ぜて笑った。
「白竜に逃げられたそうだな」
ルーファンスはなにも言わなかった。実際、白竜を逃がした件だけならそれほど動揺しているわけでもない。問題はその先だった。
「騎竜隊長も先日から行方が分からぬと聞いたが?」
やはりきたかと、ルーファンスは思った。公爵はそういう人物だ。動揺を悟られぬよう、ルーファンスは口をつぐみ続けた。公爵はそれを見透かすように目を細めた。
「とうとう、頼りのアレクスにも見捨てられたか」
いかにもいやみな公爵から目をそらし、ようやくルーファンスは小声で呟いた。
「そうかもね。わたしはたくさん悪いことをしたから」
ルーファンスは横目に、誰も座っていない玉座を見やった。
「わたしは王になってはいけなかったんだ」
「そう思うのであれば、わたしにその座を譲ってはどうだ」
軽蔑の視線をよこす公爵にルーファンスは向き直り、低めた声で、しかしはっきりと言った。
「いやだ」
ルーファンスの拒絶の言葉に、公爵はさらに目を細くした。
「お前は自分が王に向いていないと思っているのだろう? ならばわたしに譲ればそんなことを思わずにすみ、すべて収まる。なにが気に入らない」
ルーファンスはじっと公爵の目を見据えた。
「あなただからいやなんだ。あなたは優れた王だった父上を殺した」
公爵は興味深そうに眉を開いた。
「面白い話だ。証拠があるか?」
黙って上着の隠しに手を入れると、ルーファンスは片手で握り込めるほど小さな瓶を取り出した。コルクでしっかりと蓋のされたその中には、白っぽい色の粉が四分の一程度入っていた。かすかに公爵の頬が強張るのを見てから、ルーファンスは抑えた声音で言った。
「父上が死んだあと、これを見つけたんだ。あなたはこれで父上を殺した。眠っている間に少しずつ吸い込むように枕に仕込んで。毒を体に蓄積させて、病気に見せかけて殺したんだ。協力した従僕の言質はとれている――もう彼はいないけれど」
うっすらと、ルーファンスは口角を持ち上げた。
「あなたに王位はあげない。本当はわたしも殺すつもりだったのでしょう? わたしの身辺は他ならぬ父上が誰よりも厳しく目配りしていたから、簡単にはいかなかっただけだ」
つかの間二人は睨みあったが、サーランド公爵はすぐにルーファンスから顔をそむけた。
「証人もいないような証拠、話しにならんな」
吐き捨てるように言って公爵はルーファンスに背中を向けると、出入り口の大扉に向かって歩き出した。ルーファンスは公爵を呼び止めることもなく、ただじっとその背中を見据えた。
公爵が広間のなかばを過ぎたころ、ルーファンスは手の中の小瓶を無言で仕舞った。
離れていこうとする公爵の背中に音もなく迫る。あと一歩で公爵に届く位置で、腰に帯びた剣を鞘から引き抜く。そこでようやく、公爵は背後に迫った気配に気づいて振り返ったが、もう遅かった。ルーファンスの剣は、彼の体を貫いた。
呻き声を聞きながら、ルーファンスは剣をそのまま横に薙いだ。肉を切る感触と臓器がつぶれる感触が柄から掌に伝わり、えぐるように胴が裂けた。公爵は声にならない絶叫をほとばしると、ルーファンスに寄りかかるようにくずおれ、ほどなく息を引き取った。
公爵があっけなく絶命したのを確認すると、ルーファンスはその場にへたり込んだ。ズボンに生暖かい血が染み込んできたが、気にならなかったし、どうでもいいと思った。
実の叔父の死体を前にしているのに、不思議なくらいなにも感じない。身内を手にかけてしまった悲しみも、父の敵をとったという喜びも心には浮かばず、ただ、ああ死んだなと思った。
ルーファンスはゆっくりと、高い天井を仰いだ。
(父上、ぼくは父上のようにはなれない……)
うつむき、父からのたったひとつの贈り物でもある、血塗れた剣を抱き締めた。
(誰か……お願い、誰でもいいから。誰か、ぼくを……。アレクス……)
「早く、来て」
出して、出してください。ここは、いやだ……。
なにも見えない暗闇の中で、彼は泣いていた。
視界は闇の支配下で、ここがどんな場所で自分がどちらを向いているのかも分からなかった。水の流れる音が見えない壁に反響して響き渡り、深く暗い水底に沈んでいくような錯覚におちいる。足元から冷気が遠慮なく這い上がってきて、体の震えが止まらなかった。
闇の中で、時間の感覚はなかった。ここに入れられて、まだ何分も経ってないのか、もう何日も経ったのか。ひたすらに冷たい闇だけが、体の内外に滞る。
闇の虚空に響く自分の声が恐くて、彼は息を殺した。暗闇は彼に嫌な想像ばかりを掻き立てさせた。圧倒的な気配と存在感を持って、闇がうごめき出す。意味がないと分かっていても、彼はぐっと目を閉じた。
(もうやだよ。ぼくを許して、父上……)
暗く冷たく恐ろしい孤独の底で、幼い彼は泣いていた。
☫
高い位置に並ぶ窓から、早朝独特の冷え冷えとした白い光が差し込んでいた。室内を彩る金銀の装飾がその光を受けて淡く輝いている。
広間の最奧の一段高くなったところに、ひときわ贅を凝らした玉座が差し込む陽光に照らし出されていた。玉座の後ろの壁にはドラディア王家の紋章である、広げた竜の両翼が繊細に刺繍された大きなタペストリーが掲げられている。
座面に臙脂色のビロードが張られた、金の玉座。王の権威の象徴であるそれは、今はルーファンスのものだ。しかし彼はそれに座ることなく、ただ壇の下から感情のこもらない瞳で見詰めていた。
ドラディアの王祖は竜に乗って天より出でて、この地に降り立ったという。だから竜王の力を得れば、愚かな自分でもその王祖に近づけるかもしれないと思った。それも、今ではどうでもいい気がした。
冷えた空気と静寂が、広大な広間を隅々まで満たしている。今、この謁見の間にいるのは、ルーファンスだけだった。
ここに来るたびに、ルーファンスは先王である父を思い出す。
先王は、民にとって最良の王だった。実りが少ない北方の民に家畜を与え、飢饉には惜しむことなく国庫を開き、家のない民のための施設を街に作り、彼らに仕事を与えた。長雨でローラ川が決壊したときにも、彼の迅速で的確な裁量によって犠牲者は出なかった。またときには任せることも知っていた彼は、臣からの信頼も厚かった。
そんな父王がルーファンスは誇らしかった。ルーファンスは父王のようになりたいと思い、父王もそれを望んでいた。しかしその望みに、ルーファンスの器量が追いつかなかった。
ルーファンスの成長とともにそれに気づき、苛立つ父が恐かった。父の期待に応えられない自分を、ルーファンスは呪った。
なにか失敗をするたびに、なぜできないのかと殴られた。痛みに泣けば、泣くなと言ってまた殴られた。それでも次期王かと、そんなことで王が務まるものかと責める声が、幾度となく幼いルーファンスに浴びせられた。
馬から落ちて怪我をすれば、お前の王家としての威厳が足りないのだと言われ、与えられた計算式の問題を苦労の末に解けたと報告すれば、時間がかかりすぎだと叱られた。臣たちもルーファンスの器量を測っては、愚鈍で気弱な王太子にため息をついた。
そんな中で幼馴染みの少年だけが、焦ることはないと言ってくれた。ルーファンスは次第に、彼以外の者に愛情を求めることをしなくなった。その彼も、ルーファンスは失ってしまった。
ヴィナに導かれた過日の情交で、ルーファンスは射精まで至れなかった。すでに二度出したあとであったから、もう吐き出せるものがなかっただけかもしれない。それでもあの夜で、ルーファンスの中にあるなにもかもが尽きてしまったと感じた。
玉座を見詰めたまま、ルーファンスは小さく唇を噛んだ。
「たまには、かけられてはどうかな」
突然かけられた声にルーファンスは驚いたが、顔に出すことなくゆっくりと背後を振り返った。
入口の大扉から少し進んだ位置に、暗色の服を着た長身の男が立っていた。その口元に浮かぶ薄い微笑を見て、ルーファンスはわずかに目を細めた。
大扉から真っ直ぐ玉座の壇上まで敷かれた毛足の長い絨毯が足音を消し、物思いにふけっていたルーファンスは彼の接近に気づけなかった。サーランド公爵はゆっくりとルーファンスに歩み寄ってきた。
「なぜかけない。それはあなたの椅子だろうに。即位の日以来、一度も掛けていないのではないか?」
ルーファンスは答えず、歩み寄ってくる公爵を無言で見詰めた。
この叔父のことが、ルーファンスは昔から苦手だった。自身以外の何者も人とは思っていないような彼の目が、どうしても好きになれない。
ルーファンスと数歩の距離を取って立ち止まると、長身の公爵は無遠慮に見下ろしてきた。王と相対しているとは思えない明らかな不敬だったが、いつものことなのでルーファンスは気にしなかった。
向かい合ったまま一向に反応しないルーファンスに、サーランド公爵はふっと吐息を混ぜて笑った。
「白竜に逃げられたそうだな」
ルーファンスはなにも言わなかった。実際、白竜を逃がした件だけならそれほど動揺しているわけでもない。問題はその先だった。
「騎竜隊長も先日から行方が分からぬと聞いたが?」
やはりきたかと、ルーファンスは思った。公爵はそういう人物だ。動揺を悟られぬよう、ルーファンスは口をつぐみ続けた。公爵はそれを見透かすように目を細めた。
「とうとう、頼りのアレクスにも見捨てられたか」
いかにもいやみな公爵から目をそらし、ようやくルーファンスは小声で呟いた。
「そうかもね。わたしはたくさん悪いことをしたから」
ルーファンスは横目に、誰も座っていない玉座を見やった。
「わたしは王になってはいけなかったんだ」
「そう思うのであれば、わたしにその座を譲ってはどうだ」
軽蔑の視線をよこす公爵にルーファンスは向き直り、低めた声で、しかしはっきりと言った。
「いやだ」
ルーファンスの拒絶の言葉に、公爵はさらに目を細くした。
「お前は自分が王に向いていないと思っているのだろう? ならばわたしに譲ればそんなことを思わずにすみ、すべて収まる。なにが気に入らない」
ルーファンスはじっと公爵の目を見据えた。
「あなただからいやなんだ。あなたは優れた王だった父上を殺した」
公爵は興味深そうに眉を開いた。
「面白い話だ。証拠があるか?」
黙って上着の隠しに手を入れると、ルーファンスは片手で握り込めるほど小さな瓶を取り出した。コルクでしっかりと蓋のされたその中には、白っぽい色の粉が四分の一程度入っていた。かすかに公爵の頬が強張るのを見てから、ルーファンスは抑えた声音で言った。
「父上が死んだあと、これを見つけたんだ。あなたはこれで父上を殺した。眠っている間に少しずつ吸い込むように枕に仕込んで。毒を体に蓄積させて、病気に見せかけて殺したんだ。協力した従僕の言質はとれている――もう彼はいないけれど」
うっすらと、ルーファンスは口角を持ち上げた。
「あなたに王位はあげない。本当はわたしも殺すつもりだったのでしょう? わたしの身辺は他ならぬ父上が誰よりも厳しく目配りしていたから、簡単にはいかなかっただけだ」
つかの間二人は睨みあったが、サーランド公爵はすぐにルーファンスから顔をそむけた。
「証人もいないような証拠、話しにならんな」
吐き捨てるように言って公爵はルーファンスに背中を向けると、出入り口の大扉に向かって歩き出した。ルーファンスは公爵を呼び止めることもなく、ただじっとその背中を見据えた。
公爵が広間のなかばを過ぎたころ、ルーファンスは手の中の小瓶を無言で仕舞った。
離れていこうとする公爵の背中に音もなく迫る。あと一歩で公爵に届く位置で、腰に帯びた剣を鞘から引き抜く。そこでようやく、公爵は背後に迫った気配に気づいて振り返ったが、もう遅かった。ルーファンスの剣は、彼の体を貫いた。
呻き声を聞きながら、ルーファンスは剣をそのまま横に薙いだ。肉を切る感触と臓器がつぶれる感触が柄から掌に伝わり、えぐるように胴が裂けた。公爵は声にならない絶叫をほとばしると、ルーファンスに寄りかかるようにくずおれ、ほどなく息を引き取った。
公爵があっけなく絶命したのを確認すると、ルーファンスはその場にへたり込んだ。ズボンに生暖かい血が染み込んできたが、気にならなかったし、どうでもいいと思った。
実の叔父の死体を前にしているのに、不思議なくらいなにも感じない。身内を手にかけてしまった悲しみも、父の敵をとったという喜びも心には浮かばず、ただ、ああ死んだなと思った。
ルーファンスはゆっくりと、高い天井を仰いだ。
(父上、ぼくは父上のようにはなれない……)
うつむき、父からのたったひとつの贈り物でもある、血塗れた剣を抱き締めた。
(誰か……お願い、誰でもいいから。誰か、ぼくを……。アレクス……)
「早く、来て」
0
あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました
大江戸ウメコ
恋愛
幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!
藤原ライラ
恋愛
ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。
ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。
解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。
「君は、おれに、一体何をくれる?」
呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?
強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。
※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~
双真満月
恋愛
不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。
なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。
※小説家になろうでも掲載中。
※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。
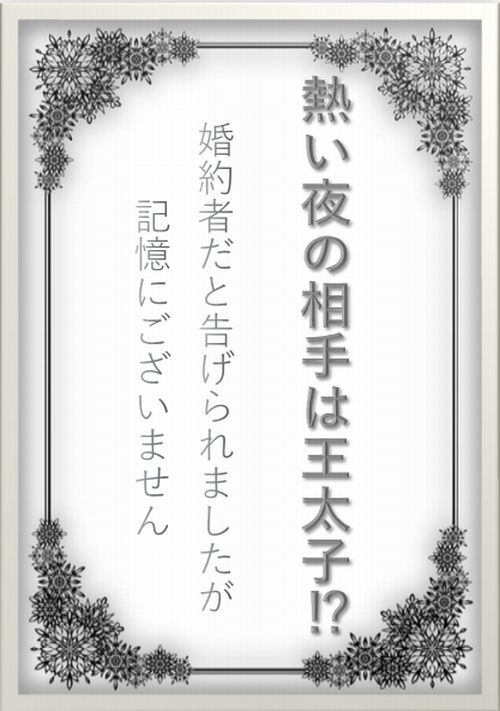
【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~
世界のボボブラ汁(エロル)
恋愛
激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。
──え……この方、誰?
相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。
けれど私は、自分の名前すら思い出せない。
訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。
「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」
……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?
しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。
もしかして、そのせいで私は命を狙われている?
公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。
全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!
※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟
飴爽かに
恋愛
この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。
彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。
クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。
悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~
花虎
恋愛
魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。
だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。
エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。
そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。
「やっと、あなたに復讐できる」
歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。
彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。
過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。
※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~
二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中
恋愛
政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。
彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。
そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。
幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。
そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















