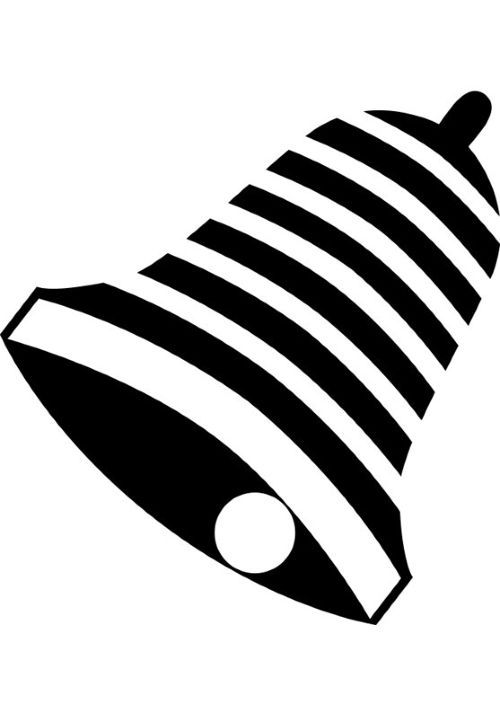6 / 6
遠い遠い西の果てブハイルの湖にて(6)
しおりを挟む9・ 薄闇
全く同じ時。カティルは夜闇の中を夢中で馬を駆る。
(急げっ)
ついに前方にブハイル湖が見えてくる。対岸はるか遠くに雲間の月光を受けて、湖に付き出したアルアシオン城の輪郭が僅かに浮かんでいる。彼は水際の小石混ざりの泥に、全力で馬を走らせる。それでも足りないと焦る。夜闇を嫌がって脚を鈍らせる馬を必死で駆る。
つい先ほどアール城で見た光景が頭にこびりついて消えない。鮮烈な映像は彼を焦らせる。相手の力を甘く見ていたことに歯ぎしりすら覚える。
そうだ、なぜこれで充分だと思ってしまったのだろう。あの猫を、ただ城内の一室に閉じ込めただけで充分と思ったなんて。確かに自分の読みが甘かった。甘すぎた。でも、まさか。
まさか、扉に火を点けて破るなど!
……黒く焦げ一部を壊された木扉を見ながら、冷徹の質のはずのアール城主が唖然の顔をさらした。
「ここまでをやるのか――ナガのラディンは?」
配された食事の油と、燭台の火を用いた。勿論その程度の火では木扉は燃えない。扉を破る道具など何もない。両掌で力づくでひたすらに打ち続けたはずだ。凄まじい苦痛と大怪我を覚悟で、それでも扉を燃やした上で叩き、蹴り、体当たりをし続けたのだ。その執念に唖然と息を飲んだ。
「これなら相当の怪我を負っているはずだぞ、まだ城内に潜んでいるはずだ」
アールの言葉に一度は納得し、城内を必死で探し続け、しかし見つからず、時間だけが進み、そして――。
はっとカティルは気付いた。
“奴ならば、絶対にそんな事はしない”
なぜ気付かなかった。奴なら決して、城内に潜んで夜を待つなんてそんな慎重な常道は取らない。そんな暇が有ったらとっくに走り出している。怪我の痛みなど無視して走り出しているはずなんだ。あの凄まじい猫ならばっ。
なぜ気付かなかった、なぜ時間を無駄にしてしまった!
判断失敗を後悔しても遅い。時間は戻らない。急げ、とにかく急げっ。
アルアシオン城の輪郭が黒く、僅かに夜闇に浮かび上がっている。その上部にたった一つだけ、小さな光が漏れている。その頼りない光が、カティルの背筋に極めて現実的な恐怖を生じさせる。
(急げっ、ハンシス――ラディン!)
ラディンもまた、闇の通廊を走る。
通廊に一つだけぽつりと灯されていた燭台を血のにじむ手で掴み、その灯りで階段を走り登る。闇の角ごとに警戒を払う。武装した衛兵が自分に飛び掛かってくる危険に、最大限の警戒を払う。
彼は知らないのだ。今この城内には、探し求める二人以外には、先程閉じ込めた男と、後は寝汚い料理番の夫婦と雑務の男二人しかいないと知らないのだ。だから彼はこれ以上無い警戒を剥きだしながら進む。両掌を中心に体の内外を苛む痛みを無視しながら城内の通廊を走り進む。
ちらりと一瞬だけ、明り取り窓から外を見た。雲間に月が光っていた。先ほど泳いだブハイル湖の湖面が黒く浮かび上がっていた。
……夜警に気付かれずに城壁を超えるには、湖側しかない。日没直後の薄光の中で城の全景を見た時、瞬時でそう判断した。判断した以上、躊躇は無かった。水の冷たさに溺れるのではとの恐怖など意識すらせずに湖に入った。
その時の事をよく思い出せない。おそらく、水は刃物のように冷たく体を苛んだはずだ。だが寒さを感覚しなかった。ただ漠然と、体が上手く動かないと思っただけだった。聖天使の御加護により手足の感覚が消える前に泳ぎ切れたが、水から上がった最初の一歩、足が動かなくて大きく転んだことだけは、妙に明確に覚えていた。
次は、湖水に洗われる城壁の基部に足をかける。壁を掴んだ最初の瞬間だけ、傷だらけの掌の激痛に短く悲鳴し た。だが、あとはもう感じない。ただ、登る。なぜなら、登らないとシャダーに会えないから。
コルムとの戦役が始まった時から、シャダーに会っていない。会いたい。とにかく会いたい。
そして、あの男。会いたい。全ての質において自分を上回る男。自分と同じくシャダーを求め、自分とシャダーの間に割り込んだ男。あの男にも会いたい。会わないと、先に進めない。
燭台を握る左手が血と体液と苦痛に塗れているのに気づいた。閉じ込められた部屋の扉に苦心の末に火を点け、死に物狂いで蹴り続け、煙を吸い、叩き続け、手の皮が剥け、手の皮を切り、それでも叩き続けた掌の様を、初めて意識した。意識した途端、猛烈な痛みが蘇る。だから痛みを無視する。痛み、冷え切り、動きたがらない体を無視して、目指す場所へ向かう。
最上階にたどり付いた時、もう一度窓から黒に沈んだ湖面が見えた。彼は初めて、静寂を意識した。
ラディンは、燭台を床に置いた。通廊に湿った夜風が抜けた時、無意識に息を突いた。掌の痛みを打ち消し、奪い取った長剣を握り直した。
扉を押す。扉は僅かの力で、音もなく開く。その時、頬に隙間風の冷気が触れた。室内には、たった一本の蝋燭の火が揺れていた。
簡素な室内の隅におかれた寝台の上、穏やかな寝息を立てながらその男は寝ていた。
ハンシスは、何も気づいていない。深く冷えた夢の中に眠り続けていた。ラディンは無音の数歩で近づき、寝台の横に立つ。見下ろす。室内は冷気を帯びた緩い風と、押し殺した静寂に満ちている。
ラディンの右手が動いた。長剣を高く持ち上げ、鋭い尖った切っ先を垂直に下に向けた。最も柔らかく最も無防備な場所を、すなわち喉の下を狙いゆっくりと、ゆっくりと動かしてゆく。
その時――ハンシスの目が開いた。
互いが、互いの眼を同時に見た。この時が来た。
「動くな」
この時が来たと、ハンシスは思った。この時が来ると、ずっと前から分かっていた。必ず、いつか来ると。ずっと前から。
ずっと前? いつ頃からだろう。ナガの城館に居た頃から? シャダーへの親愛が親愛の域に収まらなくなったと自覚した頃から? シャダーの愛を一身に受けている従弟に淀んだ嫉妬を自覚した頃から。
内臓が引き締まる感覚を覚えた。従弟が冷酷な眼で自分を見おろしているのを確認した。
「絶対に動くな。少しでも動いたら、喉を突く」
ラディンは剣先を向けたまま動き、ゆっくりと従兄の体の上に跨り乗った。
「聞いているのか? ハンシス。答えろよ」
「どうせ、動けない」
答えた。ラディンの視線が動く。ハンシスの身体からゆっくりと掛布をずらしてゆき、右の肩から胸にかけてぶ厚く巻かれた包帯を見た。
「傷を負ったのか」
「腕を動かせない」
「こんな時に。悪魔に気に入られたな」
「お前も、掌が酷い。どうした? 火傷か? 傷口から血と膿が出ている」
途端、剣の先が包帯の上から傷口をゆっくり押した。ハンシスが顔を歪め、苦痛の呻きをもらした。
「止めろ、――ラディン、何があった? 今までどこにいたんだ?」
「地獄へ行け。貴様が謀ったくせに。しゃあしゃあと」
「何の事だ? 私はずっとお前を探していた。お前の護衛だったカティルがここにいる。彼も山中でお前を見失ってからずっと行方を捜し――」
「黙れ」
ハンシスは黙る。喉に触れた金属の冷たい感触に黙らざるを得ない。
剣の切っ先の向こう、ラディンの眼に静かな、本気の殺意を見つけてしまう。本能的に覚えた恐怖は、チリチリとした感覚となって身を縛り出してゆく。
「本当に――私を、殺すのか」
「そうだ」
「殺したら、どうするんだ」
「シャダーと共に帰る」
「どこに帰る? まだ知らないのか? ナガではとっくに戦闘が終了している。ナガ方とコルム方のワーリズム家は一つにまとまった。そして――当主は私だ」
「――」
「私を殺すという大罪を犯して二人で帰っても、ナガ城館は受け入れない。帰るところは無い。だから、止めろ。その方が私達にとって、皆にとって良い結末だ」
「――」
黒い猫のような眼が迷ったのは一瞬だった。薄闇の中、真っ直ぐと見据えながら、
「殺す」
言った。
「それでも殺す。そして、俺は先へ進む」
言い切った。
即座、ハンシスはその言葉を解する。――本当に殺されると!
今、この従弟に理論は通らない。ただ、自分がいるから殺す。それしか無い。もう止められない。でも、
嫌だ。自分は今、死にたくない。
まだ生きたい、シャダーと共に生きたいっ、殺されたくない!
反射的、相手の身体を蹴った。一瞬剣の切っ先がずれた隙、体ごと寝台から落ちることで逃げる。
「イッル! ルアーイド!」
途端、再び上から圧し掛かられる。左腕を踏まれる。剣が振り下ろされるのに一瞬早く気づき、右腕で相手の手首を掴み引っ張る。虚を突かれてラディンが剣を落としたのを、素早くハンシスが奪う。
「右腕が動くじゃないかよ、糞の噓つきが」
「もう止めろ!」
だがハンシスには長剣を扱えるまでの力はない。とにかく剣は寝台の下の床に投げ捨てる。
「ルアーイド! イッル! 誰か!」
「呼ぶならシャダーを呼べよ」
三度目ラディンが馬乗り、今度こそ万全の態勢で押さえつけた。両手を伸ばして首を掴んだ。
「そうだな。分かってる。お前の方が上だ。お前が当主だ」
淡々とした口調が、静寂の中に帯びて響く。
「お前の方が、全てで俺を上回っている。分かってる。お前は支配者に相応しい男だ。そうあるべきだ。貴様は俺に勝って当然だ。敵わない。だから貴様が好きだった」
え?
ハンシスが表情を変える。首に従弟の生温かい血と膿を感じながら。
「貴様の方が上で、だからずっと憧れた。好きだった。きっといつか、必ずシャダーも貴様を選ぶと、貴様に奪われると分かっていた。
俺は貴様に勝てない。シャダーも奪われる。だから、貴様を殺すしかない」
違う! 何を言っているんだ、だったら私たちは争う必要が無いじゃないか!
そう叫びたいと思った瞬間、ラディンの両腕に力が加わる。声が出ない。息が出来ない。声にならない叫びを上げる。
それならば違う! 好意を持ってくれているなら、だったら他の道が開けるじゃないか、私はずっとお前から憎悪されているものだと……、
……いや。奴の言う通りなのか?
やはり道は変わらないのか? シャダーがいる限り、自分達二人の命運の流れは変えられないのか?
脈打つ血が頭を覆う。視界が闇に落ちてゆく。それでも考えようとする。道はあるはずだと。皆がより良い場所に立てる道があると。だが――、
息が出来ない。自分はこんな所で死ぬのか? シャダーにも会わずに? そして、目の前の、最後の視界。
ラディンが哀しんでいる。自分を殺すことを心底望んでいる男が、自分を殺すことに心底悲しんでいる。なぜ?
息が出来ない。止まってゆく。
――カティルが飛び込んできたのはその時だった。
(間に合わなかったのか! ハンシス!)
弾かれた如くの動きでラディンを殴り、ハンシスから引き離す。
(間に合わなかったのか! 間に合ったのか! 慈悲の聖者!)
「ハンシスっ、息をしろ! しろ!」
動かなくなった親友の上体を起こす。
(いやっ、間に合わせる、間に合う、間に合う、間に合わせる!)
夢中で揺さぶる。顔を叩く。頬をきつく三回叩き、四回目に手を上げた時、
「慈悲の聖者様……」
僅かに胸が――包帯が緩んでしまった胸が、僅かに動き出した。
「間に合ったのか……? 生きてるのか? 生きてるのか、ハンシス?」
「……、生きているのか……?」
乾いた声が、僅かに答えた。それはカティルが生まれて初めて、全身全霊全てをもって神と聖者に感謝を思った瞬間になった。
だがそれでも猫は諦めない。寝台の下に身を伸ばして剣を拾い上げ、それでも従兄の許へ近づこうとするのを、カティルが真っ向から妨げた。
「もう止めろ」
かつての主君であるラディンに向かい、胸元から自身の短剣を取り出した。その上で、珍しくも柔らかな口調で告げた。
「ラディン。あんたでは俺に勝てない。解ってるだろう? 状況を見ろ。もう負けたんだから、止めろ」
「――。貴様もハンシスに寝返ったのか」
「認めろ。反発するだけが能じゃないだろう? 現実を受け入れれば、現実も変わってゆく」
「貴様もか。貴様とは結構親密に付き合ってきたと思ったんだがな。冷たいな」
「悪いが、情がどうとか言うのは俺の好みじゃない。それにハンシスとの出会いの方が早い。早い者勝ちだ、――いや、違うか」
「――」
「全然違うな。たとえあんたと先に出会っていたとしても、俺はハンシスの方を選んだ。
王に相応しいのはあんたじゃない。奴なんだ。奴が優れた卿となって領地を広げていくのを、ワーリズム家を強くしていく未来を見るのが、心底愉しみなんだよ」
「なんだ。結局貴様も皆と――俺と同じって事か」
妙に子供っぽくそう言って、ラディンは笑んだのだ。
カティルはゆっくりと動いていく。ラディンの目の前に立つと、一瞬で相手の長剣を奪い取った。そのまま相手の右手首を確保した。
「さあ。もう一度牢だ」
「どうした? ここで俺を殺さないのか?」
「それはあんたの従兄が決めることだ。まあ俺としては、あんたはなかなか面白くて好きだから手を下したくないが。
ハンシス、こいつを閉じ込めたらすぐに戻るからそのまま待っていてくれ」
カティルはラディンを引っ張り、通廊に出て行こうとする。それを、まだ朦朧とした意識の中でハンシスは見送る。ぼやけた視界と意識の中、何か言いたいことがある気がする。なのに言葉は生まれない。無言で漠然と見送る。
……これで終わったのだろうか。自分達が超えるべき時間はこれで、薄闇の中で終焉したのだろうか。いや。足りない。
「閉じ込められるならやはり湖側の部屋の方がいいよな? 今回は枷を付けるが悪く思うなよ」
二人は扉から出て行き、そのまま薄闇の通廊を右へと曲がり――
シャダーがいた。
その瞬間の姉弟の顔を、カティルは見てしまった。二人共の、およそ思いがけない時と場で遭遇してしまったことへ対する大きな驚きの表情。それ以上に、互いが互いを求め合う眼!
即座、まずいと判断する。ラディンの腕を力任せに引き、逆の方へ引きずろうとする。だが遅かった。シャダーが弟に駆け寄り、強く抱き締めてしまったのだ。
「なぜ、ここにいるの? なんで? ナガにいるって聞いてたのに」
カティルは当惑する。声を発さず夢中で姉を見る弟、そして喜びを満面に発する姉が抱き合うのを目の当たりにし、今どう判断すべき状況なのか判らない。今どう行動するのが正しいのか判らない。判ったのは、
(ハンシスを――)
素早く踵を返し部屋に戻ると、取り敢えずハンシスを護るべく完全に扉をしめ切ってしまった。
「待って。開けて。中に入れて」
扉の向こうから、シャダーの声が響く。
「開けて。ハンシスと話がしたいの」
全くこの先の状況の予測がつかない。だから声を無視する。今は駄目だ。取り敢えず今は何よりもハンシスの安全が最優先されるべきだ、――と思ったのだが。
「扉を開けてくれ。イッル」
はっと振り返った。
部屋の奥に座り込んだままのハンシスの顔が、一つだけの蝋燭の光に浮かび上がっていた。
「二人を中に入れてくれ」
「――。いや。駄目だ」
「良いから」
「再会した以上、ラディンがまた感情を変えるぞ。今は駄目だ。もう少し事態が落ち着いてから――」
「良いから。中に入れてくれ」
「止めろ、止めてくれっ。こんな時に何言ってるんだっ」
「“こんな時に”? 君は何を知ってるんだ、イッル?」
静かな口調の中に、強い叱咤と絶対に譲らない念があったのだ。
カティルの淡色の目が揺らぐ。心底からの想いを込めて嘆願してしまう。
「止めてくれ。頼む。本当にもう、これ以上、貴方を危険にさらしたく無いんだ」
「こちらこそ頼む。二人を中に入れて、君は出て行ってくれ。三人だけにしてくれ」
「ハンシス!」
「三人で語り合う時が来るのをずっと待っていたんだよ。ナガをいた頃からずっと。
これを避けていたら、私達は三人とも未来へ進めない」
「……」
「安心しろ。私達は仲の良い従兄弟同士だったんだから」
揺れる光の中で、僅かにハンシスは笑った。
この時に思い知った。今まで自分は、独りで何でも判断でき実行できると信じて生きてきた。その自分にも出来ない事もあるのだと、カティルは初めて知った。もう何も出来ない。この三人の行く先に自分は関われない。引きさがるしかない。
自分も笑おうとし、失敗した。ゆっくりと扉の握りに手をかけた。
「聖者に賭けて、充分に気をつけてくれ」
「有り難う」
扉を開ける。
薄闇の、音のしない通廊で、姉弟が無言で待っていた。丸切り、扉が開くことが当然のように並んで待っていた。
彼は二人に中に入ることを促し、そして自分は部屋を出て、扉を閉じた。
後は、静寂と冷気になった。
・ ・ ・
三人の従兄弟達の再会は、思いの外になった。
怖れていたより、思いの外に静かだった。三人の誰もが口を閉ざし、ただ互いを見つめていた。壁に背をかけて石床に座っているハンシスと。手を握り合って並び立っているシャダーとラディンとを。
ハンシスは、二人を見ている。
初めて、よく似た姉弟だと思った。柔らかな頬の線とか、黒いツヤのある髪とか、闇のように深い瞳とか。姉弟らしく良く似た造作であることに今、初めて気づいた。
全く音の無い、互いの息遣いが聞こえる程の静寂だった。その冷たい空気の中でハンシスは自分のすべきことを確認していった。
自分のするべき事――ずっと述べたかった事――ずっと、怖れていた事……。
“本当に、私だけを愛してくれますか。ラディンではなく、私だけを”
「何があったの? ここで?」
純粋な眼で訊ねる。たった今ここで弟と従弟が殺し合いをしていたなどおよそ想像の一片にもあるはずもなく。
「こんな夜中に突然、何が起こったの? ハンシス。貴方、酷い顔色よ。それに傷がまた開いたみたい。血が包帯に滲んでいる」
当然のようにシャダーが近づいて来るのを、
「来ないで下さい」
自ら止めた。
「ハンシス、どうしたの?」
ハンシスは、壁を背で押しながら、自ら立ち上がる。自分が思いの外に動揺していることを自覚した。胸上の傷が強く痛み、姿勢を保つことに猛烈な困難を覚えた。極力ゆっくりと石床を踏みながら数歩を進んだ。
シャダーが見ている。やっと愛を交わし合えるようになった眼が、自分を見ている。
ラディンも見ている。たった今までの殺意は消えている。今は、夜の闇のように感情を示さない眼で見ている。
この眼は、いつもシャダーの横で自分を見ていた。幸福だったナガの光のような日々、しかし決して欠いてはならない影のように存在していた。自分の目の前で、彼はシャダーに愛され続けていた。
“ラディンがいても、私を愛してくれますか?”
もし、その答えが否だったならば、自分はどうするんだろう? 殺したいと欲するんだろうか? つい先ほどまでの従弟と同じ想いに駆られるのだろうか?
もう一度シャダーを見た。
彼女を愛しているという感情は抑えようもない。神の前にもどうしようもない。だから、そのために長い長い時間と手間をかけて、何人もの手を介して、ついにはこの遠いブハイル湖までたどり着いた。ここで、彼女の心を手に入れたのだ。
――だが。それはもしかしたら、ただの自分の身勝手だったのだろうか?
『俺にナガへ行けっていうのか? あんたの従弟を見張れって? 凄い依頼だな。いいぜ。面白そうだし、何よりあんたの未来には期待しているからさ』
『ついにナガに攻撃をかけるのか! 確かに貴方にはワーリズム家当主に相応しい力量があるけれど、でも、なぜこんなに唐突に? ――急いで軍備と軍策を整えないと』
『私は貴方が当主座に就くことに、秘密裏に同意します。ただし、大願成就の暁には、私のアール城領もそれ相応に十分な報酬を頂きますが、それでもよろしいですか?』
秘かに散々に他者を巻き込み、そこまでをした身勝手と傲慢は、神の前に許されるのだろうか。そこまでして彼女を得たいという欲望は、正当化し良いのだろうか。それでも自分は今、声に出して言って良いのだろうか。
“私の方を愛してください。私だけを愛して下さい”
もう一歩を踏み出した時、右足が体重をさせなかった。はっと石床向けてよろけかけた身体をシャダーが飛び出して支えようとし、二人ともに石床にしゃがみ込んだ。
「危ない! どうしてそんなにふらついているの? ハンシス、何があったの? 苦しいの? ねえ」
崩れるように床に座り込む自分のすぐ目の前に、シャダーの顔が迫った。
「何が有ったの? なぜ答えないの?」
彼女の掌が顔に触れた時に、皮膚の下で脈打つ血の熱さが伝わった。
「なぜ答えないの? 何を隠しているの? 貴方が大切なのに」
「――。大切……」
「ええ。貴方を愛しているの。誰よりも愛している。失ったら生きていけない。なぜこんなに傷が開いているの? 言って。貴方を守るのは私だから、言って」
まるで呼吸のよう自然に、ためらい一つも無くシャダーは言ったのだ。
「――」
ハンシスは、何も応じられない。
長い時間をかけて澱となった恐怖が、こんなにも簡単に霧散することが、受け入れられない。長い長い時間――シャダーはラディンを愛し――自分は嫉妬し――やっとラディンから離れた時――シャダーは自分の愛を受け入れ――ラディンは自分に殺意を剥き――その果てに迎えたこの時に、何を表現してよいのか分からない。
“では、ラディンへは?”
やっと言いたい台詞をまとめた。そう言おうとしたその時、
――シャダーはハンシスに唇を押し付けてきたのだ。
風は、窓の隙間から抜ける。一本だけの蝋燭の火が揺れ続けている。心をそのままに映す熱い、長い、真実を告げる接吻をシャダーは与えてくる。目を閉じた闇の中、全ての想いを込めた接吻が、長く長く続いてゆく。
風が、肌をかすめてゆく。続く接吻の中、頭の隅が微かに思う。
(殺されるのだろうか? この後、目を開けた時に)
ゆっくりと唇が離れ、終わってゆく。目を開け、シャダーを見る。自分を見つめる深い黒色の眼に、長い願いが叶った事を確認する。
(ラディンに、彼に殺されるのだろうか。今)
顔を横に向け、ラディンを見る。姉とよく似た黒い眼が、自分を見ている。思考も感情も解らない眼で自分を捕えている
この眼が、次の呼吸で動くのだろうか。殺されるのだろうか。もう防備は出来ない。これが最後になるのだろうか。自分は殺されるのだろうか。
「殺さないでくれ」
心から吐露した。
「私を、殺さないでくれ……。私はシャダーを愛している。彼女を愛してしまっている。どうしようもない。受け入れてくれ」
薄闇の中に、従弟の眼が真っ直ぐに見ている。真っ直ぐの、混じりけ無い純粋の眼。
「私を、愛してくれ」
冷えた風の中、僅かにラディンの右足が動こうとした。
その時、シャダーが体を動かした。
座したまま、僅かな衣ずれの音と共に彼女はハンシスの前に出た。ハンシスと弟の間に動いた。自らが恋人を守る盾になった。静かな、しかし強い眼で弟を見たのだ。
誰もが、喋らなかった。夜の静謐だけが冷気と共に流れた。光が揺れていた。
……
ラディンが動いた。
従兄の方には進まない。音も立てずに部屋を横切り、扉口へ向かってゆく。去ってゆこうとするのを、ハンシスが声をかけて止めた。
「良いのか、ラディン? ――私を殺さなくて良いのか?」
「――」
足を止め、振り向いた。
「許してくれるのか? 私を受け入れてくれるのか?」
感情も無く静かに、従弟は応えた。
「シャダーはもう、貴様を愛してしまった。どうしようもない」
「だから、私を殺すのではないのか?」
「気付いてないのか」
「……何を?」
「シャダーの心が移ったのなら、もう覆せない。一つのものしか愛さないから。もし貴様を殺したら、俺はこの場でシャダーに殺される」
横を向き、シャダーを見た。その横顔は何の躊躇も無く真っ直ぐな意志をもって弟を見ていた。その通り、眼にはもう、かつての嫉妬を覚える偏愛は無かった。溺愛は過去になり、今は純粋な愛に変じていた。
「だからだよ。だから――」
「だから――?」
「だから俺は、貴様とシャダーを離しておきたかったものを。会わせたら、確実に貴様に奪われるとは分っていた。怖れていた。でももう遅い。もう移ってしまったから。今さらどうしようもない。――シャダーに殺されたくない」
すでに時間は動き、現実は変わっていた。新たに進みだした現実を目に留め、ラディンは受け入れたのだ。
彼は、解放された。表情の無かった顔が、薄闇の中でほんの僅かだけ笑んだ。
「ありがとう。ラディン」
そう言うシャダーの口調には、優しさと慈しみがあった。かつて愛して止まなかった弟を見る目は、もう穏やかな親愛に変じていた。音も立てずに去っていく後背を、彼女は無言で見送っていった。
長い、長い時間が終わった。過去になった。
終わった。ハンシスは解放された。
薄闇の中でハンシスは、自分の感情をとらえる事が難しかった。感情を消化するにはまだ長い無音の時間が必要だった。何をして良いのか分からなかった。ただそのまま、ハンシスとシャダーは再び唇を重ねた。
・ ・ ・
扉の外側、薄闇の通廊でずっと会話を盗み聞いていたカティルは今、歩みだした。そのまま通廊の端まで進み、すり減った螺旋階段を登っていった。
最後の一段を登り終えた時、ブハイル湖からの冷たい清浄な風が、体の上を抜けた。低い空には明けの明星が輝いていた。
ようやく、世界は長い夜を終えようとしていた。微かな光を帯び始めた物見台の上、緩い風の音を耳が受け入れた。
「結局、手に入れたか」
夜明けの風が、長い淡色の髪をなぶる。消えていく夜の最後の寒さを感じる。
終わった。内紛の戦を起こしてまで、西の果てのブハイル湖まではるばる追跡してまで、殺される危険を冒してまで、そしてハンシスは手に入れた。それが良いのか悪いのかは判らない。別に自分が判断しなくても良い。ただハンシスが一つの達成を収めたというだけだ。
珍しく、ごく自然に笑みが浮かんだ。不思議なほど魅かれた主君であり友である男の達成を、素直に喜んだ。
終わったんだ。成就したんだ。
「さて。ならば。――俺はどうするかな。これから」
明るさを帯び始めた空と湖を見やる。
「このままも良いんだけれどな。ハンシスが一層に力を付けていくのを横で見ていくのも、確かに面白そうだけれどな。まあでも今回は、同じ場に居過ぎた。そろそろここを去るのが良いかな」
視界の前方、ブハイルの湖水が少しずつ、深い瑠璃色を帯び出してゆくのが見える。
「面白かった。ハンシス。それに、ラディンも。――本当に愉しかった」
明星が消えようとしていた。秋の薄い曙光が、稜線から射し込もうとしていた。
ブハイルの湖の色が、透き通る色味を帯び出そうとしていた。
・ ・ ・
同じ時。
地階の湖側の部屋。その窓の下。壁を背に当ててルアーイドは座していた。微動だにしなかった。
窓からは、うっすらと夜明け暮光は差し込み出していた。だが彼は、微動だにしなかった。
全く動かなかった。表情の無い顔の中で、しかし眼だけが大きく見開かれていた。
……
昨夜、ラディンにより部屋に閉じ込められた。どんなに狂ったように叩いても扉は開かなかった。喚き続けても誰も来なかった。
(ならば窓からっ)
窓に駆け寄り、身を乗り出す。ほぼ垂直に切り立った壁面の下に、黒々とした夜のブハイルの湖面が広がっている。
ラディンはここを泳いだのだ。氷のように冷たい闇の湖を泳いでハンシスの許に来たのだ。だから自分もやらないと。ハンシスを守る為に、この湖に入らないと。自分にせいで危機に追い込んでしまったハンシスの為に!
そう思って、思って、何度も思って……
なのに、出来ない。どんなに決意しても、本能的な暗闇と酷寒への恐怖が体を縛ってしまい、どうしても湖に飛び込むことが出来ない。
(飛び込め! 何度ハンシスを危険にさらすんだ、何度目だっ、今すぐ飛び込め!)
そう叫んで、自らを責めて、意を決して、闇の湖面を見て、でも叫んで、喚いて、泣いて――。
でも、結局出来なかった。窓の下に座り込んでしまった。感情は高揚し、興奮し、もう何の思考もまとめられず、決意も出来ず、混乱し――泣きたいのに泣けず。こうして、物を考える事を止めてしまった。
感じる事を、止めた。ただ、窓の下に座った。眠ることもなく。物を考えず、感じず、そうやって一晩を経た。
……ゆっくりと、夜明けの時間が進んでゆく。
座ったまま、ルアーイドは全く動かなくなった。
そして山の端を割って、曙光が差し込んできた。
10・ 夜の薄闇を抜けて光の射す方向へ
長い夜を越えたのちは、静寂だった。――
時間は、ブハイル湖を取り囲んで静かに進んでいった。いつの間にか黄葉は消え、風は日毎に冷たさを増していた。短い秋は終わりを告げかけ、灰色の初冬は目前となっていた。
この静かな時間の流れの中に、奇跡のような調和が完成していた。
ハンシスとシャダーとラディンそしてカティルとルアーイドは、繊細な調和の中にいた。彼らはごく当たり前の会話を交わし、ごく当たり前に静かな、穏やかな日々を送っていった。秋の最後の時間を惜しむように日々を心から、充分に愉しんでいた。
「覚えている。ナガに来た最初の夜だったな。山羊乳のヨーグルトに蜂蜜を入れた菓子を食べさせてもらった。あんなに美味しいものを食べたのは初めてだったから、これを毎日食べられるんだったら一生ナガで暮らそうと思ったんだよ」
ついに秋の最後とも思える薄晴れの夕刻だ。空のくすんだ青色に少しずつ赤い色が混ざり合う頃合いだ。
彼らは揃って物見台へ上り、椅子に座り、陽が没するのを待っている。葡萄酒の杯を握り、心地よく酔いながら、何ら害もない、他愛のない話を途絶える事なく続けている。
「良く言うぜ。最初の日の夕刻、皆がいた食卓で貴様の顔が強張ったまま震えていたのを覚えているぜ」
ラディンは口調に皮肉を入れている。だが今、表情は信じられないほどに穏やかだ。
「そうそう。貴方は甘菓子が大好きだったものね。今はどうなの? 今も?」
「嘘だろう? 俺の知っているハンシスは甘菓子なんか絶対に喰わないぜ。そんな姿は想像出来ない。ガキの頃の話だろう?」
「実は大好きなんだよ。でもコルムでは食べられなくてね。今も昔もコルム城館の食事には甘菓子が出ないんだけど、なぜなんだろう? あの料理番の親父に理由を聞いてみたいんだけどな。――そうだよな、ルアーイド」
「――。そうだな」
ルアーイドは僅かだけ口許を上げて笑んだ。
冷たい夕刻の風に誰もが外套をきつく体にまとい、赤い葡萄酒の杯が進む。意味の無い会話を続ける。だが決してこの秋の間に起こった波乱の出来事については触れない。それに触れてしまうと、ようやく出来上がった調和が崩れてしまうのではと、誰もがどこかで敬遠している。ただ、赤味を増す空を見ながら、月の出を待ちながら、他愛ない無駄話ばかりを続けてゆく。
「ルアーイド、酔ったか?」
ハンシスはごく自然に笑いながら言った。
「どうしたんだ? 顔色があまり良くないぞ」
「葡萄酒の飲みすぎじゃない?」
「思いの外に美味しい葡萄酒だったからな。私もちょっと酔っている。いや、皆の顔を見て喋っているからだろうな、だからこんなに美味しいのかな」
「……そうだな。ハンシス。美味しい。そして皆と一緒に居られて、私も楽しいよ。
確かに、少し酔ってしまったみたいだ。それに、少し風が……」
複雑な笑顔で、ルアーイドは主君の顔を見た。
全てを終えた今、ハンシスは満ち足りている。来るべき未来を恐れなく待ち構えて、曇りの無い眼を示している。右肩の傷ももう癒えた。その手でシャダーの手を握っている。並び座る二人の全身が安らぎと至福に満ちているのが、秋の夕刻の薄い光の中に映えている。
「風が冷たいから……」
笑みが硬い。あの長かった夜以来、もうルアーイドは疲労の様を隠し切れていない。ハンシスもカティルもシャダーも何度か声がけをしたのだが、その都度“少し疲れただけだから”と言って微笑んだ。微笑みで調和を保とうとした。
「……やはり、寒くて。済まないけれど、私は先に部屋に戻るよ」
「そうか。そう方が良いな。でもちょっと待ってくれ、ルアーイド。聞いてくれ」
ブハイル湖の許では、今ちょうど、陽が西の稜線に沈んだ。暮光の中に空も湖面も急激に色を変え始めた。世界は明日へ向けて着実に進んで行く。金色に染まり出した空気の中、ハンシスは一度湖と山を見、それからゆっくりと言った。
「明日、帰還する」
はっと、ルアーイドが緊張する。
「ずっとコルムとナガの状況が気になっている。早く帰還に付く必要がある。私の傷と体力ならもう問題ない。明日雨が無かったら、ここを出発して帰国の途に付くつもりだ」
「待てよ。だったらまず俺がアール城へ行く。あそこから護衛用の兵を連れてくる。それから出発しろよ」
「大丈夫だ、イッル。アール城までならシャダーの騎乗でも充分に夕方の早い時間に到着できるはずだ。私達だけで行く」
「カティルが同行するんだから、別に護衛はいらないだろう?」
ラディンの言にカティルはあっさりと言った。
「俺は戻らない」
はっと、ラディンとルアーイドが目を向けた。
「ハンシスにはもう伝えてある。ここで別れることにする。
確かに、あんた達と付き合ってワーリズム家のあれこれを見てるのは面白かったんだけれどな。でももう充分に楽しんだ。他の物も見たくなってきた」
「一人でどこへ行くの?」
「決めてない。でもこのままジュバル山地を反対側に進んでみるかな」
「さらに西へ?」
「さらに西へ進むと、海が有るらしい。一度、海を見てみたい。何も無い、ただ青い色が無限に広がっているそうだから見てみたい」
嬉しそうに言った。
「あんたも一緒に来るか、ラディン?」
「止めて。ラディンは私達と一緒に帰るんだから。
そうよね、ラディン? まさかカティルと一緒に行くなんて言わないわよね?」
「――」
ラディンは無言で立ち上がった。物見台の縁まで進み、包帯を巻いた両掌を手すりについた。
「止めて。そこには座らないで。手の怪我もまだ治りきっていないのよ」
そのまま、ラディンはブハイル湖を見ている。夕陽の中に金色を帯び始めた湖面を見据え続け、そして言う。
「ナガに帰らない。カティルとも行かない。俺はもうしばらくここに残る」
「なぜ! 理由は何?」
「もう少しここに残りたいだけだ。気が向いたら、それからナガに戻る」
それだけ言うと、あとは湖を見ながら葡萄酒の杯を口に運んだ。でも! と姉がさらに続けようとするのを、ハンシスが彼女の手を強く握りしめて止めた。
終わったんだ。
繊細な調和の時間は、もうお終いだ。時間は、現実は、止まらずに先へ進んでゆく。それだけだ。
湖の上では、空気の色が赤味を帯びてゆく。秋の夕刻が進んで行く。ルアーイドの疲弊した眼がラディンを、そして手を握り合うハンシスとシャダーを見る。彼もまた、時間が未来へ動いてゆくのを実感している。自分はそれに拒絶したいのだろうかと、体のどこかが思う。感情がくぐもってゆくのを、どこか遠くで自覚する。
「ルアーイド。君ももう少し残った方が良いと思う」
その時ハンシスが言った。
「何だかずっと体調が悪そうだ。私達なら大丈夫だから、ここに残って充分に休養をとってからコルムに戻ってきてくれ」
「――。いや……貴方が心配だから、私も一緒に行く。イッルもラディン殿もいないのだから尚更……」
「本当に大丈夫だ。アール城から先は護衛を付けてもらうよ。君は残って休んでくれ、ルアーイド」
「――」
真摯な気遣いの言葉を受けながら、もはやルアーイドは表情を失った。ただ、僅かに血走り赤味を帯びた眼でハンシスを見続けるだけだった。
東の空には、蒼ざめた色彩の月が現れ始めた。必死の抵抗を示すように、空は赤味を増していく。風だけが強く流れて、五人の纏う外套の裾をたなびかせて行く。明日が近づいて来る。
「これが、皆で囲む最後になるのね」
シャダーの声が、夕刻の最後の時間の中に響いた。
「きっとまたいつかは会えるだろうけれど、でもいつになるか分からないわね。色々とあったから――本当に色々とあったから。別れるのは少し寂しい」
「そうだな。このブハイル湖での時間はお終いだ。これからはコルムとナガで、新しい時間が待っている」
「ああ。長いさようならだな」
淡色の髪を風に流されながら、カティルが続ける。
「本当に、あんた達に会えてよかったよ。面白かった。」
ラディンも無言のままこちらを見ている。その顔が少しだけ笑っている。
すっと、ハンシスの葡萄酒の杯を握った右手が、前に伸ばされた。風の中、真っ直ぐに声が通った。
「皆の未来が、光り輝くよりに。神の御加護の許に光の方向へ進むように。そして、いつの日かの皆での再会を願って」
赤い夕刻の中に杯を差し出し、四人は乾杯をしたのであった。
ハンシスとシャダー、そしてカティルが笑んでいる。ラディンは再び、暗くなってゆく湖を見ている。その眼からはもう、かつての掴みどころの無さが消えている。全てを受け入れている。
ルアーイドが小声で嗚咽し始めた。赤くなった目に涙をあふれさせ、何も泣くことは無いだろう? とカティルにからかわれる羽目になった。
風が確実に冷えていった。一日の最後の瞬間に、世界は赤い色に染まった。その雲間に肥えた月だけが異様に白く、しかし美しかった。
・ ・ ・
翌朝は、秋の最後を予感させる朝になった。――
なんとか、雨だけは免れそうだった。だが灰色の雲が空の大部分を覆い、風は深く冷え込んでいた。強く吹いていた。
その風の中を、分厚い外套を着たハンシスとシャダー、そしてルアーイドの三人は、受けている。
「イッルはもう西へ出発したのか?」
アルアシオン城の城門の許。手袋をはめながら、ハンシスは言った。
「随分と早かったんだな。最後にもう一度会いたかったのに。まあ、奴らしいといえば奴らしいけど」
「……そうだな」
「ラディンは? ねえ、ルアーイド。ラディンはどこに行ったのか知っている?」
シャダーは早々に馬に跨っている。早く出発したいという想いに満ちた顔だ。
「本当にどこへ行っちゃたのかしら。見送りにもこないなんて……。まあ、すぐにナガ城館へ戻って来て会えるとは思うけど……」
「さあ。――おそらく城からは出ていないと思いますが……」
「これもラディンらしいな」
ハンシスは笑う。
“シャダーは渡さない。その為に貴様を殺す”。
あの殺意の眼はもう、遠い過去になった。古い時間はとっくに終わったのだ。彼もまた今、新しい未来に踏み出そうとしているのだろう。
「ハンシス。本当にもう傷は大丈夫なのか」
「完全に塞がっている。一応まだきつく縛ってあるが、もう痛みもない。シャダーと一緒に急がずにゆっくりと遠乗りを楽しみながらアール城に向かうよ。秋の最後の景色を楽しみながらね。
それより――。君にまだ伝えていなかった。言わないと」
すっと、手袋をはめた手が伸ばされ、相手の肩を掴んだ。
「今回は私達の事で、君に大変な困難と心労をかけてしまった。迷惑をかけてしまい本当に申し訳なかった。謝罪と、それに感謝を述べたいんだ。
有り難う。心から、有り難う――」
「……」
「今も、私達のせいで疲れが溜まっているんだろう? もう何日も顔色が冴えない。済まない。もう一度繰り返すよ、有り難う」
強く抱き締めて、深い誠実を示した。
ルアーイドは無言だった。ただ、泣き出しそうに顔を歪めた。
「目も赤いぞ。本当に大丈夫なのか?」
「……いや、ずっと眠れなかっただけだ。それだけ……そうだな。多分、今夜になれば良く眠れるんじゃないかな」
「そうだよな、私達のような面倒な荷物になる厄介者が去れば、君もやっと安心して眠れるな。
ルアーイド。コルムで再会できるのを楽しみに待っているよ」
冷たい風を受けながら、ハンシスは踵を返す。葦毛の馬に跨ると、シャダーの馬の横に並び、二人で顔を見合わせる。だからその時、ルアーイドの顔から表情が消えてゆくのには気が付かなかったのだ。
ちょうど、灰色の空に雲の切れ間が出来た。秋の最後の陽射しが湖を、そして馬上の二人を照らした。
「アール城までは二人切りの騎行になるけれど、大丈夫ですか、シャダー?」
「じゃあ、今日一日は私が貴方を護るわ」
極上の笑顔と共に、彼女は当たり前のように馬を寄せてゆく。どちらからともなく、鞍上のまま二人は唇を重ねていった。
一対の馬はぴったりと並び、二人は会話を交わしていく。急ぐことなく散歩でもするように湖の水際をゆっくりと進み出した。秋の最後の日差しを楽しみながら、光の射す方向へと出発していった。
・ ・ ・
光の射す世界へと進む二人を見ていた。
最上階の湖側の自室。その部屋の窓からは湖が、山が、世界が良く見える。その窓枠に丸くなって座りながら、ラディンはブハイル湖の全景を、秋の最後の遠景を見通していた。
二頭の馬が湖沿いに現れてきたのが見える。水際に寄ったり止まったり。止まって会話を交わしたり。その満ち足りた姿が、淡い光を返す風景の中に映えている。
ふと、口が動き、呟いた。
「シャダーと、ハンシス」
王者を目指すハンシス。
そのハンシスを全身全霊をもって愛するシャダー。
光と風の中、二人が笑ったのが遠く見えた。自分の感情のどこかを、僅かに何かがかすった気がした。
……あの夜。
あの時。あの音の無い室内。
シャダーを独占するために、ハンシスを殺すはずだった。
だが、シャダーが自分の前に進みはだかりハンシスを護ろうとした時。――もう現実は動いたのだと解かった。
あの時。もう時間は移ったと知った。シャダーの愛が他者に移った以上、どうあがいても取り戻すことは出来ない。例えハンシスを殺しても、ただ殺される程の憎悪を買うだけだ。決して彼女の感情は戻らない。シャダーはそういう女性だ。長く愛され続けた自分こそが、誰よりもそれを理解している。
憎しみや哀しみという感情を覚える余地すら無い。現実は驚くほど単純に自分を覆う。だから自分も単純に受け入れた。それが時間を進める道だと分かった。あの長く、冷たかった夜に。
あとは、調和の時だ。もう感情を屈折させる必要も無い。シャダーの愛が変ずることに恐怖と警戒を覚える必要はない。ハンシスを憎み、そして愛していたことももう、否定しなくて良い。
……窓枠に座して観る世界に、陽が当たっていた。
眩しい、と思った。光が眩しく、そして心地良い。現実は受け入れた。未来を考えてみたくなった。その為にも二人から離れ、もう少しここに残って陽を受けていたい。
「どうするかな。これから」
光を体に受けて、暖かい。光を受けてブハイルの色も、世界も美しい。遠景で、愛し合う馬上の二人はまだ水際に遊んでいる。シャダーの顔も、ハンシスの顔も笑っている。
空を見上げた。大きな鳥が数羽、湖の上を渡ってくるのが見えた。その向こう側では、雲が速く流れていた。風が強かった。
「どうするかな。俺は」
言った。光を心地良いと感じながら。世界が暖かいと感じながら。
その時強い突風が抜けた。
一瞬はっと動かした視界に、鳥がいた。鳥の影が自分の顔の上を走った時、思わず息を飲み身を動かし、体の重心がぶれた。素早く窓枠を掴もうと右手を伸ばし、その包帯を巻いた掌が滑った。
あっ、という小さな声をあげ最上階からブハイル湖へ落ちていく時、妙に冷静に死ぬなと思った。そういえば、あの夜も湖を泳いだな。あの時は何の恐怖も冷たさも無かったなと、落ちてゆく僅かな時間に思った。水に触れた瞬間、冷たいとだけ思った。
あとは、何も無い。
誰にも気付かれることなく、ラディンは瑠璃色のブハイル湖に吸い込まれて、消えた。
・ ・ ・
陽射しの中、ルアーイドは世界を見ていた。
秋の最後の陽射しが眩しい、と思った。
……
二人が馬の腹を蹴って出発した後、すぐに踵を返して城内に戻った。二度と振り返らなかった。ただ一歩ずつ歩いた。一歩ずつ、何も考えずに――考えられずに歩いた。城内の通廊を進み、螺旋の石階段を登り、物見台に至った。
風が強く、冷たい。雲が素早く流れている。雲間に陽が輝き、光を受けたブハイルの湖面は透き通った瑠璃色に染まっている。だが、すぐに雲が空を覆うのだろ。その時には、湖の色も褪せるのだろうか。
物見台の最も前へ進む。手すりの許で下を見る。
ハンシスとシャダーが水際に留まって、何やら喋っているのが見えた。はるか遠目からでも二人の姿からは、未来への希望を感じる事ができた。
ハンシスは幸福の様だ。
ずっとずっと求め続けたシャダーの愛を手に入れて。戦まで起こして。その戦を放棄して失踪してまで。ラディンの前に命を賭してまで。そこまでして。
シャダーも笑っている。
愛する男を手に入れて、幸せに笑っている。つい先日まではラディンを偏愛し続け、その為に信頼を失わせ、その為に戦を招き、敗れ、一族の当主座を追われる羽目にまで追い込んで。
シャダーが幸福に笑っている。彼女は新しい男と共に、新しい未来へと進むのだ。
「それは、正しいことなのか?」
子供のように素直に、疑問に思う。
ならば、もしシャダーがさらに、新たに愛する男を見つけたら?
その時はまた騒乱を呼ぶのか? ハンシスは失墜の道をたどるのか? ラディンと同じ様に?
「正しくて、良いことなのか? ハンシスにとって」
冷たい風に吹かれる。ルアーイドは右手の中で、古びた巻上式弩弓を握り直す。
ふと振り向くと、昨夕に皆が座った椅子が残っていた。昨日の夕刻、赤く輝いた空気の中で皆が座っていた。“皆の未来が神の御加護で光り輝くものであれ”。ハンシスがそう高らかに言った。
自分もまた光の射す方向へ行けるのか? 大罪を犯し、永久に嘘を貫き続けながら?
「未来は、光り輝くのか?」
一度だけ、躊躇する。
目の前に広がる世界を見る。陽はそろそろ雲に屈し、姿を消すだろう。ブハイル湖の瑠璃色も光を失うだろう。
もう一度だけ、迷う。
だがもう思考が出来ない。感情も消える。もう自分が怒りたいのだか笑いたいのだか泣きたいのか判らない。低い空に、黒い鳥が数羽渡っていくのが見えた。一陣の突風を全身で受け止めた。
ルアーイドはゆっくりと、右手の弩弓を見る。数日前に、城の倉庫の片隅に打ち捨てられていたものを見つけて、手に入れた。丁寧に丁寧に修繕をほどこし、撫でるように磨き続けた。大切に隠し持ち続けてきた。今、その弦の巻上式のハンドルを動かし出した。
「光の未来を護らないと。私が」
腕に力が入らない。苦労をしながらゆっくりとゆっくりと弦のハンドルを巻き上げていく。
「命に賭けて護ることが、大罪を犯した私の贖罪だから。この男ならば、素晴らしい王になるとずっと信じてきたから。愛してきたから」
かちりと小さな音を立てて、巻き上げられた弦は固定された。
その瞬間、吐き気を覚えた。それすらもう、どうでもよかった。銃身に矢をつがえる。物見台の手すりに弩弓を置き据える。
世界の中に、秋の最後の陽光が射している。二人はまだ水際にいる。長らく何やらを親しく喋り交わした後、今ようやく馬を並べて先へ進みだそうとしている。
秋の光の中、ハンシスの纏う外套の濃緑色、シャダーの纏う外套の緋色が映えていた。美しい色だと思った。
「私の、贖罪だから」
弩弓の尻側を右肩に乗せた時、ずしりとした重さに苦痛を覚えた。緩慢な動きで、弩弓を前方に構えた。標的を、静かに見定める。
恐怖は無い。それ以外の感情も。何も感じる事無く、引鉄に人差し指をかけた。
「贖罪だから。使命だから。ハンシスを光の射す方向へ。だから。」
だから。
体のどこかに微かな喜びを覚えた気がした。僅かな笑顔になった。
引鉄を、引いた。
……
ルアーイドは僅かに笑んだままだった。
矢が飛んで行く長い長い時間も。その後も。
矢がシャダーの背中を完璧に打ちぬいた瞬間も。一言も発すること無く、彼女の身体がブハイル湖の水際に落ちて行った時も。
その瞬間、ハンシスもまた一言も発さなかった。
幸福を分かち合っていた恋人がたった今、水際で骸に化したのを目にした時も。その現実を理解できずに、無言の、無表情のままだった。物見台に立つルアーイドの遠目に、ハンシスの無表情の顔が、不思議な程に鮮明に映った。
次の瞬間、
ハンシスとルアーイドは同時に叫んだ。長い叫びは、ブハイル湖の透き通った瑠璃色の中に吸い込まれていった。
風が強い。そろそろ空は一面にわたり、雲が覆いつくそうとしていた。
陽が雲の裏に消えて、世界の色彩が薄れはじめていった。
……短かった秋が終わり、ブハイル湖には灰色の冬が訪れようとしていた。
【 終 】
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
4
この作品の感想を投稿する
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる