3 / 10
03 氷蔦城
しおりを挟む
#03
氷蔦城は美しくも堅固な城塞だった。グラシエラ山脈から魔物の侵入を防ぐ前哨であり、騎士団の駐屯地をかねる。
「馬を頼む」
玄関前まで六脚馬で乗り付けたシルヴィオは、セラフィナを抱き下ろすと駆け寄った馬番に愛馬を任せた。
「自分で歩けます」
「靴がないでしょう。無理はしないことですよ、レディ」
シルヴィオはセラフィナを抱いて城に入った。
(暖かい……こんなに天井が高くて広いのに)
外は凍えそうなほどの寒さでありながら、屋内に一歩入るとまるで春の陽気のようだった。
あまりの気温差に体が慣れず、頭がくらくらする。
「まあまあまあ、連絡がないから心配していたら……!」
小走りで駆けてきたのはドレスを着た貴婦人だった。装いから、尋ねるまでもなくセラフィナは彼女が誰かわかった。
侯爵夫人だ。
シルヴィオの腕から飛び降りて、セラフィナは頭を下げた。
「東部神殿から参りました、セラフィナです。お見苦しくて申し訳ありません」
コートを脱いだセラフィナは、神殿の簡素な薄い礼服姿だった。自分が持っている一番上等な服とはいえ、仕立てられたのは10年も前だ。侯爵夫人のドレスにくらべると、あまりにみすぼらしく感じる。
「挨拶は後でいいですから。母上、まず彼女を風呂に案内してあげてください。凍えて死ぬところだったんです」
後ろからシルヴィオが口をはさむ。
セラフィナの手を握って侯爵夫人は頷いた。
「その通りね。あなた、唇が真っ青よ。手もこんなに冷えて……よその地域の人に北の寒さは堪えたでしょう。まず暖まってちょうだい」
案内されたのは大浴場だった。グラシエラ山脈のうち、一部は火山なので北部では温泉が豊富に湧くらしい。そのお湯を流すパイプが地下にも張り巡らされているので、どの家も冬でも暖かいそうだ。
「北部の人はみんな、寒さに強いのかと……」
「強い人もいるけど、少数よ。みんな家ではぬくぬくしながら、なるべく我慢はせずに冬を乗り越えるの」
同じ湯に浸かりながら侯爵夫人は笑った。
湯浴みの侍女をつけると言われて、一人で入れると言ったらなぜか侯爵夫人と一緒に入ることになった。
緊張しすぎで、湯の温かさなどよくわからない。
「……セラフィナさん」
「は、はい!」
改まった様子で名前を呼ばれて、セラフィナは居住まいを正した。やっぱりこの結婚はなかったことに──とでも言われるんだろうか。
「どうか、あの子をお願い。救ってあげてほしいの。大変な負担だということはよくわかっています。私たちにできることなら何でもするわ。でも、私たちにはあの子を助けてあげられないの……っ」
セラフィナの手を握って夫人は頭を下げた。
状況が飲み込めない。だが夫人がセラフィナのような人間にも頭を下げるほど追い詰められているのは理解できる。
「私に……何ができるかはわかりませんが、できる限りの努力をします。ご期待にそえるかはわかりませんが――」
それがセラフィナに言える精一杯だった。
涙ぐんで夫人は頷いた。
「どうか息子を、お願いします」
着替えのないセラフィナのために侯爵夫人がナイトガウンを貸してくれた。新品同然の絹製で、これほど肌触りのいい布に触れたのは初めてだった。
「馬車から振り落とされて魔物に襲われるなんて、ひどい災難だったわね。荷物は明日、誰かに探しに行かせるから今夜はどうか休んでね。お腹は空いていない?」
侯爵夫人はセラフィナのために服を用意し、部屋を温めるよう言い、とても優しくしてくれた。夫人本来の優しさというよりも、息子のためになんとかセラフィナをとどまらせようとする痛々しいほどの気遣いだった。
食堂でセラフィナが温かいスープをごちそうになっていると、老年の紳士がやってきて侯爵夫人に耳打ちした。
「シルヴィオが戻ったみたい」
セラフィナを侯爵夫人に託すと、夫となる黒炎の騎士は「まだ仕事があるので」とすぐにまた吹雪く外へと戻っていったのだ。
心配そうな侯爵夫人が「ごめんなさいね、ゆっくり食べていて」と出ていったので、言われたとおりにセラフィナはスープを平らげた。
食べ終わると手持ち無沙汰で、一応自分も夫になる人を気にかけたほうがいいかとセラフィナは玄関ホールへ向かった。
外は吹雪がひどくなったようで、外から戻った彼のマントにはたくさんの雪がまとわりついていた。
セラフィナに気づくと、彼は古びたカバンを差し出した。
「あなたのものでは?」
馬車に置いたまま持ち去られた、セラフィナのカバンだった。
「……取りに行ってくださったんですか?」
「大切なものかと。……馭者には厳重注意をしました。魔物がグラシエラ山脈を越えていると警告が出ていたのに、確認を怠って客を危険にさらしたあげく、見捨てて逃げた。立件するかは当局の管轄ですが、この地の安全を所管する者としてお詫びします。本当に申し訳ありません」
胸に手を当て、シルヴィオは深々と頭を下げた。
「……頭を上げてください。死にかけましたが、あなたのせいではありません。命を助けてもらいました。こちらこそお礼を言います。……騎士団のみなさまを危険にさらして申し訳ありません」
警告のことをセラフィナは知らなかった。無知の結果死にかけて、助けるために騎士団が危険をおかしたのは事実だ。もしも騎士団に負傷者や死人が出ていたら、それはセラフィナのせいだった。
魔物と戦う騎士を救うために聖女は存在しているのに、あまりにひどい失態だ。
「あなたはこの地に初めて来られた。責められるいわれはないでしょう。……本音を言えば、連絡が欲しかったですが。事情を説明し、迎えをやりました。なぜこんな夜更けに一人で山道を行くなんて無茶をなさったんです」
連絡をしたら誰かが迎えに来てくれるという経験を一度もしたことがなかったから。そんな発想さえなかった。
「……すみません。乗換駅で列車を間違えて――遅くなる連絡をしようにも、到着したときには郵便局が閉まっていたので。日をまたぐよりは、遅くならないうちにと」
「役場の『話し環』を使えばよかったでしょう。氷蔦城と専用回線でつながっているので、交換手は不要です。あなたの身分を明かせば問題なく使えたはずです」
話し環――遠方の人物と直接会話ができる最新式の魔道具だ。王都にはあると聞いていたが、セラフィナがいた東部にはほとんど普及しておらず、当然使ったことがないし、使い方もわからない。
それをなぜ使わなかったのかと責められるのは、無知を責め立てられているようで辛かった。こんなあたりまえのことも出来ないのかと言われている気分になる。
「遠くから来てくれた方に、なんて口の利き方をしているの! もっと言い方というものがあるでしょう!!」
隣でやりとりを見守っていた侯爵夫人が息子を叱りつけた。彼女は異様なほど、セラフィナが気分を害すことがないよう気を使っている。
そうして彼女に気遣われるほど、セラフィナはみじめだった。自分にはそんな価値などないと知っているから。
夫人は何かを誤解して、セラフィナに期待している。いずれ現実を目の当たりにして失望するだろう。
「……東部で『話し環』を見たことがありませんでした。役場にあるものだということも、城とつながっていることも知らなかったのです。私の不手際で、公子にはご不快な思いをさせて申し訳ありません」
自分が無知で無能であることを認めて謝ると、シルヴィオは動揺したようだった。兜の奥で息を呑む音がした。
しばらくの沈黙のあと、初めて彼はセラフィナの前で兜を脱いだ。
「申し訳ありません。無知はこちらでした。北部の当たり前を、すべての人々の当たり前と思っていたのは俺のほうです」
彼の顔を見てセラフィナは衝撃を受けた。
まだどこか幼さを残す顔立ちや、その端正さにではない。彼の顔半分を覆う、黒い痣があまりにも痛々しかったのだ。
首から伸びる痣は魔障の印だ。丹田にある魔核から魔障は体を蝕んでいく。黒い痣に覆われたシルヴィオの左目はすでに白目が黒く変色し、瞳孔は赤く染まっていた。魔物化が進んでいるのだ。
眉間にシワを寄せて、目を細めてシルヴィオはセラフィナを見ていた。
ほんの数十秒で、彼は耐えられなくなったように片手で両目をふさいだ。
「すみません、光が眩しくて……もう明るいところではあまり見えないのです」
夜目が効く代わりに昼間はあまり見えない――魔物の特徴だ。
玄関ホールはガス灯よりも明るい光晶灯のシャンデリアで照らされていた。太陽には及ばない人工の明るさすら、彼にはもう苦痛なのだ。
「これほどひどい魔障を見たのは初めてです。お辛いでしょう」
心から同情してセラフィナは言った。
なぜこれほど財力に恵まれ、息子を愛している侯爵家の人々が彼を放置しているのかわからない。急ぎ浄化しなければ、数ヶ月ともたない重症だった。
侯爵夫人がわっと泣き出した。
「お願い、セラフィナさん。どうか息子を助けて。前の聖女様たちはダメだったの。息子を浄化できなかったのよ。あなたが最後の頼みなの。必要なら私の命だってあげるわ! お願いだから息子を助けて……!!」
氷蔦城は美しくも堅固な城塞だった。グラシエラ山脈から魔物の侵入を防ぐ前哨であり、騎士団の駐屯地をかねる。
「馬を頼む」
玄関前まで六脚馬で乗り付けたシルヴィオは、セラフィナを抱き下ろすと駆け寄った馬番に愛馬を任せた。
「自分で歩けます」
「靴がないでしょう。無理はしないことですよ、レディ」
シルヴィオはセラフィナを抱いて城に入った。
(暖かい……こんなに天井が高くて広いのに)
外は凍えそうなほどの寒さでありながら、屋内に一歩入るとまるで春の陽気のようだった。
あまりの気温差に体が慣れず、頭がくらくらする。
「まあまあまあ、連絡がないから心配していたら……!」
小走りで駆けてきたのはドレスを着た貴婦人だった。装いから、尋ねるまでもなくセラフィナは彼女が誰かわかった。
侯爵夫人だ。
シルヴィオの腕から飛び降りて、セラフィナは頭を下げた。
「東部神殿から参りました、セラフィナです。お見苦しくて申し訳ありません」
コートを脱いだセラフィナは、神殿の簡素な薄い礼服姿だった。自分が持っている一番上等な服とはいえ、仕立てられたのは10年も前だ。侯爵夫人のドレスにくらべると、あまりにみすぼらしく感じる。
「挨拶は後でいいですから。母上、まず彼女を風呂に案内してあげてください。凍えて死ぬところだったんです」
後ろからシルヴィオが口をはさむ。
セラフィナの手を握って侯爵夫人は頷いた。
「その通りね。あなた、唇が真っ青よ。手もこんなに冷えて……よその地域の人に北の寒さは堪えたでしょう。まず暖まってちょうだい」
案内されたのは大浴場だった。グラシエラ山脈のうち、一部は火山なので北部では温泉が豊富に湧くらしい。そのお湯を流すパイプが地下にも張り巡らされているので、どの家も冬でも暖かいそうだ。
「北部の人はみんな、寒さに強いのかと……」
「強い人もいるけど、少数よ。みんな家ではぬくぬくしながら、なるべく我慢はせずに冬を乗り越えるの」
同じ湯に浸かりながら侯爵夫人は笑った。
湯浴みの侍女をつけると言われて、一人で入れると言ったらなぜか侯爵夫人と一緒に入ることになった。
緊張しすぎで、湯の温かさなどよくわからない。
「……セラフィナさん」
「は、はい!」
改まった様子で名前を呼ばれて、セラフィナは居住まいを正した。やっぱりこの結婚はなかったことに──とでも言われるんだろうか。
「どうか、あの子をお願い。救ってあげてほしいの。大変な負担だということはよくわかっています。私たちにできることなら何でもするわ。でも、私たちにはあの子を助けてあげられないの……っ」
セラフィナの手を握って夫人は頭を下げた。
状況が飲み込めない。だが夫人がセラフィナのような人間にも頭を下げるほど追い詰められているのは理解できる。
「私に……何ができるかはわかりませんが、できる限りの努力をします。ご期待にそえるかはわかりませんが――」
それがセラフィナに言える精一杯だった。
涙ぐんで夫人は頷いた。
「どうか息子を、お願いします」
着替えのないセラフィナのために侯爵夫人がナイトガウンを貸してくれた。新品同然の絹製で、これほど肌触りのいい布に触れたのは初めてだった。
「馬車から振り落とされて魔物に襲われるなんて、ひどい災難だったわね。荷物は明日、誰かに探しに行かせるから今夜はどうか休んでね。お腹は空いていない?」
侯爵夫人はセラフィナのために服を用意し、部屋を温めるよう言い、とても優しくしてくれた。夫人本来の優しさというよりも、息子のためになんとかセラフィナをとどまらせようとする痛々しいほどの気遣いだった。
食堂でセラフィナが温かいスープをごちそうになっていると、老年の紳士がやってきて侯爵夫人に耳打ちした。
「シルヴィオが戻ったみたい」
セラフィナを侯爵夫人に託すと、夫となる黒炎の騎士は「まだ仕事があるので」とすぐにまた吹雪く外へと戻っていったのだ。
心配そうな侯爵夫人が「ごめんなさいね、ゆっくり食べていて」と出ていったので、言われたとおりにセラフィナはスープを平らげた。
食べ終わると手持ち無沙汰で、一応自分も夫になる人を気にかけたほうがいいかとセラフィナは玄関ホールへ向かった。
外は吹雪がひどくなったようで、外から戻った彼のマントにはたくさんの雪がまとわりついていた。
セラフィナに気づくと、彼は古びたカバンを差し出した。
「あなたのものでは?」
馬車に置いたまま持ち去られた、セラフィナのカバンだった。
「……取りに行ってくださったんですか?」
「大切なものかと。……馭者には厳重注意をしました。魔物がグラシエラ山脈を越えていると警告が出ていたのに、確認を怠って客を危険にさらしたあげく、見捨てて逃げた。立件するかは当局の管轄ですが、この地の安全を所管する者としてお詫びします。本当に申し訳ありません」
胸に手を当て、シルヴィオは深々と頭を下げた。
「……頭を上げてください。死にかけましたが、あなたのせいではありません。命を助けてもらいました。こちらこそお礼を言います。……騎士団のみなさまを危険にさらして申し訳ありません」
警告のことをセラフィナは知らなかった。無知の結果死にかけて、助けるために騎士団が危険をおかしたのは事実だ。もしも騎士団に負傷者や死人が出ていたら、それはセラフィナのせいだった。
魔物と戦う騎士を救うために聖女は存在しているのに、あまりにひどい失態だ。
「あなたはこの地に初めて来られた。責められるいわれはないでしょう。……本音を言えば、連絡が欲しかったですが。事情を説明し、迎えをやりました。なぜこんな夜更けに一人で山道を行くなんて無茶をなさったんです」
連絡をしたら誰かが迎えに来てくれるという経験を一度もしたことがなかったから。そんな発想さえなかった。
「……すみません。乗換駅で列車を間違えて――遅くなる連絡をしようにも、到着したときには郵便局が閉まっていたので。日をまたぐよりは、遅くならないうちにと」
「役場の『話し環』を使えばよかったでしょう。氷蔦城と専用回線でつながっているので、交換手は不要です。あなたの身分を明かせば問題なく使えたはずです」
話し環――遠方の人物と直接会話ができる最新式の魔道具だ。王都にはあると聞いていたが、セラフィナがいた東部にはほとんど普及しておらず、当然使ったことがないし、使い方もわからない。
それをなぜ使わなかったのかと責められるのは、無知を責め立てられているようで辛かった。こんなあたりまえのことも出来ないのかと言われている気分になる。
「遠くから来てくれた方に、なんて口の利き方をしているの! もっと言い方というものがあるでしょう!!」
隣でやりとりを見守っていた侯爵夫人が息子を叱りつけた。彼女は異様なほど、セラフィナが気分を害すことがないよう気を使っている。
そうして彼女に気遣われるほど、セラフィナはみじめだった。自分にはそんな価値などないと知っているから。
夫人は何かを誤解して、セラフィナに期待している。いずれ現実を目の当たりにして失望するだろう。
「……東部で『話し環』を見たことがありませんでした。役場にあるものだということも、城とつながっていることも知らなかったのです。私の不手際で、公子にはご不快な思いをさせて申し訳ありません」
自分が無知で無能であることを認めて謝ると、シルヴィオは動揺したようだった。兜の奥で息を呑む音がした。
しばらくの沈黙のあと、初めて彼はセラフィナの前で兜を脱いだ。
「申し訳ありません。無知はこちらでした。北部の当たり前を、すべての人々の当たり前と思っていたのは俺のほうです」
彼の顔を見てセラフィナは衝撃を受けた。
まだどこか幼さを残す顔立ちや、その端正さにではない。彼の顔半分を覆う、黒い痣があまりにも痛々しかったのだ。
首から伸びる痣は魔障の印だ。丹田にある魔核から魔障は体を蝕んでいく。黒い痣に覆われたシルヴィオの左目はすでに白目が黒く変色し、瞳孔は赤く染まっていた。魔物化が進んでいるのだ。
眉間にシワを寄せて、目を細めてシルヴィオはセラフィナを見ていた。
ほんの数十秒で、彼は耐えられなくなったように片手で両目をふさいだ。
「すみません、光が眩しくて……もう明るいところではあまり見えないのです」
夜目が効く代わりに昼間はあまり見えない――魔物の特徴だ。
玄関ホールはガス灯よりも明るい光晶灯のシャンデリアで照らされていた。太陽には及ばない人工の明るさすら、彼にはもう苦痛なのだ。
「これほどひどい魔障を見たのは初めてです。お辛いでしょう」
心から同情してセラフィナは言った。
なぜこれほど財力に恵まれ、息子を愛している侯爵家の人々が彼を放置しているのかわからない。急ぎ浄化しなければ、数ヶ月ともたない重症だった。
侯爵夫人がわっと泣き出した。
「お願い、セラフィナさん。どうか息子を助けて。前の聖女様たちはダメだったの。息子を浄化できなかったのよ。あなたが最後の頼みなの。必要なら私の命だってあげるわ! お願いだから息子を助けて……!!」
3
あなたにおすすめの小説


メイウッド家の双子の姉妹
柴咲もも
恋愛
シャノンは双子の姉ヴァイオレットと共にこの春社交界にデビューした。美しい姉と違って地味で目立たないシャノンは結婚するつもりなどなかった。それなのに、ある夜、訪れた夜会で見知らぬ男にキスされてしまって…?
※19世紀英国風の世界が舞台のヒストリカル風ロマンス小説(のつもり)です。

屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。


届かぬ温もり
HARUKA
恋愛
夫には忘れられない人がいた。それを知りながら、私は彼のそばにいたかった。愛することで自分を捨て、夫の隣にいることを選んだ私。だけど、その恋に答えはなかった。すべてを失いかけた私が選んだのは、彼から離れ、自分自身の人生を取り戻す道だった·····
◆◇◆◇◆◇◆
読んでくださり感謝いたします。
すべてフィクションです。不快に思われた方は読むのを止めて下さい。
ゆっくり更新していきます。
誤字脱字も見つけ次第直していきます。
よろしくお願いします。
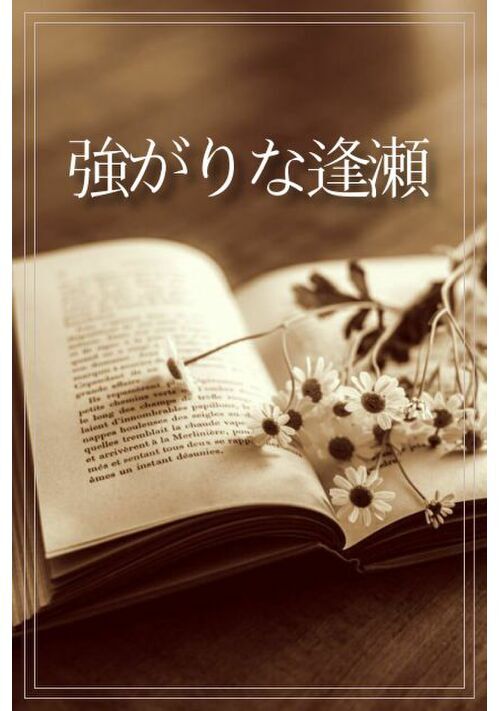

【完結】妻至上主義
Ringo
恋愛
歴史ある公爵家嫡男と侯爵家長女の婚約が結ばれたのは、長女が生まれたその日だった。
この物語はそんな2人が結婚するまでのお話であり、そこに行き着くまでのすったもんだのラブストーリーです。
本編11話+番外編数話
[作者よりご挨拶]
未完作品のプロットが諸事情で消滅するという事態に陥っております。
現在、自身で読み返して記憶を辿りながら再度新しくプロットを組み立て中。
お気に入り登録やしおりを挟んでくださっている方には申し訳ありませんが、必ず完結させますのでもう暫くお待ち頂ければと思います。
(╥﹏╥)
お詫びとして、短編をお楽しみいただければ幸いです。

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















