6 / 10
06 神聖水の泉
しおりを挟む
#06
グラシエラ山脈の北の断崖にある泉は、地下の霊気層から湧く天然の神聖水だ。
大別すれば神殿が地下深くまで掘り進めて汲んでいる通常の神聖水と大差ないが、天然の神聖水にはより強い浄化効果があると謳うものもいる。
二人目の妻に「私を苦しめたくなかったら毎日泉に行って身を清めてください」と言われてから、シルヴィオは一日も欠かさず泉に通ってきた。――浄化効果がほとんどないことは理解しながらも。
吹雪の中を六脚馬で進むこと半刻。雪に埋もれた泉を見つけて、シルヴィオは鎧も脱がずに飛び込んだ。
神聖水は夏場でも身を切るように冷たい。以前は冬なら数秒と浸かっていられなかったが、もう冷たさは感じなかった。
(申し訳ありません、セラフィナ……)
彼女を殴ってしまった感触が、まだ消えない。自分の意思ではなかった。あのときシルヴィオは、彼女が何を言ったのか理解しきれずにいたのだ。
問い直そうとしていたのに腕が勝手に動いた。肘が彼女の側頭部を殴打し、セラフィナは壁に吹っ飛んだ。
すぐ人を呼んで助けを求めたが、自分が殴ってしまった事実は変わらない。また危害を加えるのが怖くて、自分が何の役にも立たないのをいいことに、逃げるように泉に来てしまった。
(神聖刻印があれば大丈夫だと思っていた……)
自分が魔物になったら命を奪う契約が安全装置になると油断していたのだ。魔物になる前に自分は死ぬから、人を傷つけることはないと。
『あなたはもう魔物です。人と交わって、これほど女の肉が爛れることはないでしょう』
二人目の妻に言われた言葉が蘇る。彼女の言っていたことは真実だったのだと突きつけられた気がした。
「すみません。すみません、セラフィナ……」
半魔のシルヴィオの膂力は気をつけていても人の倍だ。セラフィナのような小柄な女性なんて簡単に殺してしまえる。
三人目の妻は犠牲にしたくないと心から思っていたのに、死ぬほどの暴力を振るってしまった。近寄るべきじゃなかったのだ。
彼女になにかあったら命を絶って詫びたい。自責の念に耐えられなかったのだと家族も理解してくれるだろう。
「あ……」
気づくと吹雪はやんで、水面には霧氷花が浮かんでいた。夏の間だけ咲く花だが、神聖水の泉には時折どこかからまぎれこむ。
「公子! もう上がってください」
後を追ってきた侍従のロットが火を焚いて待っていた。城でも外でも、シルヴィオは基本的に一人になることがない。いつ命を絶ってもおかしくと家族も気づいているからこそ、一人にはさせてもらえなかった。
泉のそばには、家族が建てさせた簡易な小屋がある。シルヴィオが泉から上がると、ロットはシルヴィオを中へ引っ張り込んだ。
小屋の中は魔石ストーブで暑いほどに暖房されていた。外は泉から出て数歩で服が凍りつくほどの寒さだ。
シルヴィオの鎧を脱がせて、ロットは「早く脱いでください」と急かした。
シルヴィオ自身は寒さも冷たさも感じないが、凍死して当然の真似なのだ。効果がないのに泉に来ることすら、ロットを含めた周囲の人間はよく思っていない。
「……いつもすまないな」
言われるまま素直に服を脱ぎながら、シルヴィオはロットに謝った。
小屋にはいつも、着替えやタオル、燃料が常備されていた。ここまで来れるのは六脚馬だけなので、ロットをはじめとした騎士団の人間がシルヴィオのためだけに運んでくれているのだ。
「……何かせずにはいられない公子のお気持ちはわかります。でもできるなら、吹雪の夜の強行は控えていただけると助かります」
鼻をすすりながら、ロットはシルヴィオの体をタオルで拭いた。彼の手の温かさに、自分の身体が死体のように冷えているのを自覚する。普通の人間ならとっくに死んでいるだろう。
「奥様はきっとご無事です」
なぐさめるようにロットは言った。
「頭は割れていませんでしたし、医師も脳震盪だろうと言っていたでしょう?」
「頭だぞ。どんな影響が出るかわからない」
「きっと回復されます。大丈夫ですよ」
濡れた髪の毛先までタオルで拭きながらロットは言いきかせた。
そうあって欲しい願いから、シルヴィオも頷いた。
「さあ、着替えてもう戻りましょう。奥様も意識を取り戻しているかもしれません」
気づくと夜が明けていた。差し込む光で視界が焼けて、シルヴィオは手早く着替えると兜をかぶった。これがないと、日中は活動できない。
外に出るとロットが二頭の六脚馬を集めて待っていた。
鐙《あぶみ》に足をかけてまたがると、二人で並んで氷蔦城へ向かう。
山稜を走りながら、シルヴィオはロットに尋ねた。
「今日もグラシエラ山脈は美しいか?」
「ええ、白い山々が神々しくそびえ立っていますよ」
シルヴィオの兜には、目線のところに黒色の強化ガラスが取り付けられている。光があるところではこれがないと眩しくて目を開けていられないのだ。
当然全てのものが黒みがかって見えるので、生まれたときから見て育った美しい山脈の光景をありのまま見ることはもう叶わない。
もうずっと、シルヴィオは死にたかった。浄化は叶わないと希望を捨てたときから、自分に待つのは死だけなのだと受け入れた。
諦めきれない家族が浄化効果のある水や壺を求めて騙されてからは、早く死んだほうがいいとさえ思うようになった。
自死を選ばないのは家族のためだ。彼らはシルヴィオを救うためにあらゆる努力をしている。その結果が自死では、あまりに報われないだろう。
だから領地と人々を守りたいという名目で、騎士の務めを続けている。魔物を屠れば魔障が進行すると理解しているからこそだ。
(死ぬ前に、この光景をもう一度見たかったな……)
愛するものを諦めていくのは辛い。だがそれももう少しだと、シルヴィオは自分に言い聞かせた。
氷蔦城に戻ると、セラフィナが目を覚ましたと伝えられた。
謝罪のために病室へ向かいながら、シルヴィオは恐怖でいっぱいだった。
きっと彼女は出ていくだろう。二人の妻と同じように。謝罪をしたところで何もなかったことにはならない。
それでも逃げることはできず、シルヴィオはセラフィナのいる病室を訪ねた。
「……シルヴィオ様」
起き上がろうとした彼女をシルヴィオは押し留めた。また自分の身体が勝手に動いて彼女を傷つけるのが怖く、むやみに近寄れない。
「どうか、そのままで。謝っても許されないことだとは理解していますが……本当に申し訳ありません」
膝をついてシルヴィオは頭を下げた。
衣擦れの音がして、セラフィナが近寄ってくる気配がする。あらゆる罵倒をシルヴィオは覚悟した。
「あなたのせいではありません。だから頭を上げてください」
膝をついてセラフィナはシルヴィオの肩に手をおいた。頭に巻かれた白い包帯が痛々しい。
「どうか、俺に近寄らないでください。また何をするかわかりません」
「私を殴ったのは、あなたではなく魔核でしょう。あなたに殴られるとしたら浄化の後ですから」
まだ浄化をする気があると取れる発言に、シルヴィオは顔を上げた。
彼女はからかうように笑って、シルヴィオの両手を取った。
「ほら、立って。このままじゃ私が悪妻みたいじゃないですか」
「あなたを悪妻と思う人なんて……」
「私の浄化を受けたら、あなたもきっとそう思います」
「ありえません」
反射的に言い切ってシルヴィオはハッとした。
セラフィナは言質を取ったとばかりに笑っている。
「では私のケガの痛みが引き次第、速やかに浄化をしましょう。それまで魔物退治は禁止ですよ」
グラシエラ山脈の北の断崖にある泉は、地下の霊気層から湧く天然の神聖水だ。
大別すれば神殿が地下深くまで掘り進めて汲んでいる通常の神聖水と大差ないが、天然の神聖水にはより強い浄化効果があると謳うものもいる。
二人目の妻に「私を苦しめたくなかったら毎日泉に行って身を清めてください」と言われてから、シルヴィオは一日も欠かさず泉に通ってきた。――浄化効果がほとんどないことは理解しながらも。
吹雪の中を六脚馬で進むこと半刻。雪に埋もれた泉を見つけて、シルヴィオは鎧も脱がずに飛び込んだ。
神聖水は夏場でも身を切るように冷たい。以前は冬なら数秒と浸かっていられなかったが、もう冷たさは感じなかった。
(申し訳ありません、セラフィナ……)
彼女を殴ってしまった感触が、まだ消えない。自分の意思ではなかった。あのときシルヴィオは、彼女が何を言ったのか理解しきれずにいたのだ。
問い直そうとしていたのに腕が勝手に動いた。肘が彼女の側頭部を殴打し、セラフィナは壁に吹っ飛んだ。
すぐ人を呼んで助けを求めたが、自分が殴ってしまった事実は変わらない。また危害を加えるのが怖くて、自分が何の役にも立たないのをいいことに、逃げるように泉に来てしまった。
(神聖刻印があれば大丈夫だと思っていた……)
自分が魔物になったら命を奪う契約が安全装置になると油断していたのだ。魔物になる前に自分は死ぬから、人を傷つけることはないと。
『あなたはもう魔物です。人と交わって、これほど女の肉が爛れることはないでしょう』
二人目の妻に言われた言葉が蘇る。彼女の言っていたことは真実だったのだと突きつけられた気がした。
「すみません。すみません、セラフィナ……」
半魔のシルヴィオの膂力は気をつけていても人の倍だ。セラフィナのような小柄な女性なんて簡単に殺してしまえる。
三人目の妻は犠牲にしたくないと心から思っていたのに、死ぬほどの暴力を振るってしまった。近寄るべきじゃなかったのだ。
彼女になにかあったら命を絶って詫びたい。自責の念に耐えられなかったのだと家族も理解してくれるだろう。
「あ……」
気づくと吹雪はやんで、水面には霧氷花が浮かんでいた。夏の間だけ咲く花だが、神聖水の泉には時折どこかからまぎれこむ。
「公子! もう上がってください」
後を追ってきた侍従のロットが火を焚いて待っていた。城でも外でも、シルヴィオは基本的に一人になることがない。いつ命を絶ってもおかしくと家族も気づいているからこそ、一人にはさせてもらえなかった。
泉のそばには、家族が建てさせた簡易な小屋がある。シルヴィオが泉から上がると、ロットはシルヴィオを中へ引っ張り込んだ。
小屋の中は魔石ストーブで暑いほどに暖房されていた。外は泉から出て数歩で服が凍りつくほどの寒さだ。
シルヴィオの鎧を脱がせて、ロットは「早く脱いでください」と急かした。
シルヴィオ自身は寒さも冷たさも感じないが、凍死して当然の真似なのだ。効果がないのに泉に来ることすら、ロットを含めた周囲の人間はよく思っていない。
「……いつもすまないな」
言われるまま素直に服を脱ぎながら、シルヴィオはロットに謝った。
小屋にはいつも、着替えやタオル、燃料が常備されていた。ここまで来れるのは六脚馬だけなので、ロットをはじめとした騎士団の人間がシルヴィオのためだけに運んでくれているのだ。
「……何かせずにはいられない公子のお気持ちはわかります。でもできるなら、吹雪の夜の強行は控えていただけると助かります」
鼻をすすりながら、ロットはシルヴィオの体をタオルで拭いた。彼の手の温かさに、自分の身体が死体のように冷えているのを自覚する。普通の人間ならとっくに死んでいるだろう。
「奥様はきっとご無事です」
なぐさめるようにロットは言った。
「頭は割れていませんでしたし、医師も脳震盪だろうと言っていたでしょう?」
「頭だぞ。どんな影響が出るかわからない」
「きっと回復されます。大丈夫ですよ」
濡れた髪の毛先までタオルで拭きながらロットは言いきかせた。
そうあって欲しい願いから、シルヴィオも頷いた。
「さあ、着替えてもう戻りましょう。奥様も意識を取り戻しているかもしれません」
気づくと夜が明けていた。差し込む光で視界が焼けて、シルヴィオは手早く着替えると兜をかぶった。これがないと、日中は活動できない。
外に出るとロットが二頭の六脚馬を集めて待っていた。
鐙《あぶみ》に足をかけてまたがると、二人で並んで氷蔦城へ向かう。
山稜を走りながら、シルヴィオはロットに尋ねた。
「今日もグラシエラ山脈は美しいか?」
「ええ、白い山々が神々しくそびえ立っていますよ」
シルヴィオの兜には、目線のところに黒色の強化ガラスが取り付けられている。光があるところではこれがないと眩しくて目を開けていられないのだ。
当然全てのものが黒みがかって見えるので、生まれたときから見て育った美しい山脈の光景をありのまま見ることはもう叶わない。
もうずっと、シルヴィオは死にたかった。浄化は叶わないと希望を捨てたときから、自分に待つのは死だけなのだと受け入れた。
諦めきれない家族が浄化効果のある水や壺を求めて騙されてからは、早く死んだほうがいいとさえ思うようになった。
自死を選ばないのは家族のためだ。彼らはシルヴィオを救うためにあらゆる努力をしている。その結果が自死では、あまりに報われないだろう。
だから領地と人々を守りたいという名目で、騎士の務めを続けている。魔物を屠れば魔障が進行すると理解しているからこそだ。
(死ぬ前に、この光景をもう一度見たかったな……)
愛するものを諦めていくのは辛い。だがそれももう少しだと、シルヴィオは自分に言い聞かせた。
氷蔦城に戻ると、セラフィナが目を覚ましたと伝えられた。
謝罪のために病室へ向かいながら、シルヴィオは恐怖でいっぱいだった。
きっと彼女は出ていくだろう。二人の妻と同じように。謝罪をしたところで何もなかったことにはならない。
それでも逃げることはできず、シルヴィオはセラフィナのいる病室を訪ねた。
「……シルヴィオ様」
起き上がろうとした彼女をシルヴィオは押し留めた。また自分の身体が勝手に動いて彼女を傷つけるのが怖く、むやみに近寄れない。
「どうか、そのままで。謝っても許されないことだとは理解していますが……本当に申し訳ありません」
膝をついてシルヴィオは頭を下げた。
衣擦れの音がして、セラフィナが近寄ってくる気配がする。あらゆる罵倒をシルヴィオは覚悟した。
「あなたのせいではありません。だから頭を上げてください」
膝をついてセラフィナはシルヴィオの肩に手をおいた。頭に巻かれた白い包帯が痛々しい。
「どうか、俺に近寄らないでください。また何をするかわかりません」
「私を殴ったのは、あなたではなく魔核でしょう。あなたに殴られるとしたら浄化の後ですから」
まだ浄化をする気があると取れる発言に、シルヴィオは顔を上げた。
彼女はからかうように笑って、シルヴィオの両手を取った。
「ほら、立って。このままじゃ私が悪妻みたいじゃないですか」
「あなたを悪妻と思う人なんて……」
「私の浄化を受けたら、あなたもきっとそう思います」
「ありえません」
反射的に言い切ってシルヴィオはハッとした。
セラフィナは言質を取ったとばかりに笑っている。
「では私のケガの痛みが引き次第、速やかに浄化をしましょう。それまで魔物退治は禁止ですよ」
4
あなたにおすすめの小説


メイウッド家の双子の姉妹
柴咲もも
恋愛
シャノンは双子の姉ヴァイオレットと共にこの春社交界にデビューした。美しい姉と違って地味で目立たないシャノンは結婚するつもりなどなかった。それなのに、ある夜、訪れた夜会で見知らぬ男にキスされてしまって…?
※19世紀英国風の世界が舞台のヒストリカル風ロマンス小説(のつもり)です。

屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。


届かぬ温もり
HARUKA
恋愛
夫には忘れられない人がいた。それを知りながら、私は彼のそばにいたかった。愛することで自分を捨て、夫の隣にいることを選んだ私。だけど、その恋に答えはなかった。すべてを失いかけた私が選んだのは、彼から離れ、自分自身の人生を取り戻す道だった·····
◆◇◆◇◆◇◆
読んでくださり感謝いたします。
すべてフィクションです。不快に思われた方は読むのを止めて下さい。
ゆっくり更新していきます。
誤字脱字も見つけ次第直していきます。
よろしくお願いします。
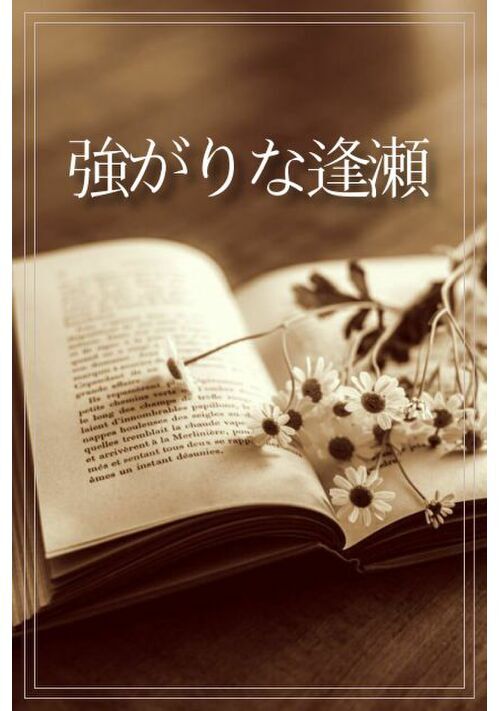

【完結】妻至上主義
Ringo
恋愛
歴史ある公爵家嫡男と侯爵家長女の婚約が結ばれたのは、長女が生まれたその日だった。
この物語はそんな2人が結婚するまでのお話であり、そこに行き着くまでのすったもんだのラブストーリーです。
本編11話+番外編数話
[作者よりご挨拶]
未完作品のプロットが諸事情で消滅するという事態に陥っております。
現在、自身で読み返して記憶を辿りながら再度新しくプロットを組み立て中。
お気に入り登録やしおりを挟んでくださっている方には申し訳ありませんが、必ず完結させますのでもう暫くお待ち頂ければと思います。
(╥﹏╥)
お詫びとして、短編をお楽しみいただければ幸いです。

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















