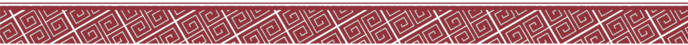51 / 59
41、寺社奉行にて3
しおりを挟む「その他に過去の浮術も残っているけど、興味があるかな」
ヒエンさんが本棚を視線で指した。
「地球からの召喚について書かれたものが見たい。といっても、俺はハナムン語が読めないし、そもそも浮流以外が大して見えない」
「大丈夫だと思いますよ。ここに残されているのは印帳です。浮者は死ぬと消えますが、印帳とそこに記された文字は消えないのです。これが記帳法の優れている点ひとつですね。後世に術の軌跡を残せるのですから」
そういうと、湯佐さんが本棚からいくつかの本を取り出して広げた。
わたしは気が進まなくて、ただそれを見ていた。
「美波、どうした」
旬さんが伺うように止まっている。
……もう帰りたいな……。
でも、せっかくここまできて帰るなんていったら、さすがの旬さんもあきれちゃうだろうし……。
「疲れたのか?」
「……うん」
「それは気つかなくてごめん。湯佐、外の四人を呼んでくれ。沢渡さん、お茶でもどうだろう?」
「はい……」
わたしはぼんやり座ったまま、旬さんの手を両手で握っていた。
四人が入って来ると、ハインリヒさんの額に傷ができていた。
「ハインリヒ、どうしたんだ、それ」
「いえ、大したことでは」
マッカリがなにかいいたげにわたしを見た。
「なにがあったの、マッカリ」
「あ、あの……」
「大したことではない。Frau沢渡、気にすることはない」
「気にするなというほうが無理です。マッカリ、いいから話して」
マッカリが手を組んで前につきだし、こうべを垂れた。
許しを請うポーズだ。
「別室でお待ちしておりましたら、第四研究室なる浮者の皆様がお見えになり、その一人が……、わたしの父の秘伝の書をお持ちでございました。父が町奉行に囚われたのだと察しまして、わたしは聞き耳を立てておりました……。下町言葉のすべては聞き取れませんでしたが……」
驚きに目を見張った。
マッカリの父親が、もう捕らえられていたなんて。
それも、秘伝の書がここにあるということは、キリ家の秘法を研究所はどうするつもりなのだろう。
「その方たちが用を済ませて部屋を出て行くのを、わたしはじっと見つめておりました。わたくしから声はかけられませんから、ただ見つめることしか……。そうしましたらば、ハインリヒ浮者が、わたしの代わりにお尋ねくださったのです」
またも意外な驚きだった。
ハインリヒさんを見ると、わずかに視線を下げただけだった。
「キリ家の娘が、父親の消息を知りたがっていること伝えてくださったのです。その方たちが書とともにわたしの前にお見えになりました。いろいろと話してくださったのですが、わたしはすべてを聞き取ることができず、応答にもあたふたしてしまい、その方たちの不興を買ってしまったようでした。そのせいか、おひとりがわたしの手を掴もうとなさったのです。それで、ハインリヒ浮者が間に入ってくださり……」
そのあとを拾って続けたのはヒエンさんだった。
「どうせ、階級を理由にいちゃもんをつけられたんだろう。ハインリヒ」
「は……」
「第四の研究員なんてお前よりはるかに浮量の足らない連中じゃないか。まあでも彼らはハインリヒに救われたね、大倉くんのお守りの怒りを買わずに済んで……」
「は」
ハインリヒさんは淡々と答えていた。
マッカリはそろりと腕から顔を上げてハインリヒさんを見た。
マッカリ、あの様子では聞きたいことも満足に聞けなかっただろう。
そうでなくても、マッカリらしくない失態だ。
よほど、父親のことが気がかりだったのだろう。
わたしはマッカリの手を取った。
「マッカリ、治癒流術できる?」
「はい」
ふたりでハインリヒさんの前に立った。
「ハインリヒさん、マッカリのためにありがとうございます。けがの手当てをしたいのですが、そこへ腰かけてもらえますか?」
「いや、この程度、なんともない」
「そんなこと言われても、こっちが気になっちゃうんです」
椅子に腰かけてもらい、マッカリがその額に流術をかけた。
それほど大きな傷ではなかったので、幸いマッカリの力でも治すことができたようだ。
「マッカリからもお礼がいいたいそうなんですが」
「うむ……」
「ハインリヒ浮者、大変なお心遣い、感謝しております……」
マッカリにしては、言葉少なだった。
「それで、マッカリのお父さんはどうなったのかわかったんですか?」
「つい先ほど、町奉行の本部に連行されたらしい。持っていた本は、事実の検証を命じられたそうだ」
「それで、マッカリのお父さんはどうなるんですか?」
ヒエンさんが口を開いた。
「まあ、いろいろ取り調べして、キリ一族の秘術とやらを検証して、終わったところで処分されるだろう。逃げた一族はもろともに」
マッカリが大きく瞳を揺らした。
その意図を汲んでわたしはヒエンさんに聞いた。
「会えるんでしょうか?」
「取り調べが終わったならあるいは。でも、会えば君のお気に入りが、よからぬ疑いをかけられるかもしれないよ。せっかく助かった命を無駄にする必要はないと思うけど」
「マッカリ……」
マッカリの手を取ると、マッカリは小さく首をふった。
「いえ、会うつもりはありません……」
本当に?
そう聞きたかったけれど、ここでマッカリの本心を聞き出すのは難しいだろう。
わたしもそれ以上口を出すのをやめた。
しばらくして、お茶が運ばれてきた。
香りの強いジャスミンだった。
「本当はコーヒーが飲みたいんだ。長年探しているけど、ハナムンにコーヒー豆に類するものがないんだよ。僕の召喚したいもの一位なんだけどね」
お茶を飲んだ後、旬さんは一通りの本を見せてもらった。
下町言葉で書かれた印帳は、わたしにはただの古ぼけた白い手帳だったが、旬さんにはマヌーケルンの青い光で文字が見えているはずだ。
旬さんが冊子をめくったり、本の間を行き来するのをわたしはじっと見つめていた。
「沢渡さん」
「はい」
振り向くと、ヒエンさんがもはやテンプレートと化したような笑顔で立っていた。
「どう、寺社奉行の研究所は? 感想を聞かせてよ」
「感想といわれても……、わたしに浮のことはわからないので」
「そんな難しく考えなくていいんだよ。なにが気づいたこととか、印象とか。なんでもいいんだ」
わたしは頭を巡らせた。
気づいたことといわれても、イスウエンのヒエラルキーや特権階級思考にげんなりとしか言いようがない。
「自分勝手だなと思いました」
「自分勝手?」
「ここで研究するのは誰のためなんでしょうか? 浮者が浮者のだけのために、研究をしたり、管理をしたり、統率して支配しているみたいで……。
自分たちのためだけに浮を使うのは違うと思います。 コーヒー豆なんて別にいらないと思います」
「君はまだ何も知らないからそんなことがいえるんだよ」
笑顔とは裏腹に重みのある低い声だった。
なに、急に……。
わたしはぎょっとして、ヒエンさんを見つめ返した。
不穏な視線を交わし合っていると、ハインリヒさんが語りだした。
「Frau沢渡はまだわかっていないのだ。誰もがあなたのようにハナムン人と信頼に足る友情関係を築けるわけではない。
誰のためといっていたな。それに対する答えの一つは、ハナムン人から食い物にされかねない浮者のためだ。
あなたがトラントランでの暮らしを愛しそこにいる人たちを大切に思うように、ここにいる者たちも、ここでしか安心して暮らせない者たちがいる。たしかに、たかがコーヒー豆だ。だが、そのたかが豆のひとつで生きる気力を失っていた浮者が気持ちを持ち直すこともあるのだ」
頭を殴られたような衝撃だった。
いわれてみれば、その通りだ。
ここでしか暮らせない人たち。
突然知らない国に連れてこられて、言葉も通じない、地球の常識とも違う。
恐怖や混乱の中、ようやくたどり着いた安全な町。
多分、ハインリヒさんもその一人だったのだ。
わたしには旬さんがいて、恵まれた環境にいて、ハナムンの人たちと一緒にいることが当たり前だったから、確かに理解できていなかったのかもしれない。
浮者として生きることの辛さや、不幸。
わたしだって、ここに来たばかりのときはずっとそう思っていたのに。
若菜に二度と会えないと考えるときの苦しさを、わたしは知っているはずなのに。
晴美先生に幸せになるところを見せられなかった悲しさ。
浮者狙いの悪者に、足首を切られた痛みや恐怖。
それでもなんとかいままでやってこれたのは、トラントランの人たちがわたしを助けてくれたから……。
「ごめんなさい……。確かに、わたしわかってないかもしれません……」
「君はまだこの国に来てたったの一年だ。わからなくて当たり前だよ。これからいろいろ知っていけばいい。僕らが力になるよ」
ヒエンさんが手を差し伸べてきた。
少し、うがった見方をしすぎていたかのかも……。
この人たちは、わたしよりはるかにこの国での暮らしを知っている。
わたしはトラントランやサイシュエンのハナムン人たちしか知らないけど、彼らはもっと多くの領地のハナムン人を知っているはずだ。
わたしの見たこと聞いたことは、事実だけど、一部でしかないのも事実だ。
わたしも手を差し伸べた。
次の瞬間、わたしの手は旬さんの左手と握手していた。
「美波に触るな」
宙にでかでかと浮かぶ文字に、ヒエンさんが苦笑した。
「さて、次はあまり期待は持てないけど、帰還浮術の研究でも覗きに行くかい?」
旬さんを見ると、あまり乗り気ではなさそうだった。
わたしは遊佐さんを見た。
「あの、研究室は何室あるんですか?」
「え……、ええと、今のところ第十六まであります」
「そんなに……。一応、すべての研究室のそれぞれのテーマを教えてもらえますか?」
遊佐さんが教えてくれた研究室のテーマを、わたしは印帳に整理して書いておいた。
これでなにか聞きたいことがあれば、役立つこともあるだろう。
「気になるテーマがあった?」
「いえ、今のところはないです。あの、もうひとつ遊佐さん、聞きたいんですけど」
「は、はあ、わたしですか?」
「先ほど、浮の推定値の話をしていたと思うんですが、参考までに教えてもらえませんか? わたしには見えないので、人が驚いたり怖がっていることがわからないんです」
「そうですね……」
ヒエンさんが突然身を乗り出してきた。
「ねぇ、沢渡さん! なんで僕じゃなくて遊佐に聞くの? 一応僕この研究所の責任者なんだけど」
「え、なんでって……、遊佐さんのほうが実務的だと思ったので。ヒエンさんはなんていうか、取締役……? ですよね? さっきからお話を聞いていても、遊佐さんの話はとても分かりやすかったので」
「まあそうだけど、僕も研究をすることもあるし、その位の質問なら僕にも答えられるよ」
「そうですか……、でも遊佐さんのほうがなんとなく聞きやすいっていうか。わかりやすいっていうか……すみません、他意はなかったんですけど」
「他意があったら傷つくよ……、そうでなくても君にも大倉くんにもすげなくされてさ」
ヒエンさんがまたあざとい顔をする。
ハインリヒさんは堅物だから若見えしていても九〇歳といわれても納得できる。
だけど、ヒエンさんはいくつかわからないけど、実年齢は見た目より上なのは明らかだ。
それでもまだあざと可愛いで世渡りしていこうなんて、肝が太すぎると思う……。
五〇歳のおじさんや九〇歳のおじいちゃんに置き換えて、脳内再生したらその違和感半端ない。
わたしはあいまいに返事をしておいて、他にも蔵書の数や、その分類や内容などを遊佐さんから教えてもらったことをかきつけておいた。
「遊佐さん、すごくわかりやすかったです。ありがとうございました」
「いえいえ」
「またわからないことがあったら聞きに来ていいですか?」
「わたしは構いませんが……」
遊佐さんがふくれ面のヒエンさんをちらと見た。
ふくれ面って、子どもか。
「部外者の研究所への立ち入りは、僕の許可が必要なんだからね」
「そのときはよろしくお願いします」
わたしは難なく頭を下げた。
ちょっとおかしな上司はどこにでもいるものだ。
「ヒエンさん、今日はとてもためになりました。またいろいろと教えてください」
にこっ!
経理部の杉並課長はこういうと大概機嫌が良くなるんだけど、ヒエンさんには効くかなあ。
「そう! よかった。またなんでも聞くといいよ!」
あ、効いた……。
やっぱり、中身はおじさんだな……。
「お昼なに食べる? 僕がご馳走してあげるよ」
こういところも、おじさん……。
わたしはテンプレートの笑顔で、おじさま接客術さしすせそのせを使う。
「せっかくなので、ありがたくいただきます」
研究所を出ると、わたしたちは町へ出た。
やっぱり竜宮城みたいなお店に案内されて、お昼だというのに高級懐石みたいな、きれいなお皿に芸術的な盛り付けのお料理がいくつものテーブルに並んだ。
「す、すごいですね……」
「ここは僕の行きつけなんだ」
「さすがですね」
「これ、ハナムンにしかないクノメっていう高級魚だよ」
「知らなかったです」
「この卵のしょうゆ漬けを海鮮丼にするとまたおいしいんだよ。いくらとはまた全然違うんだ」
「そうなんですね~」
さしすせそでほとんど話が成り立った。
お腹がいっぱいになったら、午後の予定はとても回れそうになかった。
ヒエンさんの転移の浮術で、ハインリヒさんの家に戻った。
「それじゃあ、君たちの術は明日見せてもらうっていうことでいいかな」
「はい。旬さんもそれでいいといってます」
「じゃあ、ゆっくり休んで。また明日ね」
「ありがとうございました」
ヒエンさんがまた円を書くと、一瞬で消えた。
みんなに労をねぎらっていると、旬さんがとんとんとわたしの肩をたたいた。
「今日わかったことを試してみたい」
「うん、わかった」
わたしはあとのことをマッカリたちに任せて、しばらく部屋にこもると伝えた。
つぼみはまたすぐ使うことになると思ったので、そのまま持っていてもらおうと思ったら、せめてこの大きすぎる付与だけでも抜いてくださいとお願いされたので、旬さんにそうしてもらった。
襖を締めるなり、わたしはすぐに尋ねる。
「それで、なにがわかったの?」
「今日読んだ本の中に、特定の人物の召喚に成功したというものはなかったようだ。
だが、地球とつながる経路を確保する、というようなくだりがあった」
「経路……?」
「俺は地球とハナムンと両方に存在しているから、今までそういう考えを持ったことはない。だが、体をそちらに送るには、やはり経路が必要らしい」
「あの留の黒い穴のこと?」
「あれはイレギュラーだろう。本の中にも留をつかうという記述はひとつもなかった。浮で経路をつくるってことだ」
「その経路って、どうやってつくるの?」
「そこなんだ。俺はそもそもそちらの視覚的な情報がないから、単純に経路という言葉からイメージするのはトンネルとか、線路とかなんだけど。それをどうやってそっちの世界につかなぐか」
「んー……、旬さんが得意なのは浮の具現化だよね。実際にトンネルをつくっても、だめってこと?」
「つくるだけならつくれるが、地球とつながるっていうところが難しい」
「イメージしずらいってこと? 今日のヒエンさんの術みたいに魔法陣みたいな感じはどう?」
「うまく書けるかわからないが、一応やってみるか」
旬さんが人差し指を立てた。
いつもの字を書く時のように、畳の上に丸を書いていく。
わたしには何も見えないので、ただ旬さんが畳の上を滑っているようにしか見えない。
「できた」
「どんなかんじ?」
「だめだな。やっぱりあの術は、先に印帳にいろいろ書いておかないと発動しないんだろう。丸を書くだけならできるが、俺のイメージが全然入っていかない」
「そっか……」
「机の引き出しの中のタイムマシンみたいに乗れたらいいのにな」
「そうだよね……、旬さん物体をつくるのは得意だもんね」
視覚情報がないから、イメージしづらいのか……。
ん、待って……。
地球からこちらに送りたいんだよね。
ハナムンから地球に送りたいわけじゃない。
えーと、なんだろう、今なにかひらめいた気が……。
「えと、えと……、旬さん、コルグさんの書いてくれた目、今もあるよね?」
「ああ、でも、これを最大出力にしても、マヌーケルンの青い光がくっきりするだけだし、そもそも浮流の通っていないものはほとんど見えない」
「ええと、あのね、カメラっていうか、うんと……。こっちの世界が見えることよりも、そっちの世界をこっちに映すことができたらどうかな? あ、えっと、プロジェクターっていうのかな?」
旬さんが考えるように止まった。
「そうか、こっちの視覚情報を映すか。美波、冴えてるな!」
「えっ、本当!? うれしい!」
「だとしたら、今まで使っていた浮信に近いな。そこから地球とハナムンをつなぐ経路の足掛かりが掴めるかもしれない」
「じゃあ、まずなにからはじめる?」
「そうだな。こっちの見ているものを送り、そっちで受け取るんだから、当然受け手がいるな。美波は浮が弱すぎるから、誰かに頼もう。それから、プロジェクター……よりもやっぱりスマホような通信機器をイメージしたいな。もっというと、WiFiっていうか、受信機そのものが受け手本人ていうのが望ましい。データのみが転送される状態だ」
「でも、旬さんは物体をつくるほうが得意でしょ?」
「そうだけど、そうしてしまうと、俺がそちらに転送されるというより、俺の形をした物体がそこにできてしまう気がする」
「そうなんだ……」
「俺の体そのものが転送データ、つまり体が経路を流れていかなきゃならないんだから。重要なのはまず経路だ」
「わかった、そうしたら誰に頼む?」
「俺に考えがある。時間をくれ」
「うん、わかった。いつでも言ってね」
「今から集中するから、肩から落ちないように、俺を縛り付けておいてもいいぞ」
「大丈夫、両手で持ってるから、安心して」
わたしは旬さんの手をそっと両手で包んで待った。
マッカリがそのたびに夕食やお風呂に呼んでくれたけれど、わたしはいつでも旬さんから連絡が来たら答えられるように断った。
夜、布団を敷きながら、マッカリが心配そうに声をかけてくれた。
「ご無理はなさらないでくださいね……」
「ありがとう。マッカリもお父さんのこと心配だね」
マッカリがうつむいた。
「刺されたときにもう縁は切れたと思っていたのですが、やはりすべてが悪い思い出ばかりではなくて……。実際血のつながった母のことよりも、父のほうが気になって仕方ないのです。殺されかけたのに、なにをばかなことをお思いでしょう?」
「そんなことないよ……」
「いいえ……。美波浮者はわたしを頭がいいとおっしゃってくださいましたが、わたしはばかなのです。父がわたしを認めてくれたときから、わたしは父に好かれたくて一生懸命でした。血のつながった父は早くに亡くなって、母とわたしは苦しい思いをしてきましたから、わたしは父ができたことがうれしかったのです。多少傍若無人でも、世間とは相いれない部分があっても、父に認められることで、わたしの家族像が保たれ、自分自身を肯定できました。父はわたしにいろいろと買って与えるのが好きでした。わたしが商談相手の腹の内を読んで、父がそれをうまくまとめ上げると、父はわたしにいつもご褒美をくれるのです。クランがうらやましがった着物や髪飾り、飾り紐や靴。わたしを飾り立てて、また商談へ連れて行くのが父でした。わたしも、父の役に立っていると感じることで、ここにいていいと、わたしにはそれだけの価値があると信じられたのです」
わたしは、旬さんの下から片手を抜いて、そっとマッカリの手に添えた。
「処刑の前に、父に一目……、たとえ話ができなくとも、遠くからでも一目会いたいです……」
「マッカリ、あなたの気持ちを話してくれてありがとう。明日、ハインリヒんさんに詳しく聞いてみよう。取り調べが終われば会えるかもしれないってヒエンさんもいっていたから、頼んでみよう」
「ありがとうございます……」
マッカリがいつかのようにわたしの手に伏せるようにして泣いた。
マッカリにとって、お父さんの存在がそれほど大きかったんだろう。
わたしは父と暮らしたことはないし、会ったこともない。写真すらない。
でも、もし側にいてくれたらどんな風だったろうと思ったことがないわけではない。
だけどやっぱり、世間的な父親というものはよくわからない。
仮にマッカリの気持ちを自分と置き換えるなら、晴美先生しかいない。
自分の人生の道しるべになってくれた晴美先生がもし死んでしまうとしたら、晴美先生が処刑されるなんてことは絶対にないけど、それでも、先生がいなくなってしまうなんて考えられない。
自分の船の帆をなくしてしまったような気分になる。
旬さんがこっちに来る前に、絶対晴美先生には話しておきたい。
地球からはるか離れた星で生きているって伝えたい。
晴美先生も、ずっと元気でいてくださいっていっておきたい。
「あなたがあなたを認めていくんだよ」
「え……?」
ふと、晴美先生の言葉を口にしていた。
「たとえお父さんがいなくてもお母さんがいなくても、誰もまわりにいなくても、あなたはここにいていいし、あなたには価値がある。誰かに認めてもらえなくても、あなたが自分の存在を許し、あなたの素直な心を認めてあげてね。わたしは素直なあなたのそばにいるよ」
「美波浮者……」
「晴美先生からの受け売りなの。わたしも、父と疎遠で、母が亡くなったから、いつも自信がなくて。体も弱いし、勉強もすぐ遅れちゃうしね」
「……そうだったのですか? わたしはてっきり……」
「家族のこと、クランにもあんまり話してないから。とにかく、父や母の代わりに、わたしの人生の骨組みっていうのかな、つくってくれたのは晴美先生なの。あなたの骨組みをお父さんがつくってくれたように。そういう存在は、本当に離れがたいよ」
「そうですね……」
「わたしはマッカリのお父さんみたいにはなれないけど、すくなくとも晴美先生みたいに、思い悩むマッカリの側にいたいと思うよ。ていうか、わたしにはそれくらいのことしかできないんだけど」
「すてきな先生ですわ」
「そうなの、しかも色白で美人で、ひばりみたいに歌がうまいの」
「ヒバリ、ですか?」
「うーん、鳥の名前なんだけど、こっちだとなんていうのかなあ」
「あら、美波浮者でもまだ知らないハナムン語があるのですね」
「うん、トラントランに帰ったら調べてみる」
「わたしもちゃんと下町言葉を勉強してみたいですわ」
「本当?」
マッカリが前向きな笑顔を浮かべて見せた。
笑みを浮かべて部屋を出て行く姿を見送って、わたしはまた旬さんの左手に視線を落とした。
その晩、わたしはできるだけ遅くまでずっとそうしていた。
久しぶりに、音楽室で合唱部の指導で歌う、晴美先生の姿を夢に見た。
入っても続けられないので、わたしは部活には入っていなかったけど、本当は合唱部に入りたかった。
晴美先生は、わたしが廊下の陰で歌声を聞いていたのを、知っていたのだ。
今でも、はっきりと耳に思い出せる。
はるか遠くの空まで飛んでいけそうな、あの歌声が恋しい。
8
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

神様、ありがとう! 2度目の人生は破滅経験者として
たぬきち25番
ファンタジー
流されるままに生きたノルン伯爵家の領主レオナルドは貢いだ女性に捨てられ、領政に失敗、全てを失い26年の生涯を自らの手で終えたはずだった。
だが――気が付くと時間が巻き戻っていた。
一度目では騙されて振られた。
さらに自分の力不足で全てを失った。
だが過去を知っている今、もうみじめな思いはしたくない。
※他サイト様にも公開しております。
※※皆様、ありがとう! HOTランキング1位に!!読んで下さって本当にありがとうございます!!※※
※※皆様、ありがとう! 完結ランキング(ファンタジー・SF部門)1位に!!読んで下さって本当にありがとうございます!!※※

完結 シシルナ島物語 少年薬師ノルド/ 荷運び人ノルド 蠱惑の魔剣
織部
ファンタジー
ノルドは、古き風の島、正式名称シシルナ・アエリア・エルダで育った。母セラと二人きりで暮らし。
背は低く猫背で、隻眼で、両手は動くものの、左腕は上がらず、左足もほとんど動かない、生まれつき障害を抱えていた。
母セラもまた、頭に毒薬を浴びたような痣がある。彼女はスカーフで頭を覆い、人目を避けてひっそりと暮らしていた。
セラ親子がシシルナ島に渡ってきたのは、ノルドがわずか2歳の時だった。
彼の中で最も古い記憶。船のデッキで、母セラに抱かれながら、この新たな島がゆっくりと近づいてくるのを見つめた瞬間だ。
セラの腕の中で、ぽつりと一言、彼がつぶやく。
「セラ、ウミ」
「ええ、そうよ。海」
ノルドの成長譚と冒険譚の物語が開幕します!
カクヨム様 小説家になろう様でも掲載しております。

俺様上司に今宵も激しく求められる。
美凪ましろ
恋愛
鉄面皮。無表情。一ミリも笑わない男。
蒔田一臣、あたしのひとつうえの上司。
ことあるごとに厳しくあたしを指導する、目の上のたんこぶみたいな男――だったはずが。
「おまえの顔、えっろい」
神様仏様どうしてあたしはこの男に今宵も激しく愛しこまれているのでしょう。
――2000年代初頭、IT系企業で懸命に働く新卒女子×厳しめの俺様男子との恋物語。

帰って来た勇者、現代の世界を引っ掻きまわす
黄昏人
ファンタジー
ハヤトは15歳、中学3年生の時に異世界に召喚され、7年の苦労の後、22歳にて魔族と魔王を滅ぼして日本に帰還した。帰還の際には、莫大な財宝を持たされ、さらに身につけた魔法を始めとする能力も保持できたが、マナの濃度の低い地球における能力は限定的なものであった。しかし、それでも圧倒的な体力と戦闘能力、限定的とは言え魔法能力は現代日本を、いや世界を大きく動かすのであった。
4年前に書いたものをリライトして載せてみます。
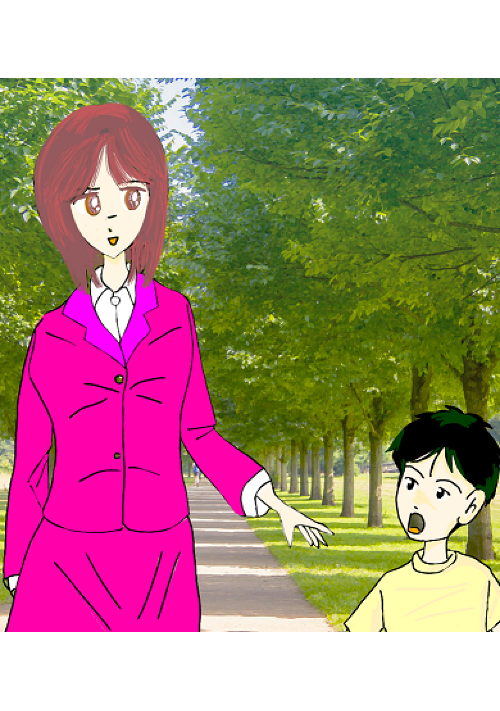
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

僕に仕えるメイドは世界最強の英雄です1~またクビになったけど、親代わりのメイドが慰めてくれるので悲しくなんてない!!~
あきくん☆ひろくん
ファンタジー
仕事を失い、居場所をなくした青年。
彼に仕えるのは――世界を救った英雄たちだった。
剣も魔法も得意ではない主人公は、
最強のメイドたちに守られながら生きている。
だが彼自身は、
「守られるだけの存在」でいることを良しとしなかった。
自分にできることは何か。
この世界で、どう生きていくべきか。
最強の力を持つ者たちと、
何者でもない一人の青年。
その主従関係は、やがて世界の歪みと過去へと繋がっていく。
本作は、
圧倒的な安心感のある日常パートと、
必要なときには本格的に描かれる戦い、
そして「守られる側の成長」を軸にした
完結済み長編ファンタジーです。
シリーズ作品の一編ですが、本作単体でもお楽しみいただけます。
最後まで安心して、一気読みしていただければ幸いです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる