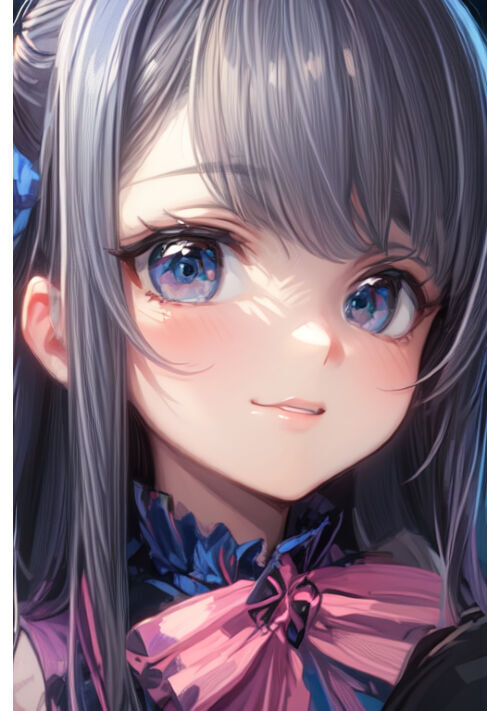30 / 35
時空が重なる奇跡
動き出した歯車
しおりを挟む
語学学校の帰りに寄った行きつけのカフェで私は頭を抱えていた。
夕方の4時過ぎということもあり、殆どの席は埋まっていて、一人で本を読んだりタブレットで映画を見ている人がいれば、グループでお喋りを楽しんでいたりする。オランダでは陽気で騒々しいことを好む人が多いけれど、ドイツは真面目な気質の人が多いせいか、こういった場所でもお喋りの時は声を低くし周りに迷惑をかけないように気配りをしてる人が殆どだ。稀に騒々しいグループがいるなと思うと、大概が英語や外国語を話しているドイツ人以外の集団だったりする。
混んでいる割にBGMのジャズが軽やかに耳に流れ込むこの場所で、私はハァと深い溜息をついた。
八方塞がり状態といえばいいのか、それとも行き詰まったといえばいいのか。打つ手がないとはまさにに今の状態だろう。
両手で顔を覆っていると、カタンと椅子が動く音がした。
「カノン?どうしたの~?」
アナが大荷物をかかえて目の前に立っているのに気がつき、私は苦笑いしながら隣の椅子を引いた。ヴァイオリンのケースを注意深く壁に立てかけ、ボストンバッグを肩から下ろしたアナが「よっこらしょ」とつぶやきながら私の隣に座る。
「カノンらしくないね、すっごいストレスかかってます、って顔」
アナは、無造作に肩にかけていたグレーにフューシャピンクの花模様が織り込まれたストールを丁寧にかけなおして、心配そうに瞬きをしながら私の顔を覗き込んだ。
私はiPadの電源を落として、また、ハァと溜息をついて苦笑いした。
「落とし穴があったっていうか、不測の事態になっちゃって……」
独り言のようにそう答えて、きゅっと唇を噛んだ。
「物事が進むべき方向に進んでいるように見えたのに、渡ろうと思った橋が行く先になくて、渡し船も見当たらず、向こう岸に渡れないって感じかなぁ」
「それってユリウスのことだよね?」
「うん……」
私は苦笑しつつ、薄暗い窓の外に目をやった。夕方の4時すぎだというのに、もう空は夕闇に包まれ、街はクリスマスの飾り付けのイルミネーションが点灯している。
11月の終わりになり、ベルリンは一気にクリスマスらしくなってきた。カフェもレストランも、デパートも、クリスマスの飾り付けで埋め尽くされ、日が落ちると煌びやかなイルミネーションが人々の目を引く。観光客がお目当てに来るクリスマスマーケットも昨日から始まっていて、私も今週末はクラウスと一緒に行く約束をしている。
「12月6日の聖ニコラウスの日前後はバースのスパに行くって決まったんでしょう?」
「うん……ユリウスも行くから、結局執事のカールが全部手配することになって、泊まるホテルとか、クラウスとヨナスの仕事のスケジュール調整とか全部、おまかせだったの。それで、一昨日、日程と宿泊先の連絡が来たから、念の為と思って早速、レオナにメールしてみたの。詳しいことは言わなくても、その時期、ファームにいるのかどうかは聞いておこうと思って」
「クリスマス前はラベンダーファームのショップとカフェは開いているってことだったよね」
丁度カフェのお姉さんがアナの注文したカフェマキアートをテーブルに置いた。スチームミルクで描かれた大きなハートに、二人で顔を見合わせてクスッと笑う。ちょっとしたことでハッピーな気持ちになれるものだ。
ブラウンシュガーをそのハートのど真ん中にドバッと威勢良く注ぎ込むアナを眺めつつ、私はiPadの電源を入れた。
そうなのだ。レオナがラベンダーファームに居ることを確認しようとメールしたら、予想外の返信が届いたため、頭を抱えてしまっている。
「レオナからの返信はなくて、ショップのスタッフからの代理返信で、レオナは忙しくてその時期ショップにはいないって……」
「えっ」
「オーナーがショップが開いている時期に不在なんて変だよね」
「うん……それで、どうして居ないのかって聞いたら、病院にいる予定だって」
「病院?」
アナが眉を潜め、不安げに顔を曇らせつつ、私が見せたそのメールにさっと目を通し、呟いた。
「ほんとだ、レオナはその時期は病院にいる予定って書いてある」
私は小さく頷いた。
「私も心配になって、レオナが病気なのかって聞いたら、違うって。でもそれ以上は、スタッフとしてはオーナーのプライバシーに関わることは答えられないって言われたの」
「ふうん、まぁ、病気じゃないってのならほっとするけど……ん?そうすると、他の誰かが病気とか?」
アナがハッとしたように目を見開いた。
彼女も私が考えたことと同じことを想像したらしい。
「やっぱり普通そう考えるよね」
よく考えなくても誰だって想像してしまうだろう。レオナが病気じゃないのに病院にいるということは、誰か大事な人が入院しているという可能性だ。
しばらく沈黙しつつマキアートを飲んでいたアナが、ぽつりと言う。
「でもだからって、その人がご主人とか決まったわけじゃないし……親友とか、親戚や兄弟だってこともあるよ」
私は期待を込めて大きく頷いた。
「私もそう考えて、このまま彼女とユリウスの再会を諦める理由にはならないと思ってる。だって、レオナは、ユリウスとの再会の可能性については否定はしなかったし。勿論、会ってくれるとも言わなかったけど……絶対無理な状況なら、最初からはっきり断ってくれたと思うし」
「うん、そこは激しく同意する!」
アナがにっこりと微笑むと、私もつられて笑顔になる。
「ありがとう、アナにそう言ってもらうとポジティブになれそうな気がする」
「なれそうな気がするする?ダメだよ、ならないと!」
ちょっと拗ねたように眉間に皺を寄せて睨まれ、私は苦笑した。
「うん、わかった!ポジティブにね。あ~でも、せっかくバースまで行くのに、レオナに連絡つかないんじゃ、がっかり……」
「カノンったら、バースなんていつでも行ける距離なんだから、今回は単純にホリデーを楽しむことに重点を置けばいいんだよ。クリスマスシーズンに突入してるし、きっと素敵な思い出になるよ。いいじゃん、豪華スパ旅行。執事付きの貴族御一行様なんて、私から見たら夢の世界」
「執事付きの貴族御一行様かぁ……確かにそうだよね」
私はその響きに不思議な気分になった。大体、貴族なんて過去の社交界のみ有効な肩書きで、現存しないと勝手に思い込んでいたものだから、その末裔がいることに気がついて驚いたものだ。でも良く考えれば、まだ世界中に王室は存在するし、日本だって皇室があるわけだから、伯爵や公爵の子孫がいてもおかしくない。ただ、ドイツでは貴族制度は廃止されているから、あくまでも、血筋ということだが、実際、いまだにその名残は残っている。先日知ったことだが、クラウスの本名はとても長く、正式名にはゾマーフェルドの前にフォンが付いている。このフォンが付くと貴族の末裔だということらしい。
私はふと、昨晩クラウスから聞いたことを思い出した。
「あのね、ユリウスは脳梗塞の患者だから、飛行機は当分乗ってはいけないんだって。そうすると陸路になるから移動時間がかなりかかるんだけど、ユリウスは行く気満々だってことで、車で行くことになったらしいの」
「ドイツからUKまで?確かに陸路でも行けるよね、フランスからだったらかなり近いって聞いたことある」
「そうなの。で、車で何時間も座ってるの、体に悪いんじゃないかと気になってクラウスに聞いたら、リムジンだから平気だって。負担にならないように、どこかで途中一泊していくらしいから、片道2日もかけていくことになるんだけど、ドクターも賛成してるから、強行することになったんだって」
「リムジンバス、じゃないよね。あの長い車体のリムジンだよね」
「そう。車、何台もガレージにあったから、きっとそこにリムジンもあったんだろうね」
「どんなやつなんだろう?」
「えーとね、確か……そう、メルセデスのマイバッハ・プルマンとか言ってたよ」
記憶を手繰り寄せてその名前を言うと、アナが私のiPadを手に取った。私もアナに寄り添って検索画面を覗き込む。
画面に表示されたゴージャスなリムジンのイメージに二人して言葉を失う。
全長6メートル半という想像を超える大きさに、重量感のある革張りの車内、ラグジュアリー感溢れる贅沢なインテリア。カスタム仕様になれば軽く一億は超えると書かれている。その堂々たる車体の威圧感も半端ないが、なにより、一般人とは桁の違う世界中に唖然とする。
しばらく呆然と、画面いっぱいに映されるメルセデス・マイバッハ・プルマンの豪華な写真のスライドショーを眺めていたが、やがてアナがはっと思い出したように腕時計を見た。
「あっ、いっけない、もうリハが始まっちゃう!」
時計を見ると既に5時半になっていた。
アナはこのカフェの近くにあるプライベート・コンサートホールで行われる予定になっている、クリスマスコンサートのリハーサルに参加しなければならないのだ。
立ち上がってコートを羽織りながら、アナが私のほうを振り返った。
「ね、私の顔、大丈夫かな」
「え?顔?」
びっくりしてアナの顔をじっと見る。相変わらずの透き通るような白い肌、黒目がちで長い睫毛に縁取られた大きな瞳、やや紅潮した頰が愛らしく、彼女を実際の年齢より幼く見せている。今日はちょっとだけ、ローズピンクのルージュを引いているからか、ドールフェイスっぽい雰囲気があって、普段のお茶目な感じがあまりしない。
「うん、いつも通り、美人音楽家って感じで見惚れちゃう」
思った通りに答えると、アナがはにかむように目を細めて、トンっと私の肩を押した。
「やだ、おだてすぎ!でもありがとう」
「おだててないよ!でも珍しいね、アナが自分の顔を気にするなんて」
初めてこんなことを聞かれたから、不思議に思ってそう言うと、アナが肩をすくめた。
「だってね、アダムがリハ中の写真を撮りに来るっていうものだから、私のHPに、写真を追加するんだって」
「なるほど」
私は思わず笑顔になり、くすくすと笑いだした。以前のアナなら、アダムが写真を撮ろうといつも通り自然体なままだっただろうが、ちゃんと恋人になった途端、彼の向けるレンズには美しく写りたいと思うようになったんだろう。
笑っている私を不満げに見て、なにか言おうと唇を尖らせたアナだったが、時間がないのを思い出したらしく、急いでヴァイオリンのケースに手を伸ばすと、また、「よっこらせっ」と掛け声をかけてそれを抱え上げた。
「それじゃぁ私は行くね!週末に一緒にクリスマスマーケット行けるかどうか、後で連絡するから」
「うん、待ってる!リハーサル、頑張ってね。アダムにもよろしく」
「オッケー」
アナはスカーフを翻し、早足でカフェを出て言った。彼女が出た後、ドアが音も立てずにそうっと閉まったのを合図に、私もそろそろと帰る準備を始めることにする。一人で出歩けるようにはなったけど、まだ捻挫の痛みが残っているのでゆっくりとしか歩けないのだ。
今晩はクラウスも7時過ぎには帰ると言ってた。夕食のメニューを考えながら、私は向かいの椅子にかけていたコートに手を伸ばしたのだった。
土曜日の午後1時を回る少し前に、私とクラウスはアレクサンダープラッツの世界時計塔の下に居た。昨晩、アナから連絡が来て、一緒にクリスマスマーケットに行くことになっていた。
普段は公共交通機関で出かけることの多い私達だが、今日は車で来たので、駐車場を確保するためにちょっと早めに出て来たものの、思ったよりスムースに車を停めることが出来たので、約束の時間前に待ち合わせ場所にいるわけである。
「なんだかこういう所、ドキドキする」
私が独り言のように呟いて周りを見渡すと、携帯を見ていたクラウスが顔をあげて、駅の方をみた。クリスマスマーケット目当ての観光客も多いし、人の声にクリスマスミュージックで街全体がお祭りモードだ。街のいたるところはクリスマスのデコレーションで飾られており、街行く人も、サンタの帽子を被っている人やクリスマスプレゼントを抱えている人など、普段とはちょっと雰囲気が違い、とにかく見渡す限り笑顔、そして笑顔。
自然と頰が緩み、私はじっとしていられなくなって、隣に立つクラウスの腕にぎゅうっと抱きついた。
クスッと笑った彼が、身をかがめて私の顔を覗き込む。私と目が合うと、満足そうな笑みを浮かべ、チュッと音を立てて私の額にキスをした。くすぐったくて彼の胸に顔を埋めた。子供のように興奮している自分が少し恥ずかしい。
ずっと楽しみにしていた、ドイツの風物詩、クリスマスマーケットに愛する彼と一緒に来ている。しかも、親友カップルとのダブルデートだというのに、ドキドキしないなんて絶対無理!
気温は一桁で凍えるようなのに、今日は寒いという感覚は感じないくらい気持ちが高揚していた。
「カノン!」
雑踏に紛れて私を呼ぶ声が聞こえ、顔をあげると、人混みの向こうに、真白なコートを羽織ったアナが駆けてくるのが見えた。
反射的に手を挙げて、駆け寄ってきたアナとお互い手を取り合う。
「ごめん!待った?」
「ううん、大丈夫だよ」
「電車が混んでて、一本見送ったからちょっと遅れちゃった」
アナは呼吸を整えるようにふぅと白い息を吐くと、私の背後に視線を動かした。
「やぁ アナ」
クラウスが目を細めて笑うと、パッと花が開くようにアナが明るい笑みを浮かべた。
「バイクの時以来だね。一応、改めて、初めまして、、かな?」
「そうだな。初めまして、アナ」
「よろしく、クラウス!」
二人が肩を抱き合って挨拶を交わすのを見て、私は嬉しさにぶるっと震えた。
少し遅れてアダムがやってきた。
彼はクラウスと肩を抱き合い、一言、二言交わし、私の肩を抱き寄せていつもの挨拶を交わす。その後、アダムはアナの頭を軽く小突いて、ムッとして振り返った彼女を軽く睨んだ。
「走るなって言ったの、聞こえてなかったのか」
「聞こえてたよ。いいじゃん、少しくらい」
アナがさっと私の後ろに隠れると、アダムが呆れたように、はぁと小さくため息をした。
「どうしたんだ?」
クラウスが不思議そうにアダムに聞くと、アダムがちょっと苦々しげに笑った。
「こいつ、クリスマスのコンサートが控えているのに、昨晩、階段から転げ落ちたんだ」
「えっ」
私もびっくりしてアナを振り返ると、当の本人は素知らぬ顔で明後日の方を見ている。
「幸い、かすり傷で演奏には響かない怪我だったが……2階から椅子を抱えて転げ落ちるというアクシデントだったことを思えば、奇跡的な軽傷だったんだ」
「椅子ごと落ちたって、アナ、何やってたの?!」
「えー……ハシゴが見当たらないから、2階の棚のものを下ろすのに、1階から椅子を持っていってたの。用が済んで、椅子を1階へ戻そうと階段降りてたら、滑ったんだよね。つるっと」
あははー、と屈託無く笑うアナを見て、アダムが頭が痛いというようにこめかみを押さえた。
「玄関のドアを開けるなりすごい騒音と一緒に2階から転げ落ちてくるアナと椅子が視界に入った時は、心臓が止まるかと思った。椅子は完全に大破したほどの衝撃だったし」
アダムの心配はごもっともだ。バイオリニストのアナにとっては、怪我は絶対に避けなくてはならないものだ。
「俺がジム帰りに寄ると約束した時間まで後数分とわかっていて、何故自分で椅子を2階まで運んで棚からものを下ろそうとするのか、理解できない」
「だって、待てなかったんだからしょうがないでしょ」
「たった数分のことが待てないとは、それだけ急ぎで重要なものだったんだろう」
クラウスが横から助け船を出すと、アダムが苦々しく笑う。
「……箸置き、ってやつだったけどね。箸を置く小さな陶器」
「箸置き……のために、2階まで椅子運んで?」
私とクラウスが言葉を失ってアナを見ると、彼女は眉間にシワを寄せて反論した。
「あれ、京都の町屋通りで見つけた、清水焼きの貝合わせ箸置きなの!平安時代のデザイン画が焼かれてて、とっても綺麗だから、夕食の時にアダムに見せて驚かせようと思ったんだもん」
なるほど。
だから、アダムに頼みたくなかったわけだ。ただの箸置きというわけではなかったなら、アナの気持ちもわからないでもない。
「確かに素晴らしい逸品だったが、それも擦り傷ですんだから言えることだ。腕を骨折でもしてたら演奏どころじゃなかったことを忘れるな」
アダムに説教されて、不満げに唇を尖らせてそっぽを向くアナ。
恐らく繰り返し言い聞かせられているに違いない。
少しいじけたように明後日の方を見ている彼女のかわいい捻くれように、私は笑いだしてしまった。
「わかった、アダム!今日は私がしっかりアナを捕まえておくから!」
私はそう言って、アナと腕を組んでみせた。
クラウスが可笑しそうに目を細めながらアダムを振り返る。
「いや、これじゃ尚更心配だろう」
「クラウスの言う通りだ、アナ、こっちに来い」
アダムがアナに手を伸ばし、引っ張ろうとする。
「どうして?なぜ尚更心配になるの?」
納得出来ず抗議すると、クラウスが私の腕を取りながら諭すように答える。
「君だって捻挫でやっと最近歩けるようになったばかりだろう。二人揃って転ばれたら俺たちが困る」
指摘されてハッとする。自分がまだ歩くのに痛みが残っていることを思い出す。だから今日は車で来たんだった。私がレンガを敷き詰めた道路の歪みにつまづいて、アナを道連れに転んだらもとの黙阿弥。
「さぁ、これくらいにして早速マーケットに行こう」
クラウスのその言葉に、私達は駅の向こう側へ目を向けた。
マーケットの華やかで楽しい出店を順番に見ていく。クリスマスの焼き菓子に毛糸で編まれたストールやグローブ、クリスマスのディナーテーブルを飾るカトラリーや手作りのキャンドル。行き交う人々の幸せそうな笑顔に興奮気味の幼い子供達。
フルーツを串に刺してチョコレートのコーティングをかけたものは見た目も可愛らしく、店頭の前で足を止めてじっくりと眺めた。特に目を引くのは、ドイツのクリスマス向けの伝統的な木製デコレーション。繊細なところまで丁寧に彫刻された品物はそれは見事だ。手作りで作られたツリー用の小さなオーナメント、デザインのバリエーションも豊かなくるみ割り人形、イエスキリストが生まれた馬小屋のセット……見事な職人技に目を奪われる。
商品の写真を撮ろうとしていた観光客に、店員が、大きく手を振りながら、No!No photo!と声を挙げている。彼等にとっては商売のために出店しているのに、観光客が商品は買わずに写真だけ撮って、インスタやツイッターにあげたりするのが気に入らないんだろう。
可愛らしいツリー用のオーナメントが沢山あったけれど、クラウスが実家にあるクリスマス用のデコレーションを一部こちらへ送ってもらうよう手配してもらっているから、私たちが買う予定のツリー用には、これといって新しくオーナメントを揃える必要はない。だから私達は、代わりに、クリスタルガラス製品で、窓辺に飾るのにぴったりなエンジェルや雪の結晶のオブジェを数点購入した。キャンドルを添えて飾れるので、夜はクリスタルガラスがキラキラと輝いてきっとメルヘンチックな窓辺になるだろう。アナとアダムも何やら相談しながらいくつかツリー用のオーナメントを買っている。
「ところで、クリスマスや新年はどうするんだ?」
アダムが私達のほうを見て聞いたので、クラウスが答える。
「クリスマスは多分、俺の実家に行って、新年はオランダに行こうと思ってる」
「え」
新年はオランダ、と聞いてびっくりしてクラウスを見た。クラウスが笑いながら私の肩を抱いて、いたずらっ子のようにウインクした。
「君のお茶目なおばあちゃんに会いにいくと約束したまま、まだ果たせていないだろう?」
「本当に?オランダまで一緒に行ってくれるの?」
「もちろんだ。その予定で仕事のスケジュールも調整済みだ」
私も正直、おばあちゃんが新年をどう過ごす予定か気になっていたので、一人でも行こうと考えていた矢先のことだったから、クラウスの提案に嬉しさで胸がいっぱいになる。
「ありがとう……おばあちゃん、すごーく喜ぶと思う!」
心の底からお礼を言うと、クラウスがクスッと笑って頷いた。
「そっちはどう過ごす予定なんだ?」
クラウスがアダムに聞くと、アダムとアナが顔を見合わせる。
「26日まではアナがコンサートで埋まっているから、その後はゆっくり過ごそうと思ってる」
アダムはそう答えた後、少し間を置いて、何かを思案するようにゆっくり瞬きした。
「あっ、あの店」
アナが後ろにある店に気付いて、私達から離れてチェックに行くのを見ながら、アダムが低い声でつぶやいた。
「年末は実家に行くことにしたんだ」
それを聞いて、クラウスが少し驚いたように目を見開いた。
「ねえ!こっちに来て!グリューワインあるよ!休憩しよう!」
アナの嬉しそうな声が聞こえた。
スパイス入りの温かいグリューワインをそれぞれ注文し、空いていた真っ赤なテーブルクロスの席につく。風に揺れる炎が灯る白いキャンドルも、クリスマスらしく蔦の葉や赤い木の実のデコレーションで飾られている。肌に刺すような寒風が吹く中で、温かいグラスから柔らかな湯気をたてる真紅のワインをそっと口に含むと、スパイスたっぷりでフルーティな甘さがのどを滑り落ち、お腹の中からじんわりと温まっていく。自然と満たされた気持ちになり、ゆっくりと深呼吸する。味は違うけど、ほとんどアルコールを飲まない私でも楽しめる甘酒を思い出した。
「おまえは実家から離れてもう随分と時間が経っていたな」
クラウスの問いにアダムが苦笑し、頷いた。
「先日、4年ぶりに連絡したんだ。まぁ、久しぶりだったから、母親が電話口で泣いていた」
「両親とも元気だったか」
「すこぶる元気だったさ。それに、俺もあれから考え方を変えたから、親父のことも少しは受け入れる気になった」
「そうか。それは良かった。結局のところ、血の繋がりは何をしても切れないんだから、家族としてうまくやっていくに越したことはないだろう」
クラウスの言葉に、アダムが頷きながらグリューワインのグラスを傾ける。キャンドルの炎に照らされたブロンドの前髪が風に吹かれてキラキラしていた。
「母親から聞いたんだ。親父のやつ、しばらく前にベルリンにアパート買って、たまにこっちに来ているらしい。だからといって俺に連絡はしてこなかったが」
「アパート?」
「新築売り出しのいい物件があったから、投資のために買った、と母親には言ったらしいだが、たまに工事の進み具合のチェックにベルリンに来てるらしい」
アダムはちょっとため息ををつくと、テーブルの上に置かれたシルバーのお皿にあった、ドイツのクリスマスケーキ、シュトレンのスライスを一切れとり、半分に割ると片方をアナに渡す。粉砂糖が粉雪のようにほろほろと、真っ赤なテーブルクロスの上に舞い落ちた。
「親父は、そのアパートを俺にやろうと思ってるらしくて、部屋の壁をぶち抜いてアトリエスペースを作ったり、画材や作品を保管する空調を整備したガレージを作ったり、業者に工事させてたらしい」
その話に、私とクラウスはびっくりして顔を見合わせた。
親の援助を拒否して連絡を絶っていたアダムのために、父親は隠れてそんなことをしていたのか。息子がそれを受け入れるかどうかも分からないのに。
親というものは、子供のためになることならと思えば、例え嫌われたり、拒絶される可能性などのリスクがあっても、結局は行動してしまうのだろう。
クラウスが目を細めて、楽しそうに笑った。
「どうするんだ、そのアパート。親孝行と思って受け入れる気になったか?」
アダムはしばらく黙っていたが、グリューワインの残りを一気に飲んで、ふっと肩の力を抜いたように優しい笑みを浮かべた。
「条件付で入居してやるって言った」
「えっ、それは聞いてない!わかんないって言ってたじゃない」
アナがびっくりしたように声をあげた。
「昨晩決めて、今朝電話で言ったんだ」
「えー、そうなの?場所、遠いの?」
今は二人とも歩いていけるくらい近いところに住んで行き来しているから、同じベルリン市内でも電車に乗らないと会えない距離になるのは寂しいのだろう。アナが不満そうにじっとアダムを見つめると、彼はアナが持っていたグリューワインのグラスを取って、一口飲んだ。
アナも私と同じくそれほど飲めるタイプでないので、グラス半分を飲んだ以降、口をつけてなかった。
「ね、アダム。どんな条件出したの?」
気になって、彼が言い出すのを待てずに私が聞くと、アナのグラスを空にしたアダムはテーブルに片肘をつきながら答えた。
「……防音ルーム」
「……?」
なんのことだか分からず、私はじっとアダムの顔を眺める。
彼の美しい真っ青な瞳は何かを期待させるような不思議な光があった。
隣のクラウスがクスッと笑いながら、アダムの頭を片手で小突く。
小突かれて乱れた前髪を無造作にかきあげながら、アダムは隣で目を丸くしているアナに目をやった。
「君もそろそろ今のシェアハウスの契約切れるんだろう?」
契約が切れる?
「それで親父さんはなんだって」
横から既に全てを察した様子のクラウスが聞くと、アダムは肩をすくめた。
「あっちも交換条件出して来たさ」
「だろうな。当然だろう」
クラウスが楽しげに笑いながら頷いて、アナの顔を覗き込んだ。
「アナ、年末はアダムと雪合戦だな。ノルウェーの冬の寒さは覚悟したほうがいい」
アナが驚いたように瞬きして、アダムを見た。
「……どういうこと?」
アダムは少しの間アナを見つめていたが、コートの内ポケットから携帯を出すと、それをテーブルに置いた。皆で覗くと、工事中のアパートの写真があった。何枚か見ていけば、それがかなり大きい新築アパートで、レイアウトを改造しているのがわかる。打ちっ放しのコンクリートの壁の部屋はものすごく広く、30畳くらいはありそうで、恐らくここがアトリエだろう。複数の部屋があり、見た所レイアウトが概ね完成したところで、内装はこれからという状態だ。
「防音ルームあれば時間に関係なくバイオリンも弾けるだろう」
私はようやく全てが分かって、急にドキドキしてきた。
アナの為の防音ルームだ!
アダムが携帯を取ってコートの内ポケットにしまいながら、目をまん丸にして絶句したアナを見つめて微笑んだ。
「昨晩君が階段から真っ逆さまに落ちてくるのを見た後に思いついたんだ」
「……アダム」
「親父のやつ、防音ルームも作ると即答したさ。その代わり、年末に顔見せに帰ってこいと。防音ルームを使う彼女も連れて来るってのが条件だと」
その言葉に、アナが突然両手で顔を覆ってテーブルに突っ伏した。
彼女も驚いたに違いない。アダムが離れたところに引っ越してしまうと思っていたら、その計画に、自分も入っていたと判明したのだから。しかもアダムの両親に紹介されることになったなんて、思いもよらないニュースの連続だったに違いない。
3人ともしばらく黙っていたが、やがて、耳を赤くしたアナが顔を上げて、掠れた声でつぶやいた。
「もう、アダム、いきなりすぎるよ……」
いつになく弱々しいアナをアダムが笑いながら片手で抱き寄せ、なだめるようにそっと髪を撫でた。いつも威勢のいいアナがこんなに照れて参っている様子がとても新鮮で、幸せそうな二人を眺めながら、私も嬉しくてクラウスと目を合わせ頷きあう。
「親父の押し付けがましい援助はずっと鬱陶しかったが、さすがにあれだけいいロケーションで、スペース的にも理想的なアパートは、今の俺には確保出来なかった。タイミング的にも、今の場所が手狭になってきて、新しくアパートを探すか、別にアトリエを借りるか考えていたところだったから、正直なところ、有難い」
「一人っ子のおまえしか生き甲斐がないんだろう。親孝行と思って好意を受け入れるのもたまには悪いことじゃない。少なくとも、おまえのアートに宣伝投資するのではなく、応援するためのベースを作ってやりたいなんて、健気なものだ」
楽しそうにクラウスがそう言うと、アダムが苦笑して頷いた。
アダムの実家はかなりの資産家だが、彼がアーティストにキャリアチェンジした後、財力にものを言わせてアダムを業界に売り込もうとした両親を彼はかたくなに拒否し、もうずっと自分だけの力で頑張って来たのだ。そして今、彼の才能は花を開き、雑誌やネットニュースでも掲載され、国内外から大きなプロジェクトのオファーが入ってくるようになっている。
つい先週も、マリアとコラボして作った作品を、ドイツに移住しているシリア難民支援のチャリティイベントに寄贈したとテレビのローカルニュースで見た。
「レイアウトは親父がもう完成させてたから、内装はヨナスに手伝ってもらって自分でやることにしたんだ。親父にやらせるとアパート中の壁を病院みたく真っ白に塗りつぶしかねない」
アダムの言葉に思わず笑いが漏れる。アーティストで器用なアダムのことだ、きっと彼等にぴったりのアパートを作り上げることだろう。
ようやく落ち着きを取り戻した様子のアナが、はぁと大きなため息ををついた後、嬉しそうに微笑んだ。
「一足早くクリスマスと新年が来たみたい!アダム、ありがとう。びっくりしたけど、ほんとに嬉しい。新しいシェアハウス探すの、結構難航してたし……」
ドイツでは、結婚していない恋人同士が同棲するのは全然珍しいことではない。若者は実家を出た後、ほとんどの人は一人暮らしする経済力がないため、シェアハウスで暮らすことが多い。だからといって、ハウスメイトと必ずしもうまく行くとは限らないので、ある程度真剣な付き合いをしている恋人がいるなら、同棲することを選ぶ人が多い。もちろん、破局した時は、場合によっては同居解消が泥沼化する可能性は無きにしも非ずだが。
「来年は私達皆、引っ越しだね」
「ほんと、偶然にもタイミング重なったね」
アナがくすぐったそうに笑うと、まだ驚きが消えないかのように大きく肩を上下させて深呼吸する。
私も一応まだ自分のアパートがあるので、現在、クラウスのアパートに入り浸りになっているものの、正式な同棲は来年からとなる。
ひとしきり笑った後、まだまだ続く広いクリスマスマーケット会場巡りで楽しい午後は過ぎていった。
ようやく朝日が昇り始め空が明るくなってきた土曜日の午前8時すぎ、外で車のクラクションが鳴ったのが聞こえ、私は小走りで玄関の扉を開け外を確認した。見慣れたメタリックシルバーの大型のベンツが停まっている。
「クラウス、来てるよ!」
私が後方に声を張り上げると、スーツケースを2つ抱えた彼がベッドルームから出て来た。今日の彼はいつもよりリラックスした装いだ。久し振りに彼がジーンズを穿いているのを見た気がする。Dieselのネイビーブルーのジーンズにブラックのトップス、チョコレートブラウンのレザーコート。
ふと、出会って間もない頃の「ニッキー」を思い出して、甘酸っぱい気持ちになる。
「さぁベイビー、戸締りは君の仕事だ」
美しいブルーグレーの瞳を優しく細めて微笑む彼に、大きく頷いて見せた。
表に出て、私が注意深く鍵を閉めて確認している間に、彼はもう階段の下に停まっている車のトランクにスーツケースを入れ、私が階段を降りようと振り返った時には戻ってきていて、当たり前のように手を差し出していた。
私の怪我の件では、クラウスは私が戸惑うくらい心配しており、もう事故後、二週間が経ち普通の歩行には問題なくなっているにも関わらず、こうして文字通り手取り足取りサポートしてくれる。もう大丈夫と言っても、私が無理していると疑っているものだから、私が何言っても変わらない。この度を超える過保護ぶりには流石に兄のヨナスもからかって笑うが、クラウスはそれでもやめない。
「ありがとう」
素直にお礼を言って、手を繋いでゆっくり階段をおりる。
私の背中の内出血の跡が数カ所残っているから、それが完全に消える頃には彼も心配しなくなるだろう。
「おはよう!」
後ろのドアをマリアが開けてくれたので乗り込むと、クラウスがドアをゆっくり閉める。
続いて運転席のヨナスの隣にクラウス乗り込む。
ついに、バースのスパへ行く日になったのだ。
眠そうにあくびするマリアが、後部座席で伸びをした。
「スパに持って行く水着を探すのに時間かかって、睡眠不足なのよ。まさか冬に水着使うと思ってなかったから、夏物の衣類の山の中からそれを見つけるの大変だったわ」
車が発進し、同時に音楽が流れ始めた。ロマンチックなギターのイントロに続き、ハスキーで深みのある女性のイタリア語の歌が重なる。
「あ……Laura PausiniのE Ritorino da Teのアルバム」
ドラマティックなこの曲は私を切なくも情熱的な気持ちにする。
これから始まる旅行の1番の目的を胸に抱いて、私はぎゅっと両手を握りしめた。
どうなるかなんて、誰にもわからない。
でも、あの地でしか、奇跡は起こらない。
運命というものが存在するのなら。
偶然や必然というすべての条件が重なれば。
神様、お願い。
目を閉じれば脳裏に鮮明に浮かび上がる、あの深い苔色の瞳の人が私に向けてくれた優しい眼差し。心地よく耳に流れ込む彼女の穏やかな声。
蘇るレオナの記憶に胸が燃えるように熱くなった私は、浮かんだ涙で滲む視界をもとに戻そうと、数度、瞬きを繰り返した。
「執事のカールに確認したところ、レオナの苗字、Facklerは彼女の旧姓だということがわかった」
ヨナスの言葉にハッとして顔をあげる。
つまり、彼女は再婚していないということだ……
バックミラー越しにヨナスと目が合う。
「それ以上は聞けなかった。カールが不審に思うからな。今回、予定されているゾマーフェルド家の会合の議題項目確認のついでに聞いたんだ」
その言葉に、クラウスが後ろの私を振り返った。
「カノン、君にはまだ話していなかったが、俺もゾマーフェルドから出て、母方の旧姓になることも議題にあがっている」
「えっ」
驚いて身を乗り出した。
それは、ヨナス同様に、正式にゾマーフェルド家から除籍されるということだ。
「それは……でも、ユリウスが困る……息子が二人とも家を出るなんて」
ニコルはすでに結婚してゾマーフェルド家を出ているし、そうなるとユリウスには跡継ぎは一人もいないということになる。
青ざめていると、ヨナスが大したことないというように笑った。
「心配するな。父も最悪それでいいと言っている。自分が家系存続のプレッシャーに負けて取り返しのない間違いをしたことを、俺たちにはさせたくないんだろう。ダニエラが居なくなった今、俺やクラウスのプライベートなことを親戚が口出ししたところで、父にとっては痛いところはなくなった。俺たちが付き合う相手のことを、家系存続だの、人種や国籍なんかを理由に難癖つけたいのなら、同じゾマーフェルドの名を持つ他の家から当主を選べばいいだけのことだ。今この時代に、古い貴族の血筋を守るなど、時代錯誤も甚だしい。拘りたいやつが家長になればいいことさ」
「ゾマーフェルドを出ても、父が俺たちの父であることは変わらない」
クラウスはそう言いながら、サングラスを掛けて前方を見る。
車は空港へ向かい、高速に入る。ヨナスがアクセルを踏み込むと車が音もなくスムースに加速し波に乗るように高速の流れに入った。
「でも、実際にクラウスがゾマーフェルド家を出る場合は、メディアが騒いで面倒なことになりそうよね」
マリアの言葉に私はギョッとした。
私の動揺に気付いたマリアが、片手で私の肩を抱いて勇気付けるように微笑んだ。
「ヨナスの時もメディアがいろいろ詮索して報道して、結構大変だったの。クラウスも業界紙ではたまに名前が載る御曹司の一人だから、ネタ探しに血眼になってるメディアが食いつくのは間違いないと思う。でも、クラウスなら上手くさばいてカノンを守ってくれるから大丈夫よ」
「そんな……」
メディアに報道されるなんて考えもしなかったが、それだけ歴史のある家系の嫡男であれば、彼のプライベートの動向も世間の注目を浴びてしまうということだ。
そんな由緒ある家系の人と付き合っていると再認識して、急に怖くなる。私なんて絶対に釣り合わない人なんだ。本来なら、きっと、話す機会もないような、そんな別世界の人。
前の座席に座り、ヨナスと笑いながら何か楽しそうに話をしている彼の後ろ姿を見て、切ない思いに胸が痛くなる。
彼が家を出るくらいのリスクを取らせてしまうような価値が、私にあるのだろうか。
彼にそこまでさせていいのだろうか。
私などのために。
「カノン!」
耳元で鋭い囁き声を聞き、びくっとして我にかえる。
マリアのオリーブ色の瞳が強く輝いて私をまっすぐに見つめていた。
「いい?貴女の尊さは、クラウスにしか分からないの!自分で己の価値を推し量ろうなんて、しないことよ。うるさい外野なんて、ただの鬱陶しいBGMと思って、心の中でこうしとけばいいのよ!」
そう囁くと、マリアが眉を潜め前方をキッと睨むと、右手の中指を立ててみせた。
「ぶっ……マリアったら!」
最強の冒瀆ポーズをカッコよくキメるマリアに私は吹き出した。
あぁ、マリアは本当に私の女神様だ。彼女の天性の優しさと強さに私はこれまでもどれだけ救われてきたか。いや、彼女に出会わずして今の私はない。マリアこそ、私の人生を180度変えた張本人だ。
大笑いしているところで、ヨナスが声をあげた。
「さぁ、空港が見えて来たぞ!」
その声に、前方を見るとテーゲル空港が現れた。
上空に丁度離陸し上昇していく飛行機が見え、自ずと胸の高鳴りを感じて息を飲む。
私はこの旅で待ち受ける何かを強く感じていた。
夕方の4時過ぎということもあり、殆どの席は埋まっていて、一人で本を読んだりタブレットで映画を見ている人がいれば、グループでお喋りを楽しんでいたりする。オランダでは陽気で騒々しいことを好む人が多いけれど、ドイツは真面目な気質の人が多いせいか、こういった場所でもお喋りの時は声を低くし周りに迷惑をかけないように気配りをしてる人が殆どだ。稀に騒々しいグループがいるなと思うと、大概が英語や外国語を話しているドイツ人以外の集団だったりする。
混んでいる割にBGMのジャズが軽やかに耳に流れ込むこの場所で、私はハァと深い溜息をついた。
八方塞がり状態といえばいいのか、それとも行き詰まったといえばいいのか。打つ手がないとはまさにに今の状態だろう。
両手で顔を覆っていると、カタンと椅子が動く音がした。
「カノン?どうしたの~?」
アナが大荷物をかかえて目の前に立っているのに気がつき、私は苦笑いしながら隣の椅子を引いた。ヴァイオリンのケースを注意深く壁に立てかけ、ボストンバッグを肩から下ろしたアナが「よっこらしょ」とつぶやきながら私の隣に座る。
「カノンらしくないね、すっごいストレスかかってます、って顔」
アナは、無造作に肩にかけていたグレーにフューシャピンクの花模様が織り込まれたストールを丁寧にかけなおして、心配そうに瞬きをしながら私の顔を覗き込んだ。
私はiPadの電源を落として、また、ハァと溜息をついて苦笑いした。
「落とし穴があったっていうか、不測の事態になっちゃって……」
独り言のようにそう答えて、きゅっと唇を噛んだ。
「物事が進むべき方向に進んでいるように見えたのに、渡ろうと思った橋が行く先になくて、渡し船も見当たらず、向こう岸に渡れないって感じかなぁ」
「それってユリウスのことだよね?」
「うん……」
私は苦笑しつつ、薄暗い窓の外に目をやった。夕方の4時すぎだというのに、もう空は夕闇に包まれ、街はクリスマスの飾り付けのイルミネーションが点灯している。
11月の終わりになり、ベルリンは一気にクリスマスらしくなってきた。カフェもレストランも、デパートも、クリスマスの飾り付けで埋め尽くされ、日が落ちると煌びやかなイルミネーションが人々の目を引く。観光客がお目当てに来るクリスマスマーケットも昨日から始まっていて、私も今週末はクラウスと一緒に行く約束をしている。
「12月6日の聖ニコラウスの日前後はバースのスパに行くって決まったんでしょう?」
「うん……ユリウスも行くから、結局執事のカールが全部手配することになって、泊まるホテルとか、クラウスとヨナスの仕事のスケジュール調整とか全部、おまかせだったの。それで、一昨日、日程と宿泊先の連絡が来たから、念の為と思って早速、レオナにメールしてみたの。詳しいことは言わなくても、その時期、ファームにいるのかどうかは聞いておこうと思って」
「クリスマス前はラベンダーファームのショップとカフェは開いているってことだったよね」
丁度カフェのお姉さんがアナの注文したカフェマキアートをテーブルに置いた。スチームミルクで描かれた大きなハートに、二人で顔を見合わせてクスッと笑う。ちょっとしたことでハッピーな気持ちになれるものだ。
ブラウンシュガーをそのハートのど真ん中にドバッと威勢良く注ぎ込むアナを眺めつつ、私はiPadの電源を入れた。
そうなのだ。レオナがラベンダーファームに居ることを確認しようとメールしたら、予想外の返信が届いたため、頭を抱えてしまっている。
「レオナからの返信はなくて、ショップのスタッフからの代理返信で、レオナは忙しくてその時期ショップにはいないって……」
「えっ」
「オーナーがショップが開いている時期に不在なんて変だよね」
「うん……それで、どうして居ないのかって聞いたら、病院にいる予定だって」
「病院?」
アナが眉を潜め、不安げに顔を曇らせつつ、私が見せたそのメールにさっと目を通し、呟いた。
「ほんとだ、レオナはその時期は病院にいる予定って書いてある」
私は小さく頷いた。
「私も心配になって、レオナが病気なのかって聞いたら、違うって。でもそれ以上は、スタッフとしてはオーナーのプライバシーに関わることは答えられないって言われたの」
「ふうん、まぁ、病気じゃないってのならほっとするけど……ん?そうすると、他の誰かが病気とか?」
アナがハッとしたように目を見開いた。
彼女も私が考えたことと同じことを想像したらしい。
「やっぱり普通そう考えるよね」
よく考えなくても誰だって想像してしまうだろう。レオナが病気じゃないのに病院にいるということは、誰か大事な人が入院しているという可能性だ。
しばらく沈黙しつつマキアートを飲んでいたアナが、ぽつりと言う。
「でもだからって、その人がご主人とか決まったわけじゃないし……親友とか、親戚や兄弟だってこともあるよ」
私は期待を込めて大きく頷いた。
「私もそう考えて、このまま彼女とユリウスの再会を諦める理由にはならないと思ってる。だって、レオナは、ユリウスとの再会の可能性については否定はしなかったし。勿論、会ってくれるとも言わなかったけど……絶対無理な状況なら、最初からはっきり断ってくれたと思うし」
「うん、そこは激しく同意する!」
アナがにっこりと微笑むと、私もつられて笑顔になる。
「ありがとう、アナにそう言ってもらうとポジティブになれそうな気がする」
「なれそうな気がするする?ダメだよ、ならないと!」
ちょっと拗ねたように眉間に皺を寄せて睨まれ、私は苦笑した。
「うん、わかった!ポジティブにね。あ~でも、せっかくバースまで行くのに、レオナに連絡つかないんじゃ、がっかり……」
「カノンったら、バースなんていつでも行ける距離なんだから、今回は単純にホリデーを楽しむことに重点を置けばいいんだよ。クリスマスシーズンに突入してるし、きっと素敵な思い出になるよ。いいじゃん、豪華スパ旅行。執事付きの貴族御一行様なんて、私から見たら夢の世界」
「執事付きの貴族御一行様かぁ……確かにそうだよね」
私はその響きに不思議な気分になった。大体、貴族なんて過去の社交界のみ有効な肩書きで、現存しないと勝手に思い込んでいたものだから、その末裔がいることに気がついて驚いたものだ。でも良く考えれば、まだ世界中に王室は存在するし、日本だって皇室があるわけだから、伯爵や公爵の子孫がいてもおかしくない。ただ、ドイツでは貴族制度は廃止されているから、あくまでも、血筋ということだが、実際、いまだにその名残は残っている。先日知ったことだが、クラウスの本名はとても長く、正式名にはゾマーフェルドの前にフォンが付いている。このフォンが付くと貴族の末裔だということらしい。
私はふと、昨晩クラウスから聞いたことを思い出した。
「あのね、ユリウスは脳梗塞の患者だから、飛行機は当分乗ってはいけないんだって。そうすると陸路になるから移動時間がかなりかかるんだけど、ユリウスは行く気満々だってことで、車で行くことになったらしいの」
「ドイツからUKまで?確かに陸路でも行けるよね、フランスからだったらかなり近いって聞いたことある」
「そうなの。で、車で何時間も座ってるの、体に悪いんじゃないかと気になってクラウスに聞いたら、リムジンだから平気だって。負担にならないように、どこかで途中一泊していくらしいから、片道2日もかけていくことになるんだけど、ドクターも賛成してるから、強行することになったんだって」
「リムジンバス、じゃないよね。あの長い車体のリムジンだよね」
「そう。車、何台もガレージにあったから、きっとそこにリムジンもあったんだろうね」
「どんなやつなんだろう?」
「えーとね、確か……そう、メルセデスのマイバッハ・プルマンとか言ってたよ」
記憶を手繰り寄せてその名前を言うと、アナが私のiPadを手に取った。私もアナに寄り添って検索画面を覗き込む。
画面に表示されたゴージャスなリムジンのイメージに二人して言葉を失う。
全長6メートル半という想像を超える大きさに、重量感のある革張りの車内、ラグジュアリー感溢れる贅沢なインテリア。カスタム仕様になれば軽く一億は超えると書かれている。その堂々たる車体の威圧感も半端ないが、なにより、一般人とは桁の違う世界中に唖然とする。
しばらく呆然と、画面いっぱいに映されるメルセデス・マイバッハ・プルマンの豪華な写真のスライドショーを眺めていたが、やがてアナがはっと思い出したように腕時計を見た。
「あっ、いっけない、もうリハが始まっちゃう!」
時計を見ると既に5時半になっていた。
アナはこのカフェの近くにあるプライベート・コンサートホールで行われる予定になっている、クリスマスコンサートのリハーサルに参加しなければならないのだ。
立ち上がってコートを羽織りながら、アナが私のほうを振り返った。
「ね、私の顔、大丈夫かな」
「え?顔?」
びっくりしてアナの顔をじっと見る。相変わらずの透き通るような白い肌、黒目がちで長い睫毛に縁取られた大きな瞳、やや紅潮した頰が愛らしく、彼女を実際の年齢より幼く見せている。今日はちょっとだけ、ローズピンクのルージュを引いているからか、ドールフェイスっぽい雰囲気があって、普段のお茶目な感じがあまりしない。
「うん、いつも通り、美人音楽家って感じで見惚れちゃう」
思った通りに答えると、アナがはにかむように目を細めて、トンっと私の肩を押した。
「やだ、おだてすぎ!でもありがとう」
「おだててないよ!でも珍しいね、アナが自分の顔を気にするなんて」
初めてこんなことを聞かれたから、不思議に思ってそう言うと、アナが肩をすくめた。
「だってね、アダムがリハ中の写真を撮りに来るっていうものだから、私のHPに、写真を追加するんだって」
「なるほど」
私は思わず笑顔になり、くすくすと笑いだした。以前のアナなら、アダムが写真を撮ろうといつも通り自然体なままだっただろうが、ちゃんと恋人になった途端、彼の向けるレンズには美しく写りたいと思うようになったんだろう。
笑っている私を不満げに見て、なにか言おうと唇を尖らせたアナだったが、時間がないのを思い出したらしく、急いでヴァイオリンのケースに手を伸ばすと、また、「よっこらせっ」と掛け声をかけてそれを抱え上げた。
「それじゃぁ私は行くね!週末に一緒にクリスマスマーケット行けるかどうか、後で連絡するから」
「うん、待ってる!リハーサル、頑張ってね。アダムにもよろしく」
「オッケー」
アナはスカーフを翻し、早足でカフェを出て言った。彼女が出た後、ドアが音も立てずにそうっと閉まったのを合図に、私もそろそろと帰る準備を始めることにする。一人で出歩けるようにはなったけど、まだ捻挫の痛みが残っているのでゆっくりとしか歩けないのだ。
今晩はクラウスも7時過ぎには帰ると言ってた。夕食のメニューを考えながら、私は向かいの椅子にかけていたコートに手を伸ばしたのだった。
土曜日の午後1時を回る少し前に、私とクラウスはアレクサンダープラッツの世界時計塔の下に居た。昨晩、アナから連絡が来て、一緒にクリスマスマーケットに行くことになっていた。
普段は公共交通機関で出かけることの多い私達だが、今日は車で来たので、駐車場を確保するためにちょっと早めに出て来たものの、思ったよりスムースに車を停めることが出来たので、約束の時間前に待ち合わせ場所にいるわけである。
「なんだかこういう所、ドキドキする」
私が独り言のように呟いて周りを見渡すと、携帯を見ていたクラウスが顔をあげて、駅の方をみた。クリスマスマーケット目当ての観光客も多いし、人の声にクリスマスミュージックで街全体がお祭りモードだ。街のいたるところはクリスマスのデコレーションで飾られており、街行く人も、サンタの帽子を被っている人やクリスマスプレゼントを抱えている人など、普段とはちょっと雰囲気が違い、とにかく見渡す限り笑顔、そして笑顔。
自然と頰が緩み、私はじっとしていられなくなって、隣に立つクラウスの腕にぎゅうっと抱きついた。
クスッと笑った彼が、身をかがめて私の顔を覗き込む。私と目が合うと、満足そうな笑みを浮かべ、チュッと音を立てて私の額にキスをした。くすぐったくて彼の胸に顔を埋めた。子供のように興奮している自分が少し恥ずかしい。
ずっと楽しみにしていた、ドイツの風物詩、クリスマスマーケットに愛する彼と一緒に来ている。しかも、親友カップルとのダブルデートだというのに、ドキドキしないなんて絶対無理!
気温は一桁で凍えるようなのに、今日は寒いという感覚は感じないくらい気持ちが高揚していた。
「カノン!」
雑踏に紛れて私を呼ぶ声が聞こえ、顔をあげると、人混みの向こうに、真白なコートを羽織ったアナが駆けてくるのが見えた。
反射的に手を挙げて、駆け寄ってきたアナとお互い手を取り合う。
「ごめん!待った?」
「ううん、大丈夫だよ」
「電車が混んでて、一本見送ったからちょっと遅れちゃった」
アナは呼吸を整えるようにふぅと白い息を吐くと、私の背後に視線を動かした。
「やぁ アナ」
クラウスが目を細めて笑うと、パッと花が開くようにアナが明るい笑みを浮かべた。
「バイクの時以来だね。一応、改めて、初めまして、、かな?」
「そうだな。初めまして、アナ」
「よろしく、クラウス!」
二人が肩を抱き合って挨拶を交わすのを見て、私は嬉しさにぶるっと震えた。
少し遅れてアダムがやってきた。
彼はクラウスと肩を抱き合い、一言、二言交わし、私の肩を抱き寄せていつもの挨拶を交わす。その後、アダムはアナの頭を軽く小突いて、ムッとして振り返った彼女を軽く睨んだ。
「走るなって言ったの、聞こえてなかったのか」
「聞こえてたよ。いいじゃん、少しくらい」
アナがさっと私の後ろに隠れると、アダムが呆れたように、はぁと小さくため息をした。
「どうしたんだ?」
クラウスが不思議そうにアダムに聞くと、アダムがちょっと苦々しげに笑った。
「こいつ、クリスマスのコンサートが控えているのに、昨晩、階段から転げ落ちたんだ」
「えっ」
私もびっくりしてアナを振り返ると、当の本人は素知らぬ顔で明後日の方を見ている。
「幸い、かすり傷で演奏には響かない怪我だったが……2階から椅子を抱えて転げ落ちるというアクシデントだったことを思えば、奇跡的な軽傷だったんだ」
「椅子ごと落ちたって、アナ、何やってたの?!」
「えー……ハシゴが見当たらないから、2階の棚のものを下ろすのに、1階から椅子を持っていってたの。用が済んで、椅子を1階へ戻そうと階段降りてたら、滑ったんだよね。つるっと」
あははー、と屈託無く笑うアナを見て、アダムが頭が痛いというようにこめかみを押さえた。
「玄関のドアを開けるなりすごい騒音と一緒に2階から転げ落ちてくるアナと椅子が視界に入った時は、心臓が止まるかと思った。椅子は完全に大破したほどの衝撃だったし」
アダムの心配はごもっともだ。バイオリニストのアナにとっては、怪我は絶対に避けなくてはならないものだ。
「俺がジム帰りに寄ると約束した時間まで後数分とわかっていて、何故自分で椅子を2階まで運んで棚からものを下ろそうとするのか、理解できない」
「だって、待てなかったんだからしょうがないでしょ」
「たった数分のことが待てないとは、それだけ急ぎで重要なものだったんだろう」
クラウスが横から助け船を出すと、アダムが苦々しく笑う。
「……箸置き、ってやつだったけどね。箸を置く小さな陶器」
「箸置き……のために、2階まで椅子運んで?」
私とクラウスが言葉を失ってアナを見ると、彼女は眉間にシワを寄せて反論した。
「あれ、京都の町屋通りで見つけた、清水焼きの貝合わせ箸置きなの!平安時代のデザイン画が焼かれてて、とっても綺麗だから、夕食の時にアダムに見せて驚かせようと思ったんだもん」
なるほど。
だから、アダムに頼みたくなかったわけだ。ただの箸置きというわけではなかったなら、アナの気持ちもわからないでもない。
「確かに素晴らしい逸品だったが、それも擦り傷ですんだから言えることだ。腕を骨折でもしてたら演奏どころじゃなかったことを忘れるな」
アダムに説教されて、不満げに唇を尖らせてそっぽを向くアナ。
恐らく繰り返し言い聞かせられているに違いない。
少しいじけたように明後日の方を見ている彼女のかわいい捻くれように、私は笑いだしてしまった。
「わかった、アダム!今日は私がしっかりアナを捕まえておくから!」
私はそう言って、アナと腕を組んでみせた。
クラウスが可笑しそうに目を細めながらアダムを振り返る。
「いや、これじゃ尚更心配だろう」
「クラウスの言う通りだ、アナ、こっちに来い」
アダムがアナに手を伸ばし、引っ張ろうとする。
「どうして?なぜ尚更心配になるの?」
納得出来ず抗議すると、クラウスが私の腕を取りながら諭すように答える。
「君だって捻挫でやっと最近歩けるようになったばかりだろう。二人揃って転ばれたら俺たちが困る」
指摘されてハッとする。自分がまだ歩くのに痛みが残っていることを思い出す。だから今日は車で来たんだった。私がレンガを敷き詰めた道路の歪みにつまづいて、アナを道連れに転んだらもとの黙阿弥。
「さぁ、これくらいにして早速マーケットに行こう」
クラウスのその言葉に、私達は駅の向こう側へ目を向けた。
マーケットの華やかで楽しい出店を順番に見ていく。クリスマスの焼き菓子に毛糸で編まれたストールやグローブ、クリスマスのディナーテーブルを飾るカトラリーや手作りのキャンドル。行き交う人々の幸せそうな笑顔に興奮気味の幼い子供達。
フルーツを串に刺してチョコレートのコーティングをかけたものは見た目も可愛らしく、店頭の前で足を止めてじっくりと眺めた。特に目を引くのは、ドイツのクリスマス向けの伝統的な木製デコレーション。繊細なところまで丁寧に彫刻された品物はそれは見事だ。手作りで作られたツリー用の小さなオーナメント、デザインのバリエーションも豊かなくるみ割り人形、イエスキリストが生まれた馬小屋のセット……見事な職人技に目を奪われる。
商品の写真を撮ろうとしていた観光客に、店員が、大きく手を振りながら、No!No photo!と声を挙げている。彼等にとっては商売のために出店しているのに、観光客が商品は買わずに写真だけ撮って、インスタやツイッターにあげたりするのが気に入らないんだろう。
可愛らしいツリー用のオーナメントが沢山あったけれど、クラウスが実家にあるクリスマス用のデコレーションを一部こちらへ送ってもらうよう手配してもらっているから、私たちが買う予定のツリー用には、これといって新しくオーナメントを揃える必要はない。だから私達は、代わりに、クリスタルガラス製品で、窓辺に飾るのにぴったりなエンジェルや雪の結晶のオブジェを数点購入した。キャンドルを添えて飾れるので、夜はクリスタルガラスがキラキラと輝いてきっとメルヘンチックな窓辺になるだろう。アナとアダムも何やら相談しながらいくつかツリー用のオーナメントを買っている。
「ところで、クリスマスや新年はどうするんだ?」
アダムが私達のほうを見て聞いたので、クラウスが答える。
「クリスマスは多分、俺の実家に行って、新年はオランダに行こうと思ってる」
「え」
新年はオランダ、と聞いてびっくりしてクラウスを見た。クラウスが笑いながら私の肩を抱いて、いたずらっ子のようにウインクした。
「君のお茶目なおばあちゃんに会いにいくと約束したまま、まだ果たせていないだろう?」
「本当に?オランダまで一緒に行ってくれるの?」
「もちろんだ。その予定で仕事のスケジュールも調整済みだ」
私も正直、おばあちゃんが新年をどう過ごす予定か気になっていたので、一人でも行こうと考えていた矢先のことだったから、クラウスの提案に嬉しさで胸がいっぱいになる。
「ありがとう……おばあちゃん、すごーく喜ぶと思う!」
心の底からお礼を言うと、クラウスがクスッと笑って頷いた。
「そっちはどう過ごす予定なんだ?」
クラウスがアダムに聞くと、アダムとアナが顔を見合わせる。
「26日まではアナがコンサートで埋まっているから、その後はゆっくり過ごそうと思ってる」
アダムはそう答えた後、少し間を置いて、何かを思案するようにゆっくり瞬きした。
「あっ、あの店」
アナが後ろにある店に気付いて、私達から離れてチェックに行くのを見ながら、アダムが低い声でつぶやいた。
「年末は実家に行くことにしたんだ」
それを聞いて、クラウスが少し驚いたように目を見開いた。
「ねえ!こっちに来て!グリューワインあるよ!休憩しよう!」
アナの嬉しそうな声が聞こえた。
スパイス入りの温かいグリューワインをそれぞれ注文し、空いていた真っ赤なテーブルクロスの席につく。風に揺れる炎が灯る白いキャンドルも、クリスマスらしく蔦の葉や赤い木の実のデコレーションで飾られている。肌に刺すような寒風が吹く中で、温かいグラスから柔らかな湯気をたてる真紅のワインをそっと口に含むと、スパイスたっぷりでフルーティな甘さがのどを滑り落ち、お腹の中からじんわりと温まっていく。自然と満たされた気持ちになり、ゆっくりと深呼吸する。味は違うけど、ほとんどアルコールを飲まない私でも楽しめる甘酒を思い出した。
「おまえは実家から離れてもう随分と時間が経っていたな」
クラウスの問いにアダムが苦笑し、頷いた。
「先日、4年ぶりに連絡したんだ。まぁ、久しぶりだったから、母親が電話口で泣いていた」
「両親とも元気だったか」
「すこぶる元気だったさ。それに、俺もあれから考え方を変えたから、親父のことも少しは受け入れる気になった」
「そうか。それは良かった。結局のところ、血の繋がりは何をしても切れないんだから、家族としてうまくやっていくに越したことはないだろう」
クラウスの言葉に、アダムが頷きながらグリューワインのグラスを傾ける。キャンドルの炎に照らされたブロンドの前髪が風に吹かれてキラキラしていた。
「母親から聞いたんだ。親父のやつ、しばらく前にベルリンにアパート買って、たまにこっちに来ているらしい。だからといって俺に連絡はしてこなかったが」
「アパート?」
「新築売り出しのいい物件があったから、投資のために買った、と母親には言ったらしいだが、たまに工事の進み具合のチェックにベルリンに来てるらしい」
アダムはちょっとため息ををつくと、テーブルの上に置かれたシルバーのお皿にあった、ドイツのクリスマスケーキ、シュトレンのスライスを一切れとり、半分に割ると片方をアナに渡す。粉砂糖が粉雪のようにほろほろと、真っ赤なテーブルクロスの上に舞い落ちた。
「親父は、そのアパートを俺にやろうと思ってるらしくて、部屋の壁をぶち抜いてアトリエスペースを作ったり、画材や作品を保管する空調を整備したガレージを作ったり、業者に工事させてたらしい」
その話に、私とクラウスはびっくりして顔を見合わせた。
親の援助を拒否して連絡を絶っていたアダムのために、父親は隠れてそんなことをしていたのか。息子がそれを受け入れるかどうかも分からないのに。
親というものは、子供のためになることならと思えば、例え嫌われたり、拒絶される可能性などのリスクがあっても、結局は行動してしまうのだろう。
クラウスが目を細めて、楽しそうに笑った。
「どうするんだ、そのアパート。親孝行と思って受け入れる気になったか?」
アダムはしばらく黙っていたが、グリューワインの残りを一気に飲んで、ふっと肩の力を抜いたように優しい笑みを浮かべた。
「条件付で入居してやるって言った」
「えっ、それは聞いてない!わかんないって言ってたじゃない」
アナがびっくりしたように声をあげた。
「昨晩決めて、今朝電話で言ったんだ」
「えー、そうなの?場所、遠いの?」
今は二人とも歩いていけるくらい近いところに住んで行き来しているから、同じベルリン市内でも電車に乗らないと会えない距離になるのは寂しいのだろう。アナが不満そうにじっとアダムを見つめると、彼はアナが持っていたグリューワインのグラスを取って、一口飲んだ。
アナも私と同じくそれほど飲めるタイプでないので、グラス半分を飲んだ以降、口をつけてなかった。
「ね、アダム。どんな条件出したの?」
気になって、彼が言い出すのを待てずに私が聞くと、アナのグラスを空にしたアダムはテーブルに片肘をつきながら答えた。
「……防音ルーム」
「……?」
なんのことだか分からず、私はじっとアダムの顔を眺める。
彼の美しい真っ青な瞳は何かを期待させるような不思議な光があった。
隣のクラウスがクスッと笑いながら、アダムの頭を片手で小突く。
小突かれて乱れた前髪を無造作にかきあげながら、アダムは隣で目を丸くしているアナに目をやった。
「君もそろそろ今のシェアハウスの契約切れるんだろう?」
契約が切れる?
「それで親父さんはなんだって」
横から既に全てを察した様子のクラウスが聞くと、アダムは肩をすくめた。
「あっちも交換条件出して来たさ」
「だろうな。当然だろう」
クラウスが楽しげに笑いながら頷いて、アナの顔を覗き込んだ。
「アナ、年末はアダムと雪合戦だな。ノルウェーの冬の寒さは覚悟したほうがいい」
アナが驚いたように瞬きして、アダムを見た。
「……どういうこと?」
アダムは少しの間アナを見つめていたが、コートの内ポケットから携帯を出すと、それをテーブルに置いた。皆で覗くと、工事中のアパートの写真があった。何枚か見ていけば、それがかなり大きい新築アパートで、レイアウトを改造しているのがわかる。打ちっ放しのコンクリートの壁の部屋はものすごく広く、30畳くらいはありそうで、恐らくここがアトリエだろう。複数の部屋があり、見た所レイアウトが概ね完成したところで、内装はこれからという状態だ。
「防音ルームあれば時間に関係なくバイオリンも弾けるだろう」
私はようやく全てが分かって、急にドキドキしてきた。
アナの為の防音ルームだ!
アダムが携帯を取ってコートの内ポケットにしまいながら、目をまん丸にして絶句したアナを見つめて微笑んだ。
「昨晩君が階段から真っ逆さまに落ちてくるのを見た後に思いついたんだ」
「……アダム」
「親父のやつ、防音ルームも作ると即答したさ。その代わり、年末に顔見せに帰ってこいと。防音ルームを使う彼女も連れて来るってのが条件だと」
その言葉に、アナが突然両手で顔を覆ってテーブルに突っ伏した。
彼女も驚いたに違いない。アダムが離れたところに引っ越してしまうと思っていたら、その計画に、自分も入っていたと判明したのだから。しかもアダムの両親に紹介されることになったなんて、思いもよらないニュースの連続だったに違いない。
3人ともしばらく黙っていたが、やがて、耳を赤くしたアナが顔を上げて、掠れた声でつぶやいた。
「もう、アダム、いきなりすぎるよ……」
いつになく弱々しいアナをアダムが笑いながら片手で抱き寄せ、なだめるようにそっと髪を撫でた。いつも威勢のいいアナがこんなに照れて参っている様子がとても新鮮で、幸せそうな二人を眺めながら、私も嬉しくてクラウスと目を合わせ頷きあう。
「親父の押し付けがましい援助はずっと鬱陶しかったが、さすがにあれだけいいロケーションで、スペース的にも理想的なアパートは、今の俺には確保出来なかった。タイミング的にも、今の場所が手狭になってきて、新しくアパートを探すか、別にアトリエを借りるか考えていたところだったから、正直なところ、有難い」
「一人っ子のおまえしか生き甲斐がないんだろう。親孝行と思って好意を受け入れるのもたまには悪いことじゃない。少なくとも、おまえのアートに宣伝投資するのではなく、応援するためのベースを作ってやりたいなんて、健気なものだ」
楽しそうにクラウスがそう言うと、アダムが苦笑して頷いた。
アダムの実家はかなりの資産家だが、彼がアーティストにキャリアチェンジした後、財力にものを言わせてアダムを業界に売り込もうとした両親を彼はかたくなに拒否し、もうずっと自分だけの力で頑張って来たのだ。そして今、彼の才能は花を開き、雑誌やネットニュースでも掲載され、国内外から大きなプロジェクトのオファーが入ってくるようになっている。
つい先週も、マリアとコラボして作った作品を、ドイツに移住しているシリア難民支援のチャリティイベントに寄贈したとテレビのローカルニュースで見た。
「レイアウトは親父がもう完成させてたから、内装はヨナスに手伝ってもらって自分でやることにしたんだ。親父にやらせるとアパート中の壁を病院みたく真っ白に塗りつぶしかねない」
アダムの言葉に思わず笑いが漏れる。アーティストで器用なアダムのことだ、きっと彼等にぴったりのアパートを作り上げることだろう。
ようやく落ち着きを取り戻した様子のアナが、はぁと大きなため息ををついた後、嬉しそうに微笑んだ。
「一足早くクリスマスと新年が来たみたい!アダム、ありがとう。びっくりしたけど、ほんとに嬉しい。新しいシェアハウス探すの、結構難航してたし……」
ドイツでは、結婚していない恋人同士が同棲するのは全然珍しいことではない。若者は実家を出た後、ほとんどの人は一人暮らしする経済力がないため、シェアハウスで暮らすことが多い。だからといって、ハウスメイトと必ずしもうまく行くとは限らないので、ある程度真剣な付き合いをしている恋人がいるなら、同棲することを選ぶ人が多い。もちろん、破局した時は、場合によっては同居解消が泥沼化する可能性は無きにしも非ずだが。
「来年は私達皆、引っ越しだね」
「ほんと、偶然にもタイミング重なったね」
アナがくすぐったそうに笑うと、まだ驚きが消えないかのように大きく肩を上下させて深呼吸する。
私も一応まだ自分のアパートがあるので、現在、クラウスのアパートに入り浸りになっているものの、正式な同棲は来年からとなる。
ひとしきり笑った後、まだまだ続く広いクリスマスマーケット会場巡りで楽しい午後は過ぎていった。
ようやく朝日が昇り始め空が明るくなってきた土曜日の午前8時すぎ、外で車のクラクションが鳴ったのが聞こえ、私は小走りで玄関の扉を開け外を確認した。見慣れたメタリックシルバーの大型のベンツが停まっている。
「クラウス、来てるよ!」
私が後方に声を張り上げると、スーツケースを2つ抱えた彼がベッドルームから出て来た。今日の彼はいつもよりリラックスした装いだ。久し振りに彼がジーンズを穿いているのを見た気がする。Dieselのネイビーブルーのジーンズにブラックのトップス、チョコレートブラウンのレザーコート。
ふと、出会って間もない頃の「ニッキー」を思い出して、甘酸っぱい気持ちになる。
「さぁベイビー、戸締りは君の仕事だ」
美しいブルーグレーの瞳を優しく細めて微笑む彼に、大きく頷いて見せた。
表に出て、私が注意深く鍵を閉めて確認している間に、彼はもう階段の下に停まっている車のトランクにスーツケースを入れ、私が階段を降りようと振り返った時には戻ってきていて、当たり前のように手を差し出していた。
私の怪我の件では、クラウスは私が戸惑うくらい心配しており、もう事故後、二週間が経ち普通の歩行には問題なくなっているにも関わらず、こうして文字通り手取り足取りサポートしてくれる。もう大丈夫と言っても、私が無理していると疑っているものだから、私が何言っても変わらない。この度を超える過保護ぶりには流石に兄のヨナスもからかって笑うが、クラウスはそれでもやめない。
「ありがとう」
素直にお礼を言って、手を繋いでゆっくり階段をおりる。
私の背中の内出血の跡が数カ所残っているから、それが完全に消える頃には彼も心配しなくなるだろう。
「おはよう!」
後ろのドアをマリアが開けてくれたので乗り込むと、クラウスがドアをゆっくり閉める。
続いて運転席のヨナスの隣にクラウス乗り込む。
ついに、バースのスパへ行く日になったのだ。
眠そうにあくびするマリアが、後部座席で伸びをした。
「スパに持って行く水着を探すのに時間かかって、睡眠不足なのよ。まさか冬に水着使うと思ってなかったから、夏物の衣類の山の中からそれを見つけるの大変だったわ」
車が発進し、同時に音楽が流れ始めた。ロマンチックなギターのイントロに続き、ハスキーで深みのある女性のイタリア語の歌が重なる。
「あ……Laura PausiniのE Ritorino da Teのアルバム」
ドラマティックなこの曲は私を切なくも情熱的な気持ちにする。
これから始まる旅行の1番の目的を胸に抱いて、私はぎゅっと両手を握りしめた。
どうなるかなんて、誰にもわからない。
でも、あの地でしか、奇跡は起こらない。
運命というものが存在するのなら。
偶然や必然というすべての条件が重なれば。
神様、お願い。
目を閉じれば脳裏に鮮明に浮かび上がる、あの深い苔色の瞳の人が私に向けてくれた優しい眼差し。心地よく耳に流れ込む彼女の穏やかな声。
蘇るレオナの記憶に胸が燃えるように熱くなった私は、浮かんだ涙で滲む視界をもとに戻そうと、数度、瞬きを繰り返した。
「執事のカールに確認したところ、レオナの苗字、Facklerは彼女の旧姓だということがわかった」
ヨナスの言葉にハッとして顔をあげる。
つまり、彼女は再婚していないということだ……
バックミラー越しにヨナスと目が合う。
「それ以上は聞けなかった。カールが不審に思うからな。今回、予定されているゾマーフェルド家の会合の議題項目確認のついでに聞いたんだ」
その言葉に、クラウスが後ろの私を振り返った。
「カノン、君にはまだ話していなかったが、俺もゾマーフェルドから出て、母方の旧姓になることも議題にあがっている」
「えっ」
驚いて身を乗り出した。
それは、ヨナス同様に、正式にゾマーフェルド家から除籍されるということだ。
「それは……でも、ユリウスが困る……息子が二人とも家を出るなんて」
ニコルはすでに結婚してゾマーフェルド家を出ているし、そうなるとユリウスには跡継ぎは一人もいないということになる。
青ざめていると、ヨナスが大したことないというように笑った。
「心配するな。父も最悪それでいいと言っている。自分が家系存続のプレッシャーに負けて取り返しのない間違いをしたことを、俺たちにはさせたくないんだろう。ダニエラが居なくなった今、俺やクラウスのプライベートなことを親戚が口出ししたところで、父にとっては痛いところはなくなった。俺たちが付き合う相手のことを、家系存続だの、人種や国籍なんかを理由に難癖つけたいのなら、同じゾマーフェルドの名を持つ他の家から当主を選べばいいだけのことだ。今この時代に、古い貴族の血筋を守るなど、時代錯誤も甚だしい。拘りたいやつが家長になればいいことさ」
「ゾマーフェルドを出ても、父が俺たちの父であることは変わらない」
クラウスはそう言いながら、サングラスを掛けて前方を見る。
車は空港へ向かい、高速に入る。ヨナスがアクセルを踏み込むと車が音もなくスムースに加速し波に乗るように高速の流れに入った。
「でも、実際にクラウスがゾマーフェルド家を出る場合は、メディアが騒いで面倒なことになりそうよね」
マリアの言葉に私はギョッとした。
私の動揺に気付いたマリアが、片手で私の肩を抱いて勇気付けるように微笑んだ。
「ヨナスの時もメディアがいろいろ詮索して報道して、結構大変だったの。クラウスも業界紙ではたまに名前が載る御曹司の一人だから、ネタ探しに血眼になってるメディアが食いつくのは間違いないと思う。でも、クラウスなら上手くさばいてカノンを守ってくれるから大丈夫よ」
「そんな……」
メディアに報道されるなんて考えもしなかったが、それだけ歴史のある家系の嫡男であれば、彼のプライベートの動向も世間の注目を浴びてしまうということだ。
そんな由緒ある家系の人と付き合っていると再認識して、急に怖くなる。私なんて絶対に釣り合わない人なんだ。本来なら、きっと、話す機会もないような、そんな別世界の人。
前の座席に座り、ヨナスと笑いながら何か楽しそうに話をしている彼の後ろ姿を見て、切ない思いに胸が痛くなる。
彼が家を出るくらいのリスクを取らせてしまうような価値が、私にあるのだろうか。
彼にそこまでさせていいのだろうか。
私などのために。
「カノン!」
耳元で鋭い囁き声を聞き、びくっとして我にかえる。
マリアのオリーブ色の瞳が強く輝いて私をまっすぐに見つめていた。
「いい?貴女の尊さは、クラウスにしか分からないの!自分で己の価値を推し量ろうなんて、しないことよ。うるさい外野なんて、ただの鬱陶しいBGMと思って、心の中でこうしとけばいいのよ!」
そう囁くと、マリアが眉を潜め前方をキッと睨むと、右手の中指を立ててみせた。
「ぶっ……マリアったら!」
最強の冒瀆ポーズをカッコよくキメるマリアに私は吹き出した。
あぁ、マリアは本当に私の女神様だ。彼女の天性の優しさと強さに私はこれまでもどれだけ救われてきたか。いや、彼女に出会わずして今の私はない。マリアこそ、私の人生を180度変えた張本人だ。
大笑いしているところで、ヨナスが声をあげた。
「さぁ、空港が見えて来たぞ!」
その声に、前方を見るとテーゲル空港が現れた。
上空に丁度離陸し上昇していく飛行機が見え、自ずと胸の高鳴りを感じて息を飲む。
私はこの旅で待ち受ける何かを強く感じていた。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
172
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる