3 / 13
第3話 鏡の中の異物
しおりを挟む
1998年、4月。八王子の朝は、まだ少し肌寒い。
午前6時30分。目覚まし時計のデジタル数字が切り替わるのと同時に、俺――葛石任三郎は意識を覚醒させた。
隣のベッドにいたはずの老いた肉体も、深夜に響く人工呼吸器の音もない。あるのは、若々しい心臓の鼓動と、驚くほど澄んだ視界だ。
起き上がり、洗面所へ向かう。
鏡に映っているのは、昨日までと同じ15歳の少年。しかし、冷たい水で顔を洗い、歯を磨きながらその貌を凝視すると、やはり違和感がある。彫りの深い彫刻のような鼻筋、一度狙った獲物を決して逸らさない鷹のような鋭い眼光。中学生という未熟なコミュニティにおいては、あまりに鋭利な「異物」だった。
「三郎、起きてるの? 朝ごはんできてるわよ」
階下から母・美津子の声が飛ぶ。
俺はクローゼットから、まだシワ一つない学ランを取り出した。1998年、詰め襟の学生服はまだ中学生のスタンダードだ。それを窮屈に感じながらも袖を通し、鏡の前で襟を正す。
ダイニングへ降りると、美津子がトーストと目玉焼きをテーブルに並べていた。
タイトなサマーニット越しにも分かる、しなやかで整ったプロポーション。30代後半という、女性としての円熟味と瑞々しさが絶妙に同居する彼女の美しさは、この界隈では有名だ。
「あら、今日もビシッとしてるわね。なんだか、お父さんより頼もしく見えるわよ」
「……そうか。父さんは?」
「もう出勤したわ。支店長会議があるんですって。大変そうよね、銀行も」
美津子が淹れてくれたコーヒーの香りを楽しみながら、俺は朝食を口にする。
「母さん。この家、あと10年もすれば価値が半分以下になる。……早めに売り抜けて、都心のマンションに切り替えることを検討しておいてくれ」
「えっ、急に何言ってるのよ。せっかく建てた家なのに」
「……リスク管理だよ。これからは、土地が資産になる時代じゃない。『知識』と『決断』が資産になる時代だ」
俺はバッグを掴むと、困惑する美津子を背に家を出た。
通学路の角で待っていたのは、門廻邦彦だった。
「よっ、任三郎! 今日は一段とシブい顔してんな!」
小学校からの腐れ縁で、家も近い親友。
サッカー部のキャプテンを務める彼は、4月の朝日を浴びて発光しているかのように爽やかだった。整ったルックスと、運動部特有の引き締まった肉体。彼が歩くだけで、すれ違う他校の女子生徒たちが密かに視線を送る。
「……邦彦。宿題は終わったのか」
「ギクッ……。お前、相変わらず鋭いな。昨日は部活のあとに『フランスW杯』の特番見てたら、いつの間にか寝ちゃってさ。お前の見せてくれよ、親友だろ?」
二人で並んで坂道を登る。
邦彦は将来、プロのスポーツ選手になることを本気で夢見ていた。
「俺さ、高校は推薦で『市立船橋』か『帝京』あたりを狙いたいんだよな。そこで活躍して、Jリーグのスカウトを待つ。今の日本代表、見てるか? カズさんやヒデさんみたいに、俺も世界へ行きたいんだ」
俺は歩きながら、隣の少年の「価値」を審美眼で測定する。
彼には才能がある。しかし、この1998年という時代の先にあるのは、未曾有の就職氷河期と、非正規雇用の拡大だ。スポーツ推薦で進学したとしても、一度の大怪我ですべてが瓦解する脆い道。
「邦彦。推薦もいいが、勉強も捨てすぎるな。これからのスポーツ選手は、エージェントとの契約書を自分で読める知性が必要になる。……お前にとってのサッカーが『投資』なら、怪我という不渡りに備えた保険が必要だ」
「投資? 保険? お前、本当に中学3年生かよ……」
邦彦は苦笑しながら、俺のバッグから突き出た漫画雑誌に目を留めた。
「あ、『週刊少年ジャンプ』買ったのか。貸してくれよ。俺、今週の『ONE PIECE』が読みたかったんだ。……それと、この前の『サンデー』も貸してやるよ。烈火の炎、マジで熱いぜ」
1998年。娯楽の王様はまだ雑誌であり、少年たちは紙の束を通じて未来を夢見ていた。
教室に入ると、俺の席の隣に彼女がいた。
東鶴襟華。
窓から差し込む春の光を受けて、彼女の金褐色の瞳が猫のように細められる。
早熟で完成された美貌。
彼女は机の上に一冊の文庫本を置いていた。
「おはよう、葛石くん。昨日貸した『フィリップ・K・ディック』、どうだった?」
「……悪くなかったよ。現実が何重にも剥がれていく感覚は、今の日本に似ているかもしれない」
「ふふ、相変わらず感想が哲学的ね」
襟華の影響で、俺は最近、文庫や新書を手に取ることが増えていた。
1998年という時代は、ファンタジーやSFが、単なる子供向けではなく「世界の捉え方」として、漫画やアニメ、ゲームを通じて当たり前のように共有され始めた時期だ。
「……なあ、二人は『将来』をどう考えているんだ」
俺の唐突な質問に、掃除の時間、同じ班になった二人が顔を上げた。
「俺? 言っただろ、プロサッカー選手。Jリーグで活躍して、できればセリエAに行きたい。……でも、親父は『現実を見ろ、公務員を目指せ』ってうるせぇんだよな」
邦彦が、モップを剣のように振り回しながら笑う。
俺は心の中で分析する。
「東鶴さんは?」
襟華は、掃除の手を休めて窓の外を見つめた。
「私は、短大に行って、銀行の一般職として就職できればいいかな。そこで数年働いて、素敵な人と出会って寿退社して……。専業主婦になって、静かに本を読んで暮らすの」
彼女の見通しは、1998年時点では「最も手堅い勝ち組のコース」に見えた。
当時はまだ、男女雇用機会均等法が浸透しつつも、地域や家庭には「女性は若いうちに良い縁談を見つけて家庭に入るのが一番の幸せ」という価値観が根強く残っていた。
「……銀行か。悪くない選択だが、銀行という組織そのものが10年後、20年後にどうなっているかまでは、想像したことがあるか?」
「え? 銀行がなくなるなんてこと、あるわけないじゃない。日本を支えている場所なんだから」
襟華は不思議そうに小首をかしげた。
「葛石、お前はどうなんだよ」
邦彦が問い返す。
「俺か。……俺は、物語の分岐点を買い叩きに来た。いわば、プレイヤーだ」
襟華がクスリと笑った。
「それ、最近のゲームみたいね。選択肢でエンディングが変わる、マルチエンディングの……『ときメモ』とか『バイオ』みたいな?」
「家庭用ゲーム機なら『ファイナルファンタジーVII』とかだな」
邦彦が例を出す。当時の感覚としては、ゲームはすでに「物語」を体験する最先端のツールだった。
「……俺は、この世界を『トゥルーエンド』に導くために、すべてのイベントをフラグ立てする。軽口だと思うなら、それでもいい」
二人は顔を見合わせて笑ったが、襟華だけは、俺の目をじっと見つめていた。
彼女の読書家としての直感が、俺の言葉の中に、中学生の背伸びではない「何か」を感じ取っているようだった。
放課後。俺は一人、図書室の窓際に座っていた。
視界の端で、部活動の練習に励む邦彦の声が聞こえる。
掃除中に交わした、彼らの「ささやかで、それでいて眩しい夢」。
本来なら、日本が繁栄を続けていれば、それらは当然のように叶えられたはずの未来だ。
しかし、俺は知っている。
少子高齢化という「静かなる有事」の芽は、すでにあちこちに噴き出していることを。
1998年の合計特殊出生率は、すでに1.38。本来なら、この時点で国を挙げての構造改革が必要だった。だが、誰もが「まだ大丈夫だ」と、かつての成功体験にすがっている。
(銀行事務から専業主婦……。襟華、君の描くその美しい曲線は、あと20年もすれば、低賃金のパート労働と介護に追われる直線へと書き換えられる。邦彦。プロを諦めた君が、非正規雇用の現場で使い捨てられる姿を、私は二度と見たくない)
俺の中に眠る60歳の亡霊が、冷酷な計算を弾き出す。
2043年。日本は「国立生命終結センター」で高齢者を処理するだけの、死にゆく島国に成り果てていた。
その「破滅」を阻止するためには、今、この1998年で、圧倒的な資本力を手に入れ、社会の構造そのものを強引に書き換える必要がある。
「……まずは、最初の不渡りを、救済に変えることから始めるか」
俺は、東鶴襟華から借りたレイモンド・チャンドラーの文庫本を開いた。
そこに挟まれた栞代わりに、俺は一枚のメモを挟んでいた。
そこには、現時点で最も「割安」に放置されているIT関連株のリストと、間もなく始まる「ドットコム・ブーム」のシナリオが書き込まれている。
15歳の少年の皮を被った、世界で唯一「未来を逆算できる銀行マン」。
葛石任三郎の、黄金の覇道。
それは、中学3年生の何気ない放課後、親友と美少女たちの笑い声の裏側で、音もなく実行されようとしていた。
午前6時30分。目覚まし時計のデジタル数字が切り替わるのと同時に、俺――葛石任三郎は意識を覚醒させた。
隣のベッドにいたはずの老いた肉体も、深夜に響く人工呼吸器の音もない。あるのは、若々しい心臓の鼓動と、驚くほど澄んだ視界だ。
起き上がり、洗面所へ向かう。
鏡に映っているのは、昨日までと同じ15歳の少年。しかし、冷たい水で顔を洗い、歯を磨きながらその貌を凝視すると、やはり違和感がある。彫りの深い彫刻のような鼻筋、一度狙った獲物を決して逸らさない鷹のような鋭い眼光。中学生という未熟なコミュニティにおいては、あまりに鋭利な「異物」だった。
「三郎、起きてるの? 朝ごはんできてるわよ」
階下から母・美津子の声が飛ぶ。
俺はクローゼットから、まだシワ一つない学ランを取り出した。1998年、詰め襟の学生服はまだ中学生のスタンダードだ。それを窮屈に感じながらも袖を通し、鏡の前で襟を正す。
ダイニングへ降りると、美津子がトーストと目玉焼きをテーブルに並べていた。
タイトなサマーニット越しにも分かる、しなやかで整ったプロポーション。30代後半という、女性としての円熟味と瑞々しさが絶妙に同居する彼女の美しさは、この界隈では有名だ。
「あら、今日もビシッとしてるわね。なんだか、お父さんより頼もしく見えるわよ」
「……そうか。父さんは?」
「もう出勤したわ。支店長会議があるんですって。大変そうよね、銀行も」
美津子が淹れてくれたコーヒーの香りを楽しみながら、俺は朝食を口にする。
「母さん。この家、あと10年もすれば価値が半分以下になる。……早めに売り抜けて、都心のマンションに切り替えることを検討しておいてくれ」
「えっ、急に何言ってるのよ。せっかく建てた家なのに」
「……リスク管理だよ。これからは、土地が資産になる時代じゃない。『知識』と『決断』が資産になる時代だ」
俺はバッグを掴むと、困惑する美津子を背に家を出た。
通学路の角で待っていたのは、門廻邦彦だった。
「よっ、任三郎! 今日は一段とシブい顔してんな!」
小学校からの腐れ縁で、家も近い親友。
サッカー部のキャプテンを務める彼は、4月の朝日を浴びて発光しているかのように爽やかだった。整ったルックスと、運動部特有の引き締まった肉体。彼が歩くだけで、すれ違う他校の女子生徒たちが密かに視線を送る。
「……邦彦。宿題は終わったのか」
「ギクッ……。お前、相変わらず鋭いな。昨日は部活のあとに『フランスW杯』の特番見てたら、いつの間にか寝ちゃってさ。お前の見せてくれよ、親友だろ?」
二人で並んで坂道を登る。
邦彦は将来、プロのスポーツ選手になることを本気で夢見ていた。
「俺さ、高校は推薦で『市立船橋』か『帝京』あたりを狙いたいんだよな。そこで活躍して、Jリーグのスカウトを待つ。今の日本代表、見てるか? カズさんやヒデさんみたいに、俺も世界へ行きたいんだ」
俺は歩きながら、隣の少年の「価値」を審美眼で測定する。
彼には才能がある。しかし、この1998年という時代の先にあるのは、未曾有の就職氷河期と、非正規雇用の拡大だ。スポーツ推薦で進学したとしても、一度の大怪我ですべてが瓦解する脆い道。
「邦彦。推薦もいいが、勉強も捨てすぎるな。これからのスポーツ選手は、エージェントとの契約書を自分で読める知性が必要になる。……お前にとってのサッカーが『投資』なら、怪我という不渡りに備えた保険が必要だ」
「投資? 保険? お前、本当に中学3年生かよ……」
邦彦は苦笑しながら、俺のバッグから突き出た漫画雑誌に目を留めた。
「あ、『週刊少年ジャンプ』買ったのか。貸してくれよ。俺、今週の『ONE PIECE』が読みたかったんだ。……それと、この前の『サンデー』も貸してやるよ。烈火の炎、マジで熱いぜ」
1998年。娯楽の王様はまだ雑誌であり、少年たちは紙の束を通じて未来を夢見ていた。
教室に入ると、俺の席の隣に彼女がいた。
東鶴襟華。
窓から差し込む春の光を受けて、彼女の金褐色の瞳が猫のように細められる。
早熟で完成された美貌。
彼女は机の上に一冊の文庫本を置いていた。
「おはよう、葛石くん。昨日貸した『フィリップ・K・ディック』、どうだった?」
「……悪くなかったよ。現実が何重にも剥がれていく感覚は、今の日本に似ているかもしれない」
「ふふ、相変わらず感想が哲学的ね」
襟華の影響で、俺は最近、文庫や新書を手に取ることが増えていた。
1998年という時代は、ファンタジーやSFが、単なる子供向けではなく「世界の捉え方」として、漫画やアニメ、ゲームを通じて当たり前のように共有され始めた時期だ。
「……なあ、二人は『将来』をどう考えているんだ」
俺の唐突な質問に、掃除の時間、同じ班になった二人が顔を上げた。
「俺? 言っただろ、プロサッカー選手。Jリーグで活躍して、できればセリエAに行きたい。……でも、親父は『現実を見ろ、公務員を目指せ』ってうるせぇんだよな」
邦彦が、モップを剣のように振り回しながら笑う。
俺は心の中で分析する。
「東鶴さんは?」
襟華は、掃除の手を休めて窓の外を見つめた。
「私は、短大に行って、銀行の一般職として就職できればいいかな。そこで数年働いて、素敵な人と出会って寿退社して……。専業主婦になって、静かに本を読んで暮らすの」
彼女の見通しは、1998年時点では「最も手堅い勝ち組のコース」に見えた。
当時はまだ、男女雇用機会均等法が浸透しつつも、地域や家庭には「女性は若いうちに良い縁談を見つけて家庭に入るのが一番の幸せ」という価値観が根強く残っていた。
「……銀行か。悪くない選択だが、銀行という組織そのものが10年後、20年後にどうなっているかまでは、想像したことがあるか?」
「え? 銀行がなくなるなんてこと、あるわけないじゃない。日本を支えている場所なんだから」
襟華は不思議そうに小首をかしげた。
「葛石、お前はどうなんだよ」
邦彦が問い返す。
「俺か。……俺は、物語の分岐点を買い叩きに来た。いわば、プレイヤーだ」
襟華がクスリと笑った。
「それ、最近のゲームみたいね。選択肢でエンディングが変わる、マルチエンディングの……『ときメモ』とか『バイオ』みたいな?」
「家庭用ゲーム機なら『ファイナルファンタジーVII』とかだな」
邦彦が例を出す。当時の感覚としては、ゲームはすでに「物語」を体験する最先端のツールだった。
「……俺は、この世界を『トゥルーエンド』に導くために、すべてのイベントをフラグ立てする。軽口だと思うなら、それでもいい」
二人は顔を見合わせて笑ったが、襟華だけは、俺の目をじっと見つめていた。
彼女の読書家としての直感が、俺の言葉の中に、中学生の背伸びではない「何か」を感じ取っているようだった。
放課後。俺は一人、図書室の窓際に座っていた。
視界の端で、部活動の練習に励む邦彦の声が聞こえる。
掃除中に交わした、彼らの「ささやかで、それでいて眩しい夢」。
本来なら、日本が繁栄を続けていれば、それらは当然のように叶えられたはずの未来だ。
しかし、俺は知っている。
少子高齢化という「静かなる有事」の芽は、すでにあちこちに噴き出していることを。
1998年の合計特殊出生率は、すでに1.38。本来なら、この時点で国を挙げての構造改革が必要だった。だが、誰もが「まだ大丈夫だ」と、かつての成功体験にすがっている。
(銀行事務から専業主婦……。襟華、君の描くその美しい曲線は、あと20年もすれば、低賃金のパート労働と介護に追われる直線へと書き換えられる。邦彦。プロを諦めた君が、非正規雇用の現場で使い捨てられる姿を、私は二度と見たくない)
俺の中に眠る60歳の亡霊が、冷酷な計算を弾き出す。
2043年。日本は「国立生命終結センター」で高齢者を処理するだけの、死にゆく島国に成り果てていた。
その「破滅」を阻止するためには、今、この1998年で、圧倒的な資本力を手に入れ、社会の構造そのものを強引に書き換える必要がある。
「……まずは、最初の不渡りを、救済に変えることから始めるか」
俺は、東鶴襟華から借りたレイモンド・チャンドラーの文庫本を開いた。
そこに挟まれた栞代わりに、俺は一枚のメモを挟んでいた。
そこには、現時点で最も「割安」に放置されているIT関連株のリストと、間もなく始まる「ドットコム・ブーム」のシナリオが書き込まれている。
15歳の少年の皮を被った、世界で唯一「未来を逆算できる銀行マン」。
葛石任三郎の、黄金の覇道。
それは、中学3年生の何気ない放課後、親友と美少女たちの笑い声の裏側で、音もなく実行されようとしていた。
10
あなたにおすすめの小説

異世界帰りのハーレム王
ぬんまる兄貴
ファンタジー
俺、飯田雷丸。どこにでもいる普通の高校生……だったはずが、気づいたら異世界に召喚されて魔王を倒してた。すごいだろ?いや、自分でもびっくりしてる。異世界で魔王討伐なんて人生のピークじゃねぇか?でも、そのピークのまま現実世界に帰ってきたわけだ。
で、戻ってきたら、日常生活が平和に戻ると思うだろ?甘かったねぇ。何か知らんけど、妖怪とか悪魔とか幽霊とか、そんなのが普通に見えるようになっちまったんだよ!なんだこれ、チート能力の延長線上か?それとも人生ハードモードのお知らせか?
異世界で魔王を倒した俺が、今度は地球で恋と戦いとボールを転がす!最高にアツいハーレムバトル、開幕!
異世界帰りのハーレム王
朝7:00/夜21:00に各サイトで毎日更新中!

男女比1対5000世界で俺はどうすれバインダー…
アルファカッター
ファンタジー
ひょんな事から男女比1対5000の世界に移動した学生の忠野タケル。
そこで生活していく内に色々なトラブルや問題に巻き込まれながら生活していくものがたりである!

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

転生したら名家の次男になりましたが、俺は汚点らしいです
NEXTブレイブ
ファンタジー
ただの人間、野上良は名家であるグリモワール家の次男に転生したが、その次男には名家の人間でありながら、汚点であるが、兄、姉、母からは愛されていたが、父親からは嫌われていた

異世界翻訳者の想定外な日々 ~静かに読書生活を送る筈が何故か家がハーレム化し金持ちになったあげく黒覆面の最強怪傑となってしまった~
於田縫紀
ファンタジー
図書館の奥である本に出合った時、俺は思い出す。『そうだ、俺はかつて日本人だった』と。
その本をつい翻訳してしまった事がきっかけで俺の人生設計は狂い始める。気がつけば美少女3人に囲まれつつ仕事に追われる毎日。そして時々俺は悩む。本当に俺はこんな暮らしをしてていいのだろうかと。ハーレム状態なのだろうか。単に便利に使われているだけなのだろうかと。
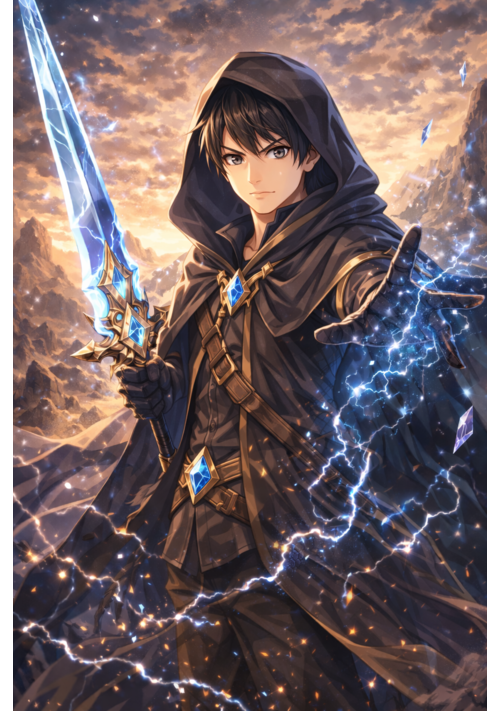
R・P・G ~転生して不死にされた俺は、最強の英雄たちと滅ぼすはずだった異世界を統治する~
イット
ファンタジー
オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の取材中、異世界の大地の女神と接触する。
半ば強制的に異世界へと転生させられた彼は、惑星そのものと同化し、“星骸の主”として不死の存在へと変貌した。
だが女神から与えられた使命は、この世界の生命を滅ぼし、星を「リセット」すること。凛人はその命令を、拒否する。
彼は、大地の女神により創造された星骸と呼ばれる伝説の六英雄の一人を従者とし、世界を知るため、そして残りの星骸を探すため旅に出る。
しかし一つ選択を誤れば世界が滅びる危うい存在……
女神の使命を「絶対拒否」する不死者と、裏ボス級の従者たち。
これは、世界を滅ぼさず、統治することを選んだ男の英雄譚である。

シシルナ島物語 少年薬師ノルド/ 荷運び人ノルド 蠱惑の魔剣
織部
ファンタジー
ノルドは、古き風の島、正式名称シシルナ・アエリア・エルダで育った。母セラと二人きりで暮らし。
背は低く猫背で、隻眼で、両手は動くものの、左腕は上がらず、左足もほとんど動かない、生まれつき障害を抱えていた。
母セラもまた、頭に毒薬を浴びたような痣がある。彼女はスカーフで頭を覆い、人目を避けてひっそりと暮らしていた。
セラ親子がシシルナ島に渡ってきたのは、ノルドがわずか2歳の時だった。
彼の中で最も古い記憶。船のデッキで、母セラに抱かれながら、この新たな島がゆっくりと近づいてくるのを見つめた瞬間だ。
セラの腕の中で、ぽつりと一言、彼がつぶやく。
「セラ、ウミ」
「ええ、そうよ。海」
ノルドの成長譚と冒険譚の物語が開幕します!
カクヨム様 小説家になろう様でも掲載しております。

転生先は上位貴族で土属性のスキルを手に入れ雑魚扱いだったものの職業は最強だった英雄異世界転生譚
熊虎屋
ファンタジー
現世で一度死んでしまったバスケットボール最強中学生の主人公「神崎 凪」は異世界転生をして上位貴族となったが魔法が土属性というハズレ属性に。
しかし職業は最強!?
自分なりの生活を楽しもうとするがいつの間にか世界の英雄に!?
ハズレ属性と最強の職業で英雄となった異世界転生譚。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















