4 / 13
第4話 巨塔の黄昏と、沈まぬ太陽
しおりを挟む
1998年、4月半ば。八王子市立第一中学校の校舎は、春の陽光に包まれていた。
昼休み。購買で買ったパンを片手に、俺――葛石任三郎は、グラウンドが見渡せる中庭のベンチに座っていた。
「よっ、任三郎! またそんな難しそうな顔してんのかよ」
声をかけてきたのは、門廻邦彦だ。
日焼けした肌に、運動部特有の引き締まった体躯。4月の光を反射するような彼の眩しさは、まさに1998年の希望そのものに見える。彼は俺の隣にどっかと腰を下ろすと、焼きそばパンを頬張りながら言った。
「なぁ、お前の親父さん、銀行員だよな。それも結構な役職なんだろ? やっぱりすげぇよな。銀行員って言えば、この時代の勝ち組じゃん。高給取りで、エリートで、合コンでもモテモテなんだろ? 羨ましいぜ、将来安泰でさ」
邦彦が無邪気に笑う。彼にとって、銀行員とは「盤石な巨塔」を守る騎士のように見えているのだろう。だが、俺の脳内にある2043年の記憶は、その巨塔が砂上の楼閣へと変わっていく過程を、残酷なまでに鮮明に記録していた。
俺は、彫りの深い顔立ちに微かな苦笑を浮かべ、遠くの校舎を見上げた。
「……給料だけを見れば、悪くないかもしれないな。だが邦彦、その対価は安くないぞ。父さんは平日は朝早くから夜遅くまで、泥のように働いている。俺と顔を合わせる暇もないほど忙しい。接待や会議に追われ、週末もゴルフだ。家では疲れ果てて、置物のように動かない。……あれを『勝ち組』と呼ぶには、失っているものが多すぎる気がするな」
「えぇ? でもさ、銀行ってのは金を持ってるんだろ? 世の中の金を回してる奴らが、なんでそんなに必死に働く必要があるんだよ」
邦彦が、口の周りにソースをつけたまま不思議そうに尋ねる。
俺は、目の前にある「1998年の平和な風景」の裏側で、すでに始まっている腐敗をどう説明すべきか考えた。
「銀行が苦しい理由は、歴史を遡ればキリがない。だが、簡単に言えば『水道管が詰まった』のさ」
俺は地面の砂を足でなぞりながら、比喩を重ねた。
「昔、たとえばオイルショックの頃とかは、金が足りない企業が山ほどいた。銀行は蛇口をひねるだけで、喉を枯らした連中が頭を下げて金を借りに来たんだ。だが、今は違う。バブルが弾けて、企業は借金という名の『毒』に懲りている。おまけに、日本という家そのものが、老朽化して水漏れを起こしているんだ」
「水道管? 水漏れ?」
「ああ。以前は『護送船団方式』なんて言って、国が銀行という船をまるごと守っていた。だが、冷戦が終わって世界が一つになり、外の強い奴らが『日本のルールは不公平だ』と怒り出したんだ。それが今の金融ビッグバンの正体さ。護送船は沈み始め、ネズミたちは逃げ出し始めている。……実際、去年の山一證券の破綻を見ただろう? あれは始まりに過ぎない。北海道拓殖銀行や、長銀……これから、誰もが『絶対』だと信じていた名前が、一つ、また一つと消えていくことになる」
「そんな……。銀行が潰れるなんて、嘘だろ?」
邦彦の顔から余裕が消える。
俺は内心で、本来ならここで長々と語るべき『BIS規制』や『自己資本比率』の話を飲み込んだ。中学生の彼に必要なのは、制度の歴史ではなく、目前の危機の手触りだ。
「企業の資金調達は、もう銀行からの借り入れだけじゃない。体力のある大企業は、自分たちで社債を発行して、市場から直接金を集められるようになった。……つまり、銀行にとっての『優良な顧客』ほど、銀行を必要としなくなっているんだ。残ったのは、倒産寸前の危うい会社や、無理なノルマを背負わされた営業の開拓先だけ。父さんが頭を下げて回っているのは、以前のように尊敬される貸し手としてじゃない。ノルマという名の鎖に繋がれた、集金人としての仕事なんだ」
「……ノルマか。サッカーの練習よりキツそうだな」
邦彦が少しだけ、俺の父親の苦労を理解したような顔をした。
1998年の会社員というものは、まだ「会社と一蓮托生」であるという幻想を捨てきれずにいた。だが、その裏側で、合併や支店整理という名の『リストラ』が、音もなく忍び寄っていたのだ。
「だから、葛石くんの将来の目標は、ゲーム制作なの?」
背後から、透き通った声がした。
振り返ると、そこには東鶴襟華が立っていた。
非の打ち所がない美貌。風に揺れる金褐色の長い髪と、モデルのようにスラリとした立ち姿は、この埃っぽい校庭でそこだけが異世界であるかのような錯覚を起こさせる。彼女は読書家らしく、文庫本を指先で弄びながら、俺の目をじっと見つめていた。
「さっきの掃除の時間の話。物語の分岐点を買い叩くって言ってたでしょ? それって、これから伸びるのがゲームみたいな仮想の世界だから?」
「……ゲーム制作そのものに興味があるわけじゃない、東鶴さん」
俺は姿勢を正し、彼女の隣に並んだ。15歳にして圧倒的な小顔とプロポーションを持つ彼女は、制服をまるでブランド物のスーツのように着こなしている。その横顔は、クールな中にもあどけなさが残り、クラス中の男子が彼女を「女神」と崇める理由がよくわかる。
「家電はもう、日本の家庭に行き渡ってしまった。これからは『箱』を売る時代ではなく、その中身、あるいは『繋がり』を売る時代が来る。東鶴さん、君が読んでいるその本も、いつかは紙ではなく、電気信号としてやり取りされるようになるかもしれない」
「本が、電気信号に……? それは少し寂しいわね」
彼女が猫のように目を細める。
「でも、わかる気がするわ。最近、携帯電話を持ってる人が急に増えたものね。あれって、単なる道具じゃなくて、自分の居場所を広げてるみたいに見えるわ」
「いい着眼点だ。携帯電話……いや、個人が常に情報を持ち歩く時代になれば、人と人の距離感は劇的に変わる。それは市場を拡大させると同時に、古い産業を根こそぎ破壊する暴力にもなるんだ」
俺はあえて、2043年の「スマートフォン」という言葉は使わなかった。今の彼女たちには、「通信機能のついた高度な情報端末」程度の認識がちょうどいい。
「……トレーディングカードゲームの話はどうだ? ほら、最近だと『遊戯王』や『ポケモンカード』が流行り始めているだろう?」
邦彦が話題に入ってくる。1998年、カードゲームは子供たちの遊びから、徐々に収集家たちの市場へと変貌しつつあった。
「あれも一種の『通貨』だよな。レアカード一枚で、何千円、何万円って取引される。……任三郎、お前の言ってる『価値の書き換え』って、そういうことか?」
「近いな。だが、あれはまだ可愛いものだ。これから俺がやろうとしているのは、そのカードの山そのものを支配し、ルールを書き換える側に回ることだ」
襟華が、俺の言葉を吟味するように頷いた。
「……相手や景気を見極める必要がある、ということね。本の中の登場人物みたいに、時代の波に飲まれるんじゃなくて、波がどこへ向かうかを知らなきゃいけない」
「その通りだ。バブルが弾けた後の今は、再編や支店整理で、金融業界はこれから血の滲むような大変な時期を迎える。そして、その空気は確実に俺たちの家庭にも降りてくる。……俺は、それを指をくわえて見ているつもりはない」
放課後の予鈴が鳴り響く。
邦彦は「部活に行ってくる!」と元気よく駆けていき、襟華は「この本の続き、明日貸してあげるわ」と微笑んで教室へ戻っていった。
一人残された俺は、図書室の隅にあるPCの前にいた。
ダイアルアップ接続のノイズが、脳内に響く。
画面に映し出されているのは、まだ無名に近いITベンチャーの株価。
(1998年。金融の巨塔が崩れ、瓦礫の中から新しい芽が吹き出す年)
父さんの帰宅は、今夜も遅いだろう。
融資ノルマに追われ、倒産寸前の企業の社長に頭を下げ、銀行という沈みゆく船の浸水を必死に防ごうとしている父。
その背中を、俺は否定しない。だが、俺は父のようにはならない。
「救済は、銀行の窓口では行われない。……資本の深淵、その一歩手前で行われるものだ」
俺は、獲物を捕らえる一瞬前の冷徹な瞳をディスプレイに向けた。
銀行という名の暴力を、飼い慣らす。
それは、中学3年生の葛石任三郎が、愛する人々を守るために選んだ、唯一にして最強の戦術だった。
窓の外では、グラウンドで邦彦がボールを追いかけ、図書室のどこかで襟華が静かにページをめくっている。
その平和な光景を、2043年の灰色の空に変えさせはしない。
昼休み。購買で買ったパンを片手に、俺――葛石任三郎は、グラウンドが見渡せる中庭のベンチに座っていた。
「よっ、任三郎! またそんな難しそうな顔してんのかよ」
声をかけてきたのは、門廻邦彦だ。
日焼けした肌に、運動部特有の引き締まった体躯。4月の光を反射するような彼の眩しさは、まさに1998年の希望そのものに見える。彼は俺の隣にどっかと腰を下ろすと、焼きそばパンを頬張りながら言った。
「なぁ、お前の親父さん、銀行員だよな。それも結構な役職なんだろ? やっぱりすげぇよな。銀行員って言えば、この時代の勝ち組じゃん。高給取りで、エリートで、合コンでもモテモテなんだろ? 羨ましいぜ、将来安泰でさ」
邦彦が無邪気に笑う。彼にとって、銀行員とは「盤石な巨塔」を守る騎士のように見えているのだろう。だが、俺の脳内にある2043年の記憶は、その巨塔が砂上の楼閣へと変わっていく過程を、残酷なまでに鮮明に記録していた。
俺は、彫りの深い顔立ちに微かな苦笑を浮かべ、遠くの校舎を見上げた。
「……給料だけを見れば、悪くないかもしれないな。だが邦彦、その対価は安くないぞ。父さんは平日は朝早くから夜遅くまで、泥のように働いている。俺と顔を合わせる暇もないほど忙しい。接待や会議に追われ、週末もゴルフだ。家では疲れ果てて、置物のように動かない。……あれを『勝ち組』と呼ぶには、失っているものが多すぎる気がするな」
「えぇ? でもさ、銀行ってのは金を持ってるんだろ? 世の中の金を回してる奴らが、なんでそんなに必死に働く必要があるんだよ」
邦彦が、口の周りにソースをつけたまま不思議そうに尋ねる。
俺は、目の前にある「1998年の平和な風景」の裏側で、すでに始まっている腐敗をどう説明すべきか考えた。
「銀行が苦しい理由は、歴史を遡ればキリがない。だが、簡単に言えば『水道管が詰まった』のさ」
俺は地面の砂を足でなぞりながら、比喩を重ねた。
「昔、たとえばオイルショックの頃とかは、金が足りない企業が山ほどいた。銀行は蛇口をひねるだけで、喉を枯らした連中が頭を下げて金を借りに来たんだ。だが、今は違う。バブルが弾けて、企業は借金という名の『毒』に懲りている。おまけに、日本という家そのものが、老朽化して水漏れを起こしているんだ」
「水道管? 水漏れ?」
「ああ。以前は『護送船団方式』なんて言って、国が銀行という船をまるごと守っていた。だが、冷戦が終わって世界が一つになり、外の強い奴らが『日本のルールは不公平だ』と怒り出したんだ。それが今の金融ビッグバンの正体さ。護送船は沈み始め、ネズミたちは逃げ出し始めている。……実際、去年の山一證券の破綻を見ただろう? あれは始まりに過ぎない。北海道拓殖銀行や、長銀……これから、誰もが『絶対』だと信じていた名前が、一つ、また一つと消えていくことになる」
「そんな……。銀行が潰れるなんて、嘘だろ?」
邦彦の顔から余裕が消える。
俺は内心で、本来ならここで長々と語るべき『BIS規制』や『自己資本比率』の話を飲み込んだ。中学生の彼に必要なのは、制度の歴史ではなく、目前の危機の手触りだ。
「企業の資金調達は、もう銀行からの借り入れだけじゃない。体力のある大企業は、自分たちで社債を発行して、市場から直接金を集められるようになった。……つまり、銀行にとっての『優良な顧客』ほど、銀行を必要としなくなっているんだ。残ったのは、倒産寸前の危うい会社や、無理なノルマを背負わされた営業の開拓先だけ。父さんが頭を下げて回っているのは、以前のように尊敬される貸し手としてじゃない。ノルマという名の鎖に繋がれた、集金人としての仕事なんだ」
「……ノルマか。サッカーの練習よりキツそうだな」
邦彦が少しだけ、俺の父親の苦労を理解したような顔をした。
1998年の会社員というものは、まだ「会社と一蓮托生」であるという幻想を捨てきれずにいた。だが、その裏側で、合併や支店整理という名の『リストラ』が、音もなく忍び寄っていたのだ。
「だから、葛石くんの将来の目標は、ゲーム制作なの?」
背後から、透き通った声がした。
振り返ると、そこには東鶴襟華が立っていた。
非の打ち所がない美貌。風に揺れる金褐色の長い髪と、モデルのようにスラリとした立ち姿は、この埃っぽい校庭でそこだけが異世界であるかのような錯覚を起こさせる。彼女は読書家らしく、文庫本を指先で弄びながら、俺の目をじっと見つめていた。
「さっきの掃除の時間の話。物語の分岐点を買い叩くって言ってたでしょ? それって、これから伸びるのがゲームみたいな仮想の世界だから?」
「……ゲーム制作そのものに興味があるわけじゃない、東鶴さん」
俺は姿勢を正し、彼女の隣に並んだ。15歳にして圧倒的な小顔とプロポーションを持つ彼女は、制服をまるでブランド物のスーツのように着こなしている。その横顔は、クールな中にもあどけなさが残り、クラス中の男子が彼女を「女神」と崇める理由がよくわかる。
「家電はもう、日本の家庭に行き渡ってしまった。これからは『箱』を売る時代ではなく、その中身、あるいは『繋がり』を売る時代が来る。東鶴さん、君が読んでいるその本も、いつかは紙ではなく、電気信号としてやり取りされるようになるかもしれない」
「本が、電気信号に……? それは少し寂しいわね」
彼女が猫のように目を細める。
「でも、わかる気がするわ。最近、携帯電話を持ってる人が急に増えたものね。あれって、単なる道具じゃなくて、自分の居場所を広げてるみたいに見えるわ」
「いい着眼点だ。携帯電話……いや、個人が常に情報を持ち歩く時代になれば、人と人の距離感は劇的に変わる。それは市場を拡大させると同時に、古い産業を根こそぎ破壊する暴力にもなるんだ」
俺はあえて、2043年の「スマートフォン」という言葉は使わなかった。今の彼女たちには、「通信機能のついた高度な情報端末」程度の認識がちょうどいい。
「……トレーディングカードゲームの話はどうだ? ほら、最近だと『遊戯王』や『ポケモンカード』が流行り始めているだろう?」
邦彦が話題に入ってくる。1998年、カードゲームは子供たちの遊びから、徐々に収集家たちの市場へと変貌しつつあった。
「あれも一種の『通貨』だよな。レアカード一枚で、何千円、何万円って取引される。……任三郎、お前の言ってる『価値の書き換え』って、そういうことか?」
「近いな。だが、あれはまだ可愛いものだ。これから俺がやろうとしているのは、そのカードの山そのものを支配し、ルールを書き換える側に回ることだ」
襟華が、俺の言葉を吟味するように頷いた。
「……相手や景気を見極める必要がある、ということね。本の中の登場人物みたいに、時代の波に飲まれるんじゃなくて、波がどこへ向かうかを知らなきゃいけない」
「その通りだ。バブルが弾けた後の今は、再編や支店整理で、金融業界はこれから血の滲むような大変な時期を迎える。そして、その空気は確実に俺たちの家庭にも降りてくる。……俺は、それを指をくわえて見ているつもりはない」
放課後の予鈴が鳴り響く。
邦彦は「部活に行ってくる!」と元気よく駆けていき、襟華は「この本の続き、明日貸してあげるわ」と微笑んで教室へ戻っていった。
一人残された俺は、図書室の隅にあるPCの前にいた。
ダイアルアップ接続のノイズが、脳内に響く。
画面に映し出されているのは、まだ無名に近いITベンチャーの株価。
(1998年。金融の巨塔が崩れ、瓦礫の中から新しい芽が吹き出す年)
父さんの帰宅は、今夜も遅いだろう。
融資ノルマに追われ、倒産寸前の企業の社長に頭を下げ、銀行という沈みゆく船の浸水を必死に防ごうとしている父。
その背中を、俺は否定しない。だが、俺は父のようにはならない。
「救済は、銀行の窓口では行われない。……資本の深淵、その一歩手前で行われるものだ」
俺は、獲物を捕らえる一瞬前の冷徹な瞳をディスプレイに向けた。
銀行という名の暴力を、飼い慣らす。
それは、中学3年生の葛石任三郎が、愛する人々を守るために選んだ、唯一にして最強の戦術だった。
窓の外では、グラウンドで邦彦がボールを追いかけ、図書室のどこかで襟華が静かにページをめくっている。
その平和な光景を、2043年の灰色の空に変えさせはしない。
10
あなたにおすすめの小説

異世界帰りのハーレム王
ぬんまる兄貴
ファンタジー
俺、飯田雷丸。どこにでもいる普通の高校生……だったはずが、気づいたら異世界に召喚されて魔王を倒してた。すごいだろ?いや、自分でもびっくりしてる。異世界で魔王討伐なんて人生のピークじゃねぇか?でも、そのピークのまま現実世界に帰ってきたわけだ。
で、戻ってきたら、日常生活が平和に戻ると思うだろ?甘かったねぇ。何か知らんけど、妖怪とか悪魔とか幽霊とか、そんなのが普通に見えるようになっちまったんだよ!なんだこれ、チート能力の延長線上か?それとも人生ハードモードのお知らせか?
異世界で魔王を倒した俺が、今度は地球で恋と戦いとボールを転がす!最高にアツいハーレムバトル、開幕!
異世界帰りのハーレム王
朝7:00/夜21:00に各サイトで毎日更新中!

男女比1対5000世界で俺はどうすれバインダー…
アルファカッター
ファンタジー
ひょんな事から男女比1対5000の世界に移動した学生の忠野タケル。
そこで生活していく内に色々なトラブルや問題に巻き込まれながら生活していくものがたりである!

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

転生したら名家の次男になりましたが、俺は汚点らしいです
NEXTブレイブ
ファンタジー
ただの人間、野上良は名家であるグリモワール家の次男に転生したが、その次男には名家の人間でありながら、汚点であるが、兄、姉、母からは愛されていたが、父親からは嫌われていた

異世界翻訳者の想定外な日々 ~静かに読書生活を送る筈が何故か家がハーレム化し金持ちになったあげく黒覆面の最強怪傑となってしまった~
於田縫紀
ファンタジー
図書館の奥である本に出合った時、俺は思い出す。『そうだ、俺はかつて日本人だった』と。
その本をつい翻訳してしまった事がきっかけで俺の人生設計は狂い始める。気がつけば美少女3人に囲まれつつ仕事に追われる毎日。そして時々俺は悩む。本当に俺はこんな暮らしをしてていいのだろうかと。ハーレム状態なのだろうか。単に便利に使われているだけなのだろうかと。
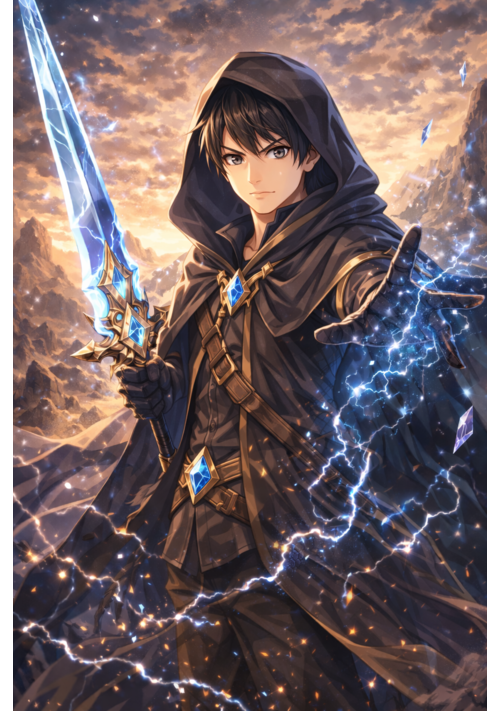
R・P・G ~転生して不死にされた俺は、最強の英雄たちと滅ぼすはずだった異世界を統治する~
イット
ファンタジー
オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の取材中、異世界の大地の女神と接触する。
半ば強制的に異世界へと転生させられた彼は、惑星そのものと同化し、“星骸の主”として不死の存在へと変貌した。
だが女神から与えられた使命は、この世界の生命を滅ぼし、星を「リセット」すること。凛人はその命令を、拒否する。
彼は、大地の女神により創造された星骸と呼ばれる伝説の六英雄の一人を従者とし、世界を知るため、そして残りの星骸を探すため旅に出る。
しかし一つ選択を誤れば世界が滅びる危うい存在……
女神の使命を「絶対拒否」する不死者と、裏ボス級の従者たち。
これは、世界を滅ぼさず、統治することを選んだ男の英雄譚である。

シシルナ島物語 少年薬師ノルド/ 荷運び人ノルド 蠱惑の魔剣
織部
ファンタジー
ノルドは、古き風の島、正式名称シシルナ・アエリア・エルダで育った。母セラと二人きりで暮らし。
背は低く猫背で、隻眼で、両手は動くものの、左腕は上がらず、左足もほとんど動かない、生まれつき障害を抱えていた。
母セラもまた、頭に毒薬を浴びたような痣がある。彼女はスカーフで頭を覆い、人目を避けてひっそりと暮らしていた。
セラ親子がシシルナ島に渡ってきたのは、ノルドがわずか2歳の時だった。
彼の中で最も古い記憶。船のデッキで、母セラに抱かれながら、この新たな島がゆっくりと近づいてくるのを見つめた瞬間だ。
セラの腕の中で、ぽつりと一言、彼がつぶやく。
「セラ、ウミ」
「ええ、そうよ。海」
ノルドの成長譚と冒険譚の物語が開幕します!
カクヨム様 小説家になろう様でも掲載しております。

転生先は上位貴族で土属性のスキルを手に入れ雑魚扱いだったものの職業は最強だった英雄異世界転生譚
熊虎屋
ファンタジー
現世で一度死んでしまったバスケットボール最強中学生の主人公「神崎 凪」は異世界転生をして上位貴族となったが魔法が土属性というハズレ属性に。
しかし職業は最強!?
自分なりの生活を楽しもうとするがいつの間にか世界の英雄に!?
ハズレ属性と最強の職業で英雄となった異世界転生譚。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















