2 / 27
約束
妖
しおりを挟む
そんなきっかけで、七瀬と秋臣は知り合い、仲良くなった。
馬が合うというのかは分からないが、秋臣のそばにいることは、七瀬にとって居心地がよかった。
何故だろう。一見するとタイプは違う二人であったが、互いに〝能力者〟であること、それぞれ家とは距離を置きたがっていること――その共通点が、二人を結び付けていたのかもしれない。
けれど、七瀬は思うのだ。〝能力者〟だとか、家庭との距離感が同じだからとか、そういうことを抜きにしても、秋臣自身には七瀬の興味をひく何かがあった。
だから七瀬は秋臣に声をかけたのだし、秋臣も似たような思いを感じたから、七瀬を拒まないのだろう。
二人はよく、高校の屋上で、何をするまでもなく、ただ空を眺めていた。
もちろん今時、学校の屋上は事故防止のために施錠されている。
しかし、妖と取引をすれば、七瀬には屋上の鍵を手に入れてスペアを作ることは簡単なことだったし、屋上に誰も近づかないように結界を張ることも難しくはなかった。
ただ彼らは静かな場所を求めていて、そしてその場に互いの存在があることが苦ではなかったから、七瀬は秋臣を誘い、秋臣もそれに乗ったのだった。
自らの能力のこと、互いの家のことを口にすることは、ほとんどなかった。互いに大体のことは知っていたし、知らないことは、相手が話そうとしないならそのままでよいと思っていた。
互いの胸の中には棘に覆われた秘密という名の花があり、それがわかっているから、あえて触れようとしなかった。
ある日、七瀬は、いつもは結界の中に入れない妖を連れてきた。
ペントハウスの陰に座っていた秋臣は、珍しいな、と目を上げていった。
通常、秋臣に妖は見えない。同じ〝能力者〟でも、七瀬が視る世界と秋臣が視る世界は違うからだ。しかし、七瀬の張る結界というのは便利なもので、術者の意思次第で、不要なものを結界からはじくことができるし、逆に入れることもできる。結界の中は、いわば七瀬の作った一つの小さな世界ともいえる。その中では、彼の意思次第で、妖も人間も可視・不可視にできるのだ。だから、現実では妖を視ることができない秋臣も、七瀬の結界の中では、七瀬が望めば、妖を視ることができるのだ。
「可愛い子だと思わない?」
その妖は、一見すると烏のようだった。しかし、その足は三本あった。
妖の類についての知識があまりない秋臣でも、おぼろげながら、その烏の姿は、彼の記憶に引っかかるものがあった。
「――八咫烏?」
肩にその妖を乗せた七瀬は、微笑んだ。
「そう呼ばれることもあるね。それはこの子たちが自称している名ではないけれど」
その烏の妖が自称している名に興味がないわけではなかったが、それよりも、何故、七瀬がその妖を連れてきたのかが気になった。
「ふうん。で、その妖はどうしたんだ」
「さっき、そこの階段で喰われそうになっているところを助けたんだ」
「喰われる?」
「妖の世界は弱肉強食だからね」
この世界と同じく、と七瀬は付け加えた。
しばらくの間、七瀬が八咫烏の艶やかな黒い背を撫でる様子を黙ってみていた秋臣は、不意に口を開いた。
「――あんたは、もう一つの世界が嫌いではないんだな」
七瀬は八咫烏に目を向けたまま、うん、と頷いた。
「妖の中には、お世話になったものもいる。うちの神社の蛇神の眷属である妖は、俺の親戚のような友人のようなものだから」
秋臣は、と七瀬は尋ねた。
「君の視る二つの世界は、嫌い?」
「……好きではない」
秋臣は、少し間を置いて答えた。
「……だが、好きでなくても視えて触れられるのだから、どうしようもない」
七瀬は八咫烏から目を上げて、秋臣を見た。
「……そうだね、どうしようもない」
七瀬は、秋臣が視る二つの世界を、直接は知らない。知るすべはない。
けれど、千里眼の能力は、時間や場所の概念がない世界とつながることで、現実での遠くの出来事や未来のことを知ることができるというものだ。そして、秋臣がその血筋ではなく、突然変異としてつながることになった、もうひとつの世界は――おそらく殺伐としたものであると想像できる。
七瀬にしても、妖の世界とつながれることは、良い事ばかりではない。
妖は人間の価値観とは別の価値観を持つ。妖は自分より弱い妖を喰うが、時々、人間も喰おうとする。危ない目にあったことも一度や二度ではない。
それに、知りたくもないことを不可抗力で知ってしまうのは、千里眼を持つ秋臣だけではない。七瀬も、知りたくないことを、妖の声で知ってしまうことがある。
だから、この現実と同様、心の底から妖の世界を好きだということはできない。けれど、嫌いでもない。
「こういう風に生まれてきちまったからな。好きではないが、あまり嫌わずに折り合っていくしかないんだよな」
それは七瀬に言うというより、独白のようだった。
返事は求められていなかったが、七瀬は敢えて、秋臣の言葉に自分なりの言葉を返した。
「折り合い……少なくとも俺は、秋臣と知り合ってから、折り合いはつけやすくなったかな」
秋臣は少し驚いたように、改めて七瀬を見た。
七瀬は微笑んだ。
「〝能力者〟の友人は初めてだし。でも、〝能力者〟かどうかは関係なくとも、秋臣みたいな友人は初めてだから」
秋臣は顔をそらした。彼の顔は影になり、その表情はよく見えない。
けれど、七瀬には、彼の表情がわかる気がした。
「この子を連れてきたのは」
秋臣が何も言わないので、七瀬は自分から言葉を紡いだ。
「助けた後、この子と話してたら、人間の友人はどういうものか見てみたいというから、俺の友人を紹介しようと思ったんだよ」
八咫烏は人間の言葉では喋らないが、妖の世界と通じる七瀬にはその言葉がわかる。結界の中では八咫烏の言葉を秋臣に聞かせることも可能だが、七瀬はそれを敢えてしなかった。
この八咫烏は妖の中ではかなり若く、人間の思惑考えなしにお喋りだったので、七瀬の言ったことをそのまま秋臣に喋りそうだったからだ。正直、七瀬自身は秋臣に聞かせてもよいが、秋臣はさらに恥ずかしがりそうだったので。
八咫烏は人間の言葉は喋れなくても、人間の言葉を理解することはできるので、七瀬の言葉を肯定するように羽を大きく広げた。そしてバランスを崩しかけて、七瀬の手に支えられた。
それを見て、秋臣は思わずといったように笑みをこぼした。
「おっちょこちょいな奴だな」
それに不満を抱いたらしく、八咫烏は再び羽を広げて秋臣のほうにくちばしを向け、威嚇した。
七瀬は軽く苦笑いをした。
「この子は妖にしては若いけれど、俺たちのほうがだいぶ若輩者だからね」
「俺は年上を無条件に敬うことはしないぞ」
と言いつつも、八咫烏の威嚇は嫌だったようで、秋臣は腕で顔をかばいながら七瀬達から少し遠ざかった。
八咫烏が落ち着きを取り戻すのを待ってから、秋臣は言った。
「それにしても、その妖は人間に興味があるのか」
「若いととくに。古老になってくると、人間に面白味を感じなくなってくるみたいだけれど」
「ああ、なんとなくわかる気がする」
秋臣は頷いた。
「妖ってのは、長生きなんだろ。あんまり長く生きてると、すべてに新鮮味をなくすよな」
妖と人間の、時間に対する認識は同じではない。しかし、神などと呼ばれる存在にまでなってくると、彼らは総じて長寿だから、さすがに退屈も感じるだろう。
「退屈を感じる前に――それよりも、他の妖に喰われる前に、いろいろと面白いことを知っておけよ」
秋臣は八咫烏にそう言って、笑いかけた。
八咫烏は、じっと彼を見つめ、それから自分を肩に乗せてくれている恩人を見つめ、何かを会得したように、一度頷いた。
馬が合うというのかは分からないが、秋臣のそばにいることは、七瀬にとって居心地がよかった。
何故だろう。一見するとタイプは違う二人であったが、互いに〝能力者〟であること、それぞれ家とは距離を置きたがっていること――その共通点が、二人を結び付けていたのかもしれない。
けれど、七瀬は思うのだ。〝能力者〟だとか、家庭との距離感が同じだからとか、そういうことを抜きにしても、秋臣自身には七瀬の興味をひく何かがあった。
だから七瀬は秋臣に声をかけたのだし、秋臣も似たような思いを感じたから、七瀬を拒まないのだろう。
二人はよく、高校の屋上で、何をするまでもなく、ただ空を眺めていた。
もちろん今時、学校の屋上は事故防止のために施錠されている。
しかし、妖と取引をすれば、七瀬には屋上の鍵を手に入れてスペアを作ることは簡単なことだったし、屋上に誰も近づかないように結界を張ることも難しくはなかった。
ただ彼らは静かな場所を求めていて、そしてその場に互いの存在があることが苦ではなかったから、七瀬は秋臣を誘い、秋臣もそれに乗ったのだった。
自らの能力のこと、互いの家のことを口にすることは、ほとんどなかった。互いに大体のことは知っていたし、知らないことは、相手が話そうとしないならそのままでよいと思っていた。
互いの胸の中には棘に覆われた秘密という名の花があり、それがわかっているから、あえて触れようとしなかった。
ある日、七瀬は、いつもは結界の中に入れない妖を連れてきた。
ペントハウスの陰に座っていた秋臣は、珍しいな、と目を上げていった。
通常、秋臣に妖は見えない。同じ〝能力者〟でも、七瀬が視る世界と秋臣が視る世界は違うからだ。しかし、七瀬の張る結界というのは便利なもので、術者の意思次第で、不要なものを結界からはじくことができるし、逆に入れることもできる。結界の中は、いわば七瀬の作った一つの小さな世界ともいえる。その中では、彼の意思次第で、妖も人間も可視・不可視にできるのだ。だから、現実では妖を視ることができない秋臣も、七瀬の結界の中では、七瀬が望めば、妖を視ることができるのだ。
「可愛い子だと思わない?」
その妖は、一見すると烏のようだった。しかし、その足は三本あった。
妖の類についての知識があまりない秋臣でも、おぼろげながら、その烏の姿は、彼の記憶に引っかかるものがあった。
「――八咫烏?」
肩にその妖を乗せた七瀬は、微笑んだ。
「そう呼ばれることもあるね。それはこの子たちが自称している名ではないけれど」
その烏の妖が自称している名に興味がないわけではなかったが、それよりも、何故、七瀬がその妖を連れてきたのかが気になった。
「ふうん。で、その妖はどうしたんだ」
「さっき、そこの階段で喰われそうになっているところを助けたんだ」
「喰われる?」
「妖の世界は弱肉強食だからね」
この世界と同じく、と七瀬は付け加えた。
しばらくの間、七瀬が八咫烏の艶やかな黒い背を撫でる様子を黙ってみていた秋臣は、不意に口を開いた。
「――あんたは、もう一つの世界が嫌いではないんだな」
七瀬は八咫烏に目を向けたまま、うん、と頷いた。
「妖の中には、お世話になったものもいる。うちの神社の蛇神の眷属である妖は、俺の親戚のような友人のようなものだから」
秋臣は、と七瀬は尋ねた。
「君の視る二つの世界は、嫌い?」
「……好きではない」
秋臣は、少し間を置いて答えた。
「……だが、好きでなくても視えて触れられるのだから、どうしようもない」
七瀬は八咫烏から目を上げて、秋臣を見た。
「……そうだね、どうしようもない」
七瀬は、秋臣が視る二つの世界を、直接は知らない。知るすべはない。
けれど、千里眼の能力は、時間や場所の概念がない世界とつながることで、現実での遠くの出来事や未来のことを知ることができるというものだ。そして、秋臣がその血筋ではなく、突然変異としてつながることになった、もうひとつの世界は――おそらく殺伐としたものであると想像できる。
七瀬にしても、妖の世界とつながれることは、良い事ばかりではない。
妖は人間の価値観とは別の価値観を持つ。妖は自分より弱い妖を喰うが、時々、人間も喰おうとする。危ない目にあったことも一度や二度ではない。
それに、知りたくもないことを不可抗力で知ってしまうのは、千里眼を持つ秋臣だけではない。七瀬も、知りたくないことを、妖の声で知ってしまうことがある。
だから、この現実と同様、心の底から妖の世界を好きだということはできない。けれど、嫌いでもない。
「こういう風に生まれてきちまったからな。好きではないが、あまり嫌わずに折り合っていくしかないんだよな」
それは七瀬に言うというより、独白のようだった。
返事は求められていなかったが、七瀬は敢えて、秋臣の言葉に自分なりの言葉を返した。
「折り合い……少なくとも俺は、秋臣と知り合ってから、折り合いはつけやすくなったかな」
秋臣は少し驚いたように、改めて七瀬を見た。
七瀬は微笑んだ。
「〝能力者〟の友人は初めてだし。でも、〝能力者〟かどうかは関係なくとも、秋臣みたいな友人は初めてだから」
秋臣は顔をそらした。彼の顔は影になり、その表情はよく見えない。
けれど、七瀬には、彼の表情がわかる気がした。
「この子を連れてきたのは」
秋臣が何も言わないので、七瀬は自分から言葉を紡いだ。
「助けた後、この子と話してたら、人間の友人はどういうものか見てみたいというから、俺の友人を紹介しようと思ったんだよ」
八咫烏は人間の言葉では喋らないが、妖の世界と通じる七瀬にはその言葉がわかる。結界の中では八咫烏の言葉を秋臣に聞かせることも可能だが、七瀬はそれを敢えてしなかった。
この八咫烏は妖の中ではかなり若く、人間の思惑考えなしにお喋りだったので、七瀬の言ったことをそのまま秋臣に喋りそうだったからだ。正直、七瀬自身は秋臣に聞かせてもよいが、秋臣はさらに恥ずかしがりそうだったので。
八咫烏は人間の言葉は喋れなくても、人間の言葉を理解することはできるので、七瀬の言葉を肯定するように羽を大きく広げた。そしてバランスを崩しかけて、七瀬の手に支えられた。
それを見て、秋臣は思わずといったように笑みをこぼした。
「おっちょこちょいな奴だな」
それに不満を抱いたらしく、八咫烏は再び羽を広げて秋臣のほうにくちばしを向け、威嚇した。
七瀬は軽く苦笑いをした。
「この子は妖にしては若いけれど、俺たちのほうがだいぶ若輩者だからね」
「俺は年上を無条件に敬うことはしないぞ」
と言いつつも、八咫烏の威嚇は嫌だったようで、秋臣は腕で顔をかばいながら七瀬達から少し遠ざかった。
八咫烏が落ち着きを取り戻すのを待ってから、秋臣は言った。
「それにしても、その妖は人間に興味があるのか」
「若いととくに。古老になってくると、人間に面白味を感じなくなってくるみたいだけれど」
「ああ、なんとなくわかる気がする」
秋臣は頷いた。
「妖ってのは、長生きなんだろ。あんまり長く生きてると、すべてに新鮮味をなくすよな」
妖と人間の、時間に対する認識は同じではない。しかし、神などと呼ばれる存在にまでなってくると、彼らは総じて長寿だから、さすがに退屈も感じるだろう。
「退屈を感じる前に――それよりも、他の妖に喰われる前に、いろいろと面白いことを知っておけよ」
秋臣は八咫烏にそう言って、笑いかけた。
八咫烏は、じっと彼を見つめ、それから自分を肩に乗せてくれている恩人を見つめ、何かを会得したように、一度頷いた。
0
あなたにおすすめの小説

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

孤独な蝶は仮面を被る
緋影 ナヅキ
BL
とある街の山の中に建っている、小中高一貫である全寮制男子校、華織学園(かしきのがくえん)─通称:“王道学園”。
全学園生徒の憧れの的である生徒会役員は、全員容姿や頭脳が飛び抜けて良く、運動力や芸術力等の他の能力にも優れていた。また、とても個性豊かであったが、役員仲は比較的良好だった。
さて、そんな生徒会役員のうちの1人である、会計の水無月真琴。
彼は己の本質を隠しながらも、他のメンバーと各々仕事をこなし、極々平穏に、楽しく日々を過ごしていた。
あの日、例の不思議な転入生が来るまでは…
ーーーーーーーーー
作者は執筆初心者なので、おかしくなったりするかもしれませんが、温かく見守って(?)くれると嬉しいです。
学生のため、ストック残量状況によっては土曜更新が出来ないことがあるかもしれません。ご了承下さい。
所々シリアス&コメディ(?)風味有り
*表紙は、我が妹である あくす(Twitter名) に描いてもらった真琴です。かわいい
*多少内容を修正しました。2023/07/05
*お気に入り数200突破!!有難う御座います!2023/08/25
*エブリスタでも投稿し始めました。アルファポリス先行です。2023/03/20


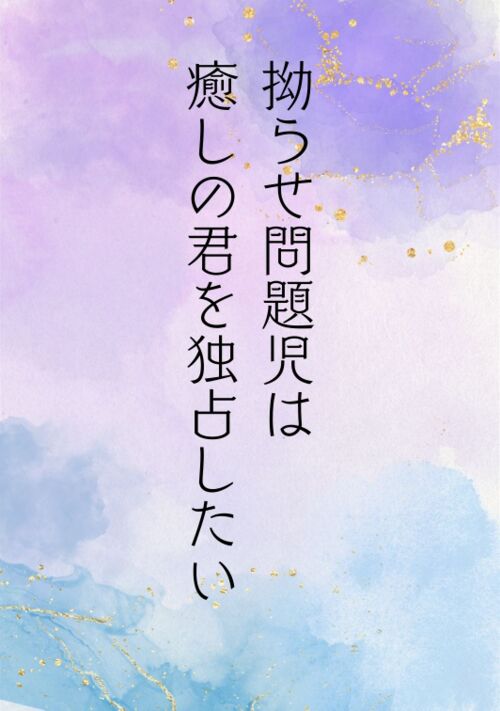
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















