24 / 27
冬の炎
過去との対峙
しおりを挟む
神社に帰り着き、律は事のあらましを語った。
それは大方、秋臣たちが予想していたことだった。死んだことを理解していないだけの幽霊なら、話し合えばあの世に行ってくれるだろうと思ったこと、納得して消えた幽霊もいたけれど、逆上した幽霊が襲ってきたのが、秋臣が駆け付けた時の状況だったことなど。ただ、秋臣に話した、八年前の火事、それから「敵意が怖い」ということは話さなかった。おそらくそれを秋臣に打ち明けたのは、動転していたからなのだろう。
そして、自分の予想と反し、幽霊への対処が上手くいかなかったのが堪えたのだろう。律はしおらしく、「鷲宮怜子と連絡が取れるまで勝手なことはしない」という七瀬の言葉に頷いた。
律はそのまま部屋にこもってしまい、あとは秋臣と七瀬が居間に残された。
七瀬は、秋臣の様子がおかしいことに気づいたのだろう。どうしたのかは問わなかったが、目線だけで話を促した。
秋臣はただ一言、「俺が見た火事は、あいつの家の火事だったらしい」とだけ言った。
七瀬が息を呑む気配がした。
「それじゃあ、秋臣が幼いころに公園で仲良くなった年下の子というのは」
「浅沼律だったらしいな」
どおりで、彼の名前が引っかかっていたわけである。
あいつはまだそれを知らない、と秋臣は言った。そして、いくらか迷ってから、やはり詳しく説明しようと口を開いた。
「だけど、あいつは、その公園の友達が自分の家に火をつけたと思っている。火事の際、俺の手に現れていた炎を見ていたらしい。何か火のついたものを持っていた、と思っているが」
どうしたもんか、と溜息を漏らして、秋臣は頭を抱える。
「せめて、火事が俺の能力のせいかどうか、分かればいいんだがな……」
放火なら、放火犯が捕まってくれていたらよかったのだが。もう八年も前のことだ。今から調べても手掛かりがあるとは思えない。しかし、もしかすると、久世家は――祖母や両親は、何か知っているのでは? けれど、秋臣がその記憶を避け続けてきたために、誰も何も言ってこないのでは?
「妖なら……」
七瀬が呟いた。
「もしかしたら、何か見ていたかもしれない。人間は誰も見ていなくても、彼らなら」
聞いてみるよ、と七瀬は秋臣の肩に手を置いて言う。
「悪いな」
なんだか自分が情けなくも思えてきて、秋臣は自嘲気味な笑みを浮かべた。
「蛇神の時といい、今回といい、どうも、お前に面白くもない過去の話をしがちだな、俺は」
すると、七瀬は秋臣の額を軽く叩いた。
「秋臣の過去も全部、おれは知りたいから、いいんだよ」
何度でも言うけども、と七瀬は今しがた叩いた額に唇を近づけた。
「おれにそういう遠慮はいらないから」
七瀬は言葉ではかなり秋臣の心臓を止まらせるようなことを言うが、行動でそうすることはあまりなかった。
彼は幼いころからスキンシップになれていないせいで、そういうものに免疫もないし慣れてもいないのである。たまに、言葉が足りないと思った時は、手を握りしめるなどはするが。
逆に秋臣は、幼いころから叔母や従姉妹たちのおもちゃにされていたせいで、スキンシップには慣れており、七瀬の言葉で心臓に負担をかけられる分、行動では彼の上手に立っていた。
それが今回、思いもかけず、七瀬から行動を起こされたせいで、秋臣は驚き、心臓が止まる思いがした。
それが七瀬なりの、精一杯踏み込んだ慰め方なのだとは分かっていた。
その気持ちと行動はどうにも嬉しく、こそばゆく、何とも言えず、秋臣は何故だか泣きたくなった。
まあ、そのあと、特に他には何も起こらず、七瀬は恥じたように台所に引っ込んでしまったが。
それでもなんだか、秋臣は、このままではいけない、と思ったのである。
過去に決着を付けなくては、と。
あれ以降、律はそれまでどおり、神崎家に滞在していたし、ちゃんとお守りも鈴も持っていたし(鈴の効果は七瀬が説明してあった)、相変わらず鷲宮凛久とは連絡がつかなかった。
ただあれから少し変化したことといえば、律の秋臣への態度が少し軟化したことである。過去のことを打ち明けられていない秋臣としては複雑だが、律のほうとしては、図らずも秋臣に助けられたことか、はたまた自分の弱さを見せてしまったことがきっかけなのか、何かしら思うところがあったようだ。訳もなく秋臣につっかかってくることはなくなり、素直になった。
だから余計、秋臣は、せめてクリスマスイブまでには、過去のこととちゃんと向き合いたいと思ったのである。
八年前の火事の一件に詳しいのは、秋臣のほかには、一番は久世家の実質的な当主である祖母だろう。次に権力の強い母は今、妊娠中であり、しかも出産予定の月であり、余計な負担はかけたくない。
秋臣は祖母が苦手だった。実質の久世家の当主ともいえる権力者であり、おそらく一族の中で一番、千里眼の能力が高い。彼女と会うたび、秋臣はすべてを見透かされているような気がして、少し恐ろしいのだった。
それでも、彼女から話を聞かなくてはならない。それも、祖母と秋臣の二人だけで。
律もおとなしくなったようなので、秋臣は一旦神崎家を離れ、実家に戻ってきた。
事前に連絡してあったので、スムーズに祖母に取り次がれた。久世家は、この祖母と会うにも、なかなか大変なのである。
珍しいことに、秋臣が通されたのは、祖母の自室だった。幼いころを思い出しても、滅多に入ったことがない。
祖母の部屋は本当にものがあまりなかった。そして彼女は、いつもの和服を着て、縁側から庭を眺めていた。
「ここへ来た理由はわかっていますよ」
と、開口一番、祖母は言った。
秋臣は用意された座布団に座らず、襖を閉めて立ったまま、彼女の横顔を見て言う。
「では、俺の問いに対する答えを持っているのですか」
祖母はちらりと孫を見た。
「あなたが自分の力と向き合う気になったのなら、答えましょう」
自分の力、とは、この場合、おそらく、千里眼ではなく、火の能力のほうだろう。
ずっと、忌むものとして蓋をしてきた。記憶そのものさえ。
しかし、ここで、向き合わなくてはならないのだ。もちろんそれは、律のためでもあり、そして何より、自分を受け入れてくれる七瀬のためでもある。
誠心誠意、自分に向き合ってくれる人がいる。ならば、自分も誠心誠意、自信と無機泡うべきだろう。
秋臣は頷いた。
「八年前、おれのもう一つの能力は目覚めました。火を発出する能力です。ちょうどそのころ、俺の知り合いの家が火事になりました。おそらく、あなたはあらゆる力を使って、その原因、俺の力との関係性の有無を調べたでしょう」
「ええ、もちろん、調べましたよ」
「だが、俺には、その結果は何も伝わっていない」
秋臣の言葉に、祖母の君江は改めて孫を見つめた。
「あなたが結果を拒否していた――どんな結果も受け付けるような状態ではなかったからですよ」
八年前、秋臣は火事を目撃した後、数日間、高熱で意識がない状態だった。それは、新しい力が発現した副作用のようなものだったのだろう。
しかし、その熱が下がっても、その新しい力の実験の最中も、秋臣はその力を拒否し続けた。それは結果的に、彼の身体にも影響を及ぼし、その精神から体へと蝕み始めた。
「え……」
祖母の説明に、秋臣は目を見開いた。
「覚えていませんか。能力の発現後、半年ほど、あなたは入退院を繰り返していましたよ」
そういわれて、秋臣は改めて自らの記憶を探る。自分の体が丈夫なことが取り柄だと思っていた。しかし――八年前の火事前後の記憶は曖昧で、あまり覚えていないのは確かだった。
「自分の気持ちが能力を受け入れられない状態では、よくあることです。それで、私たちはある決断をしました。秋臣がその能力を受け止められるようになるまで、このことには触れないようにすると」
確かに、久世家で、秋臣の火の能力についての話題はタブーだった。しかし、それは、一族の能力ではないものも発現させた突然変異を忌んでいるのだとばかり、秋臣は思っていた。〝能力者〟は、普通の人々から見たら異端、二つ以上の能力を宿す秋臣のような人物は、その〝能力者〟の中でさえ、異端である。そして、異端は忌避され嫌われる。そういう構図だとばかり思っていた。
「あなたが気に病んでいるその火事の原因があなたの能力であれ、そうでないのであれ、その話題はあなたのトラウマでした。だから、あなたには調査結果を伝えていないのですよ」
しかし、と祖母は言った。
「あなたが知りたいと思った時、私たちは結果を開示すると決めていました。そしてそれは、今このときのようですね」
祖母は部屋の片隅の小さな戸棚の引き出しから、ある紙束を取り出し、秋臣に手渡した。
「これが、あなたが知りたがっている全てです」
それは大方、秋臣たちが予想していたことだった。死んだことを理解していないだけの幽霊なら、話し合えばあの世に行ってくれるだろうと思ったこと、納得して消えた幽霊もいたけれど、逆上した幽霊が襲ってきたのが、秋臣が駆け付けた時の状況だったことなど。ただ、秋臣に話した、八年前の火事、それから「敵意が怖い」ということは話さなかった。おそらくそれを秋臣に打ち明けたのは、動転していたからなのだろう。
そして、自分の予想と反し、幽霊への対処が上手くいかなかったのが堪えたのだろう。律はしおらしく、「鷲宮怜子と連絡が取れるまで勝手なことはしない」という七瀬の言葉に頷いた。
律はそのまま部屋にこもってしまい、あとは秋臣と七瀬が居間に残された。
七瀬は、秋臣の様子がおかしいことに気づいたのだろう。どうしたのかは問わなかったが、目線だけで話を促した。
秋臣はただ一言、「俺が見た火事は、あいつの家の火事だったらしい」とだけ言った。
七瀬が息を呑む気配がした。
「それじゃあ、秋臣が幼いころに公園で仲良くなった年下の子というのは」
「浅沼律だったらしいな」
どおりで、彼の名前が引っかかっていたわけである。
あいつはまだそれを知らない、と秋臣は言った。そして、いくらか迷ってから、やはり詳しく説明しようと口を開いた。
「だけど、あいつは、その公園の友達が自分の家に火をつけたと思っている。火事の際、俺の手に現れていた炎を見ていたらしい。何か火のついたものを持っていた、と思っているが」
どうしたもんか、と溜息を漏らして、秋臣は頭を抱える。
「せめて、火事が俺の能力のせいかどうか、分かればいいんだがな……」
放火なら、放火犯が捕まってくれていたらよかったのだが。もう八年も前のことだ。今から調べても手掛かりがあるとは思えない。しかし、もしかすると、久世家は――祖母や両親は、何か知っているのでは? けれど、秋臣がその記憶を避け続けてきたために、誰も何も言ってこないのでは?
「妖なら……」
七瀬が呟いた。
「もしかしたら、何か見ていたかもしれない。人間は誰も見ていなくても、彼らなら」
聞いてみるよ、と七瀬は秋臣の肩に手を置いて言う。
「悪いな」
なんだか自分が情けなくも思えてきて、秋臣は自嘲気味な笑みを浮かべた。
「蛇神の時といい、今回といい、どうも、お前に面白くもない過去の話をしがちだな、俺は」
すると、七瀬は秋臣の額を軽く叩いた。
「秋臣の過去も全部、おれは知りたいから、いいんだよ」
何度でも言うけども、と七瀬は今しがた叩いた額に唇を近づけた。
「おれにそういう遠慮はいらないから」
七瀬は言葉ではかなり秋臣の心臓を止まらせるようなことを言うが、行動でそうすることはあまりなかった。
彼は幼いころからスキンシップになれていないせいで、そういうものに免疫もないし慣れてもいないのである。たまに、言葉が足りないと思った時は、手を握りしめるなどはするが。
逆に秋臣は、幼いころから叔母や従姉妹たちのおもちゃにされていたせいで、スキンシップには慣れており、七瀬の言葉で心臓に負担をかけられる分、行動では彼の上手に立っていた。
それが今回、思いもかけず、七瀬から行動を起こされたせいで、秋臣は驚き、心臓が止まる思いがした。
それが七瀬なりの、精一杯踏み込んだ慰め方なのだとは分かっていた。
その気持ちと行動はどうにも嬉しく、こそばゆく、何とも言えず、秋臣は何故だか泣きたくなった。
まあ、そのあと、特に他には何も起こらず、七瀬は恥じたように台所に引っ込んでしまったが。
それでもなんだか、秋臣は、このままではいけない、と思ったのである。
過去に決着を付けなくては、と。
あれ以降、律はそれまでどおり、神崎家に滞在していたし、ちゃんとお守りも鈴も持っていたし(鈴の効果は七瀬が説明してあった)、相変わらず鷲宮凛久とは連絡がつかなかった。
ただあれから少し変化したことといえば、律の秋臣への態度が少し軟化したことである。過去のことを打ち明けられていない秋臣としては複雑だが、律のほうとしては、図らずも秋臣に助けられたことか、はたまた自分の弱さを見せてしまったことがきっかけなのか、何かしら思うところがあったようだ。訳もなく秋臣につっかかってくることはなくなり、素直になった。
だから余計、秋臣は、せめてクリスマスイブまでには、過去のこととちゃんと向き合いたいと思ったのである。
八年前の火事の一件に詳しいのは、秋臣のほかには、一番は久世家の実質的な当主である祖母だろう。次に権力の強い母は今、妊娠中であり、しかも出産予定の月であり、余計な負担はかけたくない。
秋臣は祖母が苦手だった。実質の久世家の当主ともいえる権力者であり、おそらく一族の中で一番、千里眼の能力が高い。彼女と会うたび、秋臣はすべてを見透かされているような気がして、少し恐ろしいのだった。
それでも、彼女から話を聞かなくてはならない。それも、祖母と秋臣の二人だけで。
律もおとなしくなったようなので、秋臣は一旦神崎家を離れ、実家に戻ってきた。
事前に連絡してあったので、スムーズに祖母に取り次がれた。久世家は、この祖母と会うにも、なかなか大変なのである。
珍しいことに、秋臣が通されたのは、祖母の自室だった。幼いころを思い出しても、滅多に入ったことがない。
祖母の部屋は本当にものがあまりなかった。そして彼女は、いつもの和服を着て、縁側から庭を眺めていた。
「ここへ来た理由はわかっていますよ」
と、開口一番、祖母は言った。
秋臣は用意された座布団に座らず、襖を閉めて立ったまま、彼女の横顔を見て言う。
「では、俺の問いに対する答えを持っているのですか」
祖母はちらりと孫を見た。
「あなたが自分の力と向き合う気になったのなら、答えましょう」
自分の力、とは、この場合、おそらく、千里眼ではなく、火の能力のほうだろう。
ずっと、忌むものとして蓋をしてきた。記憶そのものさえ。
しかし、ここで、向き合わなくてはならないのだ。もちろんそれは、律のためでもあり、そして何より、自分を受け入れてくれる七瀬のためでもある。
誠心誠意、自分に向き合ってくれる人がいる。ならば、自分も誠心誠意、自信と無機泡うべきだろう。
秋臣は頷いた。
「八年前、おれのもう一つの能力は目覚めました。火を発出する能力です。ちょうどそのころ、俺の知り合いの家が火事になりました。おそらく、あなたはあらゆる力を使って、その原因、俺の力との関係性の有無を調べたでしょう」
「ええ、もちろん、調べましたよ」
「だが、俺には、その結果は何も伝わっていない」
秋臣の言葉に、祖母の君江は改めて孫を見つめた。
「あなたが結果を拒否していた――どんな結果も受け付けるような状態ではなかったからですよ」
八年前、秋臣は火事を目撃した後、数日間、高熱で意識がない状態だった。それは、新しい力が発現した副作用のようなものだったのだろう。
しかし、その熱が下がっても、その新しい力の実験の最中も、秋臣はその力を拒否し続けた。それは結果的に、彼の身体にも影響を及ぼし、その精神から体へと蝕み始めた。
「え……」
祖母の説明に、秋臣は目を見開いた。
「覚えていませんか。能力の発現後、半年ほど、あなたは入退院を繰り返していましたよ」
そういわれて、秋臣は改めて自らの記憶を探る。自分の体が丈夫なことが取り柄だと思っていた。しかし――八年前の火事前後の記憶は曖昧で、あまり覚えていないのは確かだった。
「自分の気持ちが能力を受け入れられない状態では、よくあることです。それで、私たちはある決断をしました。秋臣がその能力を受け止められるようになるまで、このことには触れないようにすると」
確かに、久世家で、秋臣の火の能力についての話題はタブーだった。しかし、それは、一族の能力ではないものも発現させた突然変異を忌んでいるのだとばかり、秋臣は思っていた。〝能力者〟は、普通の人々から見たら異端、二つ以上の能力を宿す秋臣のような人物は、その〝能力者〟の中でさえ、異端である。そして、異端は忌避され嫌われる。そういう構図だとばかり思っていた。
「あなたが気に病んでいるその火事の原因があなたの能力であれ、そうでないのであれ、その話題はあなたのトラウマでした。だから、あなたには調査結果を伝えていないのですよ」
しかし、と祖母は言った。
「あなたが知りたいと思った時、私たちは結果を開示すると決めていました。そしてそれは、今このときのようですね」
祖母は部屋の片隅の小さな戸棚の引き出しから、ある紙束を取り出し、秋臣に手渡した。
「これが、あなたが知りたがっている全てです」
0
あなたにおすすめの小説

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

孤独な蝶は仮面を被る
緋影 ナヅキ
BL
とある街の山の中に建っている、小中高一貫である全寮制男子校、華織学園(かしきのがくえん)─通称:“王道学園”。
全学園生徒の憧れの的である生徒会役員は、全員容姿や頭脳が飛び抜けて良く、運動力や芸術力等の他の能力にも優れていた。また、とても個性豊かであったが、役員仲は比較的良好だった。
さて、そんな生徒会役員のうちの1人である、会計の水無月真琴。
彼は己の本質を隠しながらも、他のメンバーと各々仕事をこなし、極々平穏に、楽しく日々を過ごしていた。
あの日、例の不思議な転入生が来るまでは…
ーーーーーーーーー
作者は執筆初心者なので、おかしくなったりするかもしれませんが、温かく見守って(?)くれると嬉しいです。
学生のため、ストック残量状況によっては土曜更新が出来ないことがあるかもしれません。ご了承下さい。
所々シリアス&コメディ(?)風味有り
*表紙は、我が妹である あくす(Twitter名) に描いてもらった真琴です。かわいい
*多少内容を修正しました。2023/07/05
*お気に入り数200突破!!有難う御座います!2023/08/25
*エブリスタでも投稿し始めました。アルファポリス先行です。2023/03/20


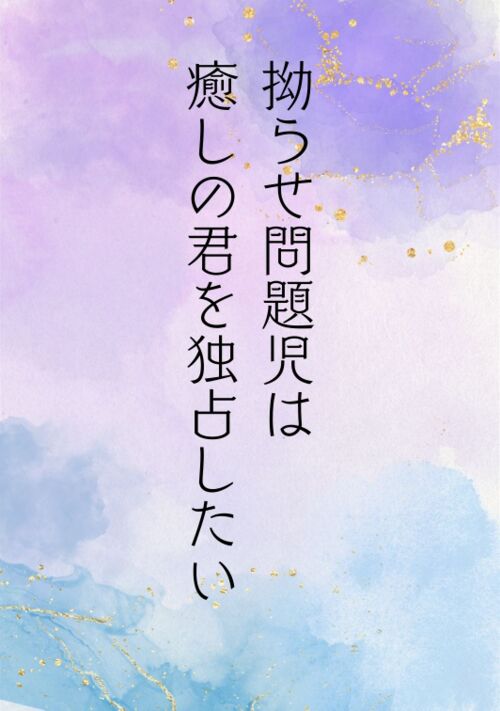
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















