33 / 49
第三章 出会いは風のごとく
⑭
しおりを挟む
客室でのまったりとしたくつろぎにも限界があって、もともと人と顔を付き合わせて長々と話をするのが苦手な僕は、ちょっと外の空気を、などとお決まりの言い訳を置き去りにして、デッキに出た。
船の後方にある手すりにもたれ、すでに豆粒ほどに小さくなっている陸地に目を向ける。大きな海と比べると、陸地のなんと小さなことか。まるでパンケーキの真ん中にポツンと垂らしたチョコレートシロップ。僕は、あんな小さなところに住んでいるのか。あんな小さなところで偉そうなことを言っているのか。ぬるま湯程度のわがままをまき散らしながら。
船の上とはいえ、海のまっただ中を運ばれている今の僕に自由はない。この船が僕を海に放り投げて、「さあ、生意気盛りの高校生よ。わがまま好き放題を言えるものなら言ってみな」と冷笑すれば、お願いです助けてくださいと懇願するしかないだろう。それなりに生意気でわがままを言う高校生なんて、場所が変わればそんなものだ、プールに投げ込まれたアリのほうがよっぽど頼もしい存在だということが、ここに立っていれば理解できる。
もとはと言えば、僕のわがままから始まったプチ家出。それが、こんな展開になるなんて。
今僕は、どうして船に乗っているんだろうな。改めてそう考えたとき、急におかしさがこみ上げてきた。手すりに両腕を乗せ、その上にアゴを乗せてクツクツ笑っていたとき、菜々実が近づいてきた。
「なによ、気持ち悪いよ、公彦」菜々実が真横に立ち、僕の焦った顔をのぞき込む。「海を見て思い出に浸っているわけ? 女の一人旅的シチュエーションは、あんたには似合わないよ」
「ほっといてくれ」僕は赤面しているのをごまかすために、反対を向いた。熱い頬に潮風が優しい。「菜々実こそ、お菓子はもういいのか? 今のうちに食べておかないと、忙しくなるかもしれないよ」
「だいじょうぶ、あたしはどんな状況下に置かれても、食べるときは食べますから」菜々実が手すりにもたれたまま笑った。
数秒間の沈黙を破ったのは菜々実だ。
「ねえ公彦。静香さんに聞いたんだけど、このドライブのきっかけは、あんただってね」菜々実が首だけ僕のほうへ向ける。「どうして? そんなこと、ぜんぜん言っていなかったじゃない。急に思いついた?」
「いや、僕が企画したっていうか、計画したのは、プチ家出だよ。ドライブじゃない」
「家出? あんた家出をする気だったの?」驚いた菜々実が体ごとこっちを向く。「どうして?」
「家出じゃなくてプチ家出」僕は横目で菜々実をにらんだ。「プチをつけてくれ、プチを」
「わかったわかった。プチね、プチ家出ね」菜々実が面倒くさそうに手を振った。「で? そのプチ君をやろうと思ったわけは?」
僕は海を見つめた。波が白い腹を見せながら遠ざかっていく。菜々実がじっと僕の答えを待っているのを横顔に感じた。
「っておい、この間はやめてくれ。タメを作って期待させるほどのことなんて、なんにもないよ」僕はまた赤面する。「そんな、たいしたことじゃない。ただ、ちょっとさ、最近カッタルいことが多いから、気分転換にというか」
「へえ。あんた、気分転換で家出をするタイプだったっけ」菜々実が首をかしげる。「あ、ごめん。プチ家出だったね」
「そんなこと、改めて聞かないでくれよな。恥ずかしいだろ」僕は唇を尖らせた。「別に説明するほどのこともないんだよ。ほんとに、ちょっとした気分転換みたいなもので。それで、あの」
「高校生だもんね。気分なんて、あそこに浮かんでいる板切れのようなものでしょ」菜々実が波に揉まれながら漂っている木片を指差した。「あたしだってそんな気になること、しょっちゅうだし。みんなそうでしょ。ただ、やるかやらないかの問題でしょ。とはいっても、やる、やらないの間には、このくらいの隔たりがあるけどね」菜々実が両手を目一杯に広げた。Tシャツの袖から海風が侵入し、胸元をばたつかせた。
「いや、だからそんなたいしたことは」と僕はいいかけてやめた。この海の上には似つかわしくない言い訳だろうから。僕は少しだけ菜々実とベクトルの方向を近づけることにした。
「まあ、ネギのようなもんだよ」僕はくるりと海に背を向けて手すりにもたれた。目の下を人差し指でかく。
「ネギ? なにそれ」
「うちの母さんは味噌汁にネギを入れるのが大嫌いでさ。でも、逆に僕はネギが大好きときたもんだ。そこで好みが分かれる」
「意見が違うっていうの? なによ、そんなの、後で入れればいいだけの話じゃない。食べるときに、パッとネギだけ放り込めば」
「そういうことじゃなくてさ、なんていうか、物足りないんだと思う。人がこれがいいと思っているものが、僕には物足りない。母さんの完成品は、僕には物足りない。父さんの意見は、一応頭では理解してできる限り尊重するけど、しっくりこないことも多い。そんなことが多すぎるんだと思う。中学生の時に比べて、それは何倍もに膨れあがったように感じるんだ。まあ、自分の意見を言えばすむことなんだろうけど、それすらカッタルいことも多いし。だから、その」
「だから、プチ家出ってことなのね」菜々実が僕の言葉を引き継いだ。「それって、大人から見ればばかばかしくてたいしたことじゃないと思えるんだよね。でも、あたしたちにとってはそうじゃない」菜々実が微笑んだ。「あたしはわかるよ、その感覚。ま、ひとえにあんたが優しすぎるから余計に悩むのでしょうけど」
「そんなことはないけどさ」僕はまたそっぽを向いた。海風が方向を変えた。菜々実のシャンプーの香りが鼻をくすぐる。「SNS、趣味なんだけど。ツイッターとか」
「うん、知ってる」菜々実が歌うように言う。
「ああいうところって、言いたいことがなんでも言えて、意見を同じくする者同士で肩を組み、意見が異なる者とはガチに議論する。それをコクのあるラーメンとするなら、現実のふれあいは、家族にしても友人にしても、病院食のような薄味のラーメンなのかも知れない。カッタルさと物足りなさがない交ぜになって、もういい加減にしてくれとラーメン鉢をひっくり返しそうになるときがあるんだ」
「あ、その感覚、わかるかも」菜々実が腕を組む。「濃い味付けになれた人は、薄味の食事なんて食べられたものじゃないって、よく言うからね」
菜々実が僕の隣りに並んで手すりに背中をあずける。腕と腕が、微かに触れ合った。お互いが意識してのことなのか、数秒間の沈黙が僕と菜々実の間を流れた。
「ねえ公彦」菜々実が客室のほうを見ながら尋ねる。「あたしたち、付き合ってるよね?」
「え? うん、そうだね」僕は鼻の頭をかいた。目を向けたところに、缶コーヒーを飲む立石さんが見えた。
「あたしと付き合ってても、物足りない?」菜々実が自分の足元に視線を落とした。「あたしって、公彦にとって物足りない女の子なのかな」
僕は菜々実に目を向けた。彼女の首筋でほつれ毛が遊んでいる。ダメだ、口が麻痺したように、動かない。
なぜ、すぐに答えない? はやく答えろよ公彦。僕は自分を責めた。答えは言うまでもないことなのに。心の中で「そんなことない」と百回繰り返しても、すぐに答えられなかったことに対して「ごめん」と二百回繰り返しても、言葉が音となって口から出てこないのはなぜなんだろう。
それでも僕は歯を噛みしめて菜々実に向き直った。でも、言葉を発するよりも、彼女の動きのほうが速かった。
「ストップ!」菜々実は両手を前に出して僕を止めた。「ストップ、ストップ。言わなくていい。今度、聞くから。今はいいよ」
そう言って、菜々実が向こうを向いた。僕は自分を殴りたくなった。
そのとき、花ちゃんがデッキに出てきた。ミニひまわりのプランターを持っている。
「この子たちに海と空を見せてあげようと思って」花ちゃんが僕と菜々実を交互に見る。「あ、お邪魔でしたか?」
「ううん、ぜんぜん」菜々実が花ちゃんに駆け寄った。「ひまわり、太陽が大好きだものね。喜ぶね」
大好きという言葉が、妙に強調されて聞こえたのは気のせいだったのだろうか。
でも、もうそんなことを考える場面は終わった。ページはめくられ、僕たちのドラマは次々と進んでいくのだろう。
僕はミニひまわりのうれしそうな表情を見るために、プランターの前にかがみ込んだ。
船の後方にある手すりにもたれ、すでに豆粒ほどに小さくなっている陸地に目を向ける。大きな海と比べると、陸地のなんと小さなことか。まるでパンケーキの真ん中にポツンと垂らしたチョコレートシロップ。僕は、あんな小さなところに住んでいるのか。あんな小さなところで偉そうなことを言っているのか。ぬるま湯程度のわがままをまき散らしながら。
船の上とはいえ、海のまっただ中を運ばれている今の僕に自由はない。この船が僕を海に放り投げて、「さあ、生意気盛りの高校生よ。わがまま好き放題を言えるものなら言ってみな」と冷笑すれば、お願いです助けてくださいと懇願するしかないだろう。それなりに生意気でわがままを言う高校生なんて、場所が変わればそんなものだ、プールに投げ込まれたアリのほうがよっぽど頼もしい存在だということが、ここに立っていれば理解できる。
もとはと言えば、僕のわがままから始まったプチ家出。それが、こんな展開になるなんて。
今僕は、どうして船に乗っているんだろうな。改めてそう考えたとき、急におかしさがこみ上げてきた。手すりに両腕を乗せ、その上にアゴを乗せてクツクツ笑っていたとき、菜々実が近づいてきた。
「なによ、気持ち悪いよ、公彦」菜々実が真横に立ち、僕の焦った顔をのぞき込む。「海を見て思い出に浸っているわけ? 女の一人旅的シチュエーションは、あんたには似合わないよ」
「ほっといてくれ」僕は赤面しているのをごまかすために、反対を向いた。熱い頬に潮風が優しい。「菜々実こそ、お菓子はもういいのか? 今のうちに食べておかないと、忙しくなるかもしれないよ」
「だいじょうぶ、あたしはどんな状況下に置かれても、食べるときは食べますから」菜々実が手すりにもたれたまま笑った。
数秒間の沈黙を破ったのは菜々実だ。
「ねえ公彦。静香さんに聞いたんだけど、このドライブのきっかけは、あんただってね」菜々実が首だけ僕のほうへ向ける。「どうして? そんなこと、ぜんぜん言っていなかったじゃない。急に思いついた?」
「いや、僕が企画したっていうか、計画したのは、プチ家出だよ。ドライブじゃない」
「家出? あんた家出をする気だったの?」驚いた菜々実が体ごとこっちを向く。「どうして?」
「家出じゃなくてプチ家出」僕は横目で菜々実をにらんだ。「プチをつけてくれ、プチを」
「わかったわかった。プチね、プチ家出ね」菜々実が面倒くさそうに手を振った。「で? そのプチ君をやろうと思ったわけは?」
僕は海を見つめた。波が白い腹を見せながら遠ざかっていく。菜々実がじっと僕の答えを待っているのを横顔に感じた。
「っておい、この間はやめてくれ。タメを作って期待させるほどのことなんて、なんにもないよ」僕はまた赤面する。「そんな、たいしたことじゃない。ただ、ちょっとさ、最近カッタルいことが多いから、気分転換にというか」
「へえ。あんた、気分転換で家出をするタイプだったっけ」菜々実が首をかしげる。「あ、ごめん。プチ家出だったね」
「そんなこと、改めて聞かないでくれよな。恥ずかしいだろ」僕は唇を尖らせた。「別に説明するほどのこともないんだよ。ほんとに、ちょっとした気分転換みたいなもので。それで、あの」
「高校生だもんね。気分なんて、あそこに浮かんでいる板切れのようなものでしょ」菜々実が波に揉まれながら漂っている木片を指差した。「あたしだってそんな気になること、しょっちゅうだし。みんなそうでしょ。ただ、やるかやらないかの問題でしょ。とはいっても、やる、やらないの間には、このくらいの隔たりがあるけどね」菜々実が両手を目一杯に広げた。Tシャツの袖から海風が侵入し、胸元をばたつかせた。
「いや、だからそんなたいしたことは」と僕はいいかけてやめた。この海の上には似つかわしくない言い訳だろうから。僕は少しだけ菜々実とベクトルの方向を近づけることにした。
「まあ、ネギのようなもんだよ」僕はくるりと海に背を向けて手すりにもたれた。目の下を人差し指でかく。
「ネギ? なにそれ」
「うちの母さんは味噌汁にネギを入れるのが大嫌いでさ。でも、逆に僕はネギが大好きときたもんだ。そこで好みが分かれる」
「意見が違うっていうの? なによ、そんなの、後で入れればいいだけの話じゃない。食べるときに、パッとネギだけ放り込めば」
「そういうことじゃなくてさ、なんていうか、物足りないんだと思う。人がこれがいいと思っているものが、僕には物足りない。母さんの完成品は、僕には物足りない。父さんの意見は、一応頭では理解してできる限り尊重するけど、しっくりこないことも多い。そんなことが多すぎるんだと思う。中学生の時に比べて、それは何倍もに膨れあがったように感じるんだ。まあ、自分の意見を言えばすむことなんだろうけど、それすらカッタルいことも多いし。だから、その」
「だから、プチ家出ってことなのね」菜々実が僕の言葉を引き継いだ。「それって、大人から見ればばかばかしくてたいしたことじゃないと思えるんだよね。でも、あたしたちにとってはそうじゃない」菜々実が微笑んだ。「あたしはわかるよ、その感覚。ま、ひとえにあんたが優しすぎるから余計に悩むのでしょうけど」
「そんなことはないけどさ」僕はまたそっぽを向いた。海風が方向を変えた。菜々実のシャンプーの香りが鼻をくすぐる。「SNS、趣味なんだけど。ツイッターとか」
「うん、知ってる」菜々実が歌うように言う。
「ああいうところって、言いたいことがなんでも言えて、意見を同じくする者同士で肩を組み、意見が異なる者とはガチに議論する。それをコクのあるラーメンとするなら、現実のふれあいは、家族にしても友人にしても、病院食のような薄味のラーメンなのかも知れない。カッタルさと物足りなさがない交ぜになって、もういい加減にしてくれとラーメン鉢をひっくり返しそうになるときがあるんだ」
「あ、その感覚、わかるかも」菜々実が腕を組む。「濃い味付けになれた人は、薄味の食事なんて食べられたものじゃないって、よく言うからね」
菜々実が僕の隣りに並んで手すりに背中をあずける。腕と腕が、微かに触れ合った。お互いが意識してのことなのか、数秒間の沈黙が僕と菜々実の間を流れた。
「ねえ公彦」菜々実が客室のほうを見ながら尋ねる。「あたしたち、付き合ってるよね?」
「え? うん、そうだね」僕は鼻の頭をかいた。目を向けたところに、缶コーヒーを飲む立石さんが見えた。
「あたしと付き合ってても、物足りない?」菜々実が自分の足元に視線を落とした。「あたしって、公彦にとって物足りない女の子なのかな」
僕は菜々実に目を向けた。彼女の首筋でほつれ毛が遊んでいる。ダメだ、口が麻痺したように、動かない。
なぜ、すぐに答えない? はやく答えろよ公彦。僕は自分を責めた。答えは言うまでもないことなのに。心の中で「そんなことない」と百回繰り返しても、すぐに答えられなかったことに対して「ごめん」と二百回繰り返しても、言葉が音となって口から出てこないのはなぜなんだろう。
それでも僕は歯を噛みしめて菜々実に向き直った。でも、言葉を発するよりも、彼女の動きのほうが速かった。
「ストップ!」菜々実は両手を前に出して僕を止めた。「ストップ、ストップ。言わなくていい。今度、聞くから。今はいいよ」
そう言って、菜々実が向こうを向いた。僕は自分を殴りたくなった。
そのとき、花ちゃんがデッキに出てきた。ミニひまわりのプランターを持っている。
「この子たちに海と空を見せてあげようと思って」花ちゃんが僕と菜々実を交互に見る。「あ、お邪魔でしたか?」
「ううん、ぜんぜん」菜々実が花ちゃんに駆け寄った。「ひまわり、太陽が大好きだものね。喜ぶね」
大好きという言葉が、妙に強調されて聞こえたのは気のせいだったのだろうか。
でも、もうそんなことを考える場面は終わった。ページはめくられ、僕たちのドラマは次々と進んでいくのだろう。
僕はミニひまわりのうれしそうな表情を見るために、プランターの前にかがみ込んだ。
0
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~
ハムえっぐ
ファンタジー
かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。
王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。
15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。
国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。
これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。


病弱な彼女は、外科医の先生に静かに愛されています 〜穏やかな執着に、逃げ場はない〜
来栖れいな
恋愛
――穏やかな微笑みの裏に、逃げられない愛があった。
望んでいたわけじゃない。
けれど、逃げられなかった。
生まれつき弱い心臓を抱える彼女に、政略結婚の話が持ち上がった。
親が決めた未来なんて、受け入れられるはずがない。
無表情な彼の穏やかさが、余計に腹立たしかった。
それでも――彼だけは違った。
優しさの奥に、私の知らない熱を隠していた。
形式だけのはずだった関係は、少しずつ形を変えていく。
これは束縛? それとも、本当の愛?
穏やかな外科医に包まれていく、静かで深い恋の物語。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

還暦の性 若い彼との恋愛模様
MisakiNonagase
恋愛
還暦を迎えた和子。保持する資格の更新講習で二十代後半の青年、健太に出会った。何気なくてLINE交換してメッセージをやりとりするうちに、胸が高鳴りはじめ、長年忘れていた恋心に花が咲く。
そんな還暦女性と二十代の青年の恋模様。
その後、結婚、そして永遠の別れまでを描いたストーリーです。
全7話
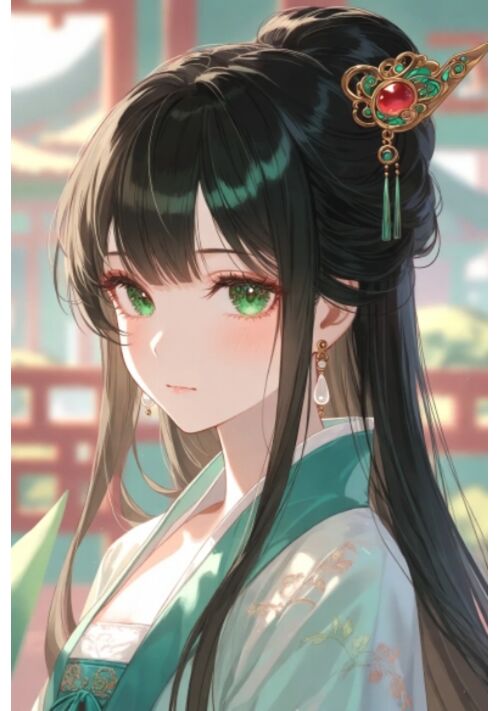
完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す―2人の皇子と失われた記憶【1/23本編完結】
雪城 冴
キャラ文芸
本編完結‼️【中華サスペンス】
皇帝が隠した禁忌の秘密。
それを“思い出してはいけない少女”がいた。
「その眼で見るな――」
特殊な眼を持つ少女・翠蓮は、忌み嫌われ、村を追われた。
居場所を失った彼女が頼れたのは、歌だけ。
宮廷歌姫を目指して辿り着いた都でも、待っていたのは差別と孤立。
そんな翠蓮に近づいたのは、
危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。
だが、その出会いをきっかけに皇位争い、皇后の執着、命を狙われる日々。
追い詰められる中で、翠蓮の忘れていた記憶が揺り動く。
かつて王家が封じた“力”とは?
翠蓮の正体とは?
声を隠して生き延びるか。
それとも、すべてを賭けて歌うのか。
運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――?
※架空の中華風ファンタジーです
※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています
※表紙絵はAI生成
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















