38 / 49
第四章 ノンストップ! キャシー号
⑤
しおりを挟む
立石さんを面接してくれる会社に近づいたとき、修太郎さんが疑い深そうな目を辺りに向けた。「今度は近くにパチンコ屋はないだろうな」
「だいじょうぶみたいね」姉貴も四方八方に目を走らせる。「隣はスーパーだから問題なしよ」
キャシー号をスーパーの駐車場に入れ、僕たちは一斉に外へ出た。大きく背筋を伸ばすと、生き返った気分になるほど気持ちがいい。
カナさんも同じように伸びをする。吹っ切れたのか、吹っ切ろうとしているのか、あるいは吹っ切れたふりをしているのかは僕にはわからないけれど、さっきまでの思い詰めた表情は、顔からすいぶん逃げ出したみたいだと思う。菜々実もそれに気づいたようで、僕と菜々実は顔を見合わせて微笑んだ。
ただ、ウエディングドレスでスーパーの駐車場にいるというのは、けっこう人目を引くらしく、行き交う人々が驚きの目で見ていた。何かの撮影と思った人もいて、ちょっと離れた場所に座り込んでこっちをじっと見ているのにはまいった。
立石さんが間違いなく約束の会社に入ったのを見届けたあと、僕はキャシー号に乗った。ここで立石さんの帰りを待つつもりだ。
庄三さんと昌枝さんは、立石さんを待つ間にスーパーに買い物に行った。花ちゃんはミニひまわりを車の外に出して太陽の光を与えていた。菜々実は、ちょっとチャッピーを探してみると言って、卓也君と一緒に歩道に出て左右をチェックしていた。昨日の敵は今日の友、でもないだろうけれど、なんとまああっさりと仲よくなったものだ。
というわけで、キャシー号の中は修太郎さんと姉貴、それにカナさんと僕の四人だけになった。カナさんはもう修太郎さんと打ち解けた様子で、広島のことをいろいろ話していた。姉貴は、彼女にしては珍しく聞き役に徹していた。二人の話にうなずくことも首を振ることもなく、ただじっと耳を傾けている感じだ。
修太郎さんとカナさんの声だけが往復する車内で、僕が缶コーヒーのプルタブを開けたとき、向こうから立石さんが歩いてくるのが見えた。どうやら面接が終わったらしい。彼に気づいたらしく、花ちゃんがミニひまわりを持って車内に入ってきた。菜々実と卓也君も急いで駆けてくる。
「で、どうだった?」姉貴が立石さんに尋ねる。
立石さんはゆっくりと座席に着いてから眉を上げた。「まあ、私なりにできるだけのことはやりました」
「なによそれ」姉貴がじれったそうな顔をする。「どうしたのよ。断られたの?」
「はっきり言ってしまえば、そういうことになります」立石さんが頭をかく。
「ええっ、なんでですか?」菜々実が汗ばんだ顔を団扇代わりの手の平であおぐ。「きちんと面接、できたんでしょ? 募集の詳細を見た限りじゃ、そんなに厳しい条件はないように見えたけどなあ」
「ちなみに、立石氏」修太郎さんが疑い深そうな目をする。「あんたのほうから提示した条件もあるんだろ? それ、なんだい?」
「はい、あります。ええと」立石さんがアゴに手を当てて考える。「独身寮は完備だから申し分なかったです。その他、給料は手取りで三十五万円、賞与は五ヶ月分、ただそれだけです。欲を言えばキリがないですから」
十分、欲を言っているじゃないか、と思ったのは僕だけじゃないだろう。みんなリアクションをすることすら忘れているように、その場の空気と一体化してる。
でも、さすがに姉貴は我慢ができなかったらしく、深呼吸を一つしてから立石さんに向き直った。
「あなたね、そんな贅沢な条件、実力を示してからのことでしょ? 努力して結果を出してから交渉すればいいじゃない。やる前からあれこれ言わないのよ」
自分を何だと思っているの、といわんばかりの姉貴。でも僕は、立石さんの社会生活不適格者ぶりよりも、姉貴のリアクションのほうに興味を引かれた。なんだかんだと口うるさく言っているようでも、きっちり立石さんの面倒を見ているような気がする。他人事だからといって手を抜かない。
そう言えば、と僕が幼稚園のときのことを思い出す。僕と姉は、母に買ってもらったばかりの紙芝居(当時、人気のあったキャラクターの紙芝居が売っていて、それを店先で見た僕が、なぜかものすごく欲しがったと記憶している)を持って家の近くにある公園に行った。姉と僕は、声も高らかに代わる代わる紙芝居屋さんを演じながら遊んでいた。いつの間にか幼稚園の友だちもやってきていて、親共々、僕たちの紙芝居を興味深そうにながめていた。
そのとき、夕立が僕たちを襲った。友だちはみんな観客の役割を放棄して逃げ去った。僕は顔を雨に打たれながらも、大きな声で紙芝居に書かれた文字をなぞった。
雨が強くなった。さすがに姉貴が僕の服をひっぱった。雨で紙芝居がダメになる、帰ろう、と僕の読み上げる声を上回る金属的な声で言った。僕はいやだ、もう少し続けたいと首を振った。姉貴は怒った。
公彦がよくても、あたしはよくないの。公彦の紙芝居はどうでもいいけど、あたしの紙芝居が濡れちゃうのはイヤよ。さあ、はやくしなさい。
僕は姉貴に引っ張られるままに、紙芝居を箱の中に入れながら、公園を走り出た。走りながらも僕は、紙芝居の文句を暗唱し続けていた。ちょうど好きなキャラクターの有名なセリフだったからだ。僕は、そこまではどうしても演じたかったのだろう。
家に向かって走っていた僕は、はっとして立ち止まった。箱の軽さに気がついたのだ。抱えていたものを見る。箱の中は空だった。雨がこれでもかと攻撃してくる中で振り返ると、箱からこぼれ落ちた紙芝居の一枚一枚が、僕たちが公園から逃げてきた証拠のように、道に並べられていた。裏返ったもの、表が上になったもの、急ごしらえの水たまりの中で泳いでいるものもあった。
大好きなキャラクターが、水たまりの底に沈んでいた。水に沈んでさえ、そのキャラクターは笑っていた。
それを見た僕は、声を上げて泣き出した。雷にも負けないくらいの声で泣いた。
先を走っていた姉貴が戻ってきた。状況を理解したらしく、自分たちの歩いてきた痕跡を消すかのように、一枚一枚拾い上げながら公園のほうへ戻っていった。
全部拾い終わった姉貴は、僕のところへ戻ってきて、僕のずぶ濡れの髪の毛をかき上げながら言った。
全部拾ったから泣かないの。ほら、はやく帰るよ。風邪引くよ。
さっきまでの姉貴の声とはうって変わって優しい声だった。僕は姉貴の集めてくれた紙芝居を抱えて、それでもまだしゃくり上げながら家を目指して走った。
家に帰ると、母が姉貴と僕の頭をタオルで拭きながら「そういうときは、雨が止むまで屋根があるところに避難していなさい。夕立はすぐに止むから。お母さんも様子を見に行こうと思っていたところよ」と言った。「紙芝居は乾かしておくわ。ちょっと使いにくいかもしれないけどね」
姉貴は「ええーっ、そうか避難かあ」と声を裏返した。思いつかなかったと悔しそうな顔をした。
心の余裕ができた僕は、姉貴の紙芝居に目を向けた。はっとする。僕の紙芝居を一生懸命に集めてきてくれた姉貴。腋の下に強く抱えていたのだろう、彼女の紙芝居は雨に打たれただけでなく紙製の箱が破れて変形していた。あの様子じゃ、中身も無事ではすまないだろう。
それを見た僕は、また泣き出した。自分の紙芝居が水に濡れたときよりも大きな声で泣いたと思う。さすがに母が呆れたような顔をしたのを覚えている。
僕が中学生になったとき、小遣いで姉貴に、彼女の好きなアイドルの写真集を買ってあげた。
なにこれ。なんでくれるの? 姉貴は不審そうな顔をしていたけれど、僕は別に、普段、世話になっているからとだけ言ってその場を去った。
「公ちゃん。さっきからあんた、なにニヤニヤしてんのよ」立石さんに説教をしていた姉貴が、僕の顔を不審そうな目で見る。昔の姉貴の目となんら変わらない。「気持ち悪いわねえ。菜々実ちゃん、気をつけたほうがいいわよ。思春期特有の症状かも。二人きりのとき、モンスターに豹変するかも」
「はい。気をつけます」菜々実が笑いながら僕の背中を叩いた。「モンスターには変身しないでよ。せめてハムスターくらいにしておいて」
誰がモンスターだ。ハムスターだ。っていうか、なんで菜々実に振る? 現実に戻った僕は、目をぐるりと回した。毒舌も、昔と変わらないな。やっぱり姉貴は姉貴だ。
僕は、はやく次の会社を探しなさいと立石さんを急かす姉貴の顔を見て、今度はこっそりと笑った。
「そういや、庄三さんたちはどうした?」修太郎さんがスーパーに目を向けた。「まだ戻ってこないぞ」
「あ、そういえばそうね。スーパーに行ったきり、戻ってこないわね」姉貴が僕の顔を見る。「公ちゃん、ちょっと見てきてくれる?」
はいはい、わかりましたと僕は腰を上げた。一緒に行こうかと言う菜々実を手で制してから、僕はスーパーに向かった。
庄三さんたちはすぐに見つかった。スーパーの入り口に設置された鏡のところにいたからだ。庄三さんと昌枝さんは、なにやら熱心に鏡を見ていた。いや、鏡に映っている自分の姿を見ていたというほうが正解か。
「どうしたんですか? みんな待っていますよ」僕は鏡に映った庄三さんに話かける。
「君はどう思うかね?」庄三さんが鏡の中の僕に問いかける。「じゃっかん右を向いたほうが、見栄えがすると思わんかね」
「え? 何がですか?」
「わしの横顔だよ。わしは、左より右のほうに自信があるんだが」
僕は鏡の中から姿を消した。「あの、みんな待っていますから行きましょう」
「ああ、すまんすまん」庄三さんが昌枝さんをうながす。「昌枝、そろそろ行くぞ。ときに、お前は決まったのか?」
昌枝さんが真剣な顔をして考え込んでいる。
「あの、決まったって、何がですか?」僕は嫌な予感に包まれながら、それでも一応、尋ねてみた。
「湯飲みを持った姿だよ。左斜めと右斜めとでは、どちらが絵になるか決めているんだ」
「左、ですね」昌枝さんがつぶやいた。そして、鏡から外れて庄三さんとともにスーパーを出た。
僕は鏡をじっとのぞいてため息をついた。が、まあ一応、顔を左右に動かして自分の横顔を確認してから、庄三さん夫妻の後を追った。
「だいじょうぶみたいね」姉貴も四方八方に目を走らせる。「隣はスーパーだから問題なしよ」
キャシー号をスーパーの駐車場に入れ、僕たちは一斉に外へ出た。大きく背筋を伸ばすと、生き返った気分になるほど気持ちがいい。
カナさんも同じように伸びをする。吹っ切れたのか、吹っ切ろうとしているのか、あるいは吹っ切れたふりをしているのかは僕にはわからないけれど、さっきまでの思い詰めた表情は、顔からすいぶん逃げ出したみたいだと思う。菜々実もそれに気づいたようで、僕と菜々実は顔を見合わせて微笑んだ。
ただ、ウエディングドレスでスーパーの駐車場にいるというのは、けっこう人目を引くらしく、行き交う人々が驚きの目で見ていた。何かの撮影と思った人もいて、ちょっと離れた場所に座り込んでこっちをじっと見ているのにはまいった。
立石さんが間違いなく約束の会社に入ったのを見届けたあと、僕はキャシー号に乗った。ここで立石さんの帰りを待つつもりだ。
庄三さんと昌枝さんは、立石さんを待つ間にスーパーに買い物に行った。花ちゃんはミニひまわりを車の外に出して太陽の光を与えていた。菜々実は、ちょっとチャッピーを探してみると言って、卓也君と一緒に歩道に出て左右をチェックしていた。昨日の敵は今日の友、でもないだろうけれど、なんとまああっさりと仲よくなったものだ。
というわけで、キャシー号の中は修太郎さんと姉貴、それにカナさんと僕の四人だけになった。カナさんはもう修太郎さんと打ち解けた様子で、広島のことをいろいろ話していた。姉貴は、彼女にしては珍しく聞き役に徹していた。二人の話にうなずくことも首を振ることもなく、ただじっと耳を傾けている感じだ。
修太郎さんとカナさんの声だけが往復する車内で、僕が缶コーヒーのプルタブを開けたとき、向こうから立石さんが歩いてくるのが見えた。どうやら面接が終わったらしい。彼に気づいたらしく、花ちゃんがミニひまわりを持って車内に入ってきた。菜々実と卓也君も急いで駆けてくる。
「で、どうだった?」姉貴が立石さんに尋ねる。
立石さんはゆっくりと座席に着いてから眉を上げた。「まあ、私なりにできるだけのことはやりました」
「なによそれ」姉貴がじれったそうな顔をする。「どうしたのよ。断られたの?」
「はっきり言ってしまえば、そういうことになります」立石さんが頭をかく。
「ええっ、なんでですか?」菜々実が汗ばんだ顔を団扇代わりの手の平であおぐ。「きちんと面接、できたんでしょ? 募集の詳細を見た限りじゃ、そんなに厳しい条件はないように見えたけどなあ」
「ちなみに、立石氏」修太郎さんが疑い深そうな目をする。「あんたのほうから提示した条件もあるんだろ? それ、なんだい?」
「はい、あります。ええと」立石さんがアゴに手を当てて考える。「独身寮は完備だから申し分なかったです。その他、給料は手取りで三十五万円、賞与は五ヶ月分、ただそれだけです。欲を言えばキリがないですから」
十分、欲を言っているじゃないか、と思ったのは僕だけじゃないだろう。みんなリアクションをすることすら忘れているように、その場の空気と一体化してる。
でも、さすがに姉貴は我慢ができなかったらしく、深呼吸を一つしてから立石さんに向き直った。
「あなたね、そんな贅沢な条件、実力を示してからのことでしょ? 努力して結果を出してから交渉すればいいじゃない。やる前からあれこれ言わないのよ」
自分を何だと思っているの、といわんばかりの姉貴。でも僕は、立石さんの社会生活不適格者ぶりよりも、姉貴のリアクションのほうに興味を引かれた。なんだかんだと口うるさく言っているようでも、きっちり立石さんの面倒を見ているような気がする。他人事だからといって手を抜かない。
そう言えば、と僕が幼稚園のときのことを思い出す。僕と姉は、母に買ってもらったばかりの紙芝居(当時、人気のあったキャラクターの紙芝居が売っていて、それを店先で見た僕が、なぜかものすごく欲しがったと記憶している)を持って家の近くにある公園に行った。姉と僕は、声も高らかに代わる代わる紙芝居屋さんを演じながら遊んでいた。いつの間にか幼稚園の友だちもやってきていて、親共々、僕たちの紙芝居を興味深そうにながめていた。
そのとき、夕立が僕たちを襲った。友だちはみんな観客の役割を放棄して逃げ去った。僕は顔を雨に打たれながらも、大きな声で紙芝居に書かれた文字をなぞった。
雨が強くなった。さすがに姉貴が僕の服をひっぱった。雨で紙芝居がダメになる、帰ろう、と僕の読み上げる声を上回る金属的な声で言った。僕はいやだ、もう少し続けたいと首を振った。姉貴は怒った。
公彦がよくても、あたしはよくないの。公彦の紙芝居はどうでもいいけど、あたしの紙芝居が濡れちゃうのはイヤよ。さあ、はやくしなさい。
僕は姉貴に引っ張られるままに、紙芝居を箱の中に入れながら、公園を走り出た。走りながらも僕は、紙芝居の文句を暗唱し続けていた。ちょうど好きなキャラクターの有名なセリフだったからだ。僕は、そこまではどうしても演じたかったのだろう。
家に向かって走っていた僕は、はっとして立ち止まった。箱の軽さに気がついたのだ。抱えていたものを見る。箱の中は空だった。雨がこれでもかと攻撃してくる中で振り返ると、箱からこぼれ落ちた紙芝居の一枚一枚が、僕たちが公園から逃げてきた証拠のように、道に並べられていた。裏返ったもの、表が上になったもの、急ごしらえの水たまりの中で泳いでいるものもあった。
大好きなキャラクターが、水たまりの底に沈んでいた。水に沈んでさえ、そのキャラクターは笑っていた。
それを見た僕は、声を上げて泣き出した。雷にも負けないくらいの声で泣いた。
先を走っていた姉貴が戻ってきた。状況を理解したらしく、自分たちの歩いてきた痕跡を消すかのように、一枚一枚拾い上げながら公園のほうへ戻っていった。
全部拾い終わった姉貴は、僕のところへ戻ってきて、僕のずぶ濡れの髪の毛をかき上げながら言った。
全部拾ったから泣かないの。ほら、はやく帰るよ。風邪引くよ。
さっきまでの姉貴の声とはうって変わって優しい声だった。僕は姉貴の集めてくれた紙芝居を抱えて、それでもまだしゃくり上げながら家を目指して走った。
家に帰ると、母が姉貴と僕の頭をタオルで拭きながら「そういうときは、雨が止むまで屋根があるところに避難していなさい。夕立はすぐに止むから。お母さんも様子を見に行こうと思っていたところよ」と言った。「紙芝居は乾かしておくわ。ちょっと使いにくいかもしれないけどね」
姉貴は「ええーっ、そうか避難かあ」と声を裏返した。思いつかなかったと悔しそうな顔をした。
心の余裕ができた僕は、姉貴の紙芝居に目を向けた。はっとする。僕の紙芝居を一生懸命に集めてきてくれた姉貴。腋の下に強く抱えていたのだろう、彼女の紙芝居は雨に打たれただけでなく紙製の箱が破れて変形していた。あの様子じゃ、中身も無事ではすまないだろう。
それを見た僕は、また泣き出した。自分の紙芝居が水に濡れたときよりも大きな声で泣いたと思う。さすがに母が呆れたような顔をしたのを覚えている。
僕が中学生になったとき、小遣いで姉貴に、彼女の好きなアイドルの写真集を買ってあげた。
なにこれ。なんでくれるの? 姉貴は不審そうな顔をしていたけれど、僕は別に、普段、世話になっているからとだけ言ってその場を去った。
「公ちゃん。さっきからあんた、なにニヤニヤしてんのよ」立石さんに説教をしていた姉貴が、僕の顔を不審そうな目で見る。昔の姉貴の目となんら変わらない。「気持ち悪いわねえ。菜々実ちゃん、気をつけたほうがいいわよ。思春期特有の症状かも。二人きりのとき、モンスターに豹変するかも」
「はい。気をつけます」菜々実が笑いながら僕の背中を叩いた。「モンスターには変身しないでよ。せめてハムスターくらいにしておいて」
誰がモンスターだ。ハムスターだ。っていうか、なんで菜々実に振る? 現実に戻った僕は、目をぐるりと回した。毒舌も、昔と変わらないな。やっぱり姉貴は姉貴だ。
僕は、はやく次の会社を探しなさいと立石さんを急かす姉貴の顔を見て、今度はこっそりと笑った。
「そういや、庄三さんたちはどうした?」修太郎さんがスーパーに目を向けた。「まだ戻ってこないぞ」
「あ、そういえばそうね。スーパーに行ったきり、戻ってこないわね」姉貴が僕の顔を見る。「公ちゃん、ちょっと見てきてくれる?」
はいはい、わかりましたと僕は腰を上げた。一緒に行こうかと言う菜々実を手で制してから、僕はスーパーに向かった。
庄三さんたちはすぐに見つかった。スーパーの入り口に設置された鏡のところにいたからだ。庄三さんと昌枝さんは、なにやら熱心に鏡を見ていた。いや、鏡に映っている自分の姿を見ていたというほうが正解か。
「どうしたんですか? みんな待っていますよ」僕は鏡に映った庄三さんに話かける。
「君はどう思うかね?」庄三さんが鏡の中の僕に問いかける。「じゃっかん右を向いたほうが、見栄えがすると思わんかね」
「え? 何がですか?」
「わしの横顔だよ。わしは、左より右のほうに自信があるんだが」
僕は鏡の中から姿を消した。「あの、みんな待っていますから行きましょう」
「ああ、すまんすまん」庄三さんが昌枝さんをうながす。「昌枝、そろそろ行くぞ。ときに、お前は決まったのか?」
昌枝さんが真剣な顔をして考え込んでいる。
「あの、決まったって、何がですか?」僕は嫌な予感に包まれながら、それでも一応、尋ねてみた。
「湯飲みを持った姿だよ。左斜めと右斜めとでは、どちらが絵になるか決めているんだ」
「左、ですね」昌枝さんがつぶやいた。そして、鏡から外れて庄三さんとともにスーパーを出た。
僕は鏡をじっとのぞいてため息をついた。が、まあ一応、顔を左右に動かして自分の横顔を確認してから、庄三さん夫妻の後を追った。
0
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~
ハムえっぐ
ファンタジー
かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。
王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。
15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。
国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。
これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。


病弱な彼女は、外科医の先生に静かに愛されています 〜穏やかな執着に、逃げ場はない〜
来栖れいな
恋愛
――穏やかな微笑みの裏に、逃げられない愛があった。
望んでいたわけじゃない。
けれど、逃げられなかった。
生まれつき弱い心臓を抱える彼女に、政略結婚の話が持ち上がった。
親が決めた未来なんて、受け入れられるはずがない。
無表情な彼の穏やかさが、余計に腹立たしかった。
それでも――彼だけは違った。
優しさの奥に、私の知らない熱を隠していた。
形式だけのはずだった関係は、少しずつ形を変えていく。
これは束縛? それとも、本当の愛?
穏やかな外科医に包まれていく、静かで深い恋の物語。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

還暦の性 若い彼との恋愛模様
MisakiNonagase
恋愛
還暦を迎えた和子。保持する資格の更新講習で二十代後半の青年、健太に出会った。何気なくてLINE交換してメッセージをやりとりするうちに、胸が高鳴りはじめ、長年忘れていた恋心に花が咲く。
そんな還暦女性と二十代の青年の恋模様。
その後、結婚、そして永遠の別れまでを描いたストーリーです。
全7話
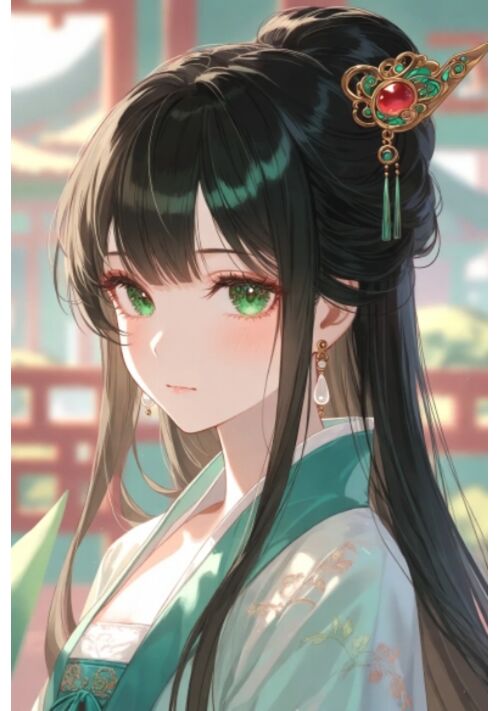
完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す―2人の皇子と失われた記憶【1/23本編完結】
雪城 冴
キャラ文芸
本編完結‼️【中華サスペンス】
皇帝が隠した禁忌の秘密。
それを“思い出してはいけない少女”がいた。
「その眼で見るな――」
特殊な眼を持つ少女・翠蓮は、忌み嫌われ、村を追われた。
居場所を失った彼女が頼れたのは、歌だけ。
宮廷歌姫を目指して辿り着いた都でも、待っていたのは差別と孤立。
そんな翠蓮に近づいたのは、
危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。
だが、その出会いをきっかけに皇位争い、皇后の執着、命を狙われる日々。
追い詰められる中で、翠蓮の忘れていた記憶が揺り動く。
かつて王家が封じた“力”とは?
翠蓮の正体とは?
声を隠して生き延びるか。
それとも、すべてを賭けて歌うのか。
運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――?
※架空の中華風ファンタジーです
※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています
※表紙絵はAI生成
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















