46 / 49
第五章 打ち上げ花火は幸せ花火
①
しおりを挟む
ドン。ドドン。ドドドドン。
重厚な音が空気を切り裂く。それは僕たちの体に直接届くものもあれば、大地を伝わり、足元から突き上げてくるものもある。
職人が趣向を凝らした花火の数々は、夜空を彩るアーティスティックなデザインはもとより、心を揺さぶるような重低音で僕たちの感情に働きかけてくる。
メガトン級の花火が開いたときの反応は人それぞれで、アルコール片手に威勢のいい声で応える者、神々しいまでの威圧感に固唾をのむ者、あるいはそれがまるで恋愛神の啓示であるがごとく、親密な間柄の者との関係をさらに密にしようとする行動に出る者など様々だ。
それは僕たちとて例外じゃない。夜空に咲いた大輪の花には誰だって魅せられる。そのあとのリアクションや感情表現は人によって異なっている。
でもまあ、この人たち──ちょいと夏の風物詩を楽しみに、という風流さから、まるでかけ離れた出で立ちの広誠連合──の場合は、少しばかり異例なわけで。
「広島バンザイ! 広誠連合、バンザイ!」場の雰囲気を壊すようなことを夜空の大輪に向かって叫びまくっていた彼らは、花ちゃんにたしなめられてしょんぼりしていた。
でも、異質なのは彼らくらいで、我がキャシー号の他のメンバーは、夏の夜を満喫していたと思う。
庄三さんと昌枝さんは、相変わらず手をつないで花火を観賞していたし、僕は、そう、僕は手をつないできた菜々実の手を握り返すという、自分でも信じられない行動に出た。まあ、これも花火のなせる技だと思うことにしよう。
それでもまだ、このタイミングでそんなことを冷静に考える自分ってどうなの、一生懸命に夜空を彩る花火に失礼だったかな、と思ったとき、目の前の修太郎さんと姉貴が花火に見守られるようにしてキスをした。
ぐ。なんて大胆な。僕と菜々実は顔を見合わせて、互いに赤面する。そのまま後ろを向くと、今度はそこで立石さんと花ちゃんが手をつないでいるのを発見した。
な。それはいったい。僕と菜々実は、逃げ場を失った視線の扱いに困っていると、広誠連合の人たちも、花ちゃんを見てアゴを外しそうになっていた。
花ちゃんが「何を見ているんですか?」と彼らに言うと、渋谷さんがマッハのスピードで顔をそむけた。
「すすす、すみません。と、とんだご無礼を」渋谷さんは世界戦争でも始まるかのような顔で、他の人たちに命令した。「野郎ども! 回れえ、右っ!」
そんなこんなで、念願の花火をそれぞれがそれぞれの思いで楽しむことができたのだった。
「すごかったわねえ」修太郎さんと腕を組んだままの姉貴がはしゃいだ声を出す。が、修太郎さんの顔を見て笑顔を少しだけ引っ込めた。「どうしたの、修太郎? やけに冷静ね。楽しくなかったの?」
「いや」修太郎さんが真面目な顔を昌枝さんに向けた。「なあ、昌枝さん。あんた花火をまともに見ていないじゃないか。さっきからキョロキョロしてばかりだ。どうしてだ?」
「私にはわかります」立石さんが物知り顔になる。すでに花ちゃんとつないでいた手は離している。「きっと花火の爆音にビビッたんだと思います。私も子供の頃、そうでしたから。花火の爆音がするたびに、ビビりまくって泣き叫んでいました。ましてや女性ならその恐怖はなおさらだと思います」
よく見ると、立石さんは鼻水を垂らして涙ぐんでいた。あのう、立石さん。子供の頃って言わなかったっけ?
「あなたと一緒にするのはどうかしらねえ」姉貴が呆れ顔になる。「それに、女性ならっていうのは偏見でしょ」
僕は、すみませんと頭をかく立石さんから昌枝さんに視線を移した。昌枝さんは修太郎さんの問いには答えず、まだ辺りを見回している。
どうしたんだろうと思っていると、菜々実が僕の手をぎゅっと握った。「なんか昌枝さん、人を探しているみたね」
なるほど、そうかもしれないと僕は思った。菜々実に言われるまで気がつかなかったけれど、たしかにそんなふうに見える。でも、もしそうだとして、いったい誰を。
昌枝さんの顔がぱっと輝いた。大きく手を振る。「大二郎!」
その声に気がついた男性が手を振りながら走ってくる。ジーンズにTシャツ姿の男性が微笑んだ。「母さん」
母さん? 大二郎? え、それってまさか……息子さん? 亡くなったのでは?
昌枝さんたちのやり取りについてはキャシー号の乗客全員が聞いていたので、みんな目を丸くして昌枝さんと大二郎と呼ばれた男性を見ていた。
中でも、飛び出さんばかりに目を丸くしていたのは、他でもない庄三さんだ。
「大二郎……なぜお前がここに」庄三さんがかすれた声を出した。僕が庄三さんと出会って以来、最も驚いた声だったと思う。
「父さん。久し振りだね」大二郎さんが庄三さんへ向き直った。「あ、俺はこれだから」そう言って、空を指さした。
「そうか、花火か」庄三さんがゆっくりとうなずいた。「そうだったな」
「元気そうだね、父さん。母さんも」大二郎さんが昌枝さんの腕に触れた。「二人とも元気そうでなによりだ」
「昌枝はいいが、わしはガタガタだよ」庄三さんがせき払いをする。「苦労ずくめで、とうとう心臓をやられた。検診で、医者に覚悟をしておけと言われたよ」
「そんなにひどいのか」大二郎さんが唇をかみしめる。「すまない父さん。俺のせいだ。申し訳ないと思ってるよ」
「あの、庄三さん」菜々実がタイミングを見計らって話に割り込んだ。「息子さん、亡くなったんじゃなかったんですか?」
「花火の夜にだけ登場する幽霊」ボソリとつぶやく立石さん。
「ちょっと、そういうの、やめてくれます?」菜々実が立石さんを睨みつける。「あたし、けっこう苦手なんで」
「あ、すみません」立石さんが体を丸めて謝った。が、向こうを向いてニンマリと微笑んだ。僕はまた立石さんの新たな一面を見たような気がした。
「いや、立石君の言う通りだ。息子は、大二郎は死んだも同然だよ。なにせ、親元から離れてこっち、一度も顔を見せんのだからな、親不孝者は死んでいるのと同じだ」
「すまないと思っている」大二郎さんがうつむいた。「けど、啖呵を切って家を出たからには、いっぱしの仕事ができるようになってから会いに行こうと決めていたんだ。やっとモノになってきたところだよ」大二郎さんが顔を上げた。空を指さす。「いい花火だったろ? 楽しんでくれたかい?」
「とってもよかったわ」庄三さんに代わって昌枝さんが答えた。「感激で、お茶が何杯でも飲めそうよ」
「そうか。それはよかった」大二郎さんがうれしそうな顔をする。「でも、お茶はほどほどにね。ところで、皆さんは?」
僕をはじめ他のみんなはとりあえず簡単に自己紹介した。大二郎さんが、父がお世話になりますと頭を下げる。
「あのう、大二郎さんって、花火職人なんですか?」僕が代表となって、みんなが最も疑問に思っているであろうことを尋ねた。
「そうです。最近になって、やっと一人前の仕事ができるようになったんだけどね」
それから大二郎さんは花火職人になったいきさつを簡単に説明してくれた。
子供のとき、親に連れて行ってもらった花火にいたく魅せられたこと。それ以来、花火を見るたびに心が躍り、挙げ句の果てには、あんなふうに人々を感動させる花火を自分で作ってみたいと思ったこと。学校を卒業後、就職してからは花火から遠ざかり、ビジネスマンとして活躍してはいたものの、久し振りに彼女と行った花火大会で再び火が点いてしまったことなど……。
「じゃあ、久し振りの花火が、大二郎さんの心に花火への情熱を引き戻したんですね」菜々実が感動的な目になっている。「それで、花火を作ってみようと」
「もちろん、それもあるけど」大二郎さんが照れくさそうに頭をかく。「彼女を自分の作った花火で、もっともっと喜ばせたいと思ったんだ。いわばダブルパンチかな」
「じゃあ、そのとき勤めていた会社をやめて、花火職人に?」僕が尋ねる。
「ああ。ある日、親父に、俺は花火職人になる、と宣言したんだよ。もちろん、親父がそんなことを認めるはずがない。安定した会社勤め、何不自由ない暮らしを突然ひっくり返すようなことを言ったんだからね。無理もないよ。当然、親父とはケンカになり、挙げ句の果てに家を飛び出してしまった」
「そんなこと、急に言われた者の身にもなってみろ」庄三さんがそっぽを向いたままつぶやいた。「たまらんわい」
「すまなかったな、親父」大二郎さんがため息をつく。「でも、やっと好きな道でがんばれる自信がついたよ。そのきっかけをくれたのは親父だ。親父と見たあのときの花火のおかげだよ。感謝している」
「まったく、この歳になっても気苦労が絶えんわい」そっぽを向いていた庄三さんが、わずかに大二郎さんのほうへ向き直った。「だが、一人前にはなったようだな」
「おかげさまで、なんとかね」大二郎さんが柔らかい微笑みを見せた。大勢いる花火の見物客を見回す。「ほら、みんないい顔しているだろ。俺の花火が、あの笑顔を引き出すための一助となったのなら、それで大満足だよ。お客さんには喜んでもらえるし、俺はお客さんから喜びというエネルギーをもらえるから、またがんばれるんだ。次はもっといい花火を作ろうってね」
「そうか」庄三さんが回りを見回した。軽くうなずいたあと、もう一度、そうかと言った。
「あの、さっき大二郎さんが言ってた彼女って」菜々実が期待を込めた目で尋ねる。「今は、その」
「ああ。やっと俺の仕事も落ち着いてきたからね」大二郎さんが頭をかく。「この秋に一緒になろうかと思っているんだ」
「そんなこと、お前」庄三さんが驚いた顔をする。
「親父とお袋には、これから報告しようと思ってたんだ。今度、彼女を連れて戻るよ」大二郎さんが遠方の高台のほうへ目を向けた。「彼女は向こうの一等地で花火を見物してもらったんだ。俺、彼女に今まで数え切れないくらいの苦労をかけてきたけど、どんなことがあっても笑顔を絶やさないでいてくれた最高の女性だよ。その笑顔に俺はずいぶん支えられたんだ。だから、今度は俺が彼女を支える番だ」
菜々実が僕の腕に自分の腕をからめてくる。肩に触れた彼女の頬が温かい。
庄三さんが唇を噛みしめてわずかにうなずいた。昌枝さんはハンカチを目に当てたままお茶を飲んでいる。
「大二郎、こんなところで油を売っていていいのか?」はたと気づいたふうに庄三さんが言う。「片付けとかあるんじゃないのか? そもそも、今、お前がここにいるということは、打上には参加しなかったのか?」
「まあ。正確に言えば、参加しなかったかな」大二郎さんが言う。「直接にはね」
「直接には? それはどういう意味だ?」
「花火職人にもいろいろあってね。花火の打上には、打ち上げ屋という専門があるんだ。俺も最近までそうだったんだけど」
「最近までということは、今は違うってことですか」立石さんがボソリとつぶやく。「今は無職ということで。私と同じく」
「立石さん、あなたは黙って就職情報誌を見ていなさい」姉貴が噛みつく。
ちょっと姉貴。この場で就職情報誌ってのはないでしょ。っていうか、他人にヘンな目で見られるし。
「俺は花火プロデューサーを目指しているんだよ」大二郎さんが微笑む。「花火の打ち上げの総合的な企画や演出を手がける仕事なんだ」
「なるほど、花火職人にもそういう仕事があるんですね」姉貴が感心する。「なんか、すごそう」
「もっともっと学んで、高いレベルで創造できるプロデューサーになりたいと思っている」大二郎さんの口調が熱を帯びた。「これはまだ先の夢なんだけど、いつかは世界中の人々を楽しませたいと思っているんだ。俺の企画、演出した花火でね」
「へえ。すごおい。なんか聞いてるだけでワクワクしちゃうな」菜々実が胸の前で両手を合わせた。
「世界中の人々を楽しませたい、か」庄三さんが深呼吸をする。笑顔を大二郎さんに向けた。今日、大二郎さんに対しての初めての笑顔だ。「なるほど、いい言葉だ」
「親父にそう言ってもらえて、うれしいよ」大二郎さんが唇を固く結んだ。「そうだ、さっきの十号玉、見てくれたかい? 俺の作品だったんだ」
「もちろんだ。打ち上げられた花火は、残らず見ていたよ。いい仕事しているな。安心したよ」
「俺が親父から一番聞きたかった言葉だ」大二郎さんが拳を握りしめた。「ありがとう、親父」
その後、昌枝さんが大二郎さんと話している隙に、庄三さんが修太郎さんにこっそりと尋ねていたのを、僕は聞いていた。「十号玉というのは、どれのことだ?」
僕と菜々実は笑いをこらえるのに苦労した。
「庄三さん、あんた、この花火大会に大二郎さんがいるってことを知ってたのかい?」修太郎さんが尋ねた。
「あ? いや、そんなことは知るわけがない」庄三さんが首を振る。「大二郎がどこで働いているのかなんて、聞かされていなかったからな」
「じゃあ、なぜこの松山の花火大会に来たかったんだ? これは来る前にも尋ねたけど、あんたは心臓がいかれていて、明日をも知れない命だからと答えたよな? だから、今日行われる松山の花火大会を見たいんだと。でもあんた、すこぶる元気そうだぜ」修太郎さんが庄三さんの体を指さす。「カーチェイスも満喫していたし、スーパーでは試食も楽しんでいた。昌枝さんにお茶をぶっかけられて血圧が上がっても平気だ。どうみても、今日明日の命とは思えない。花火見物が今日でないといけない理由、弱すぎないか? それなのに、なぜ松山なのか、俺にはわかんないぞ。第一、なぜ花火なんだ?」
「なぜって、わしはただ死ぬ前に花火が見たいから……花火は好きだし……」庄三さんが首をかしげる。「はて。そう言えばそうだな。なぜ今日、花火なんだろう」
「きっと松山の就職情報誌で、花火のバイトを見つけたんでしょう」立石さんが庄三さんの背後からそっと顔を出す。「だから、そのバイトをやろうと思って」
姉貴が無言で立石さんの持っている情報誌を指さした。立石さんは速やかに庄三さんの背後に隠れた。
「ちょっと待てよ」庄三さんが思い出したような顔をする。「昌枝、お前、数日前から変な歌を歌っていなかったか? たしかあれは、『はあなび花火、松山の花火はス、テ、キィ』ってやつだ。あれ、なんという歌だ?」
「名前はありません。私の創作歌ですから」昌枝さんが湯飲みを口に運ぶ。「それに、今のは間違っています。正確には、『はあなび花火、あ~あ松山の花火は超ス、テ、キィ』です」
……その違いに、何の意味が? 僕は全身から力が抜けそうになる。
ふと立石さんを見ると、真剣な顔で昌枝さんの歌を暗唱している。それ、覚えて何の得があるんですか。
「ま、まあ多少の違いはあるかもしれないが──おい、まさかお前」庄三さんがはっとする。「わしを誘導していたのか? わしに松山の花火を見たいと言わせるように」
「さあ、何のことかしら」昌枝さんがまたお茶を飲む。それから、さっきの歌を口ずさんだ。
「一種のサブリミナル効果だな」修太郎さんが苦笑する。「いわゆる刷り込みってやつだ。昌枝さんは、庄三さんの潜在意識に刺激を与えてメッセージを刷り込んでいたわけだ。庄三さん自ら松山の花火大会に行きたいと言わせるために」
なんとかごまかそうとする昌枝さんから強引に聞き出したところによると、こういうことらしい。
昌枝さんは実は大二郎さんと、ときどき連絡を取り合っていたらしい。とは言っても、別に親子だから当たり前のことで珍しくもなんともないのだけれど。
だから、大二郎さんの近況についてはよく知っていたし、現在どこでどういう仕事に携わっているかについても詳しく知っていた。大二郎さんが報告していたからだ。せめて母親にだけでも心配をかけまいとする大二郎さんの配慮だった。
同時に、昌枝さんは大二郎さんの仕事に理解を持ち、常に励ましてきた。大二郎さんが家を飛び出して以来、遠方からずっと見守ってきたのだ。
ただし、庄三さんには内緒にしていたらしい。連絡は、庄三さんが外出しているときに行っていたとのこと。
「なぜ言わなかった」庄三さんが非難するような目を昌枝さんに向ける。「わしに内緒にするとはどういうことだ?」
「大二郎の名前を口にするだけでも、あなたは機嫌が悪くなるでしょ」昌枝さんがため息をつく。「だから、言わなかったんです」
「知らないのはわしだけ、ということか」庄三さんが自嘲めいた笑いを浮かべる。「つまり、わしとお前の間で内緒事を作っていたということだな。わしにとっては、決して気持ちのいいものではないぞ」
「あなたに言えば、また血圧が上がるでしょ」昌枝さんが真剣な顔で庄三さんを見る。「一度、倒れたのを忘れたの?」
「忘れてはおらん。だが、倒れることよりも、わしはお前に内緒事を作られたほうが」
「そうはいきません!」昌枝さんが声を荒げた。珍しいことだったので、僕はびっくりする。
昌枝さんは深呼吸を二度ほど繰り返すと話を続けた。
「バカなことを言わないで。あなたに倒れてもらうわけにはいきません」昌枝さんが両手で包み込んでいる湯飲みが震えている。「私はあなたと、ここまでずっと一緒に歩いてきました。雨の日も風の日も、嵐の日もありましたけど、二人で乗り越えたことで悪天候を楽しさに変えてきましたよね。でも、まだ終わりではないでしょう? まだまだ道は続くのでしょう? これからも二人で歩いて行くのでしょう?」
庄三さんがはっとした。頭を殴られたような顔をして昌枝さんを見る。「昌枝、お前は……」
「もう終わりなんて言わせませんよ。私たちには、まだまだ先があるんです。進むべき道が」昌枝さんがハンカチで目を押さえた。「わたしは、あなたと一緒にもっと歩きたいんです。もっともっと、一緒に楽しみたいんです。たしかに内緒にしていたことは悪かったと思います。でも、その何倍もの楽しみでお返しするつもりでした。今風な言葉で言うのなら、サプライズってことでしょうか。一人前になった大二郎に会いに行く、あなたに大二郎の成長を見せて差し上げる。そう思っていたのです」
言葉を切った昌枝さんがハンカチを目に当てたままその場にうずくまった。それでもなんとか言葉を押し出した。
「私は……私には、あなたと大二郎の二人を見守っていく義務があります。いいえ、義務ではなく権利です。しっかりと見守らせていただきます。だから、私は」昌枝さんがうずくまったまま、庄三さんを見上げた。「私はあなたを倒れさせません。これからも一緒に歩いていくために」
庄三さんが拳を握りしめた。真っ白になった拳が震えている。唇を噛みしめたまま、空を見上げた。賑やかな花火が去り、静けさを取り戻した星空を。
「母親というのは偉大だな」庄三さんが空を見上げたまま微笑んだ。「だてに腹を痛めてはおらんわい。男が勝てるわけがない」
庄三さんがうずくまったままの昌枝さんの手をとった。昌枝さんが立ち上がる。
「昌枝。お前の手は、昔のままだな」庄三さんが昌枝さんの手を見つめる。「優しい手のままだ。全然変わっとらんわい。それに比べ、わしの手はいつの間にかささくれ立っていたようだ。少し手入れが必要だな」
庄三さんが大二郎さんへ向き直った。「大二郎、今年はいいミカンができたんだ。ごちそうしてやるから帰ってこい」
「ああ。近々帰るよ。彼女も連れてね」大二郎さんが微笑む。「庭のミカン、ぜんぶ食うかもしれないから覚悟しておいたほうがいいよ」
「お父さんね、常日頃、口には出さないけど、実はとっても寂しがっているのよ」昌枝さんがクスリと笑った。「昔、あなたと一緒に植えたミカンの木を見て過ごすことが多いもの。そうですよね、お父さん?」
「バカを言え」庄三さんがくるりと背を向けた。そこにいたニヤケた顔の立石さんと見つめ合う形になったので、九十度、方向を変える。「まあ……少しくらいは寂しいかもしれんが、少しだけだぞ。いいか、そこのところを間違えるな」
大二郎さんが庄三さんの両肩に手を置いた。「細くなったなあ、父さん。昔はもっと分厚かったけど」
「お前が心配をかけるからだ」庄三さんがうつむいた。目からしずくが落ちる。
花ちゃんが、よろしければどうぞ、とハンカチを差し出した。
「お父さんも、涙もろくなりましたよね」湯飲みのお茶がなくなったのか、昌枝さんがペットボトルのお茶のフタを開けた。「お父さんね、最近、映画やドラマで親子愛の場面を観て号泣しているんですよ。私は知っていますよ」
泣き笑いのような顔をして、昌枝さんがペットボトルを口に運んだ。喉が上下する。
「ちょっと昌枝さん、飲み過ぎですよ!」姉貴が注意する。
「そういえば、父さん。母さんに聞いたけど、検査入院してたんだって?」大二郎さんが思い出したように尋ねる。「どうだった? 心臓、だいじょうぶかい?」
「え?」庄三さんがポカンとした表情になる。「心臓? ああ、そうだ。その心臓だよ。まあ、今のところ、たいしたことはないそうだ。だが、安心はできん」
庄三さんがお腹を押さえた。ゆっくりとなでる。
「お父さん、心臓はもう少し上よ。そこは胃です」昌枝さんが眉を寄せた。
「庄三さん、あんた、本当に心臓が問題で検査入院してたのかい?」修太郎さんが疑わしげな顔をする。
「まあ、な。いや、正確に言えば、心臓というか、その」庄三さんが、みんなの目を避けるようにそっぽを向いた。「もう少し下のほうかもしれん」
「は? なんですかそれ。もう少し下って」昌枝さんが疑わしげな顔をする。「はっきり言ってください。みんな心配しているんですから」
「いや実は、痔の治療で入院していたんだ」庄三さんが頭に手を置いた。「痔では格好がつかんからな。それで心臓ってことに」
「なんてことを。では、私もだましていたんですね」昌枝さんが怒りを露わにする。「さっき、人のことをさんざん非難したくせに」
「い、いや、すまん」庄三さんがうろたえた。「花火を見に行くのに、どうせなら心臓が危ないということにすれば、みんなが本気になって連れて行ってくれると思ったから、それで」庄三さんが全員の顔を見回して頭を下げた。「申し訳ない、許してくれ」
はあ。僕は体から力が抜けた。他のみんなも、マラソンを完走した後のような疲労感を露わにしている。
「ま、でも、よかったじゃないか。大事がなくて」修太郎さんが庄三さんの肩を叩いた。「あんたのおかげで素晴らしい花火が見えたわけだし。結果オーライってことで済ませようぜ」
「まあ、それはそうね」姉貴が同意する。「人生、楽しまなきゃね。健康が一番の財産だわ」
「まったくもう。あなたはすぐ口から出任せをいうんだから」昌枝さんが苦笑する。「私は気が気じゃなかったんですよ」
「すまんすまん。だが、心臓は無事でも、子供の頃から小心者だったのは確かだ」庄三さんが立石さんの顔を見てニヤリとする。「立石君。実は、わしも子供の頃、花火の爆音を聞いてビビったクチだよ。泣きながら小便を漏らしたもんだ」
「あ、そうでしたか。同類ですね」立石さんがうれしそうな顔をする。
「実は、さっきも三滴ほど漏らしてしまったかもしれん」と庄三さんが頭をかく。
立石さんがニンマリとして手を差し出した。その手を庄三さんが固く握った。
そのニンマリはなんですか、そのニンマリは。
というか、マジに聞いているのは僕ぐらいだし。
あの、みなさん。勝手に向こうへ行かないでくれる?
重厚な音が空気を切り裂く。それは僕たちの体に直接届くものもあれば、大地を伝わり、足元から突き上げてくるものもある。
職人が趣向を凝らした花火の数々は、夜空を彩るアーティスティックなデザインはもとより、心を揺さぶるような重低音で僕たちの感情に働きかけてくる。
メガトン級の花火が開いたときの反応は人それぞれで、アルコール片手に威勢のいい声で応える者、神々しいまでの威圧感に固唾をのむ者、あるいはそれがまるで恋愛神の啓示であるがごとく、親密な間柄の者との関係をさらに密にしようとする行動に出る者など様々だ。
それは僕たちとて例外じゃない。夜空に咲いた大輪の花には誰だって魅せられる。そのあとのリアクションや感情表現は人によって異なっている。
でもまあ、この人たち──ちょいと夏の風物詩を楽しみに、という風流さから、まるでかけ離れた出で立ちの広誠連合──の場合は、少しばかり異例なわけで。
「広島バンザイ! 広誠連合、バンザイ!」場の雰囲気を壊すようなことを夜空の大輪に向かって叫びまくっていた彼らは、花ちゃんにたしなめられてしょんぼりしていた。
でも、異質なのは彼らくらいで、我がキャシー号の他のメンバーは、夏の夜を満喫していたと思う。
庄三さんと昌枝さんは、相変わらず手をつないで花火を観賞していたし、僕は、そう、僕は手をつないできた菜々実の手を握り返すという、自分でも信じられない行動に出た。まあ、これも花火のなせる技だと思うことにしよう。
それでもまだ、このタイミングでそんなことを冷静に考える自分ってどうなの、一生懸命に夜空を彩る花火に失礼だったかな、と思ったとき、目の前の修太郎さんと姉貴が花火に見守られるようにしてキスをした。
ぐ。なんて大胆な。僕と菜々実は顔を見合わせて、互いに赤面する。そのまま後ろを向くと、今度はそこで立石さんと花ちゃんが手をつないでいるのを発見した。
な。それはいったい。僕と菜々実は、逃げ場を失った視線の扱いに困っていると、広誠連合の人たちも、花ちゃんを見てアゴを外しそうになっていた。
花ちゃんが「何を見ているんですか?」と彼らに言うと、渋谷さんがマッハのスピードで顔をそむけた。
「すすす、すみません。と、とんだご無礼を」渋谷さんは世界戦争でも始まるかのような顔で、他の人たちに命令した。「野郎ども! 回れえ、右っ!」
そんなこんなで、念願の花火をそれぞれがそれぞれの思いで楽しむことができたのだった。
「すごかったわねえ」修太郎さんと腕を組んだままの姉貴がはしゃいだ声を出す。が、修太郎さんの顔を見て笑顔を少しだけ引っ込めた。「どうしたの、修太郎? やけに冷静ね。楽しくなかったの?」
「いや」修太郎さんが真面目な顔を昌枝さんに向けた。「なあ、昌枝さん。あんた花火をまともに見ていないじゃないか。さっきからキョロキョロしてばかりだ。どうしてだ?」
「私にはわかります」立石さんが物知り顔になる。すでに花ちゃんとつないでいた手は離している。「きっと花火の爆音にビビッたんだと思います。私も子供の頃、そうでしたから。花火の爆音がするたびに、ビビりまくって泣き叫んでいました。ましてや女性ならその恐怖はなおさらだと思います」
よく見ると、立石さんは鼻水を垂らして涙ぐんでいた。あのう、立石さん。子供の頃って言わなかったっけ?
「あなたと一緒にするのはどうかしらねえ」姉貴が呆れ顔になる。「それに、女性ならっていうのは偏見でしょ」
僕は、すみませんと頭をかく立石さんから昌枝さんに視線を移した。昌枝さんは修太郎さんの問いには答えず、まだ辺りを見回している。
どうしたんだろうと思っていると、菜々実が僕の手をぎゅっと握った。「なんか昌枝さん、人を探しているみたね」
なるほど、そうかもしれないと僕は思った。菜々実に言われるまで気がつかなかったけれど、たしかにそんなふうに見える。でも、もしそうだとして、いったい誰を。
昌枝さんの顔がぱっと輝いた。大きく手を振る。「大二郎!」
その声に気がついた男性が手を振りながら走ってくる。ジーンズにTシャツ姿の男性が微笑んだ。「母さん」
母さん? 大二郎? え、それってまさか……息子さん? 亡くなったのでは?
昌枝さんたちのやり取りについてはキャシー号の乗客全員が聞いていたので、みんな目を丸くして昌枝さんと大二郎と呼ばれた男性を見ていた。
中でも、飛び出さんばかりに目を丸くしていたのは、他でもない庄三さんだ。
「大二郎……なぜお前がここに」庄三さんがかすれた声を出した。僕が庄三さんと出会って以来、最も驚いた声だったと思う。
「父さん。久し振りだね」大二郎さんが庄三さんへ向き直った。「あ、俺はこれだから」そう言って、空を指さした。
「そうか、花火か」庄三さんがゆっくりとうなずいた。「そうだったな」
「元気そうだね、父さん。母さんも」大二郎さんが昌枝さんの腕に触れた。「二人とも元気そうでなによりだ」
「昌枝はいいが、わしはガタガタだよ」庄三さんがせき払いをする。「苦労ずくめで、とうとう心臓をやられた。検診で、医者に覚悟をしておけと言われたよ」
「そんなにひどいのか」大二郎さんが唇をかみしめる。「すまない父さん。俺のせいだ。申し訳ないと思ってるよ」
「あの、庄三さん」菜々実がタイミングを見計らって話に割り込んだ。「息子さん、亡くなったんじゃなかったんですか?」
「花火の夜にだけ登場する幽霊」ボソリとつぶやく立石さん。
「ちょっと、そういうの、やめてくれます?」菜々実が立石さんを睨みつける。「あたし、けっこう苦手なんで」
「あ、すみません」立石さんが体を丸めて謝った。が、向こうを向いてニンマリと微笑んだ。僕はまた立石さんの新たな一面を見たような気がした。
「いや、立石君の言う通りだ。息子は、大二郎は死んだも同然だよ。なにせ、親元から離れてこっち、一度も顔を見せんのだからな、親不孝者は死んでいるのと同じだ」
「すまないと思っている」大二郎さんがうつむいた。「けど、啖呵を切って家を出たからには、いっぱしの仕事ができるようになってから会いに行こうと決めていたんだ。やっとモノになってきたところだよ」大二郎さんが顔を上げた。空を指さす。「いい花火だったろ? 楽しんでくれたかい?」
「とってもよかったわ」庄三さんに代わって昌枝さんが答えた。「感激で、お茶が何杯でも飲めそうよ」
「そうか。それはよかった」大二郎さんがうれしそうな顔をする。「でも、お茶はほどほどにね。ところで、皆さんは?」
僕をはじめ他のみんなはとりあえず簡単に自己紹介した。大二郎さんが、父がお世話になりますと頭を下げる。
「あのう、大二郎さんって、花火職人なんですか?」僕が代表となって、みんなが最も疑問に思っているであろうことを尋ねた。
「そうです。最近になって、やっと一人前の仕事ができるようになったんだけどね」
それから大二郎さんは花火職人になったいきさつを簡単に説明してくれた。
子供のとき、親に連れて行ってもらった花火にいたく魅せられたこと。それ以来、花火を見るたびに心が躍り、挙げ句の果てには、あんなふうに人々を感動させる花火を自分で作ってみたいと思ったこと。学校を卒業後、就職してからは花火から遠ざかり、ビジネスマンとして活躍してはいたものの、久し振りに彼女と行った花火大会で再び火が点いてしまったことなど……。
「じゃあ、久し振りの花火が、大二郎さんの心に花火への情熱を引き戻したんですね」菜々実が感動的な目になっている。「それで、花火を作ってみようと」
「もちろん、それもあるけど」大二郎さんが照れくさそうに頭をかく。「彼女を自分の作った花火で、もっともっと喜ばせたいと思ったんだ。いわばダブルパンチかな」
「じゃあ、そのとき勤めていた会社をやめて、花火職人に?」僕が尋ねる。
「ああ。ある日、親父に、俺は花火職人になる、と宣言したんだよ。もちろん、親父がそんなことを認めるはずがない。安定した会社勤め、何不自由ない暮らしを突然ひっくり返すようなことを言ったんだからね。無理もないよ。当然、親父とはケンカになり、挙げ句の果てに家を飛び出してしまった」
「そんなこと、急に言われた者の身にもなってみろ」庄三さんがそっぽを向いたままつぶやいた。「たまらんわい」
「すまなかったな、親父」大二郎さんがため息をつく。「でも、やっと好きな道でがんばれる自信がついたよ。そのきっかけをくれたのは親父だ。親父と見たあのときの花火のおかげだよ。感謝している」
「まったく、この歳になっても気苦労が絶えんわい」そっぽを向いていた庄三さんが、わずかに大二郎さんのほうへ向き直った。「だが、一人前にはなったようだな」
「おかげさまで、なんとかね」大二郎さんが柔らかい微笑みを見せた。大勢いる花火の見物客を見回す。「ほら、みんないい顔しているだろ。俺の花火が、あの笑顔を引き出すための一助となったのなら、それで大満足だよ。お客さんには喜んでもらえるし、俺はお客さんから喜びというエネルギーをもらえるから、またがんばれるんだ。次はもっといい花火を作ろうってね」
「そうか」庄三さんが回りを見回した。軽くうなずいたあと、もう一度、そうかと言った。
「あの、さっき大二郎さんが言ってた彼女って」菜々実が期待を込めた目で尋ねる。「今は、その」
「ああ。やっと俺の仕事も落ち着いてきたからね」大二郎さんが頭をかく。「この秋に一緒になろうかと思っているんだ」
「そんなこと、お前」庄三さんが驚いた顔をする。
「親父とお袋には、これから報告しようと思ってたんだ。今度、彼女を連れて戻るよ」大二郎さんが遠方の高台のほうへ目を向けた。「彼女は向こうの一等地で花火を見物してもらったんだ。俺、彼女に今まで数え切れないくらいの苦労をかけてきたけど、どんなことがあっても笑顔を絶やさないでいてくれた最高の女性だよ。その笑顔に俺はずいぶん支えられたんだ。だから、今度は俺が彼女を支える番だ」
菜々実が僕の腕に自分の腕をからめてくる。肩に触れた彼女の頬が温かい。
庄三さんが唇を噛みしめてわずかにうなずいた。昌枝さんはハンカチを目に当てたままお茶を飲んでいる。
「大二郎、こんなところで油を売っていていいのか?」はたと気づいたふうに庄三さんが言う。「片付けとかあるんじゃないのか? そもそも、今、お前がここにいるということは、打上には参加しなかったのか?」
「まあ。正確に言えば、参加しなかったかな」大二郎さんが言う。「直接にはね」
「直接には? それはどういう意味だ?」
「花火職人にもいろいろあってね。花火の打上には、打ち上げ屋という専門があるんだ。俺も最近までそうだったんだけど」
「最近までということは、今は違うってことですか」立石さんがボソリとつぶやく。「今は無職ということで。私と同じく」
「立石さん、あなたは黙って就職情報誌を見ていなさい」姉貴が噛みつく。
ちょっと姉貴。この場で就職情報誌ってのはないでしょ。っていうか、他人にヘンな目で見られるし。
「俺は花火プロデューサーを目指しているんだよ」大二郎さんが微笑む。「花火の打ち上げの総合的な企画や演出を手がける仕事なんだ」
「なるほど、花火職人にもそういう仕事があるんですね」姉貴が感心する。「なんか、すごそう」
「もっともっと学んで、高いレベルで創造できるプロデューサーになりたいと思っている」大二郎さんの口調が熱を帯びた。「これはまだ先の夢なんだけど、いつかは世界中の人々を楽しませたいと思っているんだ。俺の企画、演出した花火でね」
「へえ。すごおい。なんか聞いてるだけでワクワクしちゃうな」菜々実が胸の前で両手を合わせた。
「世界中の人々を楽しませたい、か」庄三さんが深呼吸をする。笑顔を大二郎さんに向けた。今日、大二郎さんに対しての初めての笑顔だ。「なるほど、いい言葉だ」
「親父にそう言ってもらえて、うれしいよ」大二郎さんが唇を固く結んだ。「そうだ、さっきの十号玉、見てくれたかい? 俺の作品だったんだ」
「もちろんだ。打ち上げられた花火は、残らず見ていたよ。いい仕事しているな。安心したよ」
「俺が親父から一番聞きたかった言葉だ」大二郎さんが拳を握りしめた。「ありがとう、親父」
その後、昌枝さんが大二郎さんと話している隙に、庄三さんが修太郎さんにこっそりと尋ねていたのを、僕は聞いていた。「十号玉というのは、どれのことだ?」
僕と菜々実は笑いをこらえるのに苦労した。
「庄三さん、あんた、この花火大会に大二郎さんがいるってことを知ってたのかい?」修太郎さんが尋ねた。
「あ? いや、そんなことは知るわけがない」庄三さんが首を振る。「大二郎がどこで働いているのかなんて、聞かされていなかったからな」
「じゃあ、なぜこの松山の花火大会に来たかったんだ? これは来る前にも尋ねたけど、あんたは心臓がいかれていて、明日をも知れない命だからと答えたよな? だから、今日行われる松山の花火大会を見たいんだと。でもあんた、すこぶる元気そうだぜ」修太郎さんが庄三さんの体を指さす。「カーチェイスも満喫していたし、スーパーでは試食も楽しんでいた。昌枝さんにお茶をぶっかけられて血圧が上がっても平気だ。どうみても、今日明日の命とは思えない。花火見物が今日でないといけない理由、弱すぎないか? それなのに、なぜ松山なのか、俺にはわかんないぞ。第一、なぜ花火なんだ?」
「なぜって、わしはただ死ぬ前に花火が見たいから……花火は好きだし……」庄三さんが首をかしげる。「はて。そう言えばそうだな。なぜ今日、花火なんだろう」
「きっと松山の就職情報誌で、花火のバイトを見つけたんでしょう」立石さんが庄三さんの背後からそっと顔を出す。「だから、そのバイトをやろうと思って」
姉貴が無言で立石さんの持っている情報誌を指さした。立石さんは速やかに庄三さんの背後に隠れた。
「ちょっと待てよ」庄三さんが思い出したような顔をする。「昌枝、お前、数日前から変な歌を歌っていなかったか? たしかあれは、『はあなび花火、松山の花火はス、テ、キィ』ってやつだ。あれ、なんという歌だ?」
「名前はありません。私の創作歌ですから」昌枝さんが湯飲みを口に運ぶ。「それに、今のは間違っています。正確には、『はあなび花火、あ~あ松山の花火は超ス、テ、キィ』です」
……その違いに、何の意味が? 僕は全身から力が抜けそうになる。
ふと立石さんを見ると、真剣な顔で昌枝さんの歌を暗唱している。それ、覚えて何の得があるんですか。
「ま、まあ多少の違いはあるかもしれないが──おい、まさかお前」庄三さんがはっとする。「わしを誘導していたのか? わしに松山の花火を見たいと言わせるように」
「さあ、何のことかしら」昌枝さんがまたお茶を飲む。それから、さっきの歌を口ずさんだ。
「一種のサブリミナル効果だな」修太郎さんが苦笑する。「いわゆる刷り込みってやつだ。昌枝さんは、庄三さんの潜在意識に刺激を与えてメッセージを刷り込んでいたわけだ。庄三さん自ら松山の花火大会に行きたいと言わせるために」
なんとかごまかそうとする昌枝さんから強引に聞き出したところによると、こういうことらしい。
昌枝さんは実は大二郎さんと、ときどき連絡を取り合っていたらしい。とは言っても、別に親子だから当たり前のことで珍しくもなんともないのだけれど。
だから、大二郎さんの近況についてはよく知っていたし、現在どこでどういう仕事に携わっているかについても詳しく知っていた。大二郎さんが報告していたからだ。せめて母親にだけでも心配をかけまいとする大二郎さんの配慮だった。
同時に、昌枝さんは大二郎さんの仕事に理解を持ち、常に励ましてきた。大二郎さんが家を飛び出して以来、遠方からずっと見守ってきたのだ。
ただし、庄三さんには内緒にしていたらしい。連絡は、庄三さんが外出しているときに行っていたとのこと。
「なぜ言わなかった」庄三さんが非難するような目を昌枝さんに向ける。「わしに内緒にするとはどういうことだ?」
「大二郎の名前を口にするだけでも、あなたは機嫌が悪くなるでしょ」昌枝さんがため息をつく。「だから、言わなかったんです」
「知らないのはわしだけ、ということか」庄三さんが自嘲めいた笑いを浮かべる。「つまり、わしとお前の間で内緒事を作っていたということだな。わしにとっては、決して気持ちのいいものではないぞ」
「あなたに言えば、また血圧が上がるでしょ」昌枝さんが真剣な顔で庄三さんを見る。「一度、倒れたのを忘れたの?」
「忘れてはおらん。だが、倒れることよりも、わしはお前に内緒事を作られたほうが」
「そうはいきません!」昌枝さんが声を荒げた。珍しいことだったので、僕はびっくりする。
昌枝さんは深呼吸を二度ほど繰り返すと話を続けた。
「バカなことを言わないで。あなたに倒れてもらうわけにはいきません」昌枝さんが両手で包み込んでいる湯飲みが震えている。「私はあなたと、ここまでずっと一緒に歩いてきました。雨の日も風の日も、嵐の日もありましたけど、二人で乗り越えたことで悪天候を楽しさに変えてきましたよね。でも、まだ終わりではないでしょう? まだまだ道は続くのでしょう? これからも二人で歩いて行くのでしょう?」
庄三さんがはっとした。頭を殴られたような顔をして昌枝さんを見る。「昌枝、お前は……」
「もう終わりなんて言わせませんよ。私たちには、まだまだ先があるんです。進むべき道が」昌枝さんがハンカチで目を押さえた。「わたしは、あなたと一緒にもっと歩きたいんです。もっともっと、一緒に楽しみたいんです。たしかに内緒にしていたことは悪かったと思います。でも、その何倍もの楽しみでお返しするつもりでした。今風な言葉で言うのなら、サプライズってことでしょうか。一人前になった大二郎に会いに行く、あなたに大二郎の成長を見せて差し上げる。そう思っていたのです」
言葉を切った昌枝さんがハンカチを目に当てたままその場にうずくまった。それでもなんとか言葉を押し出した。
「私は……私には、あなたと大二郎の二人を見守っていく義務があります。いいえ、義務ではなく権利です。しっかりと見守らせていただきます。だから、私は」昌枝さんがうずくまったまま、庄三さんを見上げた。「私はあなたを倒れさせません。これからも一緒に歩いていくために」
庄三さんが拳を握りしめた。真っ白になった拳が震えている。唇を噛みしめたまま、空を見上げた。賑やかな花火が去り、静けさを取り戻した星空を。
「母親というのは偉大だな」庄三さんが空を見上げたまま微笑んだ。「だてに腹を痛めてはおらんわい。男が勝てるわけがない」
庄三さんがうずくまったままの昌枝さんの手をとった。昌枝さんが立ち上がる。
「昌枝。お前の手は、昔のままだな」庄三さんが昌枝さんの手を見つめる。「優しい手のままだ。全然変わっとらんわい。それに比べ、わしの手はいつの間にかささくれ立っていたようだ。少し手入れが必要だな」
庄三さんが大二郎さんへ向き直った。「大二郎、今年はいいミカンができたんだ。ごちそうしてやるから帰ってこい」
「ああ。近々帰るよ。彼女も連れてね」大二郎さんが微笑む。「庭のミカン、ぜんぶ食うかもしれないから覚悟しておいたほうがいいよ」
「お父さんね、常日頃、口には出さないけど、実はとっても寂しがっているのよ」昌枝さんがクスリと笑った。「昔、あなたと一緒に植えたミカンの木を見て過ごすことが多いもの。そうですよね、お父さん?」
「バカを言え」庄三さんがくるりと背を向けた。そこにいたニヤケた顔の立石さんと見つめ合う形になったので、九十度、方向を変える。「まあ……少しくらいは寂しいかもしれんが、少しだけだぞ。いいか、そこのところを間違えるな」
大二郎さんが庄三さんの両肩に手を置いた。「細くなったなあ、父さん。昔はもっと分厚かったけど」
「お前が心配をかけるからだ」庄三さんがうつむいた。目からしずくが落ちる。
花ちゃんが、よろしければどうぞ、とハンカチを差し出した。
「お父さんも、涙もろくなりましたよね」湯飲みのお茶がなくなったのか、昌枝さんがペットボトルのお茶のフタを開けた。「お父さんね、最近、映画やドラマで親子愛の場面を観て号泣しているんですよ。私は知っていますよ」
泣き笑いのような顔をして、昌枝さんがペットボトルを口に運んだ。喉が上下する。
「ちょっと昌枝さん、飲み過ぎですよ!」姉貴が注意する。
「そういえば、父さん。母さんに聞いたけど、検査入院してたんだって?」大二郎さんが思い出したように尋ねる。「どうだった? 心臓、だいじょうぶかい?」
「え?」庄三さんがポカンとした表情になる。「心臓? ああ、そうだ。その心臓だよ。まあ、今のところ、たいしたことはないそうだ。だが、安心はできん」
庄三さんがお腹を押さえた。ゆっくりとなでる。
「お父さん、心臓はもう少し上よ。そこは胃です」昌枝さんが眉を寄せた。
「庄三さん、あんた、本当に心臓が問題で検査入院してたのかい?」修太郎さんが疑わしげな顔をする。
「まあ、な。いや、正確に言えば、心臓というか、その」庄三さんが、みんなの目を避けるようにそっぽを向いた。「もう少し下のほうかもしれん」
「は? なんですかそれ。もう少し下って」昌枝さんが疑わしげな顔をする。「はっきり言ってください。みんな心配しているんですから」
「いや実は、痔の治療で入院していたんだ」庄三さんが頭に手を置いた。「痔では格好がつかんからな。それで心臓ってことに」
「なんてことを。では、私もだましていたんですね」昌枝さんが怒りを露わにする。「さっき、人のことをさんざん非難したくせに」
「い、いや、すまん」庄三さんがうろたえた。「花火を見に行くのに、どうせなら心臓が危ないということにすれば、みんなが本気になって連れて行ってくれると思ったから、それで」庄三さんが全員の顔を見回して頭を下げた。「申し訳ない、許してくれ」
はあ。僕は体から力が抜けた。他のみんなも、マラソンを完走した後のような疲労感を露わにしている。
「ま、でも、よかったじゃないか。大事がなくて」修太郎さんが庄三さんの肩を叩いた。「あんたのおかげで素晴らしい花火が見えたわけだし。結果オーライってことで済ませようぜ」
「まあ、それはそうね」姉貴が同意する。「人生、楽しまなきゃね。健康が一番の財産だわ」
「まったくもう。あなたはすぐ口から出任せをいうんだから」昌枝さんが苦笑する。「私は気が気じゃなかったんですよ」
「すまんすまん。だが、心臓は無事でも、子供の頃から小心者だったのは確かだ」庄三さんが立石さんの顔を見てニヤリとする。「立石君。実は、わしも子供の頃、花火の爆音を聞いてビビったクチだよ。泣きながら小便を漏らしたもんだ」
「あ、そうでしたか。同類ですね」立石さんがうれしそうな顔をする。
「実は、さっきも三滴ほど漏らしてしまったかもしれん」と庄三さんが頭をかく。
立石さんがニンマリとして手を差し出した。その手を庄三さんが固く握った。
そのニンマリはなんですか、そのニンマリは。
というか、マジに聞いているのは僕ぐらいだし。
あの、みなさん。勝手に向こうへ行かないでくれる?
0
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~
ハムえっぐ
ファンタジー
かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。
王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。
15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。
国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。
これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。


病弱な彼女は、外科医の先生に静かに愛されています 〜穏やかな執着に、逃げ場はない〜
来栖れいな
恋愛
――穏やかな微笑みの裏に、逃げられない愛があった。
望んでいたわけじゃない。
けれど、逃げられなかった。
生まれつき弱い心臓を抱える彼女に、政略結婚の話が持ち上がった。
親が決めた未来なんて、受け入れられるはずがない。
無表情な彼の穏やかさが、余計に腹立たしかった。
それでも――彼だけは違った。
優しさの奥に、私の知らない熱を隠していた。
形式だけのはずだった関係は、少しずつ形を変えていく。
これは束縛? それとも、本当の愛?
穏やかな外科医に包まれていく、静かで深い恋の物語。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

還暦の性 若い彼との恋愛模様
MisakiNonagase
恋愛
還暦を迎えた和子。保持する資格の更新講習で二十代後半の青年、健太に出会った。何気なくてLINE交換してメッセージをやりとりするうちに、胸が高鳴りはじめ、長年忘れていた恋心に花が咲く。
そんな還暦女性と二十代の青年の恋模様。
その後、結婚、そして永遠の別れまでを描いたストーリーです。
全7話
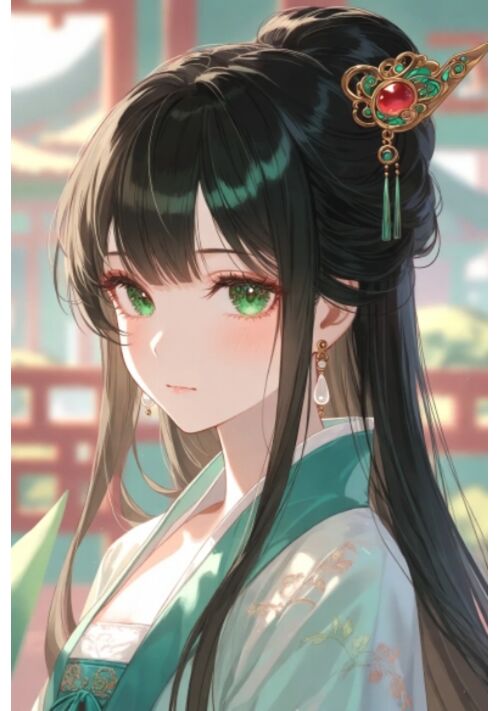
完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す―2人の皇子と失われた記憶【1/23本編完結】
雪城 冴
キャラ文芸
本編完結‼️【中華サスペンス】
皇帝が隠した禁忌の秘密。
それを“思い出してはいけない少女”がいた。
「その眼で見るな――」
特殊な眼を持つ少女・翠蓮は、忌み嫌われ、村を追われた。
居場所を失った彼女が頼れたのは、歌だけ。
宮廷歌姫を目指して辿り着いた都でも、待っていたのは差別と孤立。
そんな翠蓮に近づいたのは、
危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。
だが、その出会いをきっかけに皇位争い、皇后の執着、命を狙われる日々。
追い詰められる中で、翠蓮の忘れていた記憶が揺り動く。
かつて王家が封じた“力”とは?
翠蓮の正体とは?
声を隠して生き延びるか。
それとも、すべてを賭けて歌うのか。
運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――?
※架空の中華風ファンタジーです
※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています
※表紙絵はAI生成
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















