21 / 65
第2巻 理に堕つる者たち
第3章 灰の犬
しおりを挟む
陽が傾き、街道の先に灰色の城壁が見えた。
王都アルマ=シェル――アーレンがかつて理と罪をともに捧げた場所。
彼は足を止め、長く息を吐いた。
あの壁の向こうにあるのは、懐かしさではなく、
幾度も夢の中で踏みにじってきた記憶だった。
高い外壁は夕陽を浴び、鈍い赤に染まっている。
その色は血にも似ていたが、どこか灰を混ぜたようにくすんで見えた。
「……あれが、王都」
リュミナの声は小さく、まるで何かを怖れるようだった。
彼女の瞳に映る街は、光を返しながらも遠く、冷たかった。
「たくさん、ひとがいる?」
「多すぎるほどにな」
アーレンは、かすかに笑った。
「ここでは、理が息をしている」
「ことわり?」
「人の理、国家の理、そして神の理。
それぞれが勝手に動き、互いを飲み込みながら腐っていく」
リュミナは空を見上げた。
雲の切れ間に、白い塔が一本そびえている。
それはまっすぐに空へと伸び、
その頂で夕陽を受けてかすかに光を返していた。
「あれが、灰の塔」
アーレンの声には、わずかに震えがあった。
「おまえの“理”が生まれた場所だ」
「わたしの?」
「そうだ。
おまえがまだ名も形も持たなかった頃、
その塔の奥で、俺はおまえの欠片を拾った。
だから……あそこは、ある意味でおまえの“始まり”でもある」
リュミナは塔をじっと見つめた。
その瞳に宿るのは恐れでも憧れでもなく、
“思い出せない懐かしさ”のような静けさだった。
「おおきい……でも、さむい匂い」
「あそこは命の熱を奪って、理に変える場所だ」
風が吹き、王都の方角から灰の粉が流れてくる。
光を受けた灰が、雪のようにゆっくりと落ちた。
リュミナは掌でそれを受け止める。
「これ、灰の雪?」
「ああ。理が燃えたあとの塵だ」
アーレンはその灰を見つめながら、
言葉にできない痛みを喉の奥に押し込んだ。
かつて彼が見上げた理の光も、
いまはこの灰と同じように、
ただ静かに地へと還ろうとしている。
⸻
街道の分岐で、アーレンは足を止めた。
正門は遠く、火の灯った検問が見える。
「正面は避ける。北の旧水路を使おう。
学院にいた頃、あそこは裏道として使われていた。
今も通じているなら、誰にも見つからずに入れる」
「かくれるの?」
「まだ、見つかるわけにはいかない」
リュミナはうなずき、アーレンの袖をそっとつまんだ。
その手は少し冷たく、
けれど確かにそこに“命の温度”があった。
⸻
夜が降り始めるころ、
遠くの塔がぼんやりと光を放ち始めた。
その光は街を包むようでありながら、
見えない檻のようにも感じられた。
アーレンはその塔を見上げ、
懐かしさと嫌悪のあいだで息を詰めた。
あの塔で彼は理を創り、
そして、すべてを失った。
「……行こう」
「うん」
二人は静かに歩き出した。
背後で風が吹き、灰が夜の空に舞った。
その灰は光を帯び、
まるで失われた命の残響のようにきらめいていた。
夜が深まり、王都の外壁は闇に沈んでいた。
風は途絶え、世界が一瞬だけ呼吸を止めたように静まり返る。
アーレンはその変化を感じ取ると歩を止め、足元の湿った石を踏みしめた。
水路沿いの空気は重く、遠くから鉄と灰の匂いが混ざった気配が漂っていた。
それは、かつてこの都に満ちていた“理”の残り香に似ていた。
彼は符を取り出し、指先で淡く光を走らせる。
灰色の紋様が空気の流れを視覚化し、周囲の気配を探る。
しかし、どこにも風はなかった。
「……リュミナ」
名を呼ぶ声が静寂に吸い込まれる。
「下がれ」
その瞬間、闇が裂けた。
無音のまま刃が閃き、湿った空気が震える。
アーレンはためらいなく符を叩きつけ、灰光の壁を立ち上げた。
金属が弾ける音とともに火花が散り、夜が一瞬だけ白く照らされる。
煙の向こうに、灰の仮面をつけた三つの影が立っていた。
灰の犬――学院直属の影の部隊。
呼吸は一定で、動きに一片の迷いもない。
その姿はまるで“人の形を取った理”そのものだった。
「……灰の犬、か」
アーレンの声は低く沈む。
リュミナが怯えたように問う。
「ひと……なの?」
「昔はな。いまは命を削られ、理だけで動く器だ」
灰の犬の一人が前に出る。
仮面の奥の瞳は、色を失っていた。
刃が振り下ろされ、アーレンは即座に符陣を連結させる。
灰光が円を描き、三重の結界が弾けた。
鎖のような灰線が空間を縫い、敵の腕を絡め取る。
だが次の瞬間、鎖は静かに断たれた。
切り口は滑らかで、まるで空気そのものを斬り裂かれたようだった。
闇の奥から、もう一つの影が現れる。
その歩調には、重さと確信があった。
隊長――バルク・イェルド。
「アーレン・グレイヴ。
理を盗み、禁を破った男。
学長アストレアの命により、ここで終わってもらう」
その声は冷たく、均整の取れた響きを持っていた。
「バルク……」
アーレンは目を細めた。
「塔の犬がいまも鎖に繋がれたままとはな」
「俺は鎖を誇りに思っている。理が命じるままに生き、命じるままに死ぬ」
「それを理と呼ぶのか。
おまえたちは命令に従っているだけだ。
本当の理は、人が恐れた先にある」
応えの代わりに、刃が閃いた。
金属と灰の音が交錯し、空気が震える。
アーレンの符陣が光を放ち、バルクの灰刃とぶつかる。
灰の火花が散り、二人の輪郭が光の中で揺らめいた。
⸻
リュミナは、動けなかった。
恐怖ではない。胸の奥を焼くような痛みが走り、世界の音が遠のく。
そのかわりに、灰のざらつく感覚だけが全身を満たしていく。
呼吸のたびに空気が重くなり、頭の奥で何かが目覚める気配がした。
――白い部屋。液体に沈む無数の器。
その中で、声が言う。
「安定しています。反応、良好です」
リュミナの唇が震えた。
その瞬間、周囲の灰が舞い上がる。
光の粒が集まり、掌の先で円を描いた。
彼女が無意識に展開した防御陣だった。
敵の刃が、アーレンの背を狙って走る。
風が裂け、金属が唸る。
だがその刃は、届かなかった。
リュミナの指先から放たれた灰光が、空間ごと凍らせたのだ。
灰の犬の刃が空中で止まり、次の瞬間、逆方向へ砕け散る。
「……やめて」
その声は震えていたが、静かに響いた。
「もう、これ以上アーレンを傷つけないで」
灰の粒が彼女の周囲を巡り、
まるで彼女自身が“理”の中核であるかのように輝いた。
⸻
バルクが一歩退き、低く呟く。
「これが……再現体か。理が自我を得た器。」
「触れるな!」
アーレンが符を起動させ、灰光が走る。
「彼女はおまえたちの失敗作じゃない!」
しかし、リュミナの光は止まらなかった。
灰の粒が渦を巻き、風が唸りを上げる。
アーレンの叫びも届かない。
――塔の幻。
白い部屋。心臓のように脈打つ光。
沈む自分と、同じ顔の影。
「……いや……」
リュミナの瞳から光がこぼれ、
次の瞬間、灰光が弾けた。
轟音が夜を裂き、灰の犬たちは吹き飛ぶ。
バルクは体勢を崩しながら短く命じた。
「撤収。対象、制御不能。報告を上げる。
――再現体、覚醒段階に入った。」
灰の外套が闇に溶け、
風だけが残った。
⸻
静寂が戻る。
アーレンは膝をつき、リュミナを抱きとめた。
彼女の体は冷たく、しかしわずかに光を帯びていた。
「……ごめん、アーレン。こわかったの」
「いい。もう喋るな」
アーレンは彼女の髪を撫で、
指先についた灰の粒を見つめた。
それは冷たく、けれど人の体温のようにやさしく残っていた。
夜が明けきらぬうちに、雨が降り出した。
霧雨のような細い粒が静かに森を濡らし、
その間を抜ける風が、どこか金属めいた音を運んでくる。
アーレンは崩れた石壁の下に簡易の幕を張り、
その奥でリュミナの体を支えていた。
彼女は浅い呼吸を繰り返し、額に汗を浮かべている。
肌の奥で微かに光が脈動し、
まるで心臓の鼓動が灰光として形を取っているかのようだった。
アーレンは濡れた前髪を払うと、
符を取り出して地面に小さな陣を描いた。
符陣が青白く光り、空気がわずかに暖まる。
それでも彼の指先は震えていた。
「……符の効き目が不安定だ。
理の干渉域がまだ残っているのか」
呟く声は冷静を装っていたが、
その奥に焦りが滲んでいた。
リュミナのまぶたがゆっくりと動いた。
灰色の瞳が、薄明の光を映す。
「……アーレン」
その声はかすれていた。
「ここ……どこ?」
「北の森の外れだ。街道から離れた。
もう追っ手はいない」
「……わたし、なにか……した?」
アーレンは一瞬、言葉を失った。
彼女の指先にはまだ灰の粒が残っている。
あれほどの光を放ったというのに、
その本人には何の記憶もないようだった。
「覚えていないのか?」
「光って……あたたかくて、こわくて。
でも、それだけ。
あと、音がした。……なつかしい音。」
「音?」
「うん……鐘の音。
水の中で、ひかりが響くみたいな……」
アーレンは黙っていた。
思考の中で、過去の記録が交錯する。
“灰核反応”――理が過剰に共鳴したときに発生する現象。
本来は制御装置がなければ、
命ごと焼き切れるはずの危険領域。
だが、リュミナは生きている。
光も消え、体も安定している。
まるで“理”そのものが、
彼女を中心に再構成されたかのように。
「リュミナ、おまえ……あのとき、なにを見た?」
「……わからない。
でも、わたしの目の前に……もうひとりいたの。
わたしに似てて、
でも笑ってなかった。
その人が、塔のほうを見てた」
アーレンの胸に、冷たいものが走った。
塔の実験室で失われた無数の“試験体”。
そのどれかが――
あるいは、リュミナと同じ“設計”を持つもうひとりが、
まだこの世に存在しているのかもしれない。
⸻
雨が弱まり、灰の香りが漂う。
アーレンはリュミナの肩に上着をかけた。
その動作はゆっくりで、
まるで彼女の温度を確かめるようだった。
「無理をするな。
おまえの中の理は、まだ安定していない。
次に暴走したら、命を落とすかもしれない」
「……わたしの中に、理があるの?」
「ああ。
おまえは、理の器であり、同時にその証明だ」
リュミナは目を閉じた。
「それって……わたしが人じゃないってこと?」
問いに、アーレンはすぐに答えなかった。
代わりに、焚き火に新しい枝をくべた。
火がぱちりと音を立て、橙の光が二人の影を揺らす。
「違う。
おまえは、理に生かされた“人”だ。
俺たちが理解できないだけで、
本当の理は命と同じ場所にあるんだ」
リュミナはかすかに笑った。
「……よくわかんないけど、
アーレンが言うと、なんかやさしく聞こえる」
その言葉に、アーレンの肩の力が少しだけ抜けた。
雨が止み、夜が静かに戻る。
灰の降りしきる森の中、
二人の呼吸だけが小さく重なっていた。
王都アルマ=シェル――アーレンがかつて理と罪をともに捧げた場所。
彼は足を止め、長く息を吐いた。
あの壁の向こうにあるのは、懐かしさではなく、
幾度も夢の中で踏みにじってきた記憶だった。
高い外壁は夕陽を浴び、鈍い赤に染まっている。
その色は血にも似ていたが、どこか灰を混ぜたようにくすんで見えた。
「……あれが、王都」
リュミナの声は小さく、まるで何かを怖れるようだった。
彼女の瞳に映る街は、光を返しながらも遠く、冷たかった。
「たくさん、ひとがいる?」
「多すぎるほどにな」
アーレンは、かすかに笑った。
「ここでは、理が息をしている」
「ことわり?」
「人の理、国家の理、そして神の理。
それぞれが勝手に動き、互いを飲み込みながら腐っていく」
リュミナは空を見上げた。
雲の切れ間に、白い塔が一本そびえている。
それはまっすぐに空へと伸び、
その頂で夕陽を受けてかすかに光を返していた。
「あれが、灰の塔」
アーレンの声には、わずかに震えがあった。
「おまえの“理”が生まれた場所だ」
「わたしの?」
「そうだ。
おまえがまだ名も形も持たなかった頃、
その塔の奥で、俺はおまえの欠片を拾った。
だから……あそこは、ある意味でおまえの“始まり”でもある」
リュミナは塔をじっと見つめた。
その瞳に宿るのは恐れでも憧れでもなく、
“思い出せない懐かしさ”のような静けさだった。
「おおきい……でも、さむい匂い」
「あそこは命の熱を奪って、理に変える場所だ」
風が吹き、王都の方角から灰の粉が流れてくる。
光を受けた灰が、雪のようにゆっくりと落ちた。
リュミナは掌でそれを受け止める。
「これ、灰の雪?」
「ああ。理が燃えたあとの塵だ」
アーレンはその灰を見つめながら、
言葉にできない痛みを喉の奥に押し込んだ。
かつて彼が見上げた理の光も、
いまはこの灰と同じように、
ただ静かに地へと還ろうとしている。
⸻
街道の分岐で、アーレンは足を止めた。
正門は遠く、火の灯った検問が見える。
「正面は避ける。北の旧水路を使おう。
学院にいた頃、あそこは裏道として使われていた。
今も通じているなら、誰にも見つからずに入れる」
「かくれるの?」
「まだ、見つかるわけにはいかない」
リュミナはうなずき、アーレンの袖をそっとつまんだ。
その手は少し冷たく、
けれど確かにそこに“命の温度”があった。
⸻
夜が降り始めるころ、
遠くの塔がぼんやりと光を放ち始めた。
その光は街を包むようでありながら、
見えない檻のようにも感じられた。
アーレンはその塔を見上げ、
懐かしさと嫌悪のあいだで息を詰めた。
あの塔で彼は理を創り、
そして、すべてを失った。
「……行こう」
「うん」
二人は静かに歩き出した。
背後で風が吹き、灰が夜の空に舞った。
その灰は光を帯び、
まるで失われた命の残響のようにきらめいていた。
夜が深まり、王都の外壁は闇に沈んでいた。
風は途絶え、世界が一瞬だけ呼吸を止めたように静まり返る。
アーレンはその変化を感じ取ると歩を止め、足元の湿った石を踏みしめた。
水路沿いの空気は重く、遠くから鉄と灰の匂いが混ざった気配が漂っていた。
それは、かつてこの都に満ちていた“理”の残り香に似ていた。
彼は符を取り出し、指先で淡く光を走らせる。
灰色の紋様が空気の流れを視覚化し、周囲の気配を探る。
しかし、どこにも風はなかった。
「……リュミナ」
名を呼ぶ声が静寂に吸い込まれる。
「下がれ」
その瞬間、闇が裂けた。
無音のまま刃が閃き、湿った空気が震える。
アーレンはためらいなく符を叩きつけ、灰光の壁を立ち上げた。
金属が弾ける音とともに火花が散り、夜が一瞬だけ白く照らされる。
煙の向こうに、灰の仮面をつけた三つの影が立っていた。
灰の犬――学院直属の影の部隊。
呼吸は一定で、動きに一片の迷いもない。
その姿はまるで“人の形を取った理”そのものだった。
「……灰の犬、か」
アーレンの声は低く沈む。
リュミナが怯えたように問う。
「ひと……なの?」
「昔はな。いまは命を削られ、理だけで動く器だ」
灰の犬の一人が前に出る。
仮面の奥の瞳は、色を失っていた。
刃が振り下ろされ、アーレンは即座に符陣を連結させる。
灰光が円を描き、三重の結界が弾けた。
鎖のような灰線が空間を縫い、敵の腕を絡め取る。
だが次の瞬間、鎖は静かに断たれた。
切り口は滑らかで、まるで空気そのものを斬り裂かれたようだった。
闇の奥から、もう一つの影が現れる。
その歩調には、重さと確信があった。
隊長――バルク・イェルド。
「アーレン・グレイヴ。
理を盗み、禁を破った男。
学長アストレアの命により、ここで終わってもらう」
その声は冷たく、均整の取れた響きを持っていた。
「バルク……」
アーレンは目を細めた。
「塔の犬がいまも鎖に繋がれたままとはな」
「俺は鎖を誇りに思っている。理が命じるままに生き、命じるままに死ぬ」
「それを理と呼ぶのか。
おまえたちは命令に従っているだけだ。
本当の理は、人が恐れた先にある」
応えの代わりに、刃が閃いた。
金属と灰の音が交錯し、空気が震える。
アーレンの符陣が光を放ち、バルクの灰刃とぶつかる。
灰の火花が散り、二人の輪郭が光の中で揺らめいた。
⸻
リュミナは、動けなかった。
恐怖ではない。胸の奥を焼くような痛みが走り、世界の音が遠のく。
そのかわりに、灰のざらつく感覚だけが全身を満たしていく。
呼吸のたびに空気が重くなり、頭の奥で何かが目覚める気配がした。
――白い部屋。液体に沈む無数の器。
その中で、声が言う。
「安定しています。反応、良好です」
リュミナの唇が震えた。
その瞬間、周囲の灰が舞い上がる。
光の粒が集まり、掌の先で円を描いた。
彼女が無意識に展開した防御陣だった。
敵の刃が、アーレンの背を狙って走る。
風が裂け、金属が唸る。
だがその刃は、届かなかった。
リュミナの指先から放たれた灰光が、空間ごと凍らせたのだ。
灰の犬の刃が空中で止まり、次の瞬間、逆方向へ砕け散る。
「……やめて」
その声は震えていたが、静かに響いた。
「もう、これ以上アーレンを傷つけないで」
灰の粒が彼女の周囲を巡り、
まるで彼女自身が“理”の中核であるかのように輝いた。
⸻
バルクが一歩退き、低く呟く。
「これが……再現体か。理が自我を得た器。」
「触れるな!」
アーレンが符を起動させ、灰光が走る。
「彼女はおまえたちの失敗作じゃない!」
しかし、リュミナの光は止まらなかった。
灰の粒が渦を巻き、風が唸りを上げる。
アーレンの叫びも届かない。
――塔の幻。
白い部屋。心臓のように脈打つ光。
沈む自分と、同じ顔の影。
「……いや……」
リュミナの瞳から光がこぼれ、
次の瞬間、灰光が弾けた。
轟音が夜を裂き、灰の犬たちは吹き飛ぶ。
バルクは体勢を崩しながら短く命じた。
「撤収。対象、制御不能。報告を上げる。
――再現体、覚醒段階に入った。」
灰の外套が闇に溶け、
風だけが残った。
⸻
静寂が戻る。
アーレンは膝をつき、リュミナを抱きとめた。
彼女の体は冷たく、しかしわずかに光を帯びていた。
「……ごめん、アーレン。こわかったの」
「いい。もう喋るな」
アーレンは彼女の髪を撫で、
指先についた灰の粒を見つめた。
それは冷たく、けれど人の体温のようにやさしく残っていた。
夜が明けきらぬうちに、雨が降り出した。
霧雨のような細い粒が静かに森を濡らし、
その間を抜ける風が、どこか金属めいた音を運んでくる。
アーレンは崩れた石壁の下に簡易の幕を張り、
その奥でリュミナの体を支えていた。
彼女は浅い呼吸を繰り返し、額に汗を浮かべている。
肌の奥で微かに光が脈動し、
まるで心臓の鼓動が灰光として形を取っているかのようだった。
アーレンは濡れた前髪を払うと、
符を取り出して地面に小さな陣を描いた。
符陣が青白く光り、空気がわずかに暖まる。
それでも彼の指先は震えていた。
「……符の効き目が不安定だ。
理の干渉域がまだ残っているのか」
呟く声は冷静を装っていたが、
その奥に焦りが滲んでいた。
リュミナのまぶたがゆっくりと動いた。
灰色の瞳が、薄明の光を映す。
「……アーレン」
その声はかすれていた。
「ここ……どこ?」
「北の森の外れだ。街道から離れた。
もう追っ手はいない」
「……わたし、なにか……した?」
アーレンは一瞬、言葉を失った。
彼女の指先にはまだ灰の粒が残っている。
あれほどの光を放ったというのに、
その本人には何の記憶もないようだった。
「覚えていないのか?」
「光って……あたたかくて、こわくて。
でも、それだけ。
あと、音がした。……なつかしい音。」
「音?」
「うん……鐘の音。
水の中で、ひかりが響くみたいな……」
アーレンは黙っていた。
思考の中で、過去の記録が交錯する。
“灰核反応”――理が過剰に共鳴したときに発生する現象。
本来は制御装置がなければ、
命ごと焼き切れるはずの危険領域。
だが、リュミナは生きている。
光も消え、体も安定している。
まるで“理”そのものが、
彼女を中心に再構成されたかのように。
「リュミナ、おまえ……あのとき、なにを見た?」
「……わからない。
でも、わたしの目の前に……もうひとりいたの。
わたしに似てて、
でも笑ってなかった。
その人が、塔のほうを見てた」
アーレンの胸に、冷たいものが走った。
塔の実験室で失われた無数の“試験体”。
そのどれかが――
あるいは、リュミナと同じ“設計”を持つもうひとりが、
まだこの世に存在しているのかもしれない。
⸻
雨が弱まり、灰の香りが漂う。
アーレンはリュミナの肩に上着をかけた。
その動作はゆっくりで、
まるで彼女の温度を確かめるようだった。
「無理をするな。
おまえの中の理は、まだ安定していない。
次に暴走したら、命を落とすかもしれない」
「……わたしの中に、理があるの?」
「ああ。
おまえは、理の器であり、同時にその証明だ」
リュミナは目を閉じた。
「それって……わたしが人じゃないってこと?」
問いに、アーレンはすぐに答えなかった。
代わりに、焚き火に新しい枝をくべた。
火がぱちりと音を立て、橙の光が二人の影を揺らす。
「違う。
おまえは、理に生かされた“人”だ。
俺たちが理解できないだけで、
本当の理は命と同じ場所にあるんだ」
リュミナはかすかに笑った。
「……よくわかんないけど、
アーレンが言うと、なんかやさしく聞こえる」
その言葉に、アーレンの肩の力が少しだけ抜けた。
雨が止み、夜が静かに戻る。
灰の降りしきる森の中、
二人の呼吸だけが小さく重なっていた。
0
あなたにおすすめの小説

正しい聖女さまのつくりかた
みるくてぃー
ファンタジー
王家で育てられた(自称)平民少女が、学園で起こすハチャメチャ学園(ラブ?)コメディ。
同じ年の第二王女をはじめ、優しい兄姉(第一王女と王子)に見守られながら成長していく。
一般常識が一切通用しない少女に友人達は振り回されてばかり、「アリスちゃんメイドを目指すのになぜダンスや淑女教育が必要なの!?」
そこには人知れず王妃と王女達によるとある計画が進められていた!
果たしてアリスは無事に立派なメイドになれるのか!? たぶん無理かなぁ……。
聖女シリーズ第一弾「正しい聖女さまのつくりかた」

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する
namisan
ファンタジー
数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。
転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。
しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。
凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。
詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。
それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。
「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」
前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。
痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。
そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。
これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。

【完結】ご都合主義で生きてます。-商売の力で世界を変える。カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく-
ジェルミ
ファンタジー
28歳でこの世を去った佐藤は、異世界の女神により転移を誘われる。
その条件として女神に『面白楽しく生活でき、苦労をせずお金を稼いで生きていくスキルがほしい』と無理難題を言うのだった。
困った女神が授けたのは、想像した事を実現できる創生魔法だった。
この味気ない世界を、創生魔法とカスタマイズ可能なストレージを使い、美味しくなる調味料や料理を作り世界を変えて行く。
はい、ご注文は?
調味料、それとも武器ですか?
カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく。
村を開拓し仲間を集め国を巻き込む産業を起こす。
いずれは世界へ通じる道を繋げるために。
※本作はカクヨム様にも掲載しております。
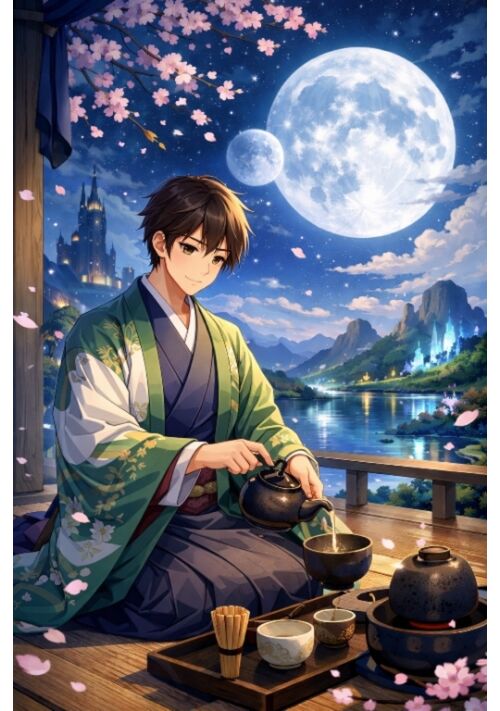
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

【完結】異世界で神の元カノのゴミ屋敷を片付けたら世界の秘密が出てきました
小豆缶
ファンタジー
父の遺したゴミ屋敷を片付けていたはずが、気づけば異世界に転移していた私・飛鳥。
しかも、神の元カノと顔がそっくりという理由で、いきなり死刑寸前!?
助けてくれた太陽神ソラリクスから頼まれた仕事は、
「500年前に別れた元恋人のゴミ屋敷を片付けてほしい」というとんでもない依頼だった。
幽霊になった元神、罠だらけの屋敷、歪んだ世界のシステム。
ポンコツだけど諦めの悪い主人公が、ゴミ屋敷を片付けながら異世界の謎を暴いていく!
ほのぼのお仕事×異世界コメディ×世界の秘密解明ファンタジー

第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

異世界転移物語
月夜
ファンタジー
このところ、日本各地で謎の地震が頻発していた。そんなある日、都内の大学に通う僕(田所健太)は、地震が起こったときのために、部屋で非常持出袋を整理していた。すると、突然、めまいに襲われ、次に気づいたときは、深い森の中に迷い込んでいたのだ……

元公爵令嬢は年下騎士たちに「用済みのおばさん」と捨てられる 〜今更戻ってこいと泣きつかれても献身的な美少年に溺愛されているのでもう遅いです〜
日々埋没。
ファンタジー
「新しい従者を雇うことにした。おばさんはもう用済みだ。今すぐ消えてくれ」
かつて婚約破棄され、実家を追放された元公爵令嬢のレアーヌ。
その身分を隠し、年下の冒険者たちの身の回りを世話する『メイド』として献身的に尽くしてきた彼女に突きつけられたのは、あまりに非情な追放宣告だった。
レアーヌがこれまで教育し、支えてきた若い男たちは、新しく現れた他人の物を欲しがり子悪魔メイドに骨抜きにされ、彼女を「加齢臭のする汚いおばさん」と蔑み、笑いながら追い出したのだ。
地位も、居場所も、信じていた絆も……すべてを失い、絶望する彼女の前に現れたのは、一人の美少年だった。
「僕とパーティーを組んでくれませんか? 貴方が必要なんです」
新米ながら将来の可能性を感じさせる彼は、レアーヌを「おばさん」ではなく「一人の女性」として、甘く狂おしく溺愛し始める。
一方でレアーヌという『真の支柱』を失った元パーティーは、自分たちがどれほど愚かな選択をしたかを知る由もなかった。
やがて彼らが地獄の淵で「戻ってきてくれ」と泣きついてきても、もう遅い。
レアーヌの隣には、彼女を離さないと誓った執着愛の化身が微笑んでいるのだから。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















