24 / 65
第2巻 理に堕つる者たち
第6章 王都潜入
しおりを挟む
灰の降る空の下、風は冷たかった。
王都を囲む外壁が、遠くの霞の向こうに見える。
その上を、薄い光の幕が包んでいた。
塔の理が外に滲み出している――アーレンには、それがはっきりと分かった。
足元の草はうっすらと灰をかぶり、踏むたびに粉が舞う。
それはただの埃ではなく、
触れると微かに脈打つような気配を持っていた。
「……あれが、王都?」
リュミナが小さな声で尋ねた。
彼女の瞳が、灰の空を映す。
「ああ。俺が昔いた場所だ」
「きれい……でも、息が、重い」
「灰のせいだ。理が空気に混じってる。
人には感じ取れないけど、おまえには分かるんだろう」
「うん。……胸の奥が、ざわざわする」
アーレンは懐から符束を取り出した。
白紙の符を取り、指先で素早く線を描く。
淡い光が走り、墨が符面に吸い込まれていく。
「手を出せ。少し冷たいぞ」
リュミナが差し出した手に、符をそっと貼る。
光が薄く脈を打ち、空気が静かになった。
灰の粒が、まるで避けるように彼女の周囲から離れていく。
「……あったかい」
「理を抑える符だ。しばらくは誰にも気づかれない」
「かくれるの?」
「ああ。塔の人間に見つかると面倒だ」
リュミナはしばらく黙っていたが、
やがて小さく呟いた。
「灰が……泣いてるみたい」
「泣いてる?」
「うん。音がするの。悲しい声みたい」
アーレンは息を止め、空を見上げた。
灰の降る音は、風と同じで“音”ではない。
だが、理が乱れているとき、
感受性の強い者には“響き”として感じられるという。
――理の声。
「……塔が呼んでるんだ」
「わたしを?」
「きっとな」
リュミナは灰の空を見上げたまま、
ほんの少しだけ寂しそうに笑った。
「ねえ、アーレン。
わたしが“そこ”から来たのなら、
帰ったら、もうわたしじゃなくなる?」
アーレンはその問いに、すぐには答えられなかった。
代わりに彼女の頭に手を置き、静かに言った。
「帰るんじゃない。確かめに行くんだ」
「……うん」
丘を下る風が吹いた。
灰が二人の間を流れ、光を受けて淡く輝く。
その向こうに、王都が息をしている。
まるで彼らの到来を待っているかのように。
王都の外壁が近づくにつれ、灰の降り方が濃くなった。
空の光は曇りガラス越しのように鈍く、
門前の街道はすでに薄い灰の膜に覆われていた。
普段なら、王都の門は早朝から商人や旅人で賑わっている。
だが今朝は違った。
列は長いのに、誰も声を発しない。
鎧をまとった衛兵たちの動きもぎこちない。
灰の中で光る紋章の輝きが、不安を隠すように揺れていた。
アーレンは列の最後尾に立ち、
フードを深くかぶったリュミナに視線を送った。
「覚えておけ。質問は少なく、答えは短く」
「うん」
「目を合わせるな。灰のせいで皆、神経が尖ってる」
リュミナはこくりと頷いた。
王都の門の上では、
符術検査装置――理の反応を測る青い水晶球が淡く光っていた。
本来なら、通行人を一人ずつ通して反応を確認する。
だが、今日は光が安定していない。
灰が触れるたび、水晶がわずかに濁る。
「……検査符、死んでるな」
アーレンが小さく呟いた。
灰に含まれる理の干渉が強すぎる。
王都の符術機構は、すでに正常に働かなくなっている。
門の前まで来たとき、
衛兵が槍の柄で地面を叩いた。
「止まれ。名と出身を」
アーレンはゆっくりと答える。
「アルバート・ルイ。地方の薬師だ。治療符の売買で来た」
用意しておいた偽名。
符商人としての身分証も、灰の影響で真偽を確かめられはしない。
「同行の少女は?」
「助手だ。調合を手伝ってる」
衛兵はリュミナを一瞥した。
灰が降りかかり、彼女の銀髪が淡く光る。
一瞬、兵の表情が固まった。
「おい、髪の色……」
もう一人の衛兵が囁く。
アーレンは即座に言葉を重ねた。
「灰だ。今朝から降り続いてるだろう。
うちの村でも皆、同じように染まってる」
嘘は滑らかだった。
兵は顔をしかめ、灰を払うように手を振った。
「……こんな天気じゃ、見分けもつかん。
とっとと通れ。だが、塔の方へは近づくな。封鎖中だ」
「承知している」
アーレンは軽く頭を下げ、
リュミナの肩を押して門をくぐった。
石畳を踏む瞬間、
リュミナが小さく息を呑む。
「ねえ……ここ、音がする」
彼女の声は震えていた。
「どんな音だ?」
「……たくさん。人の声。泣いてるみたい。
でも、どこからか分からない」
アーレンは彼女を見下ろし、
ほんの一瞬だけ目を細めた。
「街全体が、理の中にある。
塔の呼吸が、もう王都じゅうに届いてるんだ」
街の奥から、かすかに鐘の音が聞こえた。
それは警鐘でも祝福でもなく、
――まるで世界の心臓の鼓動のように、
灰色の空を震わせていた。
王都の街路は、灰に沈んでいた。
人々は屋根の下を歩き、外に出る者は少ない。
灯の符はちらつき、空気の流れがざらついている。
理の息づかいが、街そのものを満たしていた。
アーレンは裏通りを抜け、薄暗い路地に入った。
その突き当たりに、鉄の扉と古びた銘板がある。
錆びた文字には、こう刻まれていた。
《フェズ商館》
看板の意味を知らなければ、ただの倉庫のようだ。
だが、灰と理に関する資料を扱う密商――灰料屋(はいりょうや)としては、
王都でもよく知られた名だった。
扉を開けると、冷たい空気と古紙の匂いが流れ出た。
天井の低い部屋の中、所狭しと本と道具が並んでいる。
机の奥から、声がした。
「……めずらしい客だな。
こんな日に、外を歩ける物好きがいるとは」
出てきたのは、灰を被った外套を着た中年の男。
髪は乱れ、眼鏡の奥の目が妙に鋭い。
彼が、エリン・フェズだった。
「噂は聞いてる。学院から落ちた男が帰ってきたってな。
まさか、本当に来るとは思わなかったよ」
アーレンは短く息をつき、帽子の影から顔を上げた。
「俺の名前を出すな。聞かれたら厄介だ」
「安心しろ、口より紙の方が信用できる性分でな。
……で、何を探してる?」
「灰核理論の初期記録。塔が動く前の、最初の研究資料だ」
「物騒なもんを。
あんた、死にに来たのか、それともまだ生きて学びたいのか?」
皮肉にアーレンは笑わなかった。
代わりに、懐から一枚の符を差し出す。
符面に描かれた印は、学院時代の彼の個人符――その信頼印だった。
「これで足りるはずだ」
フェズは目を細め、それを一瞥してから受け取る。
「足りるどころか、久々に燃える話だ。
……ついて来い。下に、面白いものがある」
⸻
半地下の倉庫は、光がほとんど届かない。
壁に埋め込まれた小さな符灯が、弱々しい橙色の光を放っていた。
棚の上には灰の壺や古い装置が並び、
その中には、かすかに理の光を帯びた本が一冊置かれていた。
「これは……」
「灰化記録だ。百年以上前、塔の礎が築かれる前に書かれたもの。
ただし、読むな。目が焼ける」
「忠告ありがとう」
アーレンは本を手に取った。
表紙は灰の膜で覆われ、指先が触れると、微かに反応して震える。
その脈動は――人の鼓動のようだった。
「ねえ、アーレン」
背後からリュミナが囁く。
「この本、音がする」
「聞こえるのか?」
「うん。……中で、だれかが呼んでる」
フェズがその言葉に眉をひそめた。
「……“聞こえる”とは、どういう意味だ?」
「彼女は理を感じ取れる。説明は後だ」
アーレンは短く返し、慎重に本を開いた。
頁の中央に、灰色の紋章が浮かび上がる。
そしてその下に、一文だけ、手書きの記録があった。
『理の模倣体、試験体ルーメン。
灰化後、残響を確認。
“わたしはまだここにいる”』
アーレンは息をのんだ。
ルーメン――その名が、リュミナの名とわずかに響きを重ねる。
偶然ではない。
これは、同じ理の系統――“前の失敗作”だ。
「……やはり、最初から繋がっていたのか」
アーレンの声が震えた。
リュミナはそっとアーレンの袖を掴む。
「アーレン。わたし、その名前……知ってる気がする」
フェズが息を呑んだ。
「まさか……まさか、君……」
だが言葉は途中で止まった。
上階から、足音が響いた。
重く、固い靴音。
符を叩く金属音が混じっている。
アーレンは顔を上げた。
「――学院の連中だ」
足音が階段を下りてくる。
規則的で、ためらいのない音。
鍛えられた者の歩き方だった。
フェズは灯を消し、灰の帳簿を抱えた。
「アーレン、上だ。裏口は階段の奥、右の棚の影だ」
「おまえは?」
「ここで足止めする。見つかったら、俺の方が疑われる」
アーレンはためらったが、フェズの目がそれを許さなかった。
「俺の本に触れたんだ。
もう関係者だ。行け、灰に喰われる前にな」
アーレンは短く頷き、リュミナの手を取った。
「行くぞ」
棚を押すと、軋んだ音とともに壁が開いた。
狭い通路の奥に、崩れかけた石階段が続いている。
灰の粒がふわりと舞い、光を受けて白くきらめいた。
その背後で、扉が開く音。
誰かが地面を踏む。
硬い靴の底に灰が潰される音が、ゆっくりと近づいてくる。
⸻
「フェズ・エリン。学院の命令だ。
おまえが“塔の理資料”を隠していると聞いた」
声は冷たく、感情がない。
複数の足音が床を渡る。
灰の光を受け、黒い外套に刻まれた紋章がかすかに輝く。
――灰の犬。
学院直属の影部隊。
その名を聞いたことのある者は、ほとんどが二度と口にしなかった。
「知らんね。俺は商人だ。売る相手を選ぶ義理もない」
「……ここに、男と少女が入ったと報告がある」
「見間違いだろう。灰のせいで何もかも霞んで見える」
刹那、空気が軋んだ。
灰の犬の一人が手をかざす。
符の陣が浮かび、灰が渦を巻く。
フェズは舌打ちした。
「――やれやれ、これだから学院は嫌いだ」
彼は机を蹴り、灰の壺を割った。
中から立ち上がったのは、灰に混じる理の光。
封じられた符が弾け、煙のように部屋を包む。
「リュミナ、走れ!」
アーレンの声が通路に響く。
⸻
狭い通路を抜けると、裏路地へと出た。
灰が吹き溜まり、石畳が白く染まっている。
リュミナは息を切らしながらも、手を離さない。
「アーレン、後ろ!」
振り返ると、通路の奥で光が弾けた。
灰の犬の一人が符を放ったのだ。
光は灰に吸われ、空気が一瞬ひずむ。
アーレンは腰の符袋を開き、反射的に印を描いた。
防壁符が発動し、灰が固まって壁となる。
音もなく光を受け止め、空間が沈黙した。
衝撃の余波が消えると、壁は粉のように崩れた。
リュミナの頬に灰がかかる。
その灰が淡く光り、肌の上で溶けた。
「……やっぱり、わたし、灰の中で生きてる」
「今はそのおかげで助かってる」
アーレンはリュミナの手を握り、
灰の降る路地を走り出した。
⸻
そのころ、店の奥ではフェズが灰の犬に囲まれていた。
彼の手には、一枚の符が握られている。
その符の中央には、ひとつの短い言葉が刻まれていた。
――“観測者”。
灰の光が彼の身体を包む。
そして、爆ぜた。
店全体が灰に飲まれ、外へ吹き出す。
その瞬間、王都の一角で、灰の塔の光が一段と強くなった。
⸻
遠く離れた路地の影で、アーレンは振り返った。
灰の雨が強まっている。
リュミナの瞳が、塔の方を見つめていた。
「……塔が、また呼んでる」
「わかってる。だが、今は行けない。
まずは身を隠す。王都の理が完全に暴れ出す前に」
風が吹き、灰が二人の影をかすめた。
静かな灰の粒が落ちるたび、
まるで世界そのものが新しい形を探しているかのようだった。
王都を囲む外壁が、遠くの霞の向こうに見える。
その上を、薄い光の幕が包んでいた。
塔の理が外に滲み出している――アーレンには、それがはっきりと分かった。
足元の草はうっすらと灰をかぶり、踏むたびに粉が舞う。
それはただの埃ではなく、
触れると微かに脈打つような気配を持っていた。
「……あれが、王都?」
リュミナが小さな声で尋ねた。
彼女の瞳が、灰の空を映す。
「ああ。俺が昔いた場所だ」
「きれい……でも、息が、重い」
「灰のせいだ。理が空気に混じってる。
人には感じ取れないけど、おまえには分かるんだろう」
「うん。……胸の奥が、ざわざわする」
アーレンは懐から符束を取り出した。
白紙の符を取り、指先で素早く線を描く。
淡い光が走り、墨が符面に吸い込まれていく。
「手を出せ。少し冷たいぞ」
リュミナが差し出した手に、符をそっと貼る。
光が薄く脈を打ち、空気が静かになった。
灰の粒が、まるで避けるように彼女の周囲から離れていく。
「……あったかい」
「理を抑える符だ。しばらくは誰にも気づかれない」
「かくれるの?」
「ああ。塔の人間に見つかると面倒だ」
リュミナはしばらく黙っていたが、
やがて小さく呟いた。
「灰が……泣いてるみたい」
「泣いてる?」
「うん。音がするの。悲しい声みたい」
アーレンは息を止め、空を見上げた。
灰の降る音は、風と同じで“音”ではない。
だが、理が乱れているとき、
感受性の強い者には“響き”として感じられるという。
――理の声。
「……塔が呼んでるんだ」
「わたしを?」
「きっとな」
リュミナは灰の空を見上げたまま、
ほんの少しだけ寂しそうに笑った。
「ねえ、アーレン。
わたしが“そこ”から来たのなら、
帰ったら、もうわたしじゃなくなる?」
アーレンはその問いに、すぐには答えられなかった。
代わりに彼女の頭に手を置き、静かに言った。
「帰るんじゃない。確かめに行くんだ」
「……うん」
丘を下る風が吹いた。
灰が二人の間を流れ、光を受けて淡く輝く。
その向こうに、王都が息をしている。
まるで彼らの到来を待っているかのように。
王都の外壁が近づくにつれ、灰の降り方が濃くなった。
空の光は曇りガラス越しのように鈍く、
門前の街道はすでに薄い灰の膜に覆われていた。
普段なら、王都の門は早朝から商人や旅人で賑わっている。
だが今朝は違った。
列は長いのに、誰も声を発しない。
鎧をまとった衛兵たちの動きもぎこちない。
灰の中で光る紋章の輝きが、不安を隠すように揺れていた。
アーレンは列の最後尾に立ち、
フードを深くかぶったリュミナに視線を送った。
「覚えておけ。質問は少なく、答えは短く」
「うん」
「目を合わせるな。灰のせいで皆、神経が尖ってる」
リュミナはこくりと頷いた。
王都の門の上では、
符術検査装置――理の反応を測る青い水晶球が淡く光っていた。
本来なら、通行人を一人ずつ通して反応を確認する。
だが、今日は光が安定していない。
灰が触れるたび、水晶がわずかに濁る。
「……検査符、死んでるな」
アーレンが小さく呟いた。
灰に含まれる理の干渉が強すぎる。
王都の符術機構は、すでに正常に働かなくなっている。
門の前まで来たとき、
衛兵が槍の柄で地面を叩いた。
「止まれ。名と出身を」
アーレンはゆっくりと答える。
「アルバート・ルイ。地方の薬師だ。治療符の売買で来た」
用意しておいた偽名。
符商人としての身分証も、灰の影響で真偽を確かめられはしない。
「同行の少女は?」
「助手だ。調合を手伝ってる」
衛兵はリュミナを一瞥した。
灰が降りかかり、彼女の銀髪が淡く光る。
一瞬、兵の表情が固まった。
「おい、髪の色……」
もう一人の衛兵が囁く。
アーレンは即座に言葉を重ねた。
「灰だ。今朝から降り続いてるだろう。
うちの村でも皆、同じように染まってる」
嘘は滑らかだった。
兵は顔をしかめ、灰を払うように手を振った。
「……こんな天気じゃ、見分けもつかん。
とっとと通れ。だが、塔の方へは近づくな。封鎖中だ」
「承知している」
アーレンは軽く頭を下げ、
リュミナの肩を押して門をくぐった。
石畳を踏む瞬間、
リュミナが小さく息を呑む。
「ねえ……ここ、音がする」
彼女の声は震えていた。
「どんな音だ?」
「……たくさん。人の声。泣いてるみたい。
でも、どこからか分からない」
アーレンは彼女を見下ろし、
ほんの一瞬だけ目を細めた。
「街全体が、理の中にある。
塔の呼吸が、もう王都じゅうに届いてるんだ」
街の奥から、かすかに鐘の音が聞こえた。
それは警鐘でも祝福でもなく、
――まるで世界の心臓の鼓動のように、
灰色の空を震わせていた。
王都の街路は、灰に沈んでいた。
人々は屋根の下を歩き、外に出る者は少ない。
灯の符はちらつき、空気の流れがざらついている。
理の息づかいが、街そのものを満たしていた。
アーレンは裏通りを抜け、薄暗い路地に入った。
その突き当たりに、鉄の扉と古びた銘板がある。
錆びた文字には、こう刻まれていた。
《フェズ商館》
看板の意味を知らなければ、ただの倉庫のようだ。
だが、灰と理に関する資料を扱う密商――灰料屋(はいりょうや)としては、
王都でもよく知られた名だった。
扉を開けると、冷たい空気と古紙の匂いが流れ出た。
天井の低い部屋の中、所狭しと本と道具が並んでいる。
机の奥から、声がした。
「……めずらしい客だな。
こんな日に、外を歩ける物好きがいるとは」
出てきたのは、灰を被った外套を着た中年の男。
髪は乱れ、眼鏡の奥の目が妙に鋭い。
彼が、エリン・フェズだった。
「噂は聞いてる。学院から落ちた男が帰ってきたってな。
まさか、本当に来るとは思わなかったよ」
アーレンは短く息をつき、帽子の影から顔を上げた。
「俺の名前を出すな。聞かれたら厄介だ」
「安心しろ、口より紙の方が信用できる性分でな。
……で、何を探してる?」
「灰核理論の初期記録。塔が動く前の、最初の研究資料だ」
「物騒なもんを。
あんた、死にに来たのか、それともまだ生きて学びたいのか?」
皮肉にアーレンは笑わなかった。
代わりに、懐から一枚の符を差し出す。
符面に描かれた印は、学院時代の彼の個人符――その信頼印だった。
「これで足りるはずだ」
フェズは目を細め、それを一瞥してから受け取る。
「足りるどころか、久々に燃える話だ。
……ついて来い。下に、面白いものがある」
⸻
半地下の倉庫は、光がほとんど届かない。
壁に埋め込まれた小さな符灯が、弱々しい橙色の光を放っていた。
棚の上には灰の壺や古い装置が並び、
その中には、かすかに理の光を帯びた本が一冊置かれていた。
「これは……」
「灰化記録だ。百年以上前、塔の礎が築かれる前に書かれたもの。
ただし、読むな。目が焼ける」
「忠告ありがとう」
アーレンは本を手に取った。
表紙は灰の膜で覆われ、指先が触れると、微かに反応して震える。
その脈動は――人の鼓動のようだった。
「ねえ、アーレン」
背後からリュミナが囁く。
「この本、音がする」
「聞こえるのか?」
「うん。……中で、だれかが呼んでる」
フェズがその言葉に眉をひそめた。
「……“聞こえる”とは、どういう意味だ?」
「彼女は理を感じ取れる。説明は後だ」
アーレンは短く返し、慎重に本を開いた。
頁の中央に、灰色の紋章が浮かび上がる。
そしてその下に、一文だけ、手書きの記録があった。
『理の模倣体、試験体ルーメン。
灰化後、残響を確認。
“わたしはまだここにいる”』
アーレンは息をのんだ。
ルーメン――その名が、リュミナの名とわずかに響きを重ねる。
偶然ではない。
これは、同じ理の系統――“前の失敗作”だ。
「……やはり、最初から繋がっていたのか」
アーレンの声が震えた。
リュミナはそっとアーレンの袖を掴む。
「アーレン。わたし、その名前……知ってる気がする」
フェズが息を呑んだ。
「まさか……まさか、君……」
だが言葉は途中で止まった。
上階から、足音が響いた。
重く、固い靴音。
符を叩く金属音が混じっている。
アーレンは顔を上げた。
「――学院の連中だ」
足音が階段を下りてくる。
規則的で、ためらいのない音。
鍛えられた者の歩き方だった。
フェズは灯を消し、灰の帳簿を抱えた。
「アーレン、上だ。裏口は階段の奥、右の棚の影だ」
「おまえは?」
「ここで足止めする。見つかったら、俺の方が疑われる」
アーレンはためらったが、フェズの目がそれを許さなかった。
「俺の本に触れたんだ。
もう関係者だ。行け、灰に喰われる前にな」
アーレンは短く頷き、リュミナの手を取った。
「行くぞ」
棚を押すと、軋んだ音とともに壁が開いた。
狭い通路の奥に、崩れかけた石階段が続いている。
灰の粒がふわりと舞い、光を受けて白くきらめいた。
その背後で、扉が開く音。
誰かが地面を踏む。
硬い靴の底に灰が潰される音が、ゆっくりと近づいてくる。
⸻
「フェズ・エリン。学院の命令だ。
おまえが“塔の理資料”を隠していると聞いた」
声は冷たく、感情がない。
複数の足音が床を渡る。
灰の光を受け、黒い外套に刻まれた紋章がかすかに輝く。
――灰の犬。
学院直属の影部隊。
その名を聞いたことのある者は、ほとんどが二度と口にしなかった。
「知らんね。俺は商人だ。売る相手を選ぶ義理もない」
「……ここに、男と少女が入ったと報告がある」
「見間違いだろう。灰のせいで何もかも霞んで見える」
刹那、空気が軋んだ。
灰の犬の一人が手をかざす。
符の陣が浮かび、灰が渦を巻く。
フェズは舌打ちした。
「――やれやれ、これだから学院は嫌いだ」
彼は机を蹴り、灰の壺を割った。
中から立ち上がったのは、灰に混じる理の光。
封じられた符が弾け、煙のように部屋を包む。
「リュミナ、走れ!」
アーレンの声が通路に響く。
⸻
狭い通路を抜けると、裏路地へと出た。
灰が吹き溜まり、石畳が白く染まっている。
リュミナは息を切らしながらも、手を離さない。
「アーレン、後ろ!」
振り返ると、通路の奥で光が弾けた。
灰の犬の一人が符を放ったのだ。
光は灰に吸われ、空気が一瞬ひずむ。
アーレンは腰の符袋を開き、反射的に印を描いた。
防壁符が発動し、灰が固まって壁となる。
音もなく光を受け止め、空間が沈黙した。
衝撃の余波が消えると、壁は粉のように崩れた。
リュミナの頬に灰がかかる。
その灰が淡く光り、肌の上で溶けた。
「……やっぱり、わたし、灰の中で生きてる」
「今はそのおかげで助かってる」
アーレンはリュミナの手を握り、
灰の降る路地を走り出した。
⸻
そのころ、店の奥ではフェズが灰の犬に囲まれていた。
彼の手には、一枚の符が握られている。
その符の中央には、ひとつの短い言葉が刻まれていた。
――“観測者”。
灰の光が彼の身体を包む。
そして、爆ぜた。
店全体が灰に飲まれ、外へ吹き出す。
その瞬間、王都の一角で、灰の塔の光が一段と強くなった。
⸻
遠く離れた路地の影で、アーレンは振り返った。
灰の雨が強まっている。
リュミナの瞳が、塔の方を見つめていた。
「……塔が、また呼んでる」
「わかってる。だが、今は行けない。
まずは身を隠す。王都の理が完全に暴れ出す前に」
風が吹き、灰が二人の影をかすめた。
静かな灰の粒が落ちるたび、
まるで世界そのものが新しい形を探しているかのようだった。
0
あなたにおすすめの小説

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する
namisan
ファンタジー
数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。
転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。
しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。
凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。
詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。
それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。
「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」
前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。
痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。
そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。
これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!

【完結】ご都合主義で生きてます。-商売の力で世界を変える。カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく-
ジェルミ
ファンタジー
28歳でこの世を去った佐藤は、異世界の女神により転移を誘われる。
その条件として女神に『面白楽しく生活でき、苦労をせずお金を稼いで生きていくスキルがほしい』と無理難題を言うのだった。
困った女神が授けたのは、想像した事を実現できる創生魔法だった。
この味気ない世界を、創生魔法とカスタマイズ可能なストレージを使い、美味しくなる調味料や料理を作り世界を変えて行く。
はい、ご注文は?
調味料、それとも武器ですか?
カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく。
村を開拓し仲間を集め国を巻き込む産業を起こす。
いずれは世界へ通じる道を繋げるために。
※本作はカクヨム様にも掲載しております。

正しい聖女さまのつくりかた
みるくてぃー
ファンタジー
王家で育てられた(自称)平民少女が、学園で起こすハチャメチャ学園(ラブ?)コメディ。
同じ年の第二王女をはじめ、優しい兄姉(第一王女と王子)に見守られながら成長していく。
一般常識が一切通用しない少女に友人達は振り回されてばかり、「アリスちゃんメイドを目指すのになぜダンスや淑女教育が必要なの!?」
そこには人知れず王妃と王女達によるとある計画が進められていた!
果たしてアリスは無事に立派なメイドになれるのか!? たぶん無理かなぁ……。
聖女シリーズ第一弾「正しい聖女さまのつくりかた」
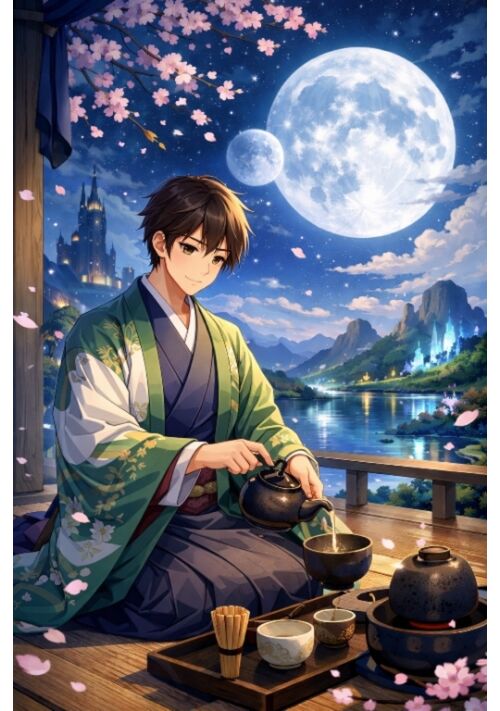
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

異世界転移物語
月夜
ファンタジー
このところ、日本各地で謎の地震が頻発していた。そんなある日、都内の大学に通う僕(田所健太)は、地震が起こったときのために、部屋で非常持出袋を整理していた。すると、突然、めまいに襲われ、次に気づいたときは、深い森の中に迷い込んでいたのだ……

【完結】異世界で神の元カノのゴミ屋敷を片付けたら世界の秘密が出てきました
小豆缶
ファンタジー
父の遺したゴミ屋敷を片付けていたはずが、気づけば異世界に転移していた私・飛鳥。
しかも、神の元カノと顔がそっくりという理由で、いきなり死刑寸前!?
助けてくれた太陽神ソラリクスから頼まれた仕事は、
「500年前に別れた元恋人のゴミ屋敷を片付けてほしい」というとんでもない依頼だった。
幽霊になった元神、罠だらけの屋敷、歪んだ世界のシステム。
ポンコツだけど諦めの悪い主人公が、ゴミ屋敷を片付けながら異世界の謎を暴いていく!
ほのぼのお仕事×異世界コメディ×世界の秘密解明ファンタジー

第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















