8 / 27
第一章 夏
第八話 アクシデント
しおりを挟む
突然のことに、魔法発動寸前だった俺の意識は右肩を掴んだ手に行った。
ところが魔法の方は既に何千回もしているために半ば無意識で実行してしまう。
いつも意識するのは一緒に召喚するあれやこれ。
結果、一緒に召喚するものを意識するべきところで肩に置かれた手を意識してしまった。
暗転した視界が戻った時、全身に酷い頼りなさを感じた。
何年も前に経験した感覚だ。
布越しだった誰かの手の感触は肌に直に感じられる。
下に目を向ければ、着ていた服は足の下。
可愛い息子もこんにちは。
少し後方まで視線を動かせば、明らかに俺のものではない服が床に落ちている。
頭を上げて恐る恐る振り返る。
有るのはポカンとしたホーリーの顔だ。
本能に逆らえずに視線を下げると、けしからんものが余すところ無くまろび出ている。
その下の臍も更にその下も全てが頼りないランプの光に浮かび上がり、あるいは翳る。
色々と危険であった。
しかし、無意識にゴクリと唾を呑み込んでしまった。
その音に反応したようにホーリーが目を瞬かせる。
「今のは何だったのだ……?」
問うでもない問いを発したホーリーがやっと違和感に気付いたのか視線を下げる。
「ああ……あっ!」
見る間に顔を赤くして、手を俺の肩から離して振り上げた。
「にああああっ!」
叫ぶその手が仄かに光る。
やばい。
魔法を放たれては家がめちゃくちゃだ。
俺は自分でもどうしてできたのか不思議なくらい俊敏に動いた。
「待て!」
俺は振り向きざまにホーリーへと全力で飛び掛かり、ホーリーの光る右手を左手で掴む。
そのまま勢い余ってホーリーに身体を浴びせかけた。
さしものホーリーも咄嗟のことで踏ん張り切れなかったらしく、身体を後ろに傾げさせてそのまま倒れていく。
その途中で右手の光が霧散する。
魔法が放たれずに済んだことに安堵しつつ、俺はホーリーと絡み合うように倒れ込んだ。
ドタンと盛大な音が木霊した後の暫しの静寂。
唇と右手が柔らかい何かに触れている。
無意識に目を瞑っていたことでその正体不明の柔らかさが鮮明に感じられた。
んんーと鼻が鳴る音で目を瞑っていることを自覚し、開けるとホーリーの顔が目前だった。
目には涙が浮かんでいる。
慌てて上体を起こす。
その際に手で踏ん張ったせいで右手のふにょんと柔らかい感触がより強くなった。
けしからんものを揉んでいた。
それが判って離さねばと思うが手が離れない。
「にあああん!」
「お嬢様! ご無事でございますか!?」
ホーリーの叫びに被さるように響いたのはペッテの声だ。
駆け込んで来たその身体は全身泡だらけであった。
俺がホーリーを押し倒しているとしか見えない光景にペッテが暫し硬直する。
「な、何をなさってらっしゃるのでございますか?」
仰け反り、首まで上げた右手をわなわなと震わせながらペッテは言った。
焦る俺。
「こ、これは……」
どうにかして誤魔化さなければとばかり考えるが、何も思い浮かばない。
右手を至福の感触から離したくない本能も交錯して身動きができない。
その間にもペッテの身体にまとわりついていた泡が流れ落ち、着痩せする肢体が露わになってゆく。
その艶めかしさにまた目が離せない。
「馬鹿者……」
声に導かれるように下を向くと、ホーリーが涙目で睨んでいた。
背筋が冷えた。
「わわ! ご、ごめん!」
慌ててホーリーの上から飛び退いた拍子に尻餅を搗いた。
目に入るのは可愛かった息子の猛々しくも雄々しいい姿。
刹那で隠す。
「馬鹿者! そんな不気味なものまで見せられたらもうお嫁に行けないではないか!」
「ええ!?」
問題はそこなのか?
「全身の肌を見られ、む、胸を揉まれ、あ、あまつさえ、く、唇まで奪われた上にそのようなものを!」
睨み付けてくるホーリーの目からは、見る間に涙がだだ漏りになる。
やばいと思った時にはもう遅かった。
「びえええええぇっ!」
両手をだらんと下げ、上を向いてわんわん泣いた。
すかさずペッテがその頭を抱き締めて「よしよし」と撫でる。
そして俺をキッと睨み付けてくる。
多分。
眉を寄せて俺が視界に入る程度に顔をこちらに向けているから多分そう。
糸目だから真偽が判らない。
しかし、美少女を泣かせたとあっては良心が痛むのもまた事実だ。
「泣くな! もし貰い手が居なかったら俺が貰ってやる!」
本能的に俺は叫んでいた。
効果覿面。
ホーリーの泣き声がピタリと止んだ。
急速に子猫ちゃんになった息子が俺の頭を冷やしていく。
猛るにも子猫になるにもどうしても時間差があるのだ。
その少し冷えた頭で考えても、今のでどうしてホーリーが泣き止むのかがさっぱり判らない。
むしろ身分違いと怒り狂うような場面ではないだろうか。
ところがホーリーはペッテの胸に埋めていた顔を少し持ち上げてチラリチラリと俺へと視線を投げかけてくる。
俺を見る時に寄っていたペッテの眉も元の位置へと戻っている。
「今のお言葉に相違ございませんか?」
ペッテが少し低い声で問い掛けて来た。
怒っているのだろうか。
「いや、その……」
「お嬢様を娶ると仰ったのは詐りだったのでございますか?」
「いえ、そんなつもりは……」
俺はしどろもどろだ。
俺がホーリーを養うのは無理な話で、逆に養われることにしかならない。
しかしペッテは容赦してくれないらしい。
無表情なのに妙に圧迫感が有る。
「娶る気がお有りかお有りでないかはっきりしてくださいませ」
「有ります。
有ります。
娶らせていただきます」
圧迫感に堪えかねてしまったが、こんな人が良さそうな美少女なら娶るのも吝かではない。
「そうでございますか」
ペッテが口角を持ち上げ、ホーリーの目元に残る涙を拭う。
そして少し弾んだ口調で言う。
「お嬢様、キープ君ゲットでございますよ」
「うん」
返事をしたホーリーが「えへへー」と笑う。
どうしてそこで喜ぶ?
「待ってくれ。
俺だとヒモにしかなないぞ? それでいいのか?」
またペッテにジトッと見られた気がしたが、やっぱり糸目で判らない。
「それにお答えする前に、いつまで不躾にお嬢様の肌をご覧になられているのでございますか?」
「ご、ごめん」
後ろ髪を引かれながらも、あたふたと半回転した。
「とにかく、身形を整えてからお話しをいたしましょう」
「う、うん」
俺は同意して、目の前に有るホーリーの服を後ろへと送った。
ホーリーが服を着け、ペッテと共に部屋を出てから俺は動き出した。
服を着て居間に行くだけのことだ。
居間ではホーリーが既に待っていて、未だににへらと笑いを浮かべている。
何がそんなに嬉しいのだろうかと疑問に思いつつ、俺はホーリーの向かいの席に着く。
するとそれに合わせたかのようにペッテが階下から上がって来た。
ペッテが座るのはホーリーの横だ。
「それでは何故お二人がふしだらな行為に及んでいたのかをご説明くださいませ」
何となく感じる圧迫感からペッテが俺を睨んでいるのだろうとは思うのだが、やはり糸目で真偽が判らない。
ペッテについてはもう直感を頼るしかないのだと断定せざるを得ない。
それはともかくとして質問には答えにくい。
どう転んでも魔法に言及しなくては説明のしようがない。
しかしながら、現象だけを語れば良いホーリーは無邪気なものだ。
「不思議だったのだ。
ノックをしても返事が無かったので部屋に入ったら、ぼんやりと立っているシモンが居るではないか。
だから肩を掴んで呼びかけようとしたのだ。
その時シモンが振り返ったと思ったら急に目の前が真っ暗になって、また見えるようになった時には裸で立っていた」
ただ、ここまでで説明を終えようとした。
その後の経緯を思い出したのだろう。
瞳が揺れた。
そしてその不自然を見逃すペッテではなかった。
「真っ暗でございますか? それはそれで後ほど訊ねさせていただきますが、それだけでございましたらあのようにはならないでございましょう?」
ホーリーの額から汗が滴る。
その先を話せば叱られるのが必至だ。
更にその先を話せば俺も叱られそうだが、話さなければきっとペッテは納得しない。
そしてその次は俺の魔法が追及される。
こうなっては俺の魔法を二人に隠し続けるのも難しく、少し心苦しくもある。
こんな僅かな期間で情が湧いたと言ったら陳腐だろうか。
「判った。
最初から話す」
俺は俺の魔法について二人に話すことにした。
俺の魔法は俺以外も一緒に召喚できると言っても、好きなものを好きなだけとはいかない。
魔力に依存して量的な上限が有るのだ。
つまり、ホーリーを一緒に召喚するだけでその上限に達し、他の一切が召喚できなかったのである。
そしてそれがそもそもの原因になったと言うことも含めて、二人に召喚魔法について話をした。
「それではシモン様は致命傷をお受けになられたのでございますか?」
俺が頷くと、ペッテはホーリーへと顔を向けた。
その額にははっきりとした青筋。
一方のホーリーは目を強く瞑って脳天を隠すように頭を抱える。
「ポンコツ様、お手をおどけくださいませ」
「嫌だ! グリグリするつもりなのだろう? あれは痛いのだ!」
「痛くしているのでございます」
従者が主人にお仕置きするのもよく判らない関係である。
「いつもしているように聞こえるんだが?」
俺の問いで今することではないと思い直したのか、ペッテは「後で覚悟してくださいませ」とホーリーに言い含めてから俺へと向き直った。
「婚姻の件と通じるのでございます」
ホーリーは似たようなことを過去に二度起こしたと言う。
いずれも婚約者で、命を落とすには至らなかったものの重傷を負わせた。
その一方は重篤に至り、第三王女ナイチアビーナの回復魔法で漸く事なきを得るほどだ。
こうなるともう婚約者は現れず、一生独身で過ごすのがほぼ確実となった。
お嫁さんになるのが野望の一つだと言うホーリーにはどうにも辛いものらしい。
そしてもしも俺が俺でなかったなら、王女でも庇えないところで、いよいよ絶望的。
それだけでなく人生も絶望的になるところであったのだとか。
「それでも俺だと志が低すぎないか?」
「贅沢は敵でございます」
「うむ。
お嫁さんの前には身分など取るに足らないのだ」
おいおい。
◆
お互いに理由が判ったところで今日は寝ることにした。
その前に俺は失敗したに等しい召喚のし直しだ。
意識を集中して送還する。
暗転。
また全身の心許ない感覚。
そして肩に感じる誰かの手。
恐る恐る振り向けば、ポカンとしたホーリーの顔が有った。
少し下に視線を動かせば、けしからんものがこんにちは。
「にああああっ!」
ホーリーの悲鳴が夜の巷に轟いた。
ところが魔法の方は既に何千回もしているために半ば無意識で実行してしまう。
いつも意識するのは一緒に召喚するあれやこれ。
結果、一緒に召喚するものを意識するべきところで肩に置かれた手を意識してしまった。
暗転した視界が戻った時、全身に酷い頼りなさを感じた。
何年も前に経験した感覚だ。
布越しだった誰かの手の感触は肌に直に感じられる。
下に目を向ければ、着ていた服は足の下。
可愛い息子もこんにちは。
少し後方まで視線を動かせば、明らかに俺のものではない服が床に落ちている。
頭を上げて恐る恐る振り返る。
有るのはポカンとしたホーリーの顔だ。
本能に逆らえずに視線を下げると、けしからんものが余すところ無くまろび出ている。
その下の臍も更にその下も全てが頼りないランプの光に浮かび上がり、あるいは翳る。
色々と危険であった。
しかし、無意識にゴクリと唾を呑み込んでしまった。
その音に反応したようにホーリーが目を瞬かせる。
「今のは何だったのだ……?」
問うでもない問いを発したホーリーがやっと違和感に気付いたのか視線を下げる。
「ああ……あっ!」
見る間に顔を赤くして、手を俺の肩から離して振り上げた。
「にああああっ!」
叫ぶその手が仄かに光る。
やばい。
魔法を放たれては家がめちゃくちゃだ。
俺は自分でもどうしてできたのか不思議なくらい俊敏に動いた。
「待て!」
俺は振り向きざまにホーリーへと全力で飛び掛かり、ホーリーの光る右手を左手で掴む。
そのまま勢い余ってホーリーに身体を浴びせかけた。
さしものホーリーも咄嗟のことで踏ん張り切れなかったらしく、身体を後ろに傾げさせてそのまま倒れていく。
その途中で右手の光が霧散する。
魔法が放たれずに済んだことに安堵しつつ、俺はホーリーと絡み合うように倒れ込んだ。
ドタンと盛大な音が木霊した後の暫しの静寂。
唇と右手が柔らかい何かに触れている。
無意識に目を瞑っていたことでその正体不明の柔らかさが鮮明に感じられた。
んんーと鼻が鳴る音で目を瞑っていることを自覚し、開けるとホーリーの顔が目前だった。
目には涙が浮かんでいる。
慌てて上体を起こす。
その際に手で踏ん張ったせいで右手のふにょんと柔らかい感触がより強くなった。
けしからんものを揉んでいた。
それが判って離さねばと思うが手が離れない。
「にあああん!」
「お嬢様! ご無事でございますか!?」
ホーリーの叫びに被さるように響いたのはペッテの声だ。
駆け込んで来たその身体は全身泡だらけであった。
俺がホーリーを押し倒しているとしか見えない光景にペッテが暫し硬直する。
「な、何をなさってらっしゃるのでございますか?」
仰け反り、首まで上げた右手をわなわなと震わせながらペッテは言った。
焦る俺。
「こ、これは……」
どうにかして誤魔化さなければとばかり考えるが、何も思い浮かばない。
右手を至福の感触から離したくない本能も交錯して身動きができない。
その間にもペッテの身体にまとわりついていた泡が流れ落ち、着痩せする肢体が露わになってゆく。
その艶めかしさにまた目が離せない。
「馬鹿者……」
声に導かれるように下を向くと、ホーリーが涙目で睨んでいた。
背筋が冷えた。
「わわ! ご、ごめん!」
慌ててホーリーの上から飛び退いた拍子に尻餅を搗いた。
目に入るのは可愛かった息子の猛々しくも雄々しいい姿。
刹那で隠す。
「馬鹿者! そんな不気味なものまで見せられたらもうお嫁に行けないではないか!」
「ええ!?」
問題はそこなのか?
「全身の肌を見られ、む、胸を揉まれ、あ、あまつさえ、く、唇まで奪われた上にそのようなものを!」
睨み付けてくるホーリーの目からは、見る間に涙がだだ漏りになる。
やばいと思った時にはもう遅かった。
「びえええええぇっ!」
両手をだらんと下げ、上を向いてわんわん泣いた。
すかさずペッテがその頭を抱き締めて「よしよし」と撫でる。
そして俺をキッと睨み付けてくる。
多分。
眉を寄せて俺が視界に入る程度に顔をこちらに向けているから多分そう。
糸目だから真偽が判らない。
しかし、美少女を泣かせたとあっては良心が痛むのもまた事実だ。
「泣くな! もし貰い手が居なかったら俺が貰ってやる!」
本能的に俺は叫んでいた。
効果覿面。
ホーリーの泣き声がピタリと止んだ。
急速に子猫ちゃんになった息子が俺の頭を冷やしていく。
猛るにも子猫になるにもどうしても時間差があるのだ。
その少し冷えた頭で考えても、今のでどうしてホーリーが泣き止むのかがさっぱり判らない。
むしろ身分違いと怒り狂うような場面ではないだろうか。
ところがホーリーはペッテの胸に埋めていた顔を少し持ち上げてチラリチラリと俺へと視線を投げかけてくる。
俺を見る時に寄っていたペッテの眉も元の位置へと戻っている。
「今のお言葉に相違ございませんか?」
ペッテが少し低い声で問い掛けて来た。
怒っているのだろうか。
「いや、その……」
「お嬢様を娶ると仰ったのは詐りだったのでございますか?」
「いえ、そんなつもりは……」
俺はしどろもどろだ。
俺がホーリーを養うのは無理な話で、逆に養われることにしかならない。
しかしペッテは容赦してくれないらしい。
無表情なのに妙に圧迫感が有る。
「娶る気がお有りかお有りでないかはっきりしてくださいませ」
「有ります。
有ります。
娶らせていただきます」
圧迫感に堪えかねてしまったが、こんな人が良さそうな美少女なら娶るのも吝かではない。
「そうでございますか」
ペッテが口角を持ち上げ、ホーリーの目元に残る涙を拭う。
そして少し弾んだ口調で言う。
「お嬢様、キープ君ゲットでございますよ」
「うん」
返事をしたホーリーが「えへへー」と笑う。
どうしてそこで喜ぶ?
「待ってくれ。
俺だとヒモにしかなないぞ? それでいいのか?」
またペッテにジトッと見られた気がしたが、やっぱり糸目で判らない。
「それにお答えする前に、いつまで不躾にお嬢様の肌をご覧になられているのでございますか?」
「ご、ごめん」
後ろ髪を引かれながらも、あたふたと半回転した。
「とにかく、身形を整えてからお話しをいたしましょう」
「う、うん」
俺は同意して、目の前に有るホーリーの服を後ろへと送った。
ホーリーが服を着け、ペッテと共に部屋を出てから俺は動き出した。
服を着て居間に行くだけのことだ。
居間ではホーリーが既に待っていて、未だににへらと笑いを浮かべている。
何がそんなに嬉しいのだろうかと疑問に思いつつ、俺はホーリーの向かいの席に着く。
するとそれに合わせたかのようにペッテが階下から上がって来た。
ペッテが座るのはホーリーの横だ。
「それでは何故お二人がふしだらな行為に及んでいたのかをご説明くださいませ」
何となく感じる圧迫感からペッテが俺を睨んでいるのだろうとは思うのだが、やはり糸目で真偽が判らない。
ペッテについてはもう直感を頼るしかないのだと断定せざるを得ない。
それはともかくとして質問には答えにくい。
どう転んでも魔法に言及しなくては説明のしようがない。
しかしながら、現象だけを語れば良いホーリーは無邪気なものだ。
「不思議だったのだ。
ノックをしても返事が無かったので部屋に入ったら、ぼんやりと立っているシモンが居るではないか。
だから肩を掴んで呼びかけようとしたのだ。
その時シモンが振り返ったと思ったら急に目の前が真っ暗になって、また見えるようになった時には裸で立っていた」
ただ、ここまでで説明を終えようとした。
その後の経緯を思い出したのだろう。
瞳が揺れた。
そしてその不自然を見逃すペッテではなかった。
「真っ暗でございますか? それはそれで後ほど訊ねさせていただきますが、それだけでございましたらあのようにはならないでございましょう?」
ホーリーの額から汗が滴る。
その先を話せば叱られるのが必至だ。
更にその先を話せば俺も叱られそうだが、話さなければきっとペッテは納得しない。
そしてその次は俺の魔法が追及される。
こうなっては俺の魔法を二人に隠し続けるのも難しく、少し心苦しくもある。
こんな僅かな期間で情が湧いたと言ったら陳腐だろうか。
「判った。
最初から話す」
俺は俺の魔法について二人に話すことにした。
俺の魔法は俺以外も一緒に召喚できると言っても、好きなものを好きなだけとはいかない。
魔力に依存して量的な上限が有るのだ。
つまり、ホーリーを一緒に召喚するだけでその上限に達し、他の一切が召喚できなかったのである。
そしてそれがそもそもの原因になったと言うことも含めて、二人に召喚魔法について話をした。
「それではシモン様は致命傷をお受けになられたのでございますか?」
俺が頷くと、ペッテはホーリーへと顔を向けた。
その額にははっきりとした青筋。
一方のホーリーは目を強く瞑って脳天を隠すように頭を抱える。
「ポンコツ様、お手をおどけくださいませ」
「嫌だ! グリグリするつもりなのだろう? あれは痛いのだ!」
「痛くしているのでございます」
従者が主人にお仕置きするのもよく判らない関係である。
「いつもしているように聞こえるんだが?」
俺の問いで今することではないと思い直したのか、ペッテは「後で覚悟してくださいませ」とホーリーに言い含めてから俺へと向き直った。
「婚姻の件と通じるのでございます」
ホーリーは似たようなことを過去に二度起こしたと言う。
いずれも婚約者で、命を落とすには至らなかったものの重傷を負わせた。
その一方は重篤に至り、第三王女ナイチアビーナの回復魔法で漸く事なきを得るほどだ。
こうなるともう婚約者は現れず、一生独身で過ごすのがほぼ確実となった。
お嫁さんになるのが野望の一つだと言うホーリーにはどうにも辛いものらしい。
そしてもしも俺が俺でなかったなら、王女でも庇えないところで、いよいよ絶望的。
それだけでなく人生も絶望的になるところであったのだとか。
「それでも俺だと志が低すぎないか?」
「贅沢は敵でございます」
「うむ。
お嫁さんの前には身分など取るに足らないのだ」
おいおい。
◆
お互いに理由が判ったところで今日は寝ることにした。
その前に俺は失敗したに等しい召喚のし直しだ。
意識を集中して送還する。
暗転。
また全身の心許ない感覚。
そして肩に感じる誰かの手。
恐る恐る振り向けば、ポカンとしたホーリーの顔が有った。
少し下に視線を動かせば、けしからんものがこんにちは。
「にああああっ!」
ホーリーの悲鳴が夜の巷に轟いた。
0
あなたにおすすめの小説

【最強モブの努力無双】~ゲームで名前も登場しないようなモブに転生したオレ、一途な努力とゲーム知識で最強になる~
くーねるでぶる(戒め)
ファンタジー
アベル・ヴィアラットは、五歳の時、ベッドから転げ落ちてその拍子に前世の記憶を思い出した。
大人気ゲーム『ヒーローズ・ジャーニー』の世界に転生したアベルは、ゲームの知識を使って全男の子の憧れである“最強”になることを決意する。
そのために努力を続け、順調に強くなっていくアベル。
しかしこの世界にはゲームには無かった知識ばかり。
戦闘もただスキルをブッパすればいいだけのゲームとはまったく違っていた。
「面白いじゃん?」
アベルはめげることなく、辺境最強の父と優しい母に見守られてすくすくと成長していくのだった。

役立たずと言われダンジョンで殺されかけたが、実は最強で万能スキルでした !
本条蒼依
ファンタジー
地球とは違う異世界シンアースでの物語。
主人公マルクは神聖の儀で何にも反応しないスキルを貰い、絶望の淵へと叩き込まれる。
その役に立たないスキルで冒険者になるが、役立たずと言われダンジョンで殺されかけるが、そのスキルは唯一無二の万能スキルだった。
そのスキルで成り上がり、ダンジョンで裏切った人間は落ちぶれざまあ展開。
主人公マルクは、そのスキルで色んなことを解決し幸せになる。
ハーレム要素はしばらくありません。

【完結】うさぎ転生 〜女子高生の私、交通事故で死んだと思ったら、気づけば現代ダンジョンの最弱モンスターに!?最強目指して生き延びる〜
旅する書斎(☆ほしい)
ファンタジー
女子高生の篠崎カレンは、交通事故に遭って命を落とした……はずが、目覚めるとそこはモンスターあふれる現代ダンジョン。しかも身体はウサギになっていた!
HPはわずか5、攻撃力もゼロに等しい「最弱モンスター」扱いの白うさぎ。それでもスライムやコボルトにおびえながら、なんとか生き延びる日々。唯一の救いは、ダンジョン特有の“スキル”を磨けば強くなれるということ。
跳躍蹴りでスライムを倒し、小動物の悲鳴でコボルトを怯ませ、少しずつ経験値を積んでいくうちに、カレンは手応えを感じ始める。
「このままじゃ終わらない。私、もっと強くなっていつか……」
最弱からの“首刈りウサギ”進化を目指して、ウサギの身体で奮闘するカレン。彼女はこの危険だらけのダンジョンで、生き延びるだけでなく“人間へ戻る術(すべ)”を探し当てられるのか? それとも新たなモンスターとしての道を歩むのか?最弱うさぎの成り上がりサバイバルが、いま幕を開ける!
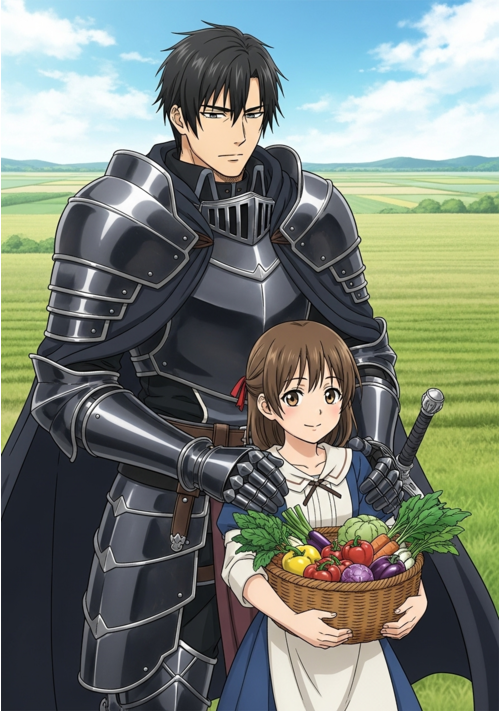
婚約破棄&濡れ衣で追放された聖女ですが、辺境で育成スキルの真価を発揮!無骨で不器用な最強騎士様からの溺愛が止まりません!
黒崎隼人
ファンタジー
「君は偽りの聖女だ」――。
地味な「育成」の力しか持たない伯爵令嬢エルナは、婚約者である王太子にそう断じられ、すべてを奪われた。聖女の地位、婚約者、そして濡れ衣を着せられ追放された先は、魔物が巣食う極寒の辺境の地。
しかし、絶望の淵で彼女は自身の力の本当の価値を知る。凍てついた大地を緑豊かな楽園へと変える「育成」の力。それは、飢えた人々の心と体を癒す、真の聖女の奇跡だった。
これは、役立たずと蔑まれた少女が、無骨で不器用な「氷壁の騎士」ガイオンの揺るぎない愛に支えられ、辺境の地でかけがえのない居場所と幸せを見つける、心温まる逆転スローライフ・ファンタジー。
王都が彼女の真価に気づいた時、もう遅い。最高のざまぁと、とろけるほど甘い溺愛が、ここにある。

アルフレッドは平穏に過ごしたい 〜追放されたけど謎のスキル【合成】で生き抜く〜
芍薬甘草湯
ファンタジー
アルフレッドは貴族の令息であったが天から与えられたスキルと家風の違いで追放される。平民となり冒険者となったが、生活するために竜騎士隊でアルバイトをすることに。
ふとした事でスキルが発動。
使えないスキルではない事に気付いたアルフレッドは様々なものを合成しながら密かに活躍していく。
⭐︎注意⭐︎
女性が多く出てくるため、ハーレム要素がほんの少しあります。特に苦手な方はご遠慮ください。

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる
竜頭蛇
ファンタジー
ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。
評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。
身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

転生貴族の移動領地~家族から見捨てられた三子の俺、万能な【スライド】スキルで最強領地とともに旅をする~
名無し
ファンタジー
とある男爵の三子として転生した主人公スラン。美しい海辺の辺境で暮らしていたが、海賊やモンスターを寄せ付けなかった頼りの父が倒れ、意識不明に陥ってしまう。兄姉もまた、スランの得たスキル【スライド】が外れと見るや、彼を見捨ててライバル貴族に寝返る。だが、そこから【スライド】スキルの真価を知ったスランの逆襲が始まるのであった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















