15 / 27
第二章 秋
第一五話 鉄杭
しおりを挟む
翌朝、メーアの愁いを含んだ瞳に見送られて宿を出た。
「で、鉄杭とロープをどう使うんだ?」
立て看板の奥、洞窟の壁がつるつるになる直前で立ち止まったホーリーに尋ねた。
「それを使うのはもう少し後だ」
ホーリーがおもむろに手を翳して魔法を放つと、薄暗い中を光球が前方の地面へと眩しいばかりの軌跡を描く。
すると、魔法の当たった床が一瞬で融けて煮えたぎった。
俺はあんなのを食らったのか……。
「ここはまだのようだな」
「まだって何が?」
ホーリーは独り納得しているが、俺は「求む説明」だ。
ところがホーリーはきょとんと俺を見て眼をパチクリさせる。
「落とし穴を先に空けてしまえば掛からずに済むだろう?」
「おう……」
確かにそうだが、ここまでの力業ができると誰が想像できようか。
ただ、目の前で見せられたことで、やろうとしていることは解った。
今し方の地面は熔岩が溜まったままになっていて、地面の下に空洞が無いのが見て取れる。
もしも落とし穴が有れば熔岩が下に落ちて空洞が覗く筈だ。
ホーリーが次々に魔法を放って溶岩溜まりを作る。
無造作に続けていることに疑問を感じる。
「そんなに魔法を連発して疲れないのか?」
「この程度、歩くくらいのものなのだ」
「そうなのか……」
魔法を使うと疲労するが、個人差が激しいために、どの程度疲れるのか傍目には判らない。
だから脚の疲れで喩えるのだ。
歩く程度、駆け足程度、全力疾走程度くらいの区別しかできないが、目安さえ判れば良い。
力の籠め方も疲れ方も相応との意味で、歩く程度なら少々使い続けても平気だと言うことになる。
つまり、俺にとってはでたらめにも見える魔法でも、ホーリー本人にとっては何でもないのであった。
「これ程の魔法ならホーリーは剣がいらなくないか?」
ホーリーが信じられないと顔に書いて反論する。
「何を言うのだ。
魔法では相手が死んでしまうではないか」
「いや、どうせ……」
魔物は殺すだろうと言い掛けて気付いた。
歩く程度でこの威力なら、極力威力を絞っても手足の一本くらいは消し炭になる。
「そうか、人相手には使えないんだな」
ホーリーが大きく頷いた。
譬え相手が犯罪者だったとしても、無闇に命に関わる傷を負わせる訳にはいかないのだった。
それが尋問のためだったとしても。
疑問も解消したところで探索の再開。
ホーリーが魔法で地面に溶岩溜まりを作りつつ進む。
最初の曲がり角を左に曲がって少しの所で変化が有った。
溶岩溜まりが出来ない。
それを確認したホーリーがその穴を起点にして四角の輪郭を描くように魔法で穿つ。
そして輪郭を描き終わると、その内側が静かに落ちて行った。
ゴガンと落とし穴の蓋の一部だったものが底に激突して音を立てるが、ぼんやりとしたランプの光の下では判然としない。
結構な深さである。
ホーリーは続けて穴の手前側の際まで魔法で崩してしまう。
一緒に融かされたことで穴の縁の角が取れた。
それから穴から二歩ほど離れた場所を指差して言う。
「シモン、ここを融かすから鉄杭を差し込んで欲しいのだ」
「え!? それって危なくないか?」
「手早くやれば大丈夫なのだ」
「だったら手本を見せてくれ!」
「やだ」
「何で!?」
「だって熱いんだもん」
ホーリーが片頬を膨らませながらプイッとそっぽを向く。
「『もん』て……」
あざとい。
あざといぞ、ホーリー。
いつもと口調からして違う。
頬を膨らませた顔も仕草も可愛らしくて二の句が継げない。
絶対に自覚してやってると思うのに、ほいほい言うことを聞いてやりたくなる。
本当に美少女は狡い。
「解ったよ……」
一つ溜め息を吐いて答えた。
そもそも雇われていながら今日はここまで何もしていない俺の仕事だろう。
「頼むのだ」
ホーリーは一転良い笑顔をする。
これではもう文句を言おうにも言えない。
「狡いなぁ」と頭では考えながらも心はホーリーのために動こうとするのだから、我ながら度し難い。
俺が鉄杭を持って構えるのを待ってホーリーが魔法を放つ。
一瞬で地面が灼熱に融けた。
その溶岩溜まりに近付いて手を伸ばすが……。
「熱っ!」
一瞬で引っ込めた。
「早く挿さないと挿し難くなるのだ」
「そう言われても……」
想像以上に熱かったからどうしても躊躇する。
ところがホーリーが脇を締めて両腕を軽く広げ、両の拳を握って可愛く言う。
「頑張って!」
天然のハニートラップだと解っていても、どうにも抗い難いものがある。
勿論一生に関わるようなものだったりするなら話は別だが、今、目の前に有るものはそうではないし、僅かな時間で済むものだ。
美少女の期待に応えたい気持ちの方が強く出る。
意を決して再度灼熱に挑む。
既に冷めてきているようで先よりも熱くない。
鉄杭を突き刺す。
粘土に突き刺すような感覚だ。
なかなか刺さらないので力を籠めると、ずぶずぶと鉄杭は熔岩に埋もれて行く。
そして俺の腕の長さほどの鉄杭が刺さること概ね三分の一。
「あっつっ!」
鉄杭が焼けるように熱くなって刹那で手を放した。
火傷した。
焼けるようにではなく、焼けていたのだった。
「良くやったのだ、シモン。
これで暫く冷めるのを待つのだ」
親指を立てたホーリーの無邪気な賛辞を素直に受け取れないのは、きっと俺の心が煤けてるのだろう。
これから暫くの間、熔岩が冷えて固まって鉄杭が固定されるのを待つ。
「ホーリーはよくこんなのを思い付いたな」
ヒリヒリする手に息を吹き掛けながら尋ねた。
鉄杭をこう使うとは予想だにしていなかった。
目の前で見た後だからホーリーが「魔法で岩が融ける」と言っていたことと繋がるが、鉄杭を買い求める時点では全く繋がらなかった。
「最初に思い付いたのは殿下なのだ」
何でも、第三王女ナイチアビーナはある日、王宮の花壇に柵を作ろうと考えたらしい。
その際、支柱を立てる工事が遅遅として進まないことや、ゴンゴンと杭を打つ音が延延と続くことに業を煮やしたと言う。
たかが柵。
されど柵。
しっかりしたものを立てようとしたならそれなりに手間暇掛かるものなのだ。
職人達も王宮でやっつけ仕事などできよう筈がない。
地盤の固い部分では地面を穿孔して杭を打ち、緩い部分では大きく掘り起こして栗石を入れ、搗き固めて杭を固定してから埋め戻した。
これでは時間も掛かれば音も出る。
これを職人達から聞き取ったナイチアビーナが知恵を絞った訳だ。
ただ、この時の試みは失敗に終わったらしい。
木杭では燃えてしまい、鉄杭でも真っ直ぐ立てるのがほぼほぼ不可能だったため、柵の支柱としては使いものにならなかったのだ。
しかし早々に杭を垂直に挿す装置を考案し、職人に開発させた。
「王女様は賢いんだな」
「うむ。
吾輩自慢の主君なのだ」
「それで、その装置は完成したのか?」
「完成したぞ。
職人とは大した者達なのだ」
「ほう」
赤の他人でも職人を褒められると、ドグを褒められたようで何だか嬉しい。
「その装置を使って柵を完成させたんだな」
「いや、柵は完成していない」
「はい?」
ホーリーに疑問の視線を向けると、彼女はふいっと視線を逸らした。
「殿下は少し気まぐれで移り気なのだ」
「柵が必要だったんじゃ?」
「特には……」
おいおい。
だとすると、エリクサー探しも気まぐれだったのではないか?
その疑問を口から出そうとして止めた。
気まぐれだったのならエリクサーとやらを探さなくても良さそうなものだが、そこに言及してホーリーが納得したなら彼女は帰って行ってしまう。
それはそれで嬉しくない。
話している間に熔岩も冷えて固まったので、ロープを結んで落とし穴の中へと降りて行く。
ホーリーが先に降りて刺を魔法で融かして水を掛けて足場を作る。
更に魔法と剣とで周囲の刺を薙ぎ払ったところに俺も降りる。
岩と同じ固さの刺をどうしてホーリーが剣で斬れるのか俺には解らない。
きっと理を超越した何かだ。
その刺は、目の前で見れば高さが俺の肩くらいまでで、先端が極めて鋭く尖っていた。
「こんな刺でも横から見たら可愛いものだな」
「おう……」
試してみたら、俺の剣ではまるで刃が立たなくて、全く可愛くなかった。
そのせいでホーリーの後ろを付いて行くしかない俺である。
刺を薙ぎ払いながら進んで右に曲がり、暫く進んで左に曲がり、もう暫く進んで行き止まりとなった。
この落とし穴は念の入ったことに、ちょっとやそっとの跳躍力では逃れられないようになっているのだ。
少し後戻り、落とし穴の蓋の上がり口になる部分をホーリーが魔法でくり抜いて落とす。
降り注いだ熔岩がまだ熱いが、避けられるものは避け、避けられないものは斬り倒した刺を上に置いて足場にしつつ壁際に寄る。
そしてホーリーの魔法で壁を融かした所に斬り倒した刺を突き立てて階段にして落とし穴から脱出した。
「抜けたー」
「思ったより時間が掛かってしまったな」
俺は安堵ばかりだったが、ホーリーは時間が気になったらしい。
言われてみればそうである。
ダンジョンの中では時間が判らないが、腹の虫の機嫌からすればもう昼時だ。
進んだ距離に対して使った時間が多かった。
一般に言われているダンジョンの攻略時間が当てにならないのは止むを得ないにしても、この先がどこまで続いているかも判らないので掛かる時間も判らない。
そして、夜までに温泉宿に戻ろうと考えたなら、ここから幾らも探索を続けられない。
「この後のことは昼を食べながら考えよう」
「うむ」
腹が減っては戦ができない。
ここでしているのは探索ではあるが、言葉の綾というものだ。
落とし穴から数歩だけ離れて座り、温泉宿で用意して貰った鳥カツタルタルサンドをぱくつく。
「今日はどのくらい進む?」
「進める所まで行くのだ」
ホーリーは即答した。
「そうしたら今日は帰れなくなるかも知れないよ?」
「この先に罠が幾つ有るかも判らぬのだ。
真っ直ぐ突破しても数日を要するやも知れない。
だから少しでも先を見ておきたいのだ」
準備不足だからとここから引き返すようなら探索は遅遅として進まない。
この先に待っているもの次第では直ぐに引き返さざるを得なくなり、一日が丸々無駄になるかも知れない。
だからできるだけ先を確認するべきで、野営の道具を持っていなくても一晩くらいなら何とかなるとのことだ。
「判った」
俺の問いは確認の意味でしかなかったので否やは無かった。
空腹が癒えたところで出発。
ずっと暗い洞窟をランプの灯りだけを頼りに進む。
下り坂になった。
随分と急だ。
慎重に下りて行く。
暫く進めば坂にも慣れる。
歩みも少し速くなろうと言うものだ。
しかし不意に足が空を切る。
悪戯なことに段差が有った。
何て意地が悪い。
内心で悪態を吐きつつ足下に神経を集中させると、幸いなことに急な階段程度の落差で足が着く。
ところが階段とは違って段差の下も斜面になっている。
踏ん張りが利かず、俺の身体は前のめりに宙を舞った。
「で、鉄杭とロープをどう使うんだ?」
立て看板の奥、洞窟の壁がつるつるになる直前で立ち止まったホーリーに尋ねた。
「それを使うのはもう少し後だ」
ホーリーがおもむろに手を翳して魔法を放つと、薄暗い中を光球が前方の地面へと眩しいばかりの軌跡を描く。
すると、魔法の当たった床が一瞬で融けて煮えたぎった。
俺はあんなのを食らったのか……。
「ここはまだのようだな」
「まだって何が?」
ホーリーは独り納得しているが、俺は「求む説明」だ。
ところがホーリーはきょとんと俺を見て眼をパチクリさせる。
「落とし穴を先に空けてしまえば掛からずに済むだろう?」
「おう……」
確かにそうだが、ここまでの力業ができると誰が想像できようか。
ただ、目の前で見せられたことで、やろうとしていることは解った。
今し方の地面は熔岩が溜まったままになっていて、地面の下に空洞が無いのが見て取れる。
もしも落とし穴が有れば熔岩が下に落ちて空洞が覗く筈だ。
ホーリーが次々に魔法を放って溶岩溜まりを作る。
無造作に続けていることに疑問を感じる。
「そんなに魔法を連発して疲れないのか?」
「この程度、歩くくらいのものなのだ」
「そうなのか……」
魔法を使うと疲労するが、個人差が激しいために、どの程度疲れるのか傍目には判らない。
だから脚の疲れで喩えるのだ。
歩く程度、駆け足程度、全力疾走程度くらいの区別しかできないが、目安さえ判れば良い。
力の籠め方も疲れ方も相応との意味で、歩く程度なら少々使い続けても平気だと言うことになる。
つまり、俺にとってはでたらめにも見える魔法でも、ホーリー本人にとっては何でもないのであった。
「これ程の魔法ならホーリーは剣がいらなくないか?」
ホーリーが信じられないと顔に書いて反論する。
「何を言うのだ。
魔法では相手が死んでしまうではないか」
「いや、どうせ……」
魔物は殺すだろうと言い掛けて気付いた。
歩く程度でこの威力なら、極力威力を絞っても手足の一本くらいは消し炭になる。
「そうか、人相手には使えないんだな」
ホーリーが大きく頷いた。
譬え相手が犯罪者だったとしても、無闇に命に関わる傷を負わせる訳にはいかないのだった。
それが尋問のためだったとしても。
疑問も解消したところで探索の再開。
ホーリーが魔法で地面に溶岩溜まりを作りつつ進む。
最初の曲がり角を左に曲がって少しの所で変化が有った。
溶岩溜まりが出来ない。
それを確認したホーリーがその穴を起点にして四角の輪郭を描くように魔法で穿つ。
そして輪郭を描き終わると、その内側が静かに落ちて行った。
ゴガンと落とし穴の蓋の一部だったものが底に激突して音を立てるが、ぼんやりとしたランプの光の下では判然としない。
結構な深さである。
ホーリーは続けて穴の手前側の際まで魔法で崩してしまう。
一緒に融かされたことで穴の縁の角が取れた。
それから穴から二歩ほど離れた場所を指差して言う。
「シモン、ここを融かすから鉄杭を差し込んで欲しいのだ」
「え!? それって危なくないか?」
「手早くやれば大丈夫なのだ」
「だったら手本を見せてくれ!」
「やだ」
「何で!?」
「だって熱いんだもん」
ホーリーが片頬を膨らませながらプイッとそっぽを向く。
「『もん』て……」
あざとい。
あざといぞ、ホーリー。
いつもと口調からして違う。
頬を膨らませた顔も仕草も可愛らしくて二の句が継げない。
絶対に自覚してやってると思うのに、ほいほい言うことを聞いてやりたくなる。
本当に美少女は狡い。
「解ったよ……」
一つ溜め息を吐いて答えた。
そもそも雇われていながら今日はここまで何もしていない俺の仕事だろう。
「頼むのだ」
ホーリーは一転良い笑顔をする。
これではもう文句を言おうにも言えない。
「狡いなぁ」と頭では考えながらも心はホーリーのために動こうとするのだから、我ながら度し難い。
俺が鉄杭を持って構えるのを待ってホーリーが魔法を放つ。
一瞬で地面が灼熱に融けた。
その溶岩溜まりに近付いて手を伸ばすが……。
「熱っ!」
一瞬で引っ込めた。
「早く挿さないと挿し難くなるのだ」
「そう言われても……」
想像以上に熱かったからどうしても躊躇する。
ところがホーリーが脇を締めて両腕を軽く広げ、両の拳を握って可愛く言う。
「頑張って!」
天然のハニートラップだと解っていても、どうにも抗い難いものがある。
勿論一生に関わるようなものだったりするなら話は別だが、今、目の前に有るものはそうではないし、僅かな時間で済むものだ。
美少女の期待に応えたい気持ちの方が強く出る。
意を決して再度灼熱に挑む。
既に冷めてきているようで先よりも熱くない。
鉄杭を突き刺す。
粘土に突き刺すような感覚だ。
なかなか刺さらないので力を籠めると、ずぶずぶと鉄杭は熔岩に埋もれて行く。
そして俺の腕の長さほどの鉄杭が刺さること概ね三分の一。
「あっつっ!」
鉄杭が焼けるように熱くなって刹那で手を放した。
火傷した。
焼けるようにではなく、焼けていたのだった。
「良くやったのだ、シモン。
これで暫く冷めるのを待つのだ」
親指を立てたホーリーの無邪気な賛辞を素直に受け取れないのは、きっと俺の心が煤けてるのだろう。
これから暫くの間、熔岩が冷えて固まって鉄杭が固定されるのを待つ。
「ホーリーはよくこんなのを思い付いたな」
ヒリヒリする手に息を吹き掛けながら尋ねた。
鉄杭をこう使うとは予想だにしていなかった。
目の前で見た後だからホーリーが「魔法で岩が融ける」と言っていたことと繋がるが、鉄杭を買い求める時点では全く繋がらなかった。
「最初に思い付いたのは殿下なのだ」
何でも、第三王女ナイチアビーナはある日、王宮の花壇に柵を作ろうと考えたらしい。
その際、支柱を立てる工事が遅遅として進まないことや、ゴンゴンと杭を打つ音が延延と続くことに業を煮やしたと言う。
たかが柵。
されど柵。
しっかりしたものを立てようとしたならそれなりに手間暇掛かるものなのだ。
職人達も王宮でやっつけ仕事などできよう筈がない。
地盤の固い部分では地面を穿孔して杭を打ち、緩い部分では大きく掘り起こして栗石を入れ、搗き固めて杭を固定してから埋め戻した。
これでは時間も掛かれば音も出る。
これを職人達から聞き取ったナイチアビーナが知恵を絞った訳だ。
ただ、この時の試みは失敗に終わったらしい。
木杭では燃えてしまい、鉄杭でも真っ直ぐ立てるのがほぼほぼ不可能だったため、柵の支柱としては使いものにならなかったのだ。
しかし早々に杭を垂直に挿す装置を考案し、職人に開発させた。
「王女様は賢いんだな」
「うむ。
吾輩自慢の主君なのだ」
「それで、その装置は完成したのか?」
「完成したぞ。
職人とは大した者達なのだ」
「ほう」
赤の他人でも職人を褒められると、ドグを褒められたようで何だか嬉しい。
「その装置を使って柵を完成させたんだな」
「いや、柵は完成していない」
「はい?」
ホーリーに疑問の視線を向けると、彼女はふいっと視線を逸らした。
「殿下は少し気まぐれで移り気なのだ」
「柵が必要だったんじゃ?」
「特には……」
おいおい。
だとすると、エリクサー探しも気まぐれだったのではないか?
その疑問を口から出そうとして止めた。
気まぐれだったのならエリクサーとやらを探さなくても良さそうなものだが、そこに言及してホーリーが納得したなら彼女は帰って行ってしまう。
それはそれで嬉しくない。
話している間に熔岩も冷えて固まったので、ロープを結んで落とし穴の中へと降りて行く。
ホーリーが先に降りて刺を魔法で融かして水を掛けて足場を作る。
更に魔法と剣とで周囲の刺を薙ぎ払ったところに俺も降りる。
岩と同じ固さの刺をどうしてホーリーが剣で斬れるのか俺には解らない。
きっと理を超越した何かだ。
その刺は、目の前で見れば高さが俺の肩くらいまでで、先端が極めて鋭く尖っていた。
「こんな刺でも横から見たら可愛いものだな」
「おう……」
試してみたら、俺の剣ではまるで刃が立たなくて、全く可愛くなかった。
そのせいでホーリーの後ろを付いて行くしかない俺である。
刺を薙ぎ払いながら進んで右に曲がり、暫く進んで左に曲がり、もう暫く進んで行き止まりとなった。
この落とし穴は念の入ったことに、ちょっとやそっとの跳躍力では逃れられないようになっているのだ。
少し後戻り、落とし穴の蓋の上がり口になる部分をホーリーが魔法でくり抜いて落とす。
降り注いだ熔岩がまだ熱いが、避けられるものは避け、避けられないものは斬り倒した刺を上に置いて足場にしつつ壁際に寄る。
そしてホーリーの魔法で壁を融かした所に斬り倒した刺を突き立てて階段にして落とし穴から脱出した。
「抜けたー」
「思ったより時間が掛かってしまったな」
俺は安堵ばかりだったが、ホーリーは時間が気になったらしい。
言われてみればそうである。
ダンジョンの中では時間が判らないが、腹の虫の機嫌からすればもう昼時だ。
進んだ距離に対して使った時間が多かった。
一般に言われているダンジョンの攻略時間が当てにならないのは止むを得ないにしても、この先がどこまで続いているかも判らないので掛かる時間も判らない。
そして、夜までに温泉宿に戻ろうと考えたなら、ここから幾らも探索を続けられない。
「この後のことは昼を食べながら考えよう」
「うむ」
腹が減っては戦ができない。
ここでしているのは探索ではあるが、言葉の綾というものだ。
落とし穴から数歩だけ離れて座り、温泉宿で用意して貰った鳥カツタルタルサンドをぱくつく。
「今日はどのくらい進む?」
「進める所まで行くのだ」
ホーリーは即答した。
「そうしたら今日は帰れなくなるかも知れないよ?」
「この先に罠が幾つ有るかも判らぬのだ。
真っ直ぐ突破しても数日を要するやも知れない。
だから少しでも先を見ておきたいのだ」
準備不足だからとここから引き返すようなら探索は遅遅として進まない。
この先に待っているもの次第では直ぐに引き返さざるを得なくなり、一日が丸々無駄になるかも知れない。
だからできるだけ先を確認するべきで、野営の道具を持っていなくても一晩くらいなら何とかなるとのことだ。
「判った」
俺の問いは確認の意味でしかなかったので否やは無かった。
空腹が癒えたところで出発。
ずっと暗い洞窟をランプの灯りだけを頼りに進む。
下り坂になった。
随分と急だ。
慎重に下りて行く。
暫く進めば坂にも慣れる。
歩みも少し速くなろうと言うものだ。
しかし不意に足が空を切る。
悪戯なことに段差が有った。
何て意地が悪い。
内心で悪態を吐きつつ足下に神経を集中させると、幸いなことに急な階段程度の落差で足が着く。
ところが階段とは違って段差の下も斜面になっている。
踏ん張りが利かず、俺の身体は前のめりに宙を舞った。
0
あなたにおすすめの小説

【最強モブの努力無双】~ゲームで名前も登場しないようなモブに転生したオレ、一途な努力とゲーム知識で最強になる~
くーねるでぶる(戒め)
ファンタジー
アベル・ヴィアラットは、五歳の時、ベッドから転げ落ちてその拍子に前世の記憶を思い出した。
大人気ゲーム『ヒーローズ・ジャーニー』の世界に転生したアベルは、ゲームの知識を使って全男の子の憧れである“最強”になることを決意する。
そのために努力を続け、順調に強くなっていくアベル。
しかしこの世界にはゲームには無かった知識ばかり。
戦闘もただスキルをブッパすればいいだけのゲームとはまったく違っていた。
「面白いじゃん?」
アベルはめげることなく、辺境最強の父と優しい母に見守られてすくすくと成長していくのだった。

役立たずと言われダンジョンで殺されかけたが、実は最強で万能スキルでした !
本条蒼依
ファンタジー
地球とは違う異世界シンアースでの物語。
主人公マルクは神聖の儀で何にも反応しないスキルを貰い、絶望の淵へと叩き込まれる。
その役に立たないスキルで冒険者になるが、役立たずと言われダンジョンで殺されかけるが、そのスキルは唯一無二の万能スキルだった。
そのスキルで成り上がり、ダンジョンで裏切った人間は落ちぶれざまあ展開。
主人公マルクは、そのスキルで色んなことを解決し幸せになる。
ハーレム要素はしばらくありません。

【完結】うさぎ転生 〜女子高生の私、交通事故で死んだと思ったら、気づけば現代ダンジョンの最弱モンスターに!?最強目指して生き延びる〜
旅する書斎(☆ほしい)
ファンタジー
女子高生の篠崎カレンは、交通事故に遭って命を落とした……はずが、目覚めるとそこはモンスターあふれる現代ダンジョン。しかも身体はウサギになっていた!
HPはわずか5、攻撃力もゼロに等しい「最弱モンスター」扱いの白うさぎ。それでもスライムやコボルトにおびえながら、なんとか生き延びる日々。唯一の救いは、ダンジョン特有の“スキル”を磨けば強くなれるということ。
跳躍蹴りでスライムを倒し、小動物の悲鳴でコボルトを怯ませ、少しずつ経験値を積んでいくうちに、カレンは手応えを感じ始める。
「このままじゃ終わらない。私、もっと強くなっていつか……」
最弱からの“首刈りウサギ”進化を目指して、ウサギの身体で奮闘するカレン。彼女はこの危険だらけのダンジョンで、生き延びるだけでなく“人間へ戻る術(すべ)”を探し当てられるのか? それとも新たなモンスターとしての道を歩むのか?最弱うさぎの成り上がりサバイバルが、いま幕を開ける!
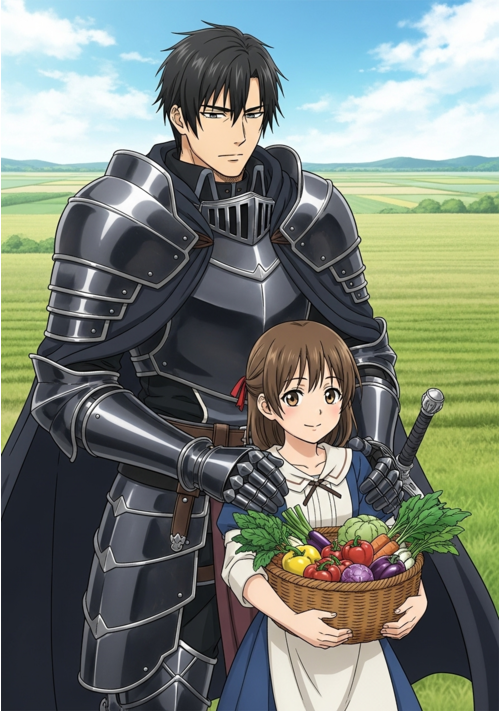
婚約破棄&濡れ衣で追放された聖女ですが、辺境で育成スキルの真価を発揮!無骨で不器用な最強騎士様からの溺愛が止まりません!
黒崎隼人
ファンタジー
「君は偽りの聖女だ」――。
地味な「育成」の力しか持たない伯爵令嬢エルナは、婚約者である王太子にそう断じられ、すべてを奪われた。聖女の地位、婚約者、そして濡れ衣を着せられ追放された先は、魔物が巣食う極寒の辺境の地。
しかし、絶望の淵で彼女は自身の力の本当の価値を知る。凍てついた大地を緑豊かな楽園へと変える「育成」の力。それは、飢えた人々の心と体を癒す、真の聖女の奇跡だった。
これは、役立たずと蔑まれた少女が、無骨で不器用な「氷壁の騎士」ガイオンの揺るぎない愛に支えられ、辺境の地でかけがえのない居場所と幸せを見つける、心温まる逆転スローライフ・ファンタジー。
王都が彼女の真価に気づいた時、もう遅い。最高のざまぁと、とろけるほど甘い溺愛が、ここにある。

アルフレッドは平穏に過ごしたい 〜追放されたけど謎のスキル【合成】で生き抜く〜
芍薬甘草湯
ファンタジー
アルフレッドは貴族の令息であったが天から与えられたスキルと家風の違いで追放される。平民となり冒険者となったが、生活するために竜騎士隊でアルバイトをすることに。
ふとした事でスキルが発動。
使えないスキルではない事に気付いたアルフレッドは様々なものを合成しながら密かに活躍していく。
⭐︎注意⭐︎
女性が多く出てくるため、ハーレム要素がほんの少しあります。特に苦手な方はご遠慮ください。

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる
竜頭蛇
ファンタジー
ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。
評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。
身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

転生貴族の移動領地~家族から見捨てられた三子の俺、万能な【スライド】スキルで最強領地とともに旅をする~
名無し
ファンタジー
とある男爵の三子として転生した主人公スラン。美しい海辺の辺境で暮らしていたが、海賊やモンスターを寄せ付けなかった頼りの父が倒れ、意識不明に陥ってしまう。兄姉もまた、スランの得たスキル【スライド】が外れと見るや、彼を見捨ててライバル貴族に寝返る。だが、そこから【スライド】スキルの真価を知ったスランの逆襲が始まるのであった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















