27 / 31
27
しおりを挟む
『シンクタンク・ユグドラシル』本部は、森林に抱かれた玲瓏で堅牢な巨大な建物である。城のような体裁を保ちながら、何度も改修と増築を繰り返し、研究所として機能している。幾つもの棟を有し、その中には研究者たちの居住区はもちろん、小さいながら礼拝堂さえも有している。
礼拝堂は小さくささやかなれど、外観に見劣りすることなく壮麗で荘厳な場所である。ただ、膨大な知識を詰め込んだ図書館の隣にある故か、学者たちがそこで足を止める回数は少ない。時折図書館から借りた本を読む人もいるようだが、やはり数は多くない。数多の学者が自身の研究に邁進する中、人気のない場所を探すならこの礼拝堂はまさにうってつけだった。
桂樹がその扉を押し開いたのは、そんな理由によるものかもしれなかった。月橘と連れ立って研究棟まで戻って来たのはいいが、総帥に会えるわけではない。昨日の今日だ。桂樹が乗り込んで行っても、一蹴されるだけだろう。月橘の言う通り、緋桐をどうしたいのか、桂樹自身に答えが出なければ動きようがなかった。
身廊を通り、祭壇の前に立つ。頭上には空の神と大地の神、その間に根を張り枝葉を広げる『世界樹』を模したステンドグラスが広がる。『世界樹』の傍には『鳥』。空の神と大地の神が引き離されて出来た大気を自由に渡る、翼を広げる『鳥』がいる。ごく当たり前のモチーフだ。『世界樹』のそばには『鳥』の飛ぶ姿が添えられる。だから人は疑ったことがない。
『鳥』が人と同じ形体をしているかもしれないことに。
『鳥籠』の中にいる『鳥』たちが、何故隠し守られるように保護されているのか。
緋桐が『鳥』かもしれない。その可能性を持って考えてみても、桂樹にはわからなかった。彼を、人ではないと知った上で同道していたのは事実だろう。連れて行かなければいけないと思ったのも、そのためだ。
だが、それが何だろうか。人であることが、重要だろうか。世界には極僅かだが、高度な文明を持つ人ではない種族も存在すると言う。『鳥』と言う特別な生き物であったとしても、彼は彼だ。意志を持ち、感情を持つ確立された一個の我だ。
あの光を放つ鮮やかな緋色が、彼を物語るものだ。彼の存在を主張するものだ。彼は彼として存在し、それ以外の何者でもない。
―――お前緋桐をどうするつもりだ?
鋭利な刃物のように、男の声が脳裏に蘇る。
問われて思い浮かぶもの。
月光のように煌めく銀糸に彩られた、鮮やかな緋色が屈託なく桂樹に笑いかけていた。
初めて名前を呼んだその声は少年特有の幼さと高さを有しており、桂樹の耳朶に甘く届いた。
―――桂樹
胸の奥の奥に、痺れるように響くまろい声。
抱きしめたい。
その薄い肩をかき抱き、何者にも怯えることがないように。その声で名前を―――。
「桂樹!!」
思考は突然静寂に響いた声に打ち破られた。礼拝堂を満たすほどの大声に、はっと振り返ると同時、胸に強い衝撃を受けて桂樹はたたらを踏んだ。
「……緋桐……?」
全身でぶつかってきた銀色が、しがみつくように桂樹の体を抱きしめる。きっと射るように睨む緋色にはうっすらと涙の膜が張り、喘ぐように薄紅色の唇が動く。
「その名で呼ぶのに、お前が俺を捨てるのか!?」
激情に任せ大声で怒鳴った緋桐の大きな瞳から、ぼろりと涙の粒が溢れ落ちた。
吸い込まれそうなほど鮮やかな緋色から零れ落ちる涙は、礼拝堂のステンドグラスの光に煌めいて、桂樹はそれを瞬きもせず凝視していた。
「ずっと、俺のそばにいて……」
か細く絞り出すような弱々しい声に、桂樹の手は無意識に彼を抱き寄せていた。
腕の中に驚くほどしっくりと収まる薄い体が、縋るように身を寄せて背中に回した手に力がこもる。
離そうなどと、桂樹は思ってもいなかったのだ。短い間同道しただけの相手だったのに、緋桐はいつの間にか桂樹の内側にするりと入り込み、動かせない位置にいた。いや、あるいは、初めから囚われていたのかもしれない。透き通る鮮やかな緋色の瞳を見た時から。一目で魂をもぎ取られたのだ。
「聞かせてくれないか、何故『森』にいたのか……」
今までずっと一緒にいて、一度たりとも口にしなかった問いかけ。
疑問は深く胸の奥に沈んでおり、桂樹の意識は考えることをやめたのだ。
彼が人ではない何かだと知っていたから。
耳元で静かに問いかけると、緋桐は腕の中でびくりと背を震わせた。抱きしめる腕から、戸惑いと緊張、そして怯えを感じる。安心させるように抱く腕に力を入れるも、彼の緊張が解かれることはなかった。
どれだけ経ったのか、長く感じた沈黙の後、緋桐は小さく頭を振った。
「……何も、知らない……気が付いたらあそこにいた……」
ぼんやりと、水の中から世界を見ているようだったと緋桐は言う。
薄くも分厚い膜に守られ、色々なことが頭を巡っていたように思う。巡る記憶と繰り返される情景と、何がどうなっているのかわからなくて、ごちゃごちゃになっていた。それが一つずつ整理されていったのがいつの頃だったのか。その時になって、ようやく意識と呼ぶようなものが働き始め、初めて外へと関心が向いた。
そうして急速に、霧が晴れるように意識が戻った。
『森』にいた理由はおろか、どうやってそこに行ったのか、それさえもわからない。
でも。
緋桐は小さく言葉を繋ぎ、何かを決意するように桂樹の腕の中で固く両手を握りしめる。
絞り出すような声は、絶望を見るように悄然としていた。
「俺はたぶん、この世界の人間じゃないんだ……」
礼拝堂は小さくささやかなれど、外観に見劣りすることなく壮麗で荘厳な場所である。ただ、膨大な知識を詰め込んだ図書館の隣にある故か、学者たちがそこで足を止める回数は少ない。時折図書館から借りた本を読む人もいるようだが、やはり数は多くない。数多の学者が自身の研究に邁進する中、人気のない場所を探すならこの礼拝堂はまさにうってつけだった。
桂樹がその扉を押し開いたのは、そんな理由によるものかもしれなかった。月橘と連れ立って研究棟まで戻って来たのはいいが、総帥に会えるわけではない。昨日の今日だ。桂樹が乗り込んで行っても、一蹴されるだけだろう。月橘の言う通り、緋桐をどうしたいのか、桂樹自身に答えが出なければ動きようがなかった。
身廊を通り、祭壇の前に立つ。頭上には空の神と大地の神、その間に根を張り枝葉を広げる『世界樹』を模したステンドグラスが広がる。『世界樹』の傍には『鳥』。空の神と大地の神が引き離されて出来た大気を自由に渡る、翼を広げる『鳥』がいる。ごく当たり前のモチーフだ。『世界樹』のそばには『鳥』の飛ぶ姿が添えられる。だから人は疑ったことがない。
『鳥』が人と同じ形体をしているかもしれないことに。
『鳥籠』の中にいる『鳥』たちが、何故隠し守られるように保護されているのか。
緋桐が『鳥』かもしれない。その可能性を持って考えてみても、桂樹にはわからなかった。彼を、人ではないと知った上で同道していたのは事実だろう。連れて行かなければいけないと思ったのも、そのためだ。
だが、それが何だろうか。人であることが、重要だろうか。世界には極僅かだが、高度な文明を持つ人ではない種族も存在すると言う。『鳥』と言う特別な生き物であったとしても、彼は彼だ。意志を持ち、感情を持つ確立された一個の我だ。
あの光を放つ鮮やかな緋色が、彼を物語るものだ。彼の存在を主張するものだ。彼は彼として存在し、それ以外の何者でもない。
―――お前緋桐をどうするつもりだ?
鋭利な刃物のように、男の声が脳裏に蘇る。
問われて思い浮かぶもの。
月光のように煌めく銀糸に彩られた、鮮やかな緋色が屈託なく桂樹に笑いかけていた。
初めて名前を呼んだその声は少年特有の幼さと高さを有しており、桂樹の耳朶に甘く届いた。
―――桂樹
胸の奥の奥に、痺れるように響くまろい声。
抱きしめたい。
その薄い肩をかき抱き、何者にも怯えることがないように。その声で名前を―――。
「桂樹!!」
思考は突然静寂に響いた声に打ち破られた。礼拝堂を満たすほどの大声に、はっと振り返ると同時、胸に強い衝撃を受けて桂樹はたたらを踏んだ。
「……緋桐……?」
全身でぶつかってきた銀色が、しがみつくように桂樹の体を抱きしめる。きっと射るように睨む緋色にはうっすらと涙の膜が張り、喘ぐように薄紅色の唇が動く。
「その名で呼ぶのに、お前が俺を捨てるのか!?」
激情に任せ大声で怒鳴った緋桐の大きな瞳から、ぼろりと涙の粒が溢れ落ちた。
吸い込まれそうなほど鮮やかな緋色から零れ落ちる涙は、礼拝堂のステンドグラスの光に煌めいて、桂樹はそれを瞬きもせず凝視していた。
「ずっと、俺のそばにいて……」
か細く絞り出すような弱々しい声に、桂樹の手は無意識に彼を抱き寄せていた。
腕の中に驚くほどしっくりと収まる薄い体が、縋るように身を寄せて背中に回した手に力がこもる。
離そうなどと、桂樹は思ってもいなかったのだ。短い間同道しただけの相手だったのに、緋桐はいつの間にか桂樹の内側にするりと入り込み、動かせない位置にいた。いや、あるいは、初めから囚われていたのかもしれない。透き通る鮮やかな緋色の瞳を見た時から。一目で魂をもぎ取られたのだ。
「聞かせてくれないか、何故『森』にいたのか……」
今までずっと一緒にいて、一度たりとも口にしなかった問いかけ。
疑問は深く胸の奥に沈んでおり、桂樹の意識は考えることをやめたのだ。
彼が人ではない何かだと知っていたから。
耳元で静かに問いかけると、緋桐は腕の中でびくりと背を震わせた。抱きしめる腕から、戸惑いと緊張、そして怯えを感じる。安心させるように抱く腕に力を入れるも、彼の緊張が解かれることはなかった。
どれだけ経ったのか、長く感じた沈黙の後、緋桐は小さく頭を振った。
「……何も、知らない……気が付いたらあそこにいた……」
ぼんやりと、水の中から世界を見ているようだったと緋桐は言う。
薄くも分厚い膜に守られ、色々なことが頭を巡っていたように思う。巡る記憶と繰り返される情景と、何がどうなっているのかわからなくて、ごちゃごちゃになっていた。それが一つずつ整理されていったのがいつの頃だったのか。その時になって、ようやく意識と呼ぶようなものが働き始め、初めて外へと関心が向いた。
そうして急速に、霧が晴れるように意識が戻った。
『森』にいた理由はおろか、どうやってそこに行ったのか、それさえもわからない。
でも。
緋桐は小さく言葉を繋ぎ、何かを決意するように桂樹の腕の中で固く両手を握りしめる。
絞り出すような声は、絶望を見るように悄然としていた。
「俺はたぶん、この世界の人間じゃないんだ……」
0
あなたにおすすめの小説

林檎を並べても、
ロウバイ
BL
―――彼は思い出さない。
二人で過ごした日々を忘れてしまった攻めと、そんな彼の行く先を見守る受けです。
ソウが目を覚ますと、そこは消毒の香りが充満した病室だった。自分の記憶を辿ろうとして、はたり。その手がかりとなる記憶がまったくないことに気付く。そんな時、林檎を片手にカーテンを引いてとある人物が入ってきた。
彼―――トキと名乗るその黒髪の男は、ソウが事故で記憶喪失になったことと、自身がソウの親友であると告げるが…。

狼の護衛騎士は、今日も心配が尽きない
結衣可
BL
戦の傷跡が癒えた共生都市ルーヴェン。
人族と獣人族が共に暮らすその街で、文官ユリス・アルヴィンは、穏やかな日々の中に、いつも自分を見守る“優しい視線”の存在を感じていた。
その正体は、狼族の戦士長出身の護衛騎士、ガルド・ルヴァーン。
無口で不器用だが、誠実で優しい彼は、いつしかユリスを守ることが日課になっていた。
モフモフ好きなユリスと、心配性すぎるガルド。
灰銀の狼と金灰の文官――
異種族の二人の関係がルーヴェンの風のようにやさしく、日々の中で少しずつ変わっていく。
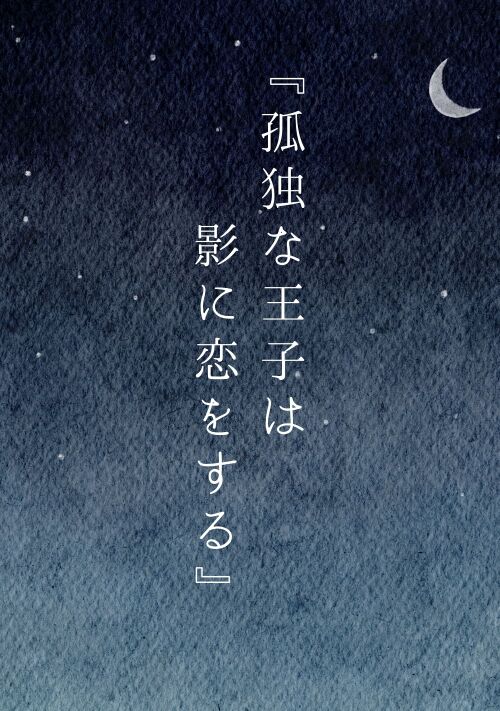
孤独な王子は影に恋をする
結衣可
BL
王国の第一王子リオネル・ヴァルハイトは、
「光」と称えられるほど完璧な存在だった。
民からも廷臣からも賞賛され、非の打ち所がない理想の王子。
しかしその仮面の裏には、孤独と重圧に押し潰されそうな本音が隠されていた。
弱音を吐きたい。誰かに甘えたい。
だが、その願いを叶えてくれる相手はいない。
――ただ一人、いつも傍に気配を寄せていた“影”に恋をするまでは。
影、王族直属の密偵として顔も名も隠し、感情を持たぬよう育てられた存在。
常に平等であれと叩き込まれ、ただ「王子を守る影」として仕えてきた。
完璧を求められる王子と、感情を禁じられてきた影。
光と影が惹かれ合い、やがて互いの鎖を断ち切ってゆく。

白花の檻(はっかのおり)
AzureHaru
BL
その世界には、生まれながらに祝福を受けた者がいる。その祝福は人ならざるほどの美貌を与えられる。
その祝福によって、交わるはずのなかった2人の運命が交わり狂っていく。
この出会いは祝福か、或いは呪いか。
受け――リュシアン。
祝福を授かりながらも、決して傲慢ではなく、いつも穏やかに笑っている青年。
柔らかな白銀の髪、淡い光を湛えた瞳。人々が息を呑むほどの美しさを持つ。
攻め――アーヴィス。
リュシアンと同じく祝福を授かる。リュシアン以上に人の域を逸脱した容姿。
黒曜石のような瞳、彫刻のように整った顔立ち。
王国に名を轟かせる貴族であり、数々の功績を誇る英雄。

happy dead end
瑞原唯子
BL
「それでも俺に一生を捧げる覚悟はあるか?」
シルヴィオは幼いころに第一王子の遊び相手として抜擢され、初めて会ったときから彼の美しさに心を奪われた。そして彼もシルヴィオだけに心を開いていた。しかし中等部に上がると、彼はとある女子生徒に興味を示すようになり——。

禁書庫の管理人は次期宰相様のお気に入り
結衣可
BL
オルフェリス王国の王立図書館で、禁書庫を預かる司書カミル・ローレンは、過去の傷を抱え、静かな孤独の中で生きていた。
そこへ次期宰相と目される若き貴族、セドリック・ヴァレンティスが訪れ、知識を求める名目で彼のもとに通い始める。
冷静で無表情なカミルに興味を惹かれたセドリックは、やがて彼の心の奥にある痛みに気づいていく。
愛されることへの恐れに縛られていたカミルは、彼の真っ直ぐな想いに少しずつ心を開き、初めて“痛みではない愛”を知る。
禁書庫という静寂の中で、カミルの孤独を、過去を癒し、共に歩む未来を誓う。

雪を溶かすように
春野ひつじ
BL
人間と獣人の争いが終わった。
和平の条件で人間の国へ人質としていった獣人国の第八王子、薫(ゆき)。そして、薫を助けた人間国の第一王子、悠(はる)。二人の距離は次第に近づいていくが、実は薫が人間国に行くことになったのには理由があった……。
溺愛・甘々です。
*物語の進み方がゆっくりです。エブリスタにも掲載しています

龍の寵愛を受けし者達
樹木緑
BL
サンクホルム国の王子のジェイドは、
父王の護衛騎士であるダリルに憧れていたけど、
ある日偶然に自分の護衛にと推す父王に反する声を聞いてしまう。
それ以来ずっと嫌われていると思っていた王子だったが少しずつ打ち解けて
いつかはそれが愛に変わっていることに気付いた。
それと同時に何故父王が最強の自身の護衛を自分につけたのか理解す時が来る。
王家はある者に裏切りにより、
無惨にもその策に敗れてしまう。
剣が苦手でずっと魔法の研究をしていた王子は、
責めて騎士だけは助けようと、
刃にかかる寸前の所でとうの昔に失ったとされる
時戻しの術をかけるが…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















