24 / 33
第三章 マリーアントワネット
7
しおりを挟む
そうして店を出てすぐ、まただ。雨が、また降り出してきた。天気の神さまの気まぐれなのか、悪戯なのか、それともわたしは雨女?
いずれにせよ、傘を持ってきて正解だった。
「紅麗亜ちゃん!」
路地を二つほど曲がったあたりだった。路地裏に体操座りで蹲る、雨晒しとなっていた紅麗亜ちゃんを発見。膝小僧に顔を埋める紅麗亜ちゃんへ、わたしは傘をさしながら歩み寄る。
紅麗亜ちゃんは、涙声で言った。
「もう、私のことは放っておいてくださいよ……結衣先輩には、なにも関係ないじゃないですか」
「いやでもさ……ほら、傘! 借りっぱなしだったしさ!」紅麗亜ちゃんの隣にしゃがみ込み、縮こまった彼女の体を傘の中に入れてあげる。「それにわたし、紅麗亜ちゃんのこと好きだしさ。やっぱり、放っておけないよ」
「好きって……」
「あ、いや! 好きってのは、恋愛の好きじゃなくて、人として好きってことね?」
「言われなくたって、分かってます……」
「だ、だよね? ははははは!」
取り繕うように笑って誤魔化す。紅麗亜ちゃんの頭に付着した雨の水玉を手で払ってあげる。そのときにも、気付いた。紅麗亜ちゃんの髪は、かなり切れ毛が多い。カラーのやり過ぎでこうなってしまったのだろうか。ほだか先生はこの髪を、どんな思いで染めていたのだろうか。また紅麗亜ちゃんは、どんな思いで髪を染め続けていたのだろうか。考えるだけで、胸が苦しくなった。
「ごめんね、紅麗亜ちゃん。なにも知らないくせに、わたし、適当なことばかり言っちゃった。紅麗亜ちゃんのこと、全然分かってあげられてなかったね……いつもこうなんだ」
「……」
「一人で勝手に暴走して、バイト辞めさせられたときだってそう。あれもね、紅麗亜ちゃんの為にやったとかじゃないんだ。本当言うとね、わたしが許せなかっただけなの。要は偽善者。自分が自分がって、そんな感じ。だからその……ごめん。今回のことも、わたしの勝手なこと言っちゃっただけ。ほんと、最低だ……わたし」
「……がう」
「ん?」
「それは、違うと……そう思います」
紅麗亜ちゃんは、ゆっくりと顔を上げてわたしのことを眺めてくる。泣き孕んだ瞳を向けてきた。
「結衣先輩は……偽善者なんかじゃありません。結衣先輩は、自分が許せなかったからって言いましたけど……でも私は、あのとき結衣先輩に助けられて、すごく安心したんです。結衣先輩が隣にいてくれたから、頑張れたんです」
「紅麗亜ちゃん……」
「だから、違う。結衣先輩は、偽善者なんかじゃない」
先ほどまで泣いていたくせに、そのときの紅麗亜ちゃんは泣くことを忘れたみたく、一生懸命に口を動かしていた。
「バイトのみんなも、結衣先輩がいたときは良かったって、そう言ってました。店長も、結衣先輩を辞めさせてしまったことすごく後悔してて、あれから、人が変わったみたいに優しくなったんです。結衣先輩は、太陽みたいな人、なんですよ。彼と同じです」
「く、紅麗亜ちゃん!」
「はい?」
「いやね……太陽みたいな人って、さすがにそれ、褒め過ぎじゃない?」
照れ笑い浮かべながら言えば、
「そうですか?」
「う、うん……」
「……」
「……」
「……かもしれません」
紅麗亜ちゃんは泣き笑いしながらそう言った。途端、わたしも声をあわせて笑っていた。
空気が変わったのは、その後にも。紅麗亜ちゃんは、自ずと過去のことを語り出した。それは店長から聞いていた親のことや、地元で悪さをしていた先輩とつるんでいたことなど。そして、人生の暗闇の中から、紅麗亜ちゃんを連れ出してくれたという『彼』のことを。
「最初は、たまたまだったんです。バス停でいきなり『髪、すごい色してるね』って話しかけられて、ナンパかなって無視してたんです。だって彼、金髪で、それに顔もカッコ良かったから、なんたかチャラいなって……だから私に声をかけてきたのは、ただ遊び目的かなって」
当時まだ中学生だった紅麗亜ちゃんからすれば、そう見えてしまったのだろうか。でも言われてみれば、当時のわたしも街を歩いている大学生を見て「チャラチャラしてるなぁ」とか思っていた気がする。今にして思えば、ただ髪が明るくしているだけ。ただそれだけのことなのに──カラーリングは見た目の印象をがらりと変えてしまうと言っていたほだか先生の言葉を、ふと思い出す。紅麗亜ちゃんは、話し続けた。
「ただなんか、妙に彼のことが頭から離れなくなってですね……それから少しして、また彼がバス停にいたんで、近くに座ったんです。そしたら彼が、『相変わらずすごい色だね』って言われて……彼と話し出したのは、それからでした」
語る紅麗亜ちゃんは、本当に幸せそうだった。そのくらい大事な思い出なのだろう。彼はなんでも、聞き上手だったみたい。彼と話していると、不思議といろいろ話してしまったらしい。そんな紅麗亜ちゃんに対して、彼は「大変だったね」と我ごとのように言って、一緒に泣いてくれたと。
「彼も、あまり良い家庭環境ではなかったみたいで、私の気持ちはよく分かると……そう言ってました。貧乏で弟もいたから、早くに働き出したそうです。『だからお前は学校くらい出とけ。いつか必ず後悔するから』って、彼、そう言ってくれました。誰かに心配されたのは、あのときが生まれてはじめてで」
それから、だったらしい。紅麗亜ちゃんは真っ当に生きようと、髪を黒に戻した。学校にも通い始めて、遅れた分を取り戻そうと必死に勉強を頑張った。そんな紅麗亜ちゃんの直向きな姿に感化されたのか、学校の先生たちも親身となって応援してくれた。悩みを聞いてくれる友達もできた。「あのとき、人の温もりを知ったんです」と、紅麗亜ちゃんは涙ながらに語ってくれた。その話を聞いていると、わたしまで泣きそうになった。
「その後も、バス停にいる彼に『学校でこんなことがあった』とか報告しに行ってました。今考えれば、なんだか私ストーカーみたい……きっと、彼も面倒くさかっただろうと思います。でも、嫌がらないんです。笑って話を聞いてくれて、いつも褒めてくれて、それがすごく嬉しくて、だから……会えないと分かったときは、もう死にたくなりました」
そこまで言ったあたりで、紅麗亜ちゃんは声を詰まらせた。感極まってしまったのだろう。そんな紅麗亜ちゃんの気持ちは、痛いほどよく分かる気がした。
自分に後ろめたさを感じているとき、無償の優しさで包み込んでくれる仏さまのような人と出会ってしまえば、誰だって好きになってしまう。わたしだってそうだったように、紅麗亜ちゃんもそうだっただけ。彼と会えなくなったショックで、昔のトラウマを思い出してしまったのだろう。結果として、髪を真っ白にしていた当時の自分が見えてしまった。
恋は人を盲目にさせる。でもその盲目さがあったからこそ、紅麗亜ちゃんがつらい現実を乗り越えることができたのも事実だ。今回はただ、好きという気持ちが暴走しただけ。決して、悪いことばかりではなかったはずだ。
わたしは紅麗亜ちゃんが泣き止むまで、背中をさすってあげた。ただ散々泣いた後の紅麗亜ちゃんとは、その胸の奥にずっとしまい込んでいた悩みを吐き出したみたく、笑っていた。心からの笑顔では、ないみたいだけれど。でも、今の紅麗亜ちゃんなら、彼の熱い思いも受け止めきれるかもしれない。
わたしはスマホを取り出して、その連絡先へとかける。不思議な顔をして見てくる紅麗亜ちゃんを横目に、電話主へと事情を説明して。
「はい、紅麗亜ちゃん。店長が話したいって」
「店長? なんで、店長が……」
「いいからいいから。ほら」
よく分かっていない紅麗亜ちゃんの手に、無理やりスマホを握らせる。紅麗亜ちゃんは「?」状態で、恐る恐る通話口に耳を近づけた。その直後だった。
『紅麗亜っ!? 大丈夫か、お前!?』
通話をしてないわたしにも聞こえるくらい大きな声。無理もない。今回のことで、一番紅麗亜ちゃんを心配していたのは店長だ。というのも、ここ最近の紅麗亜ちゃんは特に様子がおかしかったらしい。紅麗亜ちゃん自身、この時期は特に髪が白くなりやすいのだと店長にだけは伝えていたようだ。それは、彼と出会い、彼と会えなくなった時期だからとも、そのように聞いている。
また、これも先日はじめて聞かされた話。店長には、離婚経験があるらしい。そして、娘が一人だけいるのだと。今年高校生になったばかりの、紅麗亜ちゃんと同い年の娘が。そんな娘さんと、紅麗亜ちゃんの姿が重なってしまったのかもしれない。じゃあわたしはどうなんだって、まあその辺は今更考えても後の祭りだ。
それから10分程電話は続いて、紅麗亜ちゃんは「ありがとうございます」とスマホを渡してくる。また涙目となっていた。ただそれは先ほどまでの悲哀さはない。実に幸福そうな、嬉しさからくる涙なのだろう。
「……店長が、『俺のことは父親だと思ってなんでも相談しろ』って、そう言ってくれました」
「また大胆なプロポーズだねぇ。でも店長、すごく紅麗亜ちゃんのこと心配してたから。『俺の娘がぁあ』って、なんかおかしかったよ」
「結衣先輩」
「ん? なにー」
「本当に、ありがとうございます……私、人にこんなに心配されてるなんて、思いもしませんでした。いつも自分のことばかりで、なにも分かってなくて……」
「仕方ないよ。紅麗亜ちゃんは、自分のことで必死だったんだから。それにわたしも、店長だって、そんな紅麗亜ちゃんの力になってあげたいって、勝手にそう思っただけ。紅麗亜ちゃんってほら、なんか放っておけないし」
そう言って、わたしは無意識に紅麗亜ちゃんの頭を撫でていた。なんだろうか、わたしにも妹がいたらこんな感じだったのかなって、そんな気分だった。
紅麗亜ちゃんは、こっぱずかしそうにしながら、
「結衣先輩って、なんか、アレですよね……」
「アレって?」
「いや、そのぉ…………」
「?」
「……いいえ、なんでもありません。帰りましょう、一緒に」
紅麗亜ちゃんが、わたしの手を握ってきた。潤んだ瞳で、真っ直ぐ見つめられる。指なんか絡めちゃってさ……なんだろうか、一体?
まあ、いいんだけどさ。少しでも紅麗亜ちゃんの気持ちが前に向いてくれたのなら、それだけで充分だ。
その後のことについて。一度わたしだけ店へ戻り、ほだか先生に事情を説明。紅麗亜ちゃんは大丈夫そうです、との旨を伝えた。
ほだか先生は、
「本当に、あなたって人は」
呆れているのか、感心しているのかよく分からない口振りだった。
「あの、またまた勝手なことをして、その、申し訳ありません」
「そんなことは、どうだっていいんです。結衣くん」
「はい……」
怒られるのかな……そんな予感を、複雑そうなほだか先生の表情から察してしまう。ただそれも当然で、仕方のないこと。心の準備は、とうに出来ている。さあ、どんとこい! と、わたしは覚悟をしたつもりだったのだけれど。
「よく、やりましたね」
わたしの目線まで腰をかがめたほだか先生が、優しく頭を撫でてくれた。いつもの笑顔はない。何故だか、切なげに見えてしまう。
「……ほだか先生?」
「結衣くん。ボクはここ最近、よく考えていたんですよ。人は、霊に干渉していいのか、否を」
「えっと……それは、どういう意味でしょうか?」
尋ね返すと、ほだか先生は「さあ、どうなんでしょう?」と意味深なことを言って、そこでやっと笑顔を見せてくれた。いつものほだか先生だった。
「結局のところ、人は、人の繋がりでしか、その苦しみを乗り越えることはできない。ボクのやっていることは、単なる慰めに過ぎません。仮にも、その愚かしい慰めを選ぶのであれば……やはり、交わってはいけなかったかもしれません」
ますます意味が分からなかった。でもなんだか、ほだか先生が辛そうに見えて仕方がなかった。
「ほだか先生……なにか、あったんですか?」
「いいえ、なにも。なにもありません。いつものように、薫と楽しくお喋りをしただけですよ」
「天童さん? 来てたんですか?」
ほだか先生は頷いて、それ以上のことは言わなかった。
「結衣くん、明日は臨時休業です。お疲れさまでした」
最後まで、釈然としないままだった。
モヤモヤとした気分のまま、店先で待ってくれていた紅麗亜ちゃんと駅へ向かう。紅麗亜ちゃんは、店長の変化を楽しそうに語っている。一方で、わたしは憂鬱な気分。なんだか、立場が変わったみたいな感じ。
「店長、あれが本当は良い人なんですよね。ま、結衣先輩が辞めてからの影響が大きいんでしょうけど、一番大きいのは小山さんでしょうね。恋は人を成長させるって、きっとそう言うやつですよ。思いやりの気持ちに目覚めたのかもしれません」
……ん? 恋は、人を成長させるぅ?
「えーと、紅麗亜ちゃん。一体なんの話をしているのかな?」
「その様子だと、結衣先輩も二人の関係について知ってるみたいですね」
全身から冷や汗が吹き出してくる。紅麗亜ちゃんは口元に手を添えて、クスクスと笑った。
「一緒に働いているんですから、気付くに決まってるじゃないですか。大体それ、もうスタッフみんな知ってますし。周知の事実ですよ?」
Oh……おいたわしや、お二人さん。でも多分、渋谷で同棲するってことまで知らないと思いますから、黙っておきますね?
「でもほんと、二人って幸せそうなんですよね……ちょっと、羨ましいくらいです。私も、過去のことを忘れて、前に進めたらいいんですけど」
「忘れる必要は、ないと思う。いいじゃん別に、好きなら好きのままで」
「結衣先輩……」
「また会いにきたら、いいと思うし」
──あ、でも今日みたいなのは勘弁だからね? そう付け加えれば、紅麗亜ちゃんは小さく頭を下げてきた。顔を上げて、わたしのことをじっと見つめてくる。
「……結衣先輩って、本当、優しいですよね。小山さんが勘違いしちゃうのも、分からなくないです」
「えっと……はははは、モウオワッタコトダカラー」
「なんですか、それ。そうやって結衣先輩は、これまでたくさんの人を勘違いさせてきたんだろうなぁ」
「勘違いさせてきたのは紅麗亜ちゃんの方でしょ? わたし、きっと男だったら紅麗亜ちゃんのこと好きになる自信がある」
「……だから、そういうとこですよ」
「?」
「頑張ります、私……うん、頑張る」
と、よく分からないがやる気を出した紅麗亜ちゃん。そんなこんなで駅に着き、階段を登る。
「今日は本当に私、どうかしてました……この前のこともあったから、特に。反省します」
「この前のことって、なにかあったの?」
小首を傾げて尋ねると、紅麗亜ちゃんは「そう言えば結衣先輩、この前いませんでしたよね」
この前って、いつだろうか?
「ほら、髪を染めた次の日。傘を忘れたことに気付いたので、取りに伺ったんですけど……」
ああ、あの日。天童さんが店に来てたときか──
「彼のよく付けていた香水の匂いが、香ってきて……それに、声も。そんなこと、絶対あり得ないのに」
ホームに上がって、直ぐ、モノレールの光が見えた。
「ほだか先生、香水なんかつけてたっけ?」
「なんで、ほだかさんの話になるんですか?」
あれ?
「……えっと、紅麗亜ちゃんの言ってた『彼』って、ほだか先生じゃなかったの?」
紅麗亜ちゃんは「まさか」と、少し驚いていた。
「私が言っているのはほだかさんではなく、お兄さんの方です」
「え!? お兄さん!? ほだか先生の!?」
「えっと、知らなかったんですか?」
わたしは首を激しく縦に振る。紅麗亜ちゃんは少し呆れていた。でも、しょうがないじゃん。本当に知らなかったんだから。でも、そうなのか。全てがわたしの勘違い。つくづく、思い込みは怖いと思わされる。でも、ほだか先生のお兄さんって、一体どんな人なんだろうか──と、わたしは即座に聞いていた。やっぱり気になった。
モノレールが到着。扉が開いた。足を前へ出しながら、紅麗亜ちゃんは言った。
「本名は『黄昏 薫』って言うんですけど……普段は源氏名である『天童 薫』の方で名乗っていました。あ、ホストだったんですよ、薫さん」
?
「それに──」
「く、紅麗亜ちゃん! ちょっとまって!」
「はい?」
「天童さんが……ほだか先生のお兄さんだって話、ほんと?」
扉が、閉まる。モノレールが、ゆっくりと走り出して──
「そうですけど……あれ? 結衣先輩、あの美容室で働き始めたの、一ヶ月前からですよね。まさか、昔から薫さんのこと知ってたんですか?」
「いや、知らないけど」
「じゃあ、どうして……」
「……?」
「どうして、2年前に亡くなった薫さんのことを……結衣先輩が知ってるんですか?」
わたしの世界が、音を立てて静止した。
いずれにせよ、傘を持ってきて正解だった。
「紅麗亜ちゃん!」
路地を二つほど曲がったあたりだった。路地裏に体操座りで蹲る、雨晒しとなっていた紅麗亜ちゃんを発見。膝小僧に顔を埋める紅麗亜ちゃんへ、わたしは傘をさしながら歩み寄る。
紅麗亜ちゃんは、涙声で言った。
「もう、私のことは放っておいてくださいよ……結衣先輩には、なにも関係ないじゃないですか」
「いやでもさ……ほら、傘! 借りっぱなしだったしさ!」紅麗亜ちゃんの隣にしゃがみ込み、縮こまった彼女の体を傘の中に入れてあげる。「それにわたし、紅麗亜ちゃんのこと好きだしさ。やっぱり、放っておけないよ」
「好きって……」
「あ、いや! 好きってのは、恋愛の好きじゃなくて、人として好きってことね?」
「言われなくたって、分かってます……」
「だ、だよね? ははははは!」
取り繕うように笑って誤魔化す。紅麗亜ちゃんの頭に付着した雨の水玉を手で払ってあげる。そのときにも、気付いた。紅麗亜ちゃんの髪は、かなり切れ毛が多い。カラーのやり過ぎでこうなってしまったのだろうか。ほだか先生はこの髪を、どんな思いで染めていたのだろうか。また紅麗亜ちゃんは、どんな思いで髪を染め続けていたのだろうか。考えるだけで、胸が苦しくなった。
「ごめんね、紅麗亜ちゃん。なにも知らないくせに、わたし、適当なことばかり言っちゃった。紅麗亜ちゃんのこと、全然分かってあげられてなかったね……いつもこうなんだ」
「……」
「一人で勝手に暴走して、バイト辞めさせられたときだってそう。あれもね、紅麗亜ちゃんの為にやったとかじゃないんだ。本当言うとね、わたしが許せなかっただけなの。要は偽善者。自分が自分がって、そんな感じ。だからその……ごめん。今回のことも、わたしの勝手なこと言っちゃっただけ。ほんと、最低だ……わたし」
「……がう」
「ん?」
「それは、違うと……そう思います」
紅麗亜ちゃんは、ゆっくりと顔を上げてわたしのことを眺めてくる。泣き孕んだ瞳を向けてきた。
「結衣先輩は……偽善者なんかじゃありません。結衣先輩は、自分が許せなかったからって言いましたけど……でも私は、あのとき結衣先輩に助けられて、すごく安心したんです。結衣先輩が隣にいてくれたから、頑張れたんです」
「紅麗亜ちゃん……」
「だから、違う。結衣先輩は、偽善者なんかじゃない」
先ほどまで泣いていたくせに、そのときの紅麗亜ちゃんは泣くことを忘れたみたく、一生懸命に口を動かしていた。
「バイトのみんなも、結衣先輩がいたときは良かったって、そう言ってました。店長も、結衣先輩を辞めさせてしまったことすごく後悔してて、あれから、人が変わったみたいに優しくなったんです。結衣先輩は、太陽みたいな人、なんですよ。彼と同じです」
「く、紅麗亜ちゃん!」
「はい?」
「いやね……太陽みたいな人って、さすがにそれ、褒め過ぎじゃない?」
照れ笑い浮かべながら言えば、
「そうですか?」
「う、うん……」
「……」
「……」
「……かもしれません」
紅麗亜ちゃんは泣き笑いしながらそう言った。途端、わたしも声をあわせて笑っていた。
空気が変わったのは、その後にも。紅麗亜ちゃんは、自ずと過去のことを語り出した。それは店長から聞いていた親のことや、地元で悪さをしていた先輩とつるんでいたことなど。そして、人生の暗闇の中から、紅麗亜ちゃんを連れ出してくれたという『彼』のことを。
「最初は、たまたまだったんです。バス停でいきなり『髪、すごい色してるね』って話しかけられて、ナンパかなって無視してたんです。だって彼、金髪で、それに顔もカッコ良かったから、なんたかチャラいなって……だから私に声をかけてきたのは、ただ遊び目的かなって」
当時まだ中学生だった紅麗亜ちゃんからすれば、そう見えてしまったのだろうか。でも言われてみれば、当時のわたしも街を歩いている大学生を見て「チャラチャラしてるなぁ」とか思っていた気がする。今にして思えば、ただ髪が明るくしているだけ。ただそれだけのことなのに──カラーリングは見た目の印象をがらりと変えてしまうと言っていたほだか先生の言葉を、ふと思い出す。紅麗亜ちゃんは、話し続けた。
「ただなんか、妙に彼のことが頭から離れなくなってですね……それから少しして、また彼がバス停にいたんで、近くに座ったんです。そしたら彼が、『相変わらずすごい色だね』って言われて……彼と話し出したのは、それからでした」
語る紅麗亜ちゃんは、本当に幸せそうだった。そのくらい大事な思い出なのだろう。彼はなんでも、聞き上手だったみたい。彼と話していると、不思議といろいろ話してしまったらしい。そんな紅麗亜ちゃんに対して、彼は「大変だったね」と我ごとのように言って、一緒に泣いてくれたと。
「彼も、あまり良い家庭環境ではなかったみたいで、私の気持ちはよく分かると……そう言ってました。貧乏で弟もいたから、早くに働き出したそうです。『だからお前は学校くらい出とけ。いつか必ず後悔するから』って、彼、そう言ってくれました。誰かに心配されたのは、あのときが生まれてはじめてで」
それから、だったらしい。紅麗亜ちゃんは真っ当に生きようと、髪を黒に戻した。学校にも通い始めて、遅れた分を取り戻そうと必死に勉強を頑張った。そんな紅麗亜ちゃんの直向きな姿に感化されたのか、学校の先生たちも親身となって応援してくれた。悩みを聞いてくれる友達もできた。「あのとき、人の温もりを知ったんです」と、紅麗亜ちゃんは涙ながらに語ってくれた。その話を聞いていると、わたしまで泣きそうになった。
「その後も、バス停にいる彼に『学校でこんなことがあった』とか報告しに行ってました。今考えれば、なんだか私ストーカーみたい……きっと、彼も面倒くさかっただろうと思います。でも、嫌がらないんです。笑って話を聞いてくれて、いつも褒めてくれて、それがすごく嬉しくて、だから……会えないと分かったときは、もう死にたくなりました」
そこまで言ったあたりで、紅麗亜ちゃんは声を詰まらせた。感極まってしまったのだろう。そんな紅麗亜ちゃんの気持ちは、痛いほどよく分かる気がした。
自分に後ろめたさを感じているとき、無償の優しさで包み込んでくれる仏さまのような人と出会ってしまえば、誰だって好きになってしまう。わたしだってそうだったように、紅麗亜ちゃんもそうだっただけ。彼と会えなくなったショックで、昔のトラウマを思い出してしまったのだろう。結果として、髪を真っ白にしていた当時の自分が見えてしまった。
恋は人を盲目にさせる。でもその盲目さがあったからこそ、紅麗亜ちゃんがつらい現実を乗り越えることができたのも事実だ。今回はただ、好きという気持ちが暴走しただけ。決して、悪いことばかりではなかったはずだ。
わたしは紅麗亜ちゃんが泣き止むまで、背中をさすってあげた。ただ散々泣いた後の紅麗亜ちゃんとは、その胸の奥にずっとしまい込んでいた悩みを吐き出したみたく、笑っていた。心からの笑顔では、ないみたいだけれど。でも、今の紅麗亜ちゃんなら、彼の熱い思いも受け止めきれるかもしれない。
わたしはスマホを取り出して、その連絡先へとかける。不思議な顔をして見てくる紅麗亜ちゃんを横目に、電話主へと事情を説明して。
「はい、紅麗亜ちゃん。店長が話したいって」
「店長? なんで、店長が……」
「いいからいいから。ほら」
よく分かっていない紅麗亜ちゃんの手に、無理やりスマホを握らせる。紅麗亜ちゃんは「?」状態で、恐る恐る通話口に耳を近づけた。その直後だった。
『紅麗亜っ!? 大丈夫か、お前!?』
通話をしてないわたしにも聞こえるくらい大きな声。無理もない。今回のことで、一番紅麗亜ちゃんを心配していたのは店長だ。というのも、ここ最近の紅麗亜ちゃんは特に様子がおかしかったらしい。紅麗亜ちゃん自身、この時期は特に髪が白くなりやすいのだと店長にだけは伝えていたようだ。それは、彼と出会い、彼と会えなくなった時期だからとも、そのように聞いている。
また、これも先日はじめて聞かされた話。店長には、離婚経験があるらしい。そして、娘が一人だけいるのだと。今年高校生になったばかりの、紅麗亜ちゃんと同い年の娘が。そんな娘さんと、紅麗亜ちゃんの姿が重なってしまったのかもしれない。じゃあわたしはどうなんだって、まあその辺は今更考えても後の祭りだ。
それから10分程電話は続いて、紅麗亜ちゃんは「ありがとうございます」とスマホを渡してくる。また涙目となっていた。ただそれは先ほどまでの悲哀さはない。実に幸福そうな、嬉しさからくる涙なのだろう。
「……店長が、『俺のことは父親だと思ってなんでも相談しろ』って、そう言ってくれました」
「また大胆なプロポーズだねぇ。でも店長、すごく紅麗亜ちゃんのこと心配してたから。『俺の娘がぁあ』って、なんかおかしかったよ」
「結衣先輩」
「ん? なにー」
「本当に、ありがとうございます……私、人にこんなに心配されてるなんて、思いもしませんでした。いつも自分のことばかりで、なにも分かってなくて……」
「仕方ないよ。紅麗亜ちゃんは、自分のことで必死だったんだから。それにわたしも、店長だって、そんな紅麗亜ちゃんの力になってあげたいって、勝手にそう思っただけ。紅麗亜ちゃんってほら、なんか放っておけないし」
そう言って、わたしは無意識に紅麗亜ちゃんの頭を撫でていた。なんだろうか、わたしにも妹がいたらこんな感じだったのかなって、そんな気分だった。
紅麗亜ちゃんは、こっぱずかしそうにしながら、
「結衣先輩って、なんか、アレですよね……」
「アレって?」
「いや、そのぉ…………」
「?」
「……いいえ、なんでもありません。帰りましょう、一緒に」
紅麗亜ちゃんが、わたしの手を握ってきた。潤んだ瞳で、真っ直ぐ見つめられる。指なんか絡めちゃってさ……なんだろうか、一体?
まあ、いいんだけどさ。少しでも紅麗亜ちゃんの気持ちが前に向いてくれたのなら、それだけで充分だ。
その後のことについて。一度わたしだけ店へ戻り、ほだか先生に事情を説明。紅麗亜ちゃんは大丈夫そうです、との旨を伝えた。
ほだか先生は、
「本当に、あなたって人は」
呆れているのか、感心しているのかよく分からない口振りだった。
「あの、またまた勝手なことをして、その、申し訳ありません」
「そんなことは、どうだっていいんです。結衣くん」
「はい……」
怒られるのかな……そんな予感を、複雑そうなほだか先生の表情から察してしまう。ただそれも当然で、仕方のないこと。心の準備は、とうに出来ている。さあ、どんとこい! と、わたしは覚悟をしたつもりだったのだけれど。
「よく、やりましたね」
わたしの目線まで腰をかがめたほだか先生が、優しく頭を撫でてくれた。いつもの笑顔はない。何故だか、切なげに見えてしまう。
「……ほだか先生?」
「結衣くん。ボクはここ最近、よく考えていたんですよ。人は、霊に干渉していいのか、否を」
「えっと……それは、どういう意味でしょうか?」
尋ね返すと、ほだか先生は「さあ、どうなんでしょう?」と意味深なことを言って、そこでやっと笑顔を見せてくれた。いつものほだか先生だった。
「結局のところ、人は、人の繋がりでしか、その苦しみを乗り越えることはできない。ボクのやっていることは、単なる慰めに過ぎません。仮にも、その愚かしい慰めを選ぶのであれば……やはり、交わってはいけなかったかもしれません」
ますます意味が分からなかった。でもなんだか、ほだか先生が辛そうに見えて仕方がなかった。
「ほだか先生……なにか、あったんですか?」
「いいえ、なにも。なにもありません。いつものように、薫と楽しくお喋りをしただけですよ」
「天童さん? 来てたんですか?」
ほだか先生は頷いて、それ以上のことは言わなかった。
「結衣くん、明日は臨時休業です。お疲れさまでした」
最後まで、釈然としないままだった。
モヤモヤとした気分のまま、店先で待ってくれていた紅麗亜ちゃんと駅へ向かう。紅麗亜ちゃんは、店長の変化を楽しそうに語っている。一方で、わたしは憂鬱な気分。なんだか、立場が変わったみたいな感じ。
「店長、あれが本当は良い人なんですよね。ま、結衣先輩が辞めてからの影響が大きいんでしょうけど、一番大きいのは小山さんでしょうね。恋は人を成長させるって、きっとそう言うやつですよ。思いやりの気持ちに目覚めたのかもしれません」
……ん? 恋は、人を成長させるぅ?
「えーと、紅麗亜ちゃん。一体なんの話をしているのかな?」
「その様子だと、結衣先輩も二人の関係について知ってるみたいですね」
全身から冷や汗が吹き出してくる。紅麗亜ちゃんは口元に手を添えて、クスクスと笑った。
「一緒に働いているんですから、気付くに決まってるじゃないですか。大体それ、もうスタッフみんな知ってますし。周知の事実ですよ?」
Oh……おいたわしや、お二人さん。でも多分、渋谷で同棲するってことまで知らないと思いますから、黙っておきますね?
「でもほんと、二人って幸せそうなんですよね……ちょっと、羨ましいくらいです。私も、過去のことを忘れて、前に進めたらいいんですけど」
「忘れる必要は、ないと思う。いいじゃん別に、好きなら好きのままで」
「結衣先輩……」
「また会いにきたら、いいと思うし」
──あ、でも今日みたいなのは勘弁だからね? そう付け加えれば、紅麗亜ちゃんは小さく頭を下げてきた。顔を上げて、わたしのことをじっと見つめてくる。
「……結衣先輩って、本当、優しいですよね。小山さんが勘違いしちゃうのも、分からなくないです」
「えっと……はははは、モウオワッタコトダカラー」
「なんですか、それ。そうやって結衣先輩は、これまでたくさんの人を勘違いさせてきたんだろうなぁ」
「勘違いさせてきたのは紅麗亜ちゃんの方でしょ? わたし、きっと男だったら紅麗亜ちゃんのこと好きになる自信がある」
「……だから、そういうとこですよ」
「?」
「頑張ります、私……うん、頑張る」
と、よく分からないがやる気を出した紅麗亜ちゃん。そんなこんなで駅に着き、階段を登る。
「今日は本当に私、どうかしてました……この前のこともあったから、特に。反省します」
「この前のことって、なにかあったの?」
小首を傾げて尋ねると、紅麗亜ちゃんは「そう言えば結衣先輩、この前いませんでしたよね」
この前って、いつだろうか?
「ほら、髪を染めた次の日。傘を忘れたことに気付いたので、取りに伺ったんですけど……」
ああ、あの日。天童さんが店に来てたときか──
「彼のよく付けていた香水の匂いが、香ってきて……それに、声も。そんなこと、絶対あり得ないのに」
ホームに上がって、直ぐ、モノレールの光が見えた。
「ほだか先生、香水なんかつけてたっけ?」
「なんで、ほだかさんの話になるんですか?」
あれ?
「……えっと、紅麗亜ちゃんの言ってた『彼』って、ほだか先生じゃなかったの?」
紅麗亜ちゃんは「まさか」と、少し驚いていた。
「私が言っているのはほだかさんではなく、お兄さんの方です」
「え!? お兄さん!? ほだか先生の!?」
「えっと、知らなかったんですか?」
わたしは首を激しく縦に振る。紅麗亜ちゃんは少し呆れていた。でも、しょうがないじゃん。本当に知らなかったんだから。でも、そうなのか。全てがわたしの勘違い。つくづく、思い込みは怖いと思わされる。でも、ほだか先生のお兄さんって、一体どんな人なんだろうか──と、わたしは即座に聞いていた。やっぱり気になった。
モノレールが到着。扉が開いた。足を前へ出しながら、紅麗亜ちゃんは言った。
「本名は『黄昏 薫』って言うんですけど……普段は源氏名である『天童 薫』の方で名乗っていました。あ、ホストだったんですよ、薫さん」
?
「それに──」
「く、紅麗亜ちゃん! ちょっとまって!」
「はい?」
「天童さんが……ほだか先生のお兄さんだって話、ほんと?」
扉が、閉まる。モノレールが、ゆっくりと走り出して──
「そうですけど……あれ? 結衣先輩、あの美容室で働き始めたの、一ヶ月前からですよね。まさか、昔から薫さんのこと知ってたんですか?」
「いや、知らないけど」
「じゃあ、どうして……」
「……?」
「どうして、2年前に亡くなった薫さんのことを……結衣先輩が知ってるんですか?」
わたしの世界が、音を立てて静止した。
0
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

私に告白してきたはずの先輩が、私の友人とキスをしてました。黙って退散して食事をしていたら、ハイスペックなイケメン彼氏ができちゃったのですが。
石河 翠
恋愛
飲み会の最中に席を立った主人公。化粧室に向かった彼女は、自分に告白してきた先輩と自分の友人がキスをしている現場を目撃する。
自分への告白は、何だったのか。あまりの出来事に衝撃を受けた彼女は、そのまま行きつけの喫茶店に退散する。
そこでやけ食いをする予定が、美味しいものに満足してご機嫌に。ちょっとしてネタとして先ほどのできごとを話したところ、ずっと片想いをしていた相手に押し倒されて……。
好きなひとは高嶺の花だからと諦めつつそばにいたい主人公と、アピールし過ぎているせいで冗談だと思われている愛が重たいヒーローの恋物語。
この作品は、小説家になろう及びエブリスタでも投稿しております。
扉絵は、写真ACよりチョコラテさまの作品をお借りしております。

後宮薬師は名を持たない
由香
キャラ文芸
後宮で怪異を診る薬師・玉玲は、母が禁薬により処刑された過去を持つ。
帝と皇子に迫る“鬼”の気配、母の遺した禁薬、鬼神の青年・玄曜との出会い。
救いと犠牲の狭間で、玉玲は母が選ばなかった選択を重ねていく。
後宮が燃え、名を失ってもなお――
彼女は薬師として、人として、生きる道を選ぶ。

母の下着 タンスと洗濯籠の秘密
MisakiNonagase
青春
この物語は、思春期という複雑で繊細な時期を生きる少年の内面と、彼を取り巻く家族の静かなる絆を描いた作品です。
颯真(そうま)という一人の高校生の、ある「秘密」を通して、私たちは成長の過程で誰もが抱くかもしれない戸惑い、罪悪感、そしてそれらを包み込む家族の無言の理解に触れます。
物語は、現在の颯真と恋人・彩花との関係から、中学時代にさかのぼる形で展開されます。そこで明らかになるのは、彼がかつて母親の下着に対して抱いた抑えがたい好奇心と、それに伴う一連の行為です。それは彼自身が「歪んだ」と感じる過去の断片であり、深い恥ずかしさと自己嫌悪を伴う記憶です。
しかし、この物語の核心は、単なる過去の告白にはありません。むしろ、その行為に「気づいていたはず」の母親が、なぜ一言も問い詰めず、誰にも告げず、ただ静かに見守り続けたのか——という問いにこそあります。そこには、親子という関係を超えた、深い人間理解と、言葉にされない優しさが横たわっています。
センシティブな題材を、露骨な描写や扇情的な表現に頼ることなく、あくまで颯真の内省的な視点から丁寧に紡ぎ出しています。読者は、主人公の痛みと恥ずかしさを共有しながら、同時に、彼を破綻から救った「沈黙の救済」の重みと温かさを感じ取ることでしょう。
これは、一つの過ちと、その赦しについての物語です。また、成長とは時に恥ずかしい過去を背負いながら、他者の無償の寛容さによって初めて前を向けるようになる過程であること、そして家族の愛が最も深く現れるのは、時に何も言わない瞬間であることを、静かにしかし確かに伝える物語です。
どうか、登場人物たちの静かなる心の襞に寄り添いながら、ページをめくってください。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

イケメン警視、アルバイトで雇った恋人役を溺愛する。
楠ノ木雫
恋愛
蒸発した母の借金を擦り付けられた主人公瑠奈は、お見合い代行のアルバイトを受けた。だが、そのお見合い相手、矢野湊に借金の事を見破られ3ヶ月間恋人役を務めるアルバイトを提案された。瑠奈はその報酬に飛びついたが……
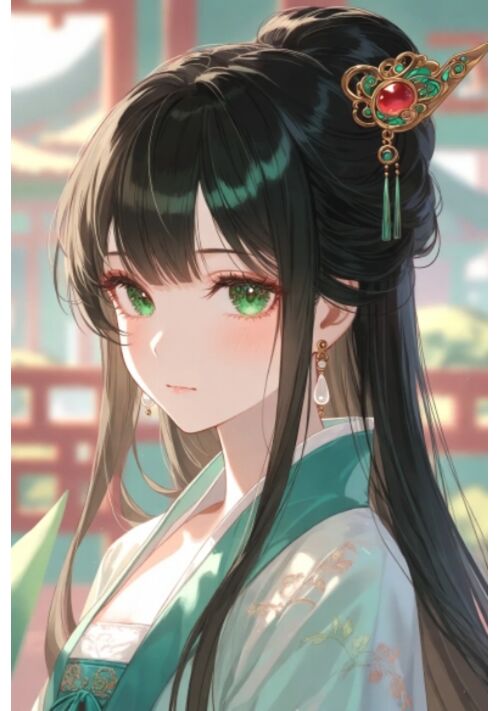
完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す〜特殊な眼を持つ歌姫が、2人の皇子と出会い、陰謀に巻き込まれながら王家の隠した真実に迫る
雪城 冴
キャラ文芸
1/23本編完結‼️
【中華サスペンス】
皇帝が隠した禁忌の秘密。
それを“思い出してはいけない少女”がいた――
【あらすじ】
特殊な眼を持つ少女・翠蓮(スイレン)は、不吉を呼ぶとして忌み嫌われ、育ての父を村人に殺されてしまう。
居場所を失った彼女は、宮廷直属の音楽団の選抜試験を受けることに。
しかし、早速差別の洗礼を受けてしまう。
そんな翠蓮を助けたのは、危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。
それをきっかけに翠蓮は皇位争いに巻き込まれ、選抜試験も敵の妨害を受けてしまう。
彼女は無事合格できるのか。
◆二章◆
仲間と出会い、心を新たにするも次なる試練が待ち受ける。
それは、ライバル歌姫との二重唱と、メンバーからの嫌がらせだった。
なんとか迎えた本番。翠蓮は招かれた地方貴族から、忌み嫌われる眼の秘密に触れる。
◆三章◆
翠蓮の歌声と真心が貴妃の目にとまる。しかし後宮で"寵愛を受けている"と噂になり、皇后に目をつけられた。
皇后の息子から揺さぶりをかけられ、もう一人の皇子とは距離が急接近。
しかし、後宮特有の嫌がらせの中で翠蓮は、自分の存在が皇子に迷惑をかけていると知る。
わずかに芽生えていた恋心とも尊敬とも付かない気持ちは、押さえつけるしかなかった。
◆最終章◆
後宮で命を狙われ、生死をさまよう翠蓮は、忘れていた記憶を取り戻す。
かつて王家が封じた“力”とは?
翠蓮の正体とは?
身分違いの恋の行方は?
声を隠すか歌うのか。
運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――
※架空の中華風ファンタジーです
※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています
※表紙絵はAI生成

迷子を助けたら生徒会長の婚約者兼女の子のパパになったけど別れたはずの彼女もなぜか近づいてくる
九戸政景
恋愛
新年に初詣に来た父川冬矢は、迷子になっていた頼母木茉莉を助け、従姉妹の田母神真夏と知り合う。その後、真夏と再会した冬矢は真夏の婚約者兼茉莉の父親になってほしいと頼まれる。
※こちらは、カクヨムやエブリスタでも公開している作品です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















