8 / 60
第一章第三節anguish1
桜まつり、家族の午後
しおりを挟む
春の光は、飽きもせず川沿いの土手を撫でていく。
堤防を覆い尽くす桜並木は今まさに盛り、
数えきれないほどの花びらが風に煽られては空中で渦を巻き、
ひとひら、またひとひらと地面へ舞い落ちていく。
土手の斜面に色とりどりのレジャーシートが敷き詰められ、
町内会の家族や子どもたちが思い思いのグループを作って膝を寄せ合う。
朝早くから準備された手作りのお弁当、コンビニのからあげ、
保温ポットのお茶、キャンディ包み。遠くからはチンドン屋の古びたラッパ、
少年野球の掛け声、小犬の甲高い鳴き声。
誰もが浮かれ気分で、この季節の“祭り”に身を委ねている。
八神家は、川にせり出すように枝を伸ばした一本の老桜の下に腰を下ろしていた。
ピンクと白のシートには、翔子が丹精を込めて作った卵焼き、海苔のおにぎり、
鮭の塩焼き、ブロッコリーの隙間に詰め込んだ冷凍食品のコロッケ。
翔子は、カーディガンの袖を肘までたくし上げ、
春風に前髪を揺らしながら「はい、唐揚げ追加ね!」と明るい声を響かせる。
その声は不思議な温度を持って広がり、
近くで見ていた町内の主婦たちも
「八神さんとこの唐揚げ、美味しいんだよねぇ」
と、うっすらとした羨望を漂わせた。
凛桜は箸をピンと揃え、完璧な手元で海苔巻きをつまみあげる。
制服姿のままの姿勢は真っすぐで、髪は高くひとつに結われている。
その横で昴流はスマホを片手に、家族全員の顔を何度もカメラ越しに覗いては、
シャッター音を連発している。「ほら、ちゃんとピースして!はい、笑って!」
翔桜はというと、誰よりも静かだ。弁当箱の端で器用に鮭をほぐし、
淡々と白飯を運ぶばかりで、時折遠い目をして桜の花びらを眺めている。
その視線の奥は、他人には決して触れられない薄い膜で覆われている。
「久しぶりにみんなで外で食べるなんて、いいね」
翔子は家族の中心で微笑む。
声には張りがあり、どこか子どもっぽささえ残しているが、
額の端には春先の細かな皺がひと筋だけ走る。
康人は口数少なく、「うん」とだけ短く頷き、新聞の折り目をいじっている。
彼の視線は時折スマホへと落ち、そのたび指先がソワソワと動くが、
家族の話題にはあえて加わらない。
桜並木の向こう、リードを引いた老犬が、子どもたちにおびえて腰を落とす。
大きなビニール袋を片手にした町内会長の山根が「おいでおいで」と声をかけると、
犬はしっぽを引きずりながら土手を駆け上がっていった。
町内の誰もがこの桜まつりを愛している。
だが、どこかで“誰か”が誰かをじっと観察している、そんな気配が確かに漂っている。
「凛桜、おかわりは?」
翔子が声をかけると、凛桜は首を小さく振って「もう十分」と微笑む。
昴流は唐揚げを口に放り込みながら、スマホのインカメに夢中。
「ママ、こっち見て!変顔してみて!」
翔子はおどけて唇を尖らせ、その拍子に桜の花びらが鼻先に落ちてきて、
「きゃっ」と小さく声をあげる。
その一瞬、翔桜がふっと息を漏らした。
シートの端では、小学生たちが輪になって花びらを投げ合い、
幼児の女の子がハンカチで泥だらけの手を拭っている。
保育園児の叫び声、風船売りの鈴の音、
サイクリングの青年の影が桜並木を切り取って走り抜ける。
時折、酔った男たちの笑い声が遠くから響き、
風下のほうでは焼きそば屋台からソースの匂いが漂ってくる。
光の反射が河面に揺れ、カラスが高い枝をひとつついばむ。
「春だねぇ」と誰かがつぶやき、空にカメラを向けた。
翔子はふと、胸元のボタンに手をやる。
昨年の桜まつりとは違い、春先にしては少し汗ばむ初夏を思わせるほどの陽気。
今日は淡いグレーのノースリーブワンピース。
その下に着た白のキャミソールが、桜色の影を透かしている。
少しうなじをなでる風が、背中にそっと忍び込んでいく。
そのとき、すぐ後ろで――「キャハハ!」と女子中学生たちが大きな声で笑った。
「昴流君のお母さんって、昔から美人で有名だったんだって」と耳打ちする声。
「スタイルも凄いよね」
すぐに別の女の子が
「胸でしょ、あれは反則」
と囁き、波のように小さな笑いが拡がった。
翔子は気づかないふりで、視線を地面に落とす。
だが、家族の輪の外側で、誰かが自分の胸元や腕、
足元の三つ折りソックスまでじっと見つめている感覚がした。
空に溶けるような柔らかな陽光、桜吹雪の中に立ち尽くす人々の影――
それぞれの物語が、静かにこの土手の上で交錯していた。
午後の風は、どこまでも優しい。
だけど、このやわらかい春の空気の中にも、どこか小さな“異物”が紛れ込んでいる。
この幸福な一日は、まだ“裂け目”を知らない。
世界は今、ただ緩やかな高揚とざわめきの中、静かに揺れていた。
堤防を覆い尽くす桜並木は今まさに盛り、
数えきれないほどの花びらが風に煽られては空中で渦を巻き、
ひとひら、またひとひらと地面へ舞い落ちていく。
土手の斜面に色とりどりのレジャーシートが敷き詰められ、
町内会の家族や子どもたちが思い思いのグループを作って膝を寄せ合う。
朝早くから準備された手作りのお弁当、コンビニのからあげ、
保温ポットのお茶、キャンディ包み。遠くからはチンドン屋の古びたラッパ、
少年野球の掛け声、小犬の甲高い鳴き声。
誰もが浮かれ気分で、この季節の“祭り”に身を委ねている。
八神家は、川にせり出すように枝を伸ばした一本の老桜の下に腰を下ろしていた。
ピンクと白のシートには、翔子が丹精を込めて作った卵焼き、海苔のおにぎり、
鮭の塩焼き、ブロッコリーの隙間に詰め込んだ冷凍食品のコロッケ。
翔子は、カーディガンの袖を肘までたくし上げ、
春風に前髪を揺らしながら「はい、唐揚げ追加ね!」と明るい声を響かせる。
その声は不思議な温度を持って広がり、
近くで見ていた町内の主婦たちも
「八神さんとこの唐揚げ、美味しいんだよねぇ」
と、うっすらとした羨望を漂わせた。
凛桜は箸をピンと揃え、完璧な手元で海苔巻きをつまみあげる。
制服姿のままの姿勢は真っすぐで、髪は高くひとつに結われている。
その横で昴流はスマホを片手に、家族全員の顔を何度もカメラ越しに覗いては、
シャッター音を連発している。「ほら、ちゃんとピースして!はい、笑って!」
翔桜はというと、誰よりも静かだ。弁当箱の端で器用に鮭をほぐし、
淡々と白飯を運ぶばかりで、時折遠い目をして桜の花びらを眺めている。
その視線の奥は、他人には決して触れられない薄い膜で覆われている。
「久しぶりにみんなで外で食べるなんて、いいね」
翔子は家族の中心で微笑む。
声には張りがあり、どこか子どもっぽささえ残しているが、
額の端には春先の細かな皺がひと筋だけ走る。
康人は口数少なく、「うん」とだけ短く頷き、新聞の折り目をいじっている。
彼の視線は時折スマホへと落ち、そのたび指先がソワソワと動くが、
家族の話題にはあえて加わらない。
桜並木の向こう、リードを引いた老犬が、子どもたちにおびえて腰を落とす。
大きなビニール袋を片手にした町内会長の山根が「おいでおいで」と声をかけると、
犬はしっぽを引きずりながら土手を駆け上がっていった。
町内の誰もがこの桜まつりを愛している。
だが、どこかで“誰か”が誰かをじっと観察している、そんな気配が確かに漂っている。
「凛桜、おかわりは?」
翔子が声をかけると、凛桜は首を小さく振って「もう十分」と微笑む。
昴流は唐揚げを口に放り込みながら、スマホのインカメに夢中。
「ママ、こっち見て!変顔してみて!」
翔子はおどけて唇を尖らせ、その拍子に桜の花びらが鼻先に落ちてきて、
「きゃっ」と小さく声をあげる。
その一瞬、翔桜がふっと息を漏らした。
シートの端では、小学生たちが輪になって花びらを投げ合い、
幼児の女の子がハンカチで泥だらけの手を拭っている。
保育園児の叫び声、風船売りの鈴の音、
サイクリングの青年の影が桜並木を切り取って走り抜ける。
時折、酔った男たちの笑い声が遠くから響き、
風下のほうでは焼きそば屋台からソースの匂いが漂ってくる。
光の反射が河面に揺れ、カラスが高い枝をひとつついばむ。
「春だねぇ」と誰かがつぶやき、空にカメラを向けた。
翔子はふと、胸元のボタンに手をやる。
昨年の桜まつりとは違い、春先にしては少し汗ばむ初夏を思わせるほどの陽気。
今日は淡いグレーのノースリーブワンピース。
その下に着た白のキャミソールが、桜色の影を透かしている。
少しうなじをなでる風が、背中にそっと忍び込んでいく。
そのとき、すぐ後ろで――「キャハハ!」と女子中学生たちが大きな声で笑った。
「昴流君のお母さんって、昔から美人で有名だったんだって」と耳打ちする声。
「スタイルも凄いよね」
すぐに別の女の子が
「胸でしょ、あれは反則」
と囁き、波のように小さな笑いが拡がった。
翔子は気づかないふりで、視線を地面に落とす。
だが、家族の輪の外側で、誰かが自分の胸元や腕、
足元の三つ折りソックスまでじっと見つめている感覚がした。
空に溶けるような柔らかな陽光、桜吹雪の中に立ち尽くす人々の影――
それぞれの物語が、静かにこの土手の上で交錯していた。
午後の風は、どこまでも優しい。
だけど、このやわらかい春の空気の中にも、どこか小さな“異物”が紛れ込んでいる。
この幸福な一日は、まだ“裂け目”を知らない。
世界は今、ただ緩やかな高揚とざわめきの中、静かに揺れていた。
0
あなたにおすすめの小説


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。
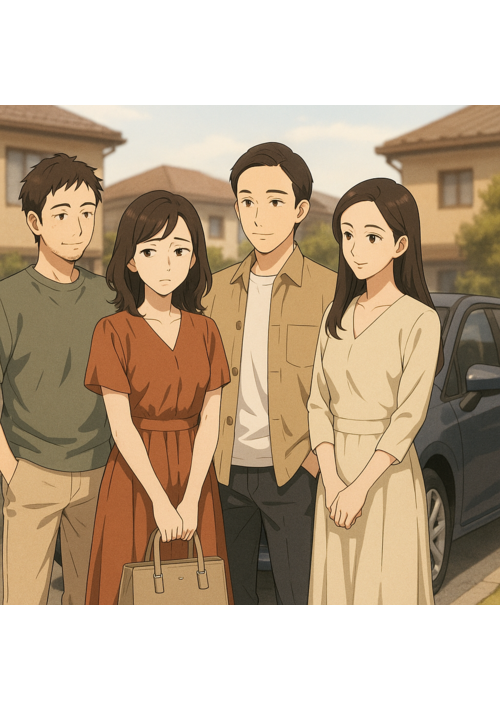



上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















