25 / 60
第二章第二節degeneration1
微熱の噂
しおりを挟む
朝の空気は澄んでいるはずなのに、
翔子の耳には昨夜の熱がまだこもっている気がした。
ベッドから起き上がると、薄いニットセーターを手に取る。
インナーの引き出しを開けた指先は、
わざとブラジャーを素通りした。
(今日は……つけない)
胸の奥で、軽く笑うような、震えるような感覚があった。
ニットの生地は柔らかいが、薄手のため形を拾いやすい。
乳首の膨らみは、姿勢を正せばクッキリと主張するだろう。
鏡の前で肩を引き、背筋を伸ばす。
布の下で、重みを持った乳房が大きくたわむのが自分でも分かった。
歩けば――もっと裸のままの乳房であることがはっきりする。
昨夜の夜翔としての高揚感が、まだ身体を温め続けていた。
町内の路地を抜け、集積所へ向かう。
すれ違う近所の主婦や老人たちの視線が、
自分に少し長くとどまっている気がした。
「……あの人……」
風に混じって届く囁きは、言葉にならないまま背中をくすぐる。
歩くたび、ニットの上からでも
乳房が大きく揺れるのを、自分でも意識してしまう。
心臓の鼓動は下腹に響き、足取りが微かに弾んだ。
午前十時過ぎ、町内の集会場の前で数人が談笑していた。
塚本、加賀美、そして山根。
視線が一瞬こちらに集まり、笑い声のトーンが変わる。
「最近、おかしいよね」
「……なんか、色っぽくなったというか」
「そう?いやらしくなったって思うけど。私は」
「確かに、今までの翔子さんの雰囲気とは違うよね」
その断片が、翔子の耳に入り込む。
(色っぽくなった……?いやらしい……?)
悪意だけではない、
わずかに含まれた羨望の響きに、胸の奥がじんとした。
午後、買い物に出た。今日はパートの公休日。
いつもは接客をしているニッコリマートでの夕飯の買い出し。
自動ドアが開くと同時に、冷気と惣菜の匂いが頬を撫でた。
ブラは――着けていない。
歩くたびに胸の中で揺れる重みが、
ブラのない自由さを誇示するように主張してくる。
(……やっぱり、わかるかな)
胸の先端が、ニット越しに自己主張しているのを自分でも感じる。
布地を押し上げる形は、隠そうにも隠せない。
入口近くの青果コーナーでキャベツを手に取ったとき、
横の鏡面棚に自分の姿が映った。
(……はっきり、わかる)
乳首の膨らみが、鏡越しの自分に突きつけられる。
見られているのではなく、自分で自分を見てしまう。
――それだけで、下腹がふっと温かくなる。
夜翔の時間が、昼の日常にまで侵食してきている。
果物売り場を抜け、総菜コーナーへ向かうと、
ふいに背後から視線を感じた。
振り返らなくてもわかる。
中年男性客がトレーを手に、
商品棚ではなく自分の胸元に焦点を合わせている。
(見られてる……)
その瞬間、乳首の先がピンと硬くなり、
布地にさらにくっきりと浮かび上がった。
通路を移動するたび、
ガラスケースや冷蔵扉に映る自分の胸が目に入る。
体温と冷気の温度差で、感覚が研ぎ澄まされていく。
(これは……夜翔のせいだ)
心の中で呟きながらも、足は鮮魚コーナーへと自然に向かっていた。
乳首の隆起を意識するたびに下腹部が熱くなる。
買い物中であるにもかかわらず、欲情が色を帯びてくる。
(もっと、もっと、見られたい。私を意識されたい…)
他人の視線を意識しながら鮮魚売り場に移動した。
銀色に輝くアジを手に取ったそのとき、背後から肩を軽く叩かれた。
振り返ると、同僚の柿本明日香が立っていた。
「ちょっと、翔子さん……」
指で示されるまま、売り場の隅へ。
「今日、ブラ付けてないよね。さっきから……見られてるよ」
冷蔵ケースのモーター音に混じって、
その言葉が翔子に静かにでもはっきりと届いた。
翔子は唇だけで笑った。
「でも……見せてるんじゃないよ」
「うん。分かってる。でも、
まるわかりだよ。服装も考えなよ。ニットじゃなくて」
柿本はおそらく同僚として、
バレーボールの仲間として忠告してくれているのは明らかだ。
「実はね、乳首が炎症起こしててね。
医者にも、生地の擦れで悪化するって言われてるの」
言い訳をした――完全な嘘だ。
でも、そう言い聞かせると、なぜか胸がひとつ、軽くなった気がした。
柿本はしばらく翔子の胸元を見て、ため息をついた。
「そうなんだ。わかった。……でも、気をつけなよ」
柿本は短くそう言い残して仕事に戻った。
柿本の言葉は少し冷たくもあり、
羨ましさを含んでいるようにも聞こえた。
買い物から家に戻っても、想像以上に胸の鼓動は収まらなかった。
柿本と別れてからも、乳首は巨峰のように固く勃ち、
ニット生地の下で自己主張を続けている。
外からは目立たないが、デニムの股間もしっとりと湿っていた。
心なしか、自分でも感じるほどの雌の匂いがふと鼻をかすめる。
(堪らない。視線の刺激が堪らない。見られている私。)
堪らない衝動がせり上がり、
キッチンの椅子に腰を下ろして乳首に指を伸ばしかけた、そのとき——
目の前のテーブルの端に、見慣れた弁当箱がぽつんと置かれているのが目に入った。
(……昴流の)
壁掛け時計の針は午前十時半を指している。
今から行けば、昼休み前には十分間に合う。
火照った身体のまま立ち上がり、玄関へ向かう途中で、一瞬だけ立ち止まる。
着替えるべきだと理性が囁く。
だが、その上からカーディガンを羽織れば……。
胸の動きは隠せなくても、直接的な輪郭はぼやけるはずだ。
(……見せてるんじゃない。見られてるだけ)
そう自分に言い訳をしながら、カーディガンの袖を通した。
玄関を出ると、昼前の空気は澄んでいて、
アスファルトから立ち上る匂いが混じる。
歩くたび、カーディガンの下で自由を得た乳房が揺れ、
その重みがデニム越しに股間の熱を刺激する。
階段や坂道を下るときの縦揺れが、太ももの内側まで熱を伝えてきた。
(学校……神聖な場所な場所なのに……)
背徳感が胸をさらに張らせ、ニットの下で乳首の硬さをさらに際立たせる。
校門をくぐると、低学年の子どもたちの笑い声が遠くから響いてくる。
昇降口付近には数人の保護者が立ち話をしていて、
その視線が胸元をかすめたような錯覚に、心拍が跳ね上がる。
ガラス窓や掲示板の反射に映る自分の姿。
そこには、カーディガン越しにわずかに突き上げる形がはっきりと浮き出ていた。
昴流の担任・山路は、職員室横の応接コーナーに腰掛けていた。
「わざわざすみません、八神さん」
差し出した弁当箱を受け取る山路の視線が、一瞬だけ胸元へと落ちた。
(……今の、見た?)
心拍がさらに速くなる。
「昴流くん、最近授業態度がとても落ち着いてきました」
「そうですか……よかったです」
「お母さんも、なんだか最近、雰囲気が変わりましたね」
「え?」
「以前より自信を持たれているというか……表情が明るい」
褒め言葉に聞こえるが、その奥に探るような響きが混じる。
「まあ……人は変わりますから」
翔子は曖昧に返すと、山路は少し笑みを深め、声を落とした。
「気をつけてくださいね。世の中には、悪意を持って見る人もいますから」
その優しい忠告は、康人にはない“守ってくれている感覚”を呼び起こす。
胸の奥で、小さな愛情の芽が顔を出すのを翔子は否定できなかった。
面談を終え廊下を歩くたび、カーディガンの下で乳房が揺れ、
(……やっぱり、見られてた)
という確信と、そこに混じる甘い興奮が足取りを少しだけ軽くした。
翔子の耳には昨夜の熱がまだこもっている気がした。
ベッドから起き上がると、薄いニットセーターを手に取る。
インナーの引き出しを開けた指先は、
わざとブラジャーを素通りした。
(今日は……つけない)
胸の奥で、軽く笑うような、震えるような感覚があった。
ニットの生地は柔らかいが、薄手のため形を拾いやすい。
乳首の膨らみは、姿勢を正せばクッキリと主張するだろう。
鏡の前で肩を引き、背筋を伸ばす。
布の下で、重みを持った乳房が大きくたわむのが自分でも分かった。
歩けば――もっと裸のままの乳房であることがはっきりする。
昨夜の夜翔としての高揚感が、まだ身体を温め続けていた。
町内の路地を抜け、集積所へ向かう。
すれ違う近所の主婦や老人たちの視線が、
自分に少し長くとどまっている気がした。
「……あの人……」
風に混じって届く囁きは、言葉にならないまま背中をくすぐる。
歩くたび、ニットの上からでも
乳房が大きく揺れるのを、自分でも意識してしまう。
心臓の鼓動は下腹に響き、足取りが微かに弾んだ。
午前十時過ぎ、町内の集会場の前で数人が談笑していた。
塚本、加賀美、そして山根。
視線が一瞬こちらに集まり、笑い声のトーンが変わる。
「最近、おかしいよね」
「……なんか、色っぽくなったというか」
「そう?いやらしくなったって思うけど。私は」
「確かに、今までの翔子さんの雰囲気とは違うよね」
その断片が、翔子の耳に入り込む。
(色っぽくなった……?いやらしい……?)
悪意だけではない、
わずかに含まれた羨望の響きに、胸の奥がじんとした。
午後、買い物に出た。今日はパートの公休日。
いつもは接客をしているニッコリマートでの夕飯の買い出し。
自動ドアが開くと同時に、冷気と惣菜の匂いが頬を撫でた。
ブラは――着けていない。
歩くたびに胸の中で揺れる重みが、
ブラのない自由さを誇示するように主張してくる。
(……やっぱり、わかるかな)
胸の先端が、ニット越しに自己主張しているのを自分でも感じる。
布地を押し上げる形は、隠そうにも隠せない。
入口近くの青果コーナーでキャベツを手に取ったとき、
横の鏡面棚に自分の姿が映った。
(……はっきり、わかる)
乳首の膨らみが、鏡越しの自分に突きつけられる。
見られているのではなく、自分で自分を見てしまう。
――それだけで、下腹がふっと温かくなる。
夜翔の時間が、昼の日常にまで侵食してきている。
果物売り場を抜け、総菜コーナーへ向かうと、
ふいに背後から視線を感じた。
振り返らなくてもわかる。
中年男性客がトレーを手に、
商品棚ではなく自分の胸元に焦点を合わせている。
(見られてる……)
その瞬間、乳首の先がピンと硬くなり、
布地にさらにくっきりと浮かび上がった。
通路を移動するたび、
ガラスケースや冷蔵扉に映る自分の胸が目に入る。
体温と冷気の温度差で、感覚が研ぎ澄まされていく。
(これは……夜翔のせいだ)
心の中で呟きながらも、足は鮮魚コーナーへと自然に向かっていた。
乳首の隆起を意識するたびに下腹部が熱くなる。
買い物中であるにもかかわらず、欲情が色を帯びてくる。
(もっと、もっと、見られたい。私を意識されたい…)
他人の視線を意識しながら鮮魚売り場に移動した。
銀色に輝くアジを手に取ったそのとき、背後から肩を軽く叩かれた。
振り返ると、同僚の柿本明日香が立っていた。
「ちょっと、翔子さん……」
指で示されるまま、売り場の隅へ。
「今日、ブラ付けてないよね。さっきから……見られてるよ」
冷蔵ケースのモーター音に混じって、
その言葉が翔子に静かにでもはっきりと届いた。
翔子は唇だけで笑った。
「でも……見せてるんじゃないよ」
「うん。分かってる。でも、
まるわかりだよ。服装も考えなよ。ニットじゃなくて」
柿本はおそらく同僚として、
バレーボールの仲間として忠告してくれているのは明らかだ。
「実はね、乳首が炎症起こしててね。
医者にも、生地の擦れで悪化するって言われてるの」
言い訳をした――完全な嘘だ。
でも、そう言い聞かせると、なぜか胸がひとつ、軽くなった気がした。
柿本はしばらく翔子の胸元を見て、ため息をついた。
「そうなんだ。わかった。……でも、気をつけなよ」
柿本は短くそう言い残して仕事に戻った。
柿本の言葉は少し冷たくもあり、
羨ましさを含んでいるようにも聞こえた。
買い物から家に戻っても、想像以上に胸の鼓動は収まらなかった。
柿本と別れてからも、乳首は巨峰のように固く勃ち、
ニット生地の下で自己主張を続けている。
外からは目立たないが、デニムの股間もしっとりと湿っていた。
心なしか、自分でも感じるほどの雌の匂いがふと鼻をかすめる。
(堪らない。視線の刺激が堪らない。見られている私。)
堪らない衝動がせり上がり、
キッチンの椅子に腰を下ろして乳首に指を伸ばしかけた、そのとき——
目の前のテーブルの端に、見慣れた弁当箱がぽつんと置かれているのが目に入った。
(……昴流の)
壁掛け時計の針は午前十時半を指している。
今から行けば、昼休み前には十分間に合う。
火照った身体のまま立ち上がり、玄関へ向かう途中で、一瞬だけ立ち止まる。
着替えるべきだと理性が囁く。
だが、その上からカーディガンを羽織れば……。
胸の動きは隠せなくても、直接的な輪郭はぼやけるはずだ。
(……見せてるんじゃない。見られてるだけ)
そう自分に言い訳をしながら、カーディガンの袖を通した。
玄関を出ると、昼前の空気は澄んでいて、
アスファルトから立ち上る匂いが混じる。
歩くたび、カーディガンの下で自由を得た乳房が揺れ、
その重みがデニム越しに股間の熱を刺激する。
階段や坂道を下るときの縦揺れが、太ももの内側まで熱を伝えてきた。
(学校……神聖な場所な場所なのに……)
背徳感が胸をさらに張らせ、ニットの下で乳首の硬さをさらに際立たせる。
校門をくぐると、低学年の子どもたちの笑い声が遠くから響いてくる。
昇降口付近には数人の保護者が立ち話をしていて、
その視線が胸元をかすめたような錯覚に、心拍が跳ね上がる。
ガラス窓や掲示板の反射に映る自分の姿。
そこには、カーディガン越しにわずかに突き上げる形がはっきりと浮き出ていた。
昴流の担任・山路は、職員室横の応接コーナーに腰掛けていた。
「わざわざすみません、八神さん」
差し出した弁当箱を受け取る山路の視線が、一瞬だけ胸元へと落ちた。
(……今の、見た?)
心拍がさらに速くなる。
「昴流くん、最近授業態度がとても落ち着いてきました」
「そうですか……よかったです」
「お母さんも、なんだか最近、雰囲気が変わりましたね」
「え?」
「以前より自信を持たれているというか……表情が明るい」
褒め言葉に聞こえるが、その奥に探るような響きが混じる。
「まあ……人は変わりますから」
翔子は曖昧に返すと、山路は少し笑みを深め、声を落とした。
「気をつけてくださいね。世の中には、悪意を持って見る人もいますから」
その優しい忠告は、康人にはない“守ってくれている感覚”を呼び起こす。
胸の奥で、小さな愛情の芽が顔を出すのを翔子は否定できなかった。
面談を終え廊下を歩くたび、カーディガンの下で乳房が揺れ、
(……やっぱり、見られてた)
という確信と、そこに混じる甘い興奮が足取りを少しだけ軽くした。
0
あなたにおすすめの小説


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。
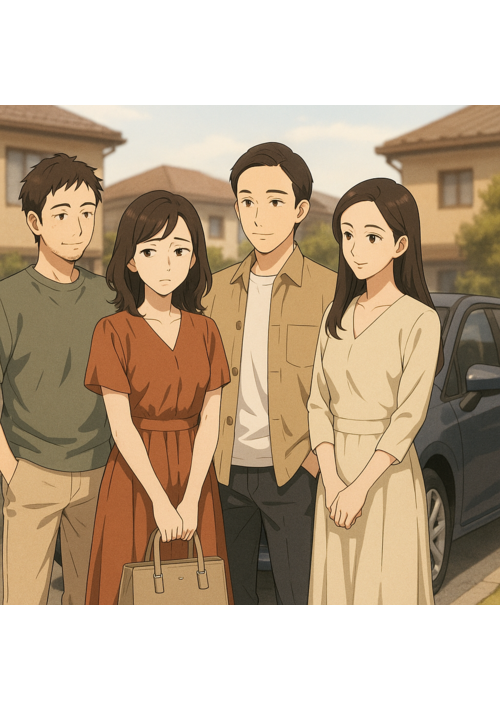



上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















