49 / 61
霜夜の冬・ミツキの雪
プレゼントはわたし?
しおりを挟む
病院を退院した僕は、もはや風前《ふうぜん》の灯《ともしび》のような身体を引きずり、なんとか帰宅することができた。そして、クリスマス一週間前に三億円の代償を知ることとなった。連日ワイドショーを賑わせる僕の容態は、自分の身体のことを知っている僕が思うよりも酷い有様。明日死んでも、いや今日死んでもおかしくないほどに最悪な病態《びょうたい》を報道している。いったいどこの誰の情報なのだろう。とにかく、僕に集まる同情が度を過ぎていることを理解したのは、大量の手紙が自宅に届いた時だった。大きな段ボールで三箱分が届いたときには、すべて読むことなど不可能に近い、と諦めざるを得なかった。
そんな僕の世間の注目に反して、花神楽美月《はなかぐらみつき》への世間の視線は冷たいもので、連日連夜、彼女の飲酒に対するバッシングは酷くなる一方だった。過去の不倫騒動まで蒸し返して、飲酒に絡めて袋叩きにする有様は見ていられない。
ちょうど冬休みに入り、学校に行かなくて良くなったミツキがどれほど安堵したか、その表情を見ても明らかだ。家の前まで記者が来ることがないだけまだいい、なんてミツキは言うのだけれど、エゴサーチをしなくても自分の情報を見せつけられるのは、どんなにミツキが強靭《きょうじん》な精神の持ち主だろうと、そのうち参ってしまうのではないかと、僕は心配している。
僕が花山健逸《はなやまけんいつ》に必ずして欲しいことを電話で伝えている最中、ミツキが僕の部屋をノックする。慌てて電話を切った僕は、どうぞ、と扉の向こうに告げた。おはよう、と俯き加減で歩み寄るミツキは、白とピンクのボーダーのニーハイソックスと、赤いギンガムチェックのミニスカートとの間の絶対領域の僅かな肌が白く、白いセーターで包んだ上半身は雲のように柔らかそうで、まるでアイドルのよう。いや、アイドルなのだけれども。
「ミツキどうしたの、こんなに朝早く」
「あ、もしかして、なにか大事な電話をしてた?」
「いや、大丈夫だよ」
「もしかして、この前の健逸さんて人?」
病院で見られてしまった花山健逸の名前は、スマホの画面に入ったひびのせいでフルネームまでは知られなかった。だけど、健逸というワードは知られてしまった。わたしのお父さんも健逸っていう名前なの、と言ったミツキに父だと気付かれなくてほっとしたのも束《つか》の間。一体誰なの、と質問攻めに遭《あ》うはめに。ごまかし切れなくなってきたのも事実で、もはや真実を告げるしかない段階にきている。
「ああ、うん。そう」
「そうなんだ。シュン君、あのね、昨晩、全然眠れなくて」
「ミツキに隠していたことがある。ごめん」
「————なにを?」
花山健逸との約束は破ることになってしまう。いや、約束などしてはいない。だけど、話すことで、もし花山健逸と会いたいなんてミツキが言い出せば、きっとまたトラブルに巻き込まれる。それだけは避けなくてはいけない。
「これから話すことは、ミツキにとってすごくショックなことかもしれないし、気分を害する話かもしれない。それと、僕の言うことは絶対に守ると約束して」
怪訝《けげん》そうな表情でミツキはベッドに腰掛ける僕の隣に座り、膝の上に置いた僕の右手にそっと左手を重ねた。ミツキは横を見る僕の瞳を見据えて言う。うん、わかったわ、と。
★☆☆
三者面談の日に出会った花山健逸は酷く怯《おび》えていたにも関わらず、会社を守ろうとしていたこと。ミツキに会うことができない理由は、楠川田賢二《くすかわだけんじ》のせいだということ。そして、時系列としては逆になってしまうけれど、少し話すのを躊躇《ためら》ったミツキの拉致事件の引き金について。楠川田賢二による花山健逸の脅迫が裏で行われていたこと。つまりミツキの知らないところで、ミツキは人質にされていたということ。志桜里と碧唯を巻き込んで。深呼吸をした後、ようやく僕はそれを話す決断をした。おそらく、如月智一《きさらぎともかず》との不倫疑惑を無理やりでっち上げたのも、その一連の流れがあったからだ、ということも。また花山健逸とミツキが会えば恐らく何らかの不都合が生じるために、楠川田賢二が会わないように仕向けていたことも。ミツキは茫然《ぼうぜん》として、まるで生気を抜かれた西洋の人形のような表情で僕を見ていた。
「だから、お父さんの件を話せなかったんだ。ごめん」
「……お父さんが。やっぱりお父さんなの?」
「違うよ。お父さんのせいだけど、お父さんも被害者だよ。一番悪いのは、悪事を働いている楠川田だ」
流れ落ちる一筋の涙が伝うミツキの頬は、朝日に照らされてキラキラと。砕かれたダイヤモンドの欠片のように反射する雫を、僕は指で拭った。ごめん、と言って僕はミツキを抱き締める。だけど、抱きしめ返してこないミツキは耳元で呟く。それでわたしが狙われていたのね、と。柔らかいセーターの生地を摩《さす》ると、ミツキは突然僕を抱き締める。そして、わんわん泣いた。今まで堪えてきた感情をすべて吐き出すように。
「それでミツキにお願いがあるんだ」
「お……ねがい?」
「ミツキの知り合いの著名人を僕に紹介して欲しい。一人の残らずすべて。電話番号でもメールアドレスでも。インストのアカウントでも、ツイーターのアカウントでも構わない。あとは僕がなんとかするから」
顔を上げたミツキは、僕が何か危険なことに足を踏み入れるのではないかと疑ったのだと思う。涙を拭って真剣な眼差しを向けるミツキの瞳は、いつもの硝子玉のような美しさを模《も》している反面、まるで僕の内心を見抜くかのように鋭く、直視できないほどその視線が痛かった。僕の肩を持って静かにかぶりを振るミツキは、やめて、と言う。
「シュン君がなにをしようとしているかは分からないけど、もう関わるのはやめて。被害に遭うのはもう、わたし一人で十分だから。もし、シュン君に何かあったら、わたしは————」
「ミツキ。僕を信じて。こんなこと言いたくないけど、もし僕に何かあったら、僕は死ぬ間際に後悔する。あの時ミツキを救ってあげられなかったって。だから、思うままにさせて欲しい」
「もうッ!! そんなこと言わないでよ!! それにずるい。そんなこと……そ……んなこと……言われたら」
また泣き始めるミツキを抱擁《ほうよう》する。今度は何も言わず無言で。髪を梳《す》いて、背中を摩って。ただ泣きじゃくるミツキがすべてを吐き出すのを待つ。ひたすら。
☆★☆
午後になると、ミツキはどうしても買い物に行きたいと言い出して聞かなかった。クリスマスを来週に控えて、買いたいものが山ほどある、と。だけど、このスキャンダルの最中に、僕とミツキがその辺に現れたら、いったいどうなってしまうのか。予想すらつかない。
「大丈夫。変装すればなんとかなるよ。シュン君は身体のこともあるし、休んでいて」
「絶対にだめ。ミツキが行くなら、僕も行く。ミツキに何かあったらどうするの」
もう言い出したら聞かないんだから、と言ったミツキに言葉をそのまま返したい。結局、黒いウィッグを付けて、ショートカットの髪型になったミツキと、ニット帽に大きい黒ぶち眼鏡を掛けさせられて、変装とは言えないのではないかと思う容姿の僕は、バスに揺られてショッピングモールに向かう。
「ねえ、通販で買えば済む話なんじゃないの?」
「そうなんだけど、たまに外の空気を吸わないと精神的にきちゃって」
僕がいてもだめなの、と言った僕は自意識過剰なのだろうか。そういう意味じゃないよ、なんて言うミツキの言いたいことは分かる。だけど、外に出てしまえば、危険性はかなり高い。初デートのようなゾンビの生息地とは違い、きっと、イオンは今頃、死肉を貪《むさぼ》るハイエナの集団の巣のような様相を見せているはず。飲酒疑惑のミツキは、一瞬で骨の髄までしゃぶられて、帰宅困難になってしまうかもしれない。
「ごめんね。ワガママで。でも、どうしても通販じゃなくて現物を見たいの。クリスマスだから」
「もし、ミツキに何かあったら、僕が命に代えても守るから。だから存分に見ていいよ」
なんて僕は言ってみたものの、何も起きないだろうとは思っていた。せいぜい冷たい視線を感じるくらいで、何かの行動を起こすような人柄の人は、この田舎にはいない、はず。
「命に代えなくても大丈夫。シュン君が言うとリアリティがあって、本当に怖いの」
確かに、なんて納得してしまう僕は、少しばかり死に慣れっこになってしまったのかもしれない。自虐的に自分の境遇を口にできるくらいになっているのだから。でも、それがミツキにとって辛いみたい。本気なのか冗談なのか分からない、なんて。それもそうかもしれないな。
バスに揺られて一〇分。まるで荒れ地のように何もない田んぼに挟まれた複合施設は、寒空の下に佇んでいた。巨大な城は相も変わらず駐車場が満車になるほど人気で、家族連れとカップルで賑わいを見せる。たまに男子高生の集団を見るけれど、彼らはゲーセンに行くか、フードコートに意味もなく居座り続ける暇人たち。女子高生は何故か集団では見ない。いても、二人組か三人組くらい。
巨大な扉を潜った先はレストラン街で、ホールのピアノに人だかりができている。ピアニストが奏でるクリスマスソングは定番のマライアキャリー。タップダンスでも披露したくなるような軽快なジャズアレンジのリズムに、子供たちが自然と飛び跳ねていた。僕が将来ダンススタジオでも経営すれば、この子たちは来てくれるかな、なんて話すと、ミツキは大賛成してくれた。
「シュン君が先生だったら、いっぱい生徒が集まるね!」
「そうかな。でも、ミツキがいればきっと集まるよね」
えへへ、なんて笑ったミツキの手を取って、エスカレーターを上がっていく。吹き抜けの天井に感動はしなくなったものの、天然石のアクセサリーショップのガラスウィンドウの中に、ミツキは感嘆の声を上げる。タケノコあるよ、なんて。タケノコと呼ばれた水晶は春から売れることなくずっと置いてあるらしい。五万円という高値で買う人はよほどのタケノコファンだ、とミツキは分析していた。
「シュン君のクリスマスプレゼントがね、悩んじゃって何がいいか分からないの。だから、聞きます。欲しいものある?」
「あ……。もしかして、それで来たの!?」
こくりと頷くミツキは、ショーウィンドウの中の照明に照らされた硝子玉の瞳が、春の時よりも煌《きら》めいているように見えた。僅か八カ月でここまで違う表情を見せるのは、やはり僕のせいなのだろうか。大人になっていくミツキを見るのが少しだけ寂しい。けど、それは、もしかしたら僕の色に染まってくれているからなのかな、なんて自分勝手にも思う。
僕のために生きる、と最近口にするミツキは、自分で自分を重い女と称する。全然そんなことないのに。むしろ、僕がミツキの色に染まっていることにミツキは気付いているのだろうか。彼女のためなら命を落とすことすらいとわない。そう、僕は自虐的でもなんでもない。本気だ。最悪、楠川田を道連れにする覚悟すらある。だから、命に代えてもミツキを救い出してみせる。
「シュン君って、欲しいものとかないんでしょ。物欲がないもんね」
「だって、現状で満足しちゃってるから。ミツキがいてくれればなにもいらないって言ってるでしょ」
「じゃあ、クリスマスプレゼントはわたしでいいわけ?」
「ああ、うん。それがいいかな。最高じゃないそれ」
もう、と言って膨れるミツキは、すごく嬉しそう。横目で僕を見て、しばらくすると噴出《ふきだ》した。わたしが箱に入って、プレゼントになっても、シュン君が気付いてくれなくてずっと閉じ込められるのは嫌だな、なんて言って。想像すると笑える。僕も思わず噴出した。
「久々に笑ったぁ。それにしても、困ったなぁ」
「逆に、ミツキは欲しいものないの?」
「シュン君がいい」
「それは無理。だって、僕、箱に入って忘れられるの嫌だもん」
そのネタはもういいよ、と笑うミツキの涙は、悲しみを帯びていない雫。自分が言い出したんじゃない、と言った僕に対してさらにお腹を抱えて笑うミツキは、とても、とても可愛らしい。やはり笑っているミツキの方が遥かにミツキらしい。いつも笑っていられるように早くしてあげないと。
「ああ、可笑《おか》しい。シュン君の物欲がない問題はさておき、飾り付けしたいから、例の雑貨屋さん行きたいんだけどいい?」
もちろん、と言って僕はミツキの左手を引いた。僕とミツキが歩いていることに気付く人が思った以上におらず、僕は胸を撫でおろしていた。どう考えても、僕とミツキが歩いていれば後ろ指を差されてもおかしくないのだけれども。
雑貨屋に差し掛かった時、目が合った女子高生は、僕を見るなり、あっ、と声を上げた。しかし、それ以上何も言うことがなく、ミツキを一瞥して立ち去る姿は、まるで僕に気を使っているよう。
その女子高生が気になったわけではないのだけれども。なんとなくツイーターをエゴサーチすれば、ハッシュタグとともに添えられた言葉は、シュンさまの最期はそっと二人きりに、と。意味が分からなかったけれど、よくよく見てみれば、僕とミツキが笑いながら歩く姿の写真や、手を繋いでいる仲睦《なかむつ》まじい写真が次から次へと出てくる。ミツキに対する皮肉や誹謗中傷もかなりあったものの、僕に対する言葉は、どれも優しい声ばかり。確かに、今すぐ死ぬ、と毎日ワイドショーが毎日のように言葉を連ねていれば、そういう流れになるのも当然か。ただ、一割程度は、僕に対しての誹謗中傷もあるのだけれども。
「ねえ、わたしこれ欲しいかも」
手に取った男の子を模したウサギのぬいぐるみを見てそう言うミツキは、もう一つ女の子のウサギのぬいぐるみを手にする。肩越しにそのウサギを見ると、なぜか女の子の方はミツキに似ている。
「ミツキにそっくりだね」
「え? わたしこんな顔してるの!?」
「え。だから欲しいんじゃなくて?」
「違うよ、この男の子がね、シュン君そっくりだから」
え。僕ってそんな間抜けな顔してるの。なんて言うと、ミツキは、うん、なんて。
「冗談だよ。でも、なんか寝ている時のシュン君みたいで可愛いの」
「やっぱり寝顔が間抜けって言ってるじゃん」
「あはは。そんなことないよ」
「でも、僕もそのウサギがいい。ミツキにそっくりだし」
「わたしは、こんな間抜けな顔しないでしょ。え、してる?」
「寝顔がそっくり……」
「もう。寝顔はみんな間抜けなの。いいじゃない。寝顔なんて毎日見てるんだから、それに、たまには間抜けな顔くらいする……よね?」
愛おしそうに抱かれたウサギは、間抜けながらも幸せそうな表情で笑っていて、お互いにそのウサギを買ってクリスマスにプレゼントし合うことになった。
間抜けな顔ができるなら、それでいい。そう思う。悲痛な表情を浮かべてうなされるミツキをもう見たくないから。多分、ミツキも僕に対してそう思っている。
クリスマスプレゼント、大事にするね。
そんな僕の世間の注目に反して、花神楽美月《はなかぐらみつき》への世間の視線は冷たいもので、連日連夜、彼女の飲酒に対するバッシングは酷くなる一方だった。過去の不倫騒動まで蒸し返して、飲酒に絡めて袋叩きにする有様は見ていられない。
ちょうど冬休みに入り、学校に行かなくて良くなったミツキがどれほど安堵したか、その表情を見ても明らかだ。家の前まで記者が来ることがないだけまだいい、なんてミツキは言うのだけれど、エゴサーチをしなくても自分の情報を見せつけられるのは、どんなにミツキが強靭《きょうじん》な精神の持ち主だろうと、そのうち参ってしまうのではないかと、僕は心配している。
僕が花山健逸《はなやまけんいつ》に必ずして欲しいことを電話で伝えている最中、ミツキが僕の部屋をノックする。慌てて電話を切った僕は、どうぞ、と扉の向こうに告げた。おはよう、と俯き加減で歩み寄るミツキは、白とピンクのボーダーのニーハイソックスと、赤いギンガムチェックのミニスカートとの間の絶対領域の僅かな肌が白く、白いセーターで包んだ上半身は雲のように柔らかそうで、まるでアイドルのよう。いや、アイドルなのだけれども。
「ミツキどうしたの、こんなに朝早く」
「あ、もしかして、なにか大事な電話をしてた?」
「いや、大丈夫だよ」
「もしかして、この前の健逸さんて人?」
病院で見られてしまった花山健逸の名前は、スマホの画面に入ったひびのせいでフルネームまでは知られなかった。だけど、健逸というワードは知られてしまった。わたしのお父さんも健逸っていう名前なの、と言ったミツキに父だと気付かれなくてほっとしたのも束《つか》の間。一体誰なの、と質問攻めに遭《あ》うはめに。ごまかし切れなくなってきたのも事実で、もはや真実を告げるしかない段階にきている。
「ああ、うん。そう」
「そうなんだ。シュン君、あのね、昨晩、全然眠れなくて」
「ミツキに隠していたことがある。ごめん」
「————なにを?」
花山健逸との約束は破ることになってしまう。いや、約束などしてはいない。だけど、話すことで、もし花山健逸と会いたいなんてミツキが言い出せば、きっとまたトラブルに巻き込まれる。それだけは避けなくてはいけない。
「これから話すことは、ミツキにとってすごくショックなことかもしれないし、気分を害する話かもしれない。それと、僕の言うことは絶対に守ると約束して」
怪訝《けげん》そうな表情でミツキはベッドに腰掛ける僕の隣に座り、膝の上に置いた僕の右手にそっと左手を重ねた。ミツキは横を見る僕の瞳を見据えて言う。うん、わかったわ、と。
★☆☆
三者面談の日に出会った花山健逸は酷く怯《おび》えていたにも関わらず、会社を守ろうとしていたこと。ミツキに会うことができない理由は、楠川田賢二《くすかわだけんじ》のせいだということ。そして、時系列としては逆になってしまうけれど、少し話すのを躊躇《ためら》ったミツキの拉致事件の引き金について。楠川田賢二による花山健逸の脅迫が裏で行われていたこと。つまりミツキの知らないところで、ミツキは人質にされていたということ。志桜里と碧唯を巻き込んで。深呼吸をした後、ようやく僕はそれを話す決断をした。おそらく、如月智一《きさらぎともかず》との不倫疑惑を無理やりでっち上げたのも、その一連の流れがあったからだ、ということも。また花山健逸とミツキが会えば恐らく何らかの不都合が生じるために、楠川田賢二が会わないように仕向けていたことも。ミツキは茫然《ぼうぜん》として、まるで生気を抜かれた西洋の人形のような表情で僕を見ていた。
「だから、お父さんの件を話せなかったんだ。ごめん」
「……お父さんが。やっぱりお父さんなの?」
「違うよ。お父さんのせいだけど、お父さんも被害者だよ。一番悪いのは、悪事を働いている楠川田だ」
流れ落ちる一筋の涙が伝うミツキの頬は、朝日に照らされてキラキラと。砕かれたダイヤモンドの欠片のように反射する雫を、僕は指で拭った。ごめん、と言って僕はミツキを抱き締める。だけど、抱きしめ返してこないミツキは耳元で呟く。それでわたしが狙われていたのね、と。柔らかいセーターの生地を摩《さす》ると、ミツキは突然僕を抱き締める。そして、わんわん泣いた。今まで堪えてきた感情をすべて吐き出すように。
「それでミツキにお願いがあるんだ」
「お……ねがい?」
「ミツキの知り合いの著名人を僕に紹介して欲しい。一人の残らずすべて。電話番号でもメールアドレスでも。インストのアカウントでも、ツイーターのアカウントでも構わない。あとは僕がなんとかするから」
顔を上げたミツキは、僕が何か危険なことに足を踏み入れるのではないかと疑ったのだと思う。涙を拭って真剣な眼差しを向けるミツキの瞳は、いつもの硝子玉のような美しさを模《も》している反面、まるで僕の内心を見抜くかのように鋭く、直視できないほどその視線が痛かった。僕の肩を持って静かにかぶりを振るミツキは、やめて、と言う。
「シュン君がなにをしようとしているかは分からないけど、もう関わるのはやめて。被害に遭うのはもう、わたし一人で十分だから。もし、シュン君に何かあったら、わたしは————」
「ミツキ。僕を信じて。こんなこと言いたくないけど、もし僕に何かあったら、僕は死ぬ間際に後悔する。あの時ミツキを救ってあげられなかったって。だから、思うままにさせて欲しい」
「もうッ!! そんなこと言わないでよ!! それにずるい。そんなこと……そ……んなこと……言われたら」
また泣き始めるミツキを抱擁《ほうよう》する。今度は何も言わず無言で。髪を梳《す》いて、背中を摩って。ただ泣きじゃくるミツキがすべてを吐き出すのを待つ。ひたすら。
☆★☆
午後になると、ミツキはどうしても買い物に行きたいと言い出して聞かなかった。クリスマスを来週に控えて、買いたいものが山ほどある、と。だけど、このスキャンダルの最中に、僕とミツキがその辺に現れたら、いったいどうなってしまうのか。予想すらつかない。
「大丈夫。変装すればなんとかなるよ。シュン君は身体のこともあるし、休んでいて」
「絶対にだめ。ミツキが行くなら、僕も行く。ミツキに何かあったらどうするの」
もう言い出したら聞かないんだから、と言ったミツキに言葉をそのまま返したい。結局、黒いウィッグを付けて、ショートカットの髪型になったミツキと、ニット帽に大きい黒ぶち眼鏡を掛けさせられて、変装とは言えないのではないかと思う容姿の僕は、バスに揺られてショッピングモールに向かう。
「ねえ、通販で買えば済む話なんじゃないの?」
「そうなんだけど、たまに外の空気を吸わないと精神的にきちゃって」
僕がいてもだめなの、と言った僕は自意識過剰なのだろうか。そういう意味じゃないよ、なんて言うミツキの言いたいことは分かる。だけど、外に出てしまえば、危険性はかなり高い。初デートのようなゾンビの生息地とは違い、きっと、イオンは今頃、死肉を貪《むさぼ》るハイエナの集団の巣のような様相を見せているはず。飲酒疑惑のミツキは、一瞬で骨の髄までしゃぶられて、帰宅困難になってしまうかもしれない。
「ごめんね。ワガママで。でも、どうしても通販じゃなくて現物を見たいの。クリスマスだから」
「もし、ミツキに何かあったら、僕が命に代えても守るから。だから存分に見ていいよ」
なんて僕は言ってみたものの、何も起きないだろうとは思っていた。せいぜい冷たい視線を感じるくらいで、何かの行動を起こすような人柄の人は、この田舎にはいない、はず。
「命に代えなくても大丈夫。シュン君が言うとリアリティがあって、本当に怖いの」
確かに、なんて納得してしまう僕は、少しばかり死に慣れっこになってしまったのかもしれない。自虐的に自分の境遇を口にできるくらいになっているのだから。でも、それがミツキにとって辛いみたい。本気なのか冗談なのか分からない、なんて。それもそうかもしれないな。
バスに揺られて一〇分。まるで荒れ地のように何もない田んぼに挟まれた複合施設は、寒空の下に佇んでいた。巨大な城は相も変わらず駐車場が満車になるほど人気で、家族連れとカップルで賑わいを見せる。たまに男子高生の集団を見るけれど、彼らはゲーセンに行くか、フードコートに意味もなく居座り続ける暇人たち。女子高生は何故か集団では見ない。いても、二人組か三人組くらい。
巨大な扉を潜った先はレストラン街で、ホールのピアノに人だかりができている。ピアニストが奏でるクリスマスソングは定番のマライアキャリー。タップダンスでも披露したくなるような軽快なジャズアレンジのリズムに、子供たちが自然と飛び跳ねていた。僕が将来ダンススタジオでも経営すれば、この子たちは来てくれるかな、なんて話すと、ミツキは大賛成してくれた。
「シュン君が先生だったら、いっぱい生徒が集まるね!」
「そうかな。でも、ミツキがいればきっと集まるよね」
えへへ、なんて笑ったミツキの手を取って、エスカレーターを上がっていく。吹き抜けの天井に感動はしなくなったものの、天然石のアクセサリーショップのガラスウィンドウの中に、ミツキは感嘆の声を上げる。タケノコあるよ、なんて。タケノコと呼ばれた水晶は春から売れることなくずっと置いてあるらしい。五万円という高値で買う人はよほどのタケノコファンだ、とミツキは分析していた。
「シュン君のクリスマスプレゼントがね、悩んじゃって何がいいか分からないの。だから、聞きます。欲しいものある?」
「あ……。もしかして、それで来たの!?」
こくりと頷くミツキは、ショーウィンドウの中の照明に照らされた硝子玉の瞳が、春の時よりも煌《きら》めいているように見えた。僅か八カ月でここまで違う表情を見せるのは、やはり僕のせいなのだろうか。大人になっていくミツキを見るのが少しだけ寂しい。けど、それは、もしかしたら僕の色に染まってくれているからなのかな、なんて自分勝手にも思う。
僕のために生きる、と最近口にするミツキは、自分で自分を重い女と称する。全然そんなことないのに。むしろ、僕がミツキの色に染まっていることにミツキは気付いているのだろうか。彼女のためなら命を落とすことすらいとわない。そう、僕は自虐的でもなんでもない。本気だ。最悪、楠川田を道連れにする覚悟すらある。だから、命に代えてもミツキを救い出してみせる。
「シュン君って、欲しいものとかないんでしょ。物欲がないもんね」
「だって、現状で満足しちゃってるから。ミツキがいてくれればなにもいらないって言ってるでしょ」
「じゃあ、クリスマスプレゼントはわたしでいいわけ?」
「ああ、うん。それがいいかな。最高じゃないそれ」
もう、と言って膨れるミツキは、すごく嬉しそう。横目で僕を見て、しばらくすると噴出《ふきだ》した。わたしが箱に入って、プレゼントになっても、シュン君が気付いてくれなくてずっと閉じ込められるのは嫌だな、なんて言って。想像すると笑える。僕も思わず噴出した。
「久々に笑ったぁ。それにしても、困ったなぁ」
「逆に、ミツキは欲しいものないの?」
「シュン君がいい」
「それは無理。だって、僕、箱に入って忘れられるの嫌だもん」
そのネタはもういいよ、と笑うミツキの涙は、悲しみを帯びていない雫。自分が言い出したんじゃない、と言った僕に対してさらにお腹を抱えて笑うミツキは、とても、とても可愛らしい。やはり笑っているミツキの方が遥かにミツキらしい。いつも笑っていられるように早くしてあげないと。
「ああ、可笑《おか》しい。シュン君の物欲がない問題はさておき、飾り付けしたいから、例の雑貨屋さん行きたいんだけどいい?」
もちろん、と言って僕はミツキの左手を引いた。僕とミツキが歩いていることに気付く人が思った以上におらず、僕は胸を撫でおろしていた。どう考えても、僕とミツキが歩いていれば後ろ指を差されてもおかしくないのだけれども。
雑貨屋に差し掛かった時、目が合った女子高生は、僕を見るなり、あっ、と声を上げた。しかし、それ以上何も言うことがなく、ミツキを一瞥して立ち去る姿は、まるで僕に気を使っているよう。
その女子高生が気になったわけではないのだけれども。なんとなくツイーターをエゴサーチすれば、ハッシュタグとともに添えられた言葉は、シュンさまの最期はそっと二人きりに、と。意味が分からなかったけれど、よくよく見てみれば、僕とミツキが笑いながら歩く姿の写真や、手を繋いでいる仲睦《なかむつ》まじい写真が次から次へと出てくる。ミツキに対する皮肉や誹謗中傷もかなりあったものの、僕に対する言葉は、どれも優しい声ばかり。確かに、今すぐ死ぬ、と毎日ワイドショーが毎日のように言葉を連ねていれば、そういう流れになるのも当然か。ただ、一割程度は、僕に対しての誹謗中傷もあるのだけれども。
「ねえ、わたしこれ欲しいかも」
手に取った男の子を模したウサギのぬいぐるみを見てそう言うミツキは、もう一つ女の子のウサギのぬいぐるみを手にする。肩越しにそのウサギを見ると、なぜか女の子の方はミツキに似ている。
「ミツキにそっくりだね」
「え? わたしこんな顔してるの!?」
「え。だから欲しいんじゃなくて?」
「違うよ、この男の子がね、シュン君そっくりだから」
え。僕ってそんな間抜けな顔してるの。なんて言うと、ミツキは、うん、なんて。
「冗談だよ。でも、なんか寝ている時のシュン君みたいで可愛いの」
「やっぱり寝顔が間抜けって言ってるじゃん」
「あはは。そんなことないよ」
「でも、僕もそのウサギがいい。ミツキにそっくりだし」
「わたしは、こんな間抜けな顔しないでしょ。え、してる?」
「寝顔がそっくり……」
「もう。寝顔はみんな間抜けなの。いいじゃない。寝顔なんて毎日見てるんだから、それに、たまには間抜けな顔くらいする……よね?」
愛おしそうに抱かれたウサギは、間抜けながらも幸せそうな表情で笑っていて、お互いにそのウサギを買ってクリスマスにプレゼントし合うことになった。
間抜けな顔ができるなら、それでいい。そう思う。悲痛な表情を浮かべてうなされるミツキをもう見たくないから。多分、ミツキも僕に対してそう思っている。
クリスマスプレゼント、大事にするね。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

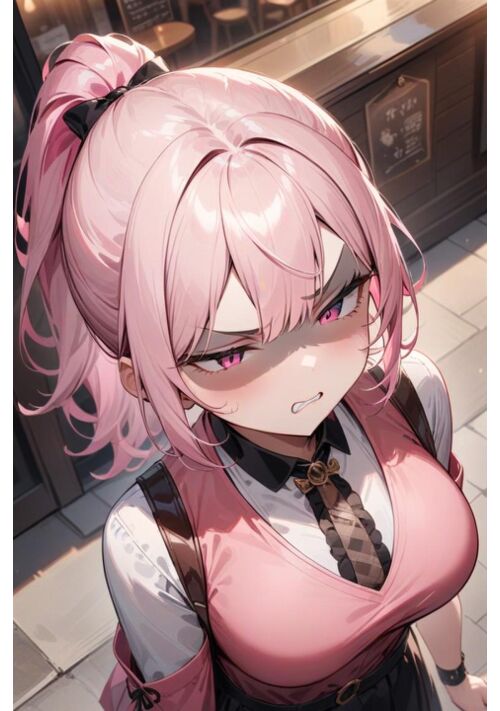
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















