50 / 61
霜夜の冬・ミツキの雪
倉美月春夜という人
しおりを挟む
クリスマスイブを明後日に控えて、僕の人生で最大の試練が訪れた。やってきたのは、都内のスタジオ。僕はある動画を配信するために、伝手《つて》という伝手を使い、なんとかこうして撮影するまでにこぎ着けたのだが。僕の隣で不安な面持ちで俯く花山健逸《はなやまけんいつ》は、本当に大丈夫なのでしょうか、と呟いては嘆息を繰り返している。なんと臆病なのか、と言いたくもなるが、その気持ちが分からなくもない。
明るい柳緑色《りゅうりょくしょく》のスクリーンをバックに、カメラマンとディレクターが何度もテストを繰り返し、花山健逸の会社の社員と思われる人々が、忙しなく行ったり来たりしている。この動画の配信をすれば、楠川田賢二《くすかわだけんじ》がどういう反応を示すのか未知数ではあるものの、きっと業を煮やして僕を責め立てるはず。しかし、僕が危惧しているのは楠川田の反応ではなく、世間がどういう捉え方をするか、である。
僕はこともあろうか、今朝早くに何も言わずに家を出てきた。無論、ミツキにも何も言わずに。だからなのだろう。先ほどからスマホの着信とメッセージがとめどなく画面に溢れていて、心が少し——いや、かなり痛い。家出だとか思われているのかも。終わったらすぐに連絡するから。
だけど、僕が今からしようとしていることは、ミツキに言えばきっと反対される。だからこそ何も言えなかった。しかし、こうする他ない。もし、僕に何かあったら、なんて思うとミツキには本当に申し訳なく思う。
「倉美月さんお願いします」
「はい」
準備が整った。さあ、はじめよう。僕の一世一代の勝負だ。
★☆☆
急いで帰宅すると、涙が枯れ果てました、と言わんばかりの表情で仁王立ちするミツキとその背後の鬼の形相をした姉さんがこちらを睨《にら》みつけながら、無言で僕を迎え入れた。ただいま、などと口にしようものならば、おかえり、などと言う言葉など掛けてもらえるはずもなく、どこに行っていたの、と刺々《とげとげ》しい呪詛《じゅそ》をもらうはめに。
居間のロッキングチェアに座る姉さんは、午後のまだ日も落ちていない時間からビールを片手に、その胸に顔を埋めて抱きつかれたミツキの頭を撫でていた。何この状況。
「シュン、言ったわよね。どんな状況でも女の子を泣かせることは絶対に間違っているって」
「——ごめん」
「せめて行先くらい、言っていきなさいよ。電話も出なければ、メッセに返信もしないなんて。あんたらしくないわよ」
「言っておかなければいけないことがあるんだ」
いつもと様子が違う僕に気付いた姉さんは、ミツキを引き離して立ち上がり、何してきたの、と低い声で訊ねてくる。一方、泣き腫《は》らした瞳を僕に向けるミツキの見上げるその表情は、眉尻を下げていて、今すぐにでも抱きしめてあげたかった。
「楠川田賢二に喧嘩を売ってきた。明日から一週間、全国の電光掲示板とニューチューブで僕の動画が配信される。だから、もし僕に何か————」
ぱちんという音とともに、僕の頬に激しい痛みが広がる。姉さんに頬を叩かれたと認識するまでに時間は掛からなかったけれど、予想外だったのは姉さんが泣いていたことだった。姉さんが泣いたところを見たのは小学生のときが最後で、それ以来見たことがない。なぜ泣いているの、と頬の痛み以上に、その涙が僕の心を激しく殴打する。
「アスカさ……ん?」
立ち上がったミツキは、自分の腕に突っ伏すように顔を隠した姉さんの肩を抱いて、その顔を覗き込む。こんなに弱々しい姉さんを見たのは初めてで、僕はどうすることもできずに、ただその様子を窺うしかできなかった。
「あんた……自分がなにをしているのか……分かっているの?」
「…………うん。分かってる。でも、こうするしか」
「楠川田からミツキちゃんを守るために、おばあちゃんがどれほど苦心したか、あんたは分かってない」
「————え?」
「————どういうことですかアスカさん!?」
ミツキちゃんを記者が追い回さないのはなぜだと思うの。週刊誌に写真が全く載らないのはなぜだと思うの。お母さんだけの力では不可能なの。それに、楠川田が直接ミツキちゃんに手を下すことをしないのはなぜだと思うの。やろうと思えば、もう一度拉致事件を起こすことだって容易なのに。もっとひどいことだってできるのに。それは、おばあちゃんが全てを知っていてミツキちゃんを守っていたからなのよ。
「それにね、あんた、勝手に楠川田と契約なんて結んで。おばあちゃんが先手を打たなかったら、あんたもスキャンダルの餌食になっていたのよ。あの男は、それをネタに、ミツキちゃんを差し出すように仕向けるはずだったの」
「なんで先に言ってくれないんだよ……すべて知っていたんだったら、教えてくれても————」
「あんたの向こう見ずの性格を知っているからよ。キレると大胆なことをするでしょ」
シュン君、と僕を見るミツキが抱きついてくる。僕の胸に顔を埋めて嗚咽《おえつ》を上げながら泣きじゃくるミツキの髪を撫でて、ごめん、と僕は呟く。その言葉を無視するミツキは、どうするのよ、とこの世の終わりのような台詞を吐いた。まるで、僕は世界を終わらせた魔王のよう。言い訳も、気の利いた言葉もすべて脳内を駆け巡ることもせずに霧散していく。自分のしたことは間違っていない、と僕はそれだけを胸に刻みつける。なにも間違っていない。そうでなければいけないんだ。そう、なにも。
☆★☆
クリスマスイブ前日。鳴り響くスマホの通知にうんざりしながら、目を覚ます僕はぼんやりと瞳を開いて、時間がもう正午になることに辟易していた。こんな時間まで起きられないなんて、どれだけ体力が落ちているのか、と。倦怠感《けんたいかん》なんて言葉で表せないような身体の不調は、精神的な面も関係しているのかな。考えないようにしていても、自分の身体のこと、楠川田のこと、それにミツキのことが脳内を堂々巡りしている。、食事も受け付けないほどに参ってしまっている自分に言ってやりたい。いつからそんなに弱くなったのだ、と。
昨晩は珍しくミツキが添い寝を求めて来なかった。部屋に籠ったまま、何かをしている様子だったけれども。気にはなったのだが身体が言うことを聞かず、すぐに横になってしまった。
誰もいない居間のロッキングチェアに座り、テレビをつけて唖然《あぜん》とした。どのチャンネルを回しても、渋谷のスクランブル交差点前の電光掲示板に映る僕の姿が流されている。そして、コメンテーターが話す言葉は、楠川田の会社のこと。あの会社はそんなことする会社ではない、と。至極《しごく》真面目で、社長の楠川田は温厚な人物であることを。
————やはりそう来たか。情報操作されることは間違いないと思っていた。
ミツキノミコトのインストグラム、ツイーター、それにニューチューブ、それぞれのアカウントに届く誹謗中傷の言葉。心無い言葉は、僕に限らずミツキにまで余波が来ているみたい。しかも、ミツキが僕に行動を起こさせた、という流れになっている。これには僕も頭を抱えざるを得なかった。
こんなはずじゃなかった。ミツキを救うはずが、逆効果になってしまったと言っても過言ではない。もしかしたら、姉さんの言うように、触れてはいけないものに触れてしまったのかも。
そして、ついにミツキの元に届いた僕が一番恐れていたこと。
————殺害予告。
居間の引き戸を引いたミツキは、涙を流すこともなく、僕を見つめたまま立ち尽くしていた。スマホを片手に力なくうな垂れる様子は、見ていられないほど弱々しい。すべて僕の責任だし、僕が悪い。謝って済む問題でもないし、第一、未だに僕は自分が間違っていないと思っている。だけど、心のどこかでそれを全否定している自分もいる。どちらが正しいのかなんて判断はできないけれど、ミツキに迷惑をかけていることは間違いない。そこに関してだけ言えば、僕は過ちを犯した。本当に申し訳なく思う。
「ミツキ、あの……」
「————わたしこれからどうしたらいいの?」
「うん……」
何も言えずに言葉が詰まってしまう。こうなった時のことを考えていなかった。確かに僕は向こう見ずの性格だし、詰めが甘かったと言わればそれまでかもしれない。でも、まだチャンスがないわけではない。
絶望が絶望を上塗りするような僕とミツキの周りの空気の中、スマホが鳴り響く。画面を見れば、見知らぬ電話番号。出ない方がいいだろう、と思ったけれど、もしかしたら、吉報の可能性だってあるわけだし。恐る恐る画面をタップして、もしもし、と。
『倉美月くん。あなた勇気があるわね。でも、少しやり方が強引だったかもね』
「新井木《あらいぎ》……さん……どうして」
悲痛な表情に変わるミツキはゆっくりと僕に近づいて、その電話の向こうの声に耳を傾けているよう。新井木遥香は、ミツキにとって天敵のような人物なのだから当然だ。
『あなたと花神楽美月《はなかぐらみつき》を助けてあげようと思って。だけど、条件があるの』
「なにを言っているんです?」
『花神楽美月と別れて、私のものになるなら、全部解決してあげてもいいけれど?』
暑くもないのに不快な汗が背中を伝う。全部解決なんてできるはずが……。
花神楽美月の不倫騒動、そして今回の飲酒騒動も含めて、仕組まれたものでした。そもそも事の発端は、彼女の父である花山健逸に対する脅迫がすべての始まりです。花山健逸は、特許の永年使用権を迫られて、それにも飽き足らず多額の現金を奪われて、今度はその会社までも乗っ取られようとしています。すべて、娘である花神楽美月を人質に取られて、断ればスキャンダルをでっち上げられてきました。こんなことが許されるはずがない。
テレビから流れる自分の言葉を横目に見ながら、電話の向こうの新井木遥香に告げる。そんなことはできない、と。しかし、新井木遥香は、ではどうするつもり、と返す。
「少し考えさせてください」
『いいわ。良い返事を期待しているね』
床にぺたんと腰を下ろす、生気をすべて抜かれてしまったようなミツキの表情が凍り付く。失望の表情を僕に見せて、何も発することなくうな垂れる。ミツキ、大丈夫だから、と言った僕の言葉を全く耳に入れようとせずに、ぽつりと呟いた台詞は、もう全部終わった、と。
「うん。そうだね。うん。でも大丈夫。約束通り、命に代えてもミツキは守るから。今から楠川田と話してくる。だから、最後くらい僕の言葉を聞いて」
「————え?」
「ミツキ、ありがとう。僕に寄り添ってくれて。僕の生きがいになってくれて、ほん……とうに……ありが……とう」
そのまま何も言わずに、僕はミツキを通り過ぎて玄関に向かう。待って、というミツキを振り返ることなく、スニーカーを履いて飛び出した。
「シュン君待って!! ねえ、やめて!!」
走ることができても息が続かない僕は、すぐにミツキに追いつかれてしまう。腕を掴まれて、背中を抱きしめられる。ミツキ、お願いだから離して。
「ごめん、シュン君。わたしが悪かったの。弱気になっちゃって。シュン君は勇気を出したのに。わたしのためにしてくれたことなのに、その気持ちもないがしろにして」
「でも、結果的に駄目だったんだ。こんなはずじゃなかったのに。もっと上手くいくと思っていたのに」
未だに鳴りやまないスマホの通知が、まるで日本刀で斬りつけるように心をズタズタにしていく。真っ二つどころか、数えきれないくらいに裁断されてしまった心は涙すら流すことができない。死ねばいいのに、という知らない誰かの言葉どおり。そうするしかミツキを救うことができないなら、そうしてやりたい。今なら、その勇気だってある。
だけど……こうして温もりを感じてしまったら、その意気地が削がれてしまう。薄く切り取られるチーズのように徐々に小さくなってやがて、僕の決心はなくなってしまう。
————こんなに震えるミツキを置いていけないよ。
「もう……馬鹿なことを考えないで。すべて失っても、またゼロから始めればいいじゃない。どこか遠いところに逃げて、心をいったん軽くして。また物語を始めればいいじゃない」
そうか……死ぬ気になればなんだってできる。ミツキの言うとおりだ。僕はなんて愚かだったんだろう。
————死んでしまうことは敗北を意味するんだ。
だから絶対に死んではいけない。選択肢に死を入れること自体、間違っている。僕にはミツキもいるし、もし僕がいなくなれば、ミツキはすべてを失ってしまう。たかがSNSに追い込まれて、まるで催眠術にでもかかったように思い込んでいた。死ねばすべて解決するなんて。
「シュン君……これ見て」
ポケットから取り出したスマホはSNSの通知が鳴り止まない様子。それを僕に見せるミツキは、その圧倒的な情報量に見入っていた。ニューチューブ、インストグラム、ツイーター、フリックする度に溢れる綴られた言葉。真剣な眼差しで発信される著名人のライブ配信。内容は————。
倉美月春夜の配信について、私は賛同し、楠川田賢二に対する被害をここで告白します。私はある日、彼の部下に呼び出されて————。
シュン様の配信を見て、あたしも決心しました。彼に脅されて渋々————。
倉美月くんの勇気ある行動に敬意を示してください。これは、僕たちのこれまで受けてきた被害を————。
彼の行動を批判する人がいても当然だと思う。だけど、俺たちは恐れをなして、あの男に立ち向かうことすらできなかったのだから————。
————風見碧唯《かざみあおい》です。花神楽美月さんはお酒なんて飲んでいません。すべて、あの男に脅されてあたしが仕組みました。すべて楠川田賢二に脅されてしたことです。
#シュン様に賛同を、という言葉を添えて、次々と著名人たちが言葉を紡ぎ始めた。澄んだ一滴の墨汁を混ぜた群青色のような星空の下、ミツキと二人凍える身体を寄せ合って、配信され続ける動画を次々と追っていく。こんなにも暗躍をしていたのかと思うと、身震いをするほど楠川田賢二という人物に恐れおののく。
————ここでお便りを紹介します。ラジオネーム、一撃のアスカロンさんから。志桜里さんこんばんは。なんだか世間が騒がしくなってきましたが、ある一人の勇気ある若者が起こした事件は、本を正せば、彼に何のメリットもないんですよね。だって、あの動画を見た限りでは、倉美月くん本人は何も被害を受けていないじゃないですか。じゃあ、なんであんなに電光掲示板まで使って、長ったらしい演説をしたのか。それって、愛ですよねん。シオリントさんもそういう恋が見つかるといいですね。って余計なお世話です。でも、本当、そういうの素敵だな~って私も思っちゃうんですよね。一撃のアスカロンさんいつもありがとう~さ~てここで一曲————。
誰かが録音した志桜里の午後のラジオ番組がツイーターに流れた。いいねが五万を超えている。そして、今も続々と増え続けているハートの数。
「ミツキ……これってもしかして」
「——シュン君……やっぱり世の中捨てたもんじゃないね」
二人で泣きながら家路についた。凍える身体を寄せ合い一台のスマホを二人で持ちながら。
明るい柳緑色《りゅうりょくしょく》のスクリーンをバックに、カメラマンとディレクターが何度もテストを繰り返し、花山健逸の会社の社員と思われる人々が、忙しなく行ったり来たりしている。この動画の配信をすれば、楠川田賢二《くすかわだけんじ》がどういう反応を示すのか未知数ではあるものの、きっと業を煮やして僕を責め立てるはず。しかし、僕が危惧しているのは楠川田の反応ではなく、世間がどういう捉え方をするか、である。
僕はこともあろうか、今朝早くに何も言わずに家を出てきた。無論、ミツキにも何も言わずに。だからなのだろう。先ほどからスマホの着信とメッセージがとめどなく画面に溢れていて、心が少し——いや、かなり痛い。家出だとか思われているのかも。終わったらすぐに連絡するから。
だけど、僕が今からしようとしていることは、ミツキに言えばきっと反対される。だからこそ何も言えなかった。しかし、こうする他ない。もし、僕に何かあったら、なんて思うとミツキには本当に申し訳なく思う。
「倉美月さんお願いします」
「はい」
準備が整った。さあ、はじめよう。僕の一世一代の勝負だ。
★☆☆
急いで帰宅すると、涙が枯れ果てました、と言わんばかりの表情で仁王立ちするミツキとその背後の鬼の形相をした姉さんがこちらを睨《にら》みつけながら、無言で僕を迎え入れた。ただいま、などと口にしようものならば、おかえり、などと言う言葉など掛けてもらえるはずもなく、どこに行っていたの、と刺々《とげとげ》しい呪詛《じゅそ》をもらうはめに。
居間のロッキングチェアに座る姉さんは、午後のまだ日も落ちていない時間からビールを片手に、その胸に顔を埋めて抱きつかれたミツキの頭を撫でていた。何この状況。
「シュン、言ったわよね。どんな状況でも女の子を泣かせることは絶対に間違っているって」
「——ごめん」
「せめて行先くらい、言っていきなさいよ。電話も出なければ、メッセに返信もしないなんて。あんたらしくないわよ」
「言っておかなければいけないことがあるんだ」
いつもと様子が違う僕に気付いた姉さんは、ミツキを引き離して立ち上がり、何してきたの、と低い声で訊ねてくる。一方、泣き腫《は》らした瞳を僕に向けるミツキの見上げるその表情は、眉尻を下げていて、今すぐにでも抱きしめてあげたかった。
「楠川田賢二に喧嘩を売ってきた。明日から一週間、全国の電光掲示板とニューチューブで僕の動画が配信される。だから、もし僕に何か————」
ぱちんという音とともに、僕の頬に激しい痛みが広がる。姉さんに頬を叩かれたと認識するまでに時間は掛からなかったけれど、予想外だったのは姉さんが泣いていたことだった。姉さんが泣いたところを見たのは小学生のときが最後で、それ以来見たことがない。なぜ泣いているの、と頬の痛み以上に、その涙が僕の心を激しく殴打する。
「アスカさ……ん?」
立ち上がったミツキは、自分の腕に突っ伏すように顔を隠した姉さんの肩を抱いて、その顔を覗き込む。こんなに弱々しい姉さんを見たのは初めてで、僕はどうすることもできずに、ただその様子を窺うしかできなかった。
「あんた……自分がなにをしているのか……分かっているの?」
「…………うん。分かってる。でも、こうするしか」
「楠川田からミツキちゃんを守るために、おばあちゃんがどれほど苦心したか、あんたは分かってない」
「————え?」
「————どういうことですかアスカさん!?」
ミツキちゃんを記者が追い回さないのはなぜだと思うの。週刊誌に写真が全く載らないのはなぜだと思うの。お母さんだけの力では不可能なの。それに、楠川田が直接ミツキちゃんに手を下すことをしないのはなぜだと思うの。やろうと思えば、もう一度拉致事件を起こすことだって容易なのに。もっとひどいことだってできるのに。それは、おばあちゃんが全てを知っていてミツキちゃんを守っていたからなのよ。
「それにね、あんた、勝手に楠川田と契約なんて結んで。おばあちゃんが先手を打たなかったら、あんたもスキャンダルの餌食になっていたのよ。あの男は、それをネタに、ミツキちゃんを差し出すように仕向けるはずだったの」
「なんで先に言ってくれないんだよ……すべて知っていたんだったら、教えてくれても————」
「あんたの向こう見ずの性格を知っているからよ。キレると大胆なことをするでしょ」
シュン君、と僕を見るミツキが抱きついてくる。僕の胸に顔を埋めて嗚咽《おえつ》を上げながら泣きじゃくるミツキの髪を撫でて、ごめん、と僕は呟く。その言葉を無視するミツキは、どうするのよ、とこの世の終わりのような台詞を吐いた。まるで、僕は世界を終わらせた魔王のよう。言い訳も、気の利いた言葉もすべて脳内を駆け巡ることもせずに霧散していく。自分のしたことは間違っていない、と僕はそれだけを胸に刻みつける。なにも間違っていない。そうでなければいけないんだ。そう、なにも。
☆★☆
クリスマスイブ前日。鳴り響くスマホの通知にうんざりしながら、目を覚ます僕はぼんやりと瞳を開いて、時間がもう正午になることに辟易していた。こんな時間まで起きられないなんて、どれだけ体力が落ちているのか、と。倦怠感《けんたいかん》なんて言葉で表せないような身体の不調は、精神的な面も関係しているのかな。考えないようにしていても、自分の身体のこと、楠川田のこと、それにミツキのことが脳内を堂々巡りしている。、食事も受け付けないほどに参ってしまっている自分に言ってやりたい。いつからそんなに弱くなったのだ、と。
昨晩は珍しくミツキが添い寝を求めて来なかった。部屋に籠ったまま、何かをしている様子だったけれども。気にはなったのだが身体が言うことを聞かず、すぐに横になってしまった。
誰もいない居間のロッキングチェアに座り、テレビをつけて唖然《あぜん》とした。どのチャンネルを回しても、渋谷のスクランブル交差点前の電光掲示板に映る僕の姿が流されている。そして、コメンテーターが話す言葉は、楠川田の会社のこと。あの会社はそんなことする会社ではない、と。至極《しごく》真面目で、社長の楠川田は温厚な人物であることを。
————やはりそう来たか。情報操作されることは間違いないと思っていた。
ミツキノミコトのインストグラム、ツイーター、それにニューチューブ、それぞれのアカウントに届く誹謗中傷の言葉。心無い言葉は、僕に限らずミツキにまで余波が来ているみたい。しかも、ミツキが僕に行動を起こさせた、という流れになっている。これには僕も頭を抱えざるを得なかった。
こんなはずじゃなかった。ミツキを救うはずが、逆効果になってしまったと言っても過言ではない。もしかしたら、姉さんの言うように、触れてはいけないものに触れてしまったのかも。
そして、ついにミツキの元に届いた僕が一番恐れていたこと。
————殺害予告。
居間の引き戸を引いたミツキは、涙を流すこともなく、僕を見つめたまま立ち尽くしていた。スマホを片手に力なくうな垂れる様子は、見ていられないほど弱々しい。すべて僕の責任だし、僕が悪い。謝って済む問題でもないし、第一、未だに僕は自分が間違っていないと思っている。だけど、心のどこかでそれを全否定している自分もいる。どちらが正しいのかなんて判断はできないけれど、ミツキに迷惑をかけていることは間違いない。そこに関してだけ言えば、僕は過ちを犯した。本当に申し訳なく思う。
「ミツキ、あの……」
「————わたしこれからどうしたらいいの?」
「うん……」
何も言えずに言葉が詰まってしまう。こうなった時のことを考えていなかった。確かに僕は向こう見ずの性格だし、詰めが甘かったと言わればそれまでかもしれない。でも、まだチャンスがないわけではない。
絶望が絶望を上塗りするような僕とミツキの周りの空気の中、スマホが鳴り響く。画面を見れば、見知らぬ電話番号。出ない方がいいだろう、と思ったけれど、もしかしたら、吉報の可能性だってあるわけだし。恐る恐る画面をタップして、もしもし、と。
『倉美月くん。あなた勇気があるわね。でも、少しやり方が強引だったかもね』
「新井木《あらいぎ》……さん……どうして」
悲痛な表情に変わるミツキはゆっくりと僕に近づいて、その電話の向こうの声に耳を傾けているよう。新井木遥香は、ミツキにとって天敵のような人物なのだから当然だ。
『あなたと花神楽美月《はなかぐらみつき》を助けてあげようと思って。だけど、条件があるの』
「なにを言っているんです?」
『花神楽美月と別れて、私のものになるなら、全部解決してあげてもいいけれど?』
暑くもないのに不快な汗が背中を伝う。全部解決なんてできるはずが……。
花神楽美月の不倫騒動、そして今回の飲酒騒動も含めて、仕組まれたものでした。そもそも事の発端は、彼女の父である花山健逸に対する脅迫がすべての始まりです。花山健逸は、特許の永年使用権を迫られて、それにも飽き足らず多額の現金を奪われて、今度はその会社までも乗っ取られようとしています。すべて、娘である花神楽美月を人質に取られて、断ればスキャンダルをでっち上げられてきました。こんなことが許されるはずがない。
テレビから流れる自分の言葉を横目に見ながら、電話の向こうの新井木遥香に告げる。そんなことはできない、と。しかし、新井木遥香は、ではどうするつもり、と返す。
「少し考えさせてください」
『いいわ。良い返事を期待しているね』
床にぺたんと腰を下ろす、生気をすべて抜かれてしまったようなミツキの表情が凍り付く。失望の表情を僕に見せて、何も発することなくうな垂れる。ミツキ、大丈夫だから、と言った僕の言葉を全く耳に入れようとせずに、ぽつりと呟いた台詞は、もう全部終わった、と。
「うん。そうだね。うん。でも大丈夫。約束通り、命に代えてもミツキは守るから。今から楠川田と話してくる。だから、最後くらい僕の言葉を聞いて」
「————え?」
「ミツキ、ありがとう。僕に寄り添ってくれて。僕の生きがいになってくれて、ほん……とうに……ありが……とう」
そのまま何も言わずに、僕はミツキを通り過ぎて玄関に向かう。待って、というミツキを振り返ることなく、スニーカーを履いて飛び出した。
「シュン君待って!! ねえ、やめて!!」
走ることができても息が続かない僕は、すぐにミツキに追いつかれてしまう。腕を掴まれて、背中を抱きしめられる。ミツキ、お願いだから離して。
「ごめん、シュン君。わたしが悪かったの。弱気になっちゃって。シュン君は勇気を出したのに。わたしのためにしてくれたことなのに、その気持ちもないがしろにして」
「でも、結果的に駄目だったんだ。こんなはずじゃなかったのに。もっと上手くいくと思っていたのに」
未だに鳴りやまないスマホの通知が、まるで日本刀で斬りつけるように心をズタズタにしていく。真っ二つどころか、数えきれないくらいに裁断されてしまった心は涙すら流すことができない。死ねばいいのに、という知らない誰かの言葉どおり。そうするしかミツキを救うことができないなら、そうしてやりたい。今なら、その勇気だってある。
だけど……こうして温もりを感じてしまったら、その意気地が削がれてしまう。薄く切り取られるチーズのように徐々に小さくなってやがて、僕の決心はなくなってしまう。
————こんなに震えるミツキを置いていけないよ。
「もう……馬鹿なことを考えないで。すべて失っても、またゼロから始めればいいじゃない。どこか遠いところに逃げて、心をいったん軽くして。また物語を始めればいいじゃない」
そうか……死ぬ気になればなんだってできる。ミツキの言うとおりだ。僕はなんて愚かだったんだろう。
————死んでしまうことは敗北を意味するんだ。
だから絶対に死んではいけない。選択肢に死を入れること自体、間違っている。僕にはミツキもいるし、もし僕がいなくなれば、ミツキはすべてを失ってしまう。たかがSNSに追い込まれて、まるで催眠術にでもかかったように思い込んでいた。死ねばすべて解決するなんて。
「シュン君……これ見て」
ポケットから取り出したスマホはSNSの通知が鳴り止まない様子。それを僕に見せるミツキは、その圧倒的な情報量に見入っていた。ニューチューブ、インストグラム、ツイーター、フリックする度に溢れる綴られた言葉。真剣な眼差しで発信される著名人のライブ配信。内容は————。
倉美月春夜の配信について、私は賛同し、楠川田賢二に対する被害をここで告白します。私はある日、彼の部下に呼び出されて————。
シュン様の配信を見て、あたしも決心しました。彼に脅されて渋々————。
倉美月くんの勇気ある行動に敬意を示してください。これは、僕たちのこれまで受けてきた被害を————。
彼の行動を批判する人がいても当然だと思う。だけど、俺たちは恐れをなして、あの男に立ち向かうことすらできなかったのだから————。
————風見碧唯《かざみあおい》です。花神楽美月さんはお酒なんて飲んでいません。すべて、あの男に脅されてあたしが仕組みました。すべて楠川田賢二に脅されてしたことです。
#シュン様に賛同を、という言葉を添えて、次々と著名人たちが言葉を紡ぎ始めた。澄んだ一滴の墨汁を混ぜた群青色のような星空の下、ミツキと二人凍える身体を寄せ合って、配信され続ける動画を次々と追っていく。こんなにも暗躍をしていたのかと思うと、身震いをするほど楠川田賢二という人物に恐れおののく。
————ここでお便りを紹介します。ラジオネーム、一撃のアスカロンさんから。志桜里さんこんばんは。なんだか世間が騒がしくなってきましたが、ある一人の勇気ある若者が起こした事件は、本を正せば、彼に何のメリットもないんですよね。だって、あの動画を見た限りでは、倉美月くん本人は何も被害を受けていないじゃないですか。じゃあ、なんであんなに電光掲示板まで使って、長ったらしい演説をしたのか。それって、愛ですよねん。シオリントさんもそういう恋が見つかるといいですね。って余計なお世話です。でも、本当、そういうの素敵だな~って私も思っちゃうんですよね。一撃のアスカロンさんいつもありがとう~さ~てここで一曲————。
誰かが録音した志桜里の午後のラジオ番組がツイーターに流れた。いいねが五万を超えている。そして、今も続々と増え続けているハートの数。
「ミツキ……これってもしかして」
「——シュン君……やっぱり世の中捨てたもんじゃないね」
二人で泣きながら家路についた。凍える身体を寄せ合い一台のスマホを二人で持ちながら。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

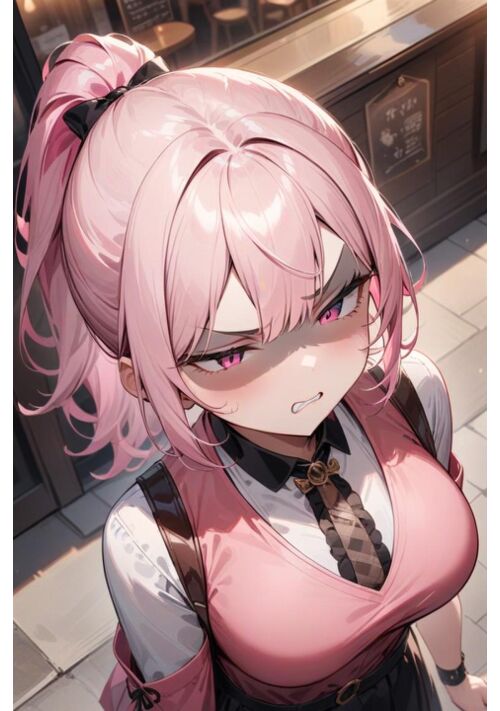
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















