15 / 18
15 母星からの訪問者
しおりを挟む
庭の木々が、夜気に揺れている。
わたし——いや、正しくは『ニャンダート・ターマ・シャグラン殿下』たるこのわたしが、
この古い家の裏庭で彼らの到着を待っているなんてことを、いったい誰が予想しただろう。
母星からの連絡は突然だった。
「地球での滞在記録を、実地観察として確認したい。とても現実とは思えない」と言うのが彼らの建前だ。
実際は、わたしのリリ子さんを実際に、見てみたいだけだろう。
母星の研究者たちは好奇心旺盛だ。とりわけ、この惑星の『人と猫』という関係性に
異様な執着を示してようだ。
木の枝の影が揺れ、ひとり、またひとりとあいつらが集まってくる。
最初に現れたのは銀色の目の三毛猫。こいつはまた来たのか。
続いて、片目が金色でもう片目が銀の白猫がふわりと芝を踏む。
そして、体の大きな鬣のある白銀の猫が枝を軋ませながら降りてきた。
あいつは獅子獣人。こう変わるのか!
最後に、垂れ耳の可愛らしい犬の姿で控えめに尻尾を振る一匹。なるほどイッヌだ。
彼らも皆、わたしと同じように、この惑星に適応するための姿に変わっている。
「ターマ様、観察の進捗はいかがですか?」
銀の目の三毛がわたしの真横に座り、低く問いかけてくる。
「随時、報告しているが」
わたしの声の冷たさなど気にした様子もなく
「猫カフェとは魅力的ですなぁ」とすまして続けた。
「そうそう、身近で細かく観察したいですね」と鬣が言うと頷きあっている。
好きにしろ、わたしの許可などいらぬだろ。
「いえ、ターマ様、作戦遂行に当たって指揮をとって頂かねば・・・」
「許可できぬ」と短く答えると口々に不満の鳴き声をあげた。
「ヌアー」「ニャッ」「ニャーヌ」「ワォ」
「まぁまずはリリ子さんとターマ様も関係を細かく観察しようではないか」
リリ子さんは、わたしがこの星で『タマ』として生活していることに一片の疑いも持たない。
亡くなったはずの猫が戻ってきた。そう信じている。
わたしは、以前のタマを同じように扱われている。優しく名前を呼ばれ、抱かれ、撫でられる。
「他の知的種族にはない事象ですね」と銀の目の三毛が笑う。
「生物間の依存、再生、疑似転生、転生。あらゆる神話のようだと。母星でも意見が白熱しています」
「我々は知るべきだ。この星の『死と再生』の概念をな」と鬣が低く唸った。
金目銀目がで庭を見渡しながら
「ターマ様の経験は非常に貴重です。しばらく、実地に観察させていただきたいです」と言った。
わたしはふっと鼻を鳴らした。
「いいだろう。だが、決して彼女の邪魔をするな」
「殿下は随分とお優しく」
鬣が、茶化して言った。
「黙れ」
その時だった。
「タマちゃん?」
低く、穏やかな声。リリ子さんが縁側の灯りを背に立っていた。
その視線は、わたしだけでなく背後に連なる銀目の三毛、白銀の鬣猫、金目銀目の白猫、
そして犬の姿にも向けられている。
彼女は何も驚いた様子を見せず、少しだけ微笑んだ。
「お友達かしら?」
「違う厄介者たちだ」と返事したが、「ニャーニュ」と変な声が出た。
母星の科学者たちは一斉に尻尾を振り、気取った礼をする。
まるで宮廷の晩餐に招かれた客人のように。
ネッコとイッヌのくせに・・・
わたしは胸の奥がむずがゆくなるのを誤魔化すように、足元の芝を引っ掻いた。
「タマちゃん、上がってもらったら?」
そう言いながら、リリ子さんは家の戸を少し開けてくれた。
三毛猫が得意顔で
「ありがたいお申し出ですな。観察の場としては最適でしょう」と言ったが
「ニャーーオォ。ミャーーーニュ」と聞こえた。
リリ子さんには変な猫の声として聞こえただろう・・・いい気味だ。
でも、わたしは小さくため息をつきながら頷き
「入っていい」と声をかけると縁側を抜け、居間に入った。
リリ子さんはいつものようにわたしの皿を取り出して
カリカリを盛りつけてくれた。
「タマちゃんは晩御飯を食べたから少しね。あなたたち晩御飯は食べたかな?」
「まだです。リリ子さんいい匂いですね」と三毛が答えた。
リリこさんは首を傾げて、わたしの分より多めに盛り付けると全員の前の置いた。
あいつら、最初は上品に食い始めたが、ガツガツ食って皿まで舐めてやがる・・・
彼らは、この星のカリカリの味を母星に報告するつもりだろうか。
滑稽だが、悪くない光景だ。
リリ子さんは小さく笑いながら言った。
「タマちゃん、いいお友達ね。みんないい子だわ。お水足りるかしら」
その言葉が、胸に染みた。この惑星は未熟で、文明水準も低い。
けれど、この温かさは、わたしの母星にはないものだ。
「泊まっていったらいいわ」と言うとリリ子さんは古いタオルを納戸から出してくれた。
「おやすみさない」と去っていくリリ子さんをあいつらは惚けて見送っていた。
わたし——いや、正しくは『ニャンダート・ターマ・シャグラン殿下』たるこのわたしが、
この古い家の裏庭で彼らの到着を待っているなんてことを、いったい誰が予想しただろう。
母星からの連絡は突然だった。
「地球での滞在記録を、実地観察として確認したい。とても現実とは思えない」と言うのが彼らの建前だ。
実際は、わたしのリリ子さんを実際に、見てみたいだけだろう。
母星の研究者たちは好奇心旺盛だ。とりわけ、この惑星の『人と猫』という関係性に
異様な執着を示してようだ。
木の枝の影が揺れ、ひとり、またひとりとあいつらが集まってくる。
最初に現れたのは銀色の目の三毛猫。こいつはまた来たのか。
続いて、片目が金色でもう片目が銀の白猫がふわりと芝を踏む。
そして、体の大きな鬣のある白銀の猫が枝を軋ませながら降りてきた。
あいつは獅子獣人。こう変わるのか!
最後に、垂れ耳の可愛らしい犬の姿で控えめに尻尾を振る一匹。なるほどイッヌだ。
彼らも皆、わたしと同じように、この惑星に適応するための姿に変わっている。
「ターマ様、観察の進捗はいかがですか?」
銀の目の三毛がわたしの真横に座り、低く問いかけてくる。
「随時、報告しているが」
わたしの声の冷たさなど気にした様子もなく
「猫カフェとは魅力的ですなぁ」とすまして続けた。
「そうそう、身近で細かく観察したいですね」と鬣が言うと頷きあっている。
好きにしろ、わたしの許可などいらぬだろ。
「いえ、ターマ様、作戦遂行に当たって指揮をとって頂かねば・・・」
「許可できぬ」と短く答えると口々に不満の鳴き声をあげた。
「ヌアー」「ニャッ」「ニャーヌ」「ワォ」
「まぁまずはリリ子さんとターマ様も関係を細かく観察しようではないか」
リリ子さんは、わたしがこの星で『タマ』として生活していることに一片の疑いも持たない。
亡くなったはずの猫が戻ってきた。そう信じている。
わたしは、以前のタマを同じように扱われている。優しく名前を呼ばれ、抱かれ、撫でられる。
「他の知的種族にはない事象ですね」と銀の目の三毛が笑う。
「生物間の依存、再生、疑似転生、転生。あらゆる神話のようだと。母星でも意見が白熱しています」
「我々は知るべきだ。この星の『死と再生』の概念をな」と鬣が低く唸った。
金目銀目がで庭を見渡しながら
「ターマ様の経験は非常に貴重です。しばらく、実地に観察させていただきたいです」と言った。
わたしはふっと鼻を鳴らした。
「いいだろう。だが、決して彼女の邪魔をするな」
「殿下は随分とお優しく」
鬣が、茶化して言った。
「黙れ」
その時だった。
「タマちゃん?」
低く、穏やかな声。リリ子さんが縁側の灯りを背に立っていた。
その視線は、わたしだけでなく背後に連なる銀目の三毛、白銀の鬣猫、金目銀目の白猫、
そして犬の姿にも向けられている。
彼女は何も驚いた様子を見せず、少しだけ微笑んだ。
「お友達かしら?」
「違う厄介者たちだ」と返事したが、「ニャーニュ」と変な声が出た。
母星の科学者たちは一斉に尻尾を振り、気取った礼をする。
まるで宮廷の晩餐に招かれた客人のように。
ネッコとイッヌのくせに・・・
わたしは胸の奥がむずがゆくなるのを誤魔化すように、足元の芝を引っ掻いた。
「タマちゃん、上がってもらったら?」
そう言いながら、リリ子さんは家の戸を少し開けてくれた。
三毛猫が得意顔で
「ありがたいお申し出ですな。観察の場としては最適でしょう」と言ったが
「ニャーーオォ。ミャーーーニュ」と聞こえた。
リリ子さんには変な猫の声として聞こえただろう・・・いい気味だ。
でも、わたしは小さくため息をつきながら頷き
「入っていい」と声をかけると縁側を抜け、居間に入った。
リリ子さんはいつものようにわたしの皿を取り出して
カリカリを盛りつけてくれた。
「タマちゃんは晩御飯を食べたから少しね。あなたたち晩御飯は食べたかな?」
「まだです。リリ子さんいい匂いですね」と三毛が答えた。
リリこさんは首を傾げて、わたしの分より多めに盛り付けると全員の前の置いた。
あいつら、最初は上品に食い始めたが、ガツガツ食って皿まで舐めてやがる・・・
彼らは、この星のカリカリの味を母星に報告するつもりだろうか。
滑稽だが、悪くない光景だ。
リリ子さんは小さく笑いながら言った。
「タマちゃん、いいお友達ね。みんないい子だわ。お水足りるかしら」
その言葉が、胸に染みた。この惑星は未熟で、文明水準も低い。
けれど、この温かさは、わたしの母星にはないものだ。
「泊まっていったらいいわ」と言うとリリ子さんは古いタオルを納戸から出してくれた。
「おやすみさない」と去っていくリリ子さんをあいつらは惚けて見送っていた。
11
あなたにおすすめの小説

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。


冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

魅了の対価
しがついつか
ファンタジー
家庭事情により給金の高い職場を求めて転職したリンリーは、縁あってブラウンロード伯爵家の使用人になった。
彼女は伯爵家の第二子アッシュ・ブラウンロードの侍女を任された。
ブラウンロード伯爵家では、なぜか一家のみならず屋敷で働く使用人達のすべてがアッシュのことを嫌悪していた。
アッシュと顔を合わせてすぐにリンリーも「あ、私コイツ嫌いだわ」と感じたのだが、上級使用人を目指す彼女は私情を挟まずに職務に専念することにした。
淡々と世話をしてくれるリンリーに、アッシュは次第に心を開いていった。

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~
Mio
ファンタジー
妻から手紙が来た。
妻が死んで18年目の今日。
息子の誕生日。
「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」
息子は…17年前に死んだ。
手紙はもう一通あった。
俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。
------------------------------

あっ、追放されちゃった…。
satomi
恋愛
ガイダール侯爵家の長女であるパールは精霊の話を聞くことができる。がそのことは誰にも話してはいない。亡き母との約束。
母が亡くなって喪も明けないうちに義母を父は連れてきた。義妹付きで。義妹はパールのものをなんでも欲しがった。事前に精霊の話を聞いていたパールは対処なりをできていたけれど、これは…。
ついにウラルはパールの婚約者である王太子を横取りした。
そのことについては王太子は特に魅力のある人ではないし、なんにも感じなかったのですが、王宮内でも噂になり、家の恥だと、家まで追い出されてしまったのです。
精霊さんのアドバイスによりブルハング帝国へと行ったパールですが…。

魔王を倒した勇者を迫害した人間様方の末路はなかなか悲惨なようです。
カモミール
ファンタジー
勇者ロキは長い冒険の末魔王を討伐する。
だが、人間の王エスカダルはそんな英雄であるロキをなぜか認めず、
ロキに身の覚えのない罪をなすりつけて投獄してしまう。
国民たちもその罪を信じ勇者を迫害した。
そして、処刑場される間際、勇者は驚きの発言をするのだった。
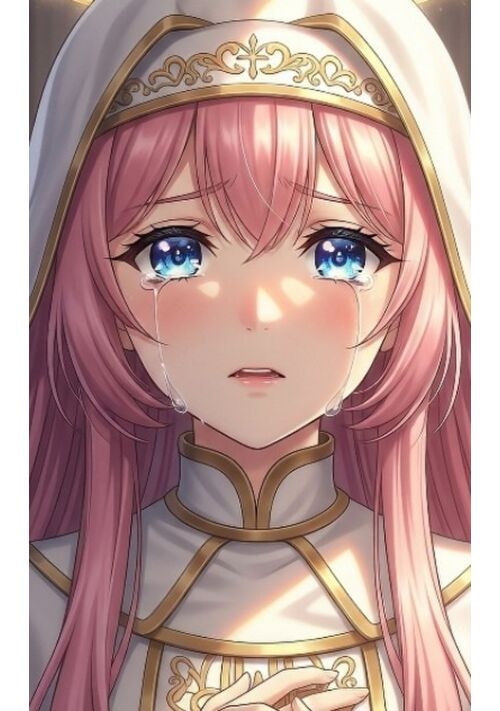
聖女は聞いてしまった
夕景あき
ファンタジー
「道具に心は不要だ」
父である国王に、そう言われて育った聖女。
彼女の周囲には、彼女を心を持つ人間として扱う人は、ほとんどいなくなっていた。
聖女自身も、自分の心の動きを無視して、聖女という治癒道具になりきり何も考えず、言われた事をただやり、ただ生きているだけの日々を過ごしていた。
そんな日々が10年過ぎた後、勇者と賢者と魔法使いと共に聖女は魔王討伐の旅に出ることになる。
旅の中で心をとり戻し、勇者に恋をする聖女。
しかし、勇者の本音を聞いてしまった聖女は絶望するのだった·····。
ネガティブ思考系聖女の恋愛ストーリー!
※ハッピーエンドなので、安心してお読みください!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















