40 / 91
六章
明かされる過去④
しおりを挟む
十分ほど走り、裏山麓の入口にまでたどり着くと、俺はそこで一旦息を整える。
目の前には、何年もろくに整備されていないであろう荒れ放題の登山道が広がっていた。その登山道はどろりとした闇が広がる山中に細々と続いており、まるで地獄へと誘う道のように見えた。
地面から生えた雑草は大人の腰の高さほどまであり、周囲からニョキニョキと伸びた枝がそれらに覆い被さって俺の行く手を阻んでいる。
「これを、登っていくのか……」
息を呑む。幽霊や妖怪などといった存在は信じていないが、この暗さともなるとさすがに恐怖を感じる。
携帯の明かりがあるとはいえ、山中では恐らく一寸先は闇状態であろう。こんな場所を、みらいは本当に登ったのだろうか。
考え過ぎなんじゃないだろうかと一瞬思う。
しかし、朝にみらいが言っていた言葉がどうしても頭から離れてくれなかった。
これを外してたら痛いな……。
覚悟を決め、俺は山の中へと足を踏み入れた。
道中には、拳大ほどの石がゴロゴロと転がっており、想像していたよりもずっと歩き難かった。
草木を掻き分け、何度も足を捻りそうになりながら、それでも俺は懸命に前へと進み続けた。この先に、彼女がいることにすべてを賭けて―――
どれほど登っただろうか。
寒さと疲れで手足の感覚が無くなりかけてきた頃、急に目の前の道が開け、浩蕩たる広場のような場所に出た。
「ここは……」
そこはまるで、ミステリーサークルのようになった巨大な草原だった。学校のグラウンド程度なら余裕で収まりそうなほどの大きさだ。
周囲には木々が密集しているが、何故か目の前の丸い草原には小さな木一本すら伸びていない。
冷たい風が吹く度に、さらさらと心地よい音を立てて、草原が波打っていた。
とても神秘的な場所のように見えた。
―――と、その中央に、俺は小さな人影を見つけた。
あれは―――
考えるよりも先に身体が動いていた。
人影に駆け寄る。
距離が近づくにつれ、徐々にその輪郭がはっきりとしてくる。
間違いない。見間違うはずもない。
あれは―――あいつは―――
「みらい‼」
ガッ、と後ろからその肩を掴み、俺は彼女の名前を叫んだ。
みらいは、ぺたんと地面に座り込み、空を見上げた格好のまま固まっていた。
賭けに近い予感が的中したことで、俺はひとまず安堵する。
「おい、みらい! 大丈夫か⁉」
ガクガクと肩を揺さぶると、みらいはようやく俺の存在に気が付いたのか、ゆっくりと振り返った。
しかし、
「―――ッ!」
その顔には表情がなかった。目に光が宿っていない。
がらんどうのように黒く塗りつぶされた二つの穴が、無表情に俺に向けられていた。
「…………だった」
「え?」
彼女の口が僅かに動いた。
「願い事、無理……だった。届かなかった」
消え入りそうな声で、彼女はそう言った。
「……お前、何言って―――」
「でき……なかった。流れ星、速すぎて……。頑張ってみたけど、全然ダメ、だった……」
「おい! しっかりしろっ!」
「こんな場所からじゃ、ダメだよ。こんなに空と遠かったら、私の声なんてきっと、聞こえないよ……」
白く無表情だった彼女の顔が、ゆっくりと歪み始める。
「帰っても、きっと何も変わらない。何も変わってないよ。明日からも、明後日からも、ずっとずっと同じ。ずっと同じ毎日が、続いて行くんだよ……」
「みらい―――」
「私、そんな贅沢なお願い……してる……?」
声に嗚咽が混じり始める。
「お金持ちになりたいとか、偉くなりたいとか……そんなこと、言ってないんだよ……? ただ、普通の家で普通に暮らして……ユウ君たちと、毎日を楽しく過ごしたいって……ただそれだけ、だよ……?」
ついに堪えきれなくなったように、みらいの目から大粒の涙がボロボロと溢れ出した。
「ねえ、どうして……? どうして私だけこんな理不尽な事に耐えなきゃいけないの? こんなに辛くてしんどい毎日なら、生まれてこない方が……よかったじゃない……!」
みらいが俺の服を掴む。
その力は、彼女のものとは思えないほどに強かった。
「毎日毎日、親の顔色窺って……怒られないように、殴られないように、びくびくしながら暮らして……そんなの……イヤだよ。生きてるなんて言えないよ。こんなに辛くて悲しくて……誰も私のことなんて必要としない世界だったら…………死んだ方が、よっぽどマシだよ」
ああぁぁぁぁぁああああ―――!
声を上げて彼女が泣いた。
彼女の泣き声が、冬の夜空に虚しくこだましては消えていく。全てを吐き出すように、彼女は俺のコートに顔を埋めながら泣き続けた。
そんな彼女の姿を見て、俺はもう何度目か、心底自分に嫌気がさした。
どうしようもなくなってからでは遅かったのだ。
応急処置ができて安心している場合などではなかった。悠長に考えている時間などは既になかったのだ。
ギリッ、と俺は奥歯を強く噛み締める。
ここまで自分を激しく呪ったのは初めてだ。
彼女の泣き声一つ一つが、鋭利な刃物のようになって俺の胸にぐさぐさと突き刺さってくる。
息が苦しい。顔が熱い。目の前で、赤い点がチカチカと点滅している。
それを認めて、俺は初めて自分が怒っているのだと理解した。他の誰にでもない、自分自身の愚かさに―――俺は強い怒りを覚えていた。
膝を折り、泣きじゃくるみらいを俺は黙って抱きしめる。低能で愚鈍な俺がしてやれることは、これくらいしかなかった。
「やだよぉ。帰りたくないよぉ……。なんでぇ……どうして、私が………」
「ごめん。ごめんな―――」
耳横で嗚咽する彼女に、俺はひたすら謝り続ける。
他に何と言っていいかわからなかった。
「どうして……? どうして私のお願い事……聞いてくれないの? 私を助けてくれないの……?」
降るような星空に向かって、みらいが縋るように手を伸ばす。
俺はきつく目を閉じた。
本当に神様という存在がいるのなら、今すぐにでも彼女を救ってやってほしかった。口先だけで何もせず、何の力もない俺の代わりに、彼女を縛り付ける残酷な現実を木端微塵に打ち砕いてほしかった。
どんな形でもいい。彼女が幸せになれるのならそれで構わない。どうか―――どうか、彼女を今ある地獄の日々から救い出してやってくれ―――
嫌味なくらいに綺麗な星空に向かって、俺も祈りを捧げる。
……だけど、俺の願いも、彼女の願いも、きっとその神様とやらには届かないのだろう。
どれだけ祈りを捧げても、どれだけ喚き、叫び、哭いたとしても、この広大な空の向こうにいる神様のもとには、俺たちの声や想いは届かない。
だから……きっと……今の彼女を助けることができるのは、やはり俺しかいないのだろう。神様など不確かな存在などではなく、今、確かにここに存在している、この俺しか―――
彼女を抱きしめる腕に力を籠める。
覚悟を決めた。今度は、しくじらない。
「なあ、みらい……聞いてくれ」
まだ泣きじゃくっていた彼女に、俺は優しく語りかけた。
「ぐ……ひっく……な、何……?」
「一つさ、提案があるんだ」
「………提案?」
ごしごしと、制服の袖で涙を拭いながら、みらいが俺の身体から離れる。
「もし、お前が嫌じゃなかったら……」
「……うん?」
充血して、真っ赤に染まった彼女の目を、俺は真っ直ぐに見つめた。
生唾を呑み込む。
そして、
「家出しよう。家出して、俺の家で一緒に暮らそう。俺と初音とお前の三人で、一緒に暮らすんだ」
一息に言った。
「……えっ?」
みらいが、驚いたように鳶色の瞳を大きくする。
当然だ。こんな発想をすること自体が馬鹿げてる。愚か者の俺らしい、安直な考え方だと思った。
家出なんて彼女の両親が許すわけがない。上手くいく保証もないし状況を更に悪化させてしまう可能性の方が圧倒的に高い。
だがそれでも、今すぐに彼女を救う方法となると、俺にはこれくらいしか思いつかなかったのだ。
「……家出、するの?」
みらいが呟くように言った。
「ああ、そうだ。あんな家、もう帰らなくていい」
「でも……私が家出なんかしたら、きっとあの人たちすっごく怒るよ。ユウ君にも、酷いことするかもしれないよ………?」
不安そうな目で俺を見てくる。
「構うもんか。そんときは返り討ちにしてやる」
俺は力を込めてそう言った。
「……本気で、言ってるの……? 本当に私、ユウ君のお家で暮らしても、いいの……?」
「ああ、本気で本当だ」
「………」
「……嫌か?」
「そんな……嫌なわけ、ないよ」
「よし。なら、決まりだ」
正直、どうなるかはわからない。行き当たりばったりの作戦もいいところだ。初音にも迷惑を掛けてしまうかもしれない。
だけど、今の彼女をこのまま放っておくことだけはできなかった。
「本当の、本当に……? 嘘とかじゃ、ない?」
まだ実感が湧かないのか、みらいは上目遣いに俺の様子を窺ってくる。
だから、
「ああ、嘘じゃない。本当だ」
きっぱりとそう言い切った。彼女を不安にさせないために。
みらいはしばらくの間、ぼーっとそんな俺の顔を見つめていたが、
「………⁉」
突如、またボロボロと大粒の涙を零し始めた。
「いい……の……? 本当に私、もうあの家に戻らなくてもいいの?」
「ああ。あんな家、もう帰らなくていい」
「怒鳴られたり、叩かれたり……しない? 髪とかも、引っ張られたりしない……?」
ズキリと胸が痛んだ。その言葉だけで、彼女が今までどんな仕打ちを受けてきたかは、十二分に想像できた。
「そんな酷いこと、させない」
呻くように言った。思わず泣きそうになったが、グッと堪えた。
「もしあいつらが俺の家に乗り込んで来たとしても、お前には指一本触れさせない」
だから心配するな、と俺は優しく、彼女に微笑みかけた。
そんな俺を見て、みらいはようやく安心したようで、
「ユウ君、そんなに逞しかったっけ……?」
と言って、表情を緩めた。
「これでも一応、男だからな」
「そうだね……。ユウ君は男の子だもんね。昔は身長も私の方が高かったのに、いつの間にか抜かされちゃったもんね……」
「そうだったか……?」
「……うん」
小さく頷く。そして、
とん、と俺の胸に頭を預けてきた。
「……ありがとう」
小さな声でそう言った。
「迎えに来てくれてありがとう。私、今とっても幸せだよ……」
俺のコートにすりすりと顔を擦りつけながらみらいが言った。
その途端、俺は急に気恥ずかしくなって、両手で彼女の髪をぐしゃぐしゃと掻き回した。
「うー、何するんだよー」
みらいが抗議の声を上げたが、俺はその手を止めなかった。身体の中がどうしようもなく熱かった。
白い吐息が夜空に吸い込まれていく。
冬の星空の下、俺たちは互いの存在を確かめ合うように、しばらくの間身体を離さなかった。
くっしゅ―――。
みらいが小さく、くしゃみをした。
「うう、寒い。もう限界だよ」
両手で身体を抱え、みらいはがくがくと足を震わせる。
そこで俺は初めて気が付いた。彼女はセーラー服一枚のみで、その上からは何も羽織っていなかったのだ。
俺は慌てて、自分の着ていたコートを彼女の肩にかけてやる。
「いいの……?」
「そのままじゃ風邪引くだろ」
「ありがとう、ユウ君」
あったかーい、とふやけた声を漏らしながら、彼女は俺のコートをすっぽりと頭まで被る。そしてそのまま、ハムスターのように地面の上で丸くなってしまった。
「おいおい、こんなところで寝転がるなよ」
「うーん……わかってるけど、もうちょっとぉ」
「寝起きの悪い奴みたいなこと言うなって」
「ユウ君にだけは言われたくないよ」
みらいが、コートの中から顔を覗かせながら言った。
「いいから早く帰るぞ。そんで風呂入ってゆっくり寝ろ」
「……ユウ君のお家で……?」
「ああ、そうだよ」
俺は大きく頷いた。
「そっかあ……」
間延びした声でそう言うと、彼女はまたひょいっと、コートの中に引っ込んでしまう。
「ちょっ、何でそうなるんだよ」
「だって寒いんだもん」
「だからって、朝までこうしてるわけにもいかないだろ」
「えー、じゃあ、ユウ君がおんぶして連れて帰ってよ」
「……へ?」
予想外の彼女の言葉に、俺は思わず変な声を出してしまう。
「だって、私はここから動きたくないけど、ユウ君は早くお家に帰りたいんでしょ? だったらユウ君が私を負ぶって帰る以外方法ないじゃない」
「いや、それはさすがに………」
俺は返しに困る。
ここへ来るまでの山道―――正直なところ、かなりきつかった。道らしき道がないというのもそうなのだが、何よりも足場が悪すぎる。大きな石ころに躓き、所々のぬかるみに足を取られ、何度も足を捻挫しそうになりながら、俺はようやくこの場所に辿り着いたのだ。
そんな山道を、今度は彼女をおんぶした状態で下るなんて―――無事に下山できる自信がなかった。
すると、みらいはそんな俺の心の中を見透かしたかのように、
「もしかして自信ないの? さっきは私を守るみたいなこと言ってたくせに」
また、ひょこっと顔半分だけを出して、今度は挑発するみたいにそう言ってきた。
「そ、それは……」
俺は言葉に詰まる。
「ほらほら、どうするの。どうするの。早くしてくれないと、本当に私風邪ひいちゃうよー」
ダメだ。ここまできてしまったらもう完全に彼女のペースだ。先ほどまでのしおらしい様子の彼女は、一体どこへ行ってしまったのだろうか……。
俺は胸の中で嘆息する。
だが何にせよ、彼女をこのまま放置しておくわけにはいかない。
………仕方ない、と俺は肩落とした。
「わかったよ。今日だけ特別だからな」
「えっ、本当に……⁉」
「ああ」
「やった!」
がばっと、みらいが勢いよく身体を起こす。
「言っとくけど、途中でこけそうになっても文句言うなよ」
「言わない言わない。大丈夫。ユウ君ならきっとできるよ」
「何でそう言い切れるかなあ……」
小言を洩らしながら、俺は地面に膝をついて彼女に背中を向けた。
「ほら。早く乗れよ」
「お邪魔しまーす」
コートを羽織ったみらいが、俺の背中に身体を預けてくる。
彼女の両足を持つと、俺はよいしょという掛け声と共に立ち上がった。
彼女の身体は、想像していたよりもずっと軽かった。そして、服越しにでも伝わってくるほどに、彼女の身体は冷たくなっていた。
平気な顔をしているが、本当はすぐにでも身体を温めたいはずだ。
ぐっと足に力を入れ、俺は歩き始める。
「おっ、さすが男の子だね」
耳元に彼女の吐息を感じながら、俺たちは波打つ広大な草原を後にした。
目の前には、何年もろくに整備されていないであろう荒れ放題の登山道が広がっていた。その登山道はどろりとした闇が広がる山中に細々と続いており、まるで地獄へと誘う道のように見えた。
地面から生えた雑草は大人の腰の高さほどまであり、周囲からニョキニョキと伸びた枝がそれらに覆い被さって俺の行く手を阻んでいる。
「これを、登っていくのか……」
息を呑む。幽霊や妖怪などといった存在は信じていないが、この暗さともなるとさすがに恐怖を感じる。
携帯の明かりがあるとはいえ、山中では恐らく一寸先は闇状態であろう。こんな場所を、みらいは本当に登ったのだろうか。
考え過ぎなんじゃないだろうかと一瞬思う。
しかし、朝にみらいが言っていた言葉がどうしても頭から離れてくれなかった。
これを外してたら痛いな……。
覚悟を決め、俺は山の中へと足を踏み入れた。
道中には、拳大ほどの石がゴロゴロと転がっており、想像していたよりもずっと歩き難かった。
草木を掻き分け、何度も足を捻りそうになりながら、それでも俺は懸命に前へと進み続けた。この先に、彼女がいることにすべてを賭けて―――
どれほど登っただろうか。
寒さと疲れで手足の感覚が無くなりかけてきた頃、急に目の前の道が開け、浩蕩たる広場のような場所に出た。
「ここは……」
そこはまるで、ミステリーサークルのようになった巨大な草原だった。学校のグラウンド程度なら余裕で収まりそうなほどの大きさだ。
周囲には木々が密集しているが、何故か目の前の丸い草原には小さな木一本すら伸びていない。
冷たい風が吹く度に、さらさらと心地よい音を立てて、草原が波打っていた。
とても神秘的な場所のように見えた。
―――と、その中央に、俺は小さな人影を見つけた。
あれは―――
考えるよりも先に身体が動いていた。
人影に駆け寄る。
距離が近づくにつれ、徐々にその輪郭がはっきりとしてくる。
間違いない。見間違うはずもない。
あれは―――あいつは―――
「みらい‼」
ガッ、と後ろからその肩を掴み、俺は彼女の名前を叫んだ。
みらいは、ぺたんと地面に座り込み、空を見上げた格好のまま固まっていた。
賭けに近い予感が的中したことで、俺はひとまず安堵する。
「おい、みらい! 大丈夫か⁉」
ガクガクと肩を揺さぶると、みらいはようやく俺の存在に気が付いたのか、ゆっくりと振り返った。
しかし、
「―――ッ!」
その顔には表情がなかった。目に光が宿っていない。
がらんどうのように黒く塗りつぶされた二つの穴が、無表情に俺に向けられていた。
「…………だった」
「え?」
彼女の口が僅かに動いた。
「願い事、無理……だった。届かなかった」
消え入りそうな声で、彼女はそう言った。
「……お前、何言って―――」
「でき……なかった。流れ星、速すぎて……。頑張ってみたけど、全然ダメ、だった……」
「おい! しっかりしろっ!」
「こんな場所からじゃ、ダメだよ。こんなに空と遠かったら、私の声なんてきっと、聞こえないよ……」
白く無表情だった彼女の顔が、ゆっくりと歪み始める。
「帰っても、きっと何も変わらない。何も変わってないよ。明日からも、明後日からも、ずっとずっと同じ。ずっと同じ毎日が、続いて行くんだよ……」
「みらい―――」
「私、そんな贅沢なお願い……してる……?」
声に嗚咽が混じり始める。
「お金持ちになりたいとか、偉くなりたいとか……そんなこと、言ってないんだよ……? ただ、普通の家で普通に暮らして……ユウ君たちと、毎日を楽しく過ごしたいって……ただそれだけ、だよ……?」
ついに堪えきれなくなったように、みらいの目から大粒の涙がボロボロと溢れ出した。
「ねえ、どうして……? どうして私だけこんな理不尽な事に耐えなきゃいけないの? こんなに辛くてしんどい毎日なら、生まれてこない方が……よかったじゃない……!」
みらいが俺の服を掴む。
その力は、彼女のものとは思えないほどに強かった。
「毎日毎日、親の顔色窺って……怒られないように、殴られないように、びくびくしながら暮らして……そんなの……イヤだよ。生きてるなんて言えないよ。こんなに辛くて悲しくて……誰も私のことなんて必要としない世界だったら…………死んだ方が、よっぽどマシだよ」
ああぁぁぁぁぁああああ―――!
声を上げて彼女が泣いた。
彼女の泣き声が、冬の夜空に虚しくこだましては消えていく。全てを吐き出すように、彼女は俺のコートに顔を埋めながら泣き続けた。
そんな彼女の姿を見て、俺はもう何度目か、心底自分に嫌気がさした。
どうしようもなくなってからでは遅かったのだ。
応急処置ができて安心している場合などではなかった。悠長に考えている時間などは既になかったのだ。
ギリッ、と俺は奥歯を強く噛み締める。
ここまで自分を激しく呪ったのは初めてだ。
彼女の泣き声一つ一つが、鋭利な刃物のようになって俺の胸にぐさぐさと突き刺さってくる。
息が苦しい。顔が熱い。目の前で、赤い点がチカチカと点滅している。
それを認めて、俺は初めて自分が怒っているのだと理解した。他の誰にでもない、自分自身の愚かさに―――俺は強い怒りを覚えていた。
膝を折り、泣きじゃくるみらいを俺は黙って抱きしめる。低能で愚鈍な俺がしてやれることは、これくらいしかなかった。
「やだよぉ。帰りたくないよぉ……。なんでぇ……どうして、私が………」
「ごめん。ごめんな―――」
耳横で嗚咽する彼女に、俺はひたすら謝り続ける。
他に何と言っていいかわからなかった。
「どうして……? どうして私のお願い事……聞いてくれないの? 私を助けてくれないの……?」
降るような星空に向かって、みらいが縋るように手を伸ばす。
俺はきつく目を閉じた。
本当に神様という存在がいるのなら、今すぐにでも彼女を救ってやってほしかった。口先だけで何もせず、何の力もない俺の代わりに、彼女を縛り付ける残酷な現実を木端微塵に打ち砕いてほしかった。
どんな形でもいい。彼女が幸せになれるのならそれで構わない。どうか―――どうか、彼女を今ある地獄の日々から救い出してやってくれ―――
嫌味なくらいに綺麗な星空に向かって、俺も祈りを捧げる。
……だけど、俺の願いも、彼女の願いも、きっとその神様とやらには届かないのだろう。
どれだけ祈りを捧げても、どれだけ喚き、叫び、哭いたとしても、この広大な空の向こうにいる神様のもとには、俺たちの声や想いは届かない。
だから……きっと……今の彼女を助けることができるのは、やはり俺しかいないのだろう。神様など不確かな存在などではなく、今、確かにここに存在している、この俺しか―――
彼女を抱きしめる腕に力を籠める。
覚悟を決めた。今度は、しくじらない。
「なあ、みらい……聞いてくれ」
まだ泣きじゃくっていた彼女に、俺は優しく語りかけた。
「ぐ……ひっく……な、何……?」
「一つさ、提案があるんだ」
「………提案?」
ごしごしと、制服の袖で涙を拭いながら、みらいが俺の身体から離れる。
「もし、お前が嫌じゃなかったら……」
「……うん?」
充血して、真っ赤に染まった彼女の目を、俺は真っ直ぐに見つめた。
生唾を呑み込む。
そして、
「家出しよう。家出して、俺の家で一緒に暮らそう。俺と初音とお前の三人で、一緒に暮らすんだ」
一息に言った。
「……えっ?」
みらいが、驚いたように鳶色の瞳を大きくする。
当然だ。こんな発想をすること自体が馬鹿げてる。愚か者の俺らしい、安直な考え方だと思った。
家出なんて彼女の両親が許すわけがない。上手くいく保証もないし状況を更に悪化させてしまう可能性の方が圧倒的に高い。
だがそれでも、今すぐに彼女を救う方法となると、俺にはこれくらいしか思いつかなかったのだ。
「……家出、するの?」
みらいが呟くように言った。
「ああ、そうだ。あんな家、もう帰らなくていい」
「でも……私が家出なんかしたら、きっとあの人たちすっごく怒るよ。ユウ君にも、酷いことするかもしれないよ………?」
不安そうな目で俺を見てくる。
「構うもんか。そんときは返り討ちにしてやる」
俺は力を込めてそう言った。
「……本気で、言ってるの……? 本当に私、ユウ君のお家で暮らしても、いいの……?」
「ああ、本気で本当だ」
「………」
「……嫌か?」
「そんな……嫌なわけ、ないよ」
「よし。なら、決まりだ」
正直、どうなるかはわからない。行き当たりばったりの作戦もいいところだ。初音にも迷惑を掛けてしまうかもしれない。
だけど、今の彼女をこのまま放っておくことだけはできなかった。
「本当の、本当に……? 嘘とかじゃ、ない?」
まだ実感が湧かないのか、みらいは上目遣いに俺の様子を窺ってくる。
だから、
「ああ、嘘じゃない。本当だ」
きっぱりとそう言い切った。彼女を不安にさせないために。
みらいはしばらくの間、ぼーっとそんな俺の顔を見つめていたが、
「………⁉」
突如、またボロボロと大粒の涙を零し始めた。
「いい……の……? 本当に私、もうあの家に戻らなくてもいいの?」
「ああ。あんな家、もう帰らなくていい」
「怒鳴られたり、叩かれたり……しない? 髪とかも、引っ張られたりしない……?」
ズキリと胸が痛んだ。その言葉だけで、彼女が今までどんな仕打ちを受けてきたかは、十二分に想像できた。
「そんな酷いこと、させない」
呻くように言った。思わず泣きそうになったが、グッと堪えた。
「もしあいつらが俺の家に乗り込んで来たとしても、お前には指一本触れさせない」
だから心配するな、と俺は優しく、彼女に微笑みかけた。
そんな俺を見て、みらいはようやく安心したようで、
「ユウ君、そんなに逞しかったっけ……?」
と言って、表情を緩めた。
「これでも一応、男だからな」
「そうだね……。ユウ君は男の子だもんね。昔は身長も私の方が高かったのに、いつの間にか抜かされちゃったもんね……」
「そうだったか……?」
「……うん」
小さく頷く。そして、
とん、と俺の胸に頭を預けてきた。
「……ありがとう」
小さな声でそう言った。
「迎えに来てくれてありがとう。私、今とっても幸せだよ……」
俺のコートにすりすりと顔を擦りつけながらみらいが言った。
その途端、俺は急に気恥ずかしくなって、両手で彼女の髪をぐしゃぐしゃと掻き回した。
「うー、何するんだよー」
みらいが抗議の声を上げたが、俺はその手を止めなかった。身体の中がどうしようもなく熱かった。
白い吐息が夜空に吸い込まれていく。
冬の星空の下、俺たちは互いの存在を確かめ合うように、しばらくの間身体を離さなかった。
くっしゅ―――。
みらいが小さく、くしゃみをした。
「うう、寒い。もう限界だよ」
両手で身体を抱え、みらいはがくがくと足を震わせる。
そこで俺は初めて気が付いた。彼女はセーラー服一枚のみで、その上からは何も羽織っていなかったのだ。
俺は慌てて、自分の着ていたコートを彼女の肩にかけてやる。
「いいの……?」
「そのままじゃ風邪引くだろ」
「ありがとう、ユウ君」
あったかーい、とふやけた声を漏らしながら、彼女は俺のコートをすっぽりと頭まで被る。そしてそのまま、ハムスターのように地面の上で丸くなってしまった。
「おいおい、こんなところで寝転がるなよ」
「うーん……わかってるけど、もうちょっとぉ」
「寝起きの悪い奴みたいなこと言うなって」
「ユウ君にだけは言われたくないよ」
みらいが、コートの中から顔を覗かせながら言った。
「いいから早く帰るぞ。そんで風呂入ってゆっくり寝ろ」
「……ユウ君のお家で……?」
「ああ、そうだよ」
俺は大きく頷いた。
「そっかあ……」
間延びした声でそう言うと、彼女はまたひょいっと、コートの中に引っ込んでしまう。
「ちょっ、何でそうなるんだよ」
「だって寒いんだもん」
「だからって、朝までこうしてるわけにもいかないだろ」
「えー、じゃあ、ユウ君がおんぶして連れて帰ってよ」
「……へ?」
予想外の彼女の言葉に、俺は思わず変な声を出してしまう。
「だって、私はここから動きたくないけど、ユウ君は早くお家に帰りたいんでしょ? だったらユウ君が私を負ぶって帰る以外方法ないじゃない」
「いや、それはさすがに………」
俺は返しに困る。
ここへ来るまでの山道―――正直なところ、かなりきつかった。道らしき道がないというのもそうなのだが、何よりも足場が悪すぎる。大きな石ころに躓き、所々のぬかるみに足を取られ、何度も足を捻挫しそうになりながら、俺はようやくこの場所に辿り着いたのだ。
そんな山道を、今度は彼女をおんぶした状態で下るなんて―――無事に下山できる自信がなかった。
すると、みらいはそんな俺の心の中を見透かしたかのように、
「もしかして自信ないの? さっきは私を守るみたいなこと言ってたくせに」
また、ひょこっと顔半分だけを出して、今度は挑発するみたいにそう言ってきた。
「そ、それは……」
俺は言葉に詰まる。
「ほらほら、どうするの。どうするの。早くしてくれないと、本当に私風邪ひいちゃうよー」
ダメだ。ここまできてしまったらもう完全に彼女のペースだ。先ほどまでのしおらしい様子の彼女は、一体どこへ行ってしまったのだろうか……。
俺は胸の中で嘆息する。
だが何にせよ、彼女をこのまま放置しておくわけにはいかない。
………仕方ない、と俺は肩落とした。
「わかったよ。今日だけ特別だからな」
「えっ、本当に……⁉」
「ああ」
「やった!」
がばっと、みらいが勢いよく身体を起こす。
「言っとくけど、途中でこけそうになっても文句言うなよ」
「言わない言わない。大丈夫。ユウ君ならきっとできるよ」
「何でそう言い切れるかなあ……」
小言を洩らしながら、俺は地面に膝をついて彼女に背中を向けた。
「ほら。早く乗れよ」
「お邪魔しまーす」
コートを羽織ったみらいが、俺の背中に身体を預けてくる。
彼女の両足を持つと、俺はよいしょという掛け声と共に立ち上がった。
彼女の身体は、想像していたよりもずっと軽かった。そして、服越しにでも伝わってくるほどに、彼女の身体は冷たくなっていた。
平気な顔をしているが、本当はすぐにでも身体を温めたいはずだ。
ぐっと足に力を入れ、俺は歩き始める。
「おっ、さすが男の子だね」
耳元に彼女の吐息を感じながら、俺たちは波打つ広大な草原を後にした。
0
あなたにおすすめの小説

それなりに怖い話。
只野誠
ホラー
これは創作です。
実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。
本当に、実際に起きた話ではございません。
なので、安心して読むことができます。
オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。
不定期に章を追加していきます。
2026/1/1:『いえい』の章を追加。2026/1/8の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/31:『たこあげ』の章を追加。2026/1/7の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/30:『ねんがじょう』の章を追加。2026/1/6の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/29:『ふるいゆうじん』の章を追加。2026/1/5の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/28:『ふゆやすみ』の章を追加。2026/1/4の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/27:『ことしのえと』の章を追加。2026/1/3の朝8時頃より公開開始予定。
2025/12/26:『はつゆめ』の章を追加。2026/1/2の朝8時頃より公開開始予定。
※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。

【完結】知られてはいけない
ひなこ
ホラー
中学一年の女子・遠野莉々亜(とおの・りりあ)は、黒い封筒を開けたせいで仮想空間の学校へ閉じ込められる。
他にも中一から中三の男女十五人が同じように誘拐されて、現実世界に帰る一人になるために戦わなければならない。
登録させられた「あなたの大切なものは?」を、互いにバトルで当てあって相手の票を集めるデスゲーム。
勝ち残りと友情を天秤にかけて、ゲームは進んでいく。
一つ年上の男子・加川準(かがわ・じゅん)は敵か味方か?莉々亜は果たして、元の世界へ帰ることができるのか?
心理戦が飛び交う、四日間の戦いの物語。
(第二回きずな児童書大賞で奨励賞を受賞しました)

終焉列島:ゾンビに沈む国
ねむたん
ホラー
2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。
最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。
会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

【完結】ホラー短編集「隣の怪異」
シマセイ
ホラー
それは、あなたの『隣』にも潜んでいるのかもしれない。
日常風景が歪む瞬間、すぐそばに現れる異様な気配。
襖の隙間、スマートフォンの画面、アパートの天井裏、曰く付きの達磨…。
身近な場所を舞台にした怪異譚が、これから続々と語られていきます。
じわりと心を侵食する恐怖の記録、短編集『隣の怪異』。
今宵もまた、新たな怪異の扉が開かれる──。

黒に染まった華を摘む
馬場 蓮実
青春
夏の終わりに転校してきたのは、忘れられない初恋の相手だった——。
高須明希は、人生で“二番目”に好きになった相手——河西栞に密かに想いを寄せている。
「夏休み明けの初日。この席替えで、彼女との距離を縮めたい。話すきっかけがほしい——」
そんな願いを胸に登校したその朝、クラスに一人の転校生がやってくる。
彼女の名は、立石麻美。
昔の面影を残しながらも、まるで別人のような気配をまとう彼女は——明希にとって、忘れられない“初恋の人”だった。
この再会が、静かだった日常に波紋を広げていく。
その日の放課後。
明希は、"性の衝動"に溺れる自身の姿を、麻美に見られてしまう——。
塞がっていた何かが、ゆっくりと崩れはじめる。
そして鬱屈した青春は、想像もしていなかった熱と痛みを帯びて動き出す。
すべてに触れたとき、
明希は何を守り、何を選ぶのか。
光と影が交錯する、“遅れてきた”ひと夏の物語。
前編 「恋愛譚」 : 序章〜第5章
後編 「青春譚」 : 第6章〜
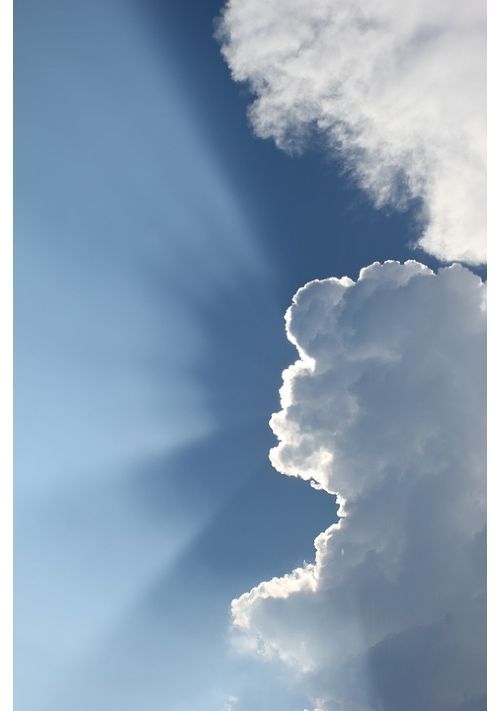
君との空へ【BL要素あり・短編おまけ完結】
Motoki
ホラー
一年前に親友を亡くした高橋彬は、体育の授業中、その親友と同じ癖をもつ相沢隆哉という生徒の存在を知る。その日から隆哉に付きまとわれるようになった彬は、「親友が待っている」という言葉と共に、親友の命を奪った事故現場へと連れて行かれる。そこで彬が見たものは、あの事故の時と同じ、血に塗れた親友・時任俊介の姿だった――。
※ホラー要素は少し薄めかも。BL要素ありです。人が死ぬ場面が出てきますので、苦手な方はご注意下さい。

神楽囃子の夜
紫音みけ🐾書籍発売中
ライト文芸
※第6回ライト文芸大賞にて奨励賞を受賞しました。応援してくださった皆様、ありがとうございました。
【あらすじ】
地元の夏祭りを訪れていた少年・狭野笙悟(さのしょうご)は、そこで見かけた幽霊の少女に一目惚れしてしまう。彼女が現れるのは年に一度、祭りの夜だけであり、その姿を見ることができるのは狭野ただ一人だけだった。
年を重ねるごとに想いを募らせていく狭野は、やがて彼女に秘められた意外な真実にたどり着く……。
四人の男女の半生を描く、時を越えた現代ファンタジー。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















