43 / 91
七章
最後の標的
しおりを挟む
―――翌朝。
眠い目をこすりながらリビングの扉を開けると、そこにはすでに、さよとみらいの姿があった。制服に着替えたさよは、テーブルの席に座り、こんがりと焼けたトーストを細かく手でちぎりながら、その小さな口に運んでいる。
「あ、ユウ君おはよー。また自分で起きれたんだ。えらいねー」
台所で洗い物をしていたみらいが、起きてきた俺に気が付いた。
「ああ、おはよ」
だが、俺は彼女の方は見ずに、ぶっきらぼうな返事を返す。
昨夜のことがあり、何となく彼女と目を合わせ辛かった。
だが、みらいは特に気にした様子もなく、
「はい、ユウ君の朝ごはんだよ。早く食べちゃってね」
俺の目の前にプレートとグラスが置かれる。プレートには目玉焼きと程よく焦げ目の付いたトーストが載せられており、グラスには麦茶が入れられていた。
「……ありがと」
彼女の焼いてくれたトーストに俺はかぶりつく。いつも通りの味だ。何も変わらない。
少しだけ安心した。
が、その時、
パリンッ―――!
台所の方から、何かが割れるような音が聞こえた。
驚いて見ると、シンクの前に立っていたみらいが、自分の足元を見たまま固まっていた。席を立って見に行くと、彼女の足元には真っ白なディナープレートが粉々になって散らばっていた。どうやら洗い物をしている最中に誤って手を滑らせてしまったようだ。
「おいおい何やってんだよ。大丈夫か?」
俺はシンク下からゴミ袋を取り出すと、散乱した破片を袋の中に入れていく。
……だが、おかしい。いつまで経っても彼女が手伝ってくれる気配がない。
不思議に思って顔を上げると―――みらいは濡れた自分の両手を見つめたまま、まるで石像のように固まっていた。鳶色の瞳が、これでもかというくらいに見開かれている。
「おい、どうしたんだ」
驚いて俺は声を掛けた。しかし、彼女は微動だにしない。
手でも切ったのかと思い、立ち上がって彼女の手を取ると、
「えっ、な、何⁉」
そこで初めて我に返ったように、彼女が声を上げた。
「いや……大丈夫か? どこか切ったのか?」
「う、ううん。大丈夫だよ。ちょっとびっくりしただけだから」
早口でそう言うと、みらいはぎこちない動きで残りの破片を片付け始めた。
そして、
「……これで全部、かな。玄関に置いておくけど、さわっちゃ駄目だよ。あと、まだ小さな破片が残ってるかもしれないから、あんまりこの辺歩かないでね。ごめんね。びっくりさせちゃって」
破片の入った袋を手に、みらいはそそくさとリビングから出て行ってしまった。
「……どうしたんだ……あいつ」
皿一枚を割ってしまった程度で、あれほど動揺するだろうか……?
首を傾げながら席に着くと、既に朝食を食べ終えたさよが、彼女の出て行った方をじっと見つめていた。
「どうしたんだよ」
俺が声を掛けると、彼女の肩が一瞬小さく跳ねたが、すぐに、
「……何がですか?」
と、いつもの落ち着いた様子に戻った。
「いや……何かじっと見てたから……」
「別に、何でもありません」
「……そうか」
それ以上訊くこともないので、俺は黙ってトーストを頬張り始める。
「……それよりも例のこと、お願いしますね」
「例のこと?」
トーストを咥えたまま俺は聞き返す。
「……あなたのクラスメイトのことです」
「ああ……そのことか」
反射的に少し顔を顰めてしまう。
「初音さんをイジメていたメンバーが狙われているとするならば、恐らく彼女で最後です」
「ああ、そうだな」
「昼間に学校を襲撃してくるような人物です。次も予想外の行動を取ってくる可能性は十分にあります。注意しておいてください」
「……わかった。次はちゃんと監視しておくよ」
「別に、あの件についてあなたを責めているつもりはありません。元々無茶なことをお願いしているのは承知しています」
「…………」
「ですが……あなた昨日、犯人の姿を見ましたよね?」
「……えっ?」
そう言われて顔を上げると、少し険しい表情をしたさよと目が合った。
「相手の顔……見ましたか?」
「いやいや、さすがに見てないよ。ていうか、見てたら真っ先に、お前に報告してるって」
「……それもそうですね」
「どうかしたのか?」
「いえ……もし犯人があなたに顔を見られたと勘違いしていたら、少し厄介だと思いまして」
「厄介って……まさか俺を殺しに来るとか……?」
「それもありますが、捕まるリスクを恐れて犯行のペースを上げてくる可能性があります」
「それって―――」
「はい。今日もしくは明日中に、最後の一人であるあなたのクラスメイトが襲われても、不思議はないということです」
「そんな……⁉」
「あくまでも可能性です。ですが、念頭には置いておいてください。ここまできたら常に最悪のケースを考えておくべきです」
緊張の籠った声でさよが言った。
「わかった」
生唾をごくりと呑み込みながら、俺は頷く。
と、その時、みらいがリビングに戻ってきた。
「ユウ君、朝ごはん食べ終わった? そろそろ用意しないと―――ってまだ全然食べてないじゃない!」
まだほとんど原形を残した俺のトーストを見て、みらいが声を上げる。
「わ、悪い。すぐに食べるよ」
話に夢中で食べることを忘れていた。
熱が抜けて冷たくなってしまったトーストに、俺は勢いよくかぶりついた。
# # #
昨日の惨事により、俺の教室は当然使用不可となっていた。そのため俺たちのクラスには、予備教室が用意されていた。同じ階にある廊下の一番奥の教室だ。
予備教室は意外にも綺麗で、隅々まで掃除は行き届いているようだった。備品も全て揃っている。
席は特に指定されていないようだったので、俺は廊下側の真ん中の席に腰を下ろした。
あんな出来事があったにもかかわらず、クラスにはほとんどの生徒が登校してきていた。だがその表情は、やはり暗い。教室内には、昨日までよりもさらに重たい空気が漂っていた。
時折、女子生徒たちのひそひそ声が聞こえてくる。その声に耳を傾けていると、
―――が、死んだ。
―――ダメだった。
そんな声が、断片的に俺の耳に入ってきた。
それだけで、俺は何のことか理解することができた。
そうか。やっぱり―――
予想はしていたがやはりショックだった。初音をイジメていた奴とはいえ、あのような形でクラスメイトが一人欠けてしまうのは、精神的に辛いものがある。
一瞬、感傷に浸ってしまいそうになったが、今はそんな感情に囚われている場合ではないと、俺は頭を強く振った。
自分が今すべきことを考える。朝さよに言われたことを思い出す。そう。俺が今すべきことは―――
俺は窓際の、一番後ろの席に視線を移す。そこには彼女が座っていた。机に頭を突っ伏している。
次の犯行を阻止し犯人を捕まえるため、少しでも長く彼女のことを監視しておかなければならない。次に狙われるのは間違いなく彼女だろう。そこに、どんな動機があるのかはわからないが……。
俺は席を立ち、背後から彼女に近づいた。
昨日と同じ轍を踏まないよう、今のうちにできる対策はしておこうと思った。もしかしたら犯人は今日、彼女の命を狙ってくるかもしれないのだ。
「ちょっといいか」
俺が横から声を掛けると、彼女の背中が大きく跳ねた。そして、弾かれたようにこちらを振り返る。
「と、時坂君……⁉」
俺の顔を見ると、彼女はその表情を少し引き攣らせた。口端がピクピクと痙攣している。
彼女の顔は遠目からでもわかるくらいに青ざめており、目の下には大きな隈ができていた。いつも手入れが行き届いていたはずの茶髪のロングヘアは、その艶を失いボサボサになっている。
「ど、どうしたの? 声掛けてくるなんて珍しいね」
震えた声で彼女が言った。
「あ、いや、ちょっと話があるんだけど……大丈夫か? 体調でも悪いのか?」
明らかに具合の悪そうな彼女を俺は心配する。同じ学年の友人が立て続けに三人も亡くなったのだから、精神的ショックで体調を崩すことも無理はないが、それにしても、今の彼女はひどく具合が悪そうで、そして何かに怯えているようだった。もしかすると彼女も、薄々勘づき始めているのだろうか。次の標的が自分かもしれないということに。
「……保健室、行くか?」
「う、ううん。全然大丈夫だよ」
不格好な笑みを浮かべて、彼女は早口に俺の申し出を断った。
「それより何? 話って」
上擦った声で彼女が訊ねてきた。
具合が悪そうな彼女のことは依然心配だったが、
「……話したいことっていうか、守ってほしいことがあるんだけど……」
と、俺は曖昧に話を切り出した。
「うん……? 何?」
「その……これからは、一人になるときは出来るだけ俺に声を掛けてくれないか?」
「えっ……? 何で……?」
当然のことながら、彼女は怪訝そうな顔をする。
当然だ。クラスメイトとはいえ、よく話したこともない男子から、突然こんなことを言われれば気味悪がるに決まっている。
俺は誤解を解くために、
「いや……ほら、この頃変な事故が続いているだろ。だからなるべく一人にならない方がいいかなと思ってさ……」
「あ、ああ……そう、だね。でも、どうして……私なの?」
「そ、それは―――」
そこで俺は言葉を詰まらせた。
まさか、今まで亡くなった生徒たちが誰かに呪い殺された可能性が高く、次に狙われるのはお前だからだ、なんて答えるわけにはいかない。そんなことを言えば彼女を不必要に動揺させてしまうことになり、結果として彼女の監視が難しくなってしまう。
どう説明したものか―――。
俺は考える。昨日のうちに理由を考えてくればよかったと少し後悔した。
……どうして私なの、か。
頭の中で、俺は今しがたの彼女の言葉を反芻した。
その時、俺の中でずっと蓋をしていたパンドラの箱が少しだけ開き、中からどす黒い感情が溢れ出してきた。それはバケツの水に絵の具を溶かすみたいに、胸の内をじわじわと侵食していき、やがて俺の正気を奪った。
「……お前が、初音をイジメていた奴らの仲間だからじゃないのか」
しまったと思った時には遅かった。
気づいた時には口に出していた。
俺がそう言った途端、彼女の目は大きく見開かれた。
「どうして……それを……」
蚊の啼くような小さな声が彼女の口から漏れる。
「い、いや、違うんだ―――」
俺は慌てて取り繕うとした―――
しかし、
「一体何だっていうんだよ!」
突然、彼女がヒステリックに叫んだ。
「今頃なんだっていうんだよ! 何で私たちがこんな目に遭わなくちゃいけないんだよ⁉ あいつの亡霊でもいるっていうのかよっ⁉」
ボサボサの髪を鷲掴みにしながら、彼女は激しく取り乱す。
「な、何を―――」
「次に殺されるのは私だっていうの⁉ ふざけんなっ! 私は関係ない! 私はやってない! あんなのはもう時効だろっ!」
俺の声を遮り、いやいやと首を横に振り、彼女はこれでもかというくらいに喚き散らした。肩を上下させ、荒い息を吐き出している。
そんな彼女の姿を、俺はしばらく呆然と眺めていた。
彼女の金切り声が、鼓膜の奥でわんわんと反響している。こんなにも動揺を露にする彼女を見るのは初めてだった。
だがやがて、
キーンコーンカーンコーン―――
そんな間延びしたチャイムの音で、俺たちは我に返った。
「あ……」
怯えたような上目遣いで、彼女が俺を見てくる。
俺は、
「……後で詳しく聞かせてくれ」
それだけ言うと、自分の席に戻った。
クラスの視線が俺たちに集まっていたが、そんなものは気にならなかった。それよりも……
やはり、彼女たちが初音をイジメていたことは事実だった―――
そのことが、今の俺の頭を支配していた。
しかも彼女は、次は自分が狙われるようなことを言っていた。
どうやら彼女も、今回の一連の出来事はただの事故などではなく、二年前に俺の妹をイジメていた自分のグループが狙われているということに気付いているらしい。
全く、どうして俺はあんな奴を守らないといけないんだろうな―――
自嘲するような笑みを浮かべて、俺は窓の外を見る。
空には重たそうな雲が広がっていた。
すまん初音。こんな俺を許してくれ―――
俺は、胸の中で彼女に謝った。
眠い目をこすりながらリビングの扉を開けると、そこにはすでに、さよとみらいの姿があった。制服に着替えたさよは、テーブルの席に座り、こんがりと焼けたトーストを細かく手でちぎりながら、その小さな口に運んでいる。
「あ、ユウ君おはよー。また自分で起きれたんだ。えらいねー」
台所で洗い物をしていたみらいが、起きてきた俺に気が付いた。
「ああ、おはよ」
だが、俺は彼女の方は見ずに、ぶっきらぼうな返事を返す。
昨夜のことがあり、何となく彼女と目を合わせ辛かった。
だが、みらいは特に気にした様子もなく、
「はい、ユウ君の朝ごはんだよ。早く食べちゃってね」
俺の目の前にプレートとグラスが置かれる。プレートには目玉焼きと程よく焦げ目の付いたトーストが載せられており、グラスには麦茶が入れられていた。
「……ありがと」
彼女の焼いてくれたトーストに俺はかぶりつく。いつも通りの味だ。何も変わらない。
少しだけ安心した。
が、その時、
パリンッ―――!
台所の方から、何かが割れるような音が聞こえた。
驚いて見ると、シンクの前に立っていたみらいが、自分の足元を見たまま固まっていた。席を立って見に行くと、彼女の足元には真っ白なディナープレートが粉々になって散らばっていた。どうやら洗い物をしている最中に誤って手を滑らせてしまったようだ。
「おいおい何やってんだよ。大丈夫か?」
俺はシンク下からゴミ袋を取り出すと、散乱した破片を袋の中に入れていく。
……だが、おかしい。いつまで経っても彼女が手伝ってくれる気配がない。
不思議に思って顔を上げると―――みらいは濡れた自分の両手を見つめたまま、まるで石像のように固まっていた。鳶色の瞳が、これでもかというくらいに見開かれている。
「おい、どうしたんだ」
驚いて俺は声を掛けた。しかし、彼女は微動だにしない。
手でも切ったのかと思い、立ち上がって彼女の手を取ると、
「えっ、な、何⁉」
そこで初めて我に返ったように、彼女が声を上げた。
「いや……大丈夫か? どこか切ったのか?」
「う、ううん。大丈夫だよ。ちょっとびっくりしただけだから」
早口でそう言うと、みらいはぎこちない動きで残りの破片を片付け始めた。
そして、
「……これで全部、かな。玄関に置いておくけど、さわっちゃ駄目だよ。あと、まだ小さな破片が残ってるかもしれないから、あんまりこの辺歩かないでね。ごめんね。びっくりさせちゃって」
破片の入った袋を手に、みらいはそそくさとリビングから出て行ってしまった。
「……どうしたんだ……あいつ」
皿一枚を割ってしまった程度で、あれほど動揺するだろうか……?
首を傾げながら席に着くと、既に朝食を食べ終えたさよが、彼女の出て行った方をじっと見つめていた。
「どうしたんだよ」
俺が声を掛けると、彼女の肩が一瞬小さく跳ねたが、すぐに、
「……何がですか?」
と、いつもの落ち着いた様子に戻った。
「いや……何かじっと見てたから……」
「別に、何でもありません」
「……そうか」
それ以上訊くこともないので、俺は黙ってトーストを頬張り始める。
「……それよりも例のこと、お願いしますね」
「例のこと?」
トーストを咥えたまま俺は聞き返す。
「……あなたのクラスメイトのことです」
「ああ……そのことか」
反射的に少し顔を顰めてしまう。
「初音さんをイジメていたメンバーが狙われているとするならば、恐らく彼女で最後です」
「ああ、そうだな」
「昼間に学校を襲撃してくるような人物です。次も予想外の行動を取ってくる可能性は十分にあります。注意しておいてください」
「……わかった。次はちゃんと監視しておくよ」
「別に、あの件についてあなたを責めているつもりはありません。元々無茶なことをお願いしているのは承知しています」
「…………」
「ですが……あなた昨日、犯人の姿を見ましたよね?」
「……えっ?」
そう言われて顔を上げると、少し険しい表情をしたさよと目が合った。
「相手の顔……見ましたか?」
「いやいや、さすがに見てないよ。ていうか、見てたら真っ先に、お前に報告してるって」
「……それもそうですね」
「どうかしたのか?」
「いえ……もし犯人があなたに顔を見られたと勘違いしていたら、少し厄介だと思いまして」
「厄介って……まさか俺を殺しに来るとか……?」
「それもありますが、捕まるリスクを恐れて犯行のペースを上げてくる可能性があります」
「それって―――」
「はい。今日もしくは明日中に、最後の一人であるあなたのクラスメイトが襲われても、不思議はないということです」
「そんな……⁉」
「あくまでも可能性です。ですが、念頭には置いておいてください。ここまできたら常に最悪のケースを考えておくべきです」
緊張の籠った声でさよが言った。
「わかった」
生唾をごくりと呑み込みながら、俺は頷く。
と、その時、みらいがリビングに戻ってきた。
「ユウ君、朝ごはん食べ終わった? そろそろ用意しないと―――ってまだ全然食べてないじゃない!」
まだほとんど原形を残した俺のトーストを見て、みらいが声を上げる。
「わ、悪い。すぐに食べるよ」
話に夢中で食べることを忘れていた。
熱が抜けて冷たくなってしまったトーストに、俺は勢いよくかぶりついた。
# # #
昨日の惨事により、俺の教室は当然使用不可となっていた。そのため俺たちのクラスには、予備教室が用意されていた。同じ階にある廊下の一番奥の教室だ。
予備教室は意外にも綺麗で、隅々まで掃除は行き届いているようだった。備品も全て揃っている。
席は特に指定されていないようだったので、俺は廊下側の真ん中の席に腰を下ろした。
あんな出来事があったにもかかわらず、クラスにはほとんどの生徒が登校してきていた。だがその表情は、やはり暗い。教室内には、昨日までよりもさらに重たい空気が漂っていた。
時折、女子生徒たちのひそひそ声が聞こえてくる。その声に耳を傾けていると、
―――が、死んだ。
―――ダメだった。
そんな声が、断片的に俺の耳に入ってきた。
それだけで、俺は何のことか理解することができた。
そうか。やっぱり―――
予想はしていたがやはりショックだった。初音をイジメていた奴とはいえ、あのような形でクラスメイトが一人欠けてしまうのは、精神的に辛いものがある。
一瞬、感傷に浸ってしまいそうになったが、今はそんな感情に囚われている場合ではないと、俺は頭を強く振った。
自分が今すべきことを考える。朝さよに言われたことを思い出す。そう。俺が今すべきことは―――
俺は窓際の、一番後ろの席に視線を移す。そこには彼女が座っていた。机に頭を突っ伏している。
次の犯行を阻止し犯人を捕まえるため、少しでも長く彼女のことを監視しておかなければならない。次に狙われるのは間違いなく彼女だろう。そこに、どんな動機があるのかはわからないが……。
俺は席を立ち、背後から彼女に近づいた。
昨日と同じ轍を踏まないよう、今のうちにできる対策はしておこうと思った。もしかしたら犯人は今日、彼女の命を狙ってくるかもしれないのだ。
「ちょっといいか」
俺が横から声を掛けると、彼女の背中が大きく跳ねた。そして、弾かれたようにこちらを振り返る。
「と、時坂君……⁉」
俺の顔を見ると、彼女はその表情を少し引き攣らせた。口端がピクピクと痙攣している。
彼女の顔は遠目からでもわかるくらいに青ざめており、目の下には大きな隈ができていた。いつも手入れが行き届いていたはずの茶髪のロングヘアは、その艶を失いボサボサになっている。
「ど、どうしたの? 声掛けてくるなんて珍しいね」
震えた声で彼女が言った。
「あ、いや、ちょっと話があるんだけど……大丈夫か? 体調でも悪いのか?」
明らかに具合の悪そうな彼女を俺は心配する。同じ学年の友人が立て続けに三人も亡くなったのだから、精神的ショックで体調を崩すことも無理はないが、それにしても、今の彼女はひどく具合が悪そうで、そして何かに怯えているようだった。もしかすると彼女も、薄々勘づき始めているのだろうか。次の標的が自分かもしれないということに。
「……保健室、行くか?」
「う、ううん。全然大丈夫だよ」
不格好な笑みを浮かべて、彼女は早口に俺の申し出を断った。
「それより何? 話って」
上擦った声で彼女が訊ねてきた。
具合が悪そうな彼女のことは依然心配だったが、
「……話したいことっていうか、守ってほしいことがあるんだけど……」
と、俺は曖昧に話を切り出した。
「うん……? 何?」
「その……これからは、一人になるときは出来るだけ俺に声を掛けてくれないか?」
「えっ……? 何で……?」
当然のことながら、彼女は怪訝そうな顔をする。
当然だ。クラスメイトとはいえ、よく話したこともない男子から、突然こんなことを言われれば気味悪がるに決まっている。
俺は誤解を解くために、
「いや……ほら、この頃変な事故が続いているだろ。だからなるべく一人にならない方がいいかなと思ってさ……」
「あ、ああ……そう、だね。でも、どうして……私なの?」
「そ、それは―――」
そこで俺は言葉を詰まらせた。
まさか、今まで亡くなった生徒たちが誰かに呪い殺された可能性が高く、次に狙われるのはお前だからだ、なんて答えるわけにはいかない。そんなことを言えば彼女を不必要に動揺させてしまうことになり、結果として彼女の監視が難しくなってしまう。
どう説明したものか―――。
俺は考える。昨日のうちに理由を考えてくればよかったと少し後悔した。
……どうして私なの、か。
頭の中で、俺は今しがたの彼女の言葉を反芻した。
その時、俺の中でずっと蓋をしていたパンドラの箱が少しだけ開き、中からどす黒い感情が溢れ出してきた。それはバケツの水に絵の具を溶かすみたいに、胸の内をじわじわと侵食していき、やがて俺の正気を奪った。
「……お前が、初音をイジメていた奴らの仲間だからじゃないのか」
しまったと思った時には遅かった。
気づいた時には口に出していた。
俺がそう言った途端、彼女の目は大きく見開かれた。
「どうして……それを……」
蚊の啼くような小さな声が彼女の口から漏れる。
「い、いや、違うんだ―――」
俺は慌てて取り繕うとした―――
しかし、
「一体何だっていうんだよ!」
突然、彼女がヒステリックに叫んだ。
「今頃なんだっていうんだよ! 何で私たちがこんな目に遭わなくちゃいけないんだよ⁉ あいつの亡霊でもいるっていうのかよっ⁉」
ボサボサの髪を鷲掴みにしながら、彼女は激しく取り乱す。
「な、何を―――」
「次に殺されるのは私だっていうの⁉ ふざけんなっ! 私は関係ない! 私はやってない! あんなのはもう時効だろっ!」
俺の声を遮り、いやいやと首を横に振り、彼女はこれでもかというくらいに喚き散らした。肩を上下させ、荒い息を吐き出している。
そんな彼女の姿を、俺はしばらく呆然と眺めていた。
彼女の金切り声が、鼓膜の奥でわんわんと反響している。こんなにも動揺を露にする彼女を見るのは初めてだった。
だがやがて、
キーンコーンカーンコーン―――
そんな間延びしたチャイムの音で、俺たちは我に返った。
「あ……」
怯えたような上目遣いで、彼女が俺を見てくる。
俺は、
「……後で詳しく聞かせてくれ」
それだけ言うと、自分の席に戻った。
クラスの視線が俺たちに集まっていたが、そんなものは気にならなかった。それよりも……
やはり、彼女たちが初音をイジメていたことは事実だった―――
そのことが、今の俺の頭を支配していた。
しかも彼女は、次は自分が狙われるようなことを言っていた。
どうやら彼女も、今回の一連の出来事はただの事故などではなく、二年前に俺の妹をイジメていた自分のグループが狙われているということに気付いているらしい。
全く、どうして俺はあんな奴を守らないといけないんだろうな―――
自嘲するような笑みを浮かべて、俺は窓の外を見る。
空には重たそうな雲が広がっていた。
すまん初音。こんな俺を許してくれ―――
俺は、胸の中で彼女に謝った。
0
あなたにおすすめの小説

それなりに怖い話。
只野誠
ホラー
これは創作です。
実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。
本当に、実際に起きた話ではございません。
なので、安心して読むことができます。
オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。
不定期に章を追加していきます。
2025/12/31:『たこあげ』の章を追加。2026/1/7の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/30:『ねんがじょう』の章を追加。2026/1/6の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/29:『ふるいゆうじん』の章を追加。2026/1/5の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/28:『ふゆやすみ』の章を追加。2026/1/4の朝4時頃より公開開始予定。
2025/12/27:『ことしのえと』の章を追加。2026/1/3の朝8時頃より公開開始予定。
2025/12/26:『はつゆめ』の章を追加。2026/1/2の朝8時頃より公開開始予定。
2025/12/25:『がんじつのおおあめ』の章を追加。2026/1/1の朝4時頃より公開開始予定。
※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。

終焉列島:ゾンビに沈む国
ねむたん
ホラー
2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。
最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。
会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

【完結】ホラー短編集「隣の怪異」
シマセイ
ホラー
それは、あなたの『隣』にも潜んでいるのかもしれない。
日常風景が歪む瞬間、すぐそばに現れる異様な気配。
襖の隙間、スマートフォンの画面、アパートの天井裏、曰く付きの達磨…。
身近な場所を舞台にした怪異譚が、これから続々と語られていきます。
じわりと心を侵食する恐怖の記録、短編集『隣の怪異』。
今宵もまた、新たな怪異の扉が開かれる──。

【完結】知られてはいけない
ひなこ
ホラー
中学一年の女子・遠野莉々亜(とおの・りりあ)は、黒い封筒を開けたせいで仮想空間の学校へ閉じ込められる。
他にも中一から中三の男女十五人が同じように誘拐されて、現実世界に帰る一人になるために戦わなければならない。
登録させられた「あなたの大切なものは?」を、互いにバトルで当てあって相手の票を集めるデスゲーム。
勝ち残りと友情を天秤にかけて、ゲームは進んでいく。
一つ年上の男子・加川準(かがわ・じゅん)は敵か味方か?莉々亜は果たして、元の世界へ帰ることができるのか?
心理戦が飛び交う、四日間の戦いの物語。
(第二回きずな児童書大賞で奨励賞を受賞しました)

黒に染まった華を摘む
馬場 蓮実
青春
夏の終わりに転校してきたのは、忘れられない初恋の相手だった——。
高須明希は、人生で“二番目”に好きになった相手——河西栞に密かに想いを寄せている。
「夏休み明けの初日。この席替えで、彼女との距離を縮めたい。話すきっかけがほしい——」
そんな願いを胸に登校したその朝、クラスに一人の転校生がやってくる。
彼女の名は、立石麻美。
昔の面影を残しながらも、まるで別人のような気配をまとう彼女は——明希にとって、忘れられない“初恋の人”だった。
この再会が、静かだった日常に波紋を広げていく。
その日の放課後。
明希は、"性の衝動"に溺れる自身の姿を、麻美に見られてしまう——。
塞がっていた何かが、ゆっくりと崩れはじめる。
そして鬱屈した青春は、想像もしていなかった熱と痛みを帯びて動き出す。
すべてに触れたとき、
明希は何を守り、何を選ぶのか。
光と影が交錯する、“遅れてきた”ひと夏の物語。
前編 「恋愛譚」 : 序章〜第5章
後編 「青春譚」 : 第6章〜
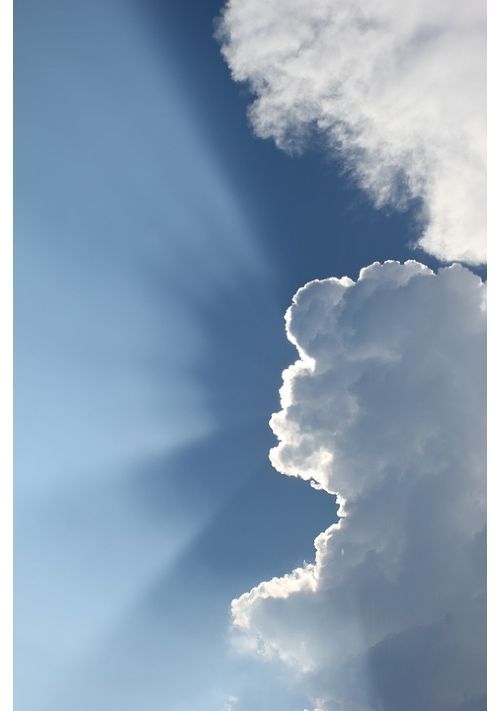
君との空へ【BL要素あり・短編おまけ完結】
Motoki
ホラー
一年前に親友を亡くした高橋彬は、体育の授業中、その親友と同じ癖をもつ相沢隆哉という生徒の存在を知る。その日から隆哉に付きまとわれるようになった彬は、「親友が待っている」という言葉と共に、親友の命を奪った事故現場へと連れて行かれる。そこで彬が見たものは、あの事故の時と同じ、血に塗れた親友・時任俊介の姿だった――。
※ホラー要素は少し薄めかも。BL要素ありです。人が死ぬ場面が出てきますので、苦手な方はご注意下さい。

靴屋の娘と三人のお兄様
こじまき
恋愛
靴屋の看板娘だったデイジーは、母親の再婚によってホークボロー伯爵令嬢になった。ホークボロー伯爵家の三兄弟、長男でいかにも堅物な軍人のアレン、次男でほとんど喋らない魔法使いのイーライ、三男でチャラい画家のカラバスはいずれ劣らぬキラッキラのイケメン揃い。平民出身のにわか伯爵令嬢とお兄様たちとのひとつ屋根の下生活。何も起こらないはずがない!?
※小説家になろうにも投稿しています。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















