9 / 18
第二章「魔法使いの町。」
00
しおりを挟むまことしやかに囁かれる都市伝説のような町。
ここはそういう場所で、どの地図にも載っていないし、どこの国のものでもない。
強いて言えば、そうだ。ここに王として君臨すべきは、十人の弟子をとって消えたという原初の魔法使いくらいのものだろう。
男とも女とも知れぬその魔法使いは、様々な魔法を駆使するといわれている。
何しろ島を一つ、魔法で作り上げてしまうほどだ。
この町にいる魔法使いも、魔女も、彼女の弟子の系譜を持つものばかりで、その全員が合わさっても島など、造れるかどうか。
いや、作れはしない。
この町だって、何人もの人垣の上に成り立っているようなものだ。
(ともすれば、原初の魔法使いとは、どれほどのものだったのか)
男、マギサ・バルサーモはじ、と目の前のフラスコが青色の液体を煮えたぎらせるのを見つめた。
錬金術師として生計を立てる彼は、こうして薬を作っては、商人に流すのが仕事だった。
「そういえば、ウェルダーパークの方で何やら騒ぎがあったそうだよ」
ぎい、と音を立てて入ってきた声に、彼は苦虫を嚙み潰したような顔を向けた。
「……ジェルマン。納品はまだかと思うが」
「心得ているよ、バルサーモ公。今日の私はただの客人さ」
かっちりとしたスーツに身を包んだ紳士は、軽く会釈した。
その頭に乗ったシルクハットがふわっと一瞬とんで、男の頭を離れる。
男が顔をあげると、シルクハットはまた元の位置にひとりでに戻った。
「僕のことを『公』などと呼ぶのはやめにしてくれ。何度も言っているだろう。僕には誇るべき地位など何もない」
「謙遜はよしたまえよ。君はこの町の錬金術師の中で間違いなくトップクラス。それはこの町の誰もがわかっていることだろう」
「ははは。また馬鹿げたおべんちゃらを」
彼はキッとその紳士を睨みつけた。
サン・ジェルマン伯爵。それが『今の』彼の名であり、当分の偽名だ。
いやもしかしたらずっと使う気なのかもしれない。何しろ十八世紀頃からずうっと使い続けているのだから。
彼には何を言っても無駄とわかっていたマギサは、はあ、と大げさにため息をつくとまたフラスコへと向き合った。
「そもそも、あんな偽物だらけの町がどうなろうと僕の知ったことじゃない」
吐き捨てるように呟くと、サン・ジェルマン伯爵はこつ、と足音を立てる。
「偽物の中にもホンモノは埋まっているとも。それを探すのもまた、商人としては好ましい行為のひとつだよ」
「……商人、ねえ」
最近のサン・ジェルマン伯爵がもっぱら言って回っている職業だった。
本職ではないことを、マギサはよく知っていた。
「バルサーモ公は『原初の魔法使い』に大変憧れがあっただろう?」
伯爵は勝手にソファへどかりと腰を下ろす。
そうしてその長い足を組み替えると、マギサを見た。
マギサはぴくりと反応して、手を止めた。
「……それに関することで、何かあったとでも?」
「いいや、本人じゃないがね。『彼女』の十人の弟子の方で、少し」
フラスコの火を止める。
そうしてそれを金属のトングでつかむと、そっと冷水に浸した。
ジュッという音が短くあがる。
「弟子のひとりが現れたとでもいうつもりか? それこそ笑えないジョークだ」
嘲るように、マギサは笑った。
「彼らはみな、一様に姿をくらました。それも、もう何百年にもなる」
「生きているかどうかわからない、と?」
「実際、以降動きがないんだ。そう考えたって当然のことだろう」
フラスコを冷水から引き上げると、青かった液体は紫色になっていた。
成功だ。
ニイ、と思わず口角をあげる。
「見事だ」
「!」
いつのまにか隣に伯爵が立っていた。
覗き込むように、掲げたフラスコを覗き込んでいる。
「君の錬金術はいつ見ても素晴らしい。私も覚えはあるが、ブランクがひどくてね」
マギサはフラスコを机に戻すと、ため息をついた。
「……結局何があったのかはぐらかすつもりか?」
「ああ、失礼。やはり興味があったのだね」
「嫌味なやつだ」
「誉め言葉として受け取ろう」
伯爵は、再び歩いて、今度は窓際へと行った。
その薄っぺらなガラス窓に指を這わせると、どこか遠くを見てほくそ笑むように笑った。
「悪い冗談さ。──機械仕掛けの魔法使いが現れたらしい」
「は」
手にした試験管を、危うく落とすところだった。
マギサはぐるんと体を回転させて振り返ると、伯爵に勢いよく詰め寄った。
「十人のうち、よもや、『別次元に消えた』弟子が、現れただと!」
「あくまでも噂だよ、噂。魔術師たちの流した噂のひとつにすぎない」
だが、と伯爵は続けた。
「ウェルダーパークもまた、別次元のようなものだ。こことは違う。──ならば、『その次元』と『あの町』が繋がっていてもおかしくはあるまい?」
マギサは、しばらく黙り込んだ。
それから、じり、と後ずさった。
「どうだね? 私と共に、あの町へ行ってはみないか?」
「……断る」
「ほう」
伯爵は眉をぴくりと動かした。
「それは、なぜか、理由をきいても?」
マギサは、また、実験設備の前まで戻ると、試験管に手を伸ばした。
空っぽのそれに、フラスコの中身をほんの少し入れると、試験管置き場に戻す。
そうしてまた、空っぽのそれに手を伸ばす。
「僕はあの町が嫌いだ。もし弟子がいたとしても、だ」
「……ふうむ」
その真っ赤な目に見つめられて、伯爵は困ったように唸った。
「残念だ。私としては、旧友にすがりたかったのだが」
「僕を友として数えたのがそもそもの間違いだったな」
マギサにはそれに取り合う様子がまるでなかった。
彼はもはや、自分の作業に目を向けている。
「帰りたまえよ。靡かないものに無駄な言葉をはぐ時間など、君にはないだろう」
マギサがそう吐き捨てると、ややしばらく間をあけてから、「そうするよ」と伯爵は呟いた。
ようやくのこと、諦めたようだった。
マギサがふうとため息をつくと、伯爵はぴたり、とその足を止めた。
ドアの前だった。
「もし、気が変わったなら言ってくれ。私と共にきてくれるなら、それ相応の謝礼も用意しよう」
「金なら要らない。僕には有り余っている」
「ふふ、そんなものじゃあないさ」
伯爵はまたほくそ笑むようにして、今度こそドアから外へと出ていった。
ごーん。ごーん。ごーん。
古い置時計が鳴る。
午後三時を知らせる音だった。
(休憩か)
マギサは手を止めて、ぐぐ、と体を伸ばした。
サン・ジェルマン伯爵とは長い付き合いになるが、彼だけが、原初の魔法使いを『彼女』と呼ぶ。
誰もがその姿を目にすることのない町で──彼だけが。
(会ったことがあるんだろう、あの男。詳しく話すことはないが)
その事実を加味しても、マギサはウェルダーパークには行こうと思えなかった。
あの魔術師の町にもし行く機会があるとすれば、あの町のものたちを皆殺しにするときくらいのものだ。
保冷庫をあけて、ペットボトルを手に取る。
中の液体を口の中に流し込んで、マギサはソファに座り込んだ。
ほのかに香るサン・ジェルマンの残り香が、彼の眉間に少しのしわを寄せていた。
***
ユキさんは朝からご機嫌だった。
鍋で淹れた熱々のココアと、四つ切りのふかふかトースト。
奮発してのせた四角のバターがとろけるさまは、確かに俺も少し興奮した。
ばり、という香ばしい音。
鼻腔をつく麦とカカオの匂い。
「確かに究極のトーストだよ……」
ふるふると震えながらそう呟くユキさんの姿はなんだか微笑ましかった。
トースト一つでここまで感銘を受けれる、というのが、なんとも。
「美味しいねえ、阿久津くん」
「そうだな」
ずず、と啜るココアの苦みも好ましい。
これで朝日でも窓から差し込もうものなら、本当に最高の朝である。
「今日は絵、売りにいくのか」
横目で真っ黒な布に包まれたまま、イーゼルに立てかけられているキャンバスを見る。
あれには、きちんとあの魔女の力の一部が封じ込められているらしい。
それを売るというのだから、なんだか危険な感じがするし、魔女的にもいいのかとは思ったが、『いい』らしい。
力なんて自然に回復するから、と彼女はオーリスの中で話していた。
「ウン。一応、そういうものを取り扱う商人にアテがあってね。今日は彼に会いにいく予定だよ」
「ふーん……どんなやつ?」
「ちょっと変わってるけど、昔馴染みさ。阿久津くんもついてくるかい?」
「……まあ、別に用事はないけどよ」
俺がそう切り返すと、ユキさんは少し目を丸くして驚いたようだった。
「ほ、ほんとに? ついてきてくれるの?」
「用事ねえからな。……なんだよ?」
「いや……今まで誘ってもついてきてくれなかったから……」
今度は俺がきょとんとする番だった。
誘われた記憶はほとんどないが、そういえば、そうだったかもしれない。
なんだかんだここが『家』だと認識できたのもつい最近のことだし。
「なんか、嬉しいな。キミとあの『町』を歩けると思うと、わくわくする」
「あの町って、なんだ、このへんじゃねえのか?」
「うん。絶滅危惧種的な僕らにも、町があるんだ。列車に乗るよ」
「列車って……地下鉄じゃなくて?」
ユキさんと移動するときは、もっぱら地下鉄だった。
地下鉄の付近まで箒で飛んで、そこから地下鉄に乗るのだ。
この方が魔力の削減にもなるし、近代に触れられてユキさん的に満足らしい。
今は車があることもわかったし、俺としては別に、あのオーリスでもいいのだが……。
「僕ら専用のものがあるからね。そこまで行くための『鍵』もあるんだよ」
ほら、とユキさんは懐から大きなカギを取り出した。
複製がラクそうな、アンティーク調のものだ。
今どきの鍵穴には到底はまりそうもない。
「これを、どうすんだ?」
「適当なドアをつくって、そのカギ穴に差し込んで回すだけ。そしたら向こう側にすぐ出れるの」
飲み終えたココアのカップがテーブルに置かれた。
空っぽになった皿とカップが、ひとりでにふよふよと浮いて、流しの方へ去っていく。
「さっそく準備をしよう。通貨が違うからね、向こうの硬貨を取り出さないと……ええと、どこにあったかな」
ごそごそと、ユキさんはトランクを漁り始めた。
ので、俺は自分のカップと皿を流しの方へ持っていく。
みれば流しの中は洗濯機みたいに泡だらけになっていて、食器たちがその中で泳いでいた。
ユキさんの魔法だ。
たぶん、機嫌がいいあまり、何か漏れ出してしまっているに違いない。
(……子供かよ、ほんと)
まだココアの粉は残っているし、パンも二つある。
今度はチーズトーストでも作ってやろう、とそう思った。
「ねえ、僕の手袋とか知らない? そのへんに投げてたやつ」
「あー、全部まとめて洗濯して、そのへんにしまったけど」
「ほんと? どこいっちゃったかなー」
「そもそもそのへんに投げるな。ちゃんとしまっておけよ」
「片腕だからしまいづらいんだよー」
「魔法があるだろ、魔法が」
ほどなくして俺はあの重たいトランクを持たされ、灰色の外套をかぶせられた。
マントみたいなものだ。古めかしいもので、背丈の関係上、腰より少し下くらいまでしかない。
ユキさんは珍しく杖を持っていて、それでとん、と家の壁を叩いた。
「うお」
ずず、と音を立ててドアが壁から浮き出てくる。
そのドアノブの下には、あの鍵が入りそうな大きなカギ穴があった。
「……前からこうやって出入りしてたのか?」
「うん。キミがいないときだけれどね」
ユキさんの手から離れた鍵が、ゆらゆらとただよって、がちゃり。
鍵穴でひとりでに回ると、今度はドアノブがひとりでに回って、ゆっくりとドアが開く。
あのアンティーク調の鍵はユキさんのポケットへ。
ドアの向こう側には、どこか慌ただしい駅のホームがあった。
「まじかよ……」
「まじだよ」
俺の呟きに、ユキさんはどこか自慢げにうなずいて歩き出した。
その背中を慌てて追いかける。
どこかヨーロッパの風が吹くそこを行き交う人々は、誰も彼もが、俺たちと同じように外套をまとっていた。
0
あなたにおすすめの小説

俺の婚約者は小さな王子さま?!
大和 柊霞
BL
「私の婚約者になってくれますか?」
そう言い放ったのはこの国の王子さま?!
同性婚の認められるパミュロン王国で次期国王候補の第1王子アルミスから婚約を求められたのは、公爵家三男のカイルア。公爵家でありながら、長男のように頭脳明晰でもなければ次男のように多才でもないカイルアは自由気ままに生きてかれこれ22年。
今の暮らしは性に合っているし、何不自由ない!人生は穏やかに過ごすべきだ!と思っていたのに、まさか10歳の王子に婚約を申し込まれてしまったのだ。
「年の差12歳なんてありえない!」
初めはそんな事を考えていたカイルアだったがアルミス王子と過ごすうちに少しづつ考えが変わっていき……。
頑張り屋のアルミス王子と、諦め系自由人のカイルアが織り成す救済BL

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
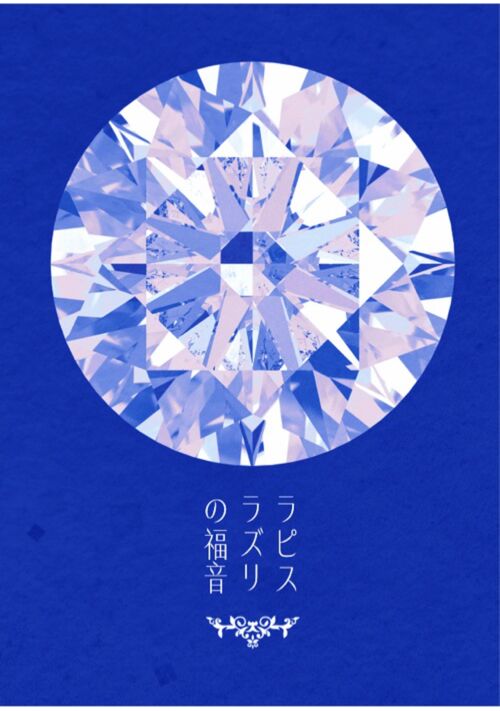
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

カフェ・コン・レーチェ
こうらい ゆあ
BL
小さな喫茶店 音雫には、今日も静かなオルゴール調のの曲が流れている。
背が高すぎるせいか、いつも肩をすぼめている常連の彼が来てくれるのを、僕は密かに楽しみにしていた。
苦いブラックが苦手なのに、毎日変わらずブラックを頼む彼が気になる。
今日はいつもより温度を下げてみようかな?香りだけ甘いものは苦手かな?どうすれば、喜んでくれる?
「君の淹れる珈琲が一番美味しい」
苦手なくせに、いつも僕が淹れた珈琲を褒めてくれる彼。
照れ臭そうに顔を赤ながらも褒めてくれる彼ともっと仲良くなりたい。
そんな、ささやかな想いを込めて、今日も丁寧に豆を挽く。
甘く、切なく、でも愛しくてたまらない――
珈琲の香りに包まれた、静かで優しい記憶の物語。

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















