10 / 18
第二章「魔法使いの町。」
01
しおりを挟む古めかしいイギリス風な列車が来ると、皆一様にそれに乗り込んだ。
その光景は俺がみてきた『通勤風景』とは全く違うもので、誰も彼もが重たそうなトランクを抱えていた。
真っ黒なコート。シルクハット。ドレス。高そうな杖。マント。アンティーク調の外套。
目に映るものすべてが新鮮で、俺は思わず足を止めそうになった。
「こらこら、後ろがつかえているでしょう」
「あ、わるい」
ユキさんに急かされて、俺も列車の中へ。
中の装飾もまるで時が止まっているみたいにアンティークものばかりで、タイムスリップしてしまったようだった。
近代の感じは何もない。あの直角のソファは、腰が痛くなりそうだ。
「失礼。スイートはどこかな、君」
俺があちこち見渡している間に、ユキさんは手早いもので、中の駅員に声をかけていた。
彼はにこやかに微笑むと、先頭の方を指さした。
「あちらです。Cの六〇号室に空きが御座います」
「そう。では、そこを貰おうか」
ユキさんは彼に数枚紙幣のようなものを渡して、それから俺の腕を引いた。
「ほら、いくよ。ここじゃキミ、落ち着いて話も出来ないだろう」
呆れるような、面白がるような。
そんな表情を浮かべるユキさんになんだか気恥ずかしくなりながら、俺もその後に続く。
車内はトランクを荷物棚にあげるひとたちでごった返していて、通路は満足に進めたもんじゃない。
そんな中を、ユキさんはひょいひょいと歩く。ついていくのがやっとだ。
(飛び交う言語もいまいちわかんねえ。日本語じゃないみたいだ)
顔立ちもグローバルなもので、髪色に至っては染めているのか地毛なのか、多種多様にカラフルだった。
布のかかった籠の中には、フクロウや蛇、猫など様々な生き物が見える。
ようやくのことたどり着いた部屋は、個室のようで、ドアがあった。
ユキさんがそこをあけると、向かい合うように設置されたソファが見えた。
ドアのレールの上には、『C 六〇』とある。
「僕ら二人だから、荷物を上にあげる必要はないね。さ、入って」
「お、おう」
直角よりも少し角度があるソファだった。
トランクをおろしてから、腰を下ろす。
長時間座ることには向いてなさそうだ。
「やー、今日も相変わらず混んでたねえ」
にこにこと、ユキさんはドアを閉めた。
それから向かい側に腰かける。
視線はすでに、窓へと向いていた。
その大きな窓からは、ホームがよく見えた。
「……ユキさん。あいつらみんな、魔法使い、なのか?」
「まさか!」
ユキさんは目を丸くしていった。
「ここにいるのは色んな連中さ。でも全員魔法や魔術、錬金術といった『神秘』の世界に属する人たちだよ」
「えー、と、つまり、普通じゃないってことか?」
「そうそう。そんな感じ」
ばたばたと足をばたつかせるユキさんは、どこかはしゃいでいるように見えた。
俺との外出が楽しいのか、この列車に乗るのが楽しいのか。いや、後者だとは思うけれど。
「でも君らの世界と同じく、ワゴンが来るよ。おかしとか食べ物売ってくれるの」
「最近はあれ、事故につながるからやめたらしいぞ」
「ええ……もったいない。面白いのに」
「何か食いたいもんでもあったのか?」
「キミと食べたいものさ。人間世界では見られないものがたくさんあるからね!」
ユキさんはコートのポケットを漁ると、窓枠にそれをばっと出した。
大中小様々な小銭、いやコインというべきか。
どこの国のものとも知れない、カラフルなものが山になった。
「もしきたら、何か買おうじゃないか。どれでもいいよ。大体のものは買えると思う」
「……さっきから思ってたんだが、それ、魔法使いの通貨なのか?」
「まあ、そんなとこ。魔法使い限定じゃないけどね」
「へえ……」
三枚ほど、手に取ってみる。
分厚さはそれぞれだ。
銅の赤い色のものから、青銅、銀、と素材も様々なようだった。
「このほか、金でも取引できるよ。昔から金だけは一定して価値があるからね」
「金って、そのまんまかよ」
「通常は金貨か金塊だね。あとは宝石とかさ」
俺の知らない世界である。
「じゃあ、日本円にはどうやって換金してるわけ? 絵が売れても貰えるのはそれってことだろ?」
「うん。金とか宝石ならそのまんま古物商とか、宝石商に換金しにいくんだけど……この硬貨は両替所でやるよ。一応、そういう施設があるからね」
「ふーん。なんか、思ったよりも現実的なんだな」
両替所とか。
換金とか。
普通に人間社会にもあるものだし、海外ではよく聞く話だ。
いや、俺は海外にいったことはないのだが。
だからこれは、あくまでもフィクションの知識である。あるいはテレビドラマとか、バラエティ番組なんかで培ったものだ。
「君たちは科学と化学で発展した。僕たちは『魔法』や『魔術』で発展した。所詮は、それだけの違いだからね」
ユキさんは、そんなことを呟いて頬杖をついた。
「じゃあ、俺とユキさんが組んだら最強なわけだ」
「へ?」
「だって、俺は家電に強いし、ユキさんは魔法に強い。そういうこったろ」
俺の言葉に、ユキさんはしばらく目を丸くして固まっていた。
そうしてほどなくしてから、とても嬉しそうに「うん!」と頷いた。
ユキさんの現代に疎い感じも、そう考えるとまあ、悪くない。
彼の足らないところを、俺が補っている。
そう考えるとなんだか、俺にとっては都合がいい。
ほどなくして列車が動き出した。
ホームがゆっくりと離れていく。
「こっから遠いのか、そこ」
くあ、と欠伸を漏らすと、ユキさんは笑った。
「二時間くらいかな。寝てるといい。ワゴンがきたら起こすよ」
なんだか吹き出してしまった。
起こす理由、ワゴンかよ。
***
宣言通り、俺はワゴンの到来と共に起こされた。
寝ぼけ眼をこすると、ドアが開いて、そこにフードを深くかぶった男が立っていた。顔はよく見えない。
男はシシッと短く笑うと、言った。
「何に致しましょう?」
彼がひいてきたワゴンには、所狭しと商品が並んでいる。
ペットボトルから、袋菓子まで多種多様だ。
「僕のおすすめはねえ、ビックリチョコでしょー、それからイモリの串焼きにー、サラザール・スナックにー」
「待て待て待て。なんだそりゃ、一個ずつ説明しろよ」
「では、僭越ながら私めが」
そういうと男は、真っ黒な四角い箱を取り出した。
「こちらがビックリチョコ。中身は開けてのお楽しみです」
果たしてそれは説明なのだろうか。
続いて、男はプラスチックの容器を取り出した。
駄菓子でよくあるスルメの容器みたいだった。
中にはくしに刺さった黒い何かがたくさん入っている。
「こちらはイモリの串焼き。メジャーなお菓子ですね。珍味にもなります」
やはりスルメである。
いや、食べたい感じは全くしないが。
それから男は、袋菓子を取り出した。
パッケージには鼻の長い老人が描かれ、『激うま!』とキャッチコピーがある。
「こちらがサラザール・スナック。当店一番人気です」
「何味なんだ、それ」
「サラザール・スナック味です」
「いやだから何味なんだよ……」
パッケージからは全く、何の味なのかわからない。
それどころか、スナックの形すらわからない。
「食べればわかるよ」
ユキさんはニコニコしながらえへへと笑った。
「……じゃ、ユキさんのオススメくれ」
「僕の?」
「ン」
短くうなずくと、ユキさんはワゴンを改めて眺めた。
それから、「じゃあ」と指をさす。
「サラザール・スナックかな! あとサラザール・ドリンクも二つ頂戴」
「かしこまりました」
男は軽く会釈すると、ユキさんが差し出した硬貨を受け取った。
それを数えもせずにポケットに放り込むと、あの袋菓子と、瓶を二本置いてまたドアの向こうへといなくなった。
瓶の中には透明でキラキラしたものが入っている。
「これ、なんだ?」
一つ手に取って宙にかざす。
窓から差し込んだ陽の光が、中身を照らすとそれは七色に輝いているように見えた。
「簡単な星の魔術だよ。中に宇宙の元素を取り込んであるから、星が輝いているように見えるだろ」
言われてみれば、確かにこれは星の輝きによく似ている。
いや、というよりは。
「へー、綺麗だな。ユキさんの魔法みたいだ」
車内の真っ黒な天井に透かす。
より鮮明に、そのキラキラが見て取れる。
ふと、ユキさんからの返答がなかったことが気になって視線を落とす。
ユキさんは、俺を見上げて頬を真っ赤に染めていた。
「……ぼ、僕の魔法、綺麗って思ってくれてたのかい?」
「あ? 今更かよ」
「いや、だって! ……なんというか、その……興味なさそうだったから」
「別に興味ねーわけじゃねえよ。ただ俺の知らない世界ってだけだ」
「そ、そう……」
ぽぽぽ、とユキさんは頬を赤く染めて嬉しそうにしていた。
何がそんなに嬉しいのかは、俺にはわからなかった。
とりあえず、と瓶のふたを開けると、かしゅ、と音がした。
どうやらこのサラザール・ドリンクとやらは炭酸飲料らしい。
匂いを嗅ぐ。……とくに香料の類はなさそうだ。何の匂いもしない。
「これもどうせ、サラザール・ドリンク味とかいうんだろ」
「飲んだらわかるよ、きっとね」
「フーン」
死にはしないだろう、と俺はその瓶に口をつけた。
しゅわ、とやはり炭酸が口内に広がって、それから、舌は甘さを感知した。
爽快感が、全身を駆け抜けては弾けて飛んでいく。
思わず目を見開いた。
なんか、おいしい。味とかよくわからないけど、舌が心地良い。
「うっま……」
「でしょう!」
俺がふいに漏らした言葉に、ユキさんはパア、と表情を明るくして顔を上げた。
「これ僕大好きなんだよね。通販とかできないか、ジェルマンくんに聞いたりしてるの」
ユキさんも、蓋をあけて瓶に口をつけた。
ふるふると身を震わせて、幸せそうに微笑むユキさんの顔をみていたら『ゲテモノかも』と思った自分がなんだか情けなくなった。
袋菓子をつまみ上げる。中を開くと、中には到底スナック菓子とは思えない、星型の透明な物体がいくつも入っていた。
それも光にすかすと、七色にきらきら輝いている。
(スナック、とは)
俺の知っているスナック菓子というのは、原材料にコーンあるいは小麦粉が使われているものばかりなのだが……。
これは一体、何で出来ているのだろうか。
「星型九角形を立体にしたもので、これにも宇宙の元素を使用しているんだ。美味しいよ」
ユキさんはそれを一つ摘まむと、口に放り込んだ。
ぱり、という薄い飴細工を砕いた時のような音が鳴る。
よくわからないものが原料のようだが、うん、まあ、物は試しだ。
俺もそれを一つ摘まむと、口へ放り投げた。
トゲトゲが口に刺さる。痛い。それを多少我慢して噛み砕くと、先ほど同様、甘みが広がった。
……なるほど。これも美味しい。
「ダズル・サラザールは占星術に長けた男で、とても大きな魔力を持つ魔法使いだった。彼は魔法使いの町、『ストレーガ』をつくるのに尽力し、魔法使いたちに居場所を与えたから人気者なんだ」
ぱくぱくとその口内にダメージを伴うスナック菓子(?)を放り込んで、ユキさんはそんなことを呟いた。
「……この爺さんが?」
「これはイメージ映像というやつさ。彼の容姿はこんなじゃない。人前にあまり出たがらない男だったから」
「ユキさん、会ったことあるのかよ」
「まあ、一応ね」
スナックを食べて、ドリンクを飲む。
その一連の流れが、また痺れるほどうまい。
スナックを口に含んだままドリンクを流し込むと、あのちくちくした痛みは全く感じない。
「あ、そうだ。向こうについたら、僕から離れちゃだめだよ。治安は比較的いいけど、常識は通用しないから」
「俺はあんたの右腕なんだろ。離れるもんかよ」
「っ!」
あっという間に袋の中身は空っぽになった。
やれやれと包みをくしゃくしゃに丸めていると、ユキさんがまた顔を赤くして固まっている。
「……なんだよ?」
「いや、その……なんか、改めて言われると恥ずかしいっていうか……」
「?」
「だって君、つい最近まで素っ気なかったし……そんなふうに思われてると思ってなくて」
「あー……」
ふと、脳裏にあの雪の日が思い浮かぶ。
一年経つ間に、ふらふらと自由にする俺をただ帰る場所として迎え入れてくれたのはユキさんだけだ。
言葉にして伝えたことはなかったが、なるほど、この人にはそれの『特別さ』がわからないのか。
「……別に、そういうことだって、あるだろ」
口にしようとしたが、喉から言葉は出ていかなかった。
代わりに出てきたのは、そんな言葉たちだった。
なんだか顔が熱くて、俺は視線を窓の外に逃がした。
遠くの方に、たくさんの煙突と建物が見えてきていた。
0
あなたにおすすめの小説

俺の婚約者は小さな王子さま?!
大和 柊霞
BL
「私の婚約者になってくれますか?」
そう言い放ったのはこの国の王子さま?!
同性婚の認められるパミュロン王国で次期国王候補の第1王子アルミスから婚約を求められたのは、公爵家三男のカイルア。公爵家でありながら、長男のように頭脳明晰でもなければ次男のように多才でもないカイルアは自由気ままに生きてかれこれ22年。
今の暮らしは性に合っているし、何不自由ない!人生は穏やかに過ごすべきだ!と思っていたのに、まさか10歳の王子に婚約を申し込まれてしまったのだ。
「年の差12歳なんてありえない!」
初めはそんな事を考えていたカイルアだったがアルミス王子と過ごすうちに少しづつ考えが変わっていき……。
頑張り屋のアルミス王子と、諦め系自由人のカイルアが織り成す救済BL

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
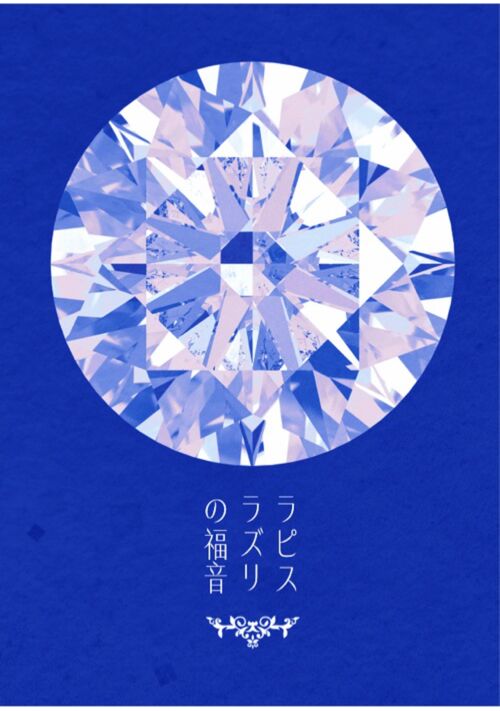
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

カフェ・コン・レーチェ
こうらい ゆあ
BL
小さな喫茶店 音雫には、今日も静かなオルゴール調のの曲が流れている。
背が高すぎるせいか、いつも肩をすぼめている常連の彼が来てくれるのを、僕は密かに楽しみにしていた。
苦いブラックが苦手なのに、毎日変わらずブラックを頼む彼が気になる。
今日はいつもより温度を下げてみようかな?香りだけ甘いものは苦手かな?どうすれば、喜んでくれる?
「君の淹れる珈琲が一番美味しい」
苦手なくせに、いつも僕が淹れた珈琲を褒めてくれる彼。
照れ臭そうに顔を赤ながらも褒めてくれる彼ともっと仲良くなりたい。
そんな、ささやかな想いを込めて、今日も丁寧に豆を挽く。
甘く、切なく、でも愛しくてたまらない――
珈琲の香りに包まれた、静かで優しい記憶の物語。


隊長さんとボク
ばたかっぷ
BL
ボクの名前はエナ。
エドリアーリアナ国の守護神獣だけど、斑色の毛並みのボクはいつもひとりぼっち。
そんなボクの前に現れたのは優しい隊長さんだった――。
王候騎士団隊長さんが大好きな小動物が頑張る、なんちゃってファンタジーです。
きゅ~きゅ~鳴くもふもふな小動物とそのもふもふを愛でる隊長さんで構成されています。
えろ皆無らぶ成分も極小ですσ(^◇^;)本格ファンタジーをお求めの方は回れ右でお願いします~m(_ _)m
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















