12 / 18
第二章「魔法使いの町。」
03
しおりを挟む「え? 列車が運休!?」
銀行での換金を済ませ、とりあえずチケットだけ買おうと立ち寄った駅で、俺とユキさんは途方に暮れていた。
駅舎には俺たちの他にもたくさん人影があって、皆それぞれ、天井近くの掲示板をみて固まっていた。
「……列車不具合のため再開は未定だとよ。どうする?」
「困ったなあ……」
ユキさんは、おなかのあたりをさすりながら呟いた。
腹はまあ、俺も普通に減っている。
この後は二人でどこかに食いに行くつもりだったし。
「箒に乗って帰れたりしねえの」
「この町はね、誰かの侵入を許さないように『異空間』にあるの。出入口を結ぶのはこの列車だけなんだ」
「まじか……」
異空間ときたか。
普通に空があって、太陽があって、風が吹いているここが、異空間。
にわかには信じがたいが……。
「宿とかあったりすんの、ここ」
帰れないとなれば、もはや泊まるしかない。
車両の不具合といわれてしまえば、解決のしようもないし。
他の原因というなら、まあ、何かやりようもあるものだが……。
「あるにはあるけど……キミ、モンスターとかと出会ったことある?」
ユキさんがそんなことを尋ねるので、俺はため息をついた。
なんだよ。モンスターって。
「ねえよ。あるわけねえだろ」
「いや宿にはドラゴンとかも泊まったりするから……遭遇したときに叫んで攻撃したりすると困るなと」
「しねえよ! いきなり叫んで攻撃するやついるかよ!」
「いやほら、ゲームとかではよくあるみたいだし……なんだっけ? モンスターを攻撃して倒すやつあるでしょう。四人くらいでやるやつ」
「あくまでもあれゲームだから! 実際にやるわけねえだろ!」
とにかく、と俺はユキさんの腕を引いた。
「動かないもんはしゃあないだろ。飯食って、宿探そうぜ」
「……なんていうか、キミは本当に環境適応能力が高いよね」
「うるせえ」
***
俺とユキさんが立ち寄ったのは、細い路地裏にある小さな喫茶店だった。
いろいろ店は探したのだが、列車に足を止められた連中でごった返していて、とてもじゃないが入れそうにない。
この分では宿探しだって難しそうだ。
「おや、見ない顔と、久しぶりに見る顔だ」
席に着くなり、ベストを着た店員の男はそういった。
ユキさんもふっと微笑むと、「やあ、店長」と切り返した。
……店員ではなく、店長だったか。
「珍しく列車が止まったんだってね。さっき聞いたよ」
店長の男はテーブルにグラスを置いて、それからメニュー表を置いた。
ユキさんはそれを手に取ることなく、す、と魔法で開いた。
「ね。珍しいよね、こういうの」
現代社会で生きてきた俺的には、さして珍しくもないのだが……。
まあ、この列車は止まらないのに、と思う気持ちがわからないわけじゃない。
そういう路線の列車だってあるにはある。
正確にはトラブルが起きにくい路線だが。
「まるで誰かをここから『手放したくない』とでも言っているかのようだ」
店長の男は、そんなことを呟くと、「では、ごゆっくり」と消えていった。
店内には俺たちの他には人がほとんどおらず、すみっこの方にローブをまとった男が一人いるくらいのものだった。
あまり知られていないのか、あるいは何か魔術的な施しでもしてあるのか。
「ユキさん?」
「え、あ、なに?」
しばらく黙りこけていたユキさんを呼ぶ。
彼の目線はメニュー表に落ちていたようだったが、どうやらメニューを選んでいたわけではなさそうだ。
「何か心当たりでもあんのか?」
視線をメニュー表に落とす。
案外普通の品物が並んでいるようだ。
珈琲に、紅茶に、緑茶に……て、緑茶あるのかよ。
「……さっき会った絵の商人だけれどね」
「? おう」
「あいつなら、列車に細工をして運航不能にするくらいは、まあ、できるかなあ、と」
思っちゃって、とユキさんはつづけた。
なるほど。
ユキさんの懸念はよくわかった。
「つまり、あいつが俺たちを足止めしてる、って言いたいんだな」
「あくまでも憶測だけどね……」
去り際見せたあの『目』は、憶測以上のものではないだろうか。
「でもなあ、だとしたってアレとやりあうのは骨が折れるっていうか……」
「?」
きょとんとしてしまった。
だってユキさんはすごい。
あの夜も、前の夜も、あっさりと問題を解決してしまった。
そのユキさんが、ため息をついて頭を抱えている。
「いやね、彼はいうなれば凄腕のスパイなんだ。それこそ各国、種族間を駆け抜け、錬金術にも精通していた。エリクサーという単語はゲームにもあるだろう?」
「あー、回復剤みたいなやつ?」
「ホンモノはもっと質が悪い。何しろ、『不老不死』の薬なんだ」
「!」
不老不死。
フィクションでしか聞かない単語である。
「ただの人間が数世紀も生きてるなんて異常なことなんだよ、本来はね」
「……それ、もうただの人間じゃなくない?」
「いいや、ただの人間さ。その肉体に魔物のような強度はない」
ぺら、とメニュー表がめくれる。
次のページにはナポリタンとか、喫茶店の定番メニューが載っていた。
「そんなただの人間が、数世紀も『薬』だけで生き抜ける。そりゃあもうしぶといし、いろんな意味で手ごわいに決まってる」
「……まあ……」
ゲームでも漫画でもアニメでも、『人間』というのは一律でしぶとい。
諦めないし、しつこいし、面倒で、なおかつ無鉄砲だ。
そうかと思えば死にたくないと足掻きに足掻き、その最後の悪あがきで生き残ってしまうようなしぶとさを持つ。
その種族の一員、として俺も一応名を連ねているとは思うのだが、そんな俺からしたって、そんな男は敵に回したくはない。
いや、もう回っているようなものなのだが、それはそれとして。
「ま、いっか。さ、何食べる? 僕はねえ、ナポリタンだな!」
「切り替えはっや」
「別にいいでしょう。お腹減ったんだよ」
それもそうである。
「じゃあ、俺もそれ。同じやつでいいや」
「飲み物は? アイスコーヒーでいい?」
「ン」
視線を窓の外に向ける。
細い路地裏とあって、人通りはほとんどない。
たまに視線を横切っていくのは猫くらいのものだ。
あとは、はらはらと舞ってくる木の葉とか。
「すみませーん。注文いいですか?」
店内にも改めて視線を向ける。
厨房は奥まったところにあって見えないが、今のところ店長という男しか見えない。
その彼は、ユキさんの声に反応してこちらに歩いてきていた。
「どうぞ」
「ナポリタン二つと、アイスコーヒー二つ」
端っこの方、あの深くローブを纏った男がいる方には、らせん状の階段があった。
この店、どうやら二階もあるらしい。
壁にかけられた絵は抽象画のようなもので、ユキさんの描いたああいう禍々しい感じはしなかった。
「かしこまりました」
男がまた、厨房へと消えていく。
注文を伝えていないようなので、もしかしたら男一人で切り盛りしているのかもしれなかった。
「……ユキさんは、あの男から依頼を受けて絵を描いてたのか?」
「ううん。別の依頼主がいたのだけれど、だいぶ前に死んでしまってね」
ずず、とお冷を飲みながら、ユキさんは遠い目をした。
「住処を探して、東洋の島国まで来た。そんなときに、キミを見つけたんだよ」
「じゃあそいつが死ぬまでは、ずっとそいつのところで絵を?」
「うん、そんなところ。僕としては死んでくれて済々しているけれどね。半分幽閉されていたようなものだし」
「ゆ、幽閉」
また物騒なキーワードが出てきやがった。
「依頼主とあの商人が仲が良くてね。それで、死後にしつこかったんだよ。絵を描いてほしいって」
それはすぐに目に浮かぶようだった。
あのうさん臭い笑顔で、ユキさんに迫ったのだろう。
パッと見、一般人から見たらある意味で事案である。
ユキさん、見た目子供っぽいし。
「出向いた先で、困っている人間たちのために何枚か描いた絵は全部彼が買ってくれたからとても助かったんだけどさ」
「……ふーん」
確かに、ユキさんの魔法、『化け物を絵に閉じ込める』というのは使い勝手がいいだろう。
どんな幽霊も等しく無力化するに等しい。
まして、そういうものを集めている人間には高く売れたりするのかもしれない。
(案外、そういう霊媒師的な職業にした方が儲かるんじゃねえの)
じ、とユキさんを見下ろしていると、ユキさんは小首を傾げた。
「なあに?」
「いや、なんでも」
ほどなくしてナポリタン二つと、アイスコーヒーがきた。
やはり持ってきたのも店長だった。たぶんこの店には店長しかいないのだ。
「うわあ、美味しそう」
ユキさんはテーブルの端っこにあるフォークをとってはしゃぎ始めた。
「ほらほら、冷めないうちに食べよう!」
「お、おう」
俺に差し出されたフォークを受け取る。
ナポリタンからはいい感じに湯気が上がっていた。
フォークでその赤い麺を巻き取って、口へ。
もぐもぐと咀嚼し、飲み込むとふわ、とケチャップの懐かしい香りが広がった。
……美味しい。
ただ、これ、魔法とか関係ないけど。
「美味しいねえ」
ユキさんが顔をあげると、その口の周りにはケチャップがついていた。
だめだ。あとで拭いてやらねばならない。
「おう」
だけど今はまあ、いいかと放っておくことにした。
その笑顔を見ながら食べるとなんだか倍美味しい気がした。
(ナポリタンか。これそんなに難しくはないんだよな、これなら作ってやれるかも)
いつもは簡単な料理ばかりだが、これもまた、新たなレパートリーにくわえられるかもしれない。
そんなことを思いながら、そのどこか懐かしいナポリタンを食べていると、不意にからんからん、とお店のベルが鳴った。
ドアがゆっくりと開き、ばたばたと複数の足音が入ってくる。
「──お客さん、じゃなさそうなんだけど」
少し不機嫌そうな店長の声に、俺も思わず入り口に目を向けた。
そこには、複数の黒スーツの男たちが整列していた。
「何の用かな。当店、戦闘の類は一切を禁止しているよ。そういうのがお好みなら、今すぐ外に出ることだ」
ごくん、とナポリタンを飲み込む。
ユキさんは全く視線を向けなかった。
目の前のナポリタンに夢中である。
「……隻腕の魔法使いを探している。ただ、それだけだ」
スーツの一人がそう告げると、店長は「はあ?」と切り返した。
「見つけたら連れて出る。それだけだ」
「その際に戦闘は一切ないって約束できるの?」
「それは向こう次第だ。少なくとも我々には事を荒立てるつもりがない」
「ふうん?」
頷くわりには、店長の男は動かなかった。
かわりに動いたのは、端っこで座ったまま動かなかったローブの男だ。
「おや」
近づいてきた彼に、店長は道を譲るように退いた。
その途端の出来事である。
「あ」
男たちはそんな声をあげると共に、店の入り口からぱっと消え失せてしまった。
「……ふん。口ほどにもない」
何をしたのか全く分からなかった。
思わず持っていたフォークが落ちる。
ユキさんは本当に微動だにしなくて、目の前でナポリタンを完食し、アイスコーヒーを啜っていた。
「おい」
男から声がした。
ローブをかぶったままなので、誰に話しかけているかわからない。
「隻腕の魔法使い」
おっと、ユキさんあてか。
「お前の客だった。……貸しが一つだ」
「……僕は別に頼んだ覚えはないよ」
アイスコーヒーも飲み終わって、ユキさんはようやくのこと入り口の方に体を向けた。
「事実に違いはあるまい」
男の足がこちらへ向く。
かつん。かつん。かつん。
ゆっくりとしたもので、その手は途中でローブをとった。
そのローブの下にある顔があらわになる。
「うお」
思わず声をあげてしまった。
顔には大きくツギハギの痕が、首のあたりにも同様の痕がある。
しかし基本的には整った顔立ちだった。その青色の目は、じ、とユキさんを睨みつけていた。
「列車が止まったままで、人が溢れかえってうるさいったらありゃしない。なんとかしてくれ」
「……む」
「僕はしがない錬金術師なので出来ないが、そのくらい、かの高名な『隻腕の魔法使い』サマならお手のものだろう?」
くつくつと嫌味っぽく笑う男をみて、ユキさんは深くため息をついた。
店長はというと、すでにここに姿はなく、厨房の方へまた去っていったようだった。
ユキさんと知り合い……なのだろうか、この男。
0
あなたにおすすめの小説

俺の婚約者は小さな王子さま?!
大和 柊霞
BL
「私の婚約者になってくれますか?」
そう言い放ったのはこの国の王子さま?!
同性婚の認められるパミュロン王国で次期国王候補の第1王子アルミスから婚約を求められたのは、公爵家三男のカイルア。公爵家でありながら、長男のように頭脳明晰でもなければ次男のように多才でもないカイルアは自由気ままに生きてかれこれ22年。
今の暮らしは性に合っているし、何不自由ない!人生は穏やかに過ごすべきだ!と思っていたのに、まさか10歳の王子に婚約を申し込まれてしまったのだ。
「年の差12歳なんてありえない!」
初めはそんな事を考えていたカイルアだったがアルミス王子と過ごすうちに少しづつ考えが変わっていき……。
頑張り屋のアルミス王子と、諦め系自由人のカイルアが織り成す救済BL

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
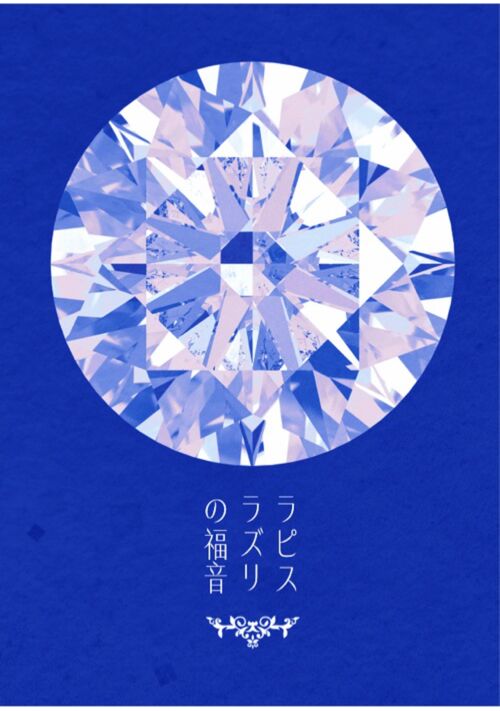
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

カフェ・コン・レーチェ
こうらい ゆあ
BL
小さな喫茶店 音雫には、今日も静かなオルゴール調のの曲が流れている。
背が高すぎるせいか、いつも肩をすぼめている常連の彼が来てくれるのを、僕は密かに楽しみにしていた。
苦いブラックが苦手なのに、毎日変わらずブラックを頼む彼が気になる。
今日はいつもより温度を下げてみようかな?香りだけ甘いものは苦手かな?どうすれば、喜んでくれる?
「君の淹れる珈琲が一番美味しい」
苦手なくせに、いつも僕が淹れた珈琲を褒めてくれる彼。
照れ臭そうに顔を赤ながらも褒めてくれる彼ともっと仲良くなりたい。
そんな、ささやかな想いを込めて、今日も丁寧に豆を挽く。
甘く、切なく、でも愛しくてたまらない――
珈琲の香りに包まれた、静かで優しい記憶の物語。

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















