13 / 18
第二章「魔法使いの町。」
04
しおりを挟む工房から、やけに騒がしい窓の下を見下ろす。
彼が寝泊まりをしているビルの前には、人だかりが出来ていた。
「……うん?」
窓を少し開けて、下の喧噪を耳に入れる。
ほどなくして、彼らがビルの警備員に何を詰めよっているのか理解できた。
(列車が止まっている、と)
ほとんどありえないことだ。
その車体を作り上げたのは他でもない彼であり、整備を務める職員にも顔見知りが何人かいる。
原因不明の故障などでっちあげにも等しい。
何しろ過去数百年ほど、ただの一度も故障などなかったのだから。
(僕にどうにかしろというわけか)
自分ではどうにかできないからと他人に押し付ける性は生まれながらのものらしい。
少し考えれば『異常などあるわけがない』と気づき、これが『ほかのモノ』による陰謀だということには気が付きそうなものだが……。
「……サン・ジェルマンめ……」
彼は窓からそっと離れると、頭を抱えた。
先ほどやけにすんなり諦めていくとは思った。それが奇妙なことだとも理解していた。
けれど深くは考えなかった。……結局は下で喚く烏合の衆と、自分も変わらない。
「失礼します」
ノックの音と同時に、女が入ってきた。
このビルのオーナーの秘書を務める女だった。
長く伸びたエルフ耳がぴくぴくと動いている。
背から伸びる妖精の羽根は、儚げにきらきらと光り輝いていた。
──この女は、妖精……ではなく、妖精に似せて作り上げた『ホムンクルス』である。
その長いまつげも、透けるようなブロンドの髪も、年を取らない整った顔立ちも、数百年と変わらない。
まるで陶器のようだ。当然である。作り物なのだから。
「そろそろ来る頃だと思っていたよ、リゼ」
「では用件もおわかりですね」
彼女はニコリと口元だけ弧を描いて見せた。
その目はまるで笑っていなかった。
「どうせ僕に今回の件をどうにかしろというんだろう」
マギサは、大げさにため息をついて見せた。
「お断りだ。あのサン・ジェルマン伯爵が裏で糸をひいているにきまってる。僕程度の錬金術師がどうにかできるわけないだろう」
「おや、そこまでお分かりになっているのに『何も』なさらない、と?」
「当然だ。……待て、どうしてお前はそれを知っているんだ?」
リゼと呼ばれた女は、今度は瞼もにっこりと弧を描くようにして笑って見せた。
やはり作り物のような人形の笑顔だ、とマギサは思った。
「何故って、サン・ジェルマン伯爵から声明がこちらに届いておりましたので」
「声明?」
マギサは顔をしかめた。
そんなものは聞いた覚えはない。
が、リゼはきょとんとしている。
「聞かせましょうか」
「ああ」
コホン、と咳ばらいを一度してから、リゼは音声を再生するように言葉を紡いだ。
……サン・ジェルマン伯爵の声音を、ぴったり真似して。
「敬愛なるストレーガ鉄道局長。此度の細工をどうか許してほしい。目的が達成されれば、この事態はただちに解消すると約束しよう。私の目的とはこの町に潜んでいる『隻腕の魔法使い』の確保である。もし協力してくれるのならば、事態はすぐにでも好転するだろう」
「……ハッ」
思わず吐き捨てるような笑いが漏れた。
「なんだそれは。脅迫文じゃないか」
サン・ジェルマンらしい厭らしさがよく出ている、とマギサはつづけた。
対照的に、リゼは笑いひとつこぼさなかった。
何が面白いのかわからないようだった。
表情を無に戻してから、マギサは言った。
「いいだろう。その隻腕の魔法使いとやら、僕が探して見せよう」
「では、捕獲も?」
「いいや、それはしない」
クツクツと、マギサはまた笑った。
「僕はアレの邪魔をするだけだ。魔法使いに味方して、サン・ジェルマンの企みを砕いてやる」
「……まあ、オーナーは解決を望まれておりましたのでその方法を問うことはないでしょうが……」
リゼは、抱えていたバインダーをテーブルの上に置いた。
「一応、声明文のコピーと、『隻腕の魔法使い』についての情報です。どうぞ」
「ん」
もはやマギサの視線はそこにはなかった。
足は実験テーブル側に向き、視線はその棚に向いていた。
リゼは、それを見てから部屋を出ていった。
それを確認してから、マギサは置かれたファイルに手を伸ばす。
「これは……」
彼は小さく感嘆の声をあげて、それからすぐにローブをひっつかむと、その部屋から飛び出していった。
──というのが、つい一時間ほど前のことだ。
マギサは、まじまじと目の前に座る、魔法使いを見つめた。
隻腕の魔法使いだという、小さめの背丈の青年もまた、マギサを見つめたまま何も言わなかった。
「何か飲むかい」
見かねたように、店長の男が厨房から出てきた。
その問いかけにマギサは、「紅茶を」と告げた。
「サン・ジェルマン伯爵と君とが『グル』じゃないという証拠は何かあるかい」
店長が紅茶を運んでくると、ようやくのこと魔法使いは口を開いた。
「証拠だと?」
「そう。マギサ・バルサーモといえばあの列車を手掛けた錬金術師だろう。僕だって名前くらいは知っている」
「それは光栄だ。僕も『隻腕の魔法使い』の逸話はかねがね聞いているよ」
名前くらいは、といわれるほど偉大なつもりはマギサにはなかった。
目の前の隻腕の魔法使いにくらべれば、それはもう月とすっぽんだ。
彼が敬愛してやまない『原初の魔法使い』──その弟子かもしれないと詠われるほど、隻腕の魔法使いが扱う魔法はすさまじい。
ほかの誰もが扱うことのできない、特異な魔法なのだ。
「何しろ魔法使いは今も何人かいるが、君ほどの魔法使いとなると稀有だ。あの十人の弟子にも並ぶことだろう」
「錬金術師だってそう多くはないだろう? それにこの町にいる連中なんて、みんな似たり寄ったりさ」
魔法使いは目を伏せてそう言った。
が、マギサはすぐに否定の言葉を述べた。
「そんなことはない。君の代わりというのが『ない』というサン・ジェルマン伯爵の気持ちがわからないわけじゃないからな。──だが、それをわかったうえで、今の僕は『彼』の邪魔がしたい」
ニタリ、とマギサがほほ笑むと、魔法使いは少しキョトンとした顔を浮かべた。
そうして、それから、
「なんだ。キミも彼が気にくわないのなら、そう言ってくれればよかったのに」
と呟いた。
肌につたわるピリピリした空気が緩和されるのを感じた。
どうやら、味方であると信じてくれたようだった。
魔法使いの隣に腰かけていた男の方は、こちらには関せず、ナポリタンの入った皿に視線を落としていた。
***
ユキさんがそのマギサだかいう男と少し打ち解けたのは、あの騒動から少し経ってからのことだった。
なんだかいけ好かない感じだったが、ユキさんが警戒心をなくしたのをみて、俺も睨みつけるのをやめた。
サン・ジェルマンだかいうあの商人の男が気にくわないのは、この三人、見解が一致しているのだ。
二人がどう思っているかはしらないが、俺は一発ぶん殴ってやりたいと思っている。
「ウェルダーパークという町はご存じかな」
俺たち二人は、マギサという男の錬金術工房であるビルの一室に招かれていた。
室内はまるで理科の実験室だ。
ビーカーやらフラスコやら試験管、アルコールランプまで懐かしいものがたくさんある。
ダッチオーブンのような鉄の鍋もいくつかあるし、昔ながらの釜のようなものもあった。
あとは真鍮で出来た見たこともない器具がいくつかあって、それにいたっては名前すらわからない。
「知っているよ。魔術師の町だろう」
ユキさんはコクリと頷いた。
俺は当然のことながら、そんな街に覚えはない。
「あの町に、原初の魔法使いがとった十人の弟子たちのうち、一人が現れたらしくてね」
「それはまた、珍しいね」
「サン・ジェルマンはそこにいくつもりだった。……少なくとも最初は、僕と共にね」
「断ったというわけだね。賢明なことだ」
差し出された紅茶を一口飲んで、ユキさんは頷いた。
俺は全くの蚊帳の外である。
「そして候補は僕に移ったわけか。全く、その弟子にあって彼は何をするつもりなんだか……」
「さあな。僕には想像もつかない」
だが、とマギサは続けた。
「つまり僕は奴の誘いを断り姿をくらまし、お前も元の場所に帰ればさすがのアレも諦めるとは思わないか?」
くつくつというこの卑屈な笑い方は、きっとこの男の癖なのだろう。
俺も紅茶を一口含む。
あ、存外美味しい。
「そうはいっても、列車を直す方法にあてはあるのかい?」
「あるとも。そこで隻腕の魔法使い、キミの出番だ」
「僕?」
ユキさんは、小首を傾げた。
「あのね、僕は魔法使いだけれど、万能ってわけでは……」
「使い魔がいるじゃないか。そいつに強化魔法をかけて、アレを足止めしてくれていればいい」
ようやくのこと、俺に視線が向いた。
「使い魔って俺のことか?」
そりゃまあ、確かにユキさんに買われた身だ。
そういう呼ばれ方をするのかもしれないが、そんな呼ばれ方をするのは初めてだ。
「ちょっと。阿久津くんは僕の片腕であって、使い魔なんてものじゃないよ」
ユキさんはむう、と頬を膨らませて抗議した。
可愛い。なにその挙動。
「なんだっていいが、伯爵は魔法こそ使えないが身体スキルはアホみたいに高いからな。僕ではとてもじゃないが止められない」
「……そりゃまあ、僕の阿久津くんは優秀だけど……」
ちらり、と俺の意見をうかがうようにユキさんが視線をくれる。
がしがしと頭を掻いた。
こういう作戦会議は、なんだか苦手だ。やっぱり居心地が悪い。
「あー、俺があの伯爵ぶん殴って止めてる間に、あんたが列車直してくれるんだな?」
「ああ。それは約束しよう。三十分もあれば間違いない」
「それじゃ、そうしようぜ。ちょうど俺もあいつ殴りたかったところだし」
ユキさんとマギサは、キョトンとした視線を俺に向けた。
「なんだよ」
居心地の悪い視線に、俺の目もおのずと細くなる。
「いや……怖いもの知らずだな、と」
マギサは、そうつぶやくと、続けて言った。
「あのサン・ジェルマン伯爵という男は素手でドラゴンと戦う男だ。その拳は分厚い鉄板を容易に貫くといわれている」
「ユキさん? やっぱここに住まない?」
0
あなたにおすすめの小説

俺の婚約者は小さな王子さま?!
大和 柊霞
BL
「私の婚約者になってくれますか?」
そう言い放ったのはこの国の王子さま?!
同性婚の認められるパミュロン王国で次期国王候補の第1王子アルミスから婚約を求められたのは、公爵家三男のカイルア。公爵家でありながら、長男のように頭脳明晰でもなければ次男のように多才でもないカイルアは自由気ままに生きてかれこれ22年。
今の暮らしは性に合っているし、何不自由ない!人生は穏やかに過ごすべきだ!と思っていたのに、まさか10歳の王子に婚約を申し込まれてしまったのだ。
「年の差12歳なんてありえない!」
初めはそんな事を考えていたカイルアだったがアルミス王子と過ごすうちに少しづつ考えが変わっていき……。
頑張り屋のアルミス王子と、諦め系自由人のカイルアが織り成す救済BL

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
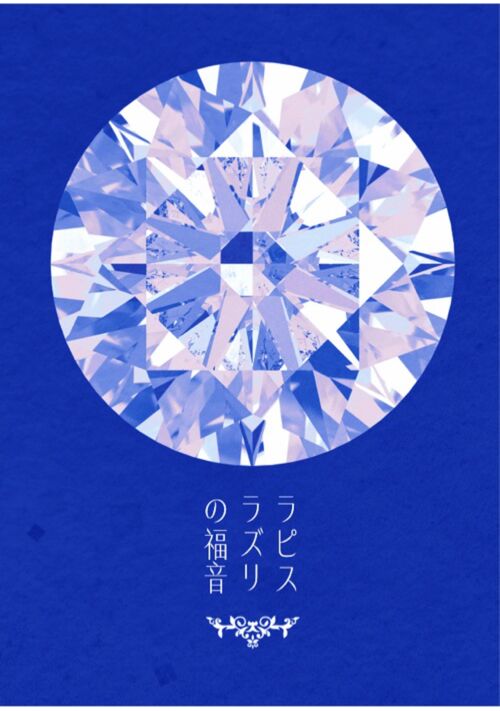
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

カフェ・コン・レーチェ
こうらい ゆあ
BL
小さな喫茶店 音雫には、今日も静かなオルゴール調のの曲が流れている。
背が高すぎるせいか、いつも肩をすぼめている常連の彼が来てくれるのを、僕は密かに楽しみにしていた。
苦いブラックが苦手なのに、毎日変わらずブラックを頼む彼が気になる。
今日はいつもより温度を下げてみようかな?香りだけ甘いものは苦手かな?どうすれば、喜んでくれる?
「君の淹れる珈琲が一番美味しい」
苦手なくせに、いつも僕が淹れた珈琲を褒めてくれる彼。
照れ臭そうに顔を赤ながらも褒めてくれる彼ともっと仲良くなりたい。
そんな、ささやかな想いを込めて、今日も丁寧に豆を挽く。
甘く、切なく、でも愛しくてたまらない――
珈琲の香りに包まれた、静かで優しい記憶の物語。

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















