あなたにおすすめの小説

俺の婚約者は小さな王子さま?!
大和 柊霞
BL
「私の婚約者になってくれますか?」
そう言い放ったのはこの国の王子さま?!
同性婚の認められるパミュロン王国で次期国王候補の第1王子アルミスから婚約を求められたのは、公爵家三男のカイルア。公爵家でありながら、長男のように頭脳明晰でもなければ次男のように多才でもないカイルアは自由気ままに生きてかれこれ22年。
今の暮らしは性に合っているし、何不自由ない!人生は穏やかに過ごすべきだ!と思っていたのに、まさか10歳の王子に婚約を申し込まれてしまったのだ。
「年の差12歳なんてありえない!」
初めはそんな事を考えていたカイルアだったがアルミス王子と過ごすうちに少しづつ考えが変わっていき……。
頑張り屋のアルミス王子と、諦め系自由人のカイルアが織り成す救済BL

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
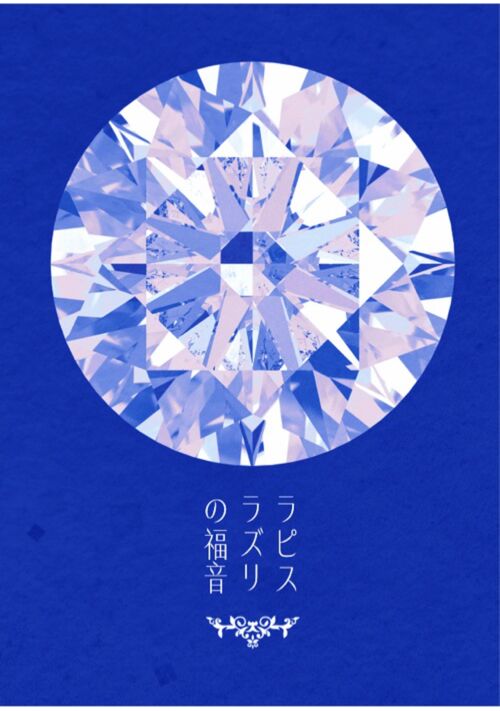
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

カフェ・コン・レーチェ
こうらい ゆあ
BL
小さな喫茶店 音雫には、今日も静かなオルゴール調のの曲が流れている。
背が高すぎるせいか、いつも肩をすぼめている常連の彼が来てくれるのを、僕は密かに楽しみにしていた。
苦いブラックが苦手なのに、毎日変わらずブラックを頼む彼が気になる。
今日はいつもより温度を下げてみようかな?香りだけ甘いものは苦手かな?どうすれば、喜んでくれる?
「君の淹れる珈琲が一番美味しい」
苦手なくせに、いつも僕が淹れた珈琲を褒めてくれる彼。
照れ臭そうに顔を赤ながらも褒めてくれる彼ともっと仲良くなりたい。
そんな、ささやかな想いを込めて、今日も丁寧に豆を挽く。
甘く、切なく、でも愛しくてたまらない――
珈琲の香りに包まれた、静かで優しい記憶の物語。


隊長さんとボク
ばたかっぷ
BL
ボクの名前はエナ。
エドリアーリアナ国の守護神獣だけど、斑色の毛並みのボクはいつもひとりぼっち。
そんなボクの前に現れたのは優しい隊長さんだった――。
王候騎士団隊長さんが大好きな小動物が頑張る、なんちゃってファンタジーです。
きゅ~きゅ~鳴くもふもふな小動物とそのもふもふを愛でる隊長さんで構成されています。
えろ皆無らぶ成分も極小ですσ(^◇^;)本格ファンタジーをお求めの方は回れ右でお願いします~m(_ _)m
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















