23 / 33
【第四章】影、点々と
22 : 端緒(ルクス、カスパル)
しおりを挟む
中央能力研究所は、士官学院とは異なる静けさに包まれていた。
ここでは訓練のように技を磨くことも、戦闘を想定した試験を行うこともない。
ただ、能力そのものを数値化し、記録し、報告する。
それが研究所の役割だった。
士官学院が〈鍛える場〉だとすれば、研究所は〈解析する場〉ーーそのふたつは、常に対をなして存在していた。
建物の中は、外観の無機質さとは違って、ひそやかな色彩と柔らかな光で満ちていた。
白を基調にした廊下の奥の空間では、小さな子どもたちが色とりどりの玩具に囲まれて遊んでいる。
しかし、それは単なる玩具ではない。
透明な球体に指を触れて反応を確かめる子、積み木のような装置を組み合わせて簡単な力場を生み出す子。
研究員たちは笑顔を見せながらも、さりげなく、その動きを記録していた。
ルクスの前を歩くカスパルは、慣れた足取りで廊下を進む。
「カスパルは、ここによく来るの?」
「学院に入学するまでは、定期的に来てた」
前を向いたまま、カスパルは淡々と答える。
「中央近辺の人間で能力の発露があれば、まずはここに来ることになる。その後は色々だけど。僕の場合は、能力の伸び方を定期的に観察して、記録を取る程度だった」
「中央近辺ってことは、もしかして、エリオも?」
「ああ、子どもの頃から来てた」
ルクスはそれを聞いて得心がいった。
カスパルとエリオの不思議な距離の近さが腑に落ちた。
「君は、入学前に一度来てるんだっけ」
ルクスがこの場所を訪れたのは、士官学院に入る直前のことだ。
〈神経投射〉の〈表〉の使い方だけを示して、あっさりと済ませた記憶がある。
だから今回も同じようなものだろうと、おおよそは想像がついていた。
「うん、そのとき以来。……だから今回も、大丈夫」
カスパルは頷くと、廊下の突き当たりを曲がる。
視線が動いた拍子に、中庭に面した窓から、石畳の中庭に入ってくる馬車が見えた。
黒い塗装に装飾された銀の紋章が、陽光を鋭く弾いて光る。
カスパルの目の奥に、かすかな警戒の色が走ったが、すぐに視線を前へと戻した。
廊下の先にある、ひとつの扉の前で立ち止まる。
「ここだ」
カスパルは短く告げ、扉を押し開けた。
大小さまざまな機器が並んだ、広い測定室。
床には淡い紋様が刻まれ、部屋の中央には半透明の柱が立つ。
柱の周囲には、端末を持った研究員が数人、すでに待機していた。
壁のパネルに「士官学院提出用・基礎特性測定」と小さく表示が灯る。
研究所で能力の分析と記録を行い、その結果を士官学院へ報告する。
研究所からの報告に基づき、士官学院は実戦的訓練を行い、その過程で生じたデータを研究所にフィードバックする。
循環の始点となる場所に、カスパルとルクスは足を踏み入れた。
「ーーでは、ルクス・フロレン。能力測定に入ります。まずは〈神経投射〉の標準発動から」
研究員が、手順を確かめるように、手元の端末資料を淡々と読み上げる。
促され、ルクスは部屋の中央の柱の前に立った。
ルクスの呼吸に呼応するように、足元の紋様が光を帯び、空気がわずかに震える。
半透明な柱の内部で、微細な粒子が渦を巻き始める。
神経と能力の回路が同期していく過程を可視化する装置ーーそう説明を受けた記憶がある。
ーーまずは〈表〉の測定。
身体強化……筋収縮度、反応速度、処理速度……粒子は明滅しながら、神経伝達の速度、同期率、出力度を数値化して、分析機器へ落とし込んでいく。
機器に表示されたグラフは、滑らかに上へ伸び、入学前に測定した記録値に重ねられた線が、僅差ながら確実に上を取る。
研究員の指が、端末の上で記録のために動く。
「測定終了。結果、改善、誤差範囲内で安定」
機器に表示された測定結果を、カスパルが読み上げた。
「次、〈寸断〉試験に移行。試験用仮想対象を展開」
カスパルは機器に視線を落としたまま、次を指示する。
ルクスは軽く頷き、深く息を吸う。
「試験用仮想対象を展開します。仮想シナプス網、モードB」
研究員の声と同時に、柱の周囲に、仮想対象装置が起動した。
淡い人影のようなホログラムが立ち上がり、擬似的な〈他者の神経回路〉があらわれる。
ルクスは意識を切り替える。
仮想対象に向けて放った〈寸断〉が、ホログラム内を走る線を断ち切る。
像がわずかに滲み、数秒後に再びもとの形になる。
二射、三射、と同じ流れを繰り返す。
データの集約が端末に積まれていく。
カスパルは機器に表示される数値を追いながら〈演算〉を展開していた。
算出していたタイミングに数値が追いついた瞬間、視線はそのまま、左手を顎にそえた。
一見、単なる思案の動作。
ルクスはその合図を拾い、〈寸断〉の集中をわずかに緩めた。
同時に、自身に〈神経投射〉をかけて、血管の収縮、心拍の上昇といった疲労と負荷を示す身体状況を作る。
その変化は、分析機器の数値に不安定な揺れとして反映され、警告音が鳴り始めた。
「測定中止」
カスパルの声とともに、ホログラムは消え、警告音も止む。
カスパルは機器から視線を上げ、ルクスに声をかける。
「……続けられるか?」
「はい」
カスパルは機器から離れ、部屋の中央に立つ柱の前へ進み、ルクスから距離をとった位置に立つ。
カスパルに代わり、研究員が合図を送る。
「〈重複〉試験に移行。カスパル・レイス、〈演算〉を安定化域まで展開」
カスパルの足元の紋様が光を帯びる。
光は静かに広がり、半透明な柱の内部でも、微細な粒子が整然と動き始める。
「〈演算〉安定化域確認。ルクス・フロレン、〈重複〉を展開」
ルクスは、展開されたカスパルの〈演算〉発動域へ〈神経投射〉を伸ばす。
明確な形と勢いで伸びる力の道のようなエリオの〈支配域〉とは異なり、カスパルの〈演算〉は、緻密に編み上げられ何層にも重なった障壁のような感触だった。
ルクスは〈神経投射〉の重ね方を変える。
隙間がないほど緻密な〈演算〉に合わせて〈神経投射〉を細く細かくほどいていく。
やがて、糸ほどに細く、さらに細かくほどかれた〈神経投射〉が、液体が染み込むように、じわりと〈演算〉に浸透していく。
「〈演算〉及び〈神経投射〉、接続確認」
ルクスはさらに〈神経投射〉を広げる。
繋がったカスパルの神経回路の処理能力を高めることで、カスパルの〈演算〉発動による負荷が軽くなり、機器に表示された発動強度を示す数値が上昇していく。
この測定も、〈寸断〉の測定と同じように進むはずだった。
カスパルが合図を送り、ルクスがそれに合わせて発動の強度を調整し、自身への負荷を演出するーーその手順で。
しかし、その時。
測定室の外、遠くない区画で鳴った低い衝撃音が、重く床を伝い響いた。
カスパルに向けて集中していたルクスの〈神経投射〉は、外からの干渉には無防備だった。
突如として押し寄せた衝撃は、回路を容赦なく引き裂き、底知れぬ闇へと引きずり込むかのような荒々しく圧倒的な力だった。
わけもわからぬまま、ただ必死に抗う。
「ーーッ」
ルクスの口から、音にならない息が漏れた。
柱の内部で粒子が大きく乱れ、制御のほころびが走った。
真っ青になったルクスの状態に気付いたカスパルは、即座に〈演算〉を解き、〈重複〉を切り離した。
「測定対象の意識レベル低下!記録中断!救護班コール!」
緊急遮断の警告音と研究員の声が響く。
ルクスの視界は白く跳ね、次の瞬間、意識が滑り落ちるように途切れた。
駆け寄ったカスパルがルクスの身体を支え、床への衝突はかろうじて避けた。
扉が開き、白衣の救護員が駆け込んでくる。
カスパルは一歩退き、必要な空間を確保しながら、計器の最終波形を目で素早くさらった。
分析機器には、『〈重複〉行使中、負荷過大により意識消失』の記録が追加されていた。
ここでは訓練のように技を磨くことも、戦闘を想定した試験を行うこともない。
ただ、能力そのものを数値化し、記録し、報告する。
それが研究所の役割だった。
士官学院が〈鍛える場〉だとすれば、研究所は〈解析する場〉ーーそのふたつは、常に対をなして存在していた。
建物の中は、外観の無機質さとは違って、ひそやかな色彩と柔らかな光で満ちていた。
白を基調にした廊下の奥の空間では、小さな子どもたちが色とりどりの玩具に囲まれて遊んでいる。
しかし、それは単なる玩具ではない。
透明な球体に指を触れて反応を確かめる子、積み木のような装置を組み合わせて簡単な力場を生み出す子。
研究員たちは笑顔を見せながらも、さりげなく、その動きを記録していた。
ルクスの前を歩くカスパルは、慣れた足取りで廊下を進む。
「カスパルは、ここによく来るの?」
「学院に入学するまでは、定期的に来てた」
前を向いたまま、カスパルは淡々と答える。
「中央近辺の人間で能力の発露があれば、まずはここに来ることになる。その後は色々だけど。僕の場合は、能力の伸び方を定期的に観察して、記録を取る程度だった」
「中央近辺ってことは、もしかして、エリオも?」
「ああ、子どもの頃から来てた」
ルクスはそれを聞いて得心がいった。
カスパルとエリオの不思議な距離の近さが腑に落ちた。
「君は、入学前に一度来てるんだっけ」
ルクスがこの場所を訪れたのは、士官学院に入る直前のことだ。
〈神経投射〉の〈表〉の使い方だけを示して、あっさりと済ませた記憶がある。
だから今回も同じようなものだろうと、おおよそは想像がついていた。
「うん、そのとき以来。……だから今回も、大丈夫」
カスパルは頷くと、廊下の突き当たりを曲がる。
視線が動いた拍子に、中庭に面した窓から、石畳の中庭に入ってくる馬車が見えた。
黒い塗装に装飾された銀の紋章が、陽光を鋭く弾いて光る。
カスパルの目の奥に、かすかな警戒の色が走ったが、すぐに視線を前へと戻した。
廊下の先にある、ひとつの扉の前で立ち止まる。
「ここだ」
カスパルは短く告げ、扉を押し開けた。
大小さまざまな機器が並んだ、広い測定室。
床には淡い紋様が刻まれ、部屋の中央には半透明の柱が立つ。
柱の周囲には、端末を持った研究員が数人、すでに待機していた。
壁のパネルに「士官学院提出用・基礎特性測定」と小さく表示が灯る。
研究所で能力の分析と記録を行い、その結果を士官学院へ報告する。
研究所からの報告に基づき、士官学院は実戦的訓練を行い、その過程で生じたデータを研究所にフィードバックする。
循環の始点となる場所に、カスパルとルクスは足を踏み入れた。
「ーーでは、ルクス・フロレン。能力測定に入ります。まずは〈神経投射〉の標準発動から」
研究員が、手順を確かめるように、手元の端末資料を淡々と読み上げる。
促され、ルクスは部屋の中央の柱の前に立った。
ルクスの呼吸に呼応するように、足元の紋様が光を帯び、空気がわずかに震える。
半透明な柱の内部で、微細な粒子が渦を巻き始める。
神経と能力の回路が同期していく過程を可視化する装置ーーそう説明を受けた記憶がある。
ーーまずは〈表〉の測定。
身体強化……筋収縮度、反応速度、処理速度……粒子は明滅しながら、神経伝達の速度、同期率、出力度を数値化して、分析機器へ落とし込んでいく。
機器に表示されたグラフは、滑らかに上へ伸び、入学前に測定した記録値に重ねられた線が、僅差ながら確実に上を取る。
研究員の指が、端末の上で記録のために動く。
「測定終了。結果、改善、誤差範囲内で安定」
機器に表示された測定結果を、カスパルが読み上げた。
「次、〈寸断〉試験に移行。試験用仮想対象を展開」
カスパルは機器に視線を落としたまま、次を指示する。
ルクスは軽く頷き、深く息を吸う。
「試験用仮想対象を展開します。仮想シナプス網、モードB」
研究員の声と同時に、柱の周囲に、仮想対象装置が起動した。
淡い人影のようなホログラムが立ち上がり、擬似的な〈他者の神経回路〉があらわれる。
ルクスは意識を切り替える。
仮想対象に向けて放った〈寸断〉が、ホログラム内を走る線を断ち切る。
像がわずかに滲み、数秒後に再びもとの形になる。
二射、三射、と同じ流れを繰り返す。
データの集約が端末に積まれていく。
カスパルは機器に表示される数値を追いながら〈演算〉を展開していた。
算出していたタイミングに数値が追いついた瞬間、視線はそのまま、左手を顎にそえた。
一見、単なる思案の動作。
ルクスはその合図を拾い、〈寸断〉の集中をわずかに緩めた。
同時に、自身に〈神経投射〉をかけて、血管の収縮、心拍の上昇といった疲労と負荷を示す身体状況を作る。
その変化は、分析機器の数値に不安定な揺れとして反映され、警告音が鳴り始めた。
「測定中止」
カスパルの声とともに、ホログラムは消え、警告音も止む。
カスパルは機器から視線を上げ、ルクスに声をかける。
「……続けられるか?」
「はい」
カスパルは機器から離れ、部屋の中央に立つ柱の前へ進み、ルクスから距離をとった位置に立つ。
カスパルに代わり、研究員が合図を送る。
「〈重複〉試験に移行。カスパル・レイス、〈演算〉を安定化域まで展開」
カスパルの足元の紋様が光を帯びる。
光は静かに広がり、半透明な柱の内部でも、微細な粒子が整然と動き始める。
「〈演算〉安定化域確認。ルクス・フロレン、〈重複〉を展開」
ルクスは、展開されたカスパルの〈演算〉発動域へ〈神経投射〉を伸ばす。
明確な形と勢いで伸びる力の道のようなエリオの〈支配域〉とは異なり、カスパルの〈演算〉は、緻密に編み上げられ何層にも重なった障壁のような感触だった。
ルクスは〈神経投射〉の重ね方を変える。
隙間がないほど緻密な〈演算〉に合わせて〈神経投射〉を細く細かくほどいていく。
やがて、糸ほどに細く、さらに細かくほどかれた〈神経投射〉が、液体が染み込むように、じわりと〈演算〉に浸透していく。
「〈演算〉及び〈神経投射〉、接続確認」
ルクスはさらに〈神経投射〉を広げる。
繋がったカスパルの神経回路の処理能力を高めることで、カスパルの〈演算〉発動による負荷が軽くなり、機器に表示された発動強度を示す数値が上昇していく。
この測定も、〈寸断〉の測定と同じように進むはずだった。
カスパルが合図を送り、ルクスがそれに合わせて発動の強度を調整し、自身への負荷を演出するーーその手順で。
しかし、その時。
測定室の外、遠くない区画で鳴った低い衝撃音が、重く床を伝い響いた。
カスパルに向けて集中していたルクスの〈神経投射〉は、外からの干渉には無防備だった。
突如として押し寄せた衝撃は、回路を容赦なく引き裂き、底知れぬ闇へと引きずり込むかのような荒々しく圧倒的な力だった。
わけもわからぬまま、ただ必死に抗う。
「ーーッ」
ルクスの口から、音にならない息が漏れた。
柱の内部で粒子が大きく乱れ、制御のほころびが走った。
真っ青になったルクスの状態に気付いたカスパルは、即座に〈演算〉を解き、〈重複〉を切り離した。
「測定対象の意識レベル低下!記録中断!救護班コール!」
緊急遮断の警告音と研究員の声が響く。
ルクスの視界は白く跳ね、次の瞬間、意識が滑り落ちるように途切れた。
駆け寄ったカスパルがルクスの身体を支え、床への衝突はかろうじて避けた。
扉が開き、白衣の救護員が駆け込んでくる。
カスパルは一歩退き、必要な空間を確保しながら、計器の最終波形を目で素早くさらった。
分析機器には、『〈重複〉行使中、負荷過大により意識消失』の記録が追加されていた。
0
あなたにおすすめの小説

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

何故よりにもよって恋愛ゲームの親友ルートに突入するのか
風
BL
平凡な学生だったはずの俺が転生したのは、恋愛ゲーム世界の“王子”という役割。
……けれど、攻略対象の女の子たちは次々に幸せを見つけて旅立ち、
気づけば残されたのは――幼馴染みであり、忠誠を誓った騎士アレスだけだった。
「僕は、あなたを守ると決めたのです」
いつも優しく、忠実で、完璧すぎるその親友。
けれど次第に、その視線が“友人”のそれではないことに気づき始め――?
身分差? 常識? そんなものは、もうどうでもいい。
“王子”である俺は、彼に恋をした。
だからこそ、全部受け止める。たとえ、世界がどう言おうとも。
これは転生者としての使命を終え、“ただの一人の少年”として生きると決めた王子と、
彼だけを見つめ続けた騎士の、
世界でいちばん優しくて、少しだけ不器用な、じれじれ純愛ファンタジー。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

僕の、しあわせ辺境暮らし
* ゆるゆ
BL
雪のなか3歳の僕を、ひろってくれたのは、やさしい16歳の男の子でした。
ふたりの、しあわせな辺境暮らし、はじまります!
ぽて と むーちゃんの動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵もあがります。
YouTube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。
プロフのwebサイトから飛べるので、もしよかったら!

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。
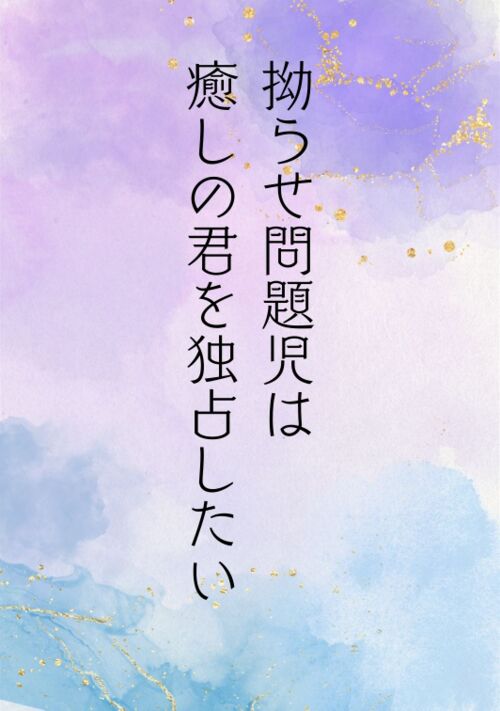
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。


狼の護衛騎士は、今日も心配が尽きない
結衣可
BL
戦の傷跡が癒えた共生都市ルーヴェン。
人族と獣人族が共に暮らすその街で、文官ユリス・アルヴィンは、穏やかな日々の中に、いつも自分を見守る“優しい視線”の存在を感じていた。
その正体は、狼族の戦士長出身の護衛騎士、ガルド・ルヴァーン。
無口で不器用だが、誠実で優しい彼は、いつしかユリスを守ることが日課になっていた。
モフモフ好きなユリスと、心配性すぎるガルド。
灰銀の狼と金灰の文官――
異種族の二人の関係がルーヴェンの風のようにやさしく、日々の中で少しずつ変わっていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















