18 / 33
【第三章】影の踊り場
17 : エリオの反省
しおりを挟む
翌朝、ルクスは熱を出した。
衛生官の診立てによれば、精神的過負荷と身体疲労の複合による一時的な自律神経の乱れであるという。
ルクスには、熱が下がるまで、部屋での静養が命じられた。
ベッドで眠るルクスの氷のうを替えながら、カスパルは思う。
過度な緊張と混乱の反動が、一晩遅れて現れたのだろう。
ルクスが静養を命じられたことは、この状況では、むしろ都合がよかった。
事情を勘ぐられることなく、従卒の任務や訓練から一時的に離すことができる。
カスパルはルクスの代理を担うことを申し出て、学院側もそれを了承した。
それから数日、カスパルは従卒代理としてエリオの部屋を訪れるたび、報告と確認事項を手短に済ませ、最後に一言二言の皮肉を添えることが日課となった。
口調は静かで、言葉遣いはあくまで乱れず。
しかし、隙間に、隠しきれぬ苛立ちと、冷えた感情が混ざる。
エリオは、ただ、姿勢を正し、カスパルの言葉を黙って受け止めた。
自らの行いが引き起こした事態に対して、弁解の余地などないと自覚していたからだ。
ルクスを動揺させ、カスパルの信頼も損なった。
その責任の重さを、ひとつひとつ噛み締めていた。
ーーにもかかわらず、エリオの言葉選びは、時折、無自覚にカスパルを逆撫でしてしていた。
カスパルが吐く皮肉の調子は、日を追うごとに、棘を帯びていった。
今日の皮肉は、婚約者候補の人数についてだった。
あの日、ルクスが「最近カスパルの顔を見ていない」と言ったことを、エリオは思い出していた。
耳にしていた情報から「縁談の下見に連れ回されているんだろう」と返した一言が発端になって、ルクスがエリオにも婚約者がいるのかと聞いてきた。
「婚約者候補が五人だなんて、よくも白々しく」
報告書の束を机に置きながら、カスパルが吐き捨てる。
「ん?違ったか?」
「違う。十二人だ。カピタンに就任してから、さらに増えてる」
「候補が何人に増えようが、最後は一人になる」
エリオはそれだけ言って、置かれた報告書の束に目を通し始める。
カスパルは、咎めるような目で見ている。
ここ数日、カスパルから向けられる視線や言葉の端々から、彼がどれほどルクスを大切に思って接しているかがわかる。
ルクス本人に対してはもちろん、ルクスを大切にしているカスパルに対しても、エリオの反省の気持ちは積もっていく。
「……衝動的だった。だが、軽く扱ったつもりはなかったんだ」
エリオは、重く呟く。
「君の〈つもり〉なんて、相手には関係ないんだよ」
カスパルは、重く息を吐く。
「いいか、エリオ。……君が自分から、誰かを欲しいなんて言ったのは、初めてのことだった」
静かな口調だったが、言葉には重みがあった。
「軽く扱ったつもりはない、という言葉にも、一定の誠意は感じている。……だが」
カスパルにの視線が鋭く、強くなる。
「衝動的だった、という一点が、すべてを台無しにする。相手にとっては、冗談にもならない」
エリオは口をつぐみ、黙ってそれを受けた。
カスパルは、さらに言葉を続けた。
「君は、誰かに求められることばかりを経験してきた。求められ、与えられ、選ぶ側でいられた。それに慣れすぎてる」
口調はあくまで静かなまま。
潜む感情は、苛立ちと、呆れとーー少しの哀しみが、混ざっていた。
「だから、自分が誰かを欲して動いたとき、相手がどう思うか、どれだけ心を揺らされるかなんて……想像もできなかったんだろう」
エリオは、痛みのようなものを胸の奥に感じた。
カスパルの指摘は正しかった。
応えるか、拒むか。
それだけを選んできた自分に、もうひとつの視点が必要だったことを、初めて知った。
「それでいて、軽んじたつもりはない……か。自分の中にだけある誠意が、すべてを赦される免罪符だとでも思ってるのか?」
カスパルの言葉は、容赦なく、真剣だった。
言葉の一つひとつが、まるで石のように重く、エリオの胸に積もっていく。
苦い沈黙の中で、自分の未熟さと身勝手さが、はっきりと際立っていた。
「……俺は……」
口を開いたものの、すぐには言葉が続かなかった。
自分の中にあるものを、うまく形にできない。
けれど、それでも、伝えなくてはならない気がした。
「…………ルクスに、悪いことをした」
ただ、その事実だけは、はっきりしていた。
あらためて思い出すほどに、自分がしてしまったことの重さがのしかかる。
カスパルは黙ってエリオの様子を観察していたがーーやがて、呆れたように、ぼそりと呟いた。
「……ほんと、君は……」
そのあとに、短く舌打ちのような音がこぼれた。
「……それで済むなら、どれほど楽か」
エリオは、ただ静かに視線を落とす。
ふたりの間に、重い沈黙が落ちた。
やがて、エリオが口を開く。
至って真面目に、心から言った。
「……やはりおまえは、プレフェクトに向いてるな」
カスパルの表情がぴくりと引きつった。
「……褒めてるんだが、気にさわったか?」
「殺意が湧くから、黙っててくれ」
それきり、カスパルは何も言わず、必要な作業を黙々とこなした。
カスパルが自室に戻ると、薄明かりの灯る中、ベッドの上で身体を起こしたルクスが、カスパルのほうを見た。
「おかえり」
やや掠れてはいたが、穏やかな響きがあった。
カスパルは驚き、すぐに歩み寄って、灯りの下で顔色を確認する。
「起きて大丈夫なのか?」
「うん、もう熱もすっかり下がったし」
その声はしっかりとしたもので、何より、ルクスの目はまっすぐにカスパルをとらえていた。
「……寝てる間、考える時間がたくさんあって……考えた……僕は、キスが不快じゃなかった」
小さな声だったが、そこに、本心を誤魔化すような色はなかった。
「……ただ、それ以外のことは、まだよくわからないんだ」
カスパルは、深く息を吸い、思考を整理するように瞼を伏せた。
やがて、静かに言った。
「だったら、試してみるのもいいかもしれない」
衛生官の診立てによれば、精神的過負荷と身体疲労の複合による一時的な自律神経の乱れであるという。
ルクスには、熱が下がるまで、部屋での静養が命じられた。
ベッドで眠るルクスの氷のうを替えながら、カスパルは思う。
過度な緊張と混乱の反動が、一晩遅れて現れたのだろう。
ルクスが静養を命じられたことは、この状況では、むしろ都合がよかった。
事情を勘ぐられることなく、従卒の任務や訓練から一時的に離すことができる。
カスパルはルクスの代理を担うことを申し出て、学院側もそれを了承した。
それから数日、カスパルは従卒代理としてエリオの部屋を訪れるたび、報告と確認事項を手短に済ませ、最後に一言二言の皮肉を添えることが日課となった。
口調は静かで、言葉遣いはあくまで乱れず。
しかし、隙間に、隠しきれぬ苛立ちと、冷えた感情が混ざる。
エリオは、ただ、姿勢を正し、カスパルの言葉を黙って受け止めた。
自らの行いが引き起こした事態に対して、弁解の余地などないと自覚していたからだ。
ルクスを動揺させ、カスパルの信頼も損なった。
その責任の重さを、ひとつひとつ噛み締めていた。
ーーにもかかわらず、エリオの言葉選びは、時折、無自覚にカスパルを逆撫でしてしていた。
カスパルが吐く皮肉の調子は、日を追うごとに、棘を帯びていった。
今日の皮肉は、婚約者候補の人数についてだった。
あの日、ルクスが「最近カスパルの顔を見ていない」と言ったことを、エリオは思い出していた。
耳にしていた情報から「縁談の下見に連れ回されているんだろう」と返した一言が発端になって、ルクスがエリオにも婚約者がいるのかと聞いてきた。
「婚約者候補が五人だなんて、よくも白々しく」
報告書の束を机に置きながら、カスパルが吐き捨てる。
「ん?違ったか?」
「違う。十二人だ。カピタンに就任してから、さらに増えてる」
「候補が何人に増えようが、最後は一人になる」
エリオはそれだけ言って、置かれた報告書の束に目を通し始める。
カスパルは、咎めるような目で見ている。
ここ数日、カスパルから向けられる視線や言葉の端々から、彼がどれほどルクスを大切に思って接しているかがわかる。
ルクス本人に対してはもちろん、ルクスを大切にしているカスパルに対しても、エリオの反省の気持ちは積もっていく。
「……衝動的だった。だが、軽く扱ったつもりはなかったんだ」
エリオは、重く呟く。
「君の〈つもり〉なんて、相手には関係ないんだよ」
カスパルは、重く息を吐く。
「いいか、エリオ。……君が自分から、誰かを欲しいなんて言ったのは、初めてのことだった」
静かな口調だったが、言葉には重みがあった。
「軽く扱ったつもりはない、という言葉にも、一定の誠意は感じている。……だが」
カスパルにの視線が鋭く、強くなる。
「衝動的だった、という一点が、すべてを台無しにする。相手にとっては、冗談にもならない」
エリオは口をつぐみ、黙ってそれを受けた。
カスパルは、さらに言葉を続けた。
「君は、誰かに求められることばかりを経験してきた。求められ、与えられ、選ぶ側でいられた。それに慣れすぎてる」
口調はあくまで静かなまま。
潜む感情は、苛立ちと、呆れとーー少しの哀しみが、混ざっていた。
「だから、自分が誰かを欲して動いたとき、相手がどう思うか、どれだけ心を揺らされるかなんて……想像もできなかったんだろう」
エリオは、痛みのようなものを胸の奥に感じた。
カスパルの指摘は正しかった。
応えるか、拒むか。
それだけを選んできた自分に、もうひとつの視点が必要だったことを、初めて知った。
「それでいて、軽んじたつもりはない……か。自分の中にだけある誠意が、すべてを赦される免罪符だとでも思ってるのか?」
カスパルの言葉は、容赦なく、真剣だった。
言葉の一つひとつが、まるで石のように重く、エリオの胸に積もっていく。
苦い沈黙の中で、自分の未熟さと身勝手さが、はっきりと際立っていた。
「……俺は……」
口を開いたものの、すぐには言葉が続かなかった。
自分の中にあるものを、うまく形にできない。
けれど、それでも、伝えなくてはならない気がした。
「…………ルクスに、悪いことをした」
ただ、その事実だけは、はっきりしていた。
あらためて思い出すほどに、自分がしてしまったことの重さがのしかかる。
カスパルは黙ってエリオの様子を観察していたがーーやがて、呆れたように、ぼそりと呟いた。
「……ほんと、君は……」
そのあとに、短く舌打ちのような音がこぼれた。
「……それで済むなら、どれほど楽か」
エリオは、ただ静かに視線を落とす。
ふたりの間に、重い沈黙が落ちた。
やがて、エリオが口を開く。
至って真面目に、心から言った。
「……やはりおまえは、プレフェクトに向いてるな」
カスパルの表情がぴくりと引きつった。
「……褒めてるんだが、気にさわったか?」
「殺意が湧くから、黙っててくれ」
それきり、カスパルは何も言わず、必要な作業を黙々とこなした。
カスパルが自室に戻ると、薄明かりの灯る中、ベッドの上で身体を起こしたルクスが、カスパルのほうを見た。
「おかえり」
やや掠れてはいたが、穏やかな響きがあった。
カスパルは驚き、すぐに歩み寄って、灯りの下で顔色を確認する。
「起きて大丈夫なのか?」
「うん、もう熱もすっかり下がったし」
その声はしっかりとしたもので、何より、ルクスの目はまっすぐにカスパルをとらえていた。
「……寝てる間、考える時間がたくさんあって……考えた……僕は、キスが不快じゃなかった」
小さな声だったが、そこに、本心を誤魔化すような色はなかった。
「……ただ、それ以外のことは、まだよくわからないんだ」
カスパルは、深く息を吸い、思考を整理するように瞼を伏せた。
やがて、静かに言った。
「だったら、試してみるのもいいかもしれない」
0
あなたにおすすめの小説

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

何故よりにもよって恋愛ゲームの親友ルートに突入するのか
風
BL
平凡な学生だったはずの俺が転生したのは、恋愛ゲーム世界の“王子”という役割。
……けれど、攻略対象の女の子たちは次々に幸せを見つけて旅立ち、
気づけば残されたのは――幼馴染みであり、忠誠を誓った騎士アレスだけだった。
「僕は、あなたを守ると決めたのです」
いつも優しく、忠実で、完璧すぎるその親友。
けれど次第に、その視線が“友人”のそれではないことに気づき始め――?
身分差? 常識? そんなものは、もうどうでもいい。
“王子”である俺は、彼に恋をした。
だからこそ、全部受け止める。たとえ、世界がどう言おうとも。
これは転生者としての使命を終え、“ただの一人の少年”として生きると決めた王子と、
彼だけを見つめ続けた騎士の、
世界でいちばん優しくて、少しだけ不器用な、じれじれ純愛ファンタジー。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

僕の、しあわせ辺境暮らし
* ゆるゆ
BL
雪のなか3歳の僕を、ひろってくれたのは、やさしい16歳の男の子でした。
ふたりの、しあわせな辺境暮らし、はじまります!
ぽて と むーちゃんの動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵もあがります。
YouTube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。
プロフのwebサイトから飛べるので、もしよかったら!

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。
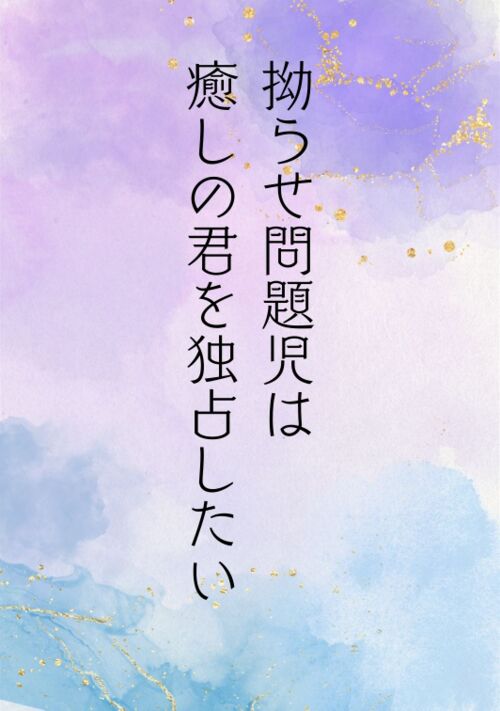
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。


狼の護衛騎士は、今日も心配が尽きない
結衣可
BL
戦の傷跡が癒えた共生都市ルーヴェン。
人族と獣人族が共に暮らすその街で、文官ユリス・アルヴィンは、穏やかな日々の中に、いつも自分を見守る“優しい視線”の存在を感じていた。
その正体は、狼族の戦士長出身の護衛騎士、ガルド・ルヴァーン。
無口で不器用だが、誠実で優しい彼は、いつしかユリスを守ることが日課になっていた。
モフモフ好きなユリスと、心配性すぎるガルド。
灰銀の狼と金灰の文官――
異種族の二人の関係がルーヴェンの風のようにやさしく、日々の中で少しずつ変わっていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















